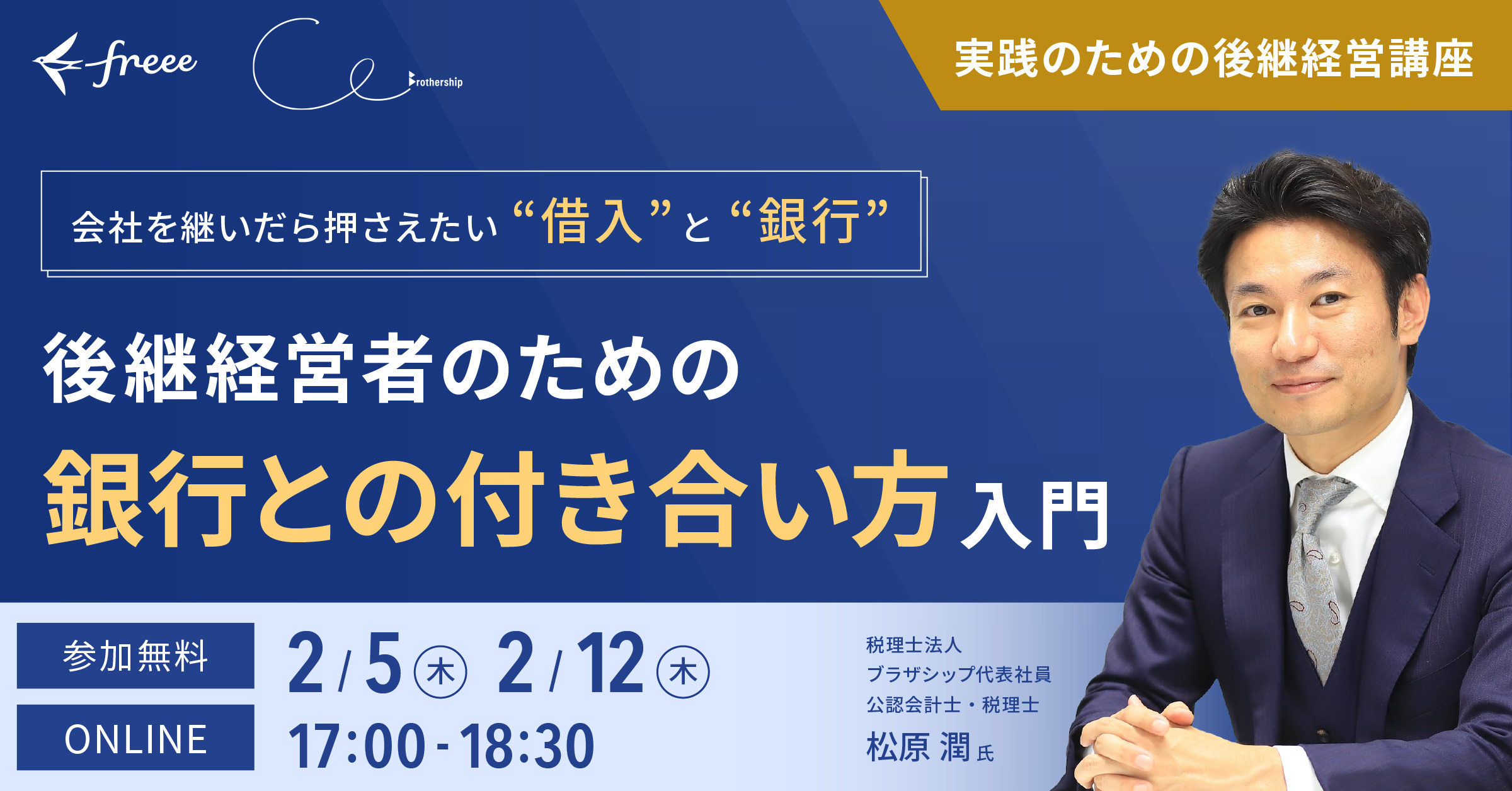公開日 /-create_datetime-/

企業をさまざまなリスクから守る法務部は、高い専門知識を持つ頭脳集団といったイメージが強いかもしれません。
法律を武器に専門職として働く法務部ですが、実際のところどれくらいの法律知識が必要とされているのでしょうか?
法務部というフィールドでどのような業務に携わるのかをご紹介しながら解説します。
法務部の必要性
平成26年時点で、国内の企業数は約385万社、弁護士の数は37,680人と、企業数に対して弁護士の数はあまりに少ないことが分かります。その上、新しい第4次産業などの対応も含め、民法などの法律は目まぐるしく変化しています。
企業は契約や企業間の訴訟など、法律に詳しい弁護士に頼りたいところですが、なにしろ弁護士もありあまる事案を抱えていることもあり、すべてがスムーズに運ばない現実があります。
そのため、近年では法律に詳しい集団「法務部」を設置する企業が増加傾向にあるようです。
商事法務研究会が行った調査では、課レベル以上の法務部署を設置している割合が7割を超えているということです。法務担当者の数も、平成12年調査の5,731人から、7,193人にまで増加しています。
法務部が企業内にあることで弁護士に事案を依頼するよりもスムーズに運ぶケースもあります。
たとえば商品などの知財案件では、詳しい法律も知識として持ち合わせている必要がありますが、商品に関する情報などにも精通している必要があり、社外の顧問弁護士に依頼するなどの際はその説明から行わなければなりません。法務部の人間であれば商品に関する情報も豊富にそろいます。
そのような観点で、法務部がこのところ以前に増して必要とされているのです。
法務部の業務
法務部は、どのような業務に携わっているのでしょうか。
- 契約関連業務
- 特許関連業務
- 社内コンプライアンス関連
- 企業間紛争関連
- 組織法務関連
- 顧問弁護士とのやり取りなど
ざっと挙げてもかなり多方面の業務があります。
これらのほとんどが法律に基づいて進める業務になりますので、かなり幅広い法律の知識が必要になることは間違いありません。
法務部に必要とされる法律知識
実際に法務部員を採用する際、どのような基準で企業側は人材を求めているのでしょうか。
商事法務研究会が行った調査では、新卒・未経験者既卒の場合、企業側は法律の知識よりも業務への関心やコミュニケーション能力などに期待を持っているようです。
しかしこれ以外の中途採用になると、最も重要視する能力に「幅広い法律の知識」を上げている企業が際立つようになります。
実際に国内大手企業の法務部採用の条件を見てみると、法務経験があり幅広い法律の知識を持つ者という記載が目立ちます。特に、M&Aに携わった経験や契約の審査から締結までを経験したことのある人材などは、即戦力として企業側は積極的に採用しているようです。
それだけでなく、近年急成長を遂げている第4次産業関連の法整備なども急ピッチで行われている背景もあり、蓄積された法律の知識に加え、新たな分野の法律など急速に変化する法律への機敏な対応が取れる人材なども、多くの企業が必要としている人材と言えます。
ただ、いくら幅広い知識と言っても弁護士のような知識を期待しているというわけではなく(もちろんあれば申し分ありませんが)、企業は「法務として」幅広い知識を持っていてほしいと期待しています。
たとえば、基本的な法律に関してはある程度の知識を持ち合わせているものの、重大な法律違反などに直面した場合などは、法務部内で解決を目指すのではなく弁護士に相談するなど、高度な専門知識が必要になる事案に関しては弁護士に協力を依頼し、それ以外の法務部内で遂行可能な業務をこなしていくといった姿勢が求められます。
企業側は法律に関する知識はもとより、コミュニケーション能力のある人材、問題解決能力のある人材、論理的思考力のある人材、また、どんな困難にも立ち向かい乗り越える粘り強さのある人材を求めます。短時間で世の中も様変わりする近年の傾向から、さまざまな変化にも柔軟に対応できる人材も喜ばれるでしょう。
もし法務部で働きたいと考えたら、今ご自身の持ち合わせている法律の知識に加え、ビジネス法務関連の資格を取得しておくといいかもしれません。それだけでなく、日々刻々と変化する法律にも常にアンテナを張り、新しい知識を吸収していくことも大切です。
さらに、法律を武器としてどのように企業を守りたいのか、どのように企業の成長に携わっていきたいのか、ご自身の思いやキャリアパスについての構想なども明確にしておくとよいでしょう。企業の頭脳、企業の守護神として活躍できるよう、希望する未来を明確に描いて、日々を過ごしてくださいね。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス
おすすめ資料 -

令和7年度 税制改正のポイント
おすすめ資料 -

労務コンプライアンス経験は転職で強い?求められるスキルと成功事例を徹底解説(前編)
ニュース -

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり
ニュース -
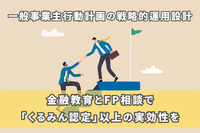
一般事業主行動計画の戦略的運用設計: 金融教育とFP相談で「くるみん認定」以上の実効性を
ニュース -

社員が自走する! 働きがいの溢れるチームの作り方【セッション紹介】
ニュース -

海外進出を成功させるグローバル人材育成戦略とは
ニュース -

全国の社宅管理担当者約100人に聞いた!社宅管理実態レポート
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -
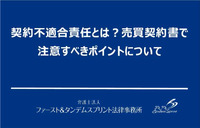
契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -
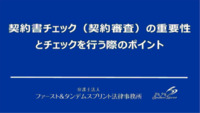
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

生成AI時代の新しい職場環境づくり
おすすめ資料 -
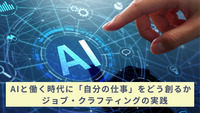
AIと働く時代に「自分の仕事」をどう創るか —ジョブ・クラフティングの実践
ニュース -
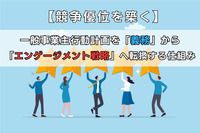
【競争優位を築く】一般事業主行動計画を「義務」から「エンゲージメント戦略」へ転換する仕組み
ニュース -
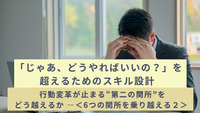
「じゃあ、どうやればいいの?」を超えるためのスキル設計― 行動変革が止まる“第二の関所”をどう越えるか ―<6つの関所を乗り越える2>
ニュース -

【社労士執筆】2026年度税制改正 年収の壁、年収178万円で合意!基礎控除・給与所得控除の変更点と実務対応
ニュース -
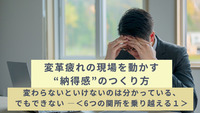
変革疲れの現場を動かす“納得感”のつくり方 ― 変わらないといけないのは分かっている、でもできない ―<6つの関所を乗り越える1>
ニュース