公開日 /-create_datetime-/
年末年始休業のお知らせ
2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。

公認会計士は、国家資格の中でも非常に高い人気を誇る資格です。令和3年(2021年)公認会計士試験の合格率は9.6%であり、取得難易度の非常に高い資格としても知られています。
今回は、公認会計士の概要や、資格条件をまとめました。
目次【本記事の内容】
公認会計士の概要と仕事内容は?
公認会計士は、企業の会計や監査を専門としています。
会社は、自社の経営状況をまとめた決算書書類を作成し、株式に報告しなければなりません。その決算書を作る際に活躍するのが公認会計士です。
公認会計士の仕事内容は多岐にわたりますが、基本的には監査に関する業務を担当します。また専門知識を活かして、コンサルティング業務や税務などに従事する公認会計士もいます。
特によく知られているのは監査業務です。
株式会社のような会社形態では、会社の所有者と、実際に経営する人々が分離しています。そして冒頭でも触れたように、経営者は「会社の経営状況を示した資料」を作成し、それを株主に報告しなければなりません。
しかし経営者と株主は、利害関係が一致しないケースも多くあります。例えば経営状態が悪い時は、決算に関して嘘の報告をすることもあり得るでしょう。そこで、決算の報告に嘘がないことを証明するために、法律上義務付けられているのが「監査(会計監査)」です。
監査が必要になる企業は、ある程度の規模を持っているケースがほとんどのため、膨大な作業が発生することになります。監査が依頼されるのは、複数の公認会計士で組織された「監査法人」が一般的です。
また、あまり知られていませんが、公認会計士は「税理士」として登録し、税理士業務を行うこともできます。税理士も非常に難易度が高い国家資格で、狭き門といわれていますが、公認会計士は別途試験を受ける必要がありません。会計だけでなく、税務に関する業務もこなせる、専門性の高い仕事です。
それから会計や税務に関する知識が豊富なので、その高度な専門性を活かして、コンサルティング業務を行う税理士もいます。企業の経営戦略やM&Aなど、幅広い分野に対応しているため、「資格を取れれば食いっぱぐれることはほとんどない」といわれています。
公認会計士の資格条件とは
ここまで公認会計士の概要をおさらいしましたが、実際に公認会計士になるためには、どのような試験を突破すれば良いのでしょうか。
まずは、最初の試験である「公認会計士試験」に合格する必要があります。
公認会計士試験は、金融庁の公認会計士・監査審査会が実施する国家試験であり、冒頭でも触れたように合格率が10%を下回る難関です。試験内容は短答形式と論文形式の二つで構成されており、幅広い知識だけでなく、論理的に物事を考えてアウトプットする力が必要になります。
なお、「短答式試験」と「論文式試験」は同時に実施されるものではありません。マークシートである短答形式に合格した場合のみ、論文形式の受験資格を得ます。
公認会計士試験は受験資格が定められていないため、基本的には誰でも受験できる試験です。実際、10代で合格する人もいれば、60代になって試験を突破する人もいます。広く門戸が開かれているため、公平性の高い試験といえるでしょう。
公認会計士になるための二つ目の条件は、実務経験を積むことです。実務(業務補助)と呼ばれるもので、2年間、業務に携わる必要があります。就職先は様々ですが、一般的には監査法人や企業の会計部門に就職し、業務をこなしていきます。
実務(業務補助)には一つ大きな特徴があります。それは、「2年間業務に携わるタイミング」を自由に選択できる点です。つまり、まだ公認会計士試験に合格していない状態でも、今後の合格を見越して実務を積むプランも選択できます。
また実務(業務補助)とは別に、実務補習も必要です。これは実務をする場所ではなく、いわゆる教育機関であり、大学のように所定の単位を獲得する必要があります。原則として3年間通うことになっており、単位を取得し終えると「修了考査」の受験資格が与えられます。
公認会計士に合格し、2年間実務経験を積みつつ、3年間の実務補習を終えてようやく「修了考査」が受けられます。「修了考査」はいわゆる最終試験です。これに合格すれば、晴れて公認会計士の資格が与えられます。
ちなみに、ここ最近の「修了考査」の合格率は50%前後です。ここまで進んできても、半数以上が不合格になってしまうと考えると、公認会計士試験がいかに難しい試験であるかがよく分かります。
なお、「修了考査」が不合格だった場合は、来年にまた同じ試験を受けることになります。公認会計士試験を再受験する必要はないため、来年以降のチャンスを窺うことになるでしょう。
まとめ
今回の記事では、公認会計士の資格条件をまとめました。公認会計士試験は高度な専門知識を要求されることもあり、国家試験の中でも屈指の難関です。また実務経験を積む必要があるため、資格を得るまでに多くの時間を必要とします。
公認会計士になりたいと考えている方は、人生をかけて臨むほどの覚悟が必要になるでしょう。
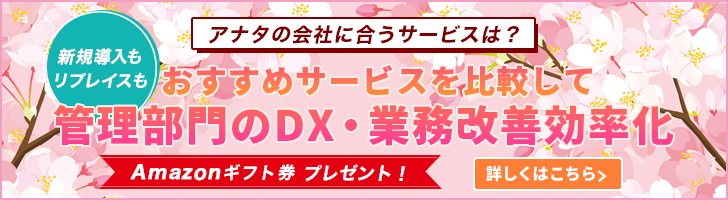
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

生成AI時代の新しい職場環境づくり
おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
おすすめ資料 -

【正社員に調査】2026年労基法改正 半数以上が「知らない」 4割が勤務時間外の業務連絡を経験
ニュース -

企業の年賀状廃止が進む理由とは?背景・代案・注意点なども紹介
ニュース -

企業の3割が「5年以内に拠点を新設・増床を予定」 国内は「関東」、「中部」が上位、中国は0.4%と低迷
ニュース -

宿泊税の勘定科目と仕訳例|宿泊費との違いや会計処理の注意点も解説
ニュース -

社内の“ハブ”になれる経理|他部署との調整力が未来のキャリアを切り拓く(前編)
ニュース -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -
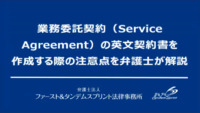
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -
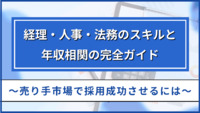
経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

【調査レポート】国際送金におけるISO20022対応状況
おすすめ資料 -

生成AIで変革する経営戦略~競争優位を築く次世代の意思決定~
ニュース -

2025年の年末年始休暇、 有給取得は少数派? 調査で見えた“意外な実態”
ニュース -

自己決定理論(SDT)が保証する:エンゲージメントとハイパフォーマンスを両立させる自律的組織の構築
ニュース -

「総務アワード2025」、受賞企業が決定。パナソニックITS株式会社がゴールドを受賞
ニュース -

【成功事例紹介】外国人雇用マネジメントサービスを活用し、外国人材を「戦力化」する具体ステップ
ニュース






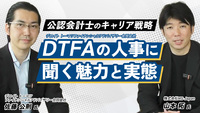


















 ポイントをGETしました
ポイントをGETしました