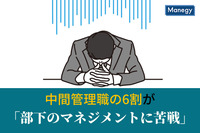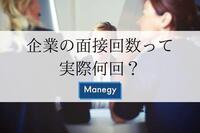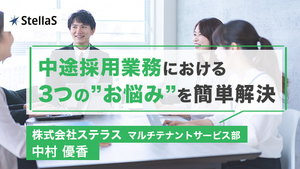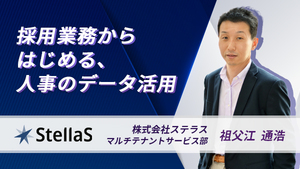公開日 /-create_datetime-/

このところ人手不足が深刻化しており、シルバー人材の活用やAIのホワイトカラー業務代行など、さまざまな対応が検討・実行されています。
そんな中、最近アルムナイという言葉がよく話題になっていることをご存じでしょうか。人事部に携わる方であればなお一層よく耳にすると思われるこのアルムナイとは、どんな意味を持ち、人手不足とどのような関係があるのか、ご紹介します。
アルムナイとは
アルムナイ(alumni)とはalumnus(男子の卒業生、同窓生)の複数形(女子は単数をalumna、複数をalumnaeと言います)で、実際の言葉は「男子の卒業生、同窓生」という意味を持ちます。これが最近では、企業における「卒業生」すなわち離職者やOB、OGを示す言葉として用いられています。
日本と比較して離職や転職、起業に寛容な海外では、離職者を重要なリソースとして捉え、組織化する動きが活発になっています。離職者に対して継続的なコミュニケーションを取り、優秀な人材の再雇用につなげるなどの取り組みとして、「アルムナイ制度」が多くの企業で取り入れられているのです。
少し前まで日本では、終身雇用が恒常化しており、退職=定年という概念が付きまとっていました。そのため日本国内では古くから根付く価値観として、離職=ネガティブな行動と捉えられがちで、離職後も積極的にコミュニケーションを取る企業は少なく、離職者を人的リソースと捉える概念はほとんど見られませんでした。
しかし最近では、このアルムナイを積極的に活用することでさまざまな恩恵を受けようと、国内でも少しずつ変化が起きています。
アルムナイの活用で人手不足を解消する
アルムナイを活用する最大の要因として、人手不足の解消、特に優秀な人材の確保が挙げられます。
2017年12月時点で、有効求人倍率は1.59倍という、1974年1月以来の高さとなっており、中小企業を中心にバブル期並みに人手不足感が高まっています。財務局の調査では、人手不足を感じるかとの問いに、1,341社中952社、71%の企業が「感じる」と答えています。さらに、一年前と調査時点の二年連続で「人手不足感がある」と答えた企業のうち、52.1%の企業が「調査時点の方がより深刻である」と回答しています。
求人側としては非常にありがたい状況ではありますが、企業側にとっては非常に深刻な事態であると言えます。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」によると、2020年以降人口の減少は加速し、特に15~64歳の人口が著しく割合を落としていくであろうと予測されています。これは労働力人口の減少という側面も持ち合わせており、現時点でも深刻な人手不足に喘ぐ企業にとっては死活問題と言っても過言ではありません。
アルムナイを活用することで、優秀な離職者の再雇用につながったり、離職者の周囲の人材を採用する、リファラル採用を可能にしたり、フリーランスの離職者に業務委託をすることも可能になります。
人材確保だけではない、アルムナイ活用のメリット
アルムナイを活用するということは、人材確保だけではなく、経営面でもさまざまなメリットをもたらすことが期待できます。
たとえば、離職後も製品やサービスを継続して使用するなどの、アンバサダー的役割として企業へメリットをもたらしたり、一般消費者として顧客となったり、時には企業顧客という立場に変化するケースも考えられます。
さらには、円満、ポジティブな離職となり、離職後も継続的に良好なコミュニケーションを取ることで、企業側にとってはレピュテーションリスクも抑えることが可能になります。
ほかにも、離職者が転職先で活躍したり、トップとなる企業を興したりすると、前職の企業価値は上がっていきます。ポジティブなイメージがつくことで、企業として、特に人事採用としてのブランディングにもなり得ます。
アルムナイとのマッチング
企業側がもう一度是非戻ってきてほしいと思うアルムナイが、実は戻りたいと思っているケースは少なくありません。そのため、アルムナイ制度が構築されていると、継続的にコミュニケーションを図ることが可能になり、「実は戻りたいけれど、声に出せない」といった潜在労働力として埋もれてしまっている優秀な人材を確保することができます。
しかし中には、戻りたいけれど今は戻れないといったケースもあり、タイミングよくコンタクトを取ることが重要になります。企業側が「戻ってほしい」という意思を表示し、アルムナイ側も状況を理解してもらえているという安心感を得ることで、双方にとって円満な復職も期待できるのです。
今、日本国内は大きな変革の時を迎えています。働き方改革を筆頭に、古くからの概念は不要なものであれば排除し、最も必要とされる考え方に生まれ変わろうとしています。
一度離職をすれば「赤の他人」「裏切り者」になるのではなく、前職の知識、技術を兼ね備えた、企業理念を理解するアルムナイとなります。
両者が前向きに、積極的にコミュニケーションを図ることで、以前よりも大きな功績をもたらすかもしれません。企業には、広く眠るアルムナイに目を向けることが求められています。
おすすめコンテンツ
関連ニュース
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

効果的なメンタルヘルス対策とは?~離職・休職につながるメンタルヘルス不調と対策の実態~
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -
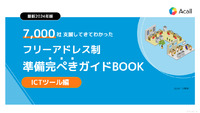
フリーアドレス制準備完ぺきガイドBOOK ICTツール編
おすすめ資料 -

取引トラブル契約事例と契約書AI審査ガイドブック
おすすめ資料 -

電子署名の適法性 ~日本の裁判手続きにおける電子署名の有効性~
おすすめ資料 -
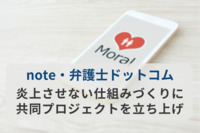
noteと弁護士ドットコム、炎上させない仕組みづくりに共同プロジェクトを立ち上げ
ニュース -
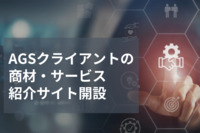
AGSクライアントの商材・サービス紹介サイト開設のお知らせ
ニュース -

【障がい者雇用】2024年4月の法定雇用率「2.5%」引き上げ、上場企業の約3分の1が“未達成”見込み。充足に向け必要な対策とは?
ニュース -

管理部門・士業に聞いた!「残業」の実態調査2024
ニュース -

健康経営の基礎知識。概念や取組・制度など基本情報を紹介!
ニュース -
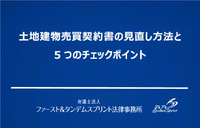
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

人事異動・新入社員のエリア配属をラクにする住居手配を効率化するヒント
おすすめ資料 -

「人事部の実態と業務効率化」に関するサーベイ結果調査レポート【MURC&DCS共同制作】
おすすめ資料 -
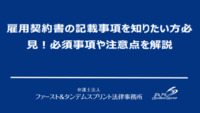
雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -
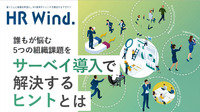
誰もが悩む5つの組織課題をサーベイ導入で解決するヒントとは?
おすすめ資料 -

個人投資家はどこをチェックする? 企業の非財務情報やESGの取り組みを整理するモデル開発
ニュース -
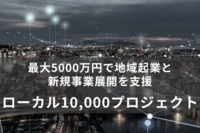
ローカル10,000プロジェクトとは?最大5000万円で地域起業と新規事業展開を支援!
ニュース -

【25卒生の本音】就職後「10年以上働きたい」就活生が5割超。“社内イベントへの参加”には9割以上が意欲的
ニュース -
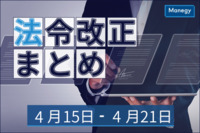
代表取締役等住所非表示措置について など|4月15日~4月21日官公庁お知らせまとめ
ニュース -
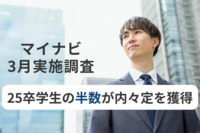
25卒学生の半数が内々定を獲得、昨年比20ポイント増 新卒採用困難に マイナビ・3月実施調査
ニュース