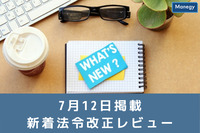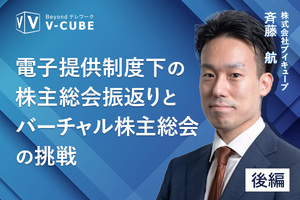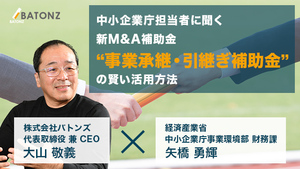公開日 /-create_datetime-/
サードプレイスとは?注目される背景とメリット、デメリットを解説

サードプレイスという言葉をご存じでしょうか?
近年、忙しく日々働くビジネスパーソンから注目を集めるようになり、最近では定年後の生活を豊かにする上でも重要であると考えられています。
そこで今回は、サードプレイスとは何か、注目されるようになった背景、サードプレイスを持つことのメリット、デメリットについて詳しくご紹介しましょう。
サードプレイスとは?
サードプレイスとは直訳すると「第3の場所」という意味で、「職場、家庭以外で、人と交流できる心地よい居場所」を意味します。
もともとアメリカの社会学者のオルデンバーグが提唱した概念です。日本の場合だと、行きつけの喫茶店・居酒屋・食堂、サークル・クラブ活動、習い事などが該当します。行きつけの喫茶店・居酒屋に行ってマスターや常連と会話をする、サークル・クラブ活動で楽しく活動するといったことができる場合、そこはサードプレイスになります。
普段忙しく働いている人の場合、人と交流できる場は家庭と職場の二つのみになりがちです。その際、必ずつきまとうのが「利害関係」です。家庭は「愛情」や「絆」などで結ばれている面がある一方で、「働いて家計を支えないといけない」という家族が求める使命感・義務感から逃れられない場でもあります。職場では報酬・給料をもらうために、あるいは出世するために、ストレスを抱えながらも仕事に集中しなければなりません。
サードプレイスとは、こうした利害関係から離れた、のびのびと人と交流できる場所です。たとえば、地域の将棋クラブがサードプレイスの場合、そこで親しくなった将棋仲間との関係性には利害関係がありません。純粋に将棋の楽しみを共有できる間柄であり、そこでは社会的地位や収入額、家族・親族といった各種のしがらみから離れられるわけです。
こうしたサードプレイスを持つことが、近年ではビジネスパーソンにとって大切であるといわれるようになってきました。
サードプレイスに注目が集まる背景にある労働生産性の低さ
なぜ働く人間にとって、サードプレイスが重要と認識されるようになったのでしょうか。
その背景要因の一つとして挙げられるのが、日本における労働生産性の低さです。労働生産性とは、従業員1人あたりの付加価値額のことで、労働の効率性を測定する尺度として用いられます。日本人というと世界の他の国々から「勤勉」「長時間労働をしている」「ワーカホリック」といわれることでも有名ですが、実際のところ、労働生産性は高くありません。
たとえば2020年に行われた調査によると、日本の労働生産性は、OECD(経済協力開発機構)加盟国の38カ国中では下位集団の23位、先進7カ国(G7)では最下位です。日本人の1時間あたりの労働生産性は49.5ドルで、アメリカの80.5ドルの6割程度の水準となっています。
こうした労働生産性の低さを是正する上で重要と考えられているのが、サードプレイスの確保です。職場でのワーキングタイムと、サードプレイスでの自由な時間との間にメリハリをつけることで、「だらだらと仕事をする」「集中力に欠けた状態で勤務し続ける」といった状況を改善できるのではないか、というわけです。
また、サードプレイスで気分をリフレッシュできるようになれば、心身状態を改善させ、労働生産性の向上につながるとの期待ももてるでしょう。
サードプレイスを持つメリット
サードプレイスを持つことには次のようなメリットがあります。
●ストレス発散
仕事で受けたストレスを、家庭で発散できるとは限りません。その場合、もし家庭と職場を往復するだけの毎日だったら、ストレスを発散できる場所がないことになります。
しかし、たとえばマスター・主人と会話を楽しめる行きつけの居酒屋・小料理屋があれば、そこでストレスを解消できます。この場合、居酒屋・小料理屋がサードプレイスに該当します。このような居場所を持つことで、ストレスを内にためずに済むわけです。
●人との交流の幅を広げられる
職場と家庭の往復だけだと、同僚・上司と家族とばかり会うようになり、新たな友人・知人を作ることが難しくなります。
しかしサードプレイスに行けば、それまでの生活では出会えないような人との交流を楽しめます。共通の趣味を持っている人など、利害関係とは無関係の人脈が広がると、それだけで人生が豊かになるでしょう。
●知的な刺激を受けられる
サードプレイスでは仕事・生活環境が異なる人とコミュニケーションを取ることができ、これまで知らなかった知識・知見を得たり、新たな経験ができたりします。家庭・職場では得られない人生の知恵を学ぶことは、自分の生き方を見直すきっかけにもなるでしょう。
●老後の居場所としても活用できる
現行の日本の制度でいえば、ビジネスパーソンは一般的に65歳~70歳で引退します。その後、居場所が家庭だけになってしまうと、本人はもちろん同居の配偶者・子どもたちも窮屈に感じる恐れがあるでしょう。もし独身・一人暮らしであれば、仕事を辞めると人と会話する機会が激減します。
そんなときにサードプレイスがあれば、家庭とは異なる社会との交流場所を確保できます。現役時代のうちから作っておけば、老後の居場所として活用できるわけです。
サードプレイスのデメリット
一方で、サードプレイスにはデメリットもあるので、実際にそのような場を作ろうとする場合は注意しましょう。
●個人情報が漏れる恐れ
家庭や職場であれば、住所や電話番号などの個人情報は共有しても基本的に問題ありません。しかしサードプレイスの場合、個人情報が漏れ、第三者に悪用される恐れがあるので、情報が漏れないように注意を払う必要があります。
●費用と時間をかける必要がある
サードプレイスを作るには、職場や家庭で過ごす以外の時間を別途確保する必要があります。そのため、仕事を圧迫したり、家族との関係性を悪化させたりしないように配慮することが求められます。
また、サードプレイス作りには、それなりの出費が必要です。バー・居酒屋であれば飲食代がかかり、サークル・クラブ活動をする際もそれなりの費用がかかります。
まとめ
職場でも家庭でもない自分の居場所であるサードプレイスは、使命感や義務感から解放され、自分らしくいられる場所でもあります。心身がリフレッシュできる時間を確保するためにも、そのような場を作ってみてはいかがでしょうか。
特に50代のビジネスパーソンにとっては老後の生きがいになる場合もあるため、シニアライフを充実させるためにも、今のうちからサードプレイスを作っておくことをお勧めします。
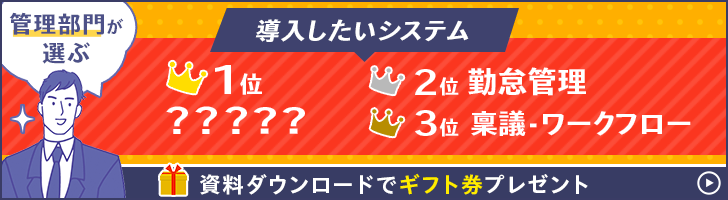
おすすめコンテンツ
関連ニュース
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

「人事部の実態と業務効率化」に関するサーベイ結果調査レポート【MURC&DCS共同制作】
おすすめ資料 -

5社比較表付き!電子帳簿保存システム選び方ガイド
おすすめ資料 -

ビジネスパーソンが知っておくべき、経費精算でも気をつけたいインボイス制度対応3つのシーン
おすすめ資料 -

<中小企業の経営者/人事の方必見!>中小企業のための はじめての産業保健
おすすめ資料 -
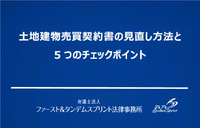
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

管理部門・士業に聞いた!「残業」の実態調査2024
ニュース -

健康経営の基礎知識。概念や取組・制度など基本情報を紹介!
ニュース -

個人投資家はどこをチェックする? 企業の非財務情報やESGの取り組みを整理するモデル開発
ニュース -
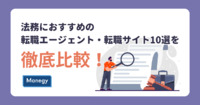
法務におすすめの転職エージェント・転職サイト10選を徹底比較!
ニュース -
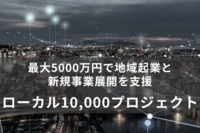
ローカル10,000プロジェクトとは?最大5000万円で地域起業と新規事業展開を支援!
ニュース -
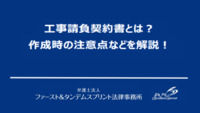
工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -
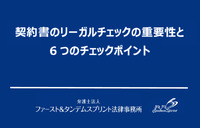
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -
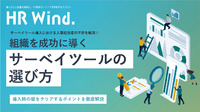
組織を成功に導くサーベイツールの選び方
おすすめ資料 -
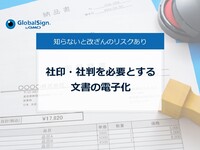
社印・社判を必要とする文書の電子化
おすすめ資料 -
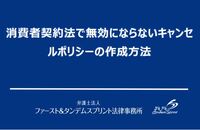
消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -

【25卒生の本音】就職後「10年以上働きたい」就活生が5割超。“社内イベントへの参加”には9割以上が意欲的
ニュース -
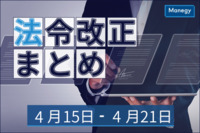
代表取締役等住所非表示措置について など|4月15日~4月21日官公庁お知らせまとめ
ニュース -

企業にとってのSNS運用と炎上対策、やってはいけない対応とは?
ニュース -
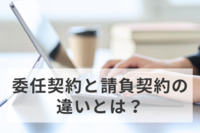
委任契約と請負契約の違いとは?業務委託契約において業務範囲を示すうえでの注意点|委託者側の契約審査(契約書レビュー)Q&A
ニュース -
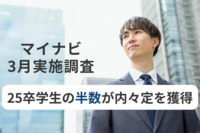
25卒学生の半数が内々定を獲得、昨年比20ポイント増 新卒採用困難に マイナビ・3月実施調査
ニュース