公開日 /-create_datetime-/
ジェンダーハラスメントとは?定義や企業が取るべき対策について解説
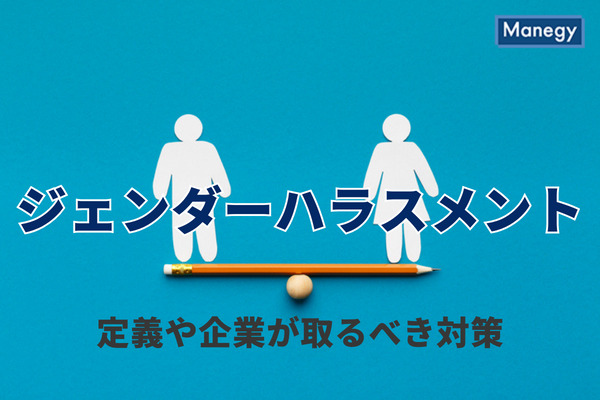
株式会社ワークポートが「職場におけるジェンダーハラスメントの実態を尋ねるアンケート調査*」の結果を公表しました。「職場は男女平等ではない」との回答が47.8%に上り、現在注目を集めています。男女雇用機会均等法などの法律が施行されているとはいえ、現場で働く人の価値観・考え方のレベルでは、まだまだジェンダー平等とはいかないのが実情といえます。
そこで今回は、ジェンダーハラスメントとは何か、について掘り下げて考えていきましょう。
*調査方法:インターネット調査
調査対象:当社を利用している全国のビジネスパーソン (20代~40代・男女) 446人
調査期間:2023年2月14日~2月21日
ジェンダーハラスメントとは
ジェンダーハラスメントとは性別に対する固定観念・役割分担意識に基づいた嫌がらせ・差別のことです。 この場合、一般的に想定されるのは女性に対する男性優位の価値観です。男性は女性よりも体力があり、仕事を遂行する能力が高く、出産・育児の影響も少なく重要なポストを任せられる、という考え方です。
「どうせ結婚・出産するときに会社を辞めるから」「女性の上司に使われるのは嫌だ」「重要な仕事は男性社員に任せた方が良い」といったことを言動、態度で表すと、ジェンダーハラスメントに該当します。
ただ、女性の側から男性の側へのジェンダーハラスメントもあります。「男のくせに情けない」「男なのに頼りにならない」といった言動も、男性に対するジェンダーハラスメントです。
また、最近特に注目を集めているのはLGBT問題です。性的マイノリティに対して「受け入れられない」といった言動・態度を示すと、ジェンダーハラスメントとみなされます。
セクシャルハラスメントとの違い
セクシャルハラスメントとは性的な嫌がらせのことで、相手の容姿や体型などに言及する発言をしたり、直接体に触ったりする行為などを指します。一方、ジェンダーハラスメントは、「男性なんだから」「女性なんだから」という性別に対する思い込み・価値観を原因とする嫌がらせ・言動です。
例えば、女性社員だけにお茶くみをさせようとすることは、セクシャルハラスメントではありませんがジェンダーハラスメントに該当します。
日本のジェンダーに対する意識は世界的に見ても低い
世界経済フォーラムは2022年7月に「The Global Gender Gap Report 2022」を発表し、各国にける男女格差を数値化した「ジェンダーギャップ指数」を明示しました。ジェンダーギャップ指数とは、「経済参画」「政治参画」「教育」「健康」の四つの分野からデータが作られ、1に近いほど完全平等に近く、0に近いほど完全不平等に近いことを意味します。
つまりジェンダーギャップ指数が低いほど男性優位の社会であり、女性はその性別を理由として不当な差別を受けていることを意味します。
この調査結果によると、最もジェンダーギャップ指数が高い国、つまり最も男女平等が実現されている国は「アイスランド」(0.908)でした。2位は「フィンランド」(0.860)、3位は「ノルウェー」(0.845)で、トップ3を北欧が占めています。「アメリカ」(0.769)は27位、「韓国」(0.689)は99位で、「日本」(0.650)はなんと116位。全146カ国なので、下から数えた方が圧倒的に早い順位です。日本は「ジェンダー後進国」の状況にあるといえます。
■関連ニュース
ジェンダー・ギャップに対する男女の認識の差 ネオマーケティング調べ
ジェンダーハラスメントへの対策
これから対策に取り組むという場合は、定期的にジェンダーハラスメントに関するヒアリング調査を行って実情を把握すること、ジェンダー理解に関する研修・勉強会の実施することなどが短期的な施策として望ましいでしょう。また、会社に相談窓口を設置するのも有効な対策です。
ただ、ジェンダーハラスメントに該当するような態度、言動が生じやすい職場は、特定のジェンダーが不利になる組織制度・体系であることが多いです。
例えば、「昇進・昇給において特定のジェンダーのみ不利になる」「管理職・役員が特定のジェンダーに集中している」といった職場で働く社員は、自然とジェンダー平等に対する意識が低くなり、ハラスメントも頻繁に生じるでしょう。
そのため企業の対策としては「昇進・昇給の男女格差をなくす」「実績に合わせて男女関係なく管理職・役員のポジションに抜擢する」といったことを、中長期的な視点で取り組んでいくこともハラスメント解消には重要です。
また、採用に関して、従業員の総数が男女どちらかに大きく偏っている場合も、ジェンダーハラスメントが起こりやすいです。例えば女性が多く勤務している職場に少数の男性が勤務するような状況だと、「男性」という括りで少数派の弱い集団との価値観が生じ、「男のくせに役に立たない」などのハラスメント言動が生じやすくなります。
男性・女性の数に大きな隔たりが出ないような採用をすることも対策の一つとなるでしょう。
まとめ
現在勤務している会社でジェンダーハラスメントを受けていて、社内に相談できる相手・窓口がないときは、各都道府県の労働局に相談するのも一つの方法です。匿名でも相談でき、本人の了承なく会社に情報提供されることはないので、安心して利用できます。問題が深刻な場合は、労働局の方から企業側へ働きかけてくれるので、積極的に利用すると良いでしょう。
今後、少子化が進展し、多くの業界で人手不足の問題が深刻化する恐れがあります。そんなとき、ジェンダー平等の働きやすい企業との評判・実績があれば、性別に関係なく優秀な人材が集まりやすいでしょう。ジェンダーハラスメント解消に取り組むことは、人材を集め、企業を存続・成長させていく上でも重要な戦略でもあるのです。
■併せて読みたい関連ニュース
ハラスメントによる離職年間約87万人 パーソル総合研究所の調査で判明
テレワークでもハラスメントは起きている!
その何気ない言動がリモハラに、リモートハラスメントの実例と対策を検証
■参考サイト
PR TIMES|【調査報告】3月8日は国際女性デー 職場の「ジェンダーハラスメント」の実態について “ジェンハラ”被害経験者は27.6% 47.8%が男女格差のある職場で働いている実態が浮き彫りに
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

【内定者フォロー施策】内定承諾後辞退を防ぐ 内定者フォロー施策アイデア43選
おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

【管理部門・士業向け】主要資格試験スケジュール一覧を一挙公開|2025年5月更新
ニュース -

ホールディングス化における 株式移転を解説! 株式交換との違いやメリット、デメリットも
ニュース -

中期経営計画で2025年にアップデートすべきこと
ニュース -

人的資本経営に向けて人事部が担うべき役割とは?
ニュース -

日本テレビが人事領域に本格参入、「日テレHR研究所」を設立し企業の人材課題解決へ
ニュース -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

Docusign CLM 導入事例(ウーブン・バイ・トヨタ株式会社)
おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

業務改善助成金とは【令和7年・2025年】中小企業が賃金を引き上げるための助成金プログラム
ニュース -

パーパスとは?企業成長におけるパーパスの役割
ニュース -

株式移転、株式交換とは? デメリットや留意点も解説
ニュース -

AI開発研究など情報通信や情報処理分野の研究開発を進める方におすすめ「戦略的創造研究推進事業(情報通信科学・イノベーション基盤創出(CRONOS))」とは
ニュース -

DXを中期経営計画に取り入れるためのポイント
ニュース












