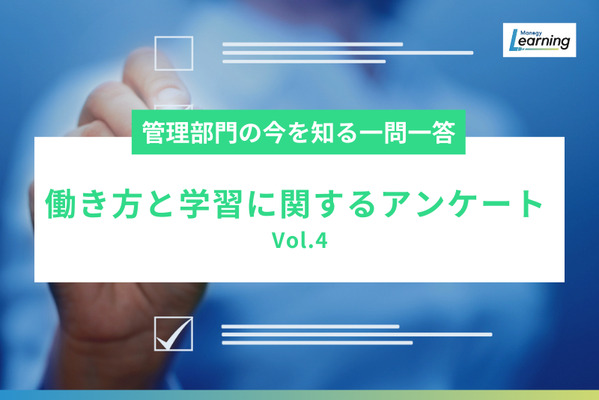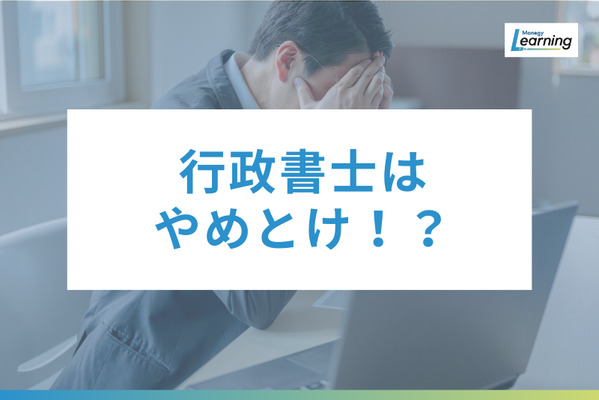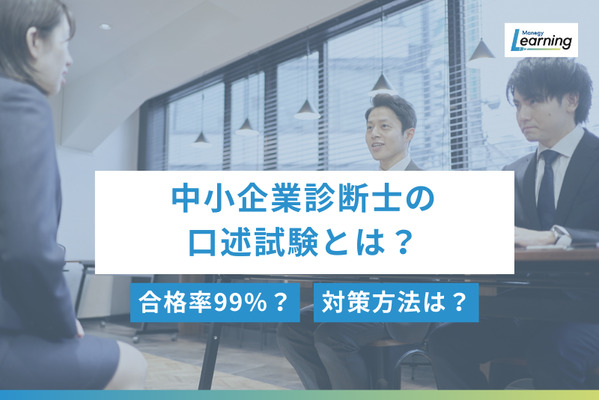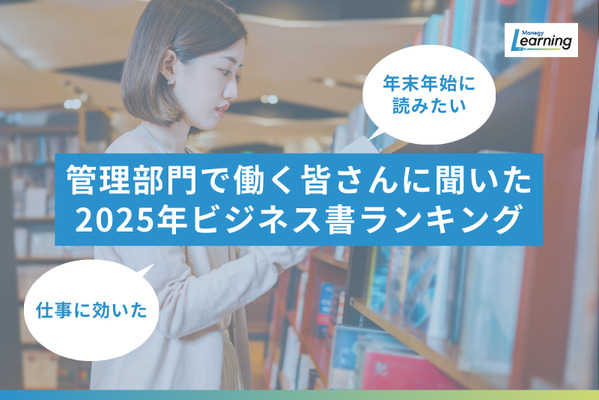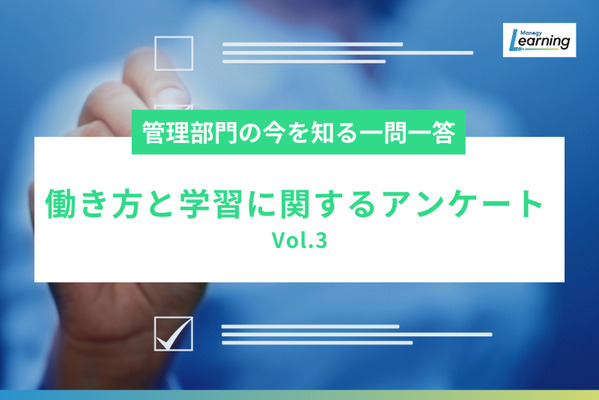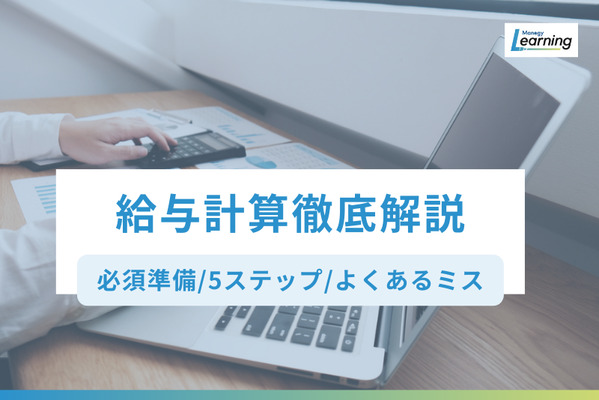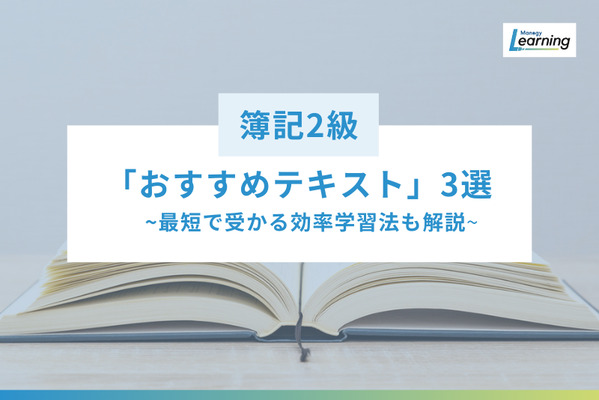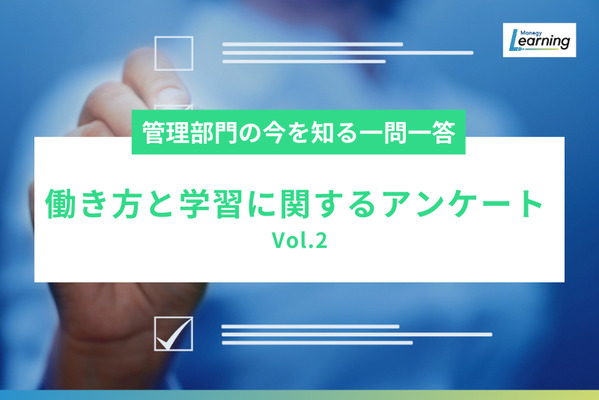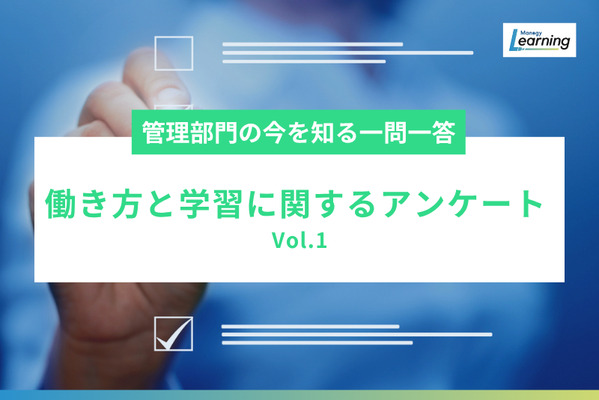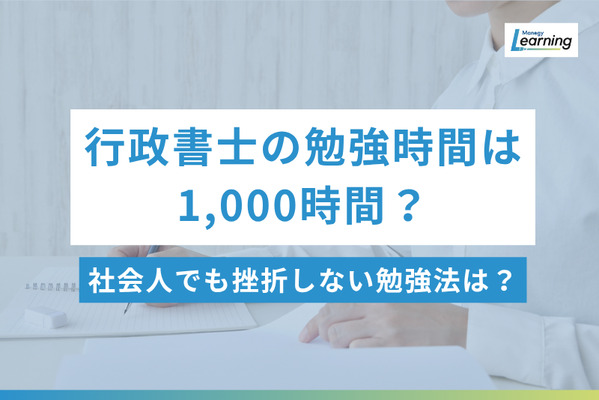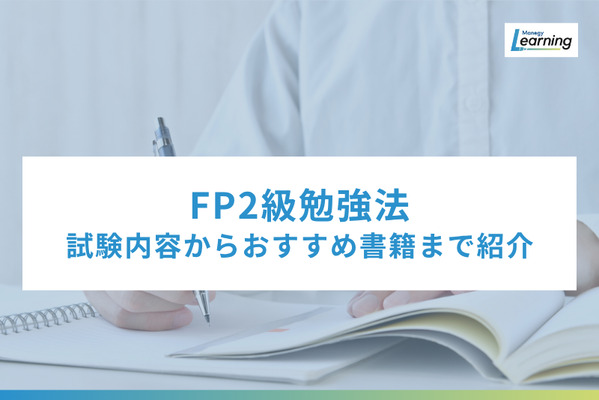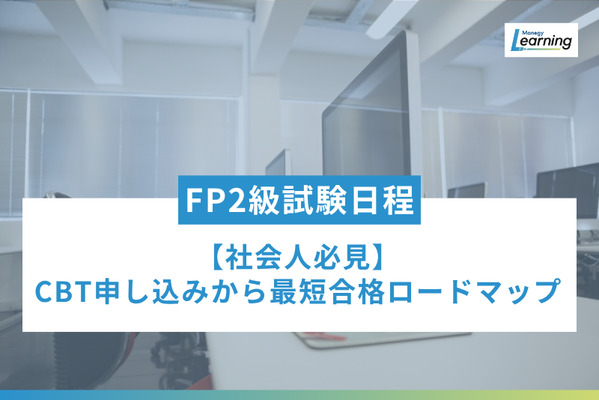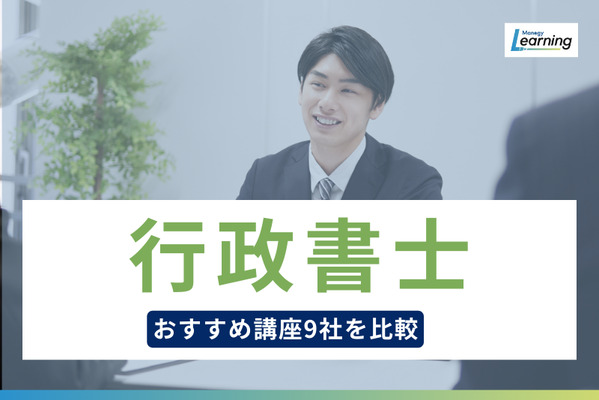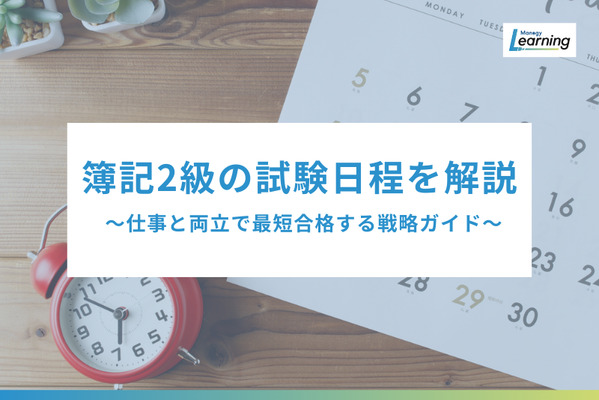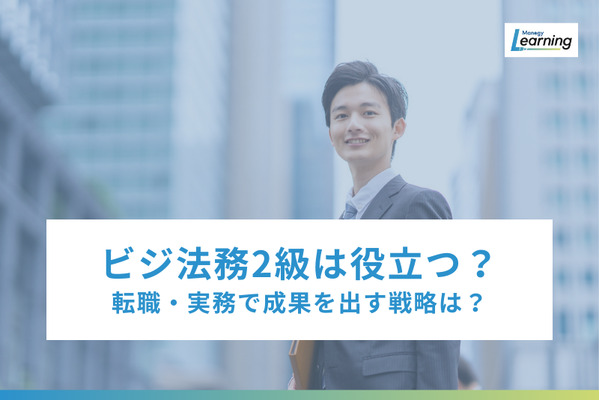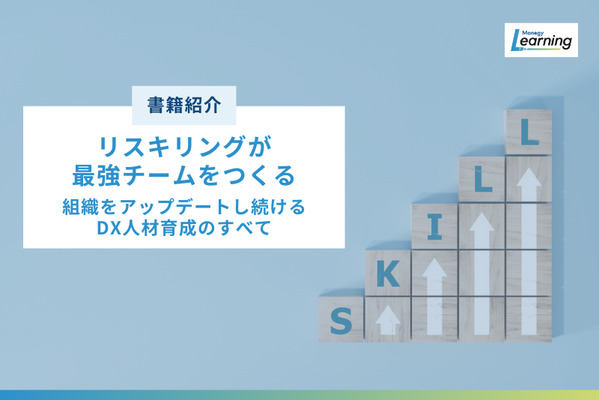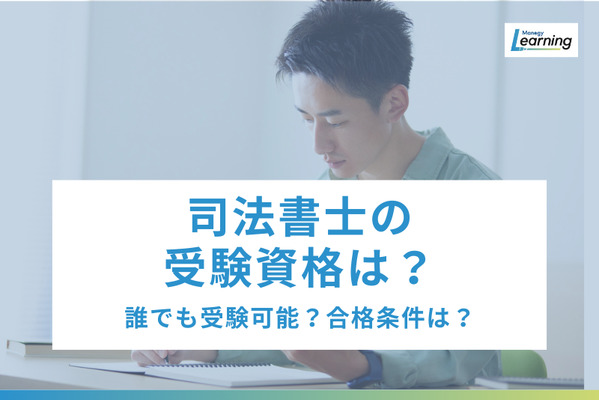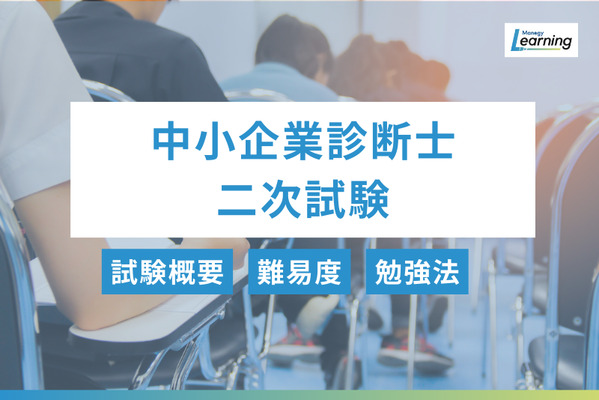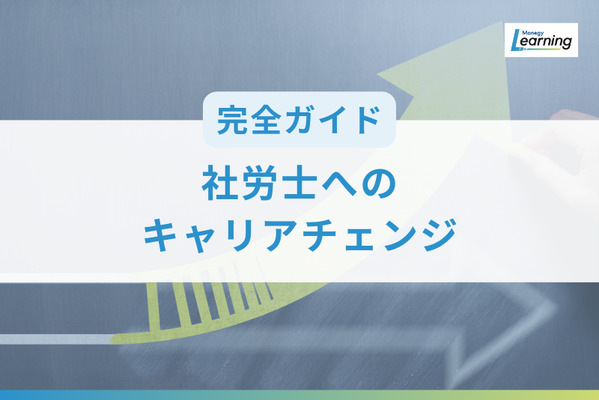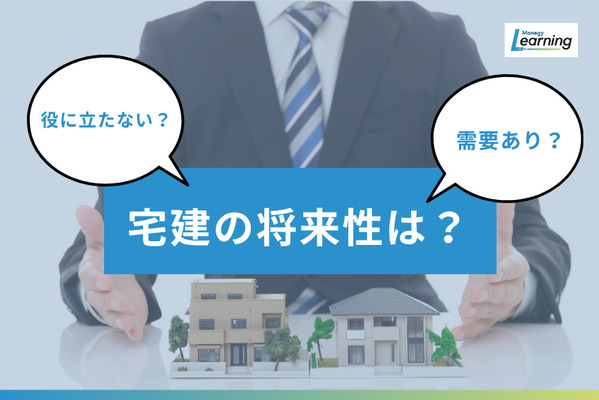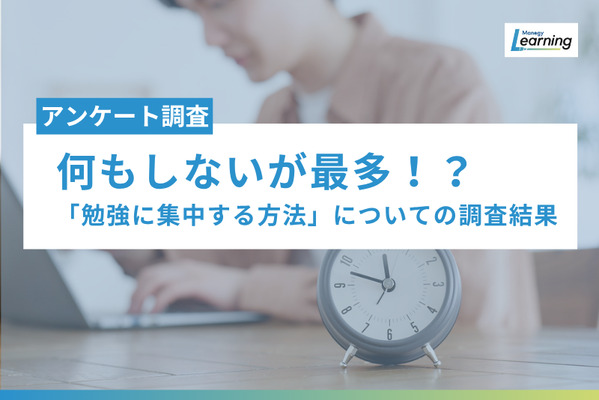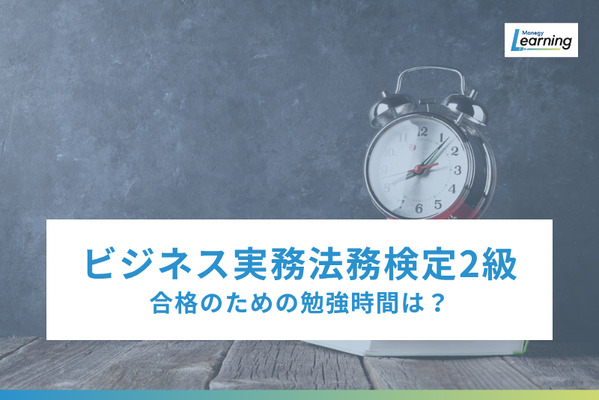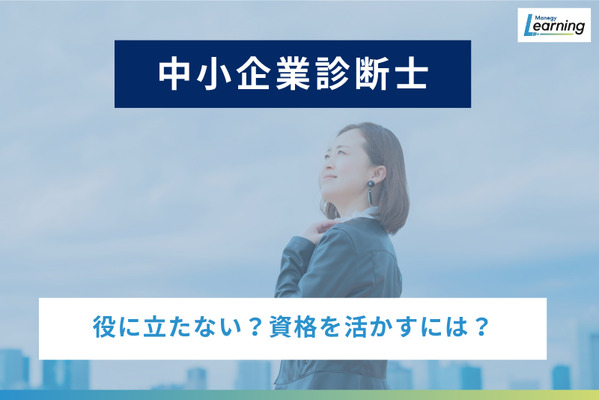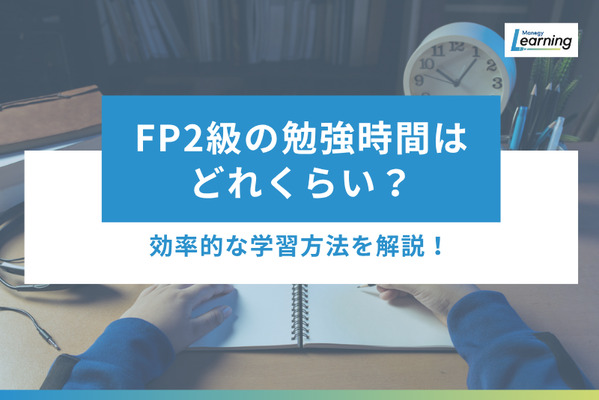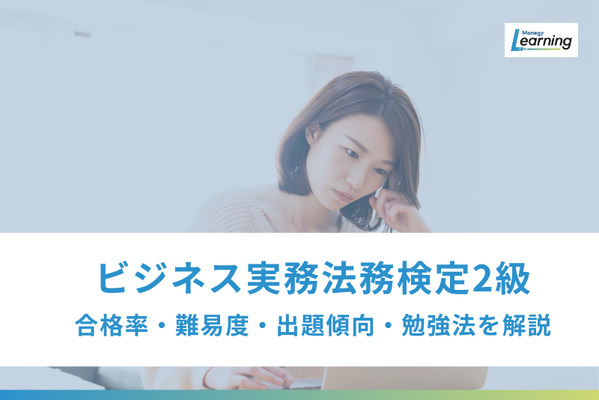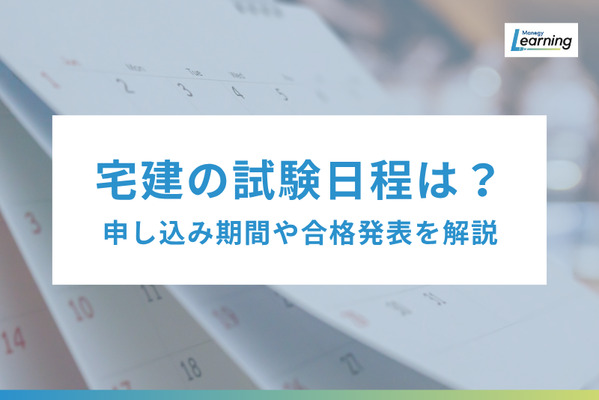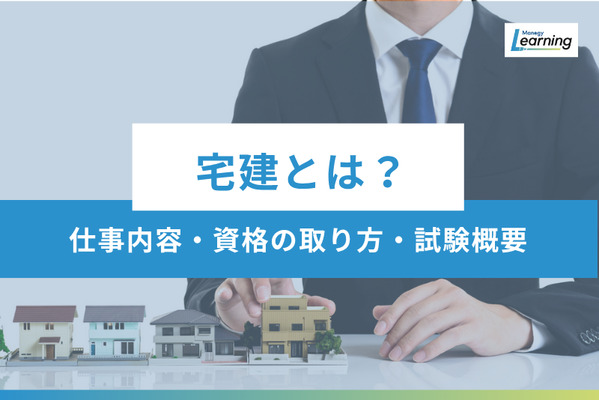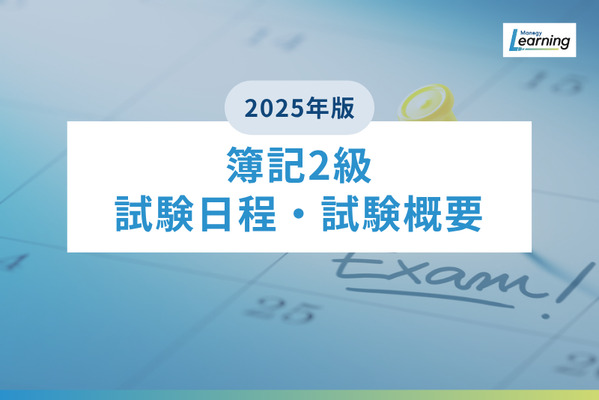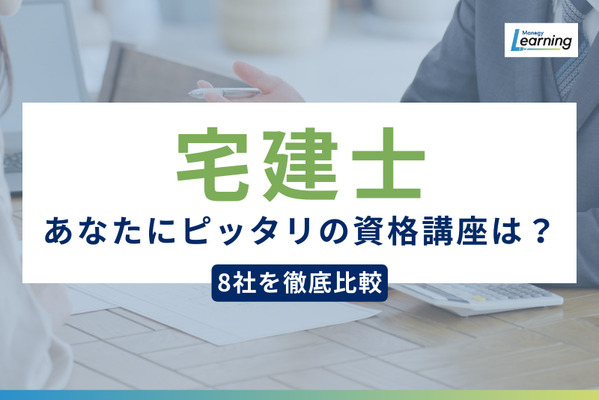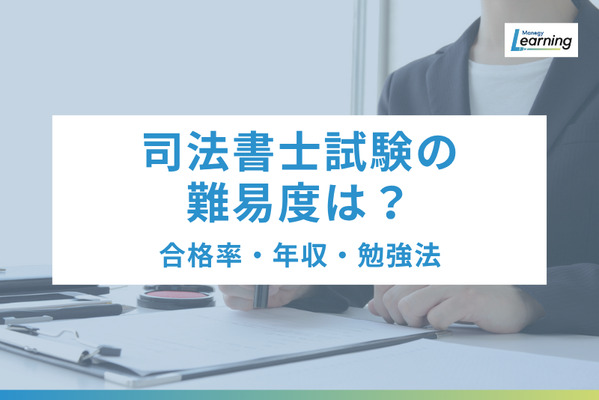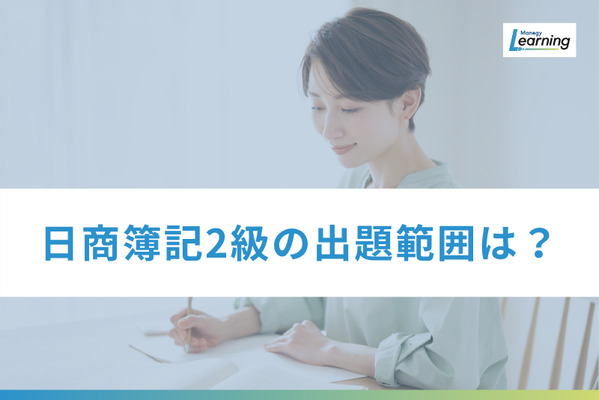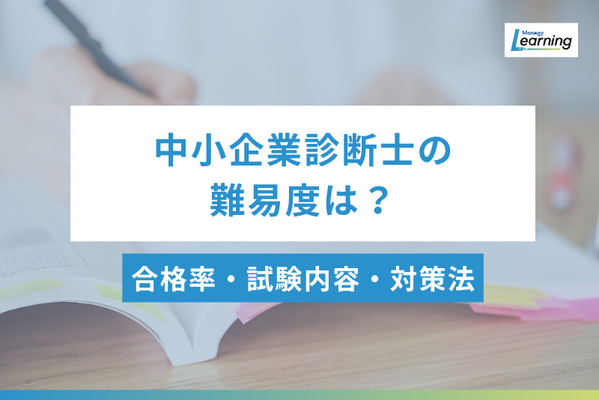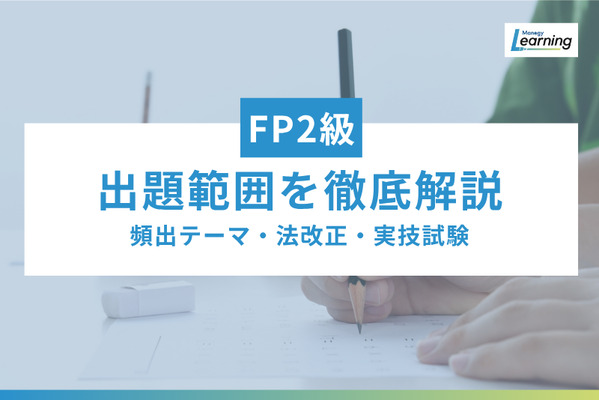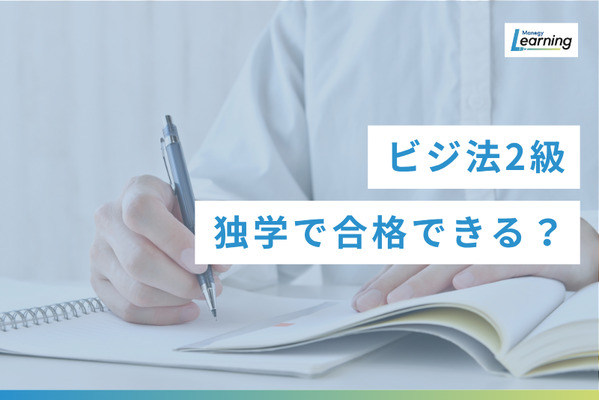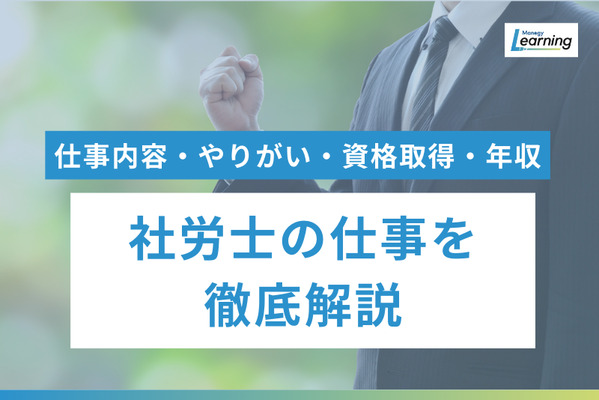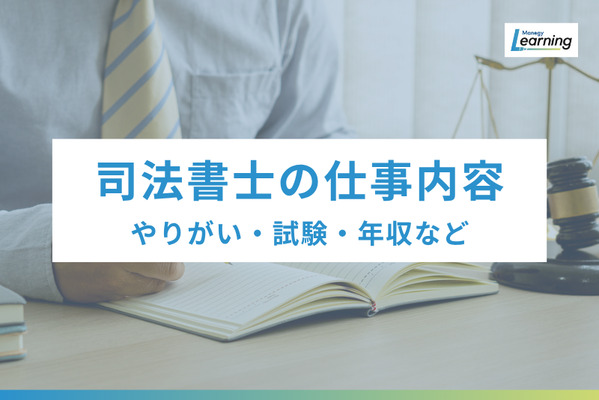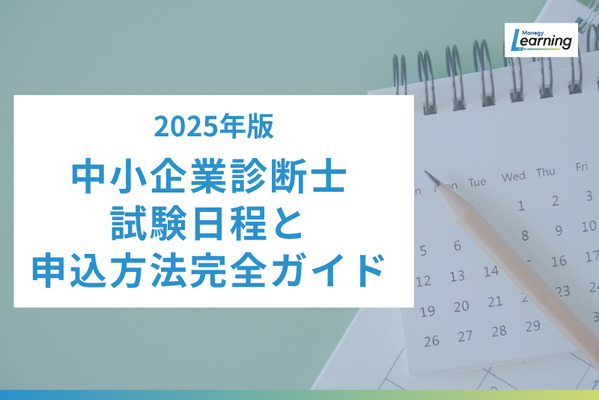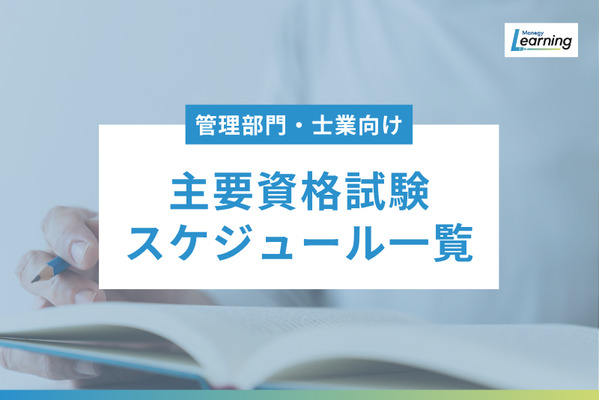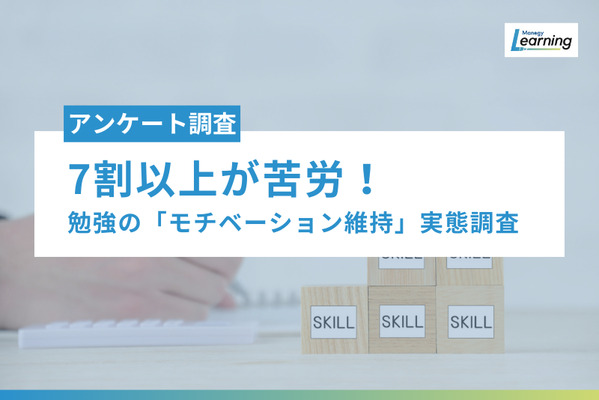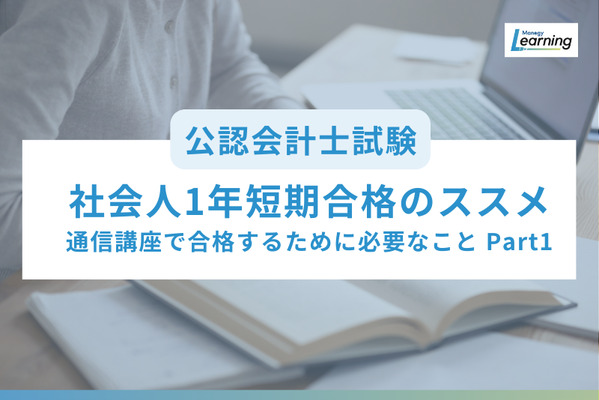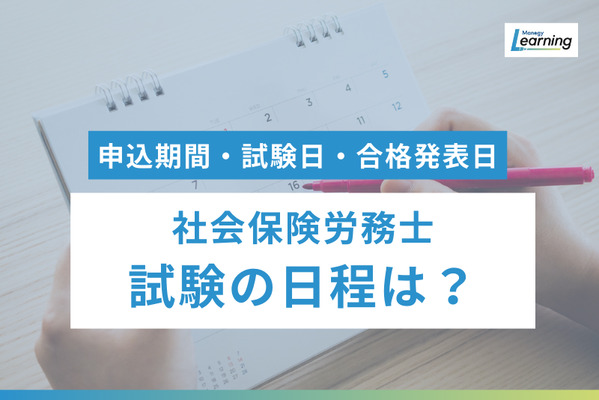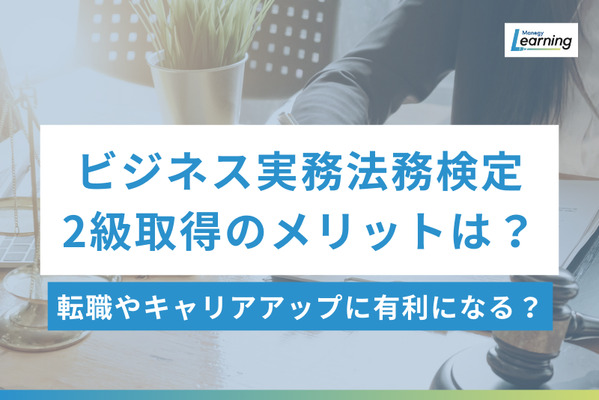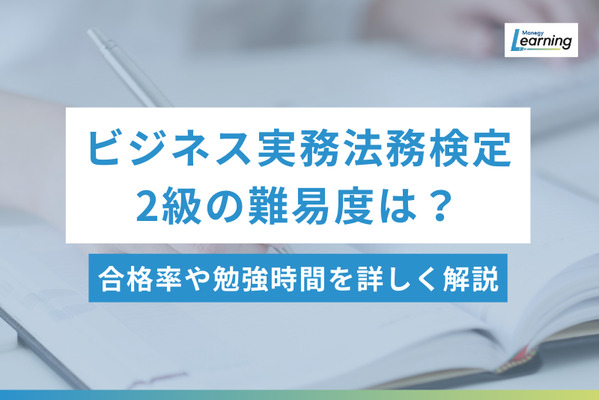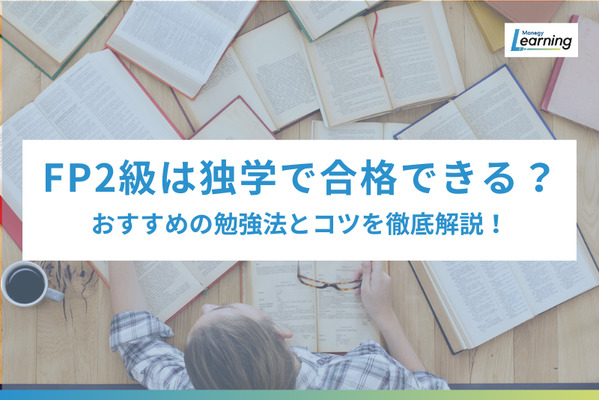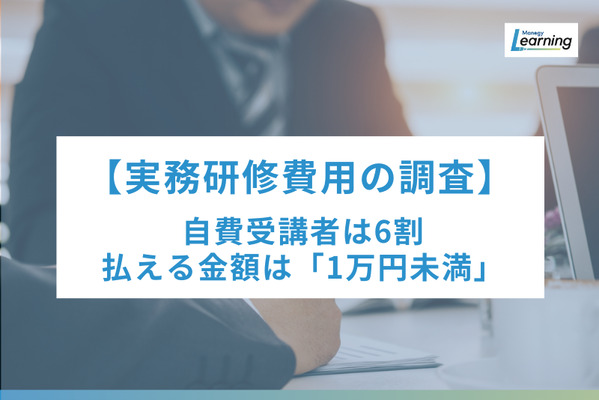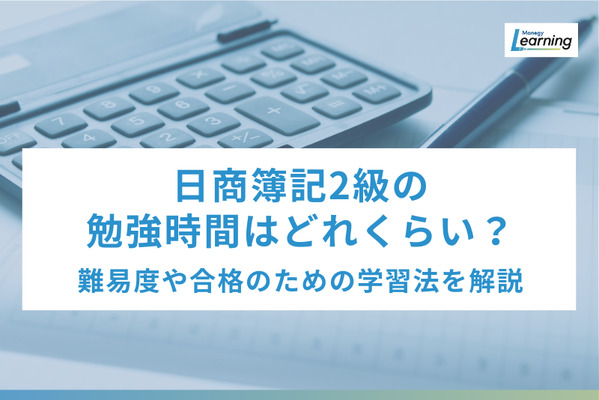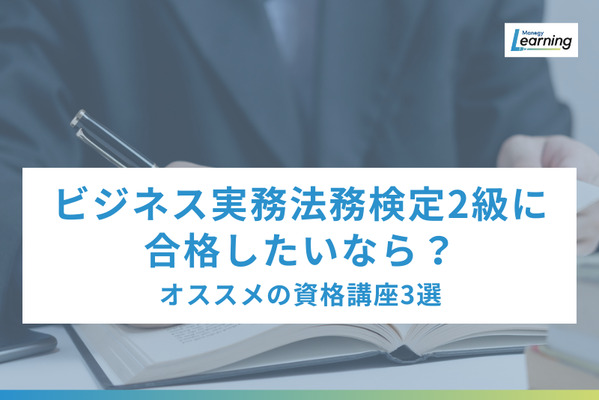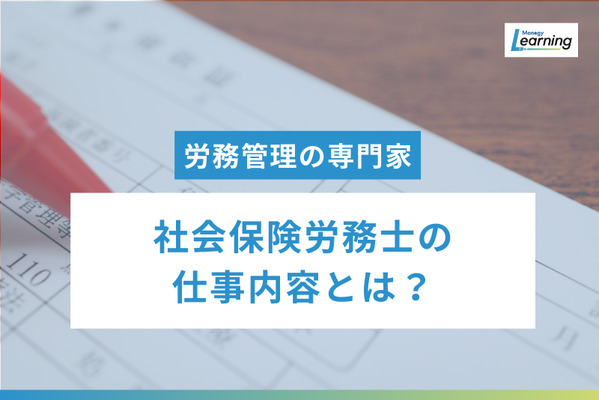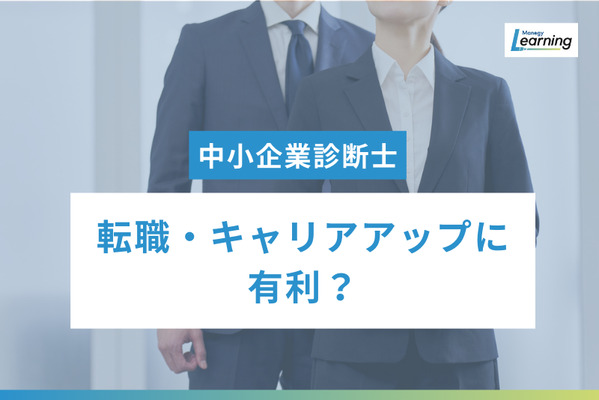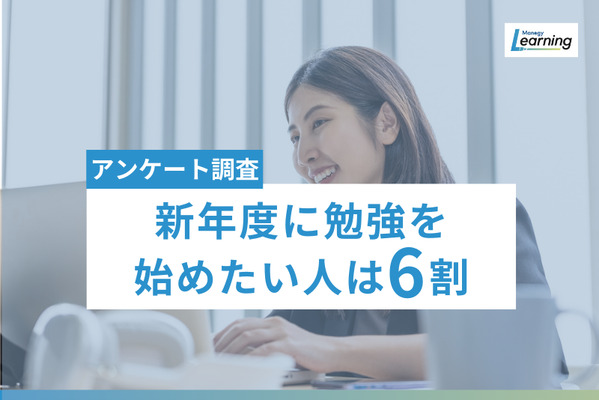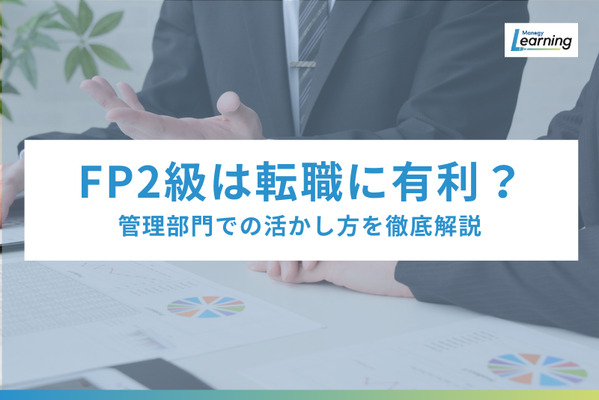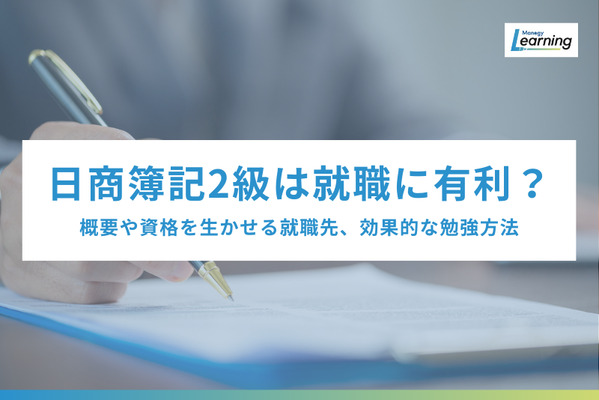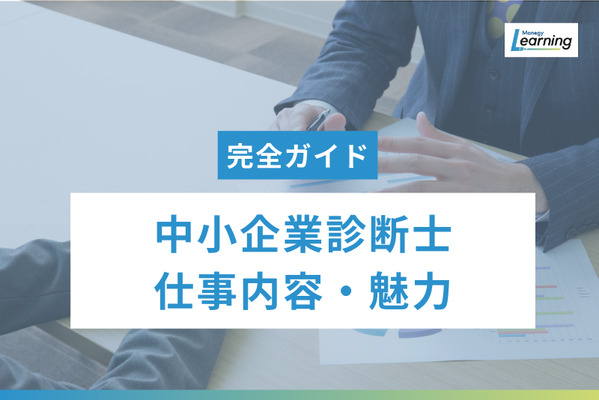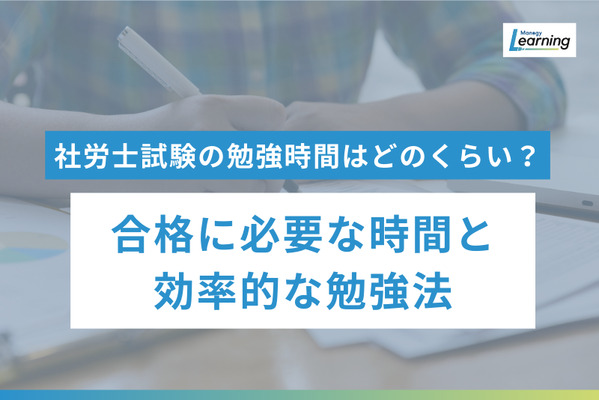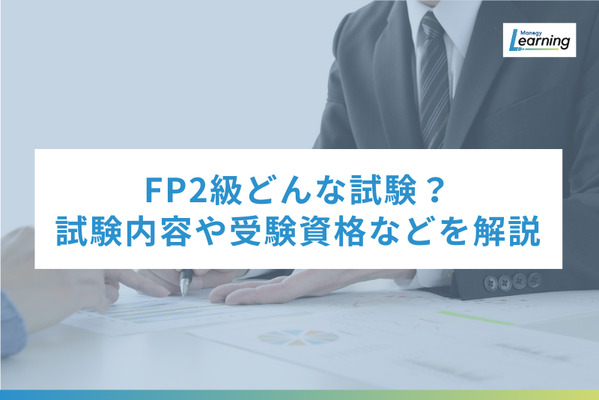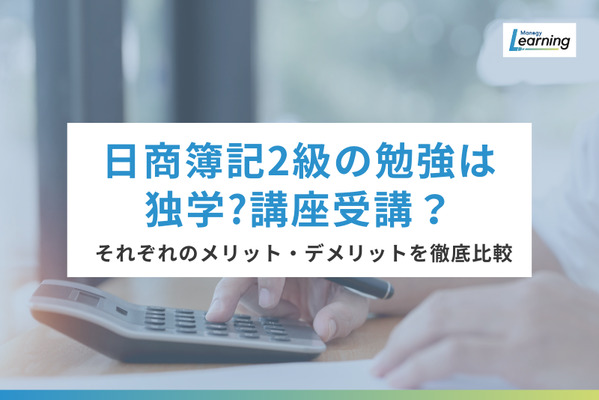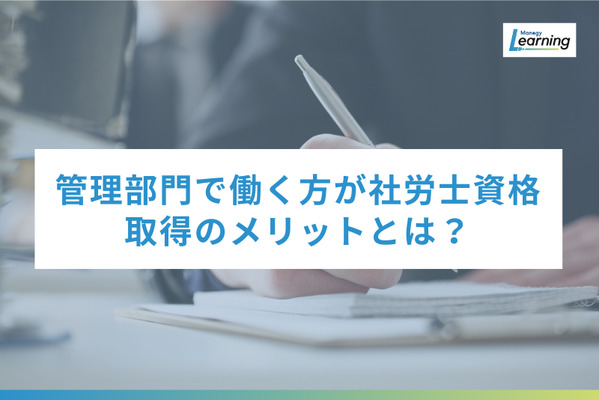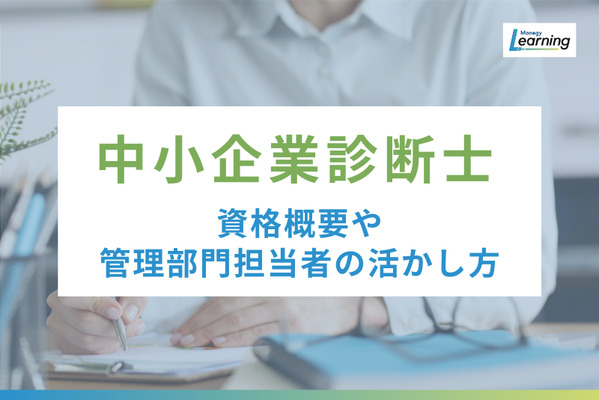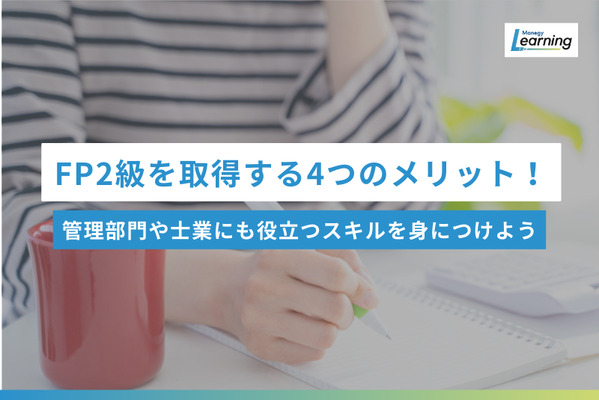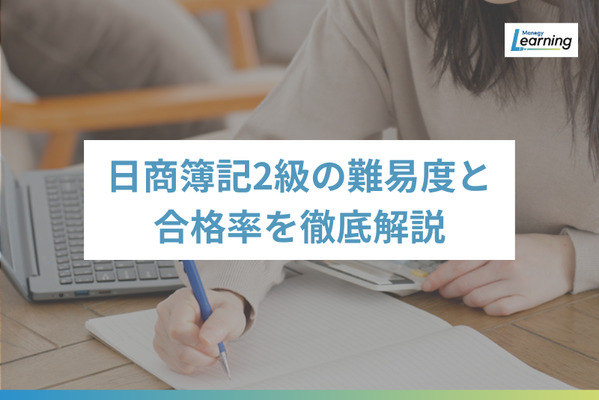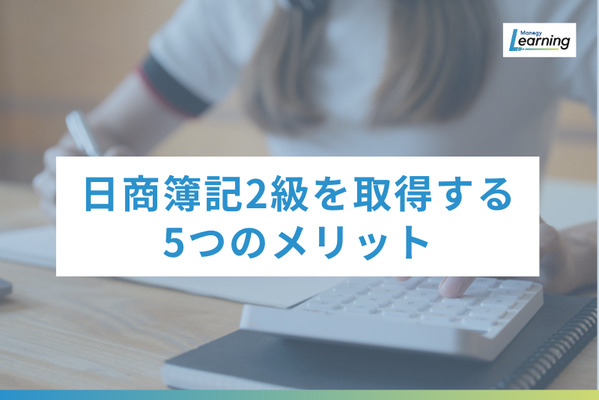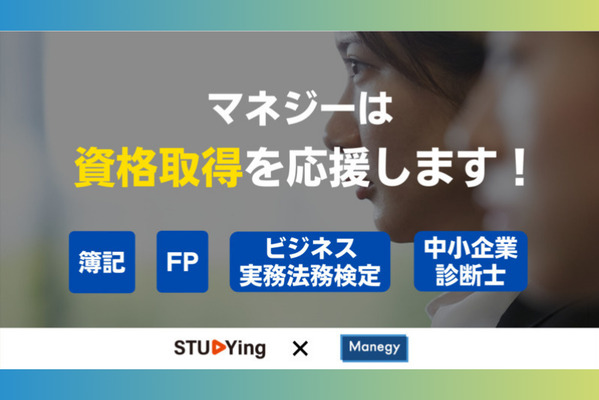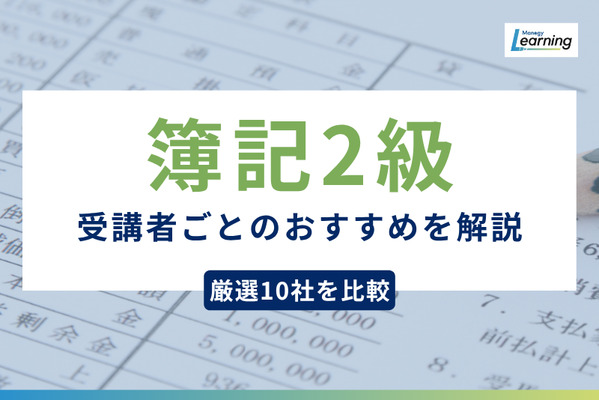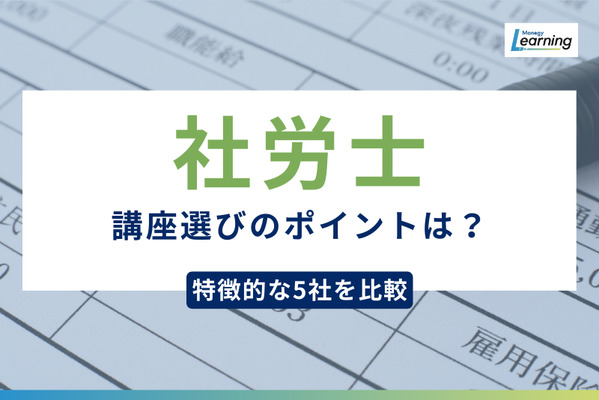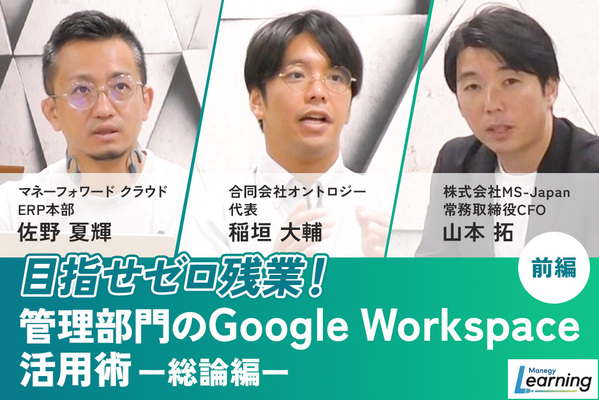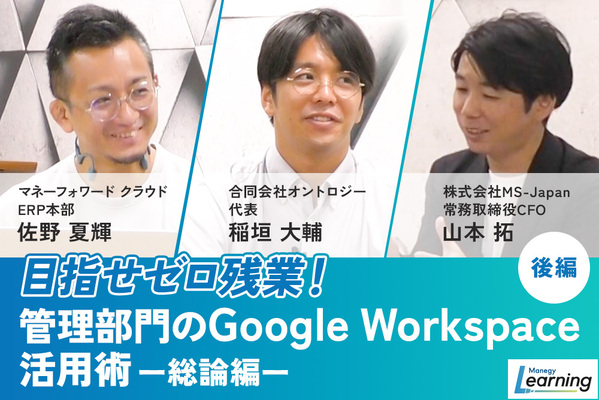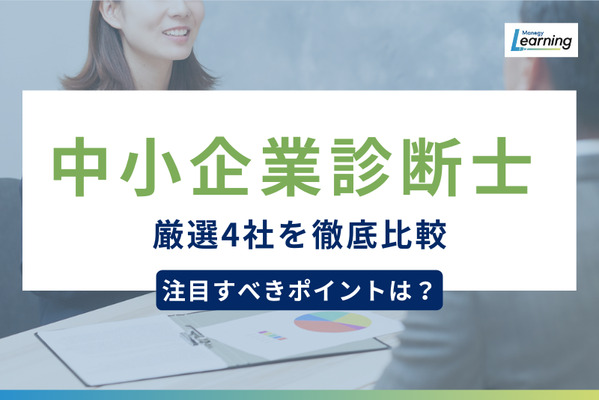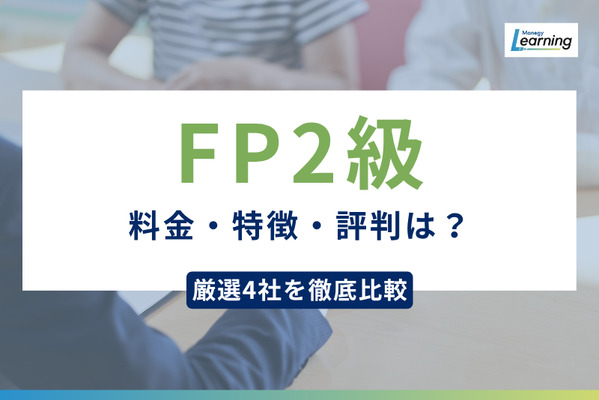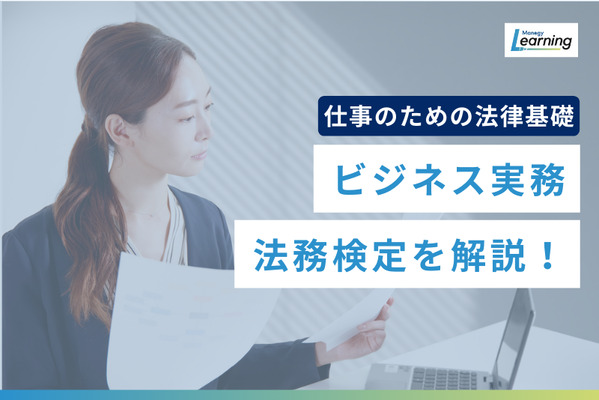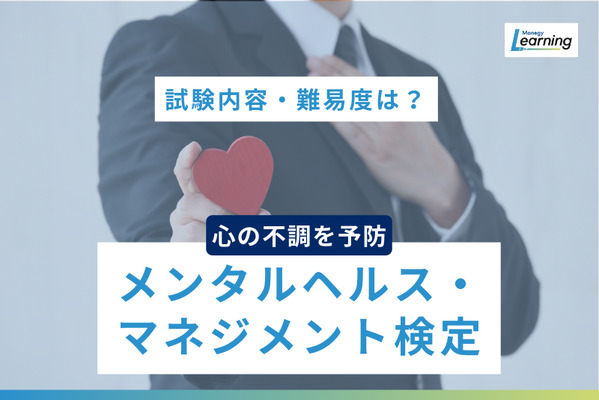司法書士は独学で合格可能?合格者の体験談から見えた「5つの壁」

後悔しない選択のために
この記事を読んでいるあなたは、「できるだけ費用を抑えて司法書士になりたい」という強い思いと、「独学合格は本当に現実的なのだろうか?」という大きな不安の間で、心を揺らしているのではないでしょうか?
仕事や家庭と両立しながら、あるいは人生を懸けた挑戦として、司法書士を目指す決意を固めたものの、その第一歩をどう踏み出すべきか、深く悩んでいるのかもしれません。
インターネットで検索すれば、「独学・短期合格!」といった華々しい成功体験が目に飛び込んできます。しかし、その裏では、声なき声として、その何倍もの人々が志半ばで挫折しているという厳しい現実もまた、存在します。
そこでこの記事では、特定の個人の体験談に偏るのではなく、数多くの合格者・不合格者の声と客観的なデータに基づき、「なぜ司法書士試験がこれほどまでに難関なのか」という事実をまず提示します。その上で、多くの独学者が直面するであろう「7つの共通の壁」を、解説します。
この記事を読めば、合理的で後悔のない学習方法を選択することができるでしょう。ぜひ最後までご一読ください。
この記事を読んだ方にオススメ!
Step 1:司法書士試験の現実を知る|データが示す客観的な難易度
まず、独学で学習を始めるかを考える前に、戦うべき相手、すなわち司法書士試験がどんなものかを正確に知る必要があります。今回は3つの客観的なデータから、その難易度を解説します。
1. 圧倒的に低い合格率:「上位5%」の狭き門
司法書士試験の厳しさは、その合格率に最も端的に表れています。直近5年分の合格率は以下の通りです。
| 試験年度 | 合格率 |
|---|---|
| 2024年度 | 5.30% |
| 2023年度 | 5.20% |
| 2022年度 | 5.19% |
| 2021年度 | 5.14% |
| 2020年度 | 5.18% |
近年の合格率は5%程度で推移しております。これは国家資格の中でも低い水準です。
2. 膨大な勉強時間:「3,000時間」という壁
司法書士試験の合格に必要とされる勉強時間は、一般的に約3,000時間と言われています。
この時間を具体的にイメージしてみましょう。
- 1年間で達成する場合: 1日あたり約8.2時間
- 2年間で達成する場合: 1日あたり約4.1時間
社会人のモデルケース: 平日2時間、休日8時間程度の勉強を、丸2年間一日も休まずに続けて、ようやく達成できる計算です。
この3,000時間という時間は、あくまで目安です。11科目にそれぞれどれくらいの時間を配分するかを考えるだけでも、その膨大さが分かります。
- 主要4科目(民法、不動産登記法、会社法、商業登記法): 約1,500時間以上
- その他7科目(民事訴訟法、憲法、刑法など): 約1,000時間
- 直前期の演習・模試など: 約500時間
日々の仕事、家事、育児、プライベートな付き合いと両立させながら、この学習時間を捻出し続けること自体が、最初の大きなハードルとなるのです。
3. 過酷な試験形式:知識・思考力・体力の限界に挑む
年に一度、7月の第一日曜日に実施される筆記試験は、まさに一日がかりの総力戦です。
午前の部(2時間): 択一式35問(憲法、民法、刑法、商法・会社法)
午後の部(3時間): 択一式35問(不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法など)+記述式2問(不動産登記・商業登記)。
特に受験生を苦しめるのが「午後の部」です。3時間という極めて短い時間の中で、難解な択一問題をこなしつつ、複雑な事例問題である記述式を2問も解き切らなければなりません。
記述式の問題では、十数ページにわたる事実関係を正確に読み解き、当事者の希望を実現するために、どのような登記を、どのような順番で、どの法令に基づいて申請すべきかを判断し、最終的に登記申請書を紙の上に再現する能力が求められます。知識量だけでなく、高度な情報処理能力、時間管理能力が試されます。
この筆記試験の合格者のみが、次の「口述試験」に進むことができます。口述試験の合格率は高いものの、司法書士としての適性や基本的な知識を問われるため、油断はできません。
この記事を読んだ方にオススメ!
Step 2:なぜ独学は難しいのか?|メリットを打ち消す「5つの壁」
非常に難易度の高い試験ですが、「費用を抑えられる」「自分のペースで学べる」といった、メリットがあるため、独学を検討する人も一定数います。
しかし、長期戦となる司法書士試験では、そのメリットが弱点に変わってしまう場合があります。
多くの人が独学で挫折するのは、本人の能力だけの問題ではなく、独学という勉強スタイルそのものに難しさがあるからです。これから、その理由である「5つの壁」について解説します。
【壁①:時間の壁】「時間がない」が致命傷になる
司法書士試験の合格には約3,000時間が必要と言われていますが、これはあくまで効率的に学習を進められた場合の目安です。
独学の場合、市販の分厚いテキストを隅から隅まで完璧に理解しようとしたり、出題可能性の低い論点に深入りしすぎたりと、非効率な学習に陥る危険があります。その結果、合格レベルに達するために3,000時間を大幅に超える時間を費やしてしまうケースも少なくありません。
講座の解決策▶
予備校のカリキュラムや教材は、過去の試験を徹底的に分析し、「合格に必要な知識」が凝縮されています。独学で陥りがちな「出題可能性の低い論点」や「深入りすべきでない箇所」はあらかじめ削ぎ落とされ、注力すべきポイントが明確です。
プロが設計した「合格への最短ルート」を辿るため、市販のテキストを一人で読み解く非効率な学習を避けられ、結果として学習時間を大幅に短縮でき、多忙な方でも効率的に合格を目指せるよう設計されています。
【壁②:計画の壁】優先順位を見極め全11科目を学習する必要がある
独学の場合、全11科目という広い学習範囲の計画を、すべて自分で立てなければなりません。
しかし、科目同士には深いつながりがあります。例えば「民法の相続」を理解していないと、「不動産登記法の相続登記」は学習できません。こうした科目間の関連性を、学習を始めたばかりの方が一人で把握するのは非常に困難です。
その結果、学習の優先順位や順番を間違えやすくなります。よくあるのが、「まず民法から」と始めたものの、完璧を目指すあまり半年以上もかかってしまう、といった失敗です。このように、非効率な進め方で貴重な時間を失ってしまう危険があります。
講座の解決策▶
予備校が提供するカリキュラムは、長年の指導実績と合格者データに基づいた「合格への最短ルート」そのものです。どの時期に、どの科目を、どのレベルまで仕上げるべきかが明確に示されています。例えば、民法を学んだ直後に、その知識を直接応用する不動産登記法を学ぶように設計されているなど、最も効率的な学習順序が確立されているため、受験生は迷うことなく学習だけに専念できます。
【壁③:理解の壁】「質問できない」が非効率と不安を生む
独学では、難解な法律の概念や、最大の関門である記述式問題に必ず突き当たります。特に記述式では、市販の問題集を解いても、自分の答案が「なぜ間違っているのか」「どこが減点対象で、どう書けば満点に近づくのか」を客観的に評価してくれる存在がいません。結果、模範解答をただ書き写すだけの非効率な演習を繰り返してしまい、実力が思うように伸びないという事態に陥る可能性があります。
講座の解決策▶
講師への質問制度や、プロ講師による詳細な添削指導は、独学では決して得られない価値があります。添削では、単なる正誤だけでなく、「なぜこの判断に至ったのか」という思考プロセスや、「根拠条文をどう示すべきか」といった答案作成の作法まで具体的に指導してくれます。このフィードバックの有無が、理解の質とスピードを飛躍的に向上させるのです。
【壁④:情報の壁】「情報格差」が合否を分ける
司法書士試験は、毎年のように行われる法改正や、最新の重要判例が出題されるため、最新情報のキャッチアップは非常に重要といえます。独学者が、官報や判例集を常にチェックし、膨大な情報の中から試験に直結する重要なものだけを見極めて収集し続けるのは、多大な労力がかかります。
講座の解決策▶
予備校を利用すれば、法改正や最新判例といった重要情報は、講義や専用の教材を通じて自動的に提供されます。常に最新の試験傾向を反映した教材で学べるため、情報収集に余計な時間を割く必要がなく、情報戦で不利になることはありません。
【壁⑤:精神の壁】「孤独」という最大の敵との戦い
合格者の平均受験回数は3〜5回とも言われ、長期戦を覚悟しなければならない試験です。相談できる相手もいない環境で、模試の成績が伸び悩むスランプや、「本当にこのままで合格できるのか」という焦りや不安に打ち勝ち学習を進めなければなりません。また、SNSで他の受験生の進捗を見ては、自信を喪失してしまうケースも少なくありません。
講座の解決策▶
講師からの激励メッセージや、同じ目標を持つ仲間とのオンラインでの繋がりが、孤独感を和らげ、モチベーションを維持する上で大きな支えとなります。定期的なカウンセリング制度を設けている予備校もあり、学習面だけでなく精神面でのサポート体制も充実しています。
これらを踏まえて、「自分には講座受講があっているかも…。」と思った方にはこちらの記事がおすすめです。
この記事を読んだ方にオススメ!
Step 3:独学で合格を目指すために大切なこと
これら「5つの壁」を理解した上で、なお独学での合格を目指すのであれば、相応の覚悟と、極めて緻密な戦略が不可欠になります。
独学合格の可能性がある人の条件
自己管理能力を持つ人:
いかなる状況でも計画通りに学習を継続できる強靭な精神力を持つ。
法律の学習経験がある人:
法学部出身者や他の法律系資格の学習経験があり、法律用語や独特の思考法に慣れている。
孤独を力に変えられる人:
他者と比較せず、一人で黙々と作業に没頭することを得意とする。
独学合格のための3つの必須ポイント
「逆算思考」による徹底したスケジュール管理:
試験日から逆算し、「年→月→週→日」の単位で詳細な学習計画を立てる。計画の進捗を定期的に確認し、遅れた場合の予備日も必ず設けておくと安心です。
教材の一元化と反復練習:
使用する基本テキストは1冊に絞り、これを完璧にする気持ちで学習を進めましょう。過去問や模試で得た知識、間違えた論点などを全てそのテキストに書き込み、情報を集約します。その一冊と過去問を、繰り返し徹底的に反復しましょう。
情報収集の習慣化と取捨選択:
法務省のウェブサイトや官報など、信頼できる一次情報源を定期的に確認して、最新情報を押さえましょう。
結論:あなたの真の目的は何か?後悔しないための合理的選択
ここまで、独学の厳しさと、それでも挑戦するための戦略を詳しく解説してきました。最後に、あなた自身に問いかけてみてください。
あなたの目的は「独学という手段で合格すること」でしょうか?
それとも「1日でも早く司法書士になるという目的を達成すること」でしょうか?
もし後者であるならば、手段に固執するあまり目的から遠ざかっては本末転倒です。講座の利用は「楽をする」ためではなく、合格の確実性を最大限に高めるための「賢明な投資」であり、不合格のリスクに対する「有効な保険」なのです。
まとめ:あなたの挑戦を、後悔で終わらせないために
司法書士を目指すという決意は、とても素晴らしいものです。
あなたの挑戦が、情報不足による無計画なものではなく、現実に即した「実現可能な計画」となるように、この記事がお役に立てば幸いです。解説した「5つの壁」をご自身の状況と照らし合わせ、冷静に今後の学習方法を判断してみてください。
数年後、「あの時、もっと賢い選択をしていれば…」と後悔することのないよう、あなたにとって最善の道が選べることを心から願っています。

Manegy Learning
Manegy Learningは管理部門・士業の皆さまに向けて、実務に役立つTIPSや資格取得のためのスクール取得などの情報を発信し、みなさまの学びをサポートします。
MS-Japan
https://www.manegy.com/learning/