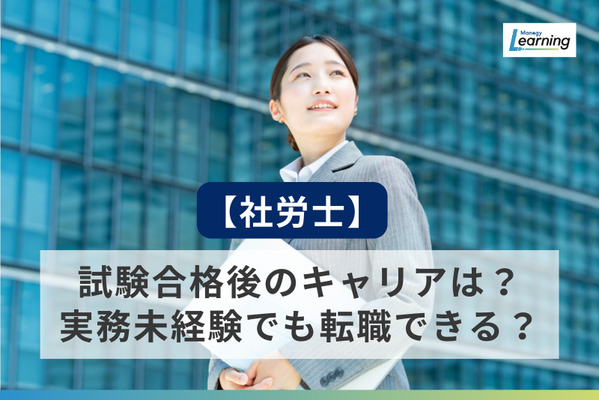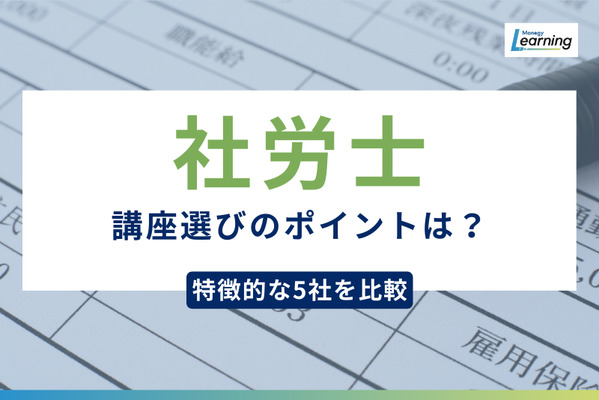【社労士解説】試験合格に向けた勉強のコツと学習計画の立て方をわかりやすく紹介
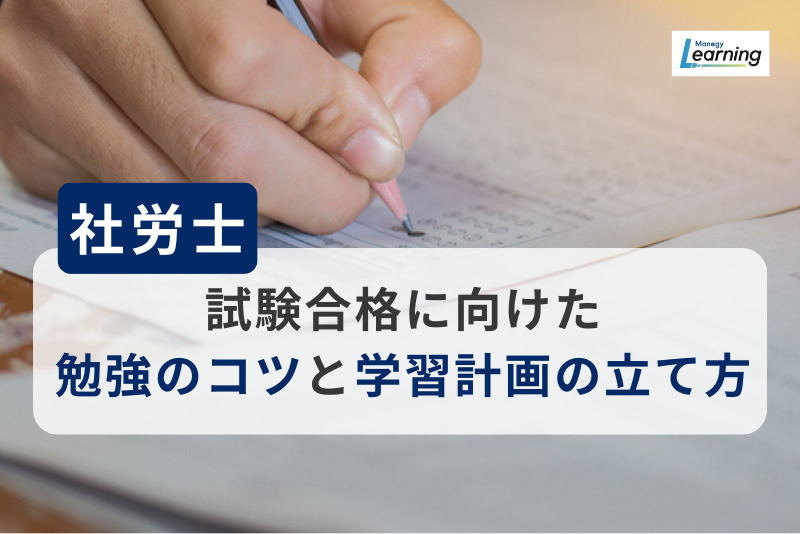
社労士試験の学習をするにあたって、そもそも勉強方法が想像できない、あるいは勉強を開始はしているけれど、今の勉強方法で合っているのかがいまいち自信がない等、一人で悩んではいませんか?特に独学で学習をされる方は、相談にのってもらえる相手もいないので不安になりますよね。
このコラムでは、そんな方のために、試験合格に向けた勉強のコツと学習計画の立て方をご紹介していきます。是非今後の学習に役立てて頂ければと思います。
社労士試験を合格する勉強のコツ
まずは、社労士試験の基本となる「労働基準法」から学習をスタートしましょう。
労働基準法は社労士試験の中の憲法のようなものであり、全ての労働科目の基本となります。労働基準法の趣旨をしっかり理解することで、他の科目へスムーズに移ることができますし、年次有給休暇、割増賃金、休憩時間・休日等、社会人にとっては比較的馴染みやすい内容も多くなっているので、とりかかりやすい科目ともいえるでしょう。労働基準法でまずは労働科目の基礎を理解し、応用となる科目に取り組んでください。
他にも「労働保険徴収法」は「労災保険法」「雇用保険法」両者の徴収手続について定めた法律です。そのため、「労災保険法」「雇用保険法」を先に学ぶべきだといえるでしょう。
また、社会保険科目では「健康保険法」が最も歴史のある法律であるため「厚生年金保険法」と「国民年金法」よりも先に勉強を始めるべきです。
そして、「国民年金法」と「厚生年金法」は年金制度でまさに同じ関係にあるといえます。1階部分が「国民年金法」、2階部分が「厚生年金法」と例えられるように、この順番で勉強をしましょう。何事も基礎が大切です。
順番としては、
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労災保険法
- 雇用保険法
- 労働保険徴収法
- 労一
- 健康保険法
- 国民年金法
- 厚生年金保険法
- 社一
という順番に理解を進めていくのが、社労士試験において、いち早く合格する秘訣です。これまで学んだ法律を復習しながら勉強することで、理解が進みやすくなるでしょう。
適切な学習開始のタイミングとは
社労士試験は科目数が多く、試験範囲が極めて広いことが最大の特徴です。そのため、計画もなく、考えなしに勉強をはじめても、試験までに学習を間に合わすことができなかったり、理解が進まずに挫折してしまう危険性が高いです。事前にしっかりと学習計画を立て、きっちりと勉強スケジュールを進めていくことで、初学者でも無理なく合格を目指すことができます。
社労士試験は、毎年8月下旬に試験が行われます。社労士試験に合格するには一般的に、最低でも「1000時間」もの勉強時間が必要といわれています。2年目、3年目の受験生であれば、その2倍、3倍と学習をしているわけですから、初学者の場合は「最低でも1000時間」という指標は肝に銘じて学習を開始してください。10科目という社労士試験の膨大な試験範囲を網羅し、合格レベルに達するには十分な学習期間を確保する必要があるのです。9月から勉強を開始すると、試験本番までちょうど1年間です。初学者の場合、1年程前から学習を開始するのがいいでしょう。
学習計画の立て方とポイント
ここからは1年で合格するための学習計画のポイント、スケジュールについてご紹介していきます。
まず、合格までに最低1000時間の学習が必要といわれていますが、試験に落ちてしまう方の多くは、そこまでの勉強時間の確保が出来なかった方ということになります。勉強時間を確保してコツコツと勉強を重ね、試験当日までにその記憶した内容をしっかりと維持をして臨むことが必要です。1年間で1000時間の勉強時間を確保するためには、平均すると、平日休日問わず「毎日3時間程度」の学習が必要となります。中には平日は仕事が忙しいという人もいるでしょう。その場合は、平日2時間ずつ、週末5時間ずつのように調整をし、1週間で20時間以上の学習時間を確保することを目安にしてください。
9月から学習を開始した場合のスケジュールの目安は以下となります。
<学習スケジュールの例>
・9月~12月末までに労働科目(労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労一)を一通り終わらせる。
・年末年始休暇で労働科目の総復習を通しで行う。
・1月中旬~5月のGW前までに社保科目(健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、社一)を一通り終わらせる。年金科目については強化期間も作る。
・GWで社会保険科目の総復習を通しで行う。
・5月の中旬から~7月は総復習・直前対策。
・8月は弱点克服。テキストの読み込み。
より詳細な学習スケジュールは以下のコラムに掲載しております。
ぜひ参考にしてください。
まとめ
この記事では、社労士試験の合格に向けた勉強のコツと学習計画の立て方についてご紹介をしました。
社労士試験は10科目と出題範囲が広く、合格することは難関ですが、しっかりと学習計画を立て、コツコツと勉強を継続すれば合格は見えてくる資格です。
自分で学習計画やスケジュール通りの学習をすることが難しい場合には、講座利用も視野に入れて学習を進めてみてください。通信講座を利用すれば自分でスケジュールを立てる必要もなく、効果的な順番で学習が進められ、予備校によっては講師のサポートもあるため、勉強のモチベーションを保つのに非常に有効です。独学で学習するよりも非常に効率的といえるでしょう。

アガルートアカデミー
アガルートアカデミーは資格試験のオンライン予備校です。 アガルートアカデミーを運営する株式会社アガルートは、「教育」によって「人を変え、社会を変え」ることをミッションに、アガルート学習コーチングやアガルートメディカル等も運営しています。
株式会社アガルート
https://www.agaroot.jp/