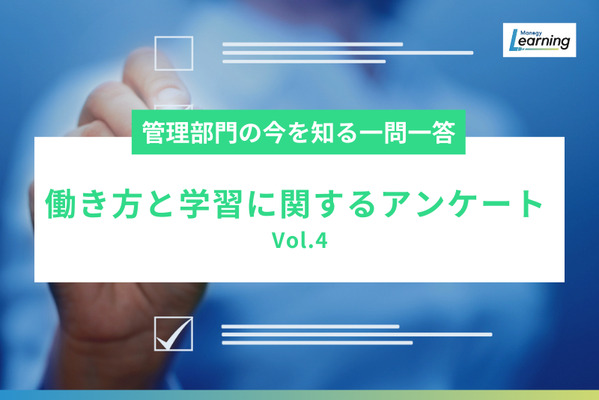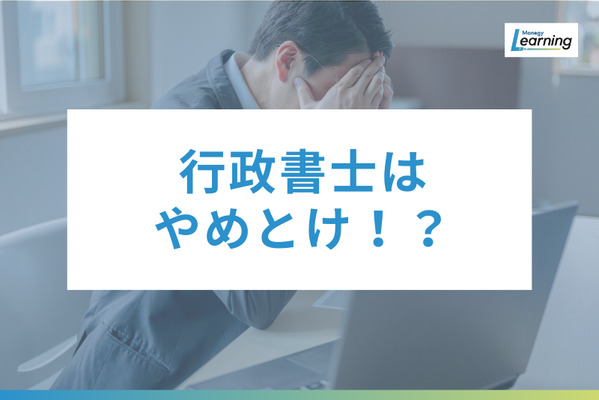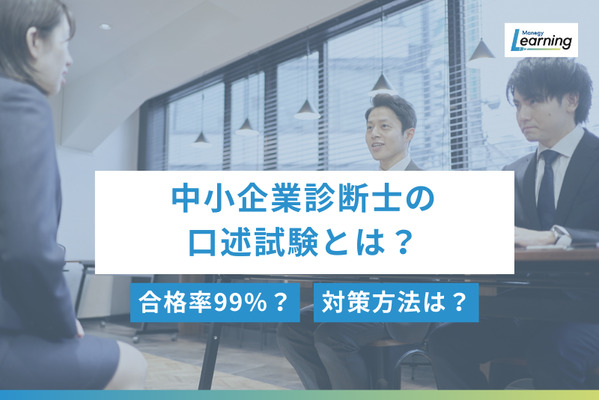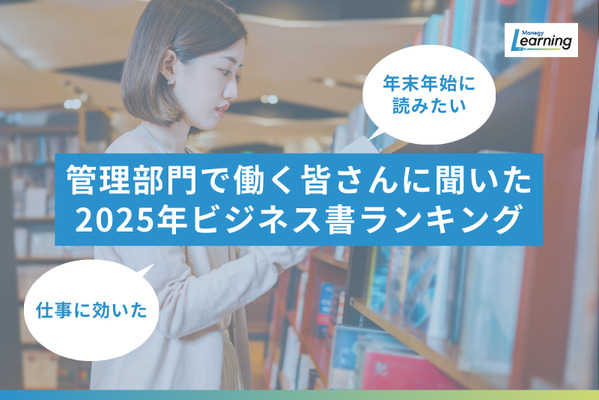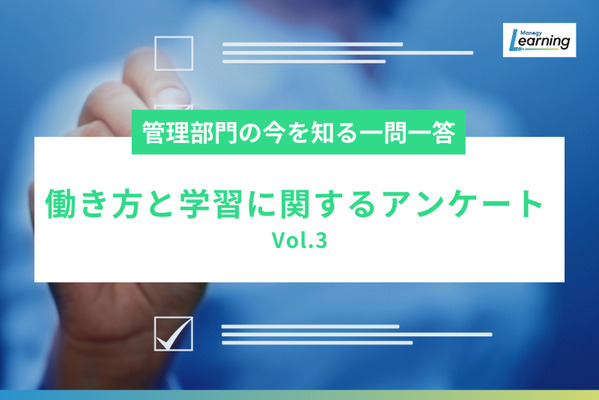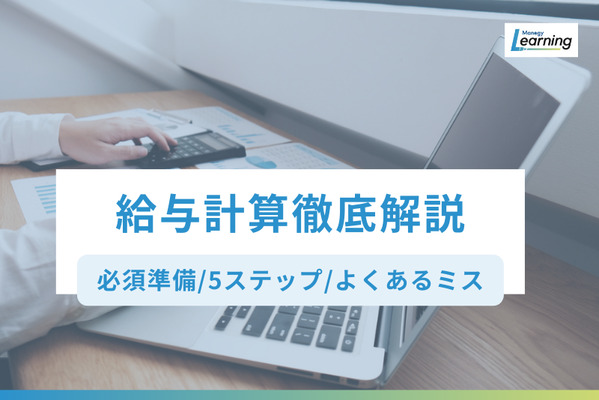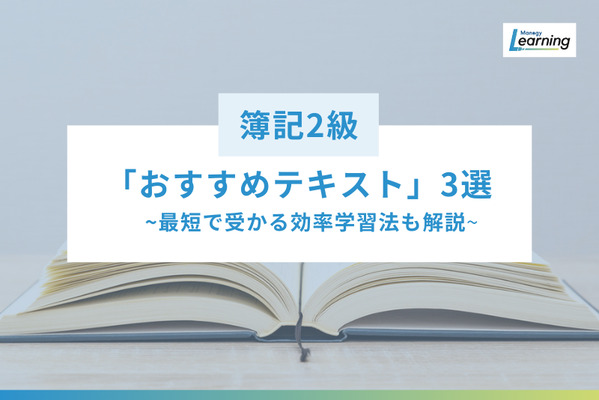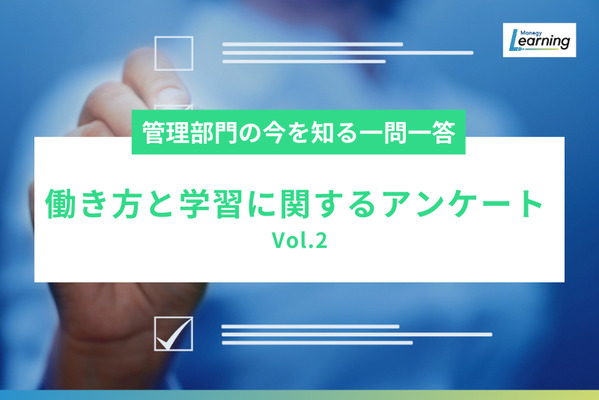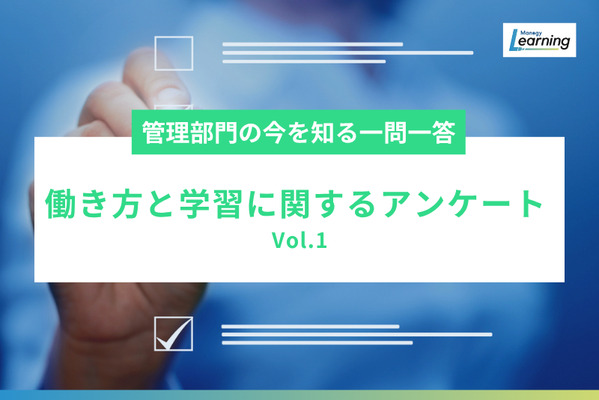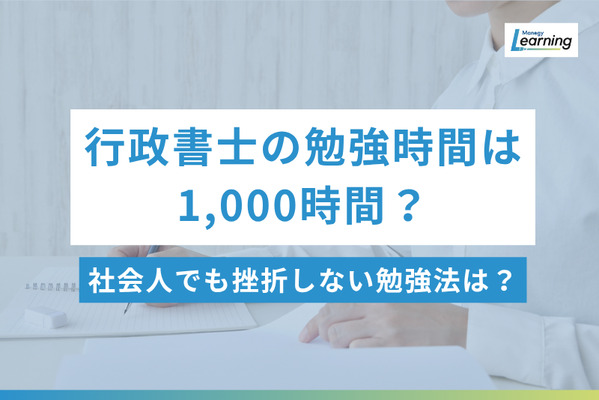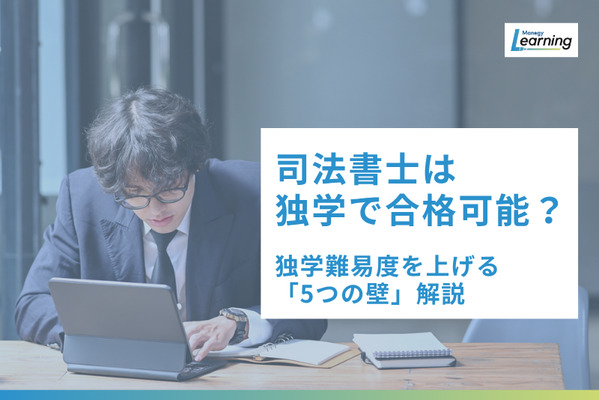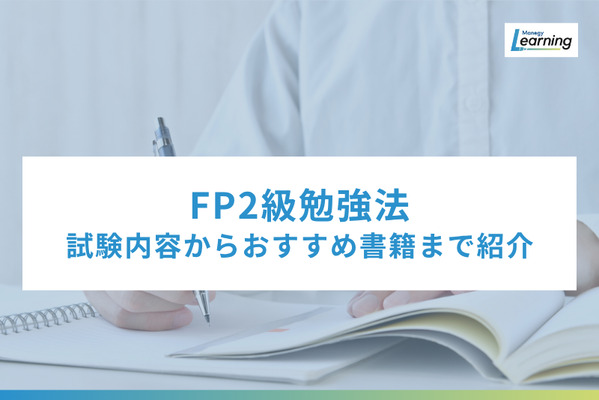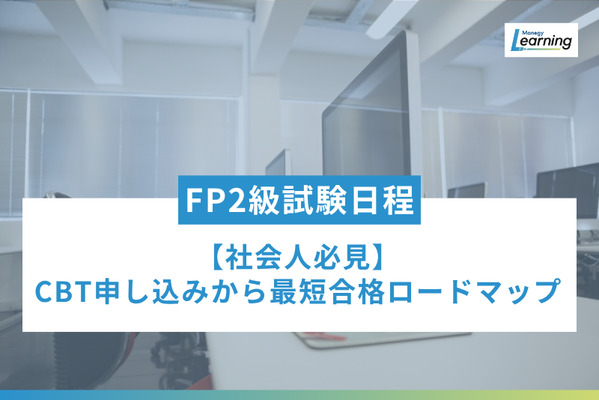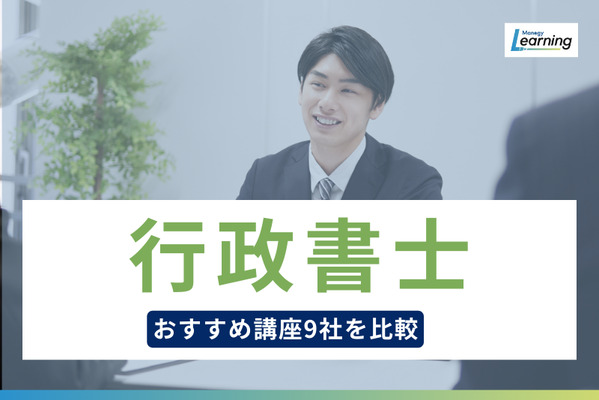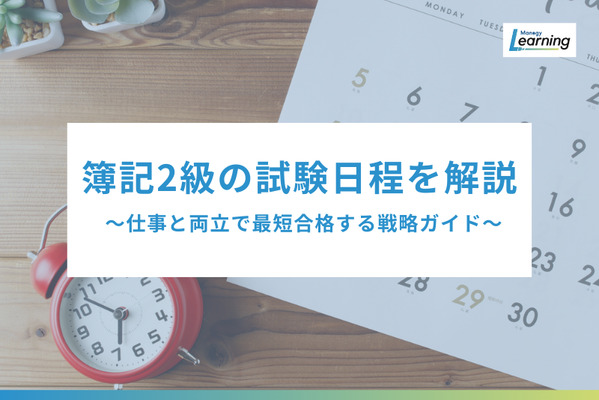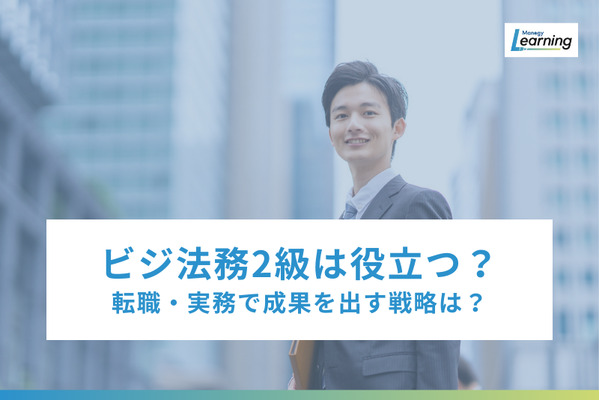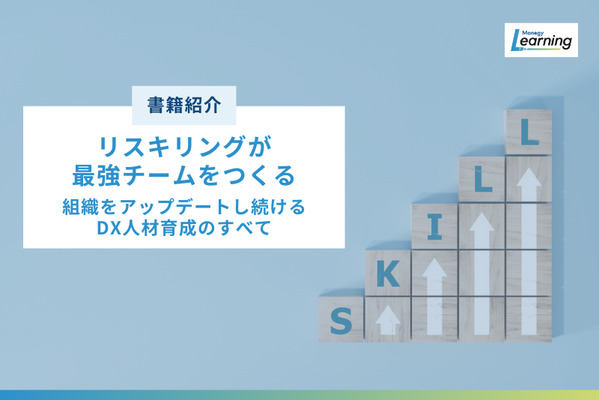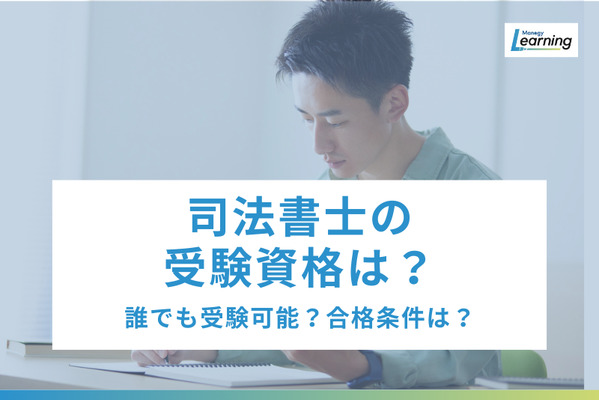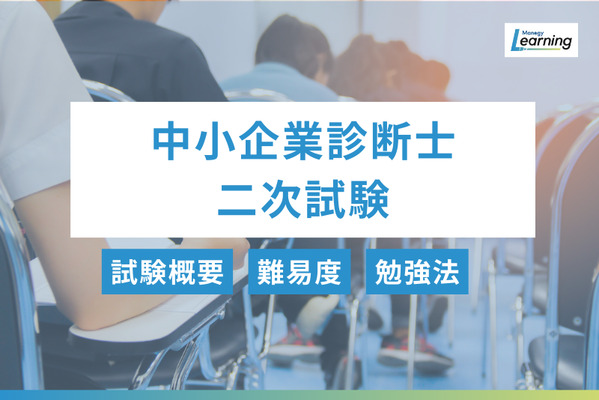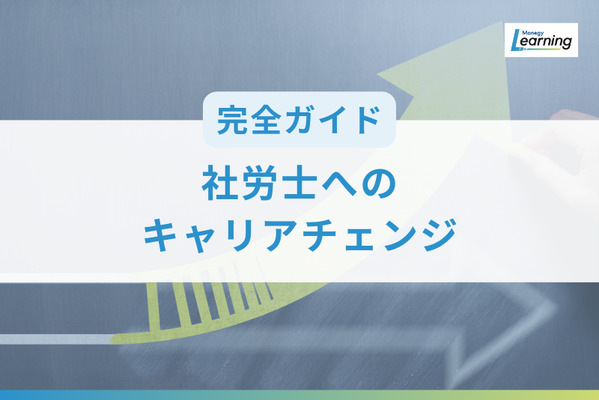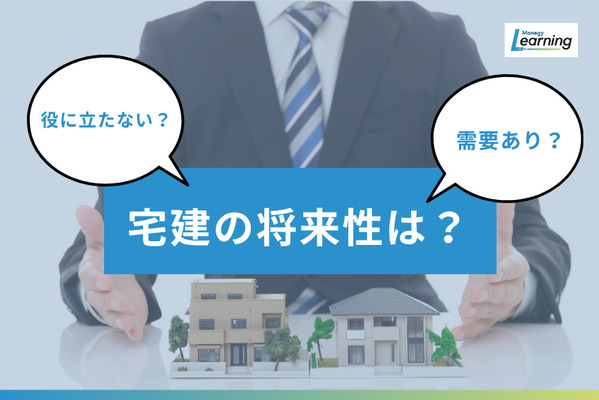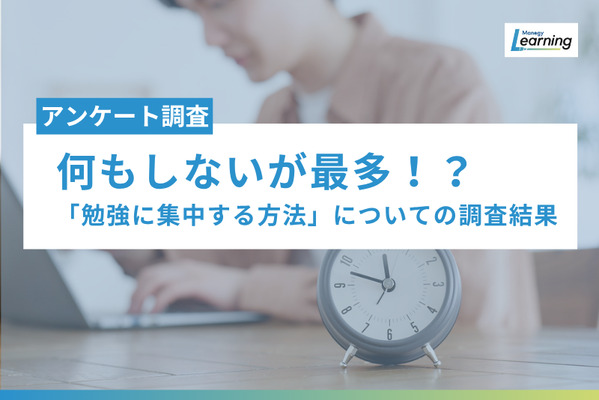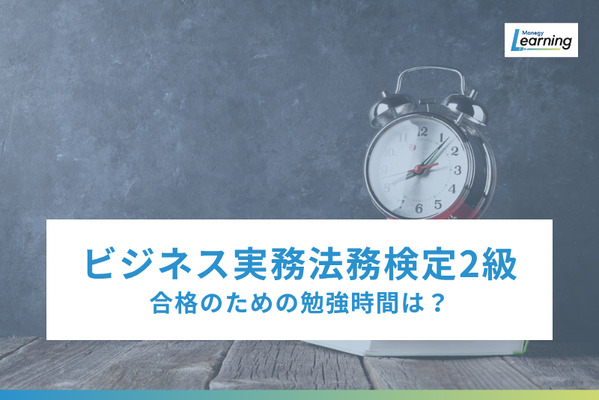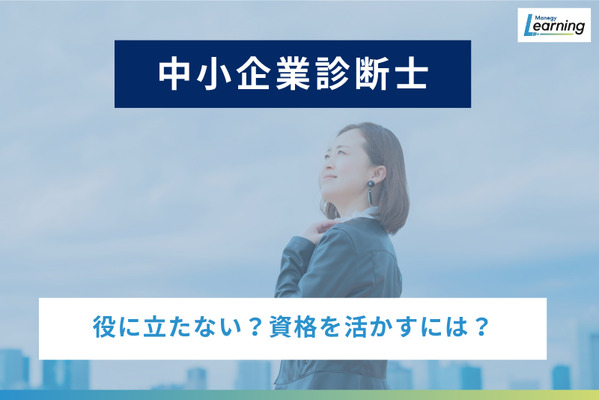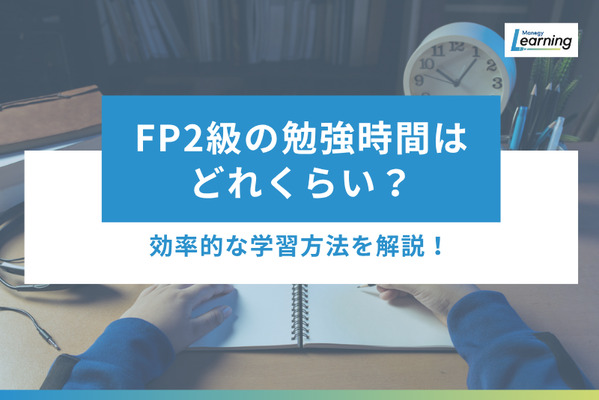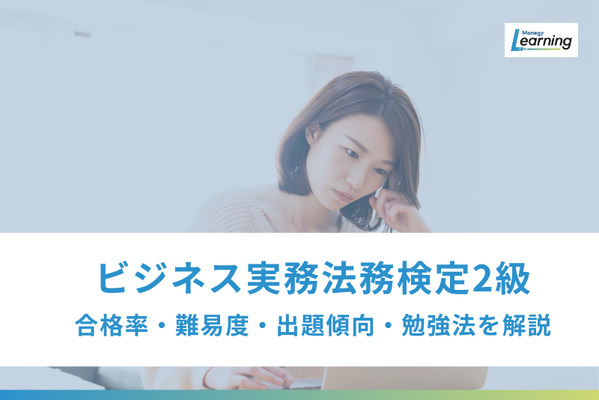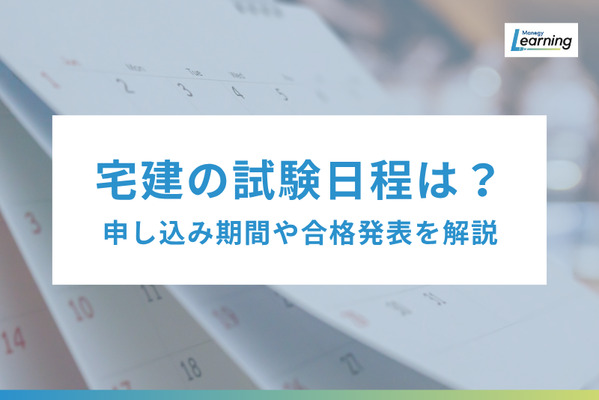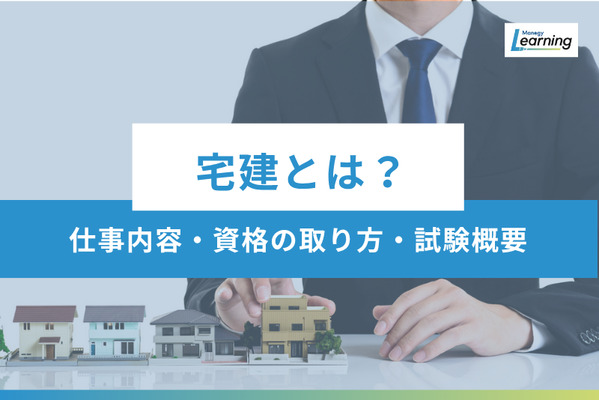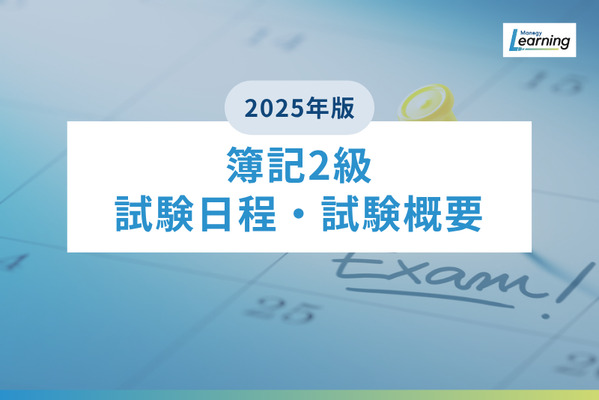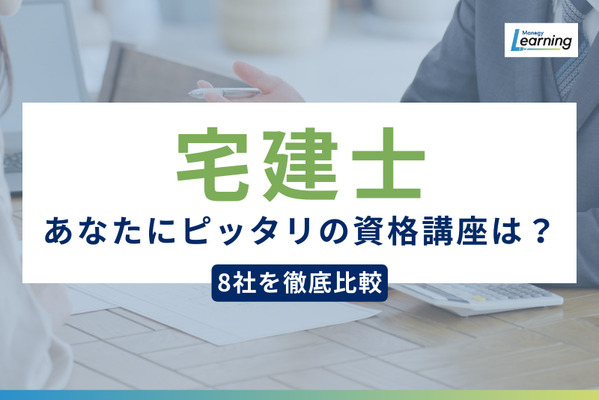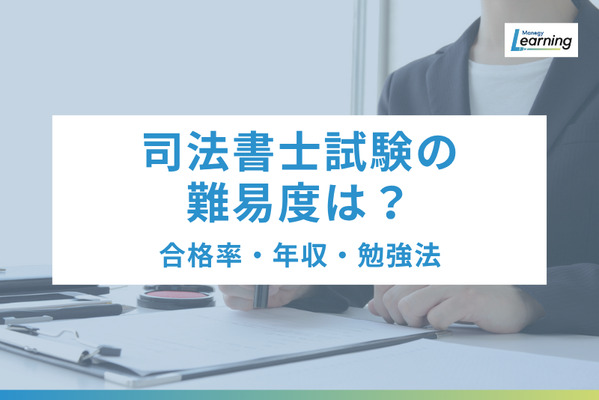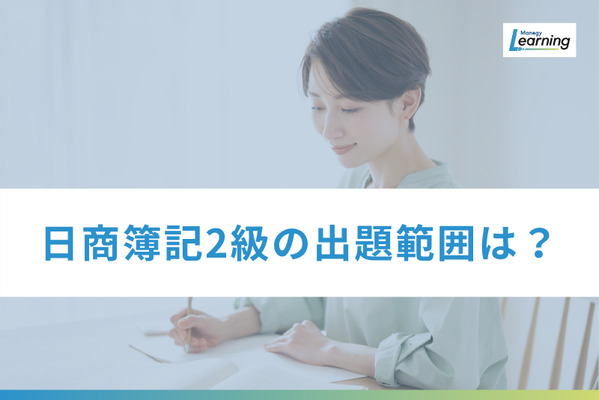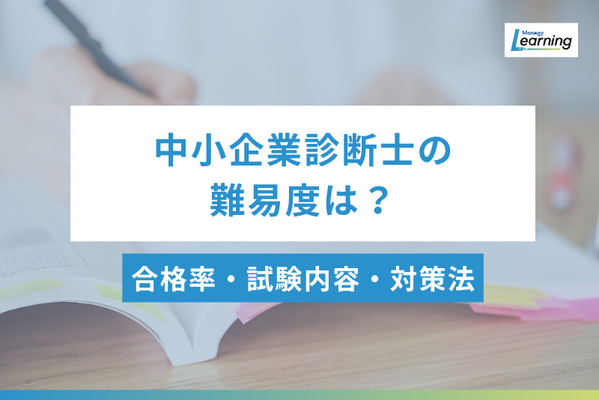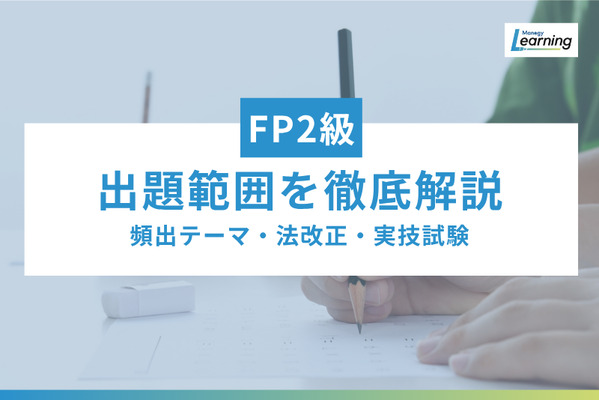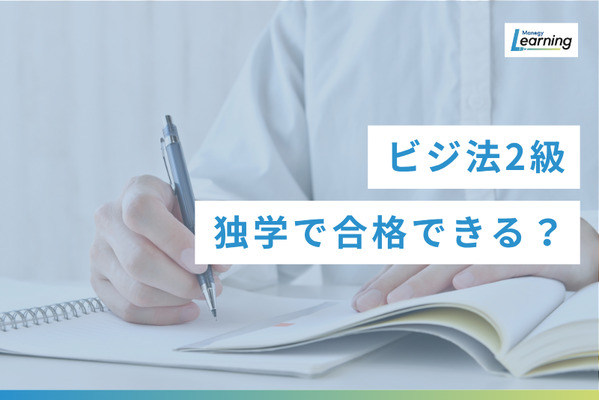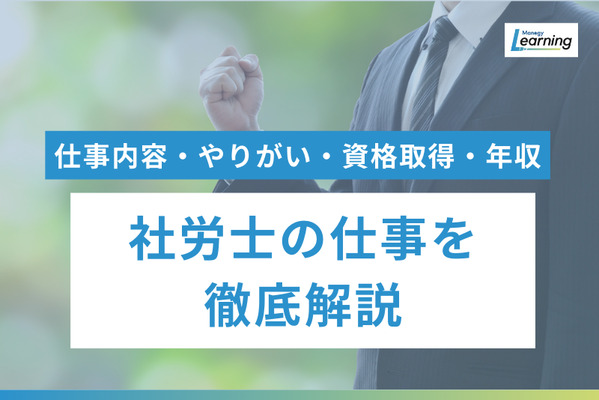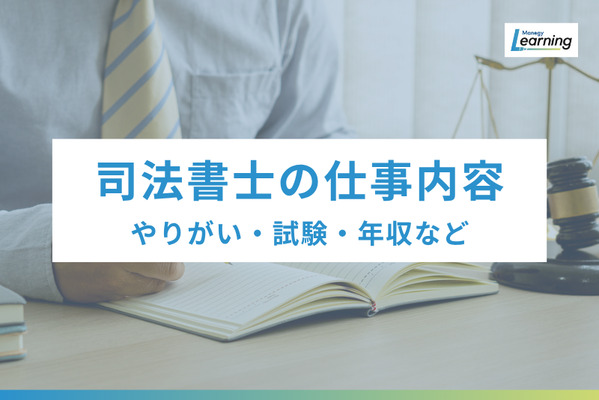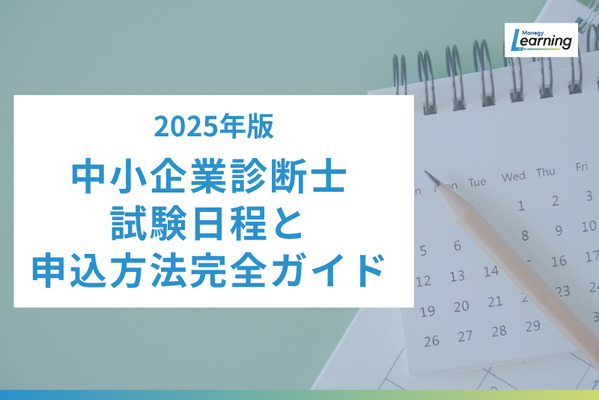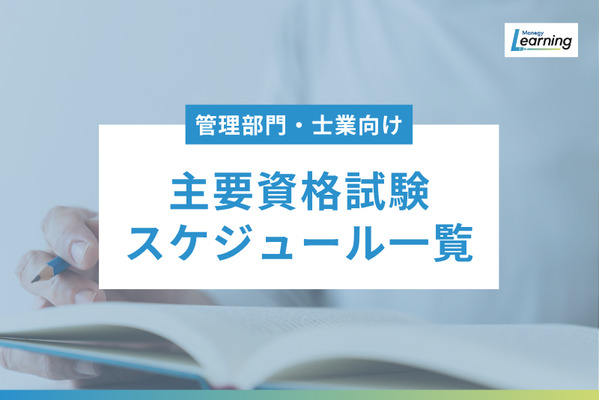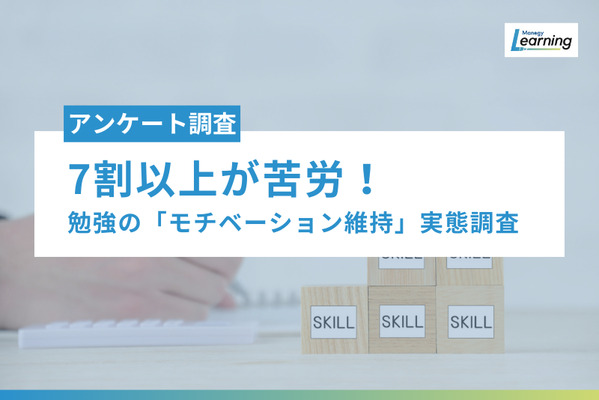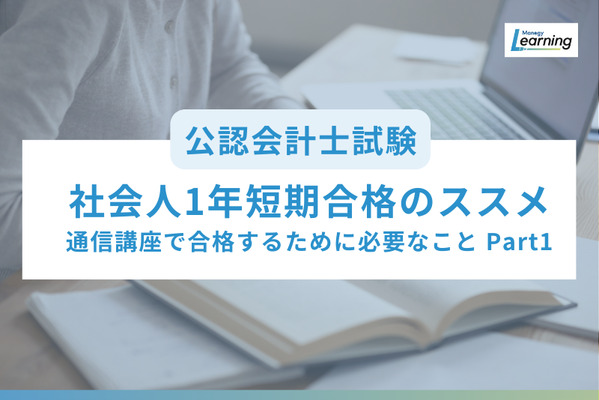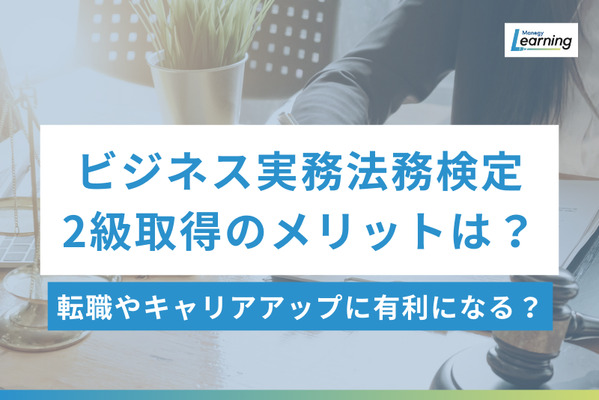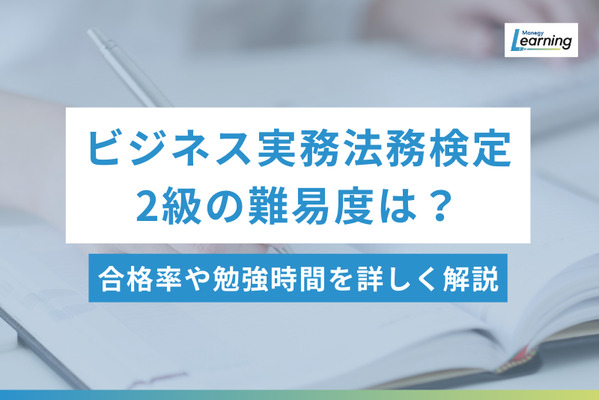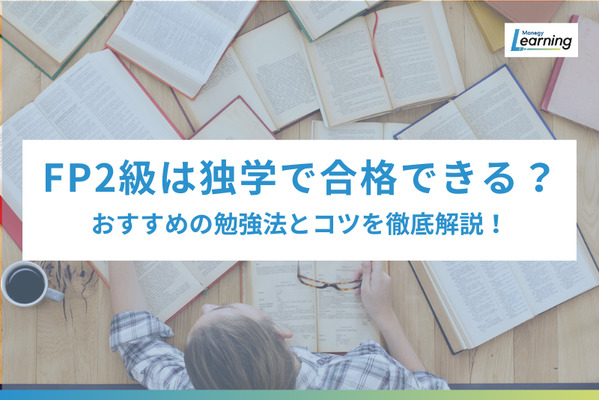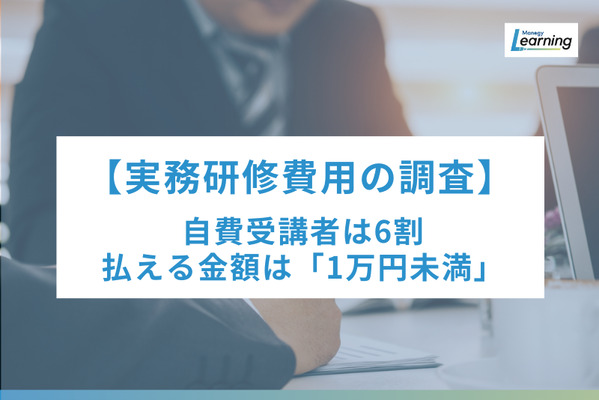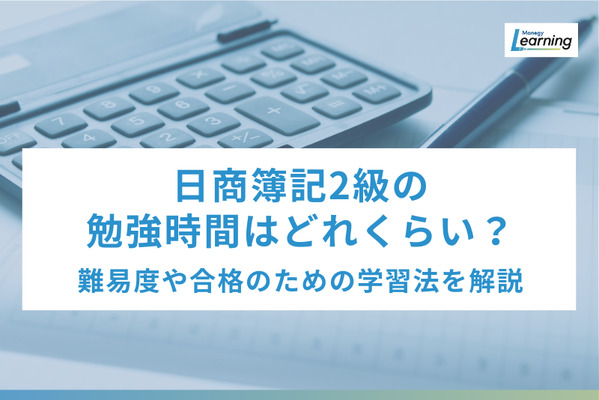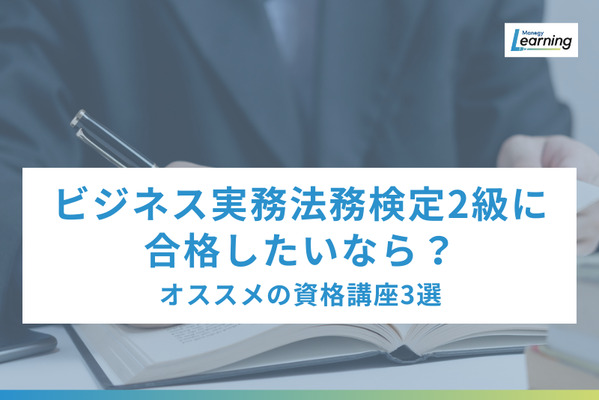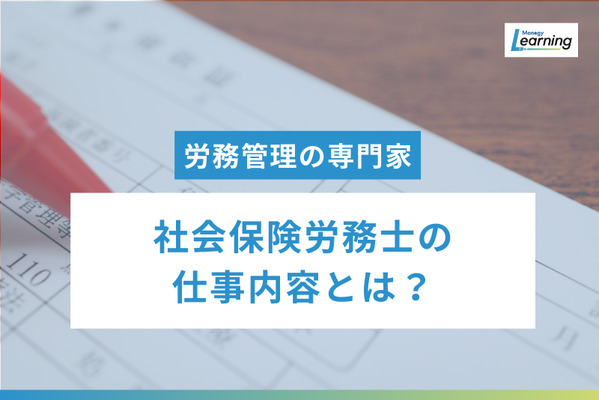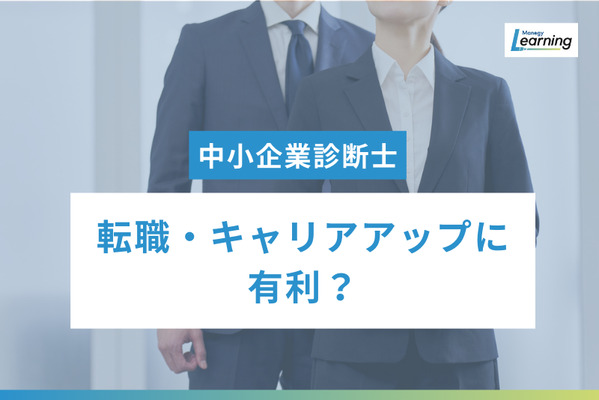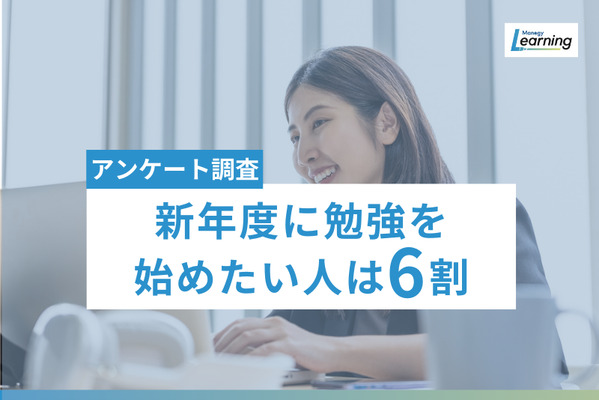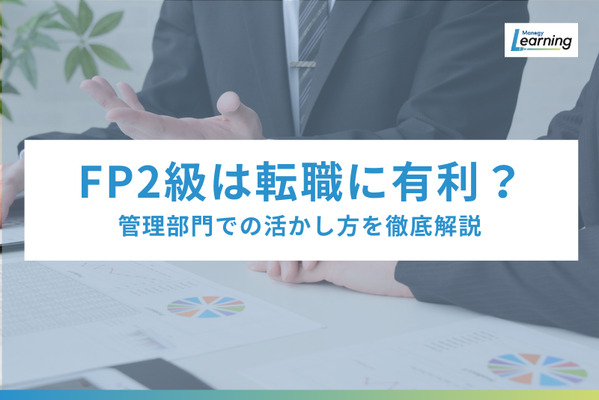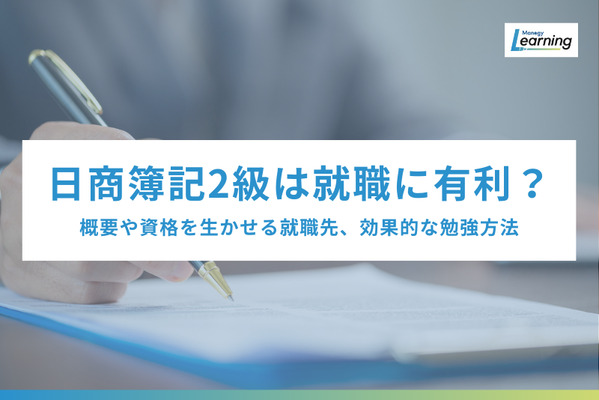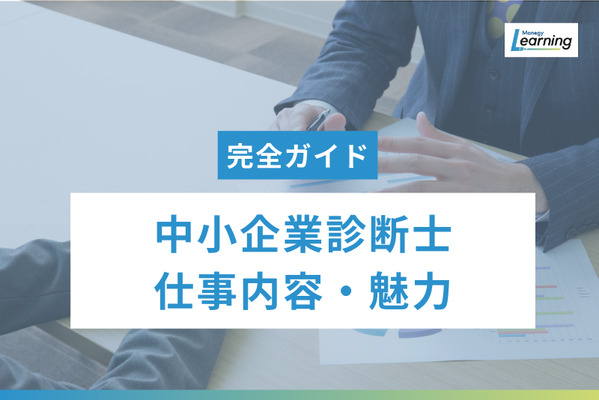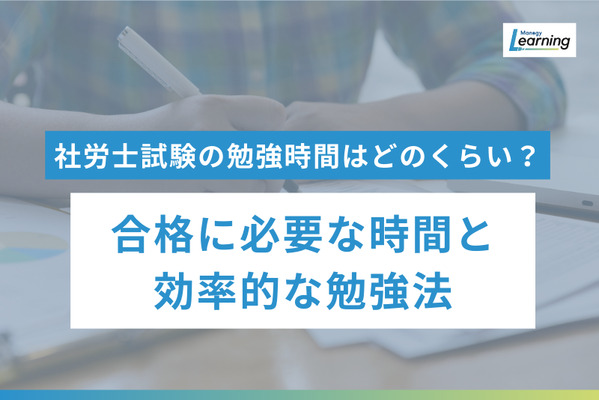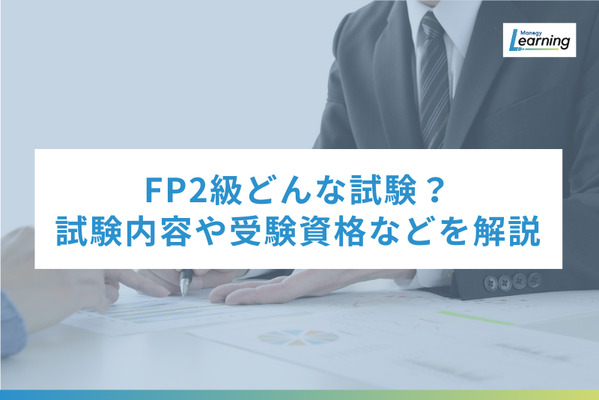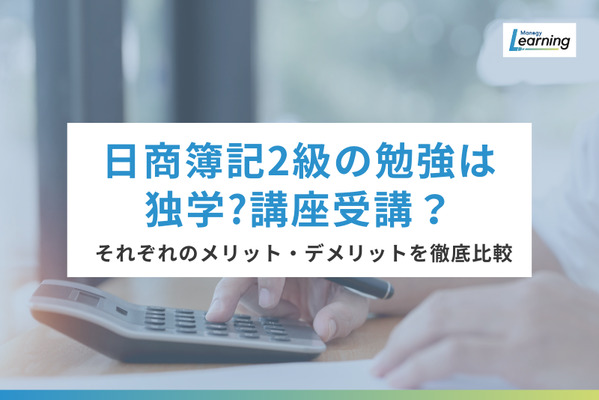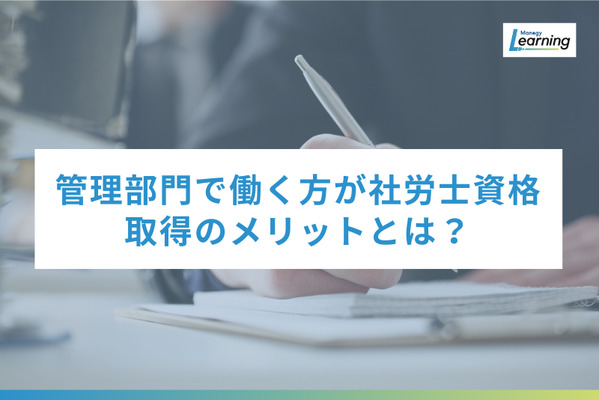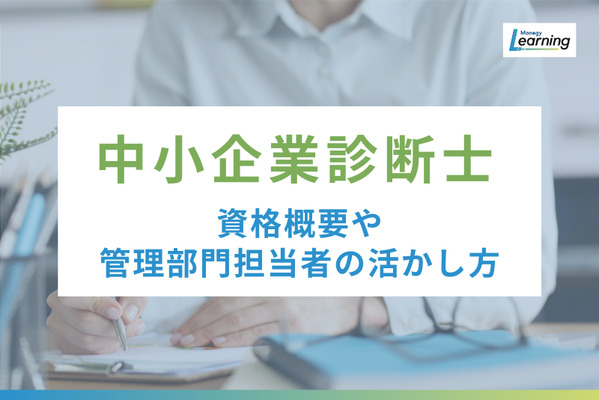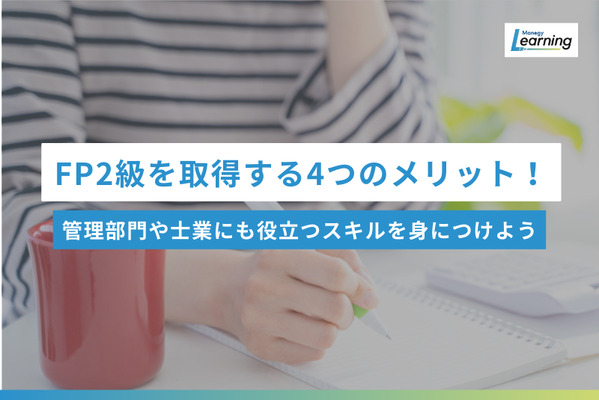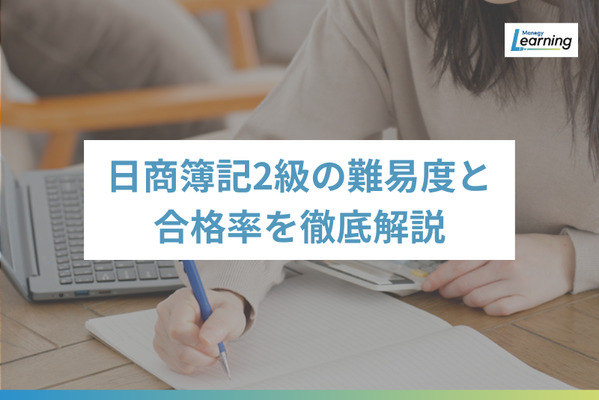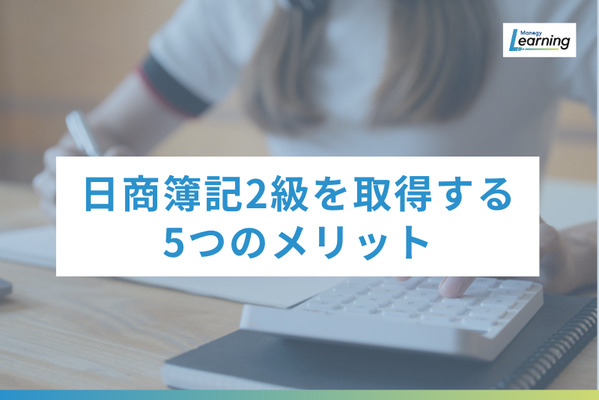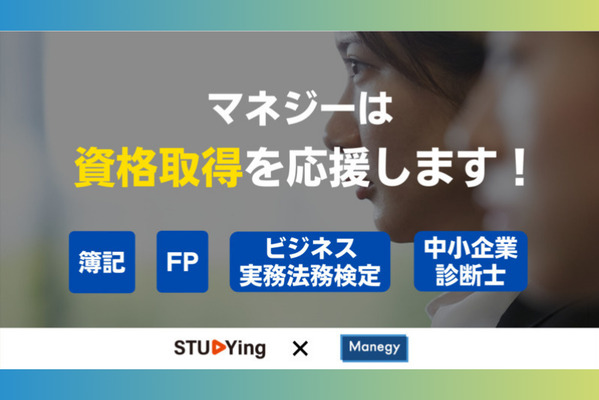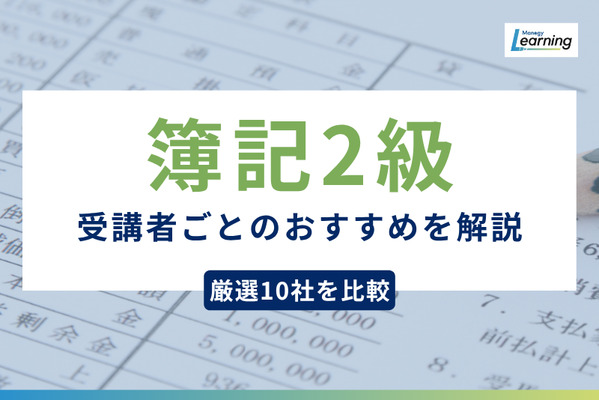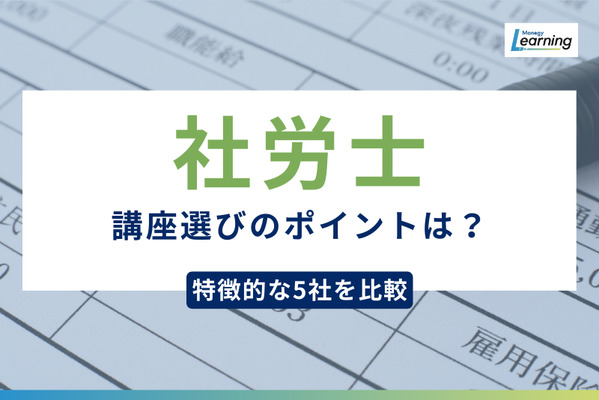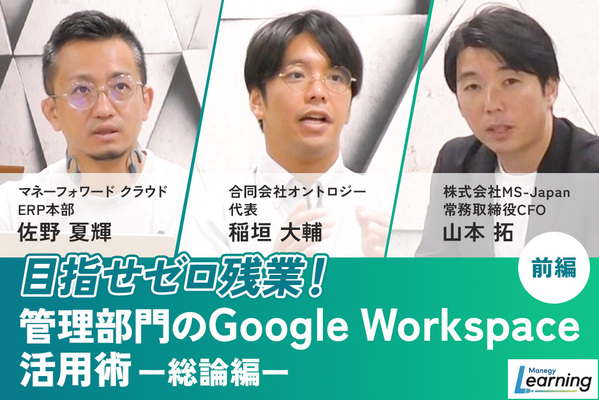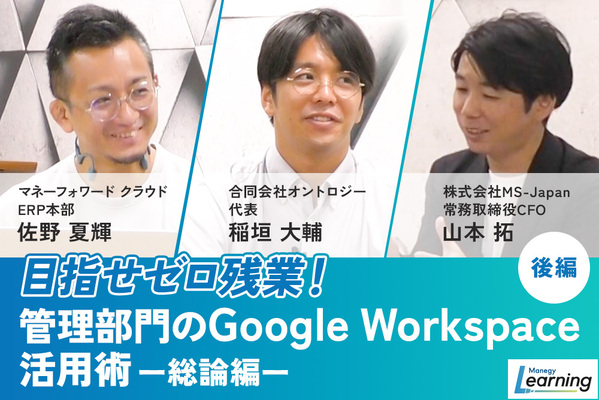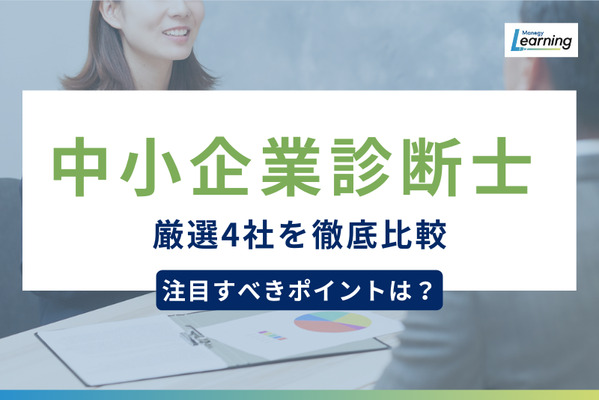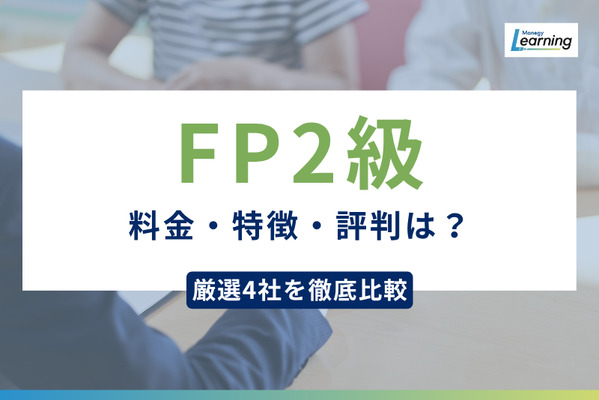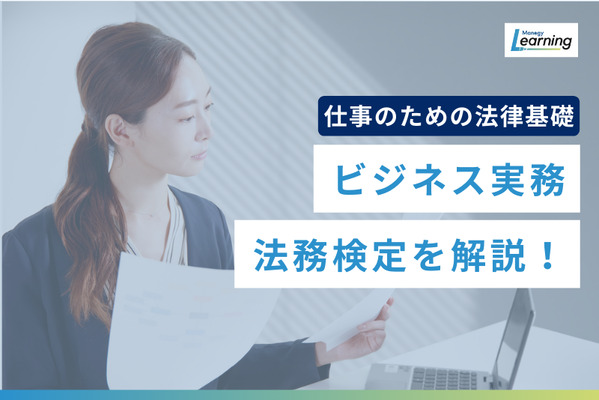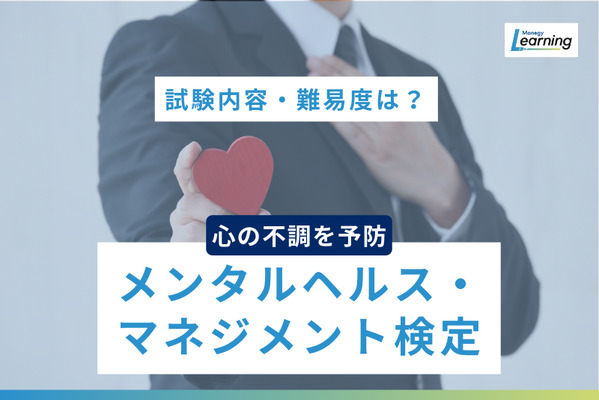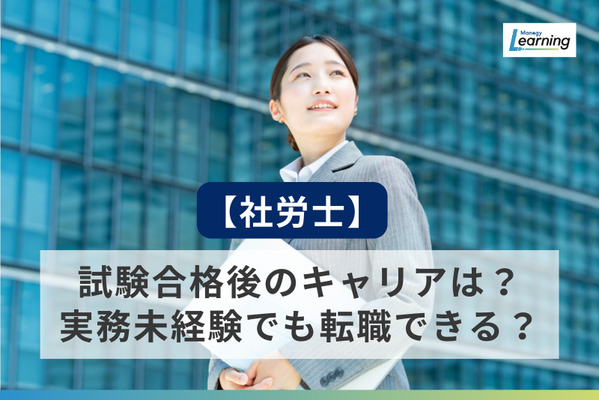社会保険労務士試験の日程は?申込方法から合格発表日まで解説!スケジュールを把握してスムーズな準備をしよう
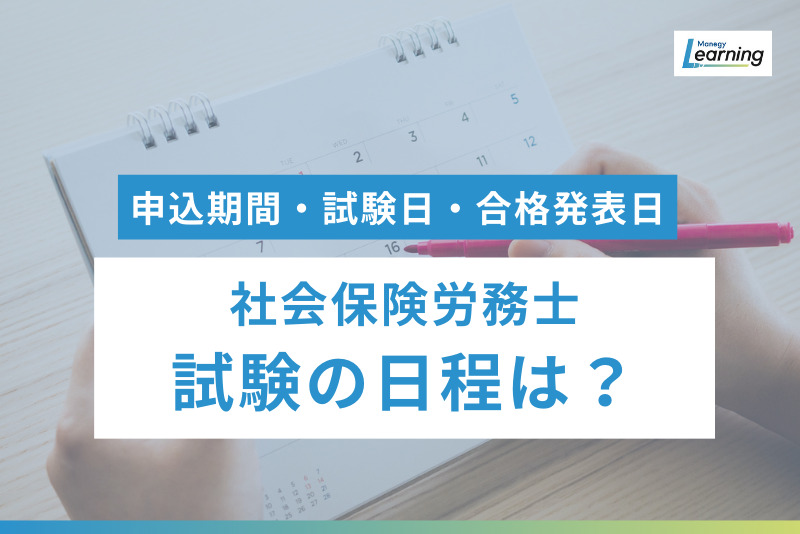
社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険に関する法律の専門家として、企業の人事・労務管理を支援する国家資格です。法改正や働き方改革への対応が求められる今、社労士のニーズは高まっており、資格取得を目指す方も増えています。
本記事では、社労士試験のスケジュールや申込方法など、受験を検討している方が知っておきたい情報をわかりやすくまとめました。合格への第一歩として、まずはスケジュールをしっかり把握してみてはいかがでしょうか。
社労士とは?―労務管理のスペシャリスト
社労士(社会保険労務士)は、企業の労働・社会保険に関する手続きの代理や、労働法規に関する相談・指導などを行う国家資格です。主な業務には以下のようなものがあります。
- 労働社会保険手続業務
- 労働管理の相談指導業務
- 年金相談業務
- 紛争解決手続代理業務(特定社労士のみ対応可)
特に企業の人事・総務部門で働く方にとっては、業務知識の強化やキャリアアップに直結する資格です。独立開業も可能で、将来的な働き方の選択肢を広げることができる点も魅力です。
社労士試験の例年のスケジュール
社労士試験は年に一度、通常8月下旬に実施されます。合格のためには計画的な準備が欠かせません。以下は例年の主なスケジュールです。
社労士になるためには、非常に難しい試験を突破しなければなりません。
資格試験に合格するためには、勉強時間を確保する事はもちろん大切ですが、どのように勉強するかも非常に大切といえるでしょう。
| 項目 | 時期(目安) |
|---|---|
| 試験案内の公表 | 4月中旬 |
| 受験申込期間 | 4月中旬〜5月末頃 |
| 試験日 | 8月下旬 |
| 合格発表 | 10月上旬 |
申込期間は約1か月半と長く見えますが、準備する書類が多く必要なので、早めに準備を進めることおすすめします。また、受験票は試験の2〜3週間前の8月上旬に発送されるのが通例です。
試験当日のスケジュール
社労士試験は、年1回、8月の第4日曜日に全国で一斉実施されます。
1日で「選択式(午前)」と「択一式(午後)」の2つの試験を受ける形式で行われるのが特徴です。それぞれの出題形式や時間帯、注意点について解説します。
午前の部:選択式試験
- 時間帯:10:30〜11:50(80分)
- 出題形式:記述式(穴埋め式)
- 科目数:8科目(労働基準法・労災保険法・雇用保険法・健康保険法など)
- 配点:各科目5点、合計40点満点
特徴と対策ポイント
選択式は、各科目につき5つの空欄を補充する記述式問題で、用語や制度の理解が問われます。各科目3点以上、合計25点以上を獲得する必要があるため、苦手科目の克服が重要です。
この記事を読んだ方にオススメ!
昼休憩
- 時間帯:11:50〜13:20(90分)
選択式が終わった後は、約90分の昼休憩があります。午後に備えてしっかり休息を取り、頭をリセットすることが大切です。昼食や水分補給の準備はあらかじめしておきましょう。
午後の部:択一式試験
- 時間帯:13:20〜16:50(210分)
- 出題形式:五肢択一式
- 科目数:7科目
- 問題数:70問(各科目10問)
- 配点:1問1点の計70点満点
特徴と対策ポイント
長時間にわたる試験のため、集中力と体力の維持が重要です。過去問演習を重ね、時間配分の感覚をつかんでおきましょう。
また、択一試験も各科目4点以上、総得点44点以上を獲得しないと合格基準には満たないため、各科目を満遍なく理解する事が求められます。、計画的な学習がカギとなります。
このように、社労士試験は1日で2種類の出題形式をこなすハードな試験です。時間配分や体調管理も重要なポイントとなるため、模試や過去問でシミュレーションしておくと安心です。
この記事を読んだ方にオススメ!
合格発表当日のスケジュール
社労士試験の合格発表は、例年10月上旬に行われます。試験の結果は、書面通知に加え、インターネットや官報でも確認する事が可能です。
書面による通知
受験者全員に「合否通知書」が郵送されます。
インターネットによる確認
社会保険労務士試験オフィシャルサイトならびに厚生労働省ホームページにて、合格者の受験番号が一覧で掲載されます。インターネットならどこでも確認できるため、速報を知りたい方にはおすすめです。
官報での公示
合格者の氏名・受験番号が官報にも掲載されます。正式な合格証明となるため、必要に応じて保管しておくと安心です。
社労士試験の申込方法
社労士試験に合格しただけでは、まだ「社会保険労務士」として業務を行うことはできません。所定の登録手続きを経て、初めて社労士を名乗ることが可能となります。
登録の流れ
社労士試験に合格しただけでは、まだ「社会保険労務士」として業務を行うことはできません。所定の登録手続きを経て、初めて社労士を名乗ることが可能となります。
登録要件の確認
以下のいずれかに該当する必要があります。
・2年以上の実務経験(社会保険事務など)
・所定の実務講習(※未経験者の場合)
必要書類の準備
・社会保険労務士登録申請書
・個人番号と本人確認ができる書類
・社会保険労務士試験合格証書の写し
・従事期間証明書(様式第8号)又は事務指定講習修了証の写し
・住民票の写し
・写真票
・氏名や戸籍の確認ができる本人確認書類
・通称併記願
都道府県社労士会への申請
上記の書類を登録する都道府県の社労士会に申請します。登録完了後、その社労士会の会員となり、活動を開始できます。
詳細は公式サイトをチェックに記載されているので、ぜひこちらもチェックください。
以上の手続きを経て、晴れて「社会保険労務士」として名乗ることができるようになります。独立・開業や企業内社労士としての活躍も視野に入れながら、次のステップに進んでいきましょう。
郵送・インターネットでの申し込みが可能
社労士試験の申込方法は、郵送またはインターネットのいずれかです。公式サイトには、「申込みは原則インターネット申込みとし、当面の間、郵送申込みも受け付けます。」と記載があるため、今後は、インターネット申し込みのみになる可能性がありそうです。
また、郵送の場合は、受験案内を入手する必要があります。受験案内の請求方法は、返信用封筒を作成し、試験センターまで郵送となります。
郵送での請求方法詳細は、公式サイトをご確認ください。
まとめ:スケジュール管理が合格への第一歩!
社労士試験は年1回のチャンスです。申込から受験、合格発表までのスケジュールをしっかりと把握して、試験当日にご自身の実力を発揮できるよう準備を進めることが大切です。以下のポイントを押さえて、計画的な学習と手続きを進めましょう。
- 試験日は8月下旬が例年
- 申込期間は4月中旬〜5月末が目安
- 午前(選択式)・午後(択一式)で出題形式が異なる
- インターネット申込が便利
この記事を読んだ方にオススメ!

Manegy Learning
Manegy Learningは管理部門・士業の皆さまに向けて、実務に役立つTIPSや資格取得のためのスクール取得などの情報を発信し、みなさまの学びをサポートします。
MS-Japan
https://www.manegy.com/learning/