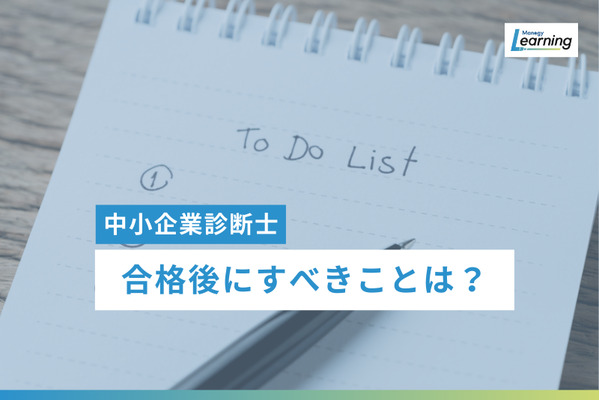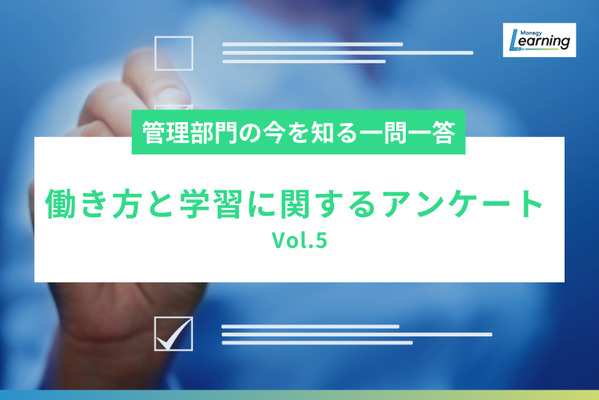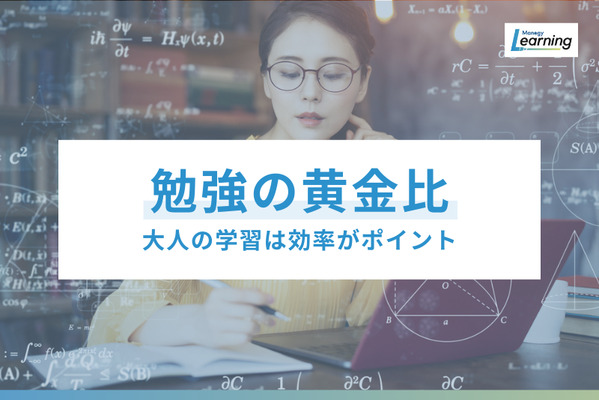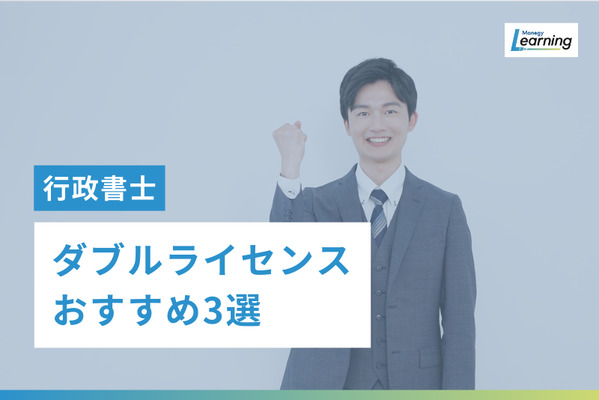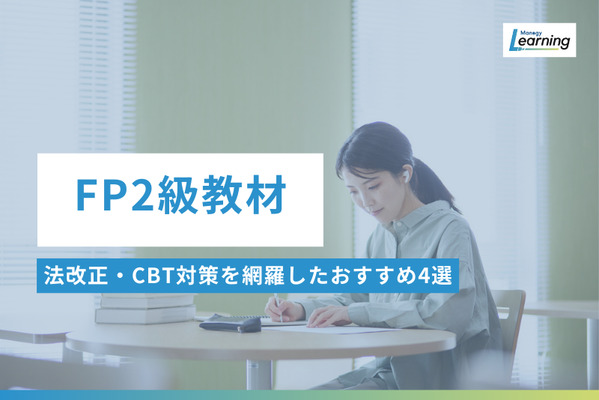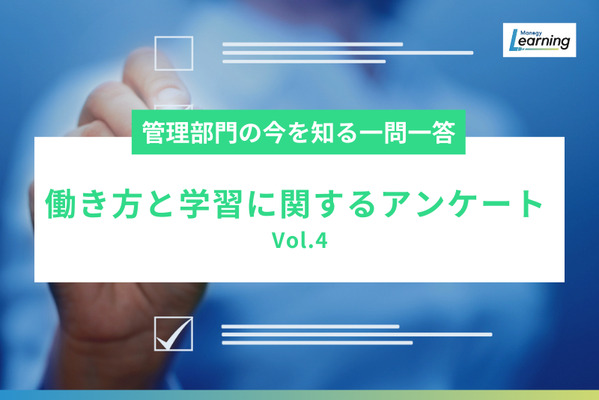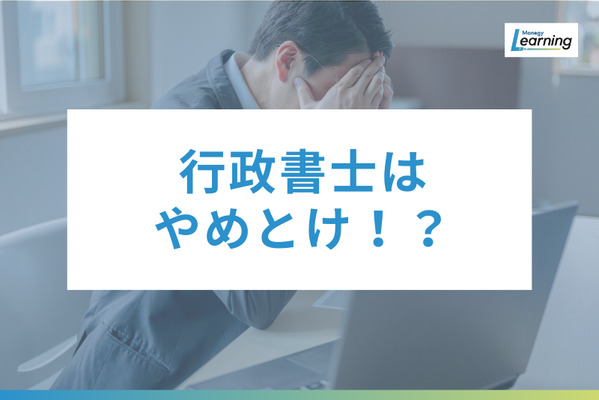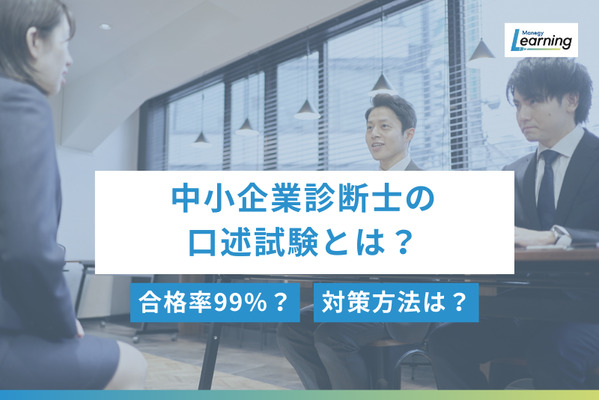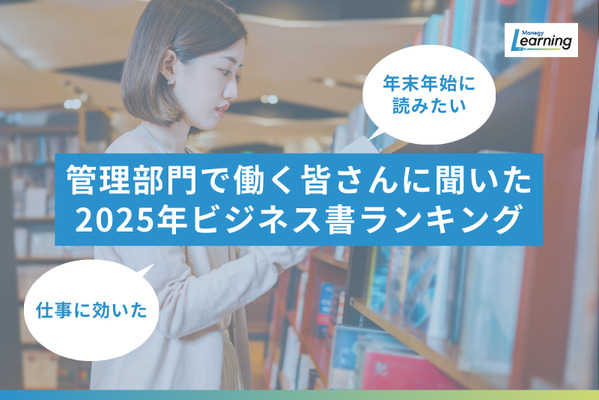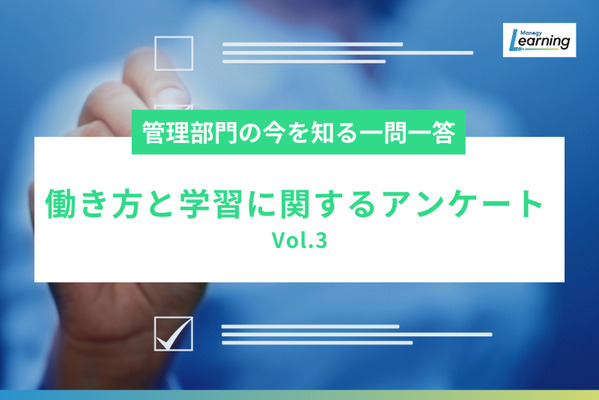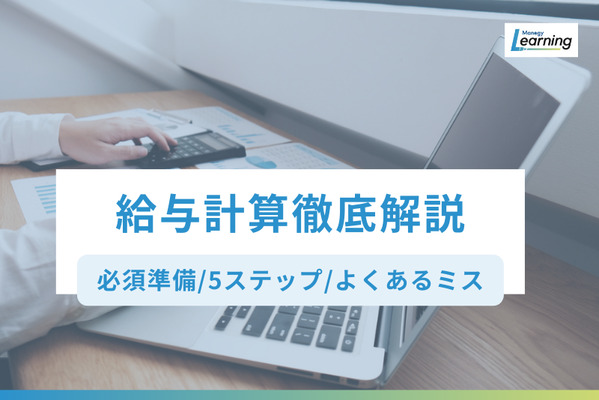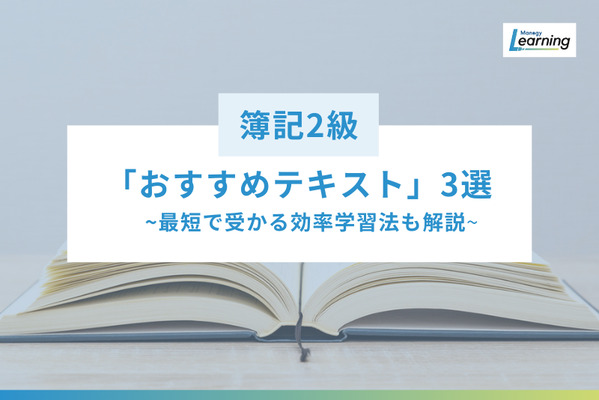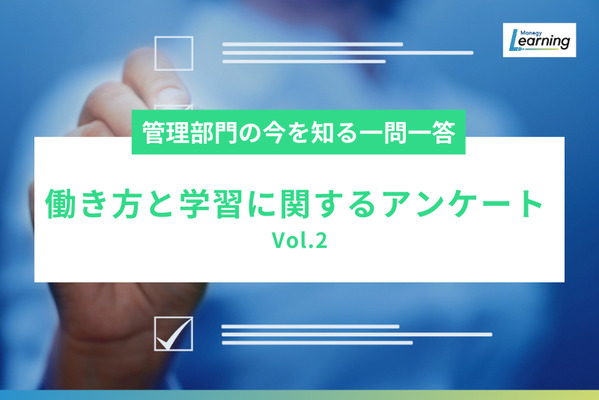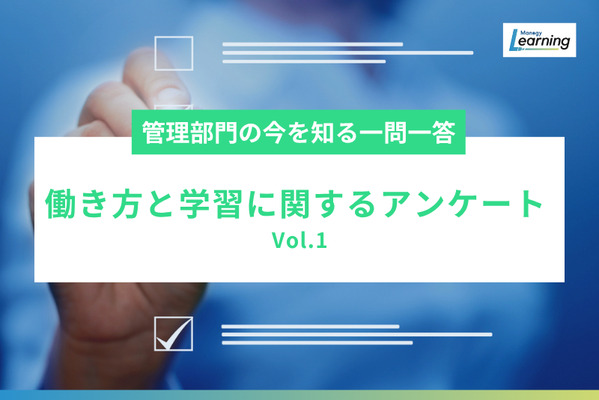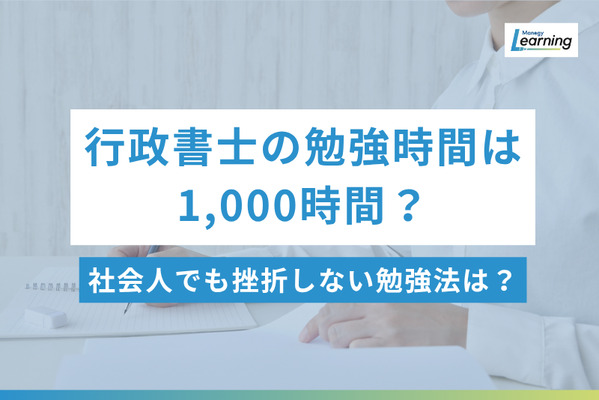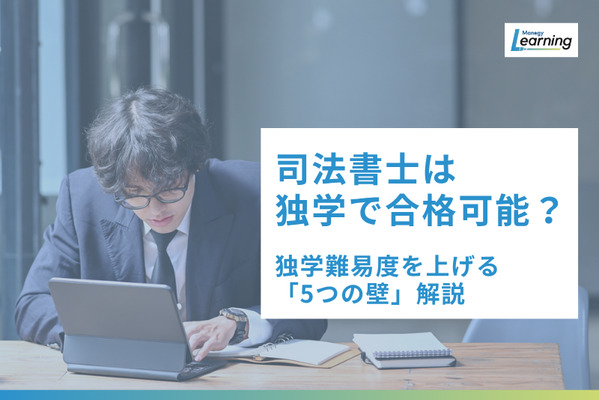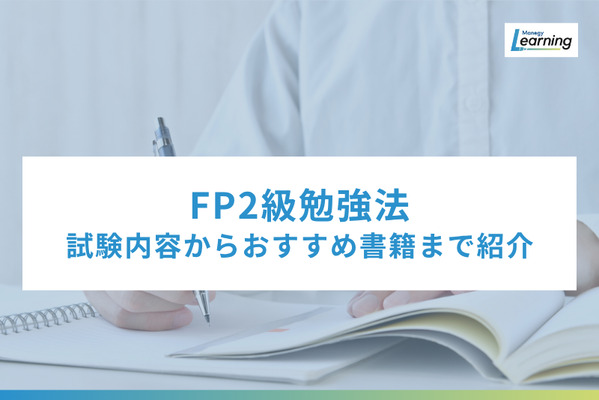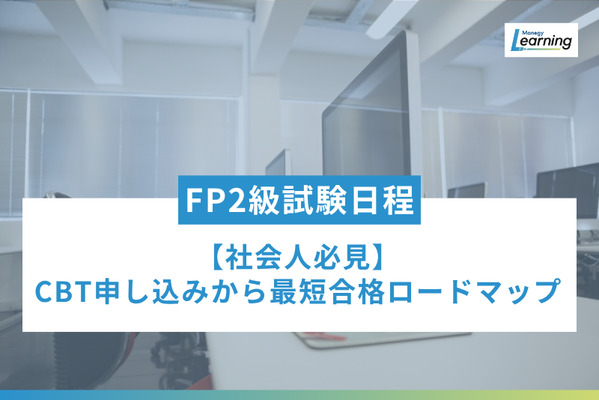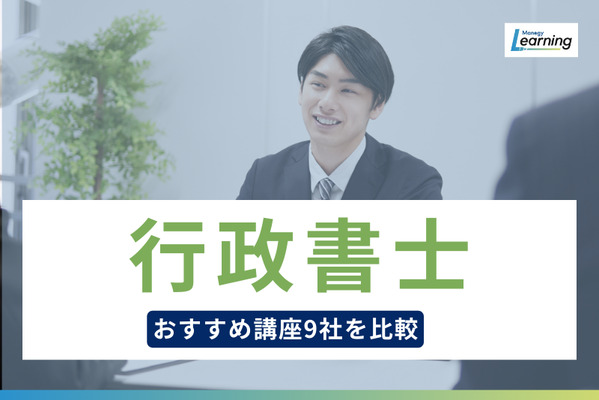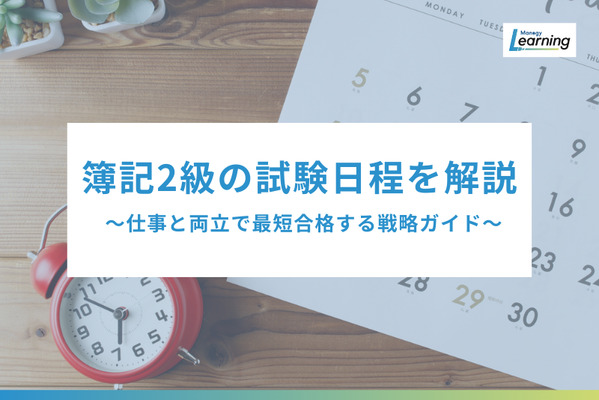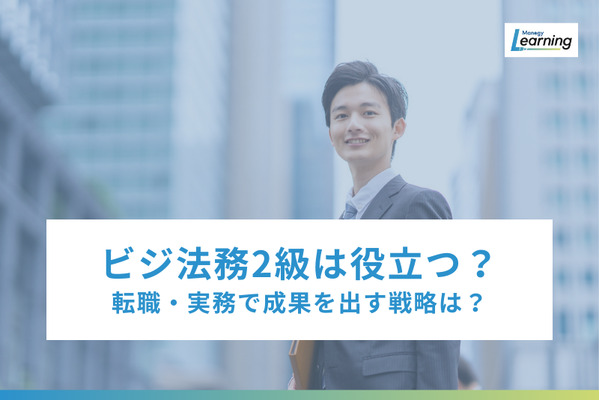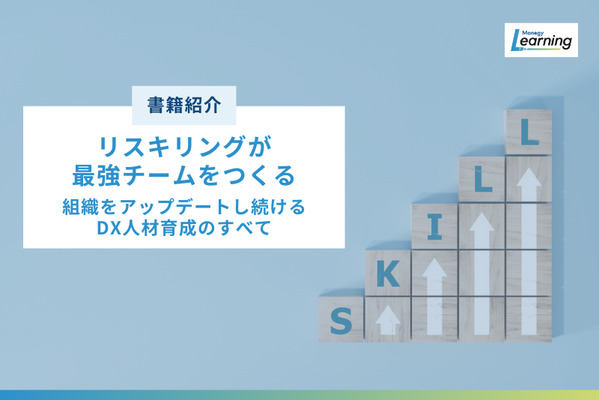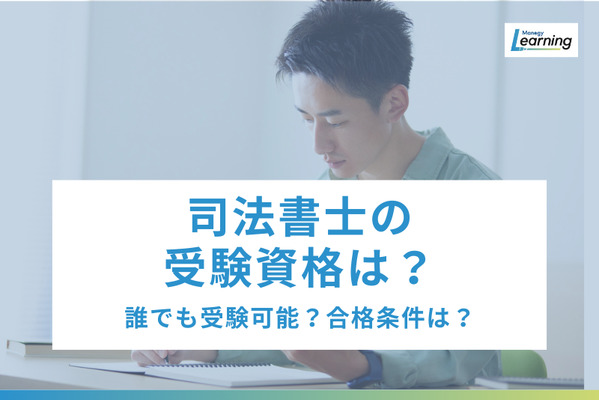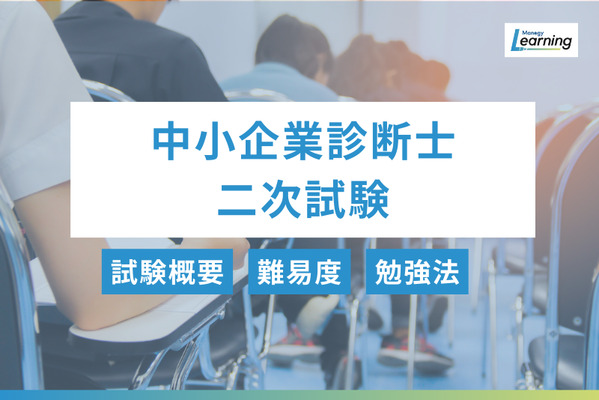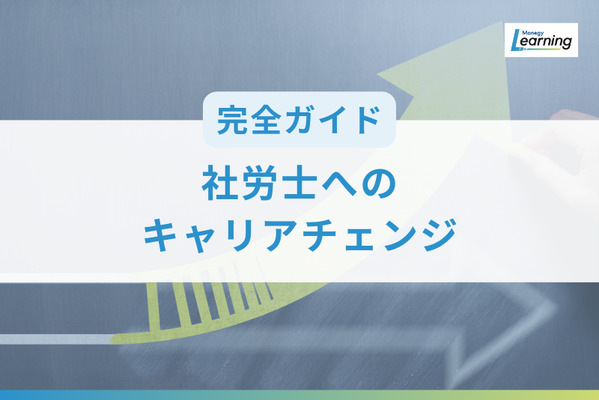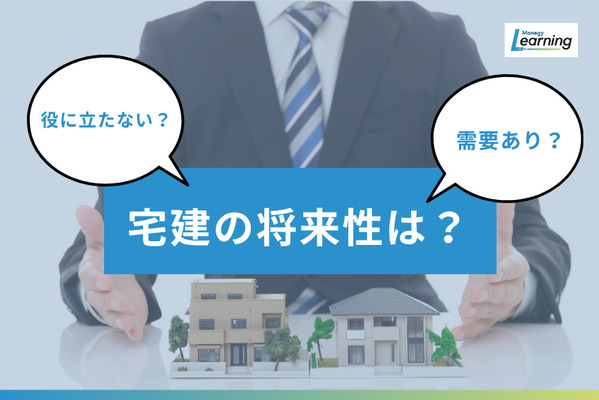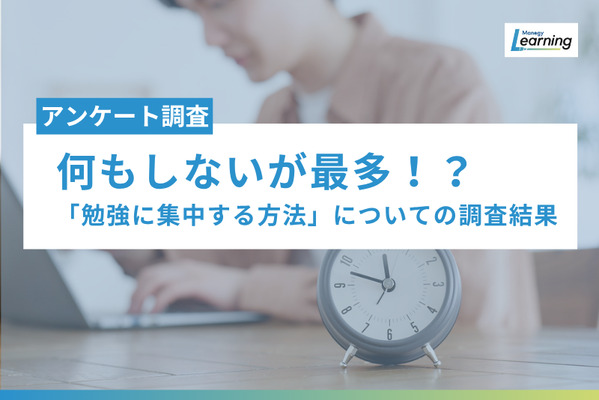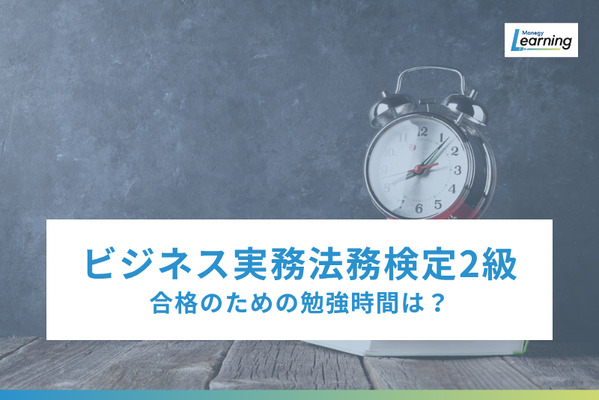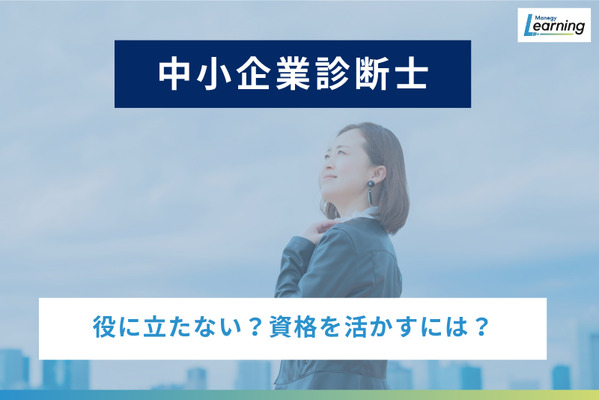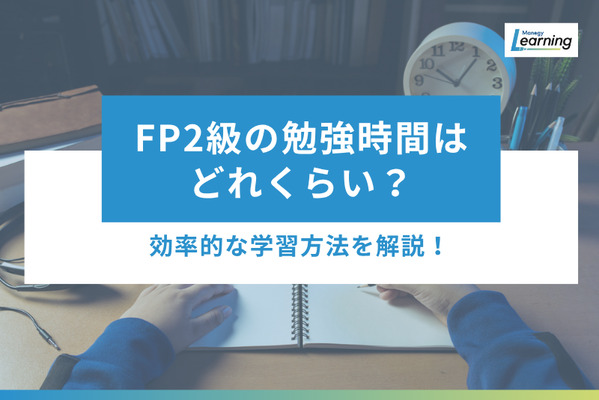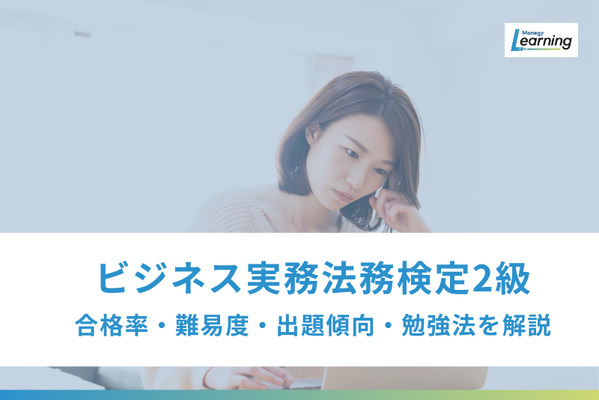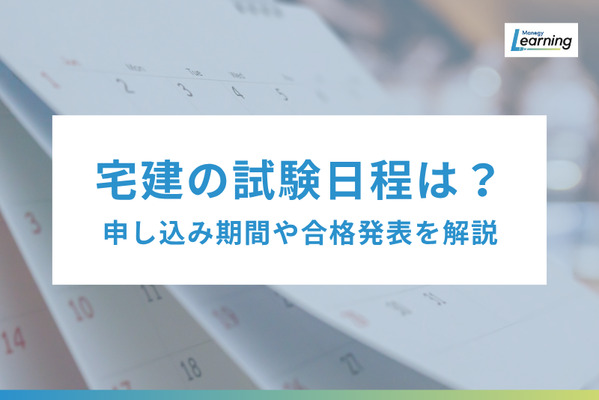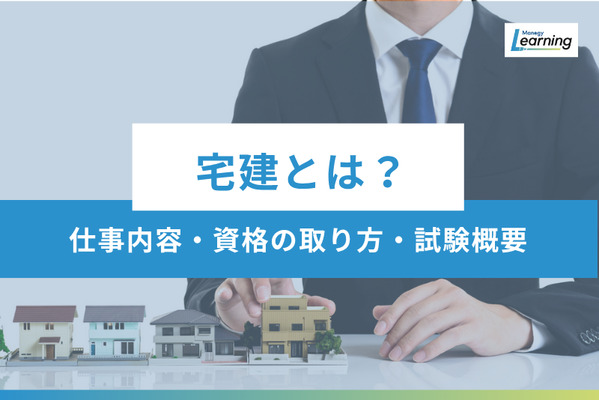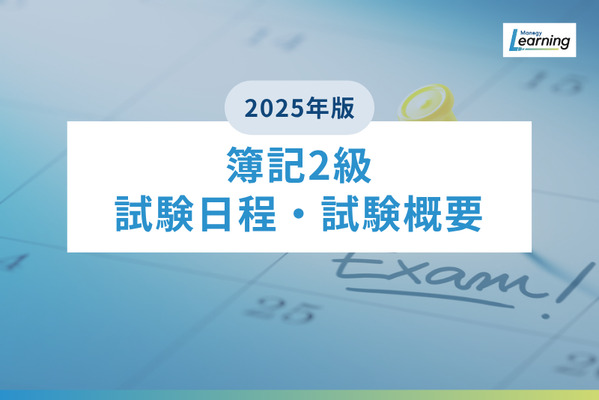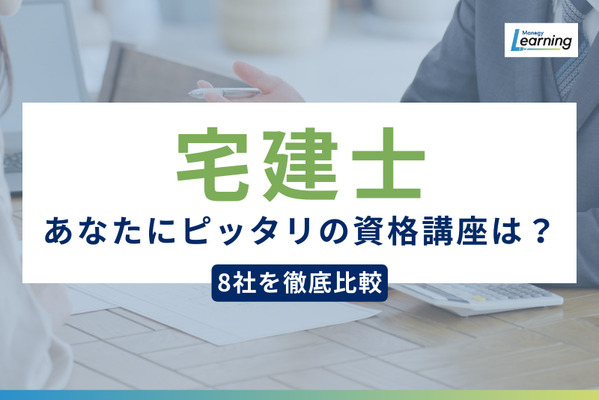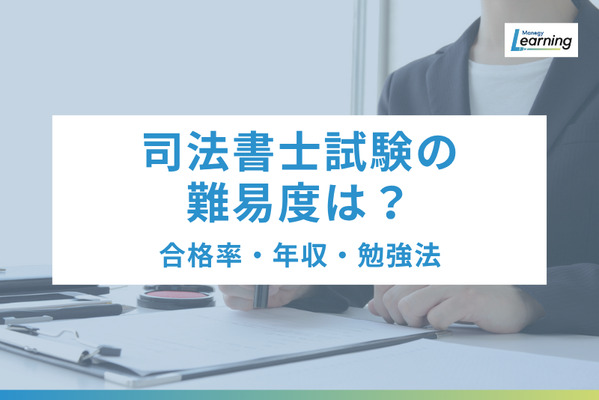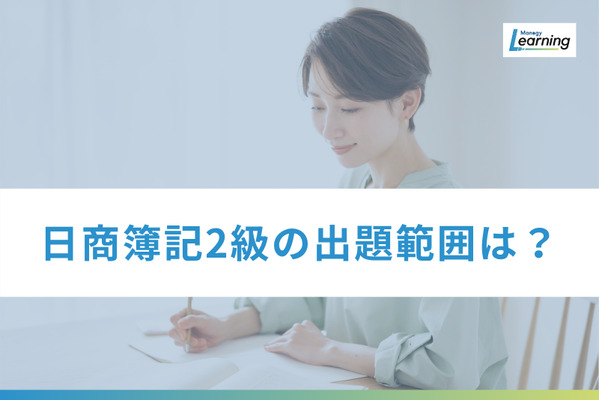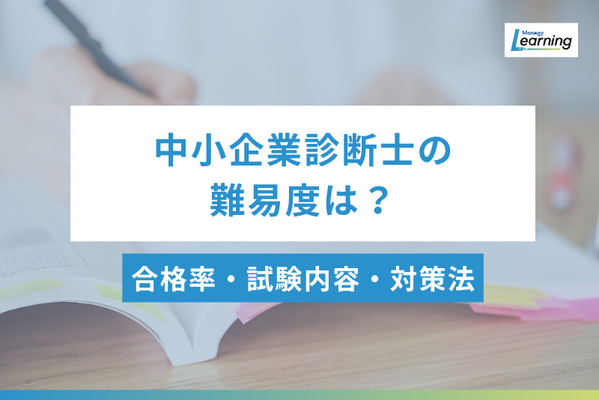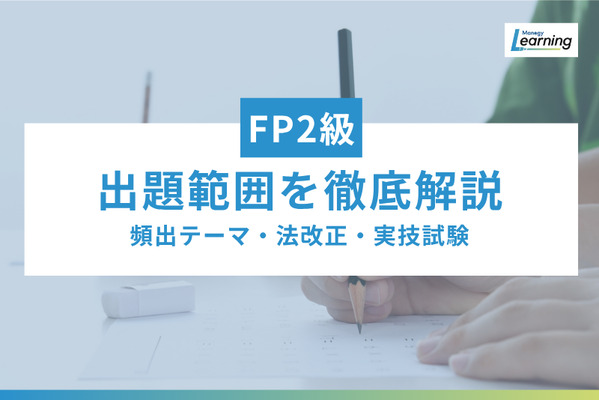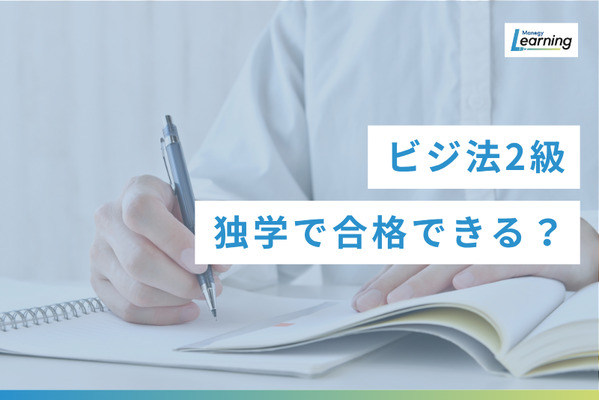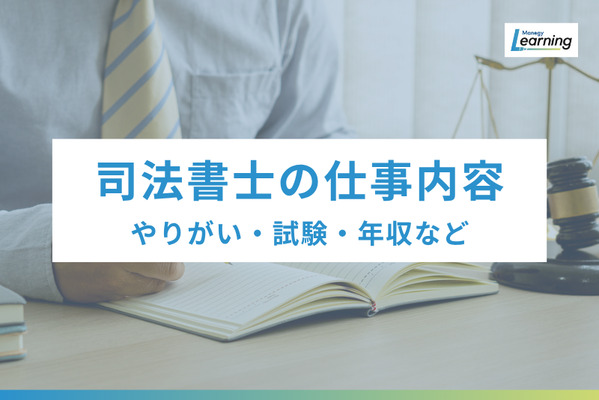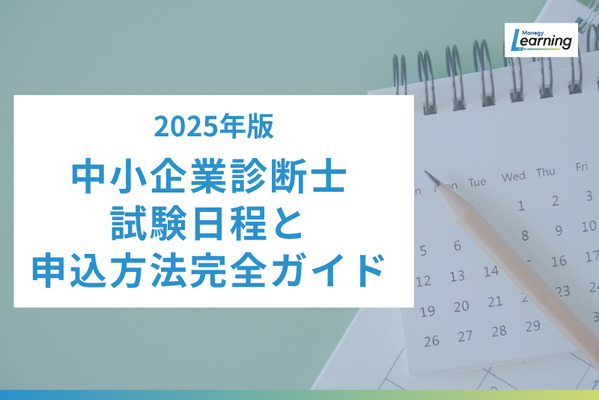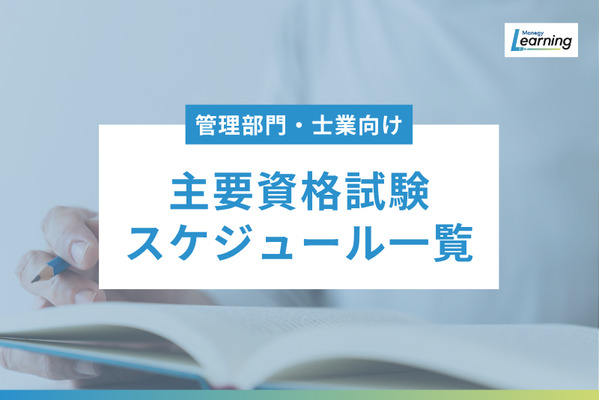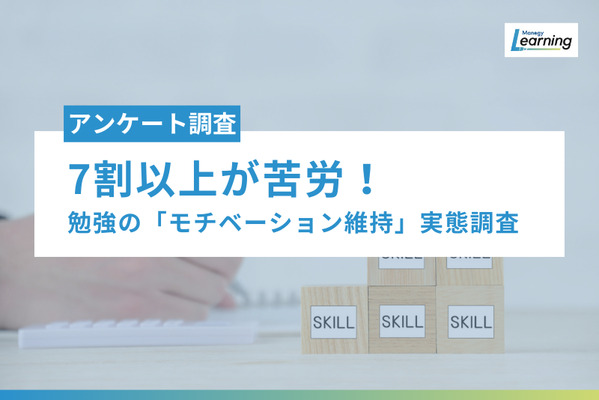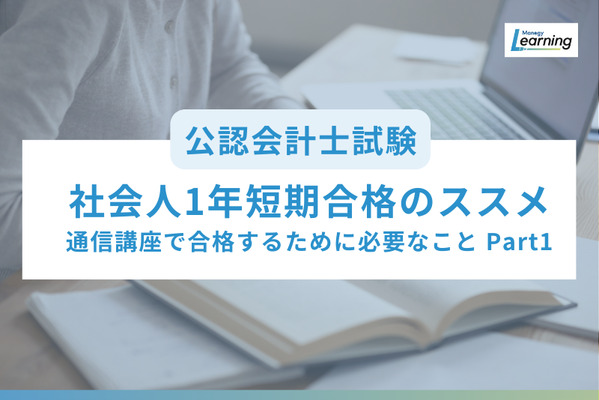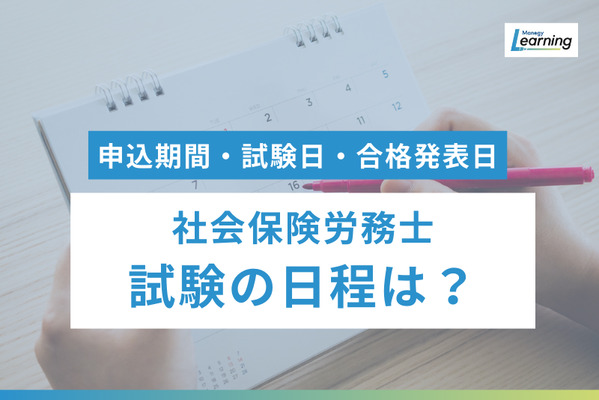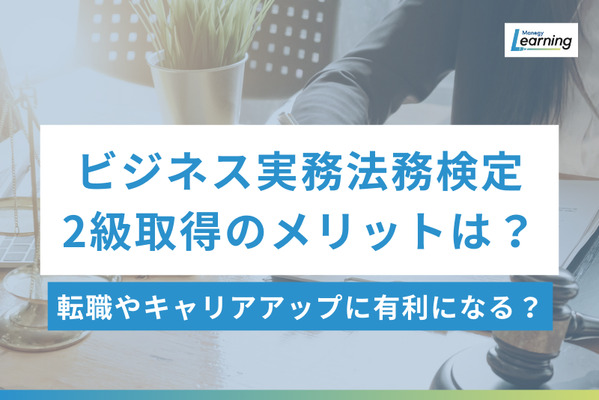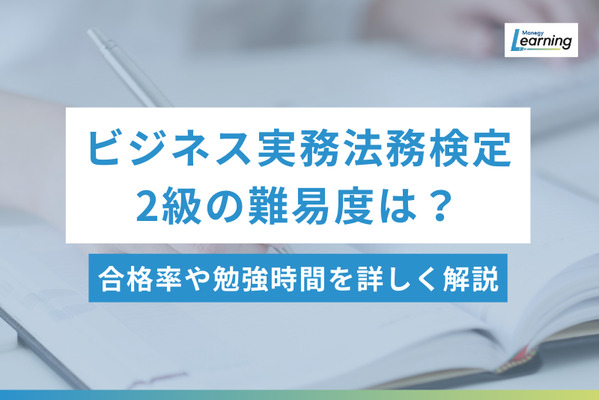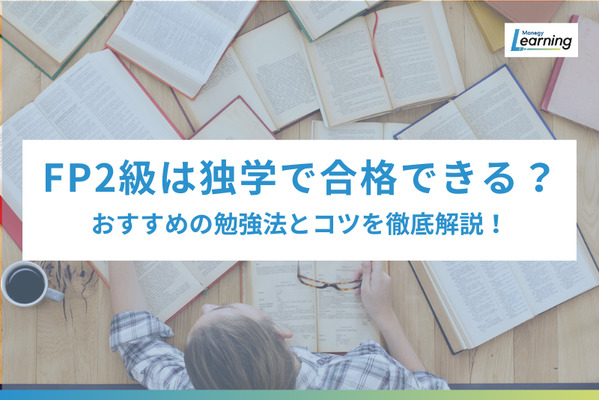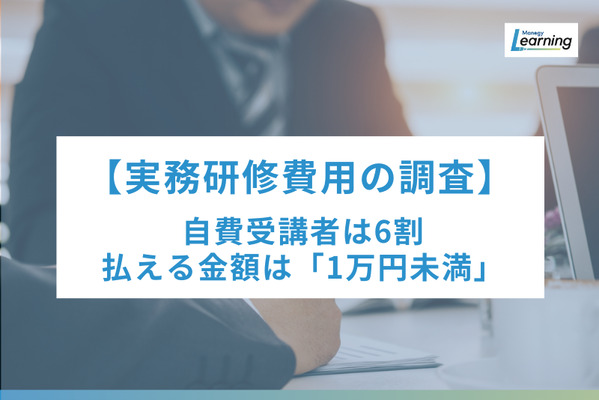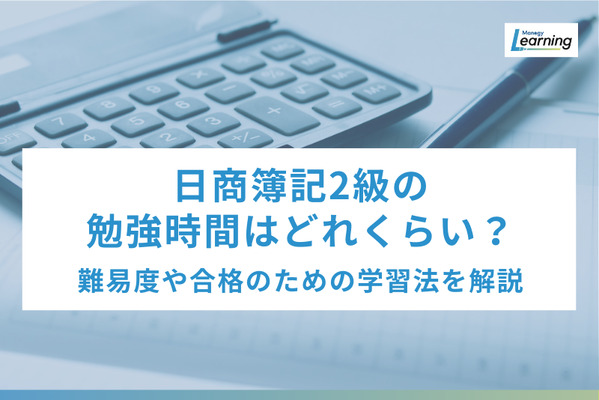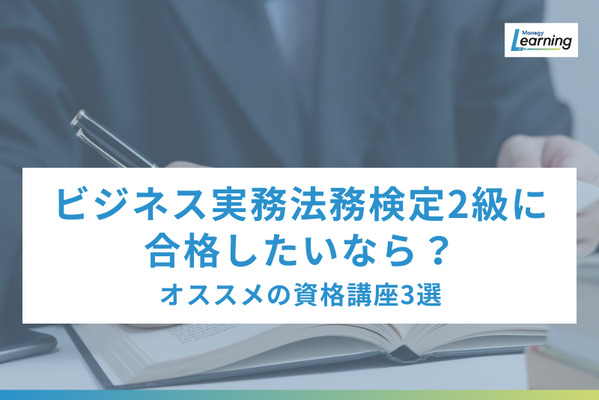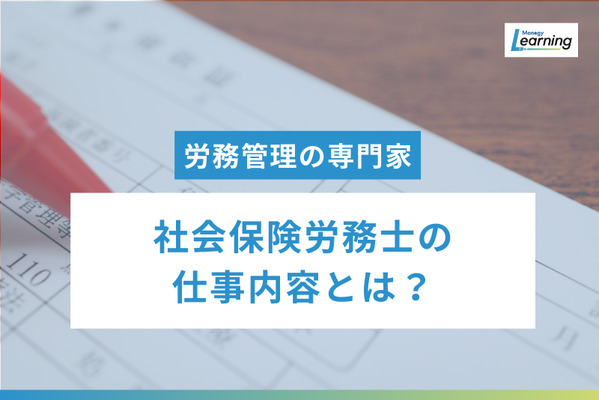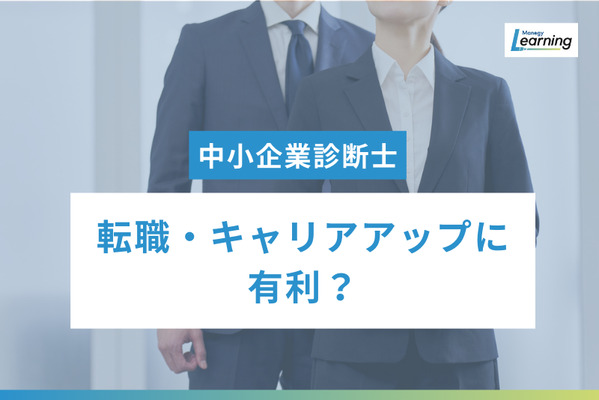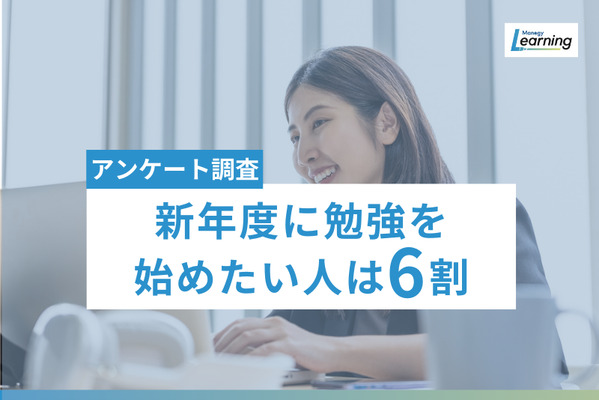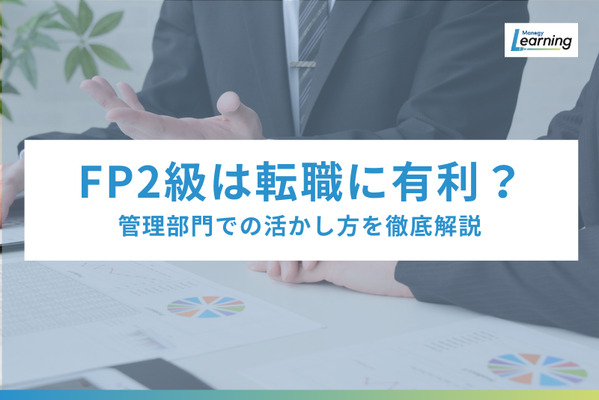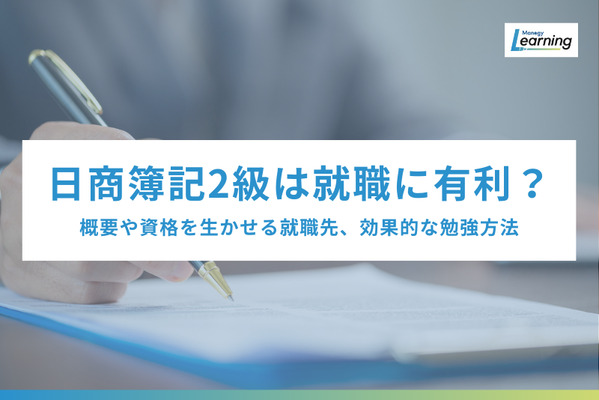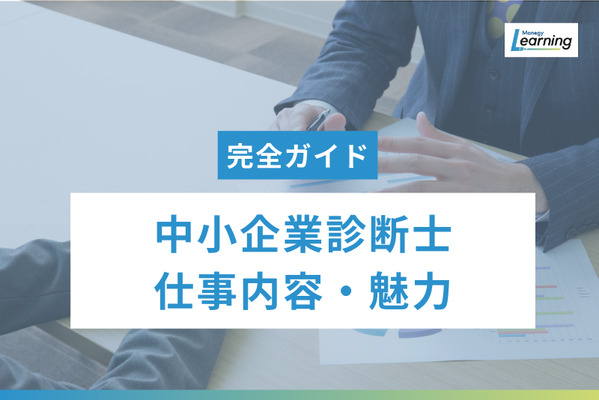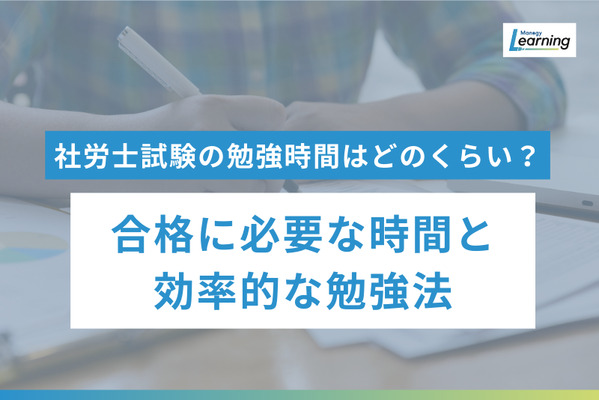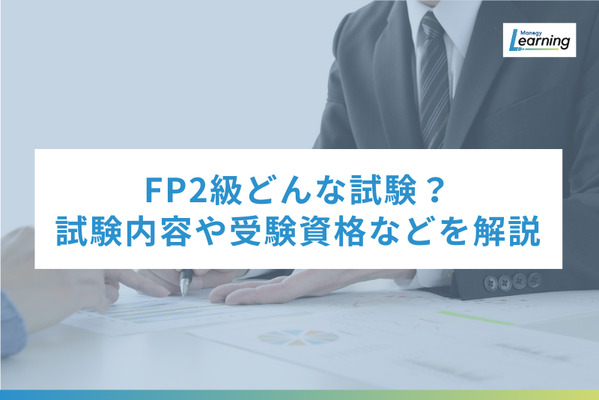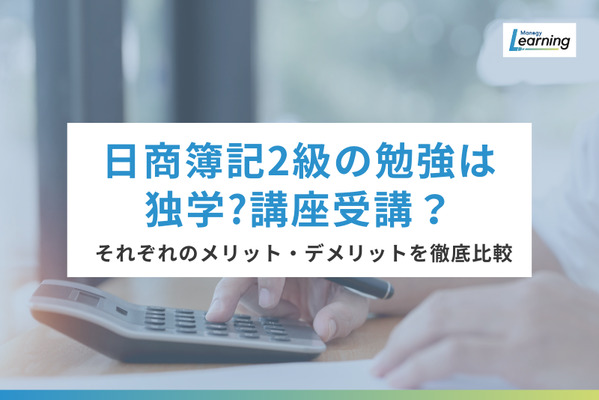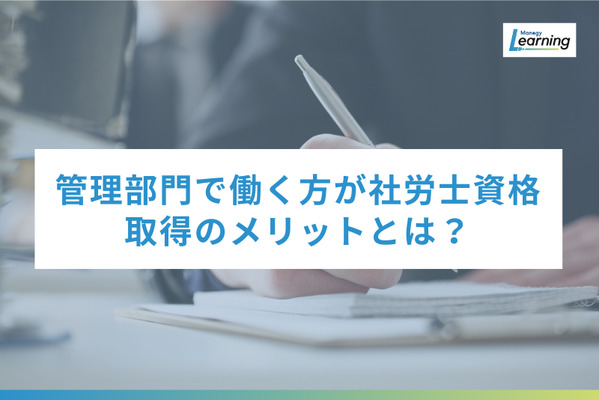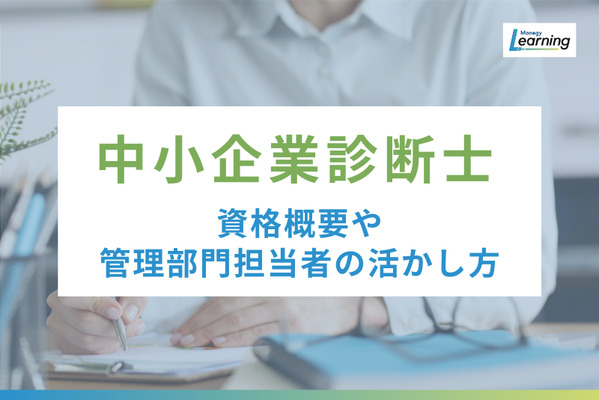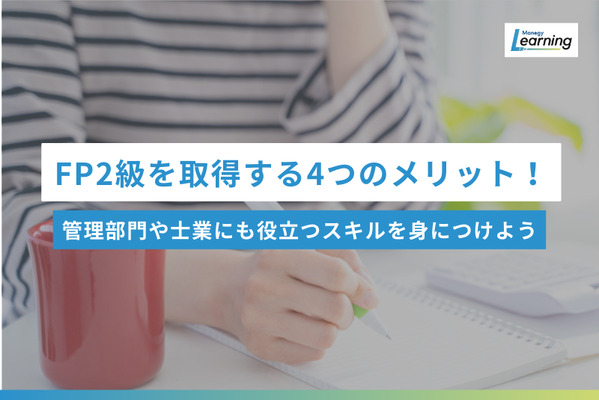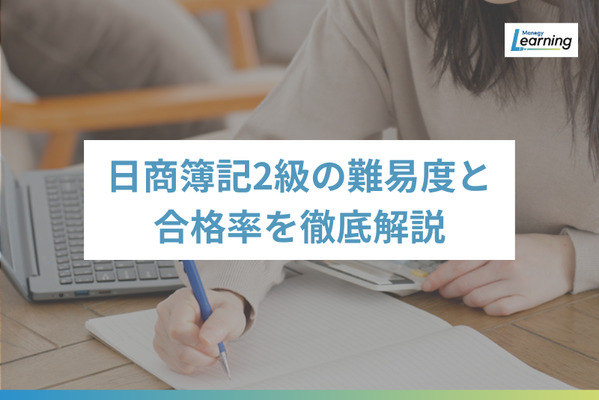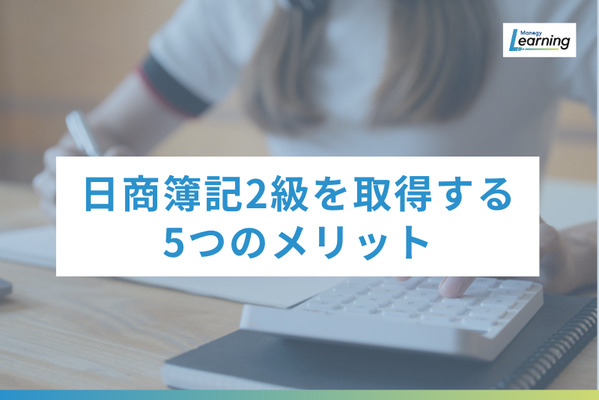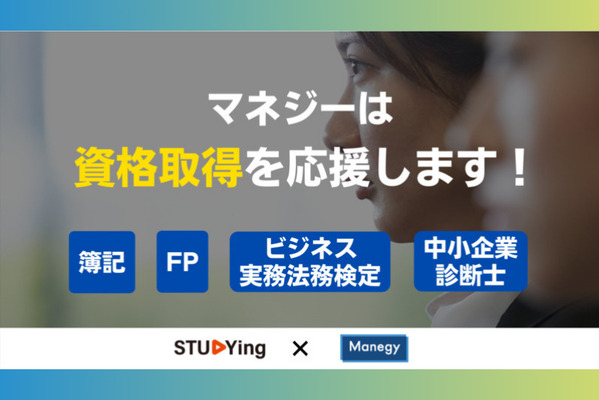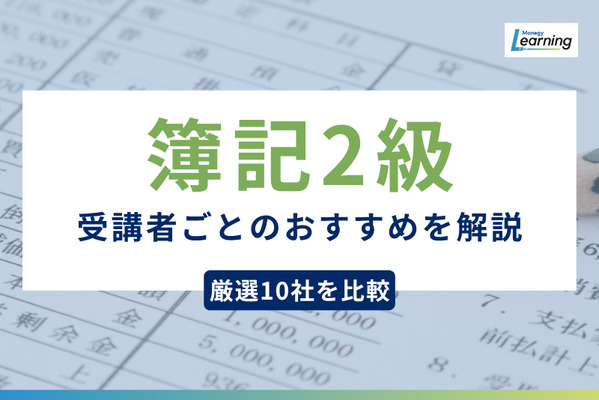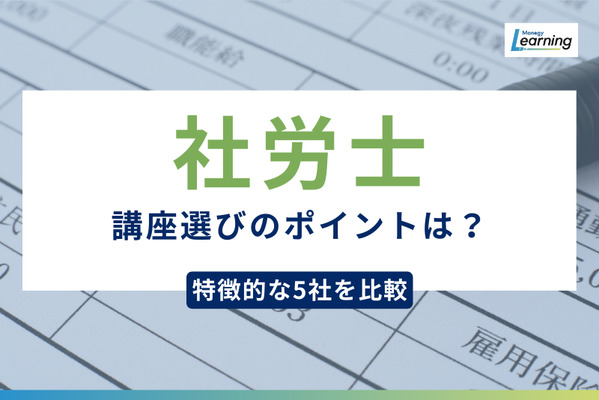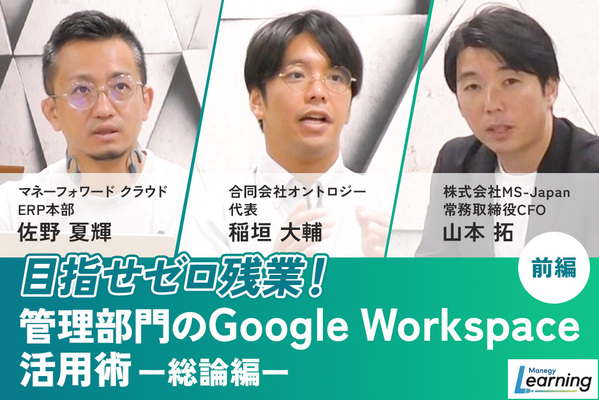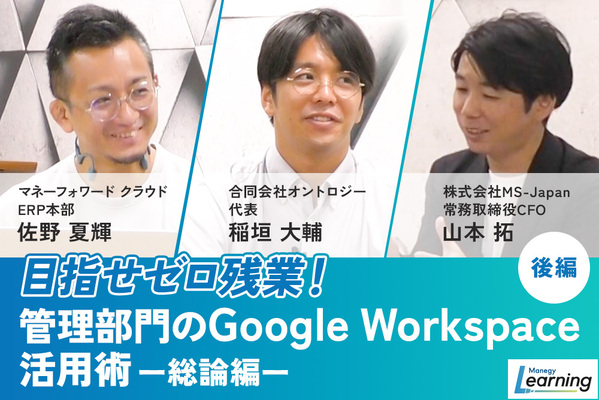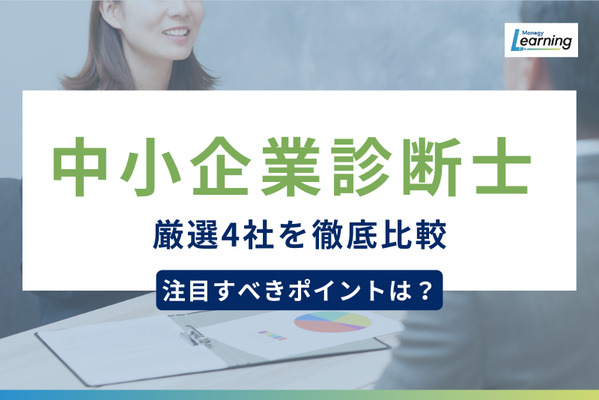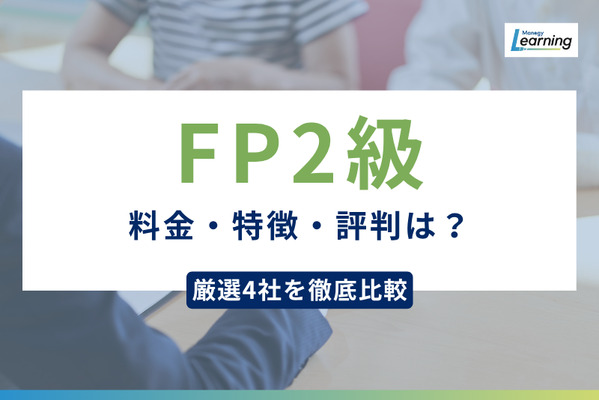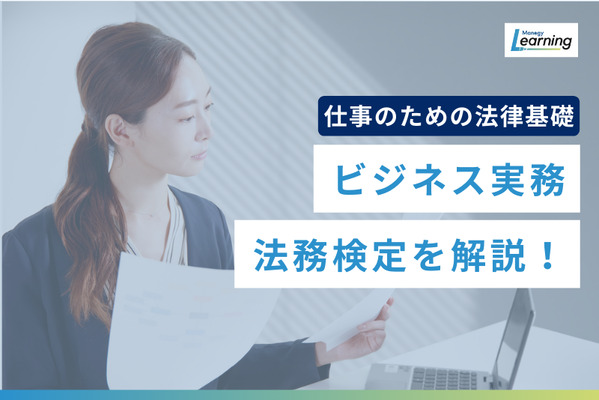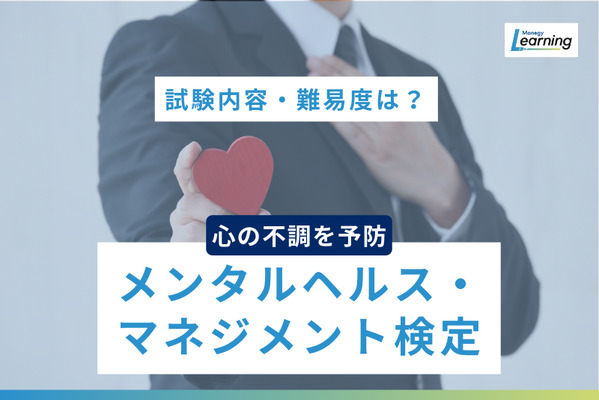社労士とは? 仕事内容・やりがい・資格取得・年収などを徹底解説!
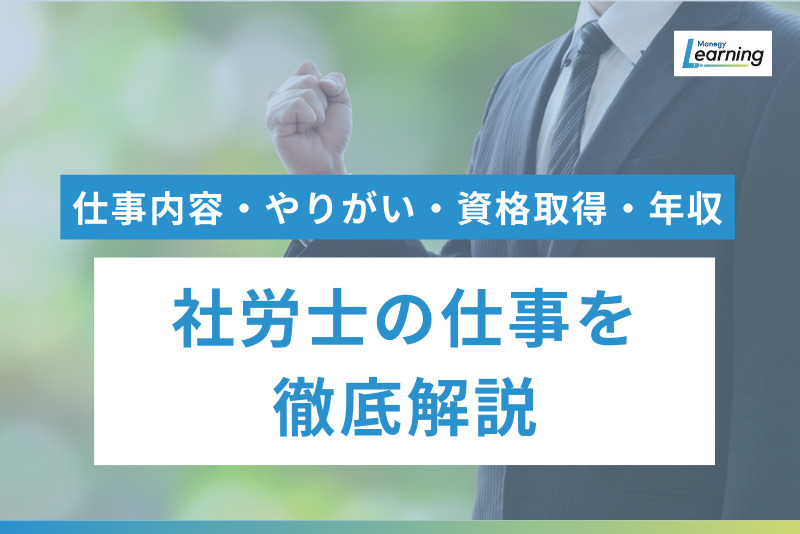
社会保険労務士(以下「社労士」)は、企業の人事・労務管理に欠かせない専門職です。社会において働き方改革や高齢化が進み、労務トラブルや人材育成など企業が抱える課題は複雑化しています。そのようななか、社労士は法的知識と実務スキルを活かしながら、企業と従業員の“橋渡し役”として活躍しています。
本記事では、「社労士とは何か」「仕事内容ややりがい」「資格の取得方法」「年収」など、幅広く解説します。
社労士とは?
社労士は、「人」に関する法律や制度を専門とする国家資格です。業務は労働法や社会保険制度などに関与し、企業での人事・労務管理、社会保険・労働保険の手続き、就業規則の作成や改定、助成金の申請代行などを担います。
企業と従業員の両方の立場を理解し、法令遵守を前提に「働きやすい環境」に整えることが、社労士の役割です。弁護士や税理士と同様、法律に基づいた業務を独占的に行える専門職として、企業経営で欠かせない存在となっています。
近年では働き方改革の推進や労働法制の改正により、社労士の重要性はさらに高まっており、企業経営の法的サポート役としての期待が大きくなっています。
社労士の仕事内容は?
社労士の仕事は、「労働社会保険手続業務」「労働管理の相談指導業務」「年金相談業務」「紛争解決手続代理業務」「補佐人の業務」の5つに大きく分類されます。
今回は、代表的なものについて詳細を解説いたします。
他の業務内容も詳しく知りたいという方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
この記事を読んだ方にオススメ!
(1)社会保険・労働保険の手続き代行
企業が従業員を雇った際の雇用保険・社会保険の加入手続きや、退職に伴う喪失手続き、年度更新や算定基礎届などの定期的な手続きなどを、社労士が企業に代わって行います。ミスや遅延が許されない、正確性が求められる事務手続きです。また、法改正により書類の届出様式などが変更されることもあり、常に最新情報を得ることが必要です。
(2)労務トラブルの予防と対応
社労士は、労働問題においても専門知識を求められます。例えば、以下のようなケースに対応します。
- 長時間労働や未払い残業代問題の是正
- ハラスメント(パワハラ・セクハラなど)対策の整備
- メンタル不調者への対応や休職復職制度の運用
- 解雇や退職に関するトラブルの防止 など
まずは上記のようなトラブルを未然に防ぐため、労働法を遵守した就業規則の整備や、内部通報制度の導入支援などに取り組みます。そのうえで、発生した労使トラブルの相談・対応も行なうのです。
(3)人事制度設計や組織改善の支援
社労士は企業の“人事・労務のコンサルタント”として、等級制度・評価制度・賃金制度などの設計・導入支援や見直しを行うこともあります。人材定着や従業員のモチベーション向上のために、適切な制度運用のアドバイスを行うなど、企業の組織改革に深く関われるのも、社労士の仕事のおもしろさです。
(4)助成金申請の支援
助成金業務は、社労士が独占的に行える仕事のひとつです。雇用関係の助成金は種類が豊富で、対象や申請要件が細かく定められています。そのため、企業勤めで専門知識がない一般的な従業員が対応すると、対応に苦労しがちです。
社労士は、助成金の受給可否の判断から必要書類の作成、申請スケジュールの管理までをまとめて行います。
社労士のやりがいと魅力は?
社労士の仕事は多岐にわたるため、仕事のやりがいも複数あります。例えば以下のような点が、社労士として働く魅力と言えるでしょう
(1)働きやすい組織づくりに貢献し、企業の成長を支えられる
社労士は、企業の“人”に関わる仕組みづくりを支援します。就業規則を整備することで従業員の働き方を改善できたり、助成金の活用で企業の人材育成を後押しできたりします。働きやすい組織づくりへの貢献は企業の発展へとつながり、大きなやりがいを感じることができるでしょう。
特に近年は、多様な働き方やワークライフバランスの重要性が高まっており、これらの実現を支援する社労士の役割はより重要になっています。
(2)専門職として信頼され、誇りを持って働くことができる
社労士は法律に基づく専門的な国家資格者であり、信用と責任を持って業務を行います。企業の経営の一翼を担える存在であること、自身の知識や経験がダイレクトに価値として評価される点も、やりがいに直結します。
(3)働き方の自由度が高い
社労士は独立開業も可能な職種です。自分の裁量で仕事を選び、働き方をコントロールする事が可能です。また、企業内社労士や社労士法人での勤務も可能なため、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方ができます。
社労士はどんな人に向いている?
では、どのような人が社労士に向いているのでしょうか? 一例を以下にあげました。
(1)人の話をよく聞き、丁寧に対応できる人
企業経営者や従業員など、さまざまな人との関係構築が求められる職種のため、コミュニケーション力が不可欠です。相手の立場や状況を理解し、適切なアドバイスができる人に向いています。
(2)法律や制度を学び続けることができる人
労働法や社会保険制度は頻繁に改正されるため、学び続ける姿勢が求められます。
2025年も引き続き、働き方に関する法改正や社会保険制度の見直しが予定されており、常に最新情報をキャッチアップする必要があります。
(3)人の役に立ちたいという気持ちが強い人
社労士の仕事は“人のために働く”ことが大前提です。働く人々をサポートすることにやりがいを感じ、役立ちたいと思える人が、この仕事に適しています。企業と従業員の双方にとってベストな解決策を模索し、提案できる人が求められています。
どうすれば社労士になれる?
社労士になるには、「社会保険労務士試験」に合格し、社労士会に登録する必要があります。ここでは、試験の概要や合格までのステップ、勉強方法まで詳しく解説します。
この記事を読んだ方にオススメ!
社労士の資格試験の概要
- 試験の実施:年1回(例年8月の第4日曜日)
- 試験科目:選択式8科目+択一式7科目
- 試験時間:選択式(80分)、択一式(210分)の2種類を受験
- 合格率:毎年6~7%前後(難関資格のひとつ)
試験科目
社労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労務管理その他の労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法
試験はマークシート形式で実施され、午前と午後に分けて行われます。特徴的なのは「科目ごとの足切り点」がある点で、総合得点が基準を満たしていても、1科目でも基準点を下回ると不合格になります。そのため、バランスよく全科目を学習することが、合格へのカギです。
受験資格について
社労士試験には受験資格が設けられており、以下のいずれかに該当している必要があります。
- 大学・短大・高等専門学校などを卒業(学部不問)
- 大学・短大・高等専門学校などを卒業(学部不問)
- 厚生労働大臣の認める国家資格(公認会計士、弁理士、税理士など)保有者
まずは自分が受験できるかを社会保険労務士オフィシャルサイトで確認しましょう
勉強方法と学習スケジュール
社労士試験は「難関国家資格」に分類され、合格までに必要な学習時間は一般的に800~1,000時間以上と言われています。1日2~3時間の勉強を1年程度続けるペースが目安です。
勉強の進め方としては、まず参考書で基礎固めをして過去問演習を徹底して解くのが良いでしょう。
主な勉強方法
(1)独学
市販のテキストや過去問を使って自己管理で進めます。費用が抑えられますが、自己管理力と情報収集力が問われます。
(2)通信講座
映像講義とテキストがセットになったコースで学習。スケジュール管理や苦手科目の克服もサポートされるため、初心者や働きながら目指す人におすすめです。
(3)通学講座
資格学校に通って対面授業を受けるスタイル。講師の解説を直接受けられる点が魅力ですが、時間や費用のハードルがあります。
試験合格のため、通信講座や通信講座を検討している方は、こちらも参考にしてみてください。
この記事を読んだ方にオススメ!
合格後の流れ
試験に合格した後、社労士として活動するには、全国社会保険労務士会連合会への登録が必要です。登録には試験合格に加え、2年以上の実務経験または事務指定講習の修了が必要です。
登録後は、「社労士証票」が交付され、正式に社労士として業務を始めることができます。
登録の種別は「開業」「社労士法人社員」「勤務」「その他」から選択でき、登録の際には登録手数料30,000円のほか、入会金・年会費などが必要です。
※金額は各都道府県の社労士会によって異なります
社労士は、制度を学び続ける姿勢と計画的な学習が求められる資格ですが、合格後には高い専門性と自由度のあるキャリアが待っています。
試験合格後のキャリアについて、さらに詳しく知りたい方には、こちらの記事がおすすめです。
この記事を読んだ方にオススメ!
社労士の年収は?
社労士の年収は、働き方や経験年数、地域、得意分野などによって大きく異なります。ここでは、勤務社労士と開業社労士それぞれのケースを詳しくご紹介します。
勤務社労士の年収
企業や社労士事務所に勤務する「勤務社労士」の平均年収は、400万円台~500万円台が一般的です。
新卒や未経験者(見習い)の場合は年収250万円前後からのスタートが多いようです。勤務3~5年の経験者だと年収400万円台~500万円台となる人が多くなり、中堅・管理職クラスになると年収600万円以上も可能に。特に、大手社労士法人や上場企業の人事部門で働く場合は、年収700万円以上となるケースもあります。
開業社労士の年収
独立開業した社労士の年収は、300万円台~1,000万円超まで幅があります。これは、顧客の数や報酬単価、営業力によって大きく変動するためです。
開業してから3年目くらいまでは年収200万円台~400万円台程度が珍しくなく、軌道に乗ってくると年収500万円台~700万円台に、さらに成功してベテランクラスともなると年収1,000万円以上も可能です。
なお、社労士の収入には地域差もあります。首都圏(東京・神奈川など)は企業数が多いため、顧問契約が取りやすく報酬単価も高めです。一方、地方では顧客単価が低い傾向がありますが、そのぶん競合が少なく、地域密着で長期的な関係性を築けるという強みもあります。
まとめ
社労士は、企業の人事・労務に関するあらゆる課題を解決に導く、現代社会に欠かせない専門職です。手続き代行だけでなく、職場環境の整備や助成金活用など、その仕事内容は多岐にわたります。
社労士のやりがいは、「人と企業の成長に貢献できること」「専門職として自立できること」「自由な働き方が選べること」です。試験は難易度が高めですが、努力次第で誰でも資格取得を目指すことが可能です。
合格率は約6~7%程度(2024年は6.9%)ですが、計画的な学習と継続的な努力により合格を目指せる資格です。
社労士は、働く人の未来を支える“縁の下の力持ち”です。興味がある人はぜひ、資格取得にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
この記事を読んだ方にオススメ!

Manegy Learning
Manegy Learningは管理部門・士業の皆さまに向けて、実務に役立つTIPSや資格取得のためのスクール取得などの情報を発信し、みなさまの学びをサポートします。
MS-Japan
https://www.manegy.com/learning/