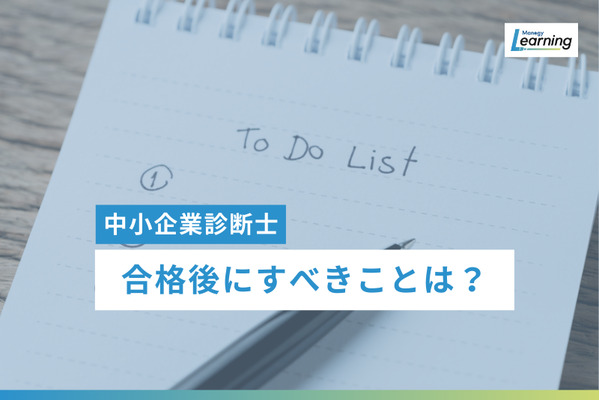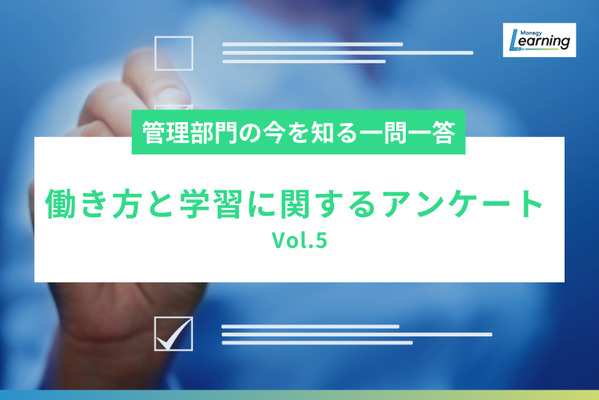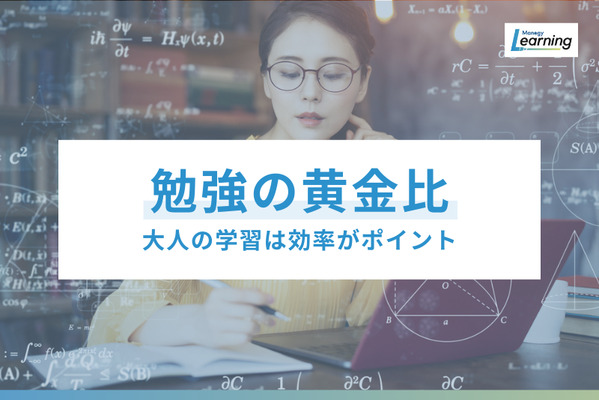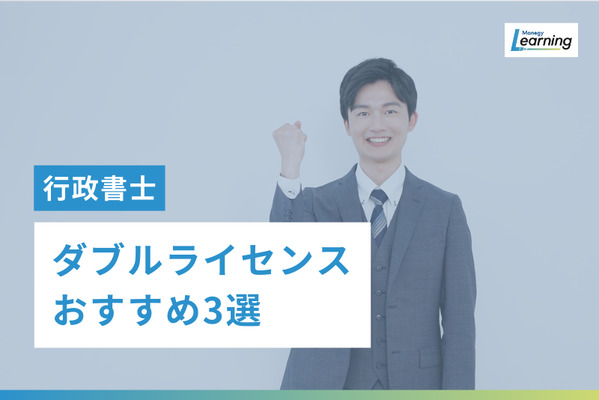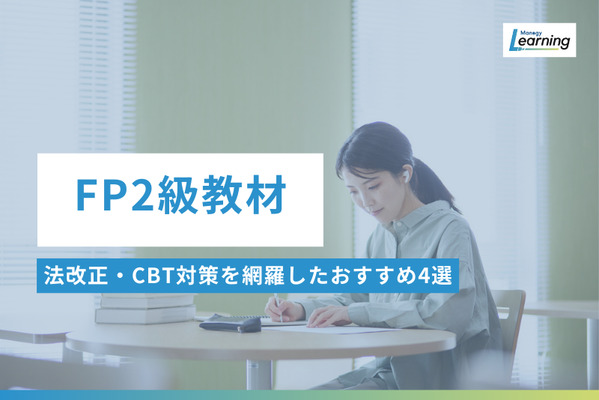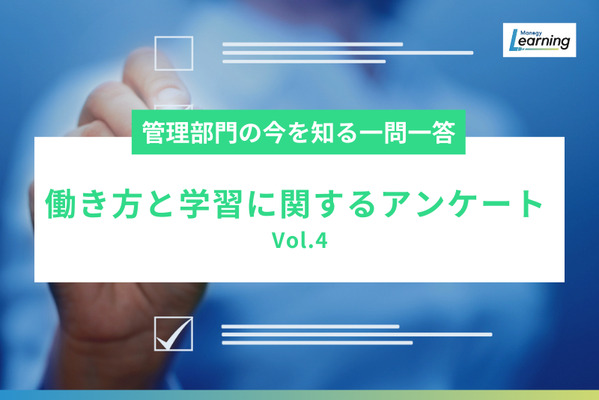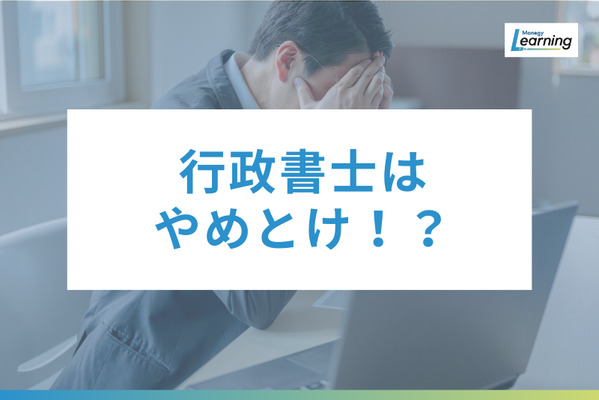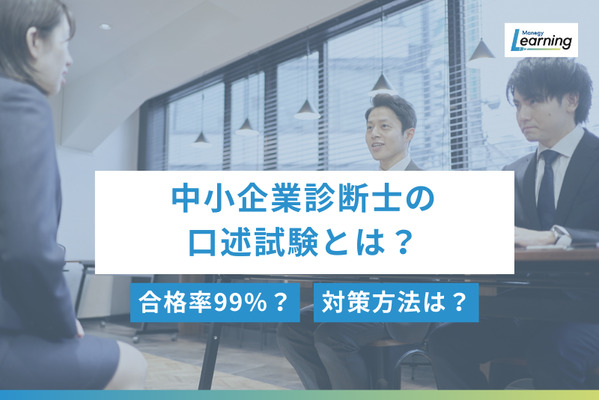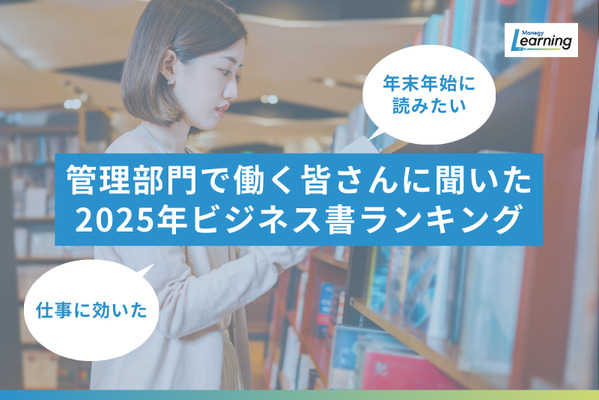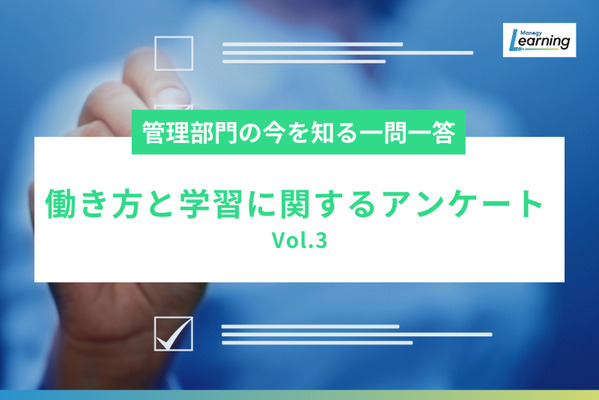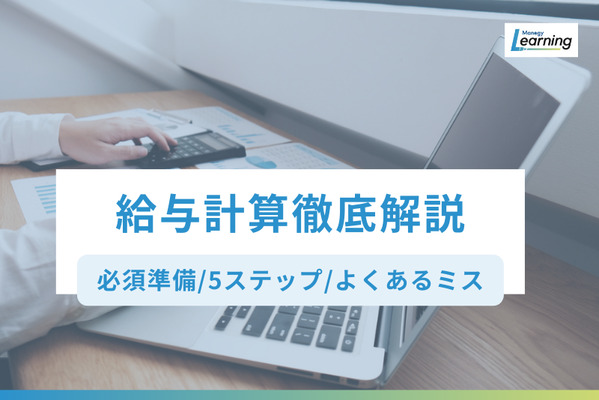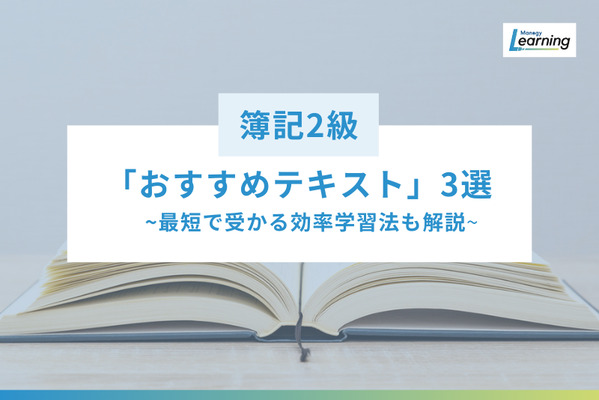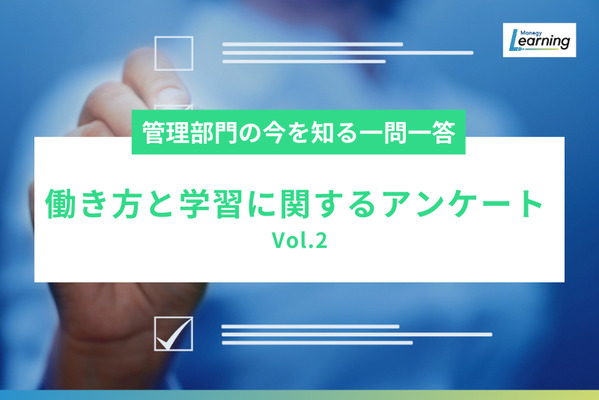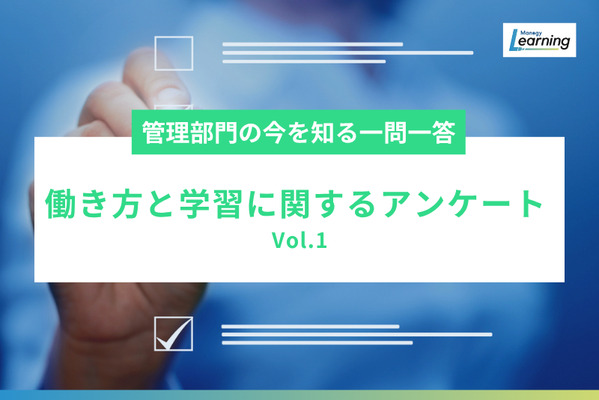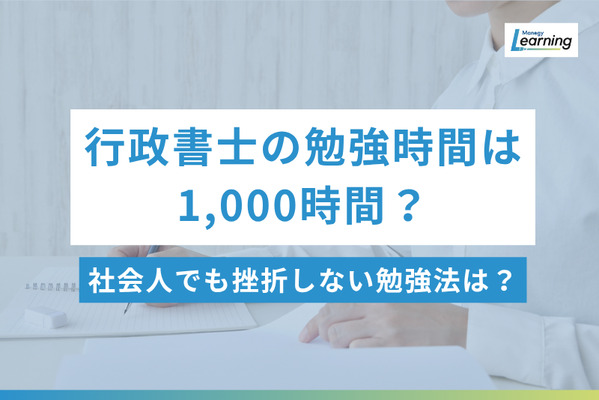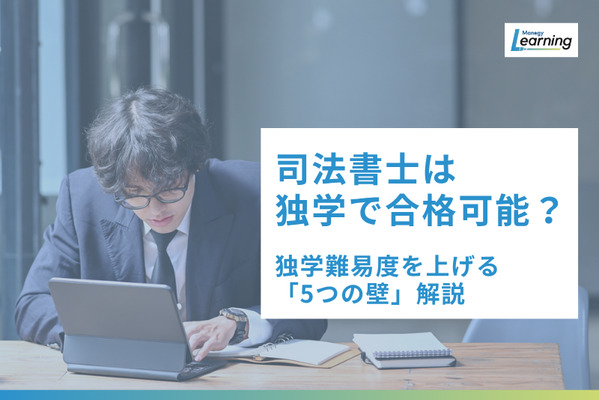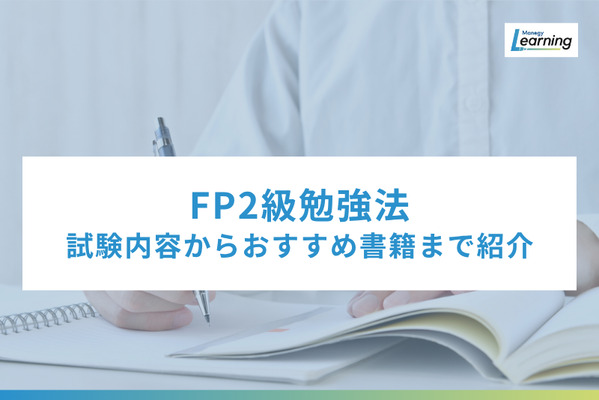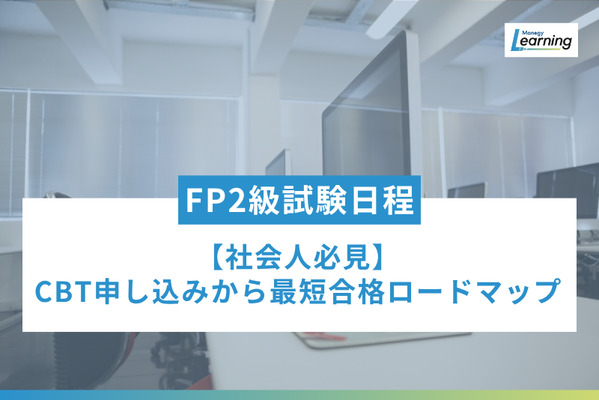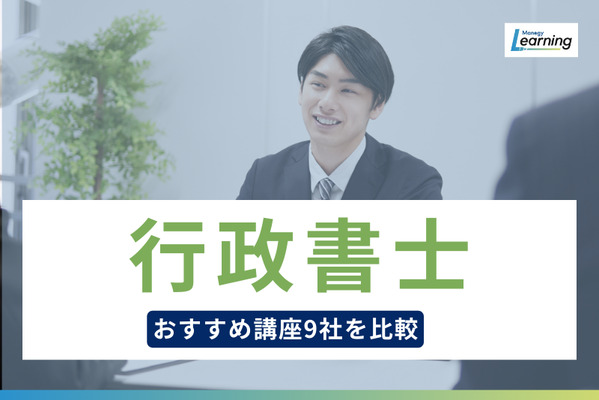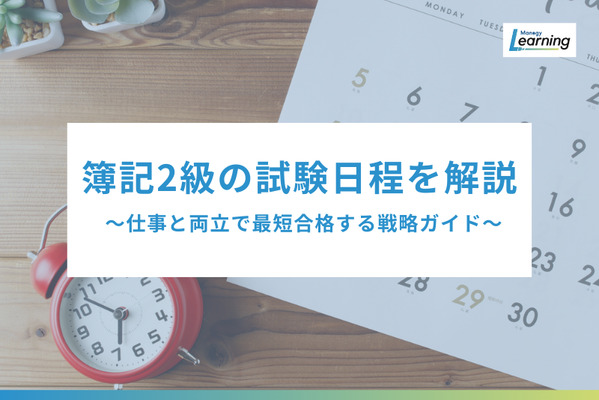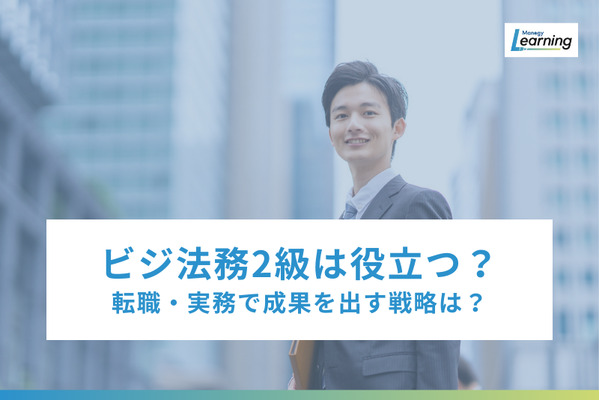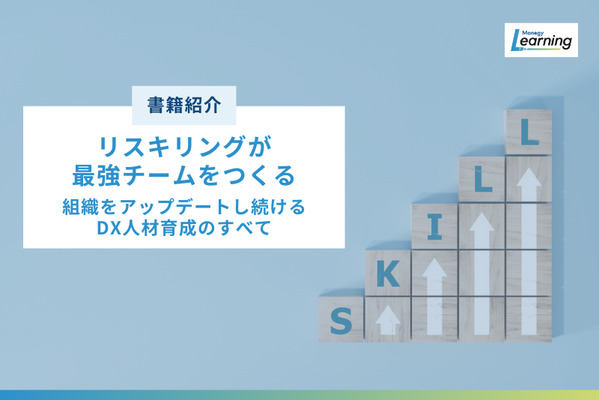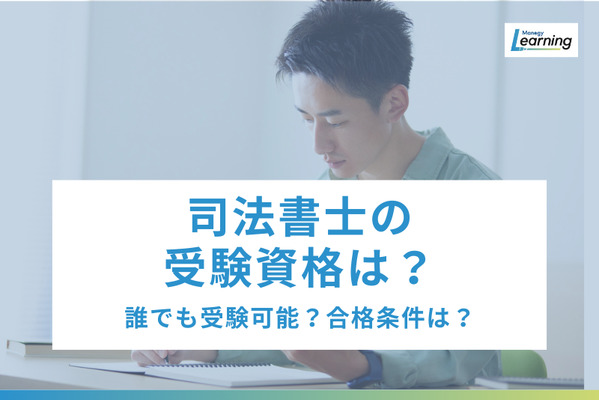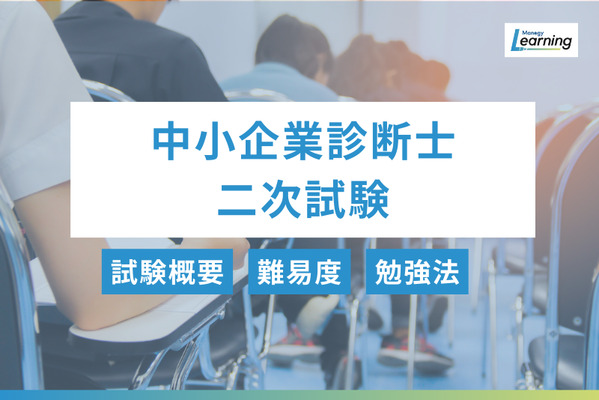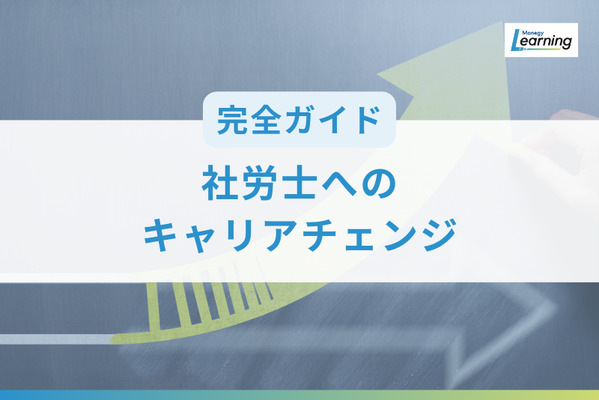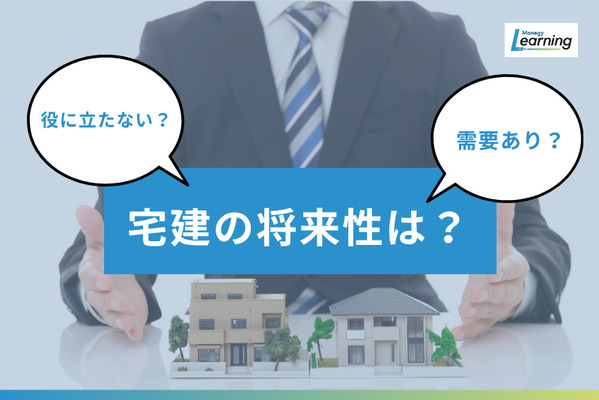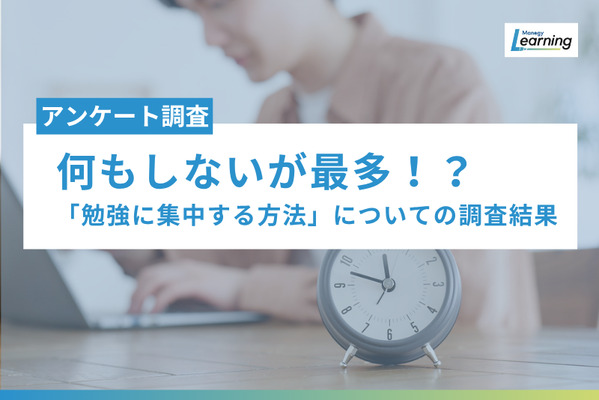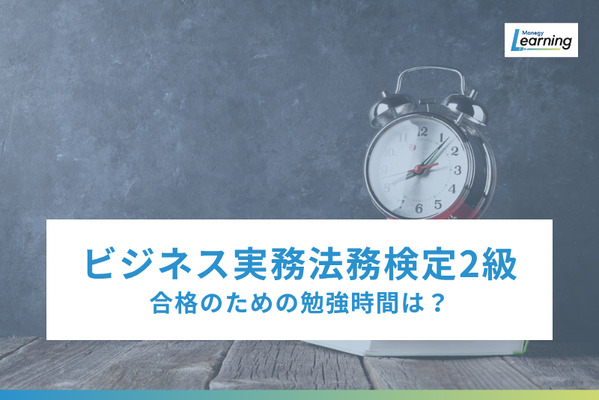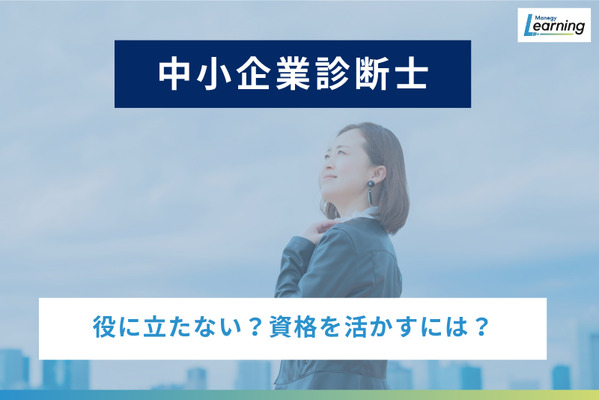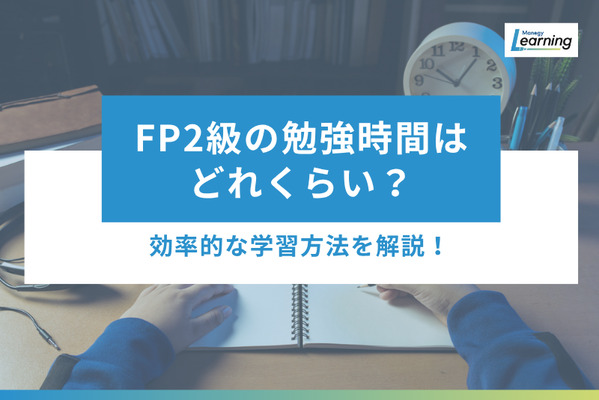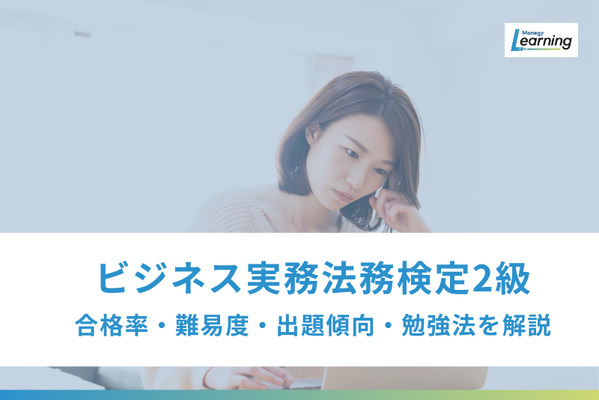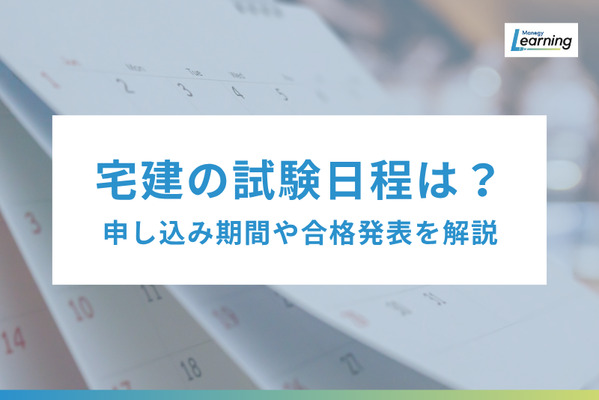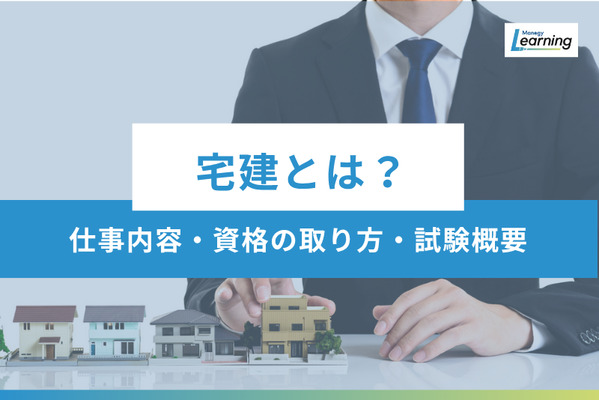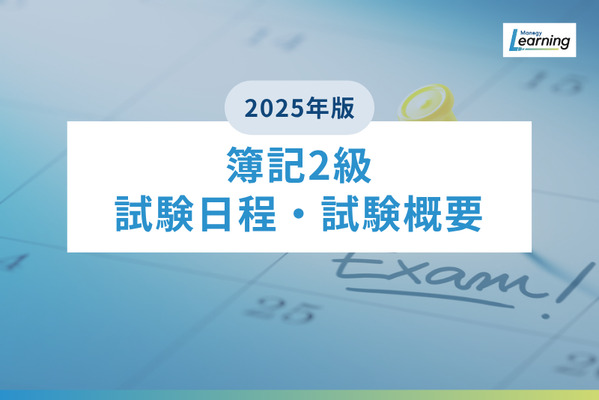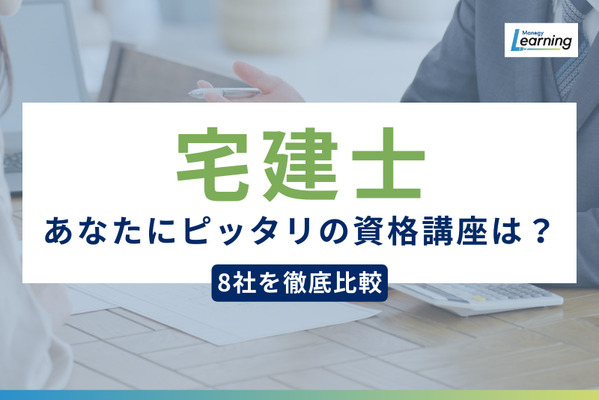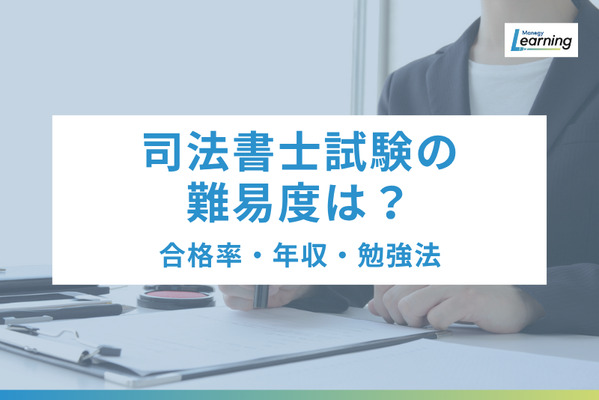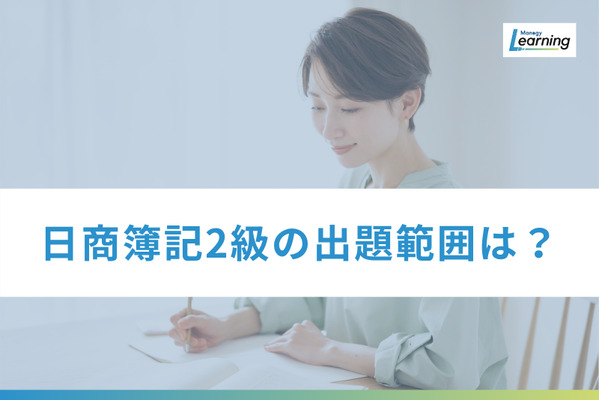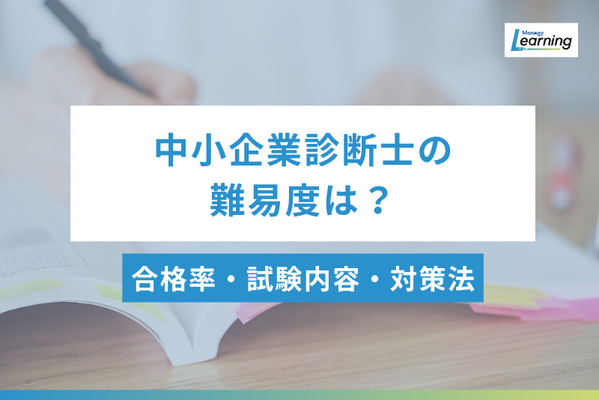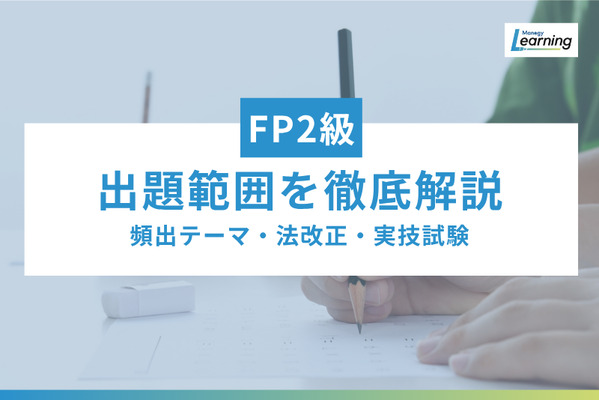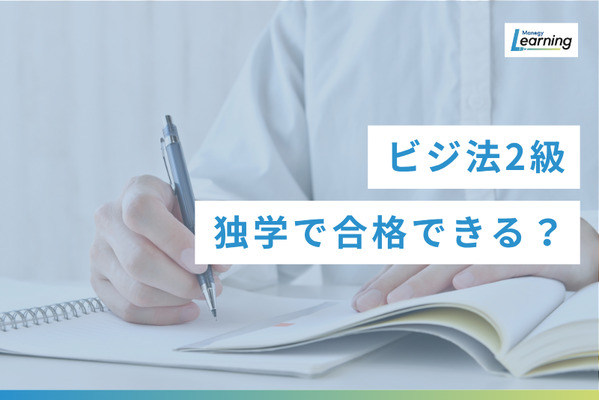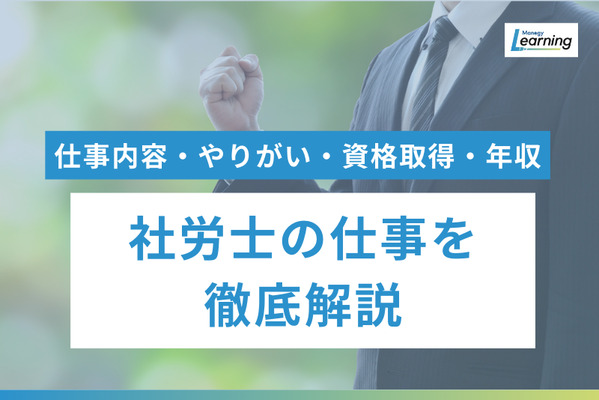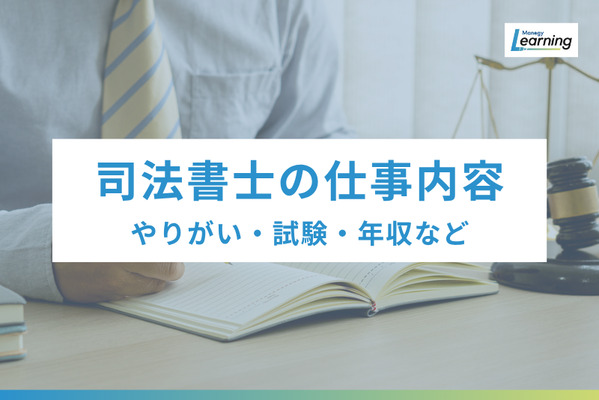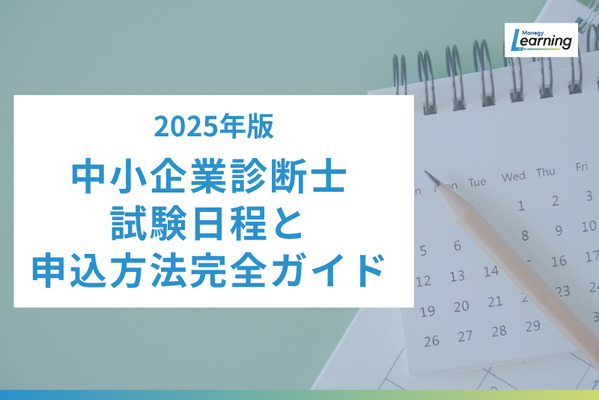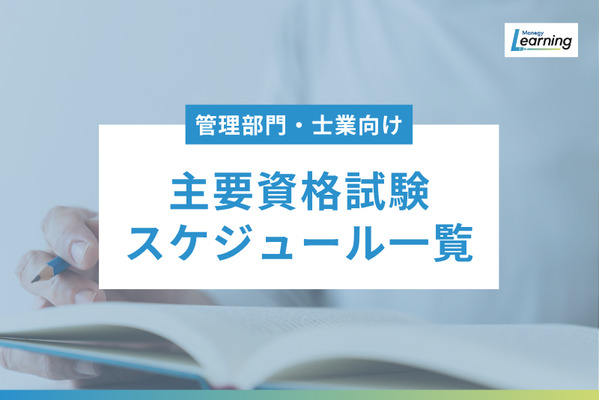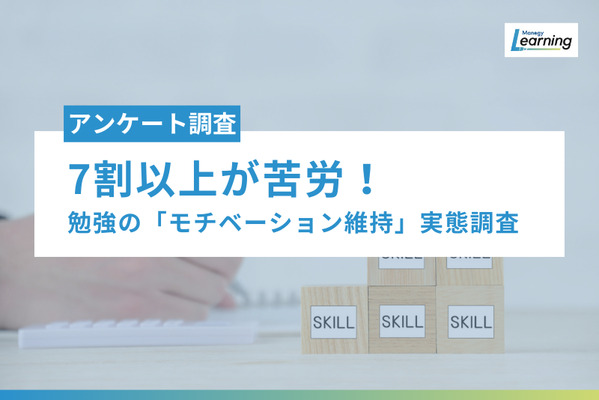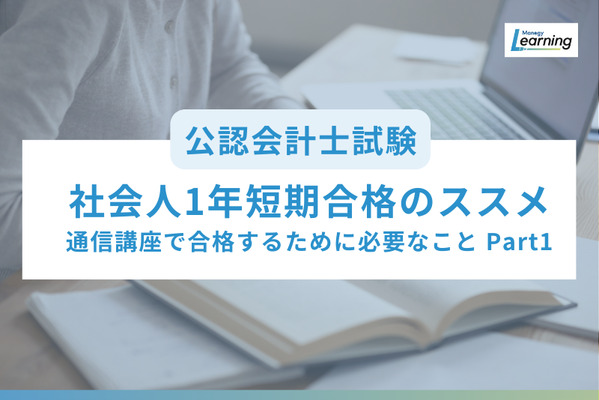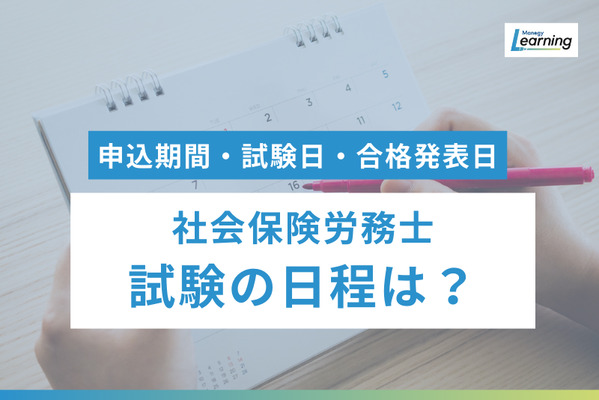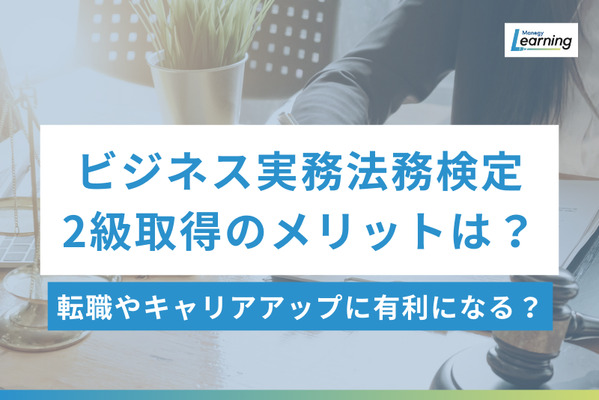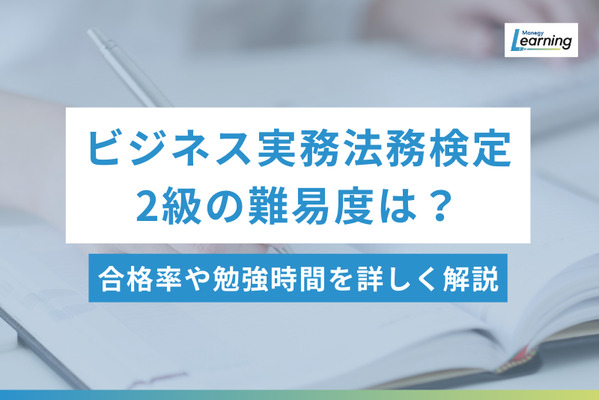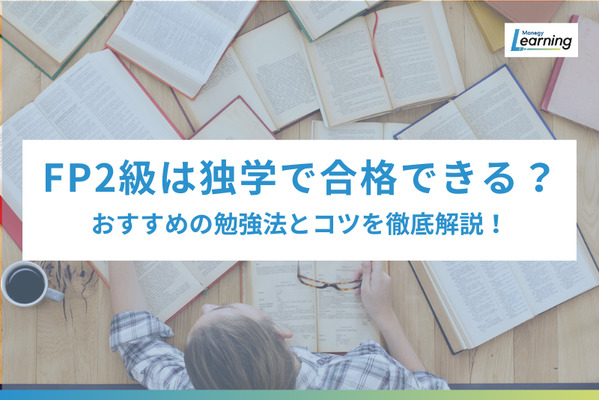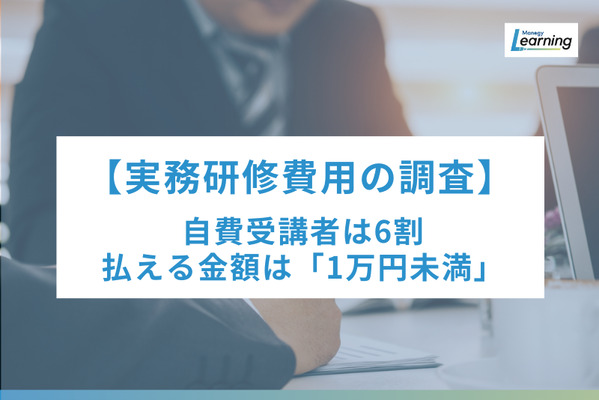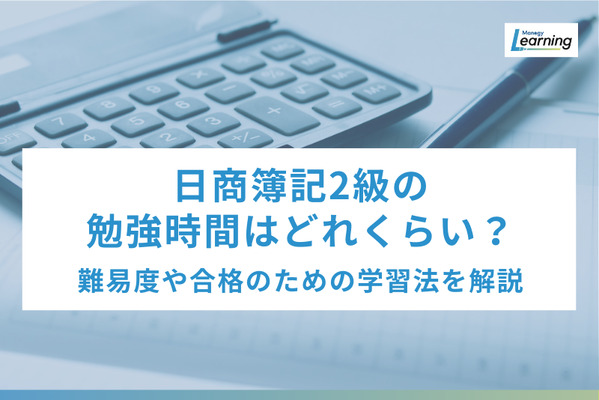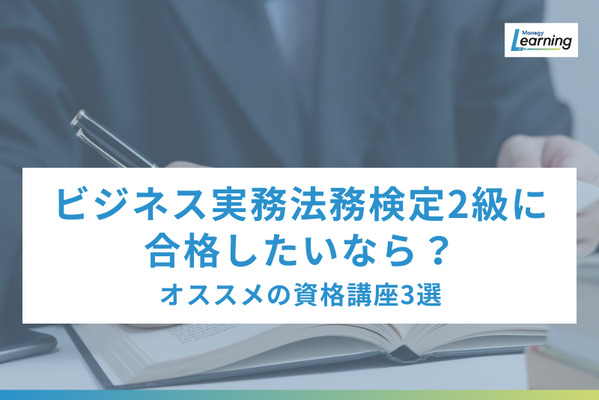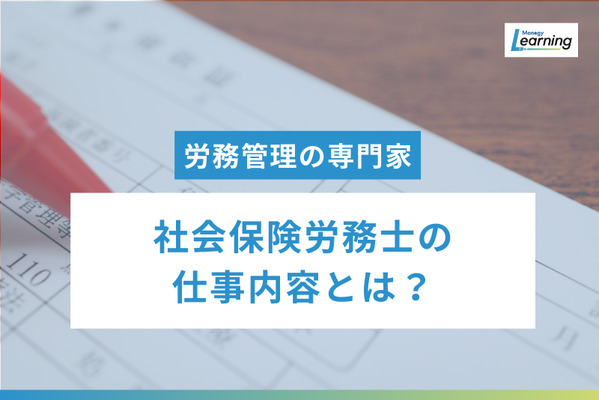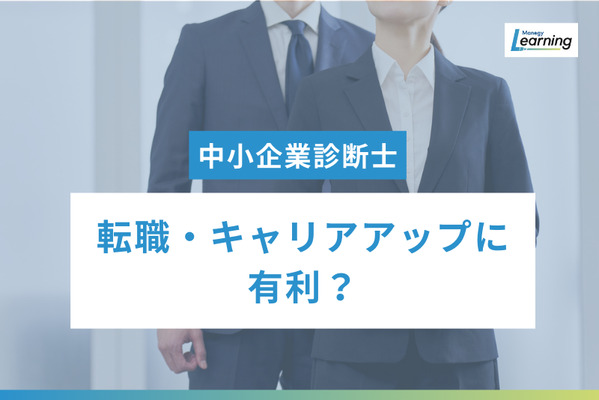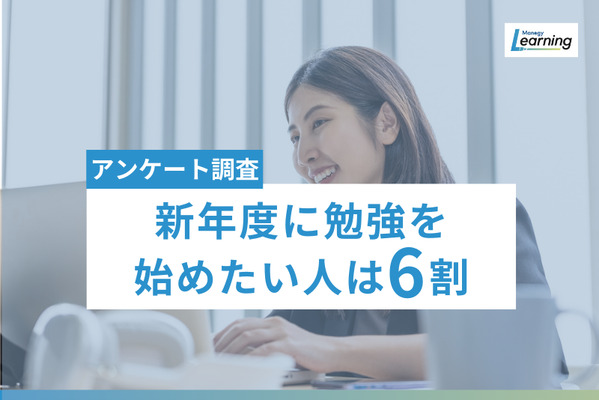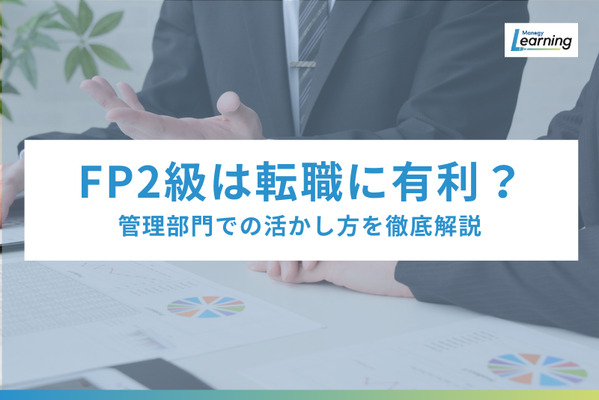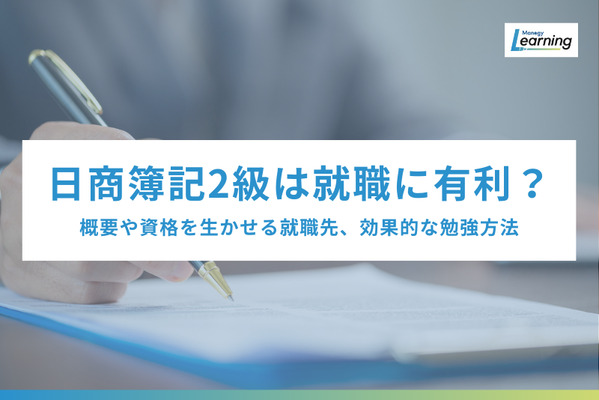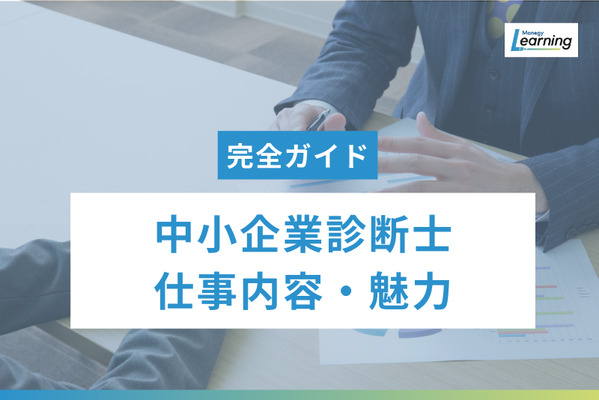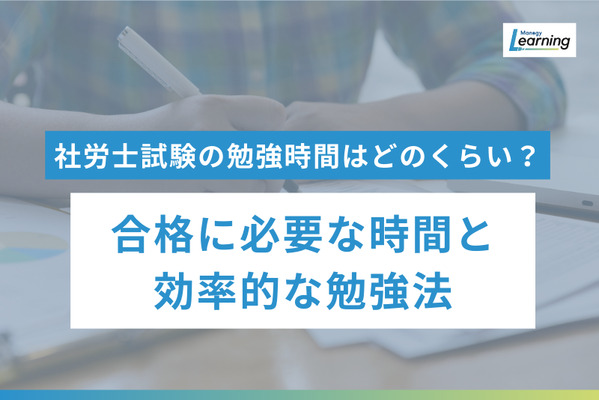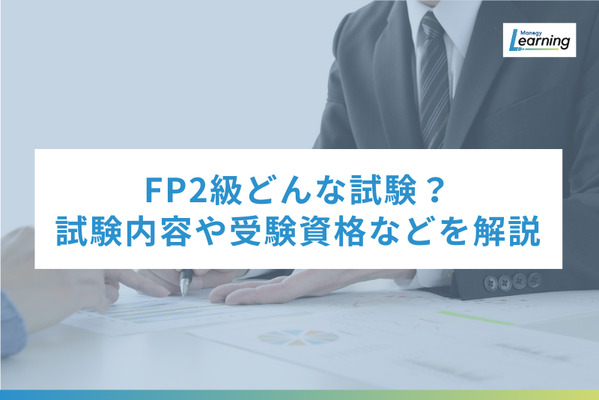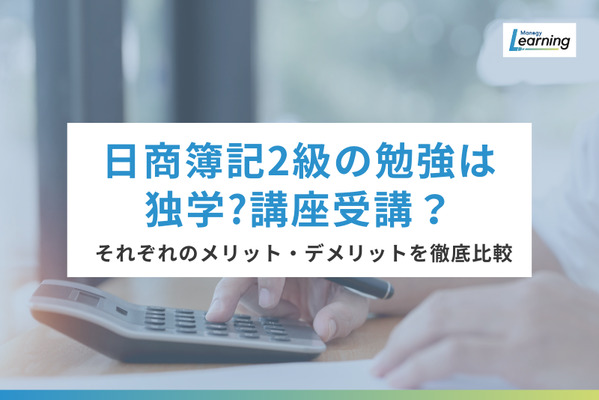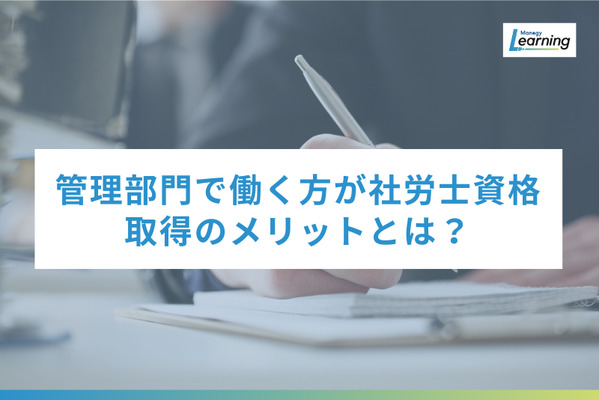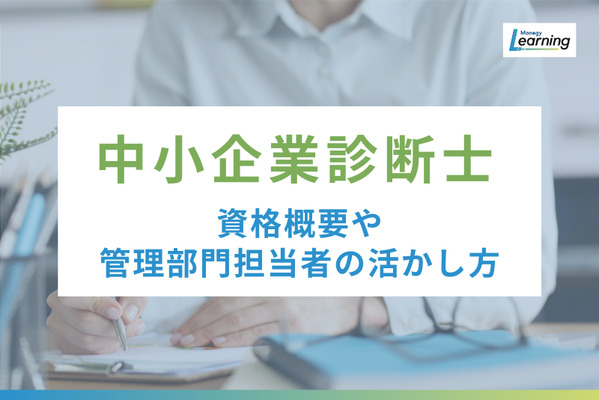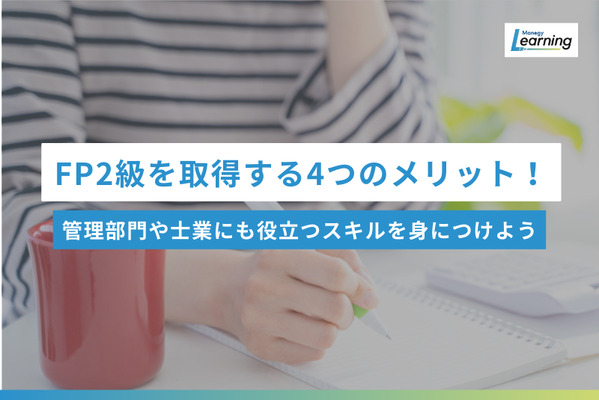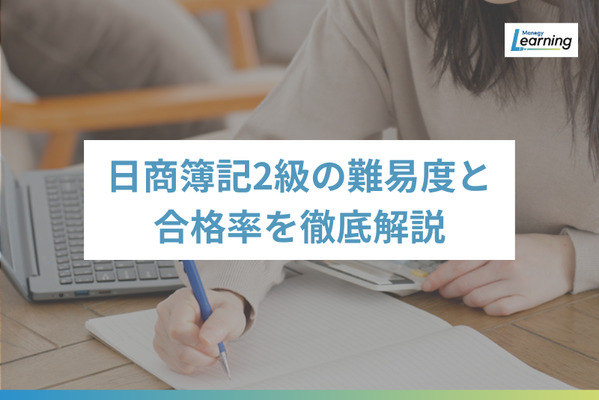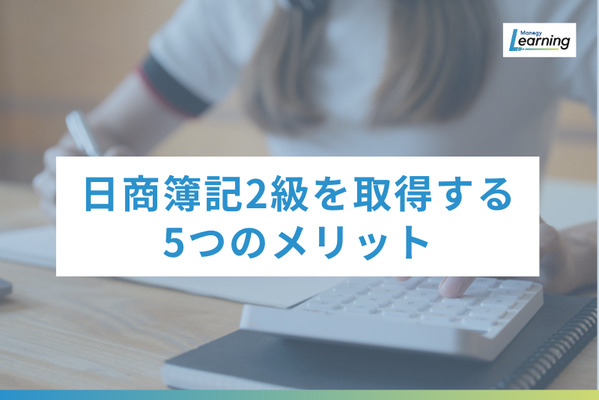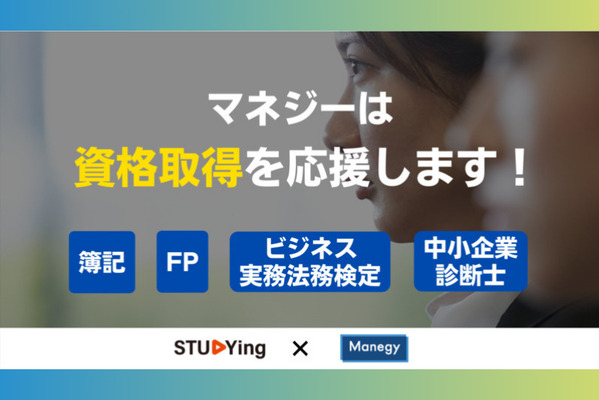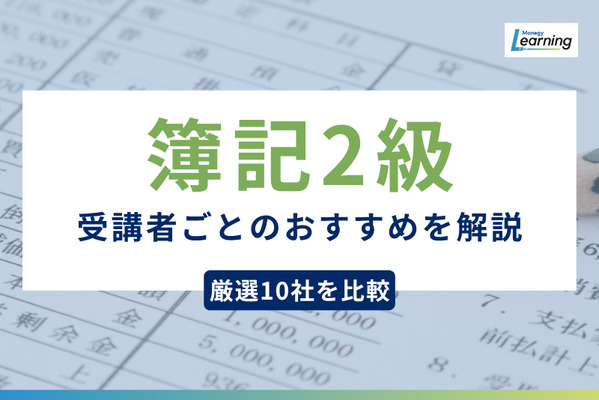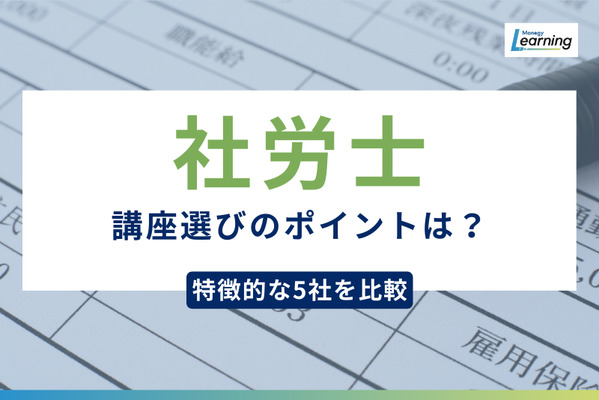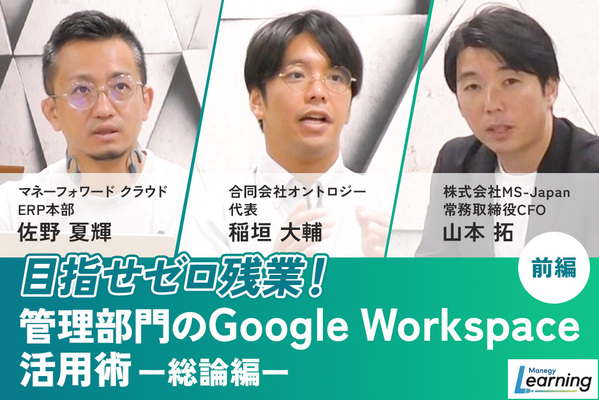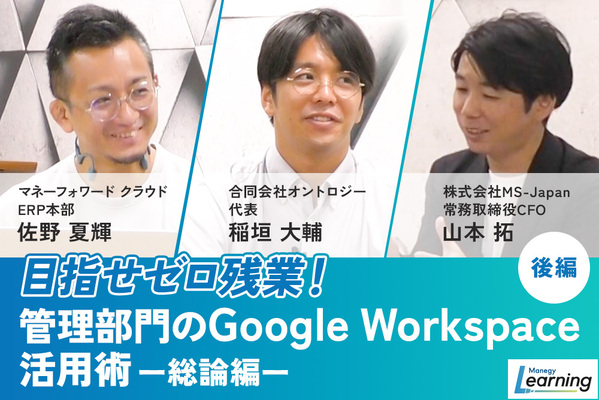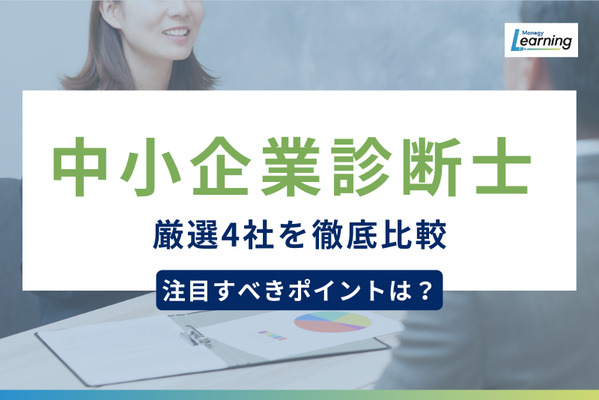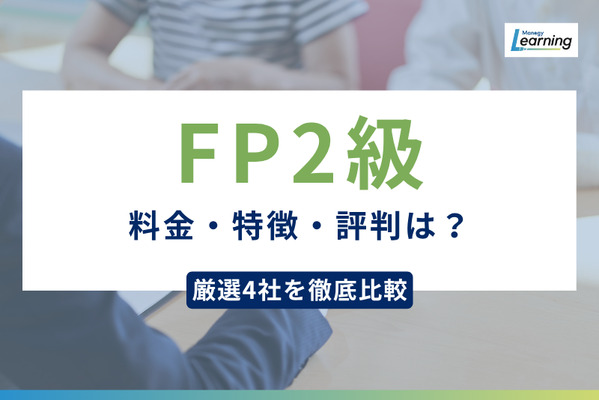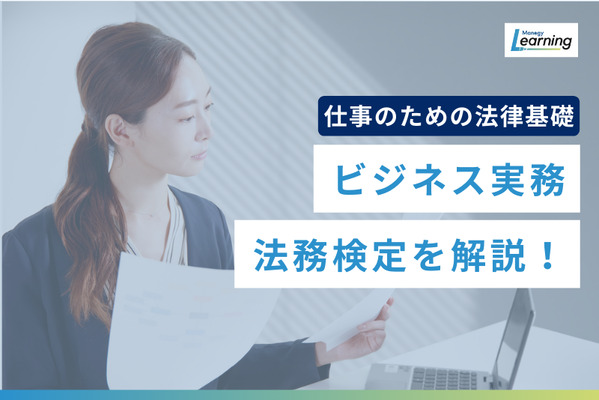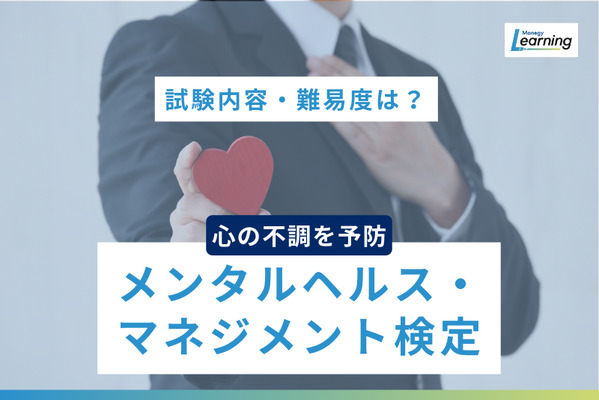【2025年版】宅建とは? 受験概要・難易度・勉強時間などをわかりやすく解説!

「不動産業界で活躍したい」「キャリアアップにつながる資格を取りたい」――そのような人に人気なのが、国家資格のひとつである「宅建(宅地建物取引士)」です。毎年20万人以上が受験するこの資格は、不動産業界はもちろん、金融や建設業界など幅広い分野で高く評価されています。
本記事では、宅建とはどのような資格なのか、合格までに必要な勉強時間や難易度、勉強法まで、初学者にもわかりやすく解説します。宅建の取得を検討している人はぜひ、参考にしてください。
宅建とは?
どんな資格?
宅地建物取引士(以下「宅建」)は、不動産の売買・賃貸などの取引を行う際に必要な知識を持ち、重要事項の説明や契約書の記名などを担う国家資格です。不動産会社には、事務所ごとに一定数の宅建士を設置する法的義務があるため、業界では必須の存在と言えます。
また、宅建は不動産業界だけでなく、金融機関や建設会社など、土地や建物に関連する業種全般で評価されることも少なくないです。日本国内に居住する人であれば学歴や年齢に関係なく誰でも受験できるため、学生や定年後の再就職希望者など、幅広い層の人々が例年挑戦しています。
宅建の資格を持っているメリットや独占業務は?
宅建の大きな特徴のひとつは、法律で定められた「独占業務」があることです。具体的には、以下の3つの業務が宅建の独占業務とされています。
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書(35条書面)への記名
- 契約内容を記した書面(37条書面)への記名
これらの業務は、宅建の資格を持っていなければ法律上行うことができません。特に「重要事項の説明」は、不動産取引において買主や借主が契約内容を正しく理解するうえで不可欠な手続きであり、非常に責任のある仕事です。
また、不動産の売買や賃貸借の仲介を行う会社は、事務所ごとに従業員5人に対して1人以上の宅建士を設置する義務があります。つまり、宅建士がいなければ不動産会社は営業ができないため、常に一定の需要がある資格と言えるのです。
宅建資格を取得することによるメリットは、独占業務に限らず、幅広い場面で活かされます。以下に代表的なメリットをあげましょう。
- 就職や転職に有利
特に、不動産業界や住宅業界、金融業界、建設業界などでの評価が高く、応募資格や採用条件に「宅建士有資格者優遇」と明記している企業も多数あります。 - 資格手当の支給
企業によっては宅建資格に対して手当を支給する制度があり、収入アップにつながります。 - 昇進・昇格に有利
管理職登用時の加点対象になることも多く、キャリアアップの一助になります。 - 法律知識の習得により実務対応力が向上
不動産取引に限らず、一般のビジネスシーンでも役立つ法的思考力が身に付きます。 - 他の資格の勉強にも有利
行政書士、マンション管理士、FPなどの関連資格の勉強において、宅建の科目と重複している箇所があるので、宅建の学習で得た知識が役立ちます
このように、宅建は不動産業界だけにとどまらず、他業界でも取得価値の高い資格であると言えるでしょう。宅建の学習で身につけた法律や不動産の知識は、行政書士やマンション管理士など他の資格試験の土台としても役立ち、今後のステップアップを目指す際にも役立つでしょう。
宅建の試験概要・出題範囲・難易度は?
試験概要
宅建試験は毎年1回、10月の第3日曜日に実施されます。試験は全国で行われます。2025年は10月19日(日)が試験日となります。また、受験資格に制限はないため、誰でも受けることができます。
- 試験形式:四肢択一式による筆記試験
- 問題数:50問(ただし、登録講習修了者[※]は45問)
- 試験時間:2時間(ただし、登録講習修了者は1時間50分)
- 合格基準:毎年変動(50問中おおむね35問の正解が必要)
※登録講習…宅地建物取引業法第16条第3項に基づいた講習で、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が実施。
主な出題範囲
出題範囲は大きく以下の4つに分けられます。
| 分野 | 問題数 | 内容 |
|---|---|---|
| 権利関係 | 14問 | 民法を中心とした法律(売買・賃貸借などの契約等 |
| 宅建業法 | 20問 | 宅建士としての業務や規制についての知識 |
| 法令上の制限 | 8問 | 都市計画法や建築基準法などの知識 |
| その他関連知識 | 8問 | 税制に関する問題など |
主な出題範囲
宅建試験の合格率は、例年13~18%程度になっています。出題範囲が広く、法律に不慣れな人にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。
毎年20万人以上という受験者の多さに対して合格者は限られており、基礎からしっかりと勉強を進めなければ合格が難しい試験です。この合格率が低い理由には、いくつかの要因があります。
1.出題範囲が非常に広い
宅建試験は前述のとおり、「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限」「その他関連知識」と、4つの幅広い分野から構成されています。それぞれに専門性があり、単なる暗記だけでは対応が難しいのが現実です。特に、民法や税制などは初めて勉強する人にとって理解しづらく、基礎から丁寧に学ばなければ点数に結びつきません。
2.専門用語が難解
宅建試験では法律や不動産関連の専門用語が多数登場します。これらを正確に理解したうえで問題を解けるレベルになるためには、相応の勉強時間が必要です。
4.ひっかけ問題が出題される
宅建試験は四肢択一式によるマークシート形式ですが、選択肢の文言が非常に紛らわしく、正確な知識を持っていないとうっかり誤答してしまうような問題が出題されます。そのため、単に知識を詰め込むだけではなく、問題演習を通じて出題パターンに慣れることが重要です。
宅建の合格率は20%を切っている理由には、このような背景が考えられます。ただし、しっかりと時間をかけて対策を立てれば、合格できる実力を十分に身に付けることが可能です。
宅建の合格にはどのくらい勉強時間が必要?
宅建の合格に必要とされる勉強時間は個人差があり、一般的に200~600時間程度と言われています。勉強時間の目安に幅があるのは、勉強方法や学習者の経歴によって変動が大きいためです。
目安としては、法律関連を初めて独学で取り組む場合は600時間以上、資格予備校に通うなら400時間程度、法学部出身者や不動産取引の知識を持っている人ならさらに短い勉強時間で合格を狙うことが可能でしょう。また、「○○時間勉強したら必ず受かる」というわけではないので、合格のためには、毎日の積み重ねで地道に勉強することが大切です。
宅建の勉強方法
独学
宅建対策テキストや問題集は豊富に揃っているため、宅建試験に独学で合格する人はいます。近年ではスマートフォンなどのアプリや無料の動画講義も充実しているので、独学でもしっかり対策をとれます。
一方で、専門用語を自力で理解する必要があり、勉強のスケジュール管理力も求められます。やるべきことを明確にし、計画的に勉強を進めることが必要です。
独学のメリット
- コストが安い
テキストや問題集などの購入代だけで済む場合もあります。前述のとおり、スマートフォンなどで無料アプリや動画を上手に利用するのもおすすめです。 - 自由に勉強できる
仕事や家庭と両立できれば、自分のペースで勉強できます。 - 自分に合った教材を選べる
市販教材の中からわかりやすいものを厳選できます。
独学のデメリット
- 疑問点をすぐに解決できない
理解しづらい部分が出てきたときに行き詰ってしまう可能性があります。 - 自己管理が必要
勉強を計画的に進められず、さぼったり挫折したりする可能性も。 - 情報のアップデートが自己責任
法改正など最新情報を自分で調べる必要があります。
講座受講
独学に不安がある人や、短期間で確実に合格したいと考えている人には、宅建講座の受講がおすすめです。講座には「通信型」「通学型」「オンライン型」などさまざまな形式があり、自分のライフスタイルに合った方法で勉強を進められます。
例えば、法改正に対応した最新の教材を使用し、講師によるわかりやすい解説が受けられるほか、質問対応や模試、進捗管理などのサポートも充実しています。費用はかかるものの、効率的に勉強を進めるための投資と考える価値は十分にあるでしょう。
講座受講のメリット
- 体系的に勉強できる
試験範囲を無駄なく網羅できます。 - プロ講師によるわかりやすい解説
専門用語も理解しやすいです。 - 質問サポートや模試などのフォローが充実
一人では対応しきれない部分も補えます。 - 法改正への即時対応
教材や講義が最新の内容に基づいて構成されています。
講座受講のデメリット
- 費用がやや高め
受講費用として数万円単位のでかかるのが一般的です。 - スケジュールが固定されやすい
特に、通学型は時間と場所の制約があります。 - 教材や授業が合わないことも
自分に合った教材や授業でない場合は、ストレスを感じるかもしれません。
まとめ
宅建は、就職や転職、キャリアアップに直結する国家資格として、非常に価値の高い資格です。合格率は13~18%程度と決して簡単ではありませんが、正しい方法で勉強を進めれば、独学でも合格可能です。一方で、専門用語に抵抗感があったり、勉強を計画的に進める自信がなかったりする場合は、講座受講を検討するのもよいでしょう。
いずれの方法を選ぶにしても、「毎日の積み重ね」と「正しい情報」を意識して勉強に取り組み、目標達成を目指すことで、合格への道につながります。宅建に興味がある人はぜひ、第一歩を踏み出してみませんか?

Manegy Learning
Manegy Learningは管理部門・士業の皆さまに向けて、実務に役立つTIPSや資格取得のためのスクール取得などの情報を発信し、みなさまの学びをサポートします。
MS-Japan
https://www.manegy.com/learning/