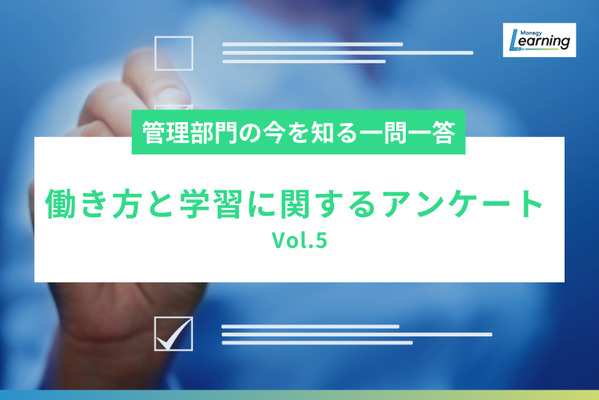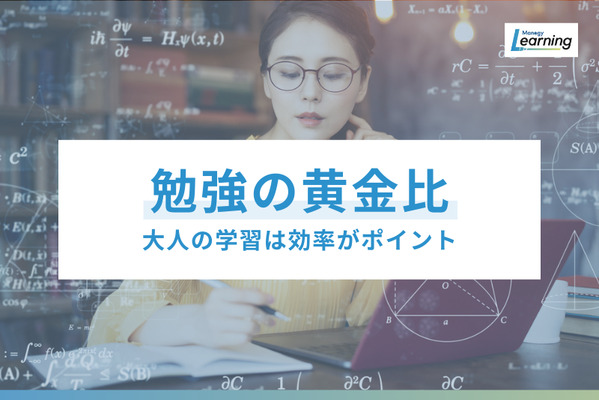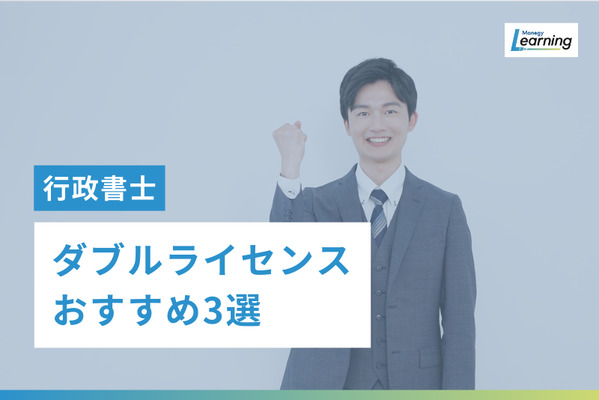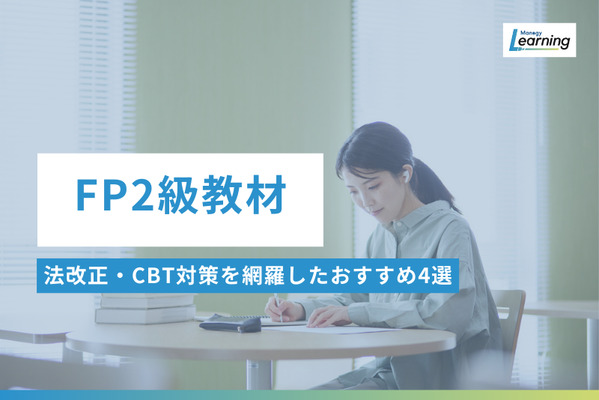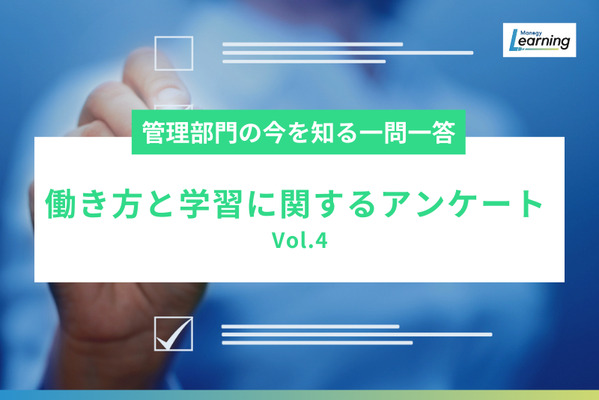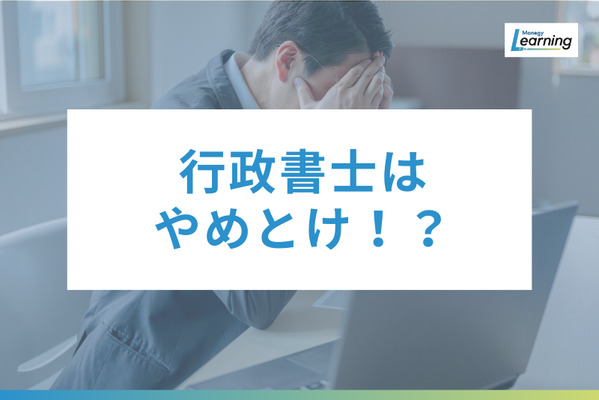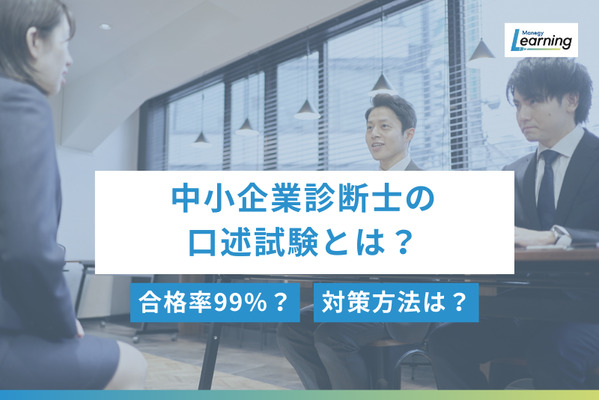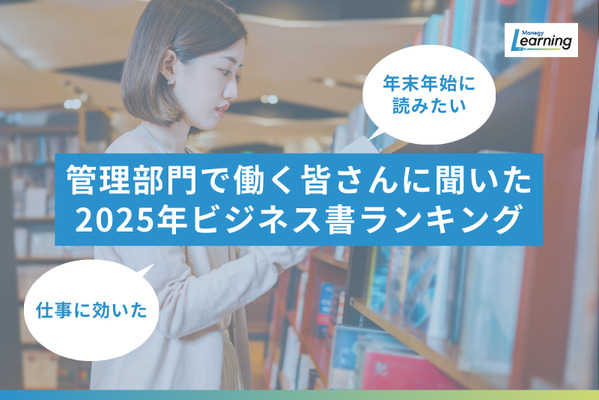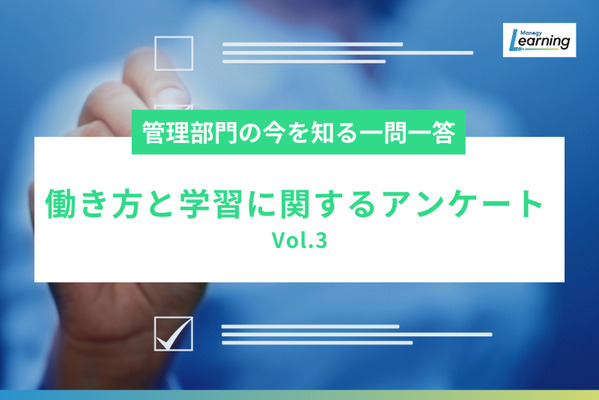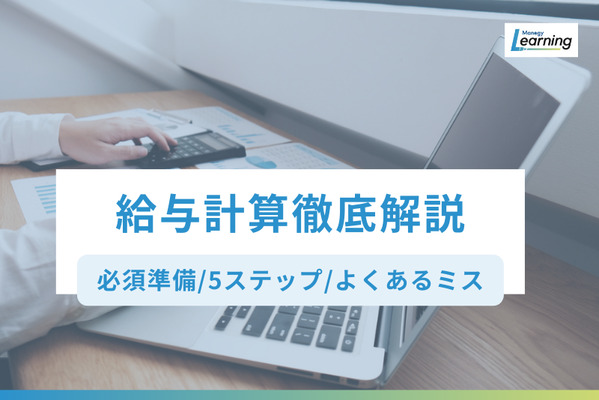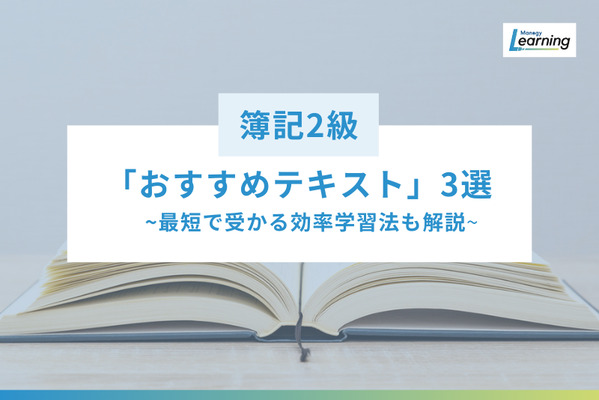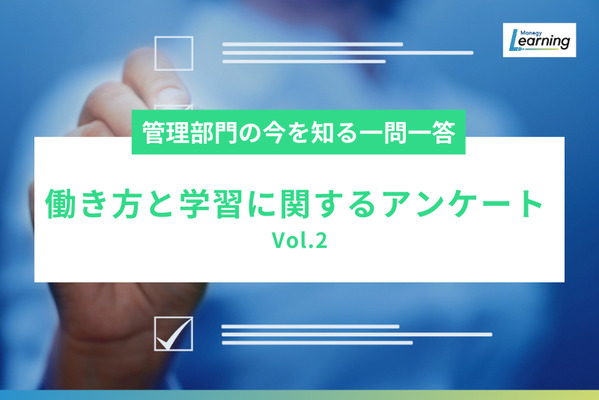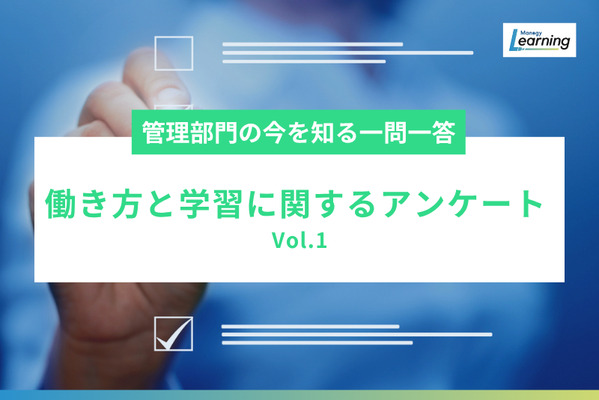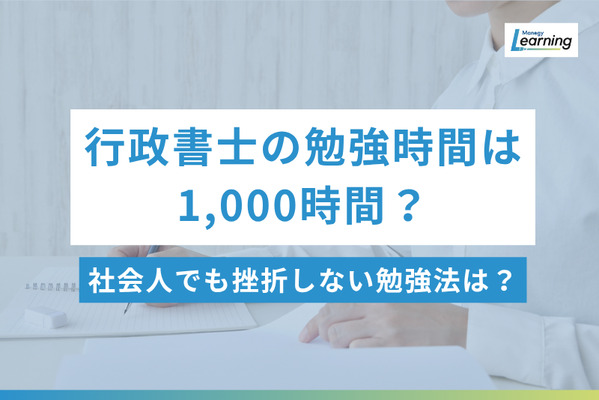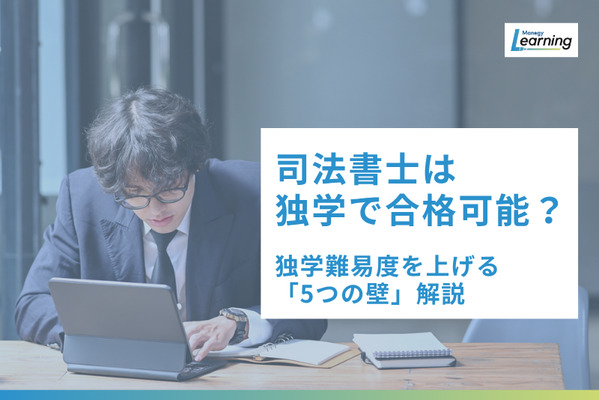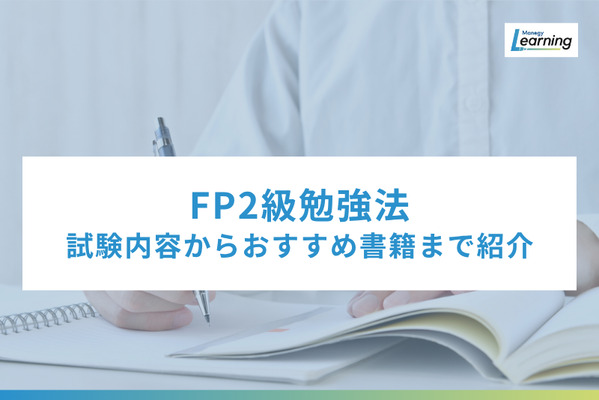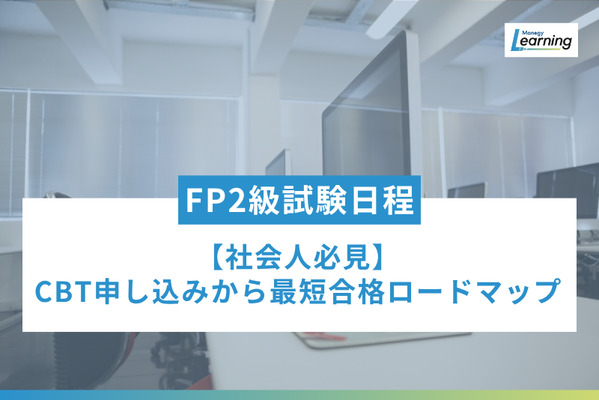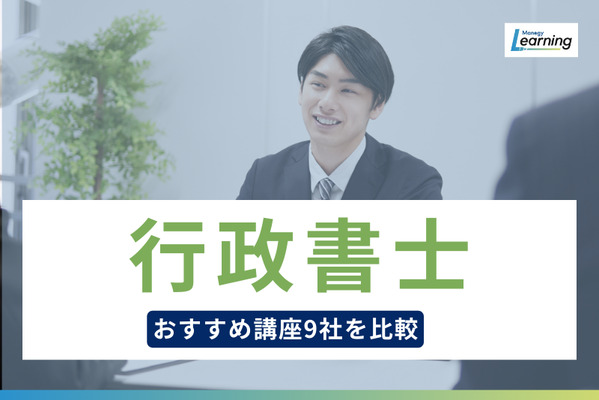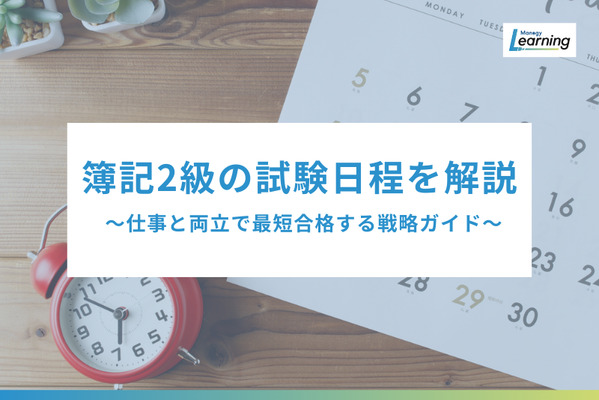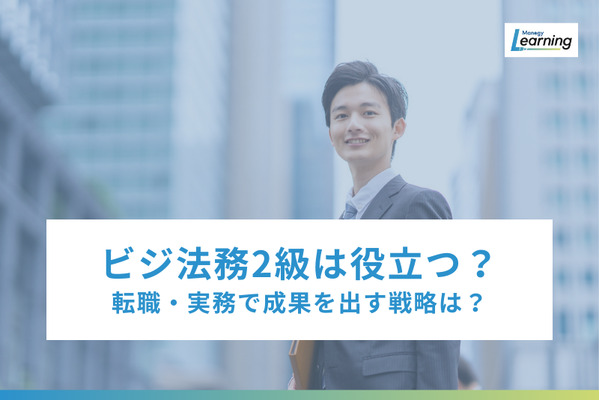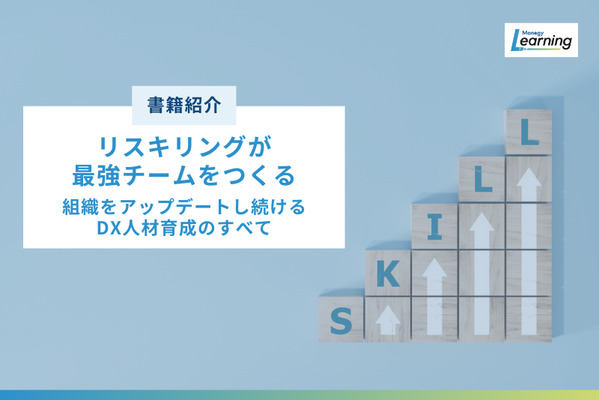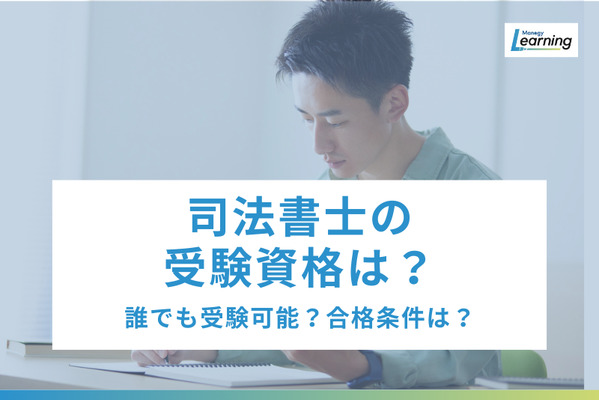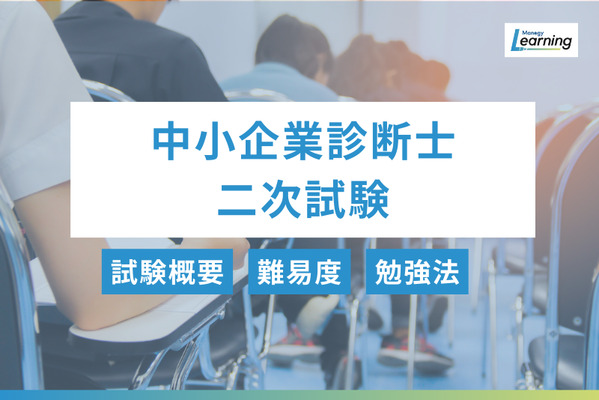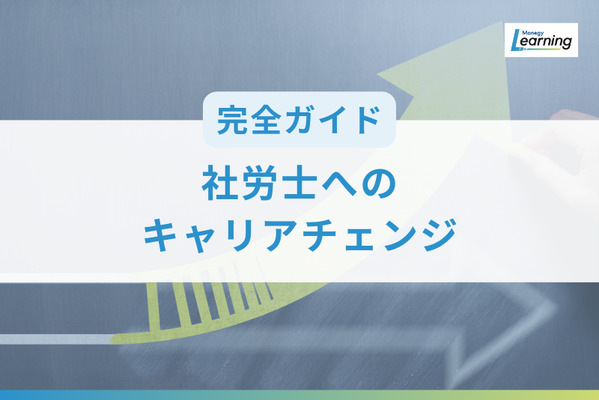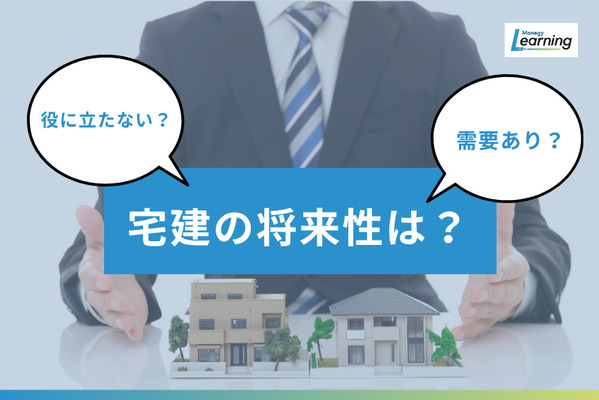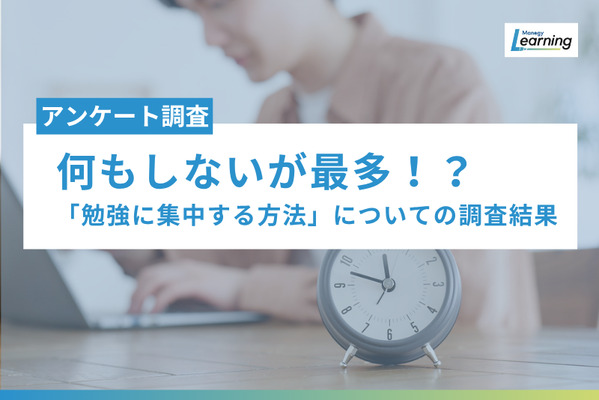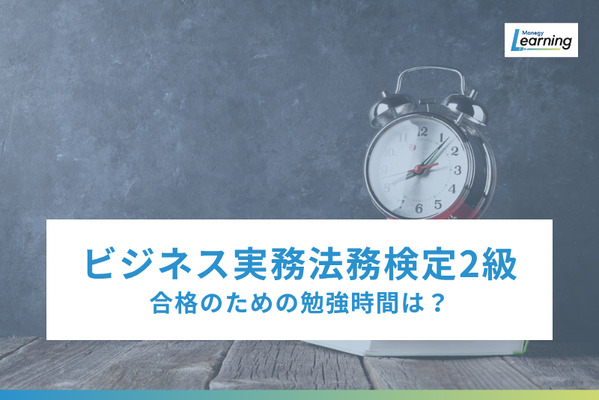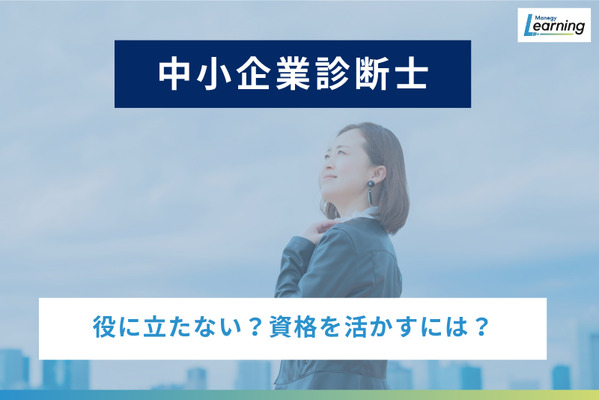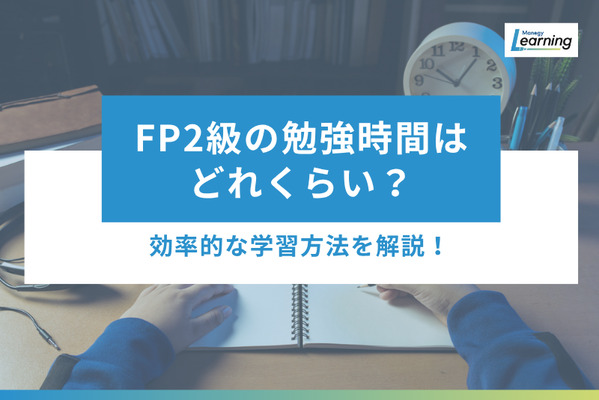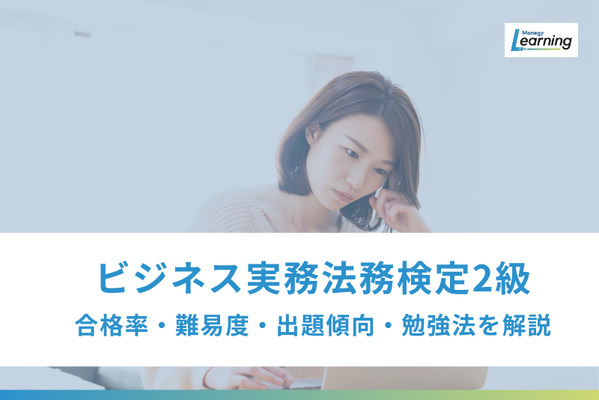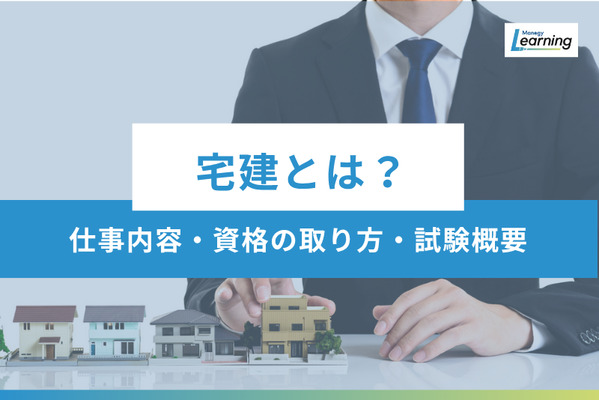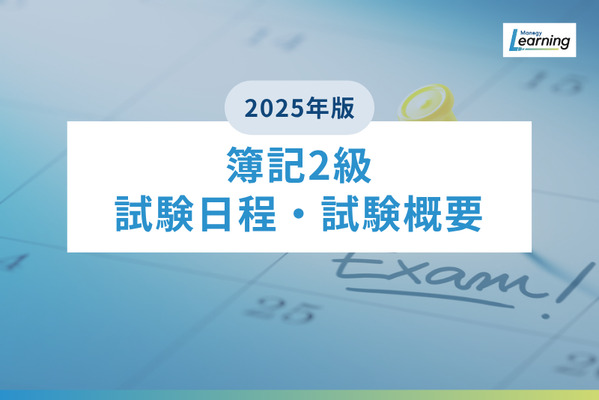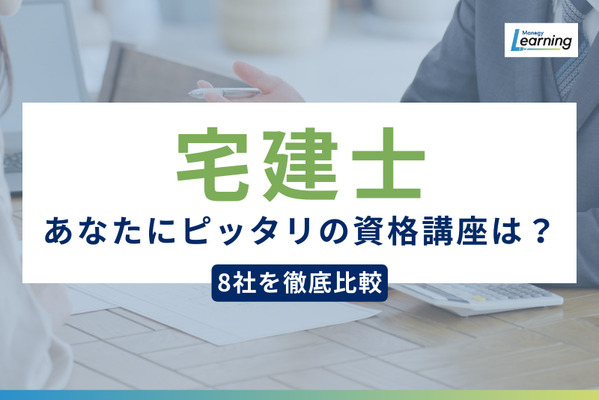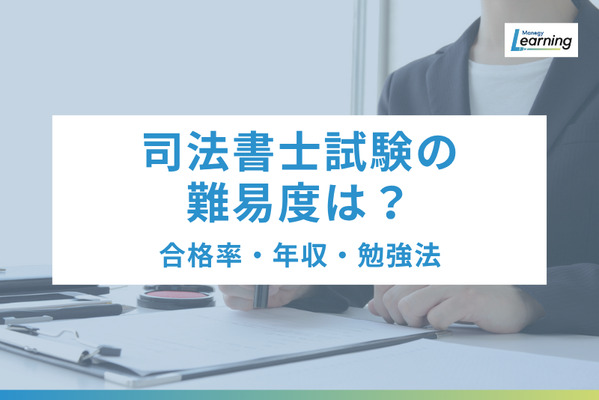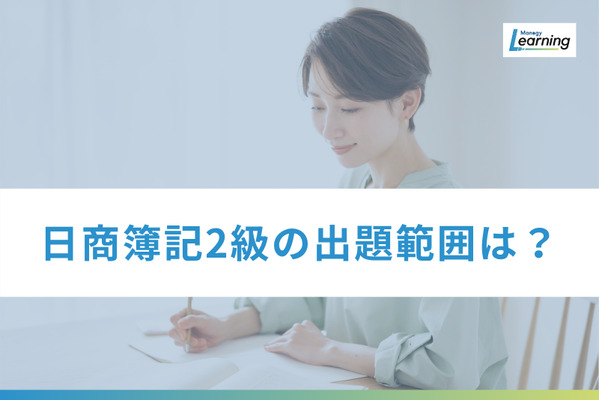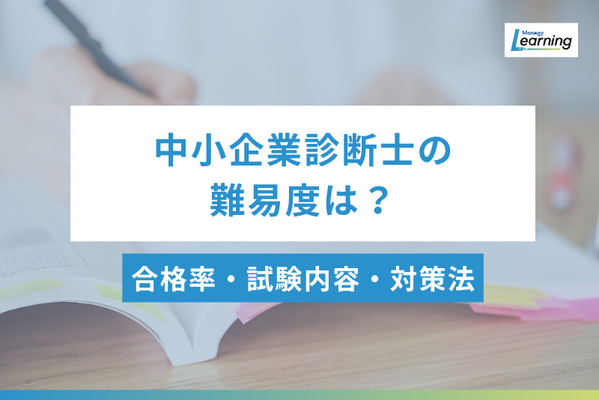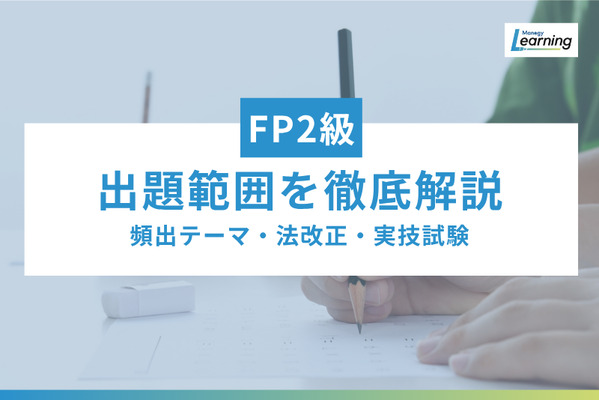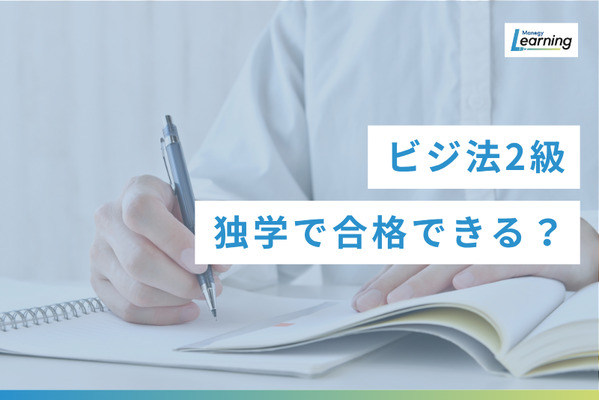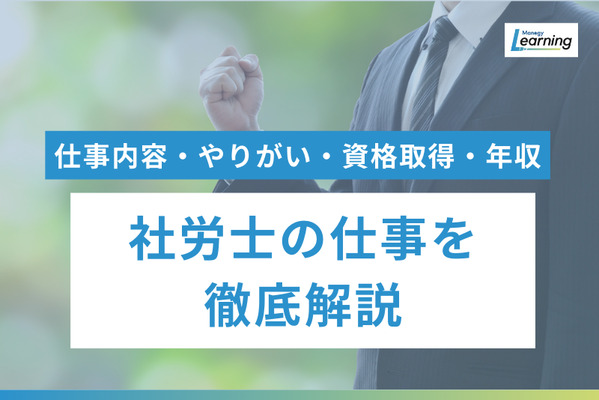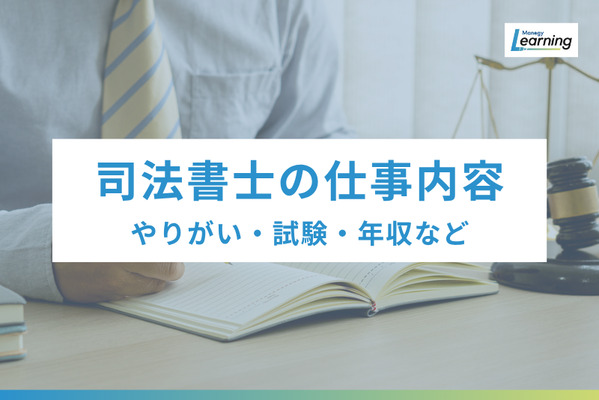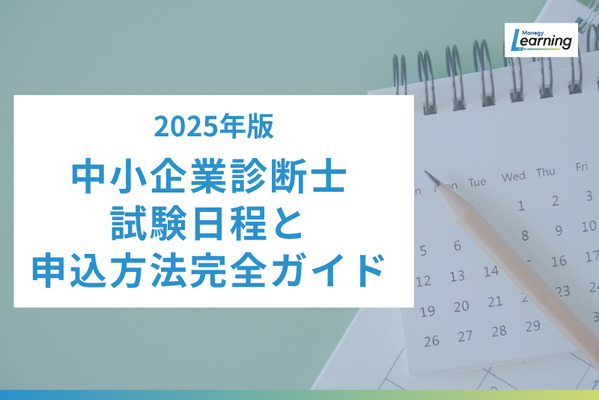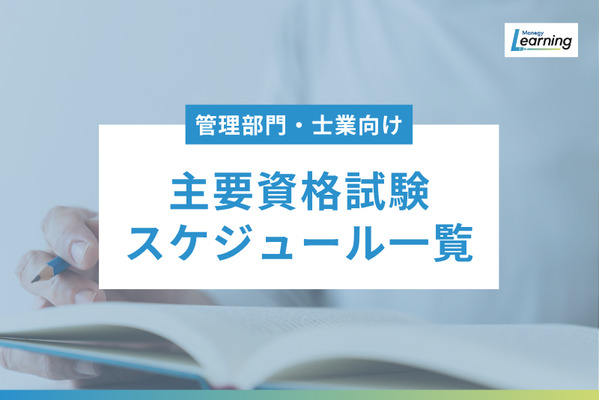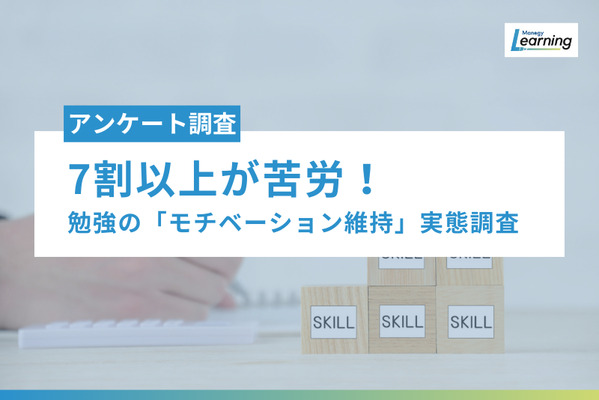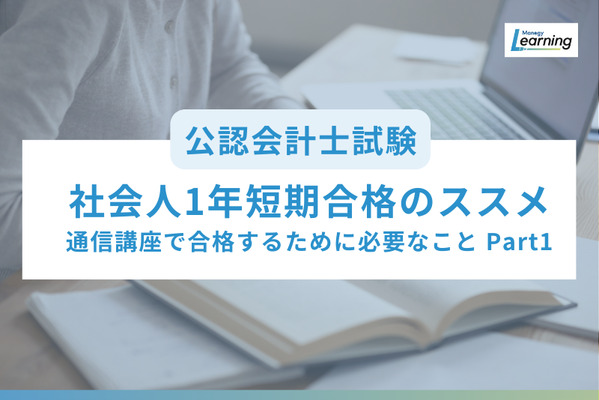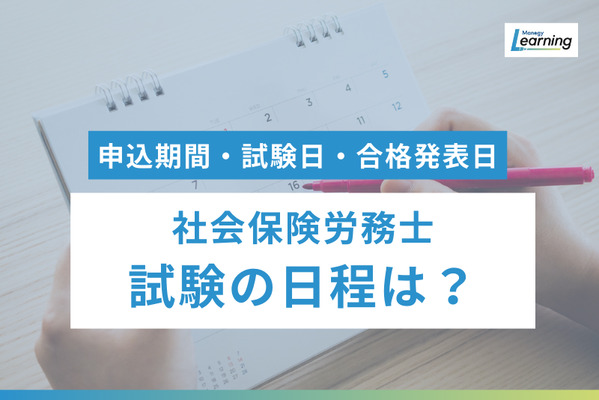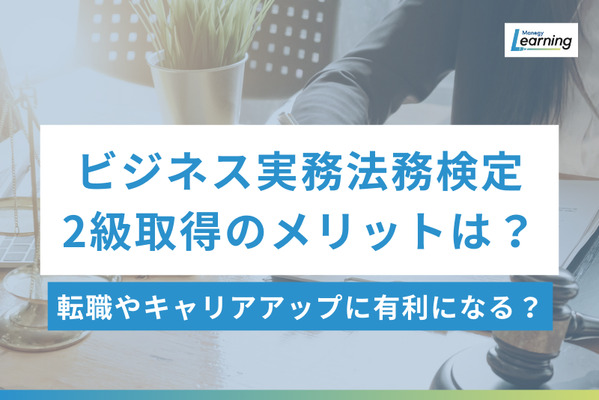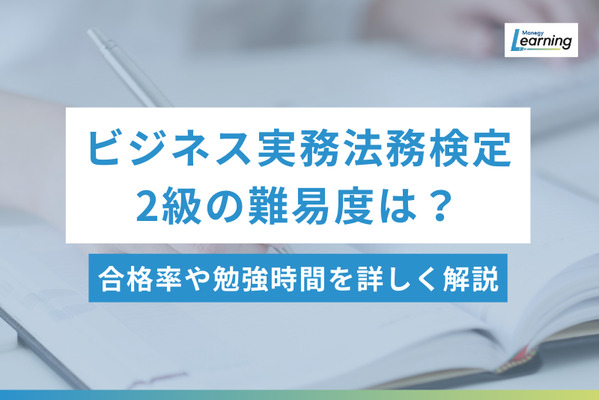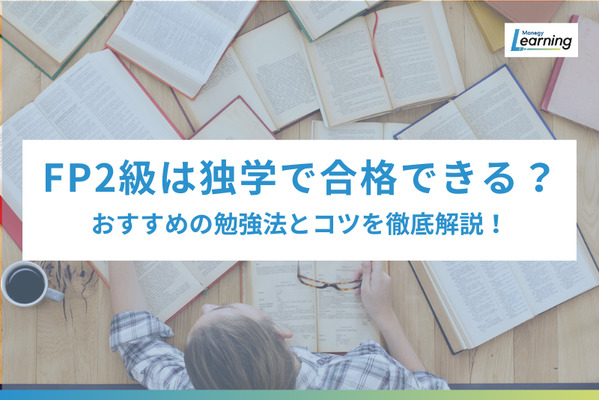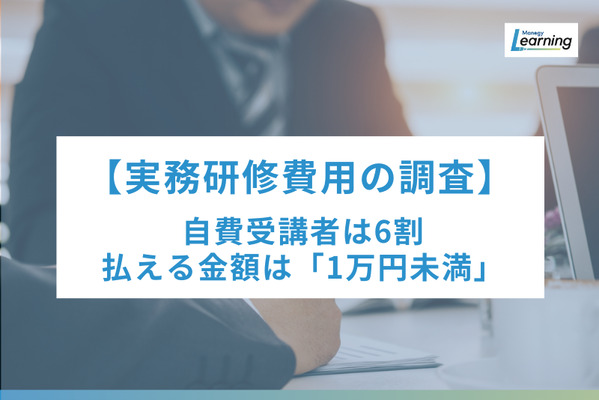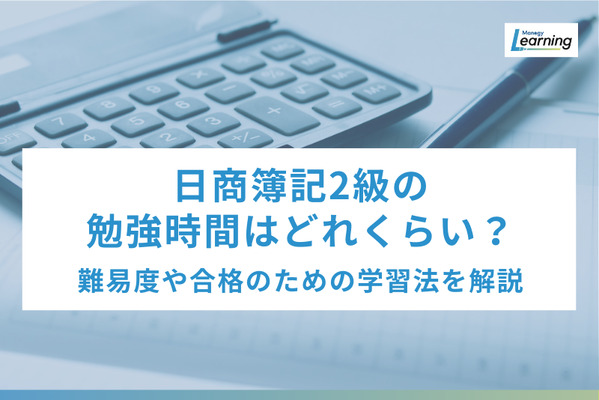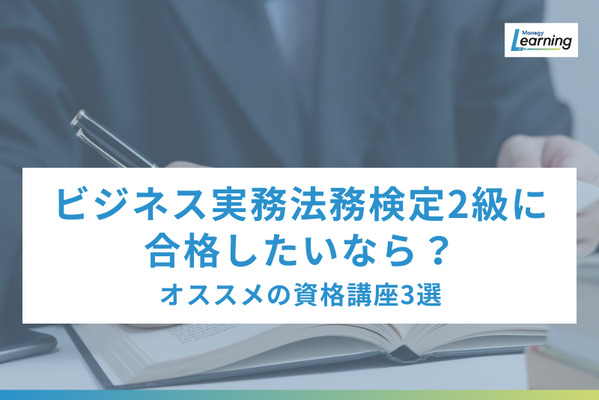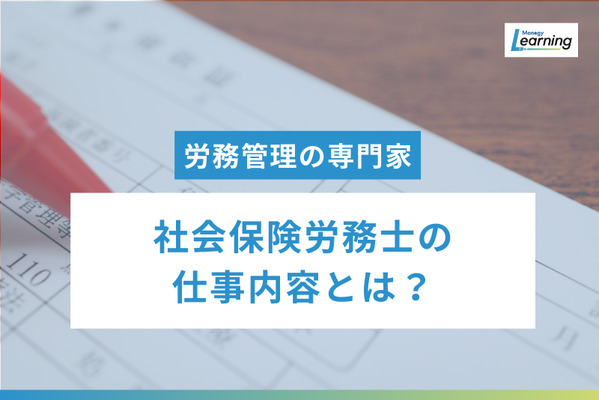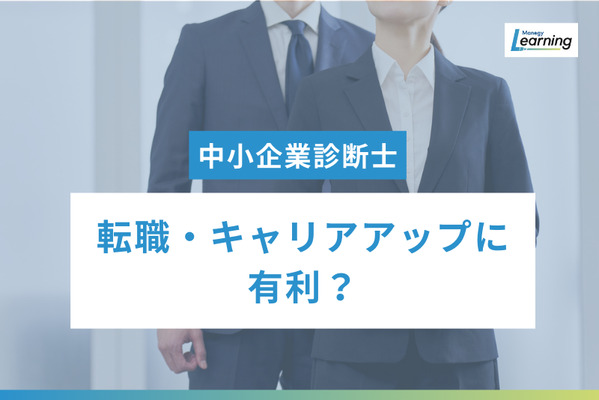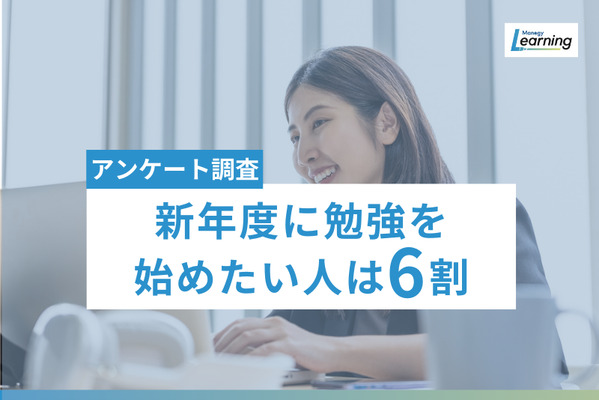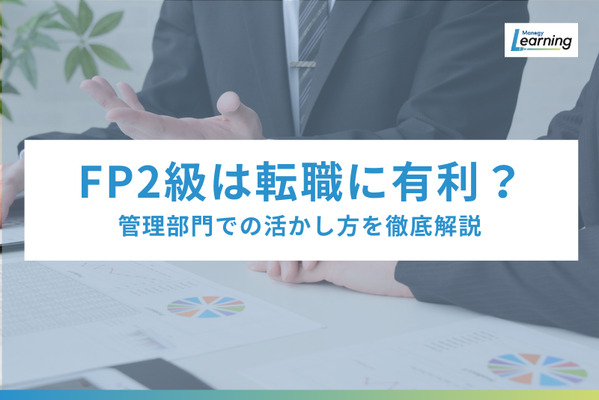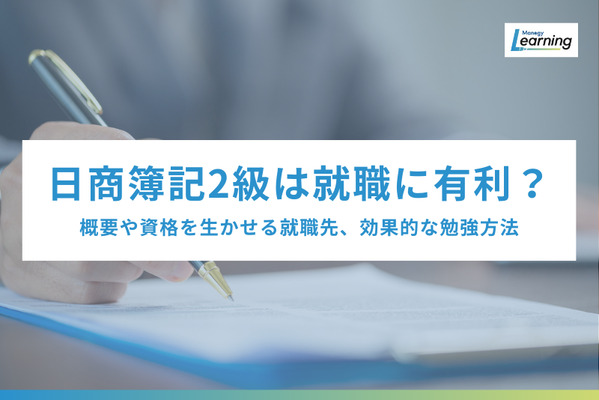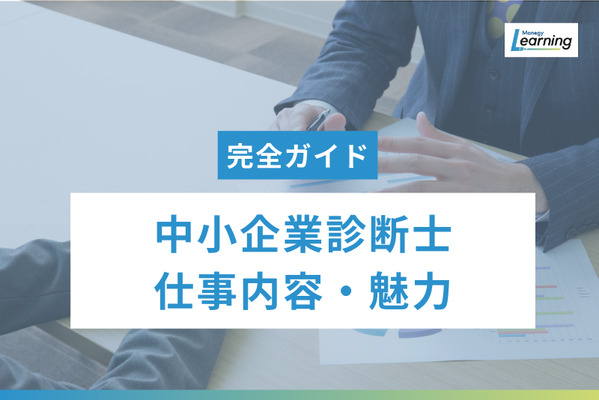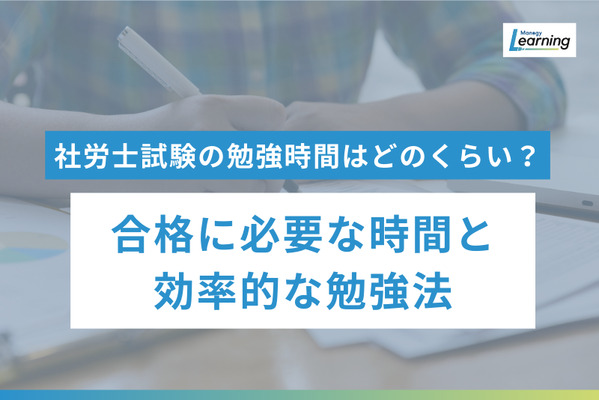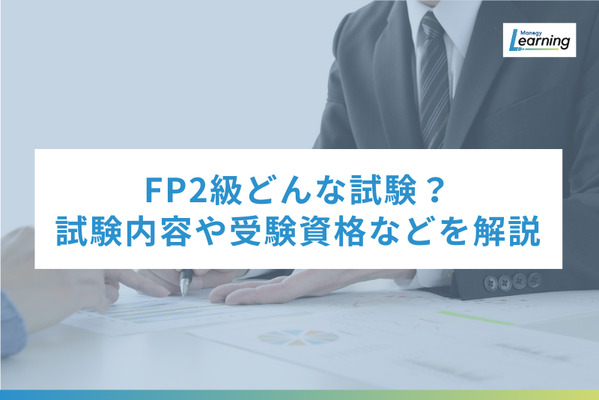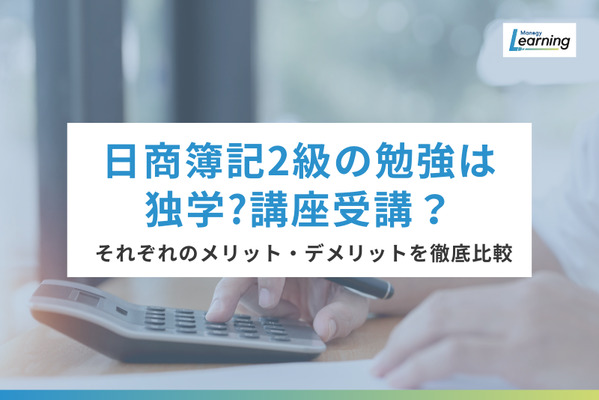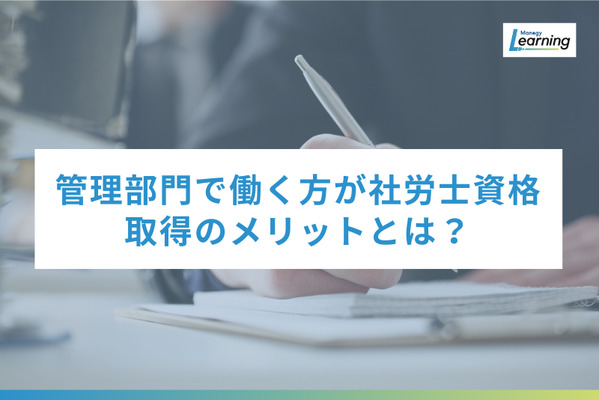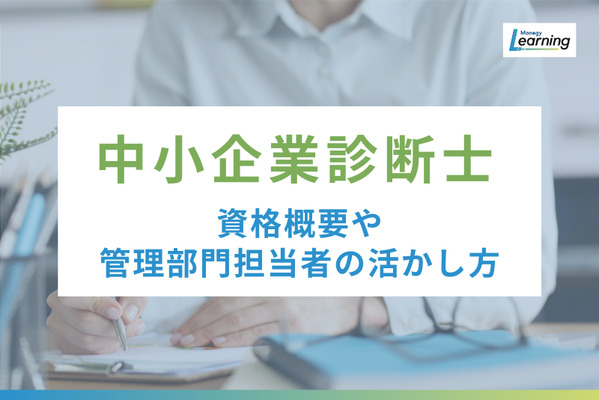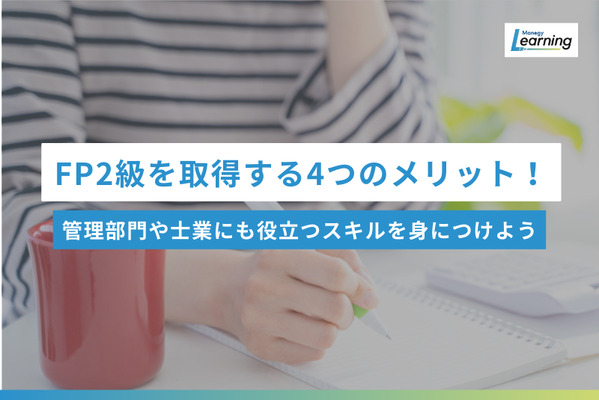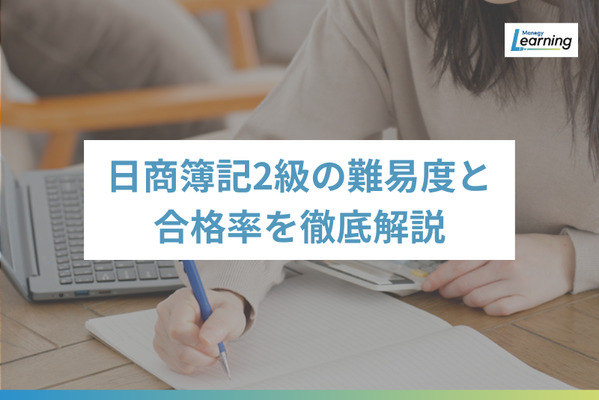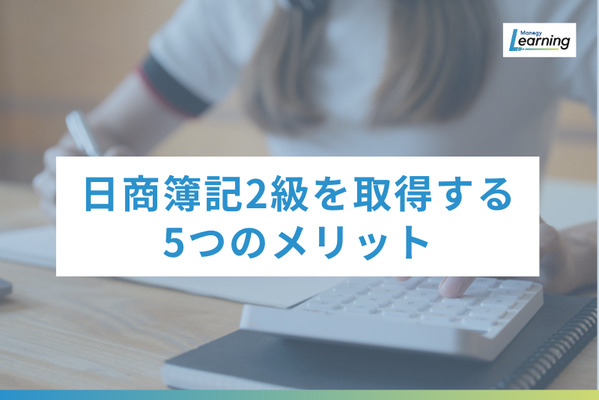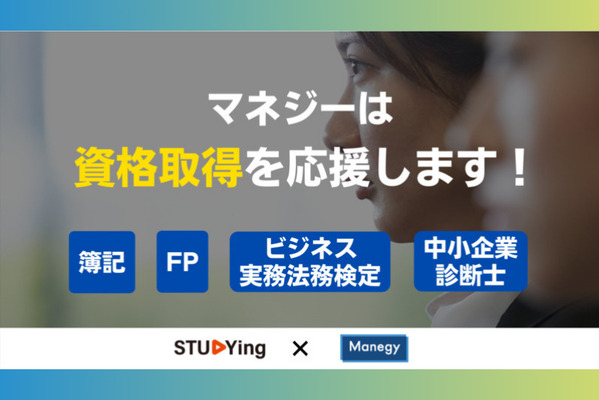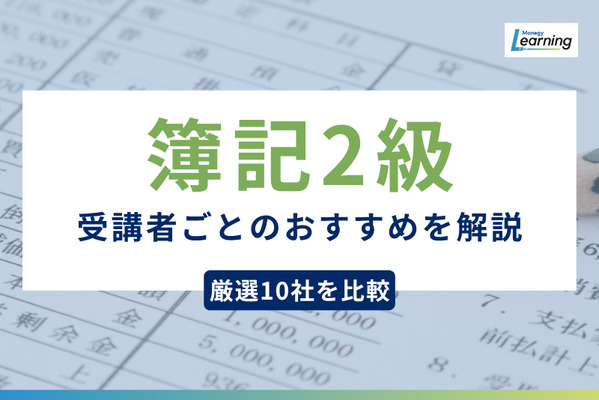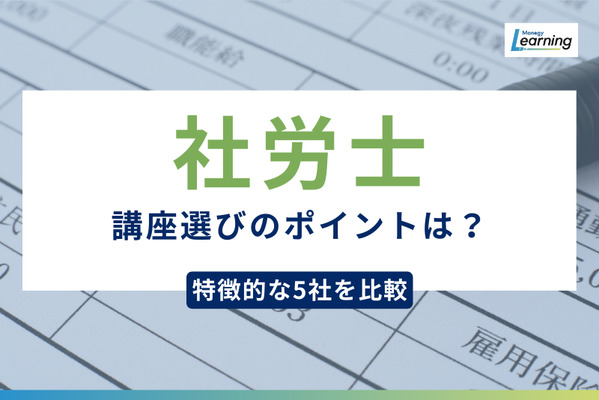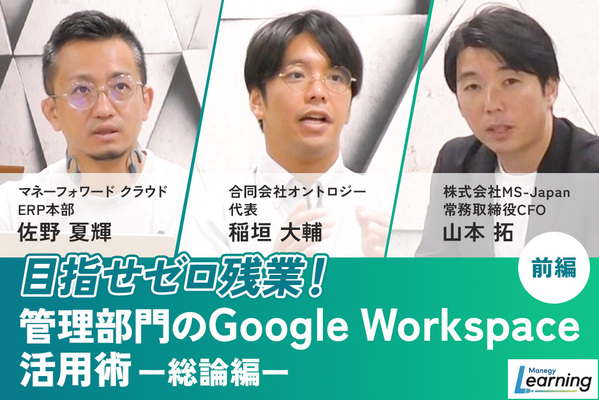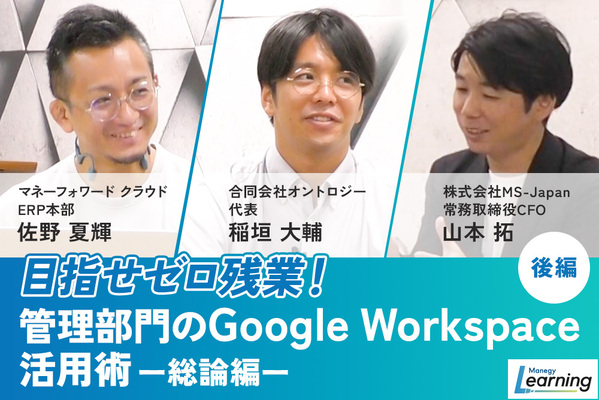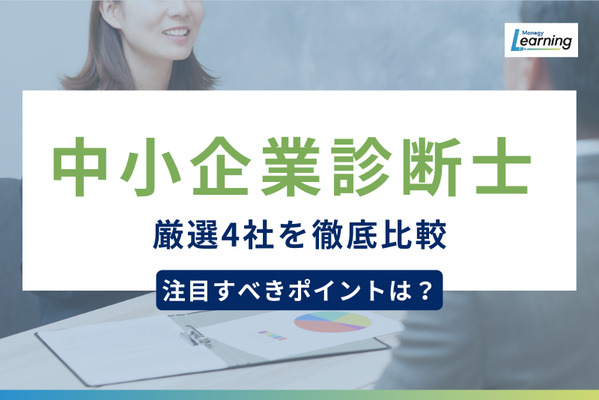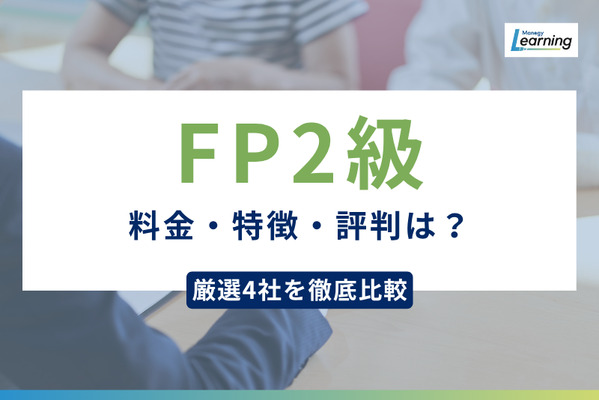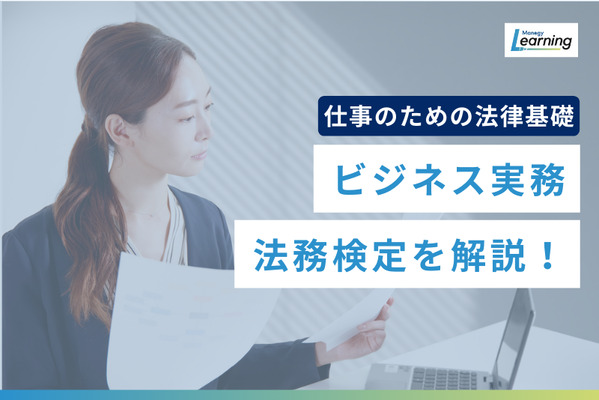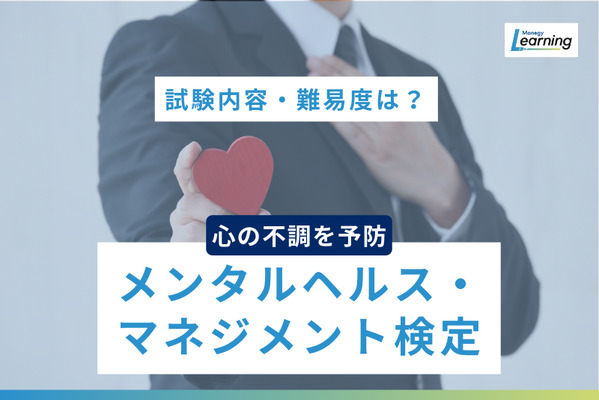2025年度 宅建の試験日程はいつ?申し込み期間や合格発表など解説【最新情報】
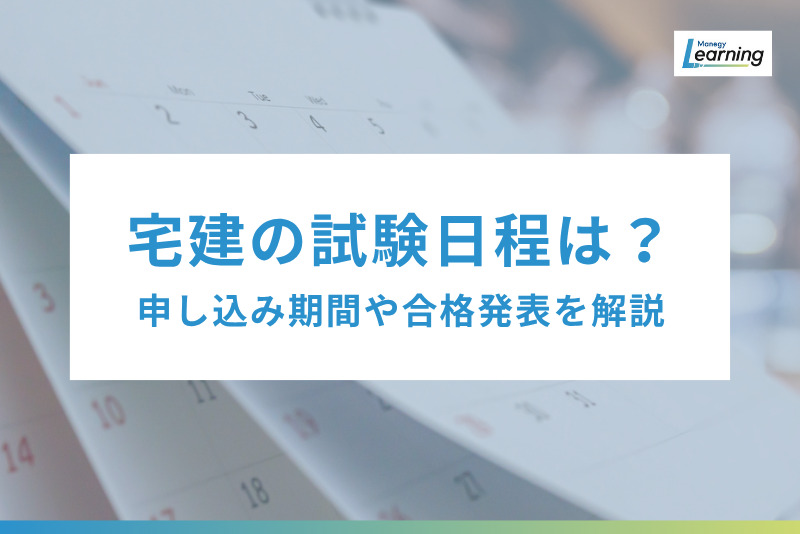
不動産業界で活躍する「宅地建物取引士(以下「宅建」)は、例年多くの人が受験する人気の国家資格です。合格するためには、計画的な勉強だけでなく、試験日程や申し込み期間などのスケジュールを早めにしっかり把握し、余裕をもって行動することが重要です。
本記事では、今年度(2025年度)の宅建の試験日程について、最新情報をもとに詳しく解説します。併せて、申し込み方法や試験の合格基準、合格発表後の流れなどについてもご紹介しますので、受験を検討している人はぜひ参考にしてください。
この記事を読んだ方にオススメ!
宅建の試験日程と時間など
試験日時や受験資格、試験形式などについて
宅建は毎年1回のみ実施される国家試験で、全国で同じ日に一斉に行われます。以下、今年度の試験の概要です。
- 試験日時:2025年10月19日(日)13時~15時(登録講習修了者は13時10分~15時)
- 受験資格:特になし
- 試験形式:四肢択一式(マークシート)による筆記試験
- 問題数:50問(ただし、登録講習修了者[※]は45問)
- 試験時間:2時間(ただし、登録講習修了者は1時間50分)
- 合格基準点:毎年変動
- 合格率の推移:例年13~18%程度
※登録講習…宅地建物取引業法第16条第3項に基づいた講習で、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が実施。
例年の試験日程について
宅建試験は、毎年「10月の第3日曜日」に行われるのが通例です。このように日程はある程度決まっているため、早い段階から勉強のスケジュールを立てることができます。 注意すべきは、宅建の試験は年に1回しか実施されない点です。受験の申し込み期限に間に合わなかった場合、次に受験できるのは翌年以降となり、資格取得が遅れます。そのため、勉強のスケジュール管理と併せて、試験日程を早めにきちんと把握しておくことが大切です。
宅建試験の申し込みはいつ?どうやって申し込む?
宅建試験の申し込み期間
宅建試験の申し込みは毎年7月に開始され、申し込み方法はインターネットと郵送の2つから選べます。以下は、今年度のそれぞれの申し込み期間です。
インターネットでの申し込み期間
2025年7月1日(火)9時30分~7月31日(木)23時59分
※インターネットでの申し込みは原則として24時間可能です
郵送の試験案内配布期間および申し込み期間
試験案内配布期間:2025年7月1日(火)~7月15日(火)
申し込み受付期間:2025年7月1日(火)~7月15日(火)※消印有効
上記のとおり、インターネットの申し込み期間は1か月間と比較的時間に余裕がありますが、郵送での申し込み期間は2週間程度しかありません。そのため、郵送で申し込む予定の人は、提出書類などを早めに準備しましょう。
郵送による申し込みの場合、試験案内(郵送申込書)が無料で配布されています。試験案内の配布場所はこちらからご確認ください(一般財団法人 不動産適正取引推進機構の公式サイトにつながります)。試験案内は、申し込もうとする試験地専用のものを入手してください。申込書のコピーや他の試験地の申込書を使って申し込むことはできず、申し込みに必要な封筒も付属のものに限ります。
宅建試験の申し込み方法(インターネット・郵送)
以下は、インターネットおよび郵送それぞれの申し込み方法です。
インターネット申し込みの場合
公式サイトよりマイページを作成したうえで、必要事項を入力します。証明写真の画像データをアップロードし、受験手数料はクレジットカードまたはコンビニ決済、もしくはペイジーで支払います。
【注意点】
申し込みの締め切り直前は、公式サイトへのアクセスが集中してサーバーがつながりにくくなることがあります。申し込み手続きの途中で、通信エラーにより作業が中断されてしまう可能性があるため、できるだけ締め切り日より早めに申し込みを済ませると安心です。また、写真データのサイズや形式にも注意し、事前に準備しておきましょう。
郵送申し込みの場合
指定の郵送申込書に必要事項を記入し、証明写真を貼付して、簡易書留で送付します。
【注意点】
申し込みは受付期限日の消印有効ですが、郵便局の受付時間に注意したうえで発送を済ませましょう。申し込み期限当日の投函はリスクが高いため、可能な限り早めの発送をおすすめします。また、証明写真の裏には氏名を記入し、申込書の記入漏れや記載ミスがないかを確認してください。
宅建試験の申し込みに必要なものと受験手数料
必要なもの一覧
必要なものは、申し込み方法(インターネット/郵送)によって異なります。以下、ご確認ください。
宅建士になる方法
証明写真
無背景、正面向きで上半身を撮影。帽子やヘアバンド、リボン、サングラス、マスクなどの着用は禁止。
郵送申し込みの場合は、写真サイズが縦4.5cm、横3.5cm(パスポート申請時と同様のサイズ)、頭頂からあごまでが長さ3.2cm以上3.6cm以下のもの。
インターネット申し込みの場合は、写真データがJPEGファイル。サイズは、縦832ピクセル×横640ピクセル。
受験申込書(郵送申し込みの場合のみ)
必要事項を記入。
受験手数料の振込証明書(郵送申し込みの場合のみ)
メールアドレス(インターネット申し込みの場合のみ)
受験手数料
金額:8,200円
支払い方法は申し込み方法に応じて異なります。
インターネット申し込みの場合
受験申し込み時に、クレジットカードによる払い込み、コンビニエンスストアでの払い込み、またはペイジー払いのいずれかを選択したうえで支払います。
郵送申し込みの場合
茨城県以外の都道府県はペイジー、茨城県はコンビニ決済により、払い込み。指定された方法以外で振り込んだ場合は、受験申し込みが受付されないので注意が必要です。
宅建試験の概要
宅建試験の出題形式と試験時間について
宅建試験は全50問で、四肢択一のマークシート方式で実施されます。試験は13時~15時の2時間です。ただし、登録講習を修了している受験者は13時10分~15時の1時間50分で受験し、問題数は45問となります。
宅建試験の出題分野と配点の内訳
宅建試験では、不動産取引に関連するさまざまな法律や制度について出題されます。点数は1問につき1点、合計で50点満点です。以下は出題分野と、それぞれの問題数・配点および内容です。
| 出題分野 | 問題数 | 配点 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 宅建業法 | 20問 | 20点 | 宅建士としての業務や規制についての知識 |
| 権利関係(民法等) | 14問 | 14点 | 民法を中心とした法律(売買・賃貸借などの契約等) |
| 法令上の制限 | 8問 | 8点 | 都市計画法や建築基準法などの知識 |
| 税・その他関連知識 | 8問 | 8点 | 税制に関する問題など |
宅建の試験内容について、詳細が気になる方はこちらの記事がおすすめ
この記事を読んだ方にオススメ!
宅建試験の合格基準は?何点取れば受かる?
宅建試験の合格点(目安)と合格率について
不動産適正取引推進機構が発表した2024年度宅建試験の合格判定基準は、50問中37問以上正解でした(登録講習修了者は45問中32問以上正解)。
過去5回分の合格点を見ると、34~37点の間で推移しています。そのため、難易度の高い年度でも37~38点を取っていれば合格、と推測できます。逆に35点前後では、年によっては不合格になる可能性もあるため、最低目標は36点、理想は38点以上を意識するとよいでしょう。
また、宅建試験の合格率は、例年13~18%程度となっています。毎年20万人以上という受験者の多さに対して合格者が非常に限られており、「難関資格」と言えます。出題範囲が広く、特に法律関連の初学者にはハードルを高く感じやすい試験です。
過去5回の合格点と合格率の推移
過去5回の試験における合格点と合格率の推移は、以下のとおりです。
| 年度 | 合格点 | 合格率 |
|---|---|---|
| 2021年10月 | 34点 | 17.9% |
| 2021年12月 | 34点 | 15.6% |
| 2022年 | 36点 | 17.0% |
| 2023年 | 36点 | 17.2% |
| 2024年 | 37点 | 18.6% |
資格講座を受講して宅建合格を目指す人にはこちらの記事がおすすめ
この記事を読んだ方にオススメ!
宅建試験の合格発表と合格後の流れ
宅建試験に合格しても、すぐに「宅建士」として名乗ることはできません。宅建士として従事する場合、合格後は受験した都道府県で資格登録を行い、その後「宅建士証(取引士証)」の交付を受ける必要があります。
なお、資格登録にあたっては実務経験もしくは登録実務講習の受講が不可欠です。例えば東京都の場合、過去10年以内に宅地建物取引業についての実務経験を2年以上求めており、経験がない場合は資格登録前に宅建士登録実務講習を受けなければなりません。実務経験については都道府県によって異なるため、確認しておきましょう。
まとめ
この記事では、宅建の試験日程や申し込み期間と方法、合格発表などについて解説しました。
宅建試験は年に1回のみ実施される国家資格であり、試験日程や申し込み方法などの把握と管理が非常に大切です。2025年度の試験は10月19日(日)に予定されており、申し込み期間や提出物、試験内容、合格発表後の流れまで、資格試験関連を早めに理解しておくことが合格への第一歩となります。スケジュール管理と勉強計画を両立させ、着実に準備を進めましょう。

Manegy Learning
Manegy Learningは管理部門・士業の皆さまに向けて、実務に役立つTIPSや資格取得のためのスクール取得などの情報を発信し、みなさまの学びをサポートします。
MS-Japan
https://www.manegy.com/learning/