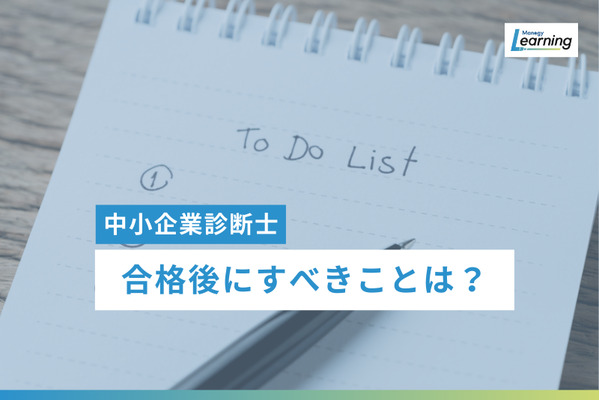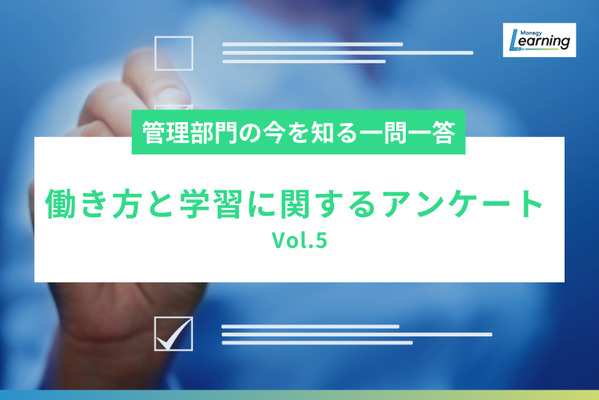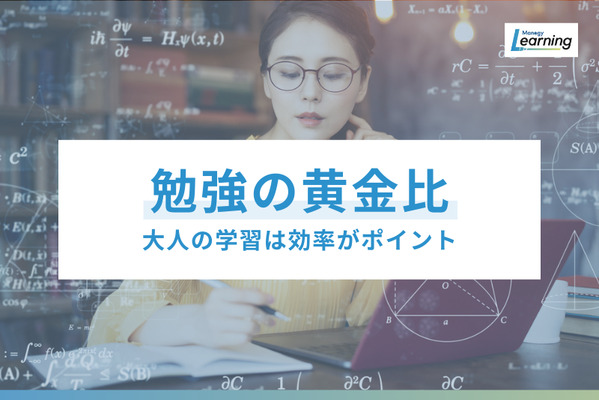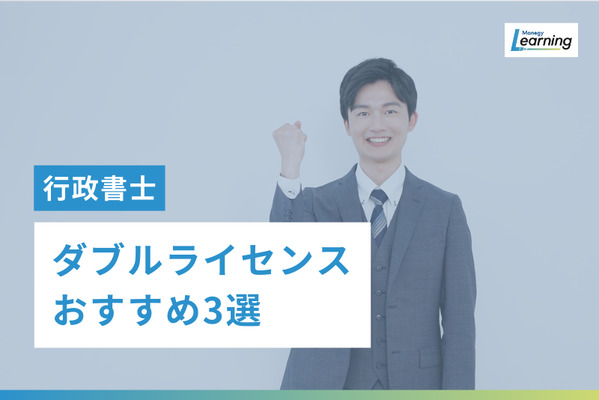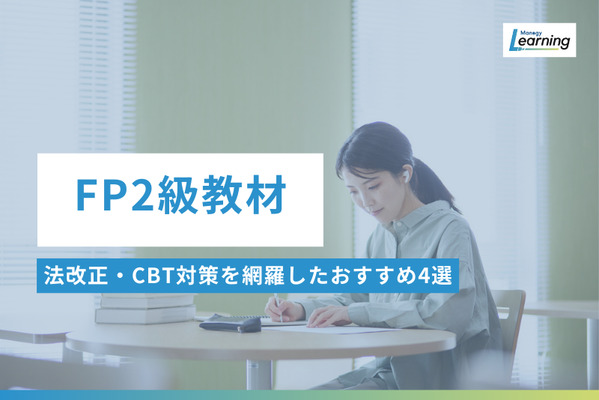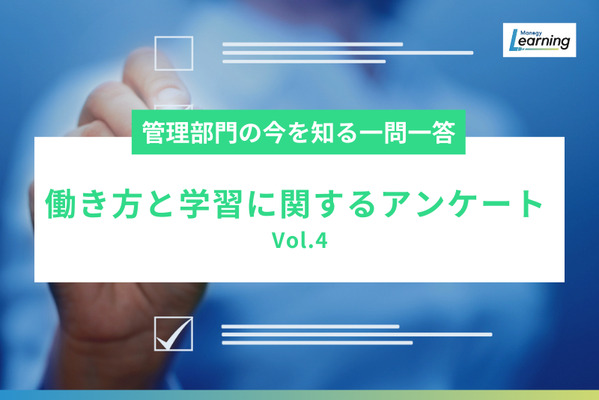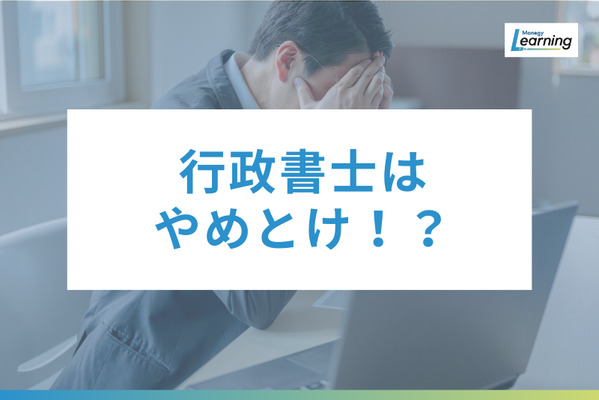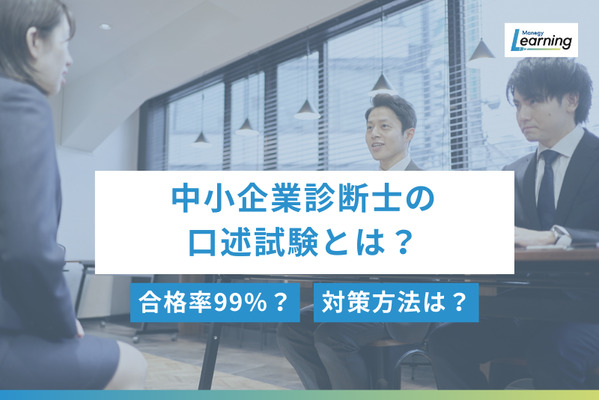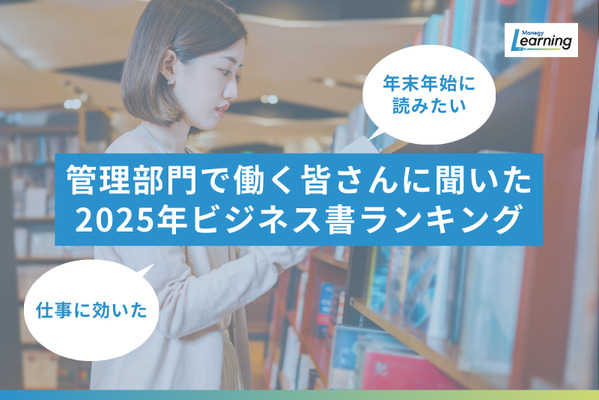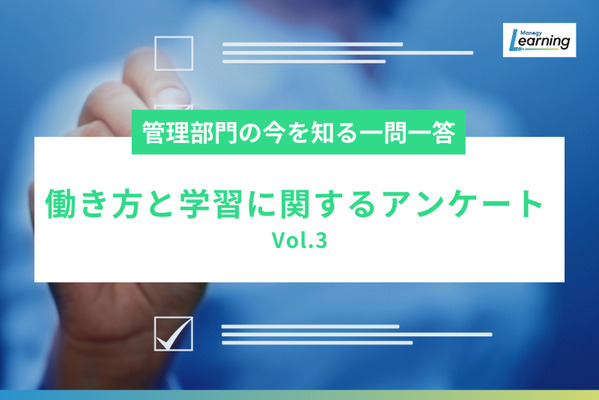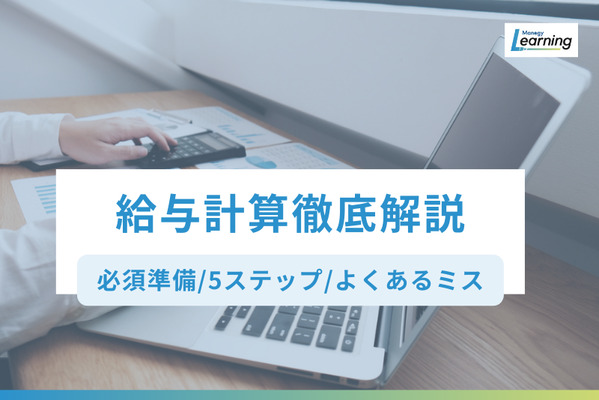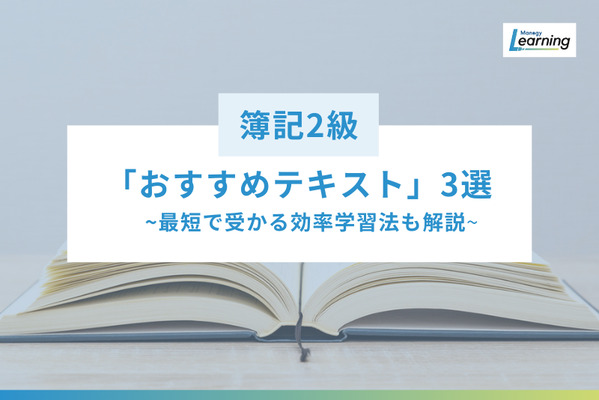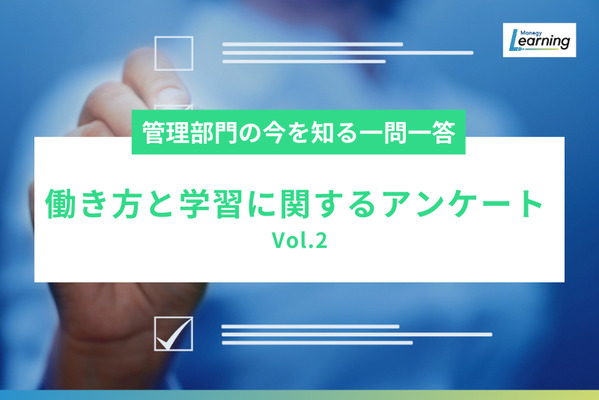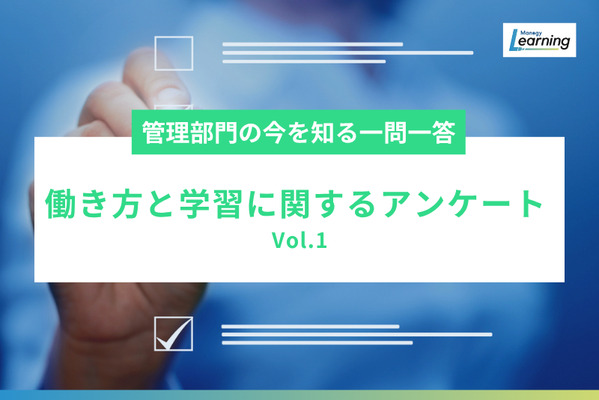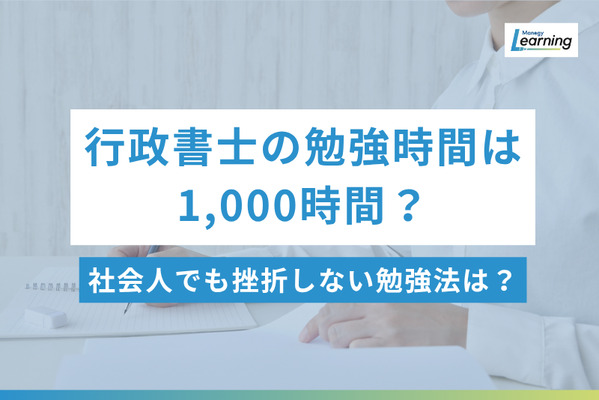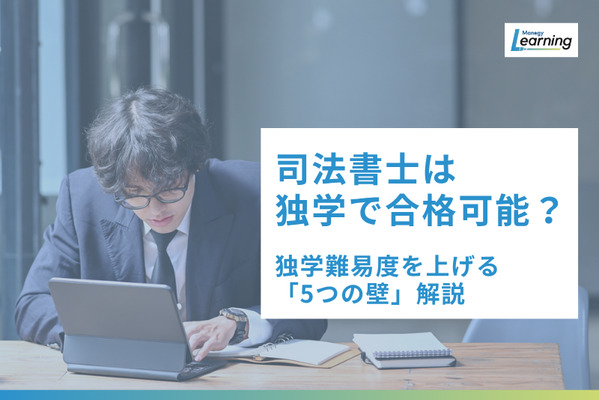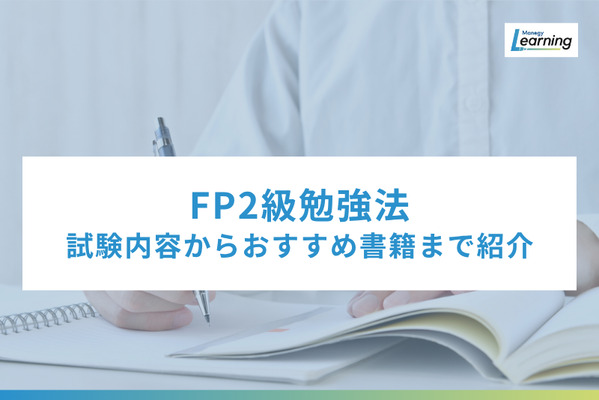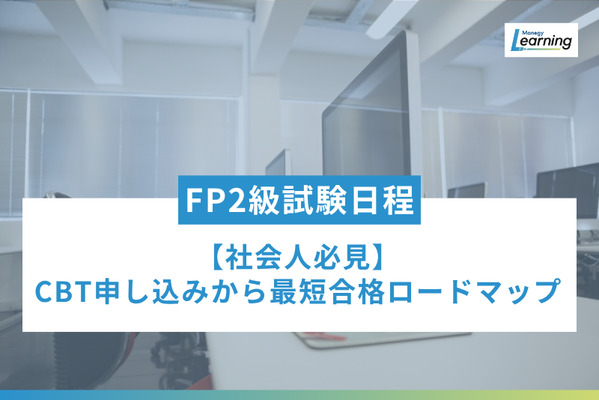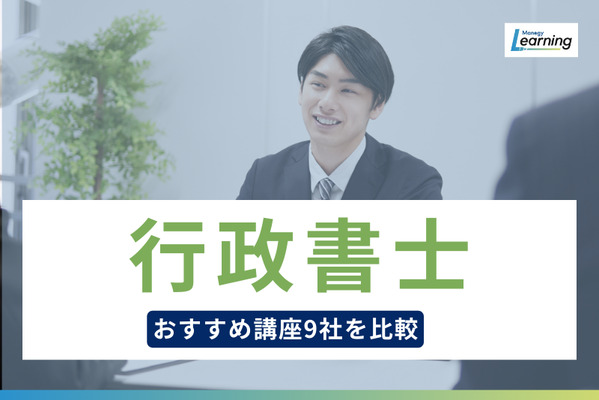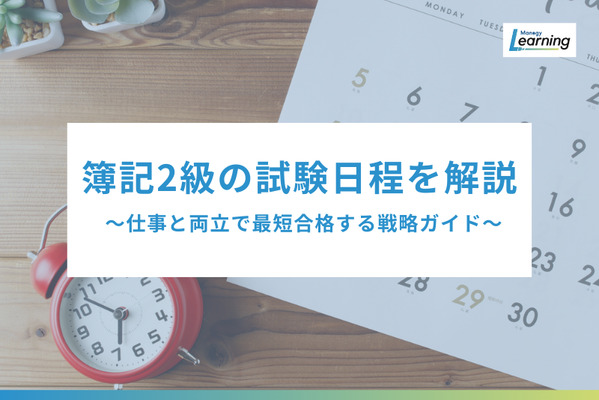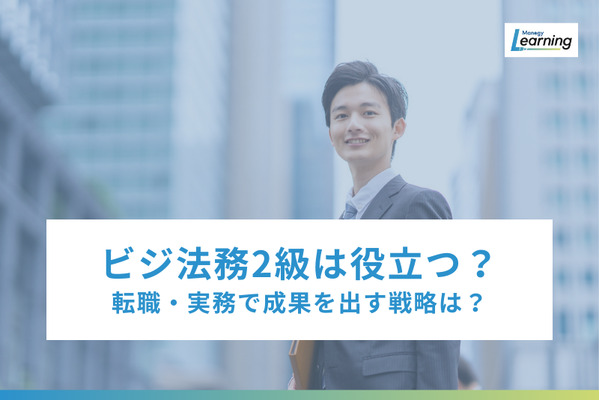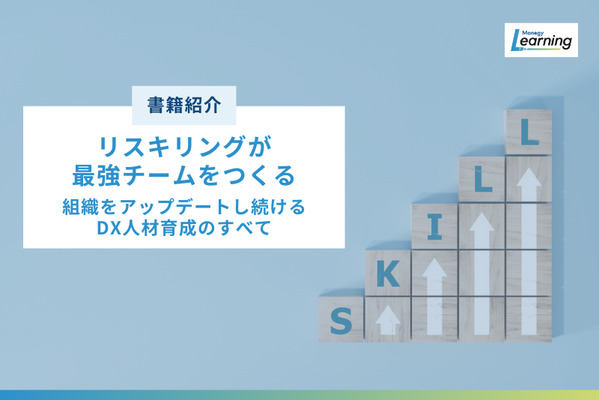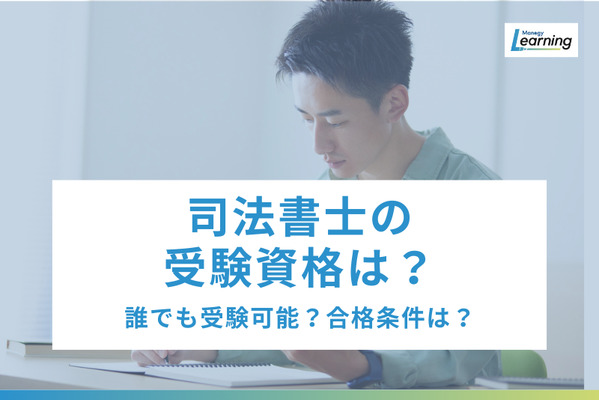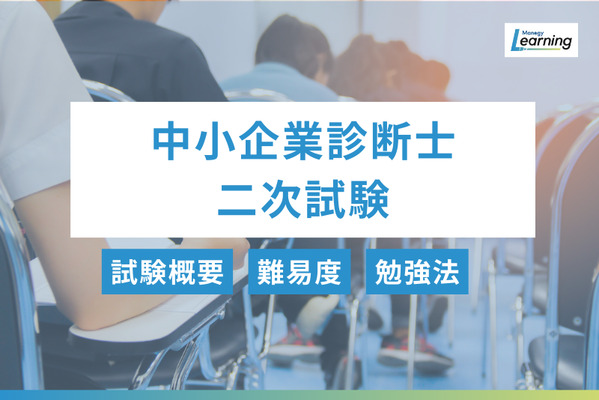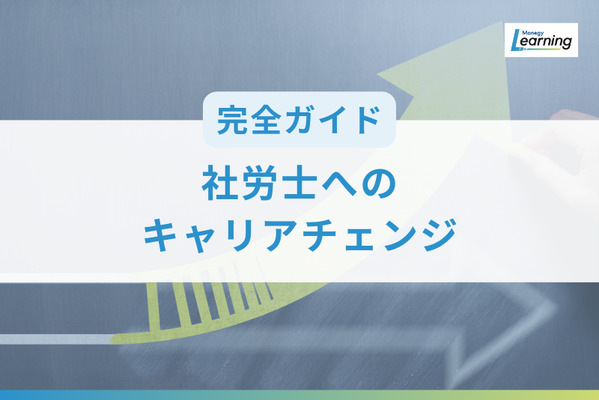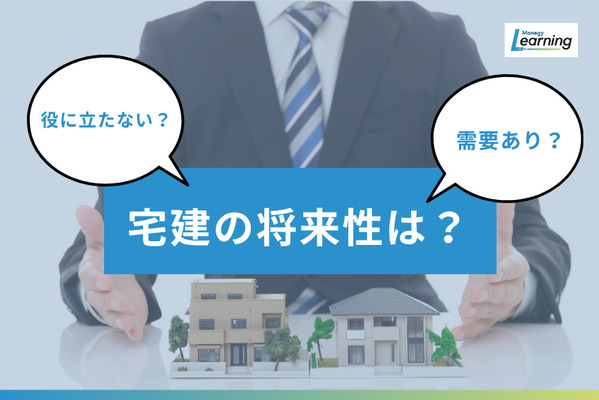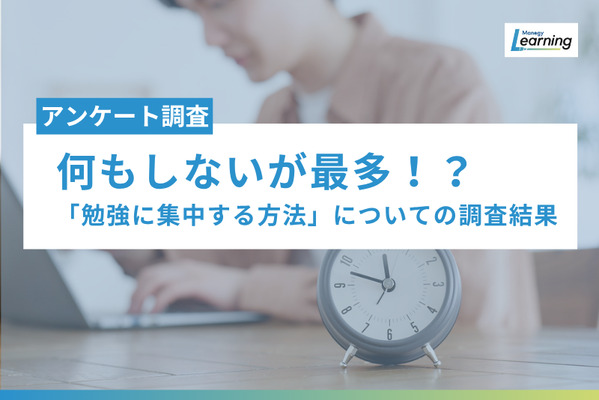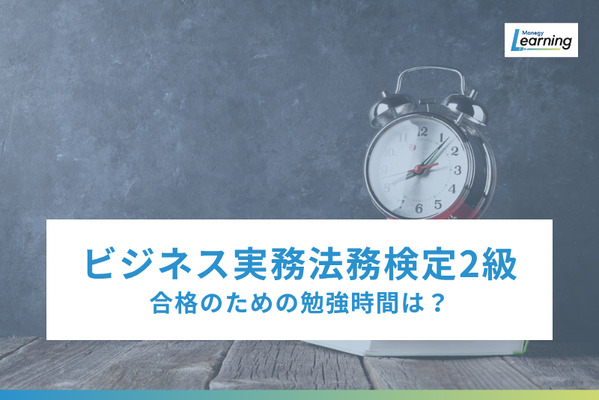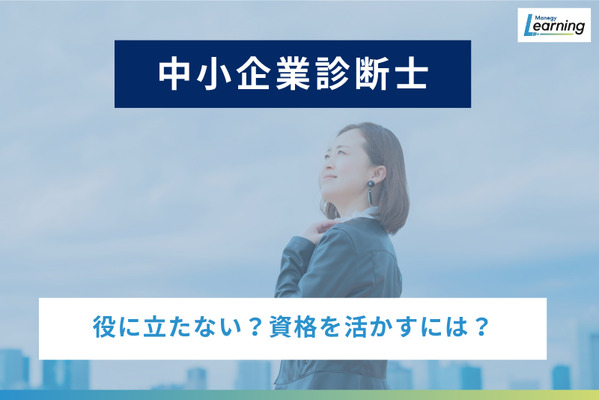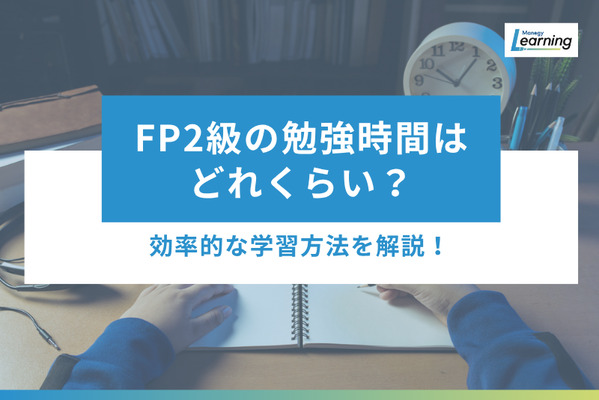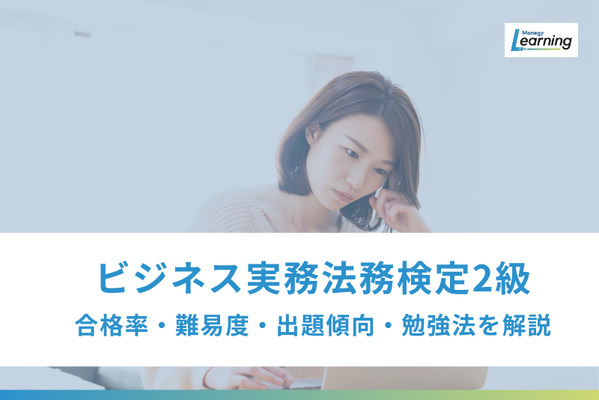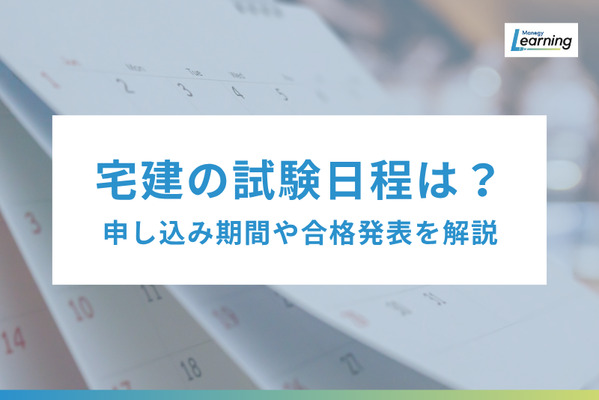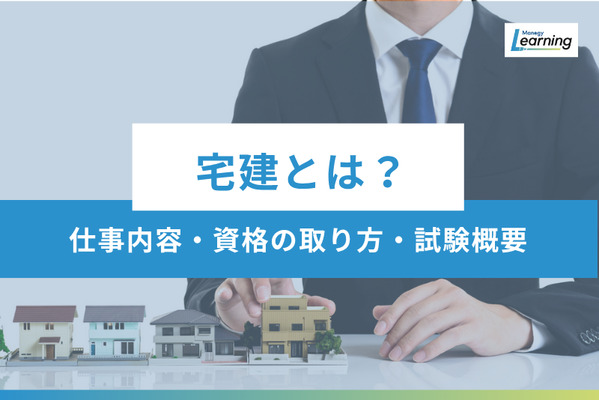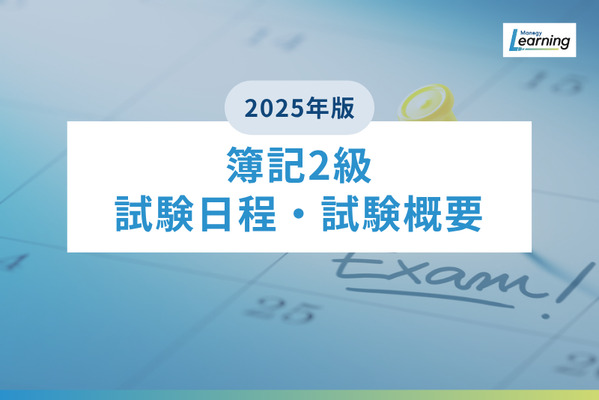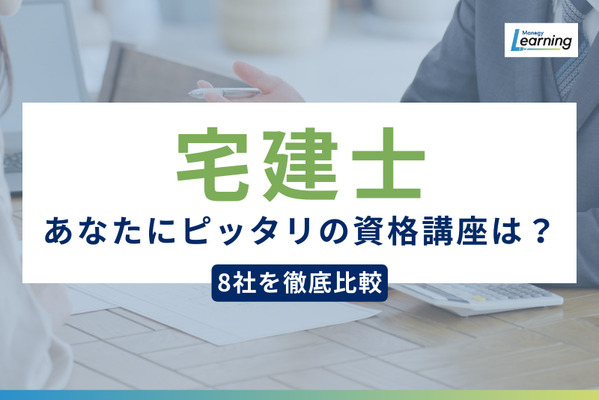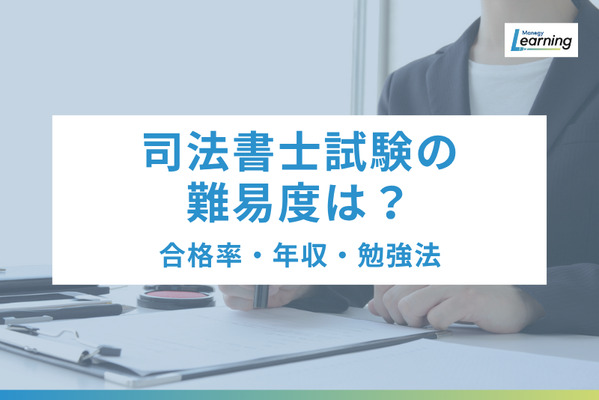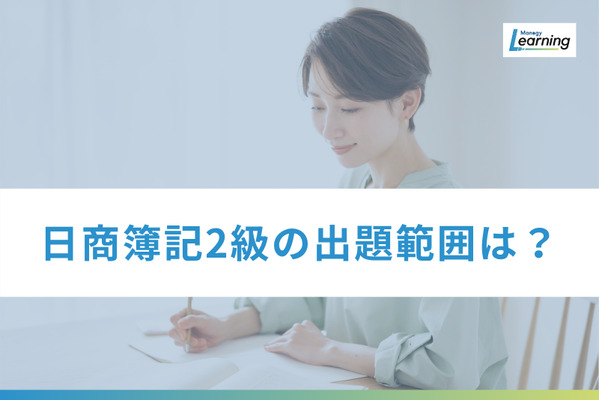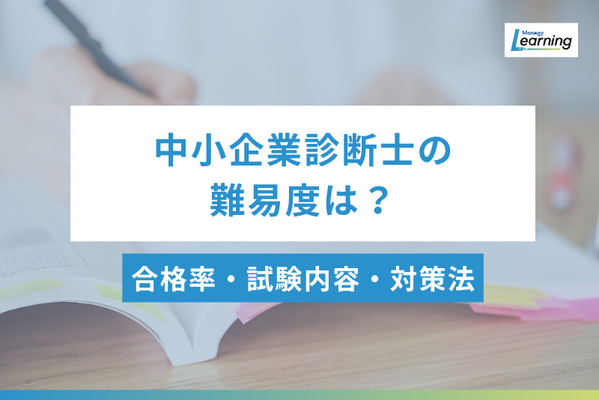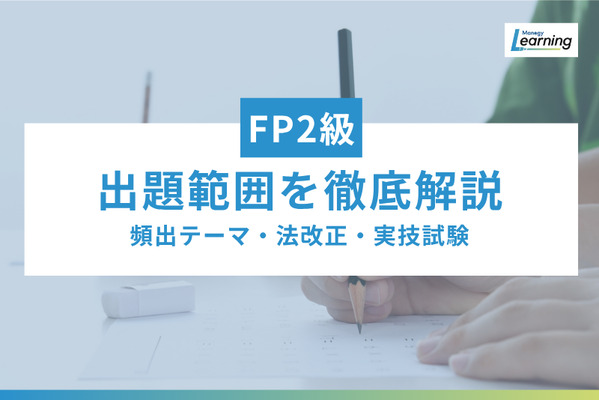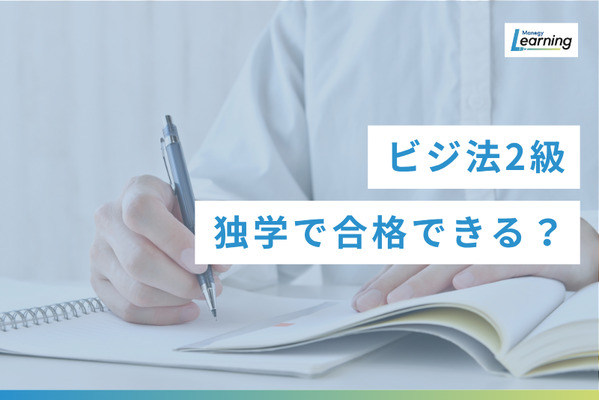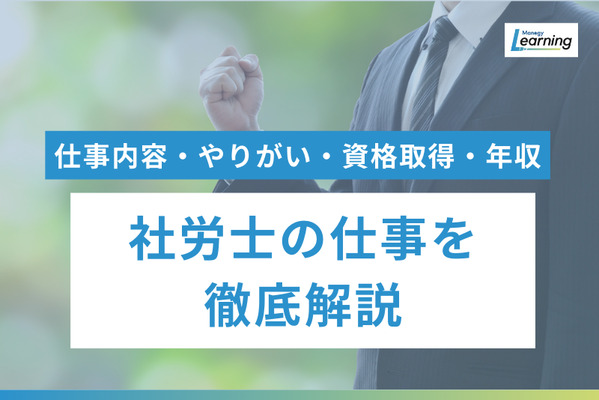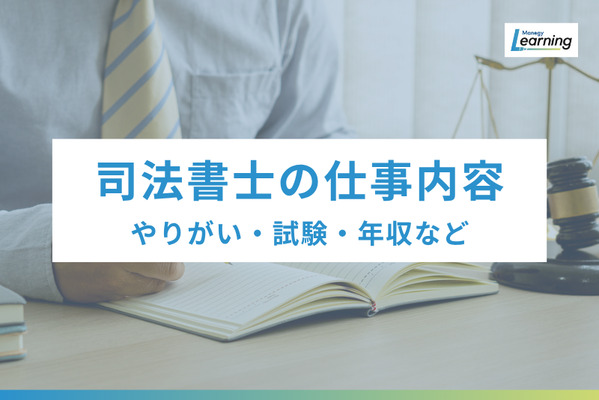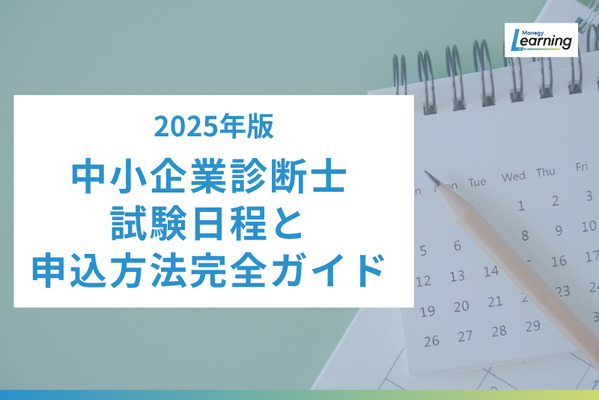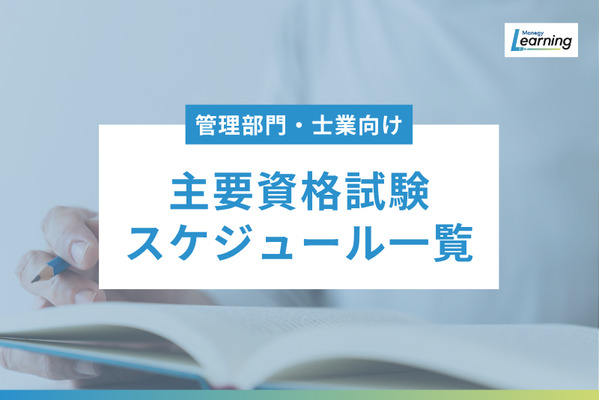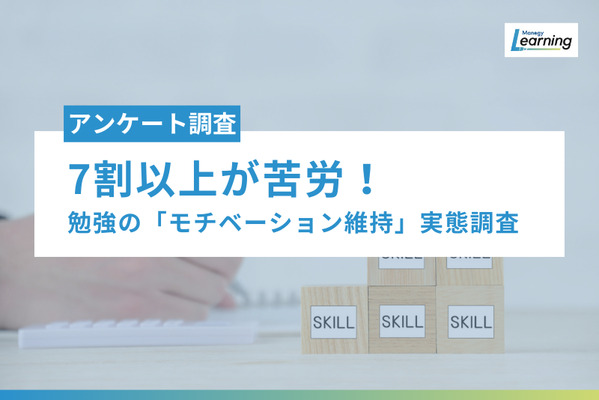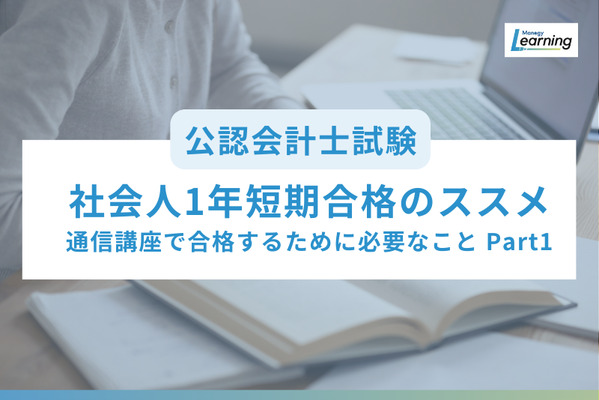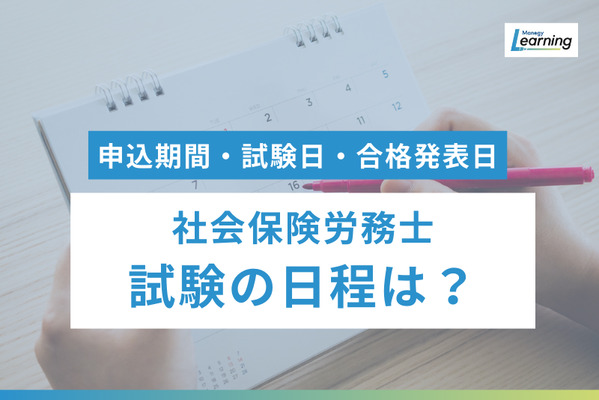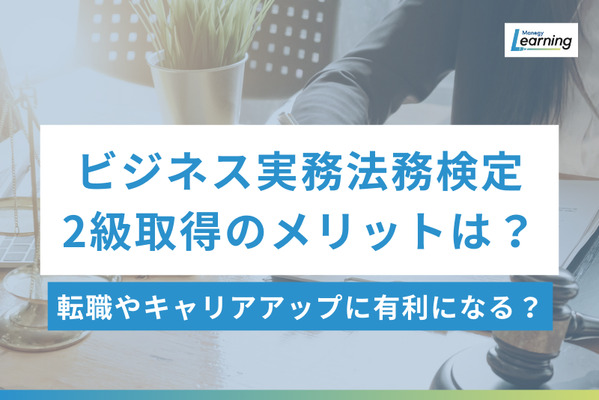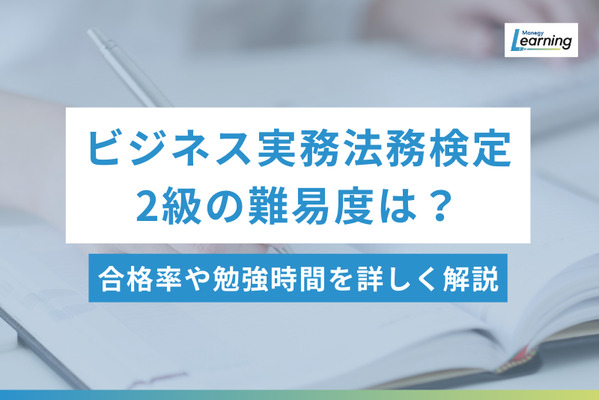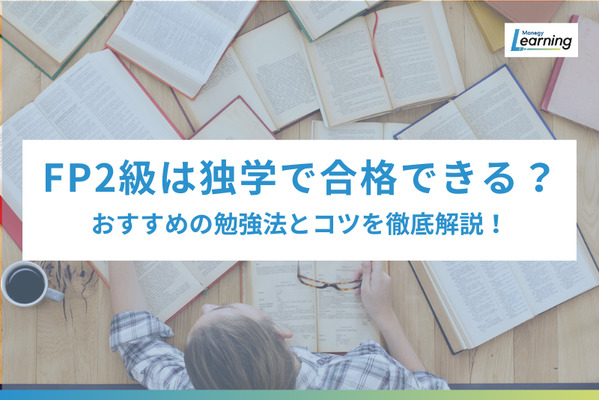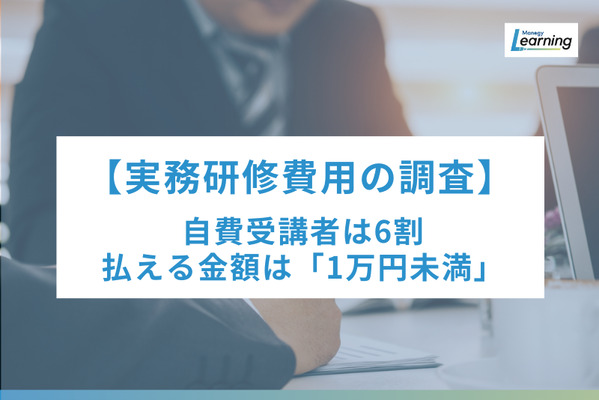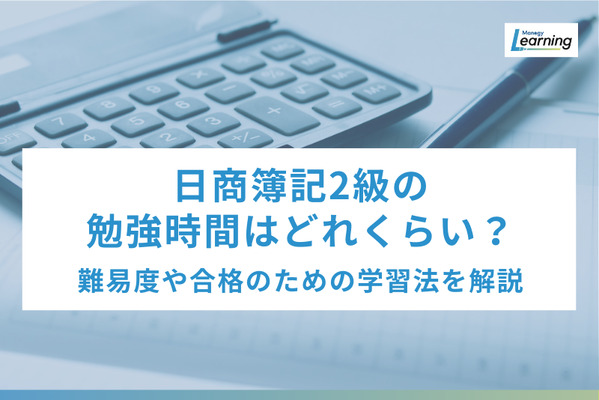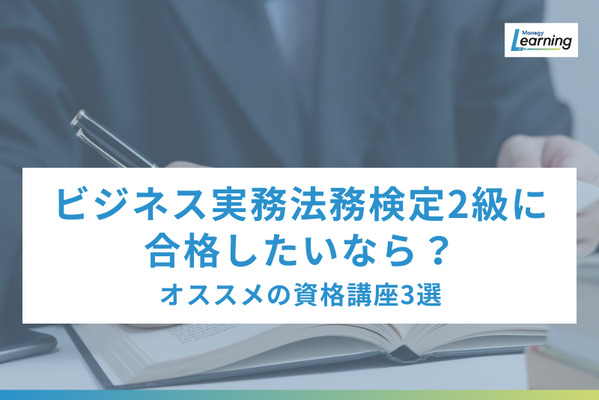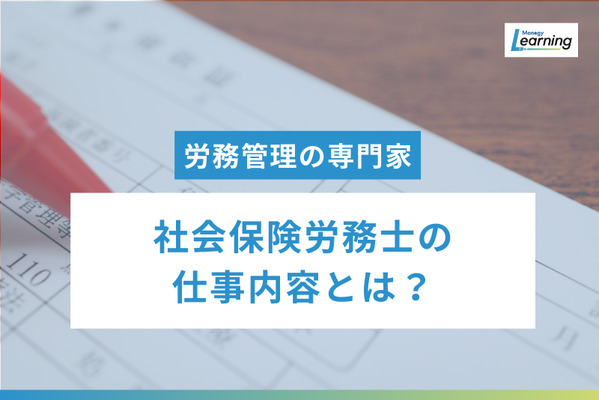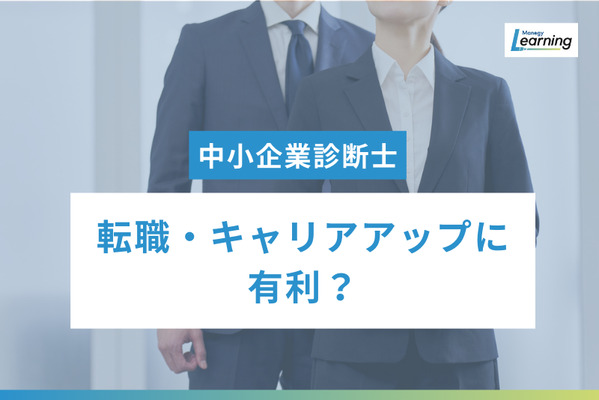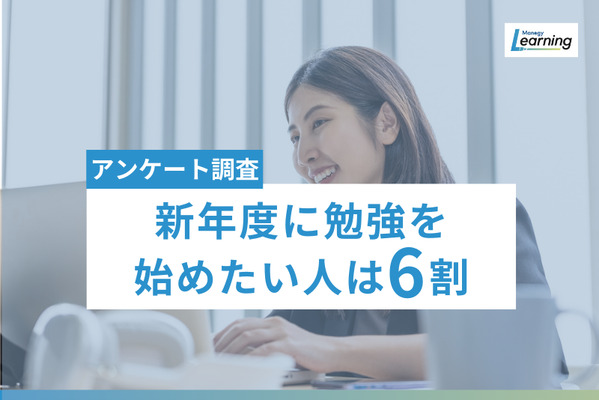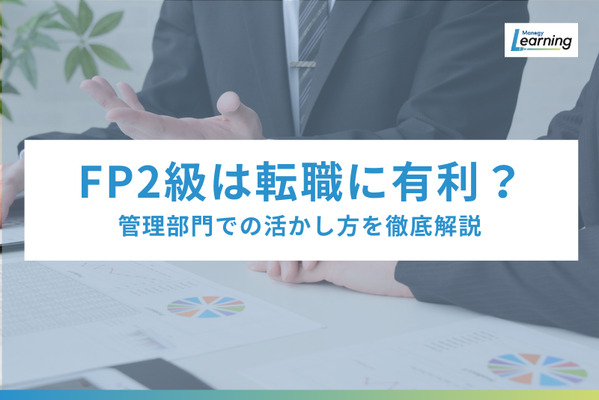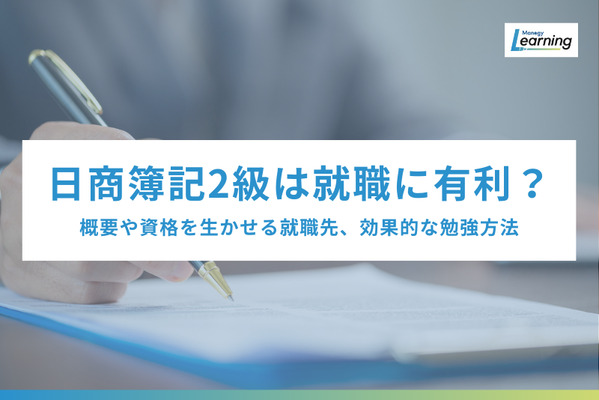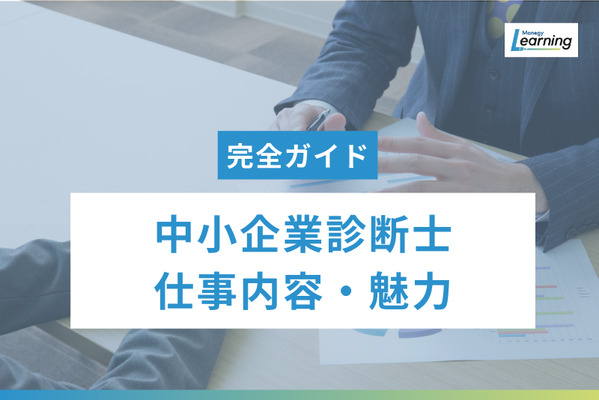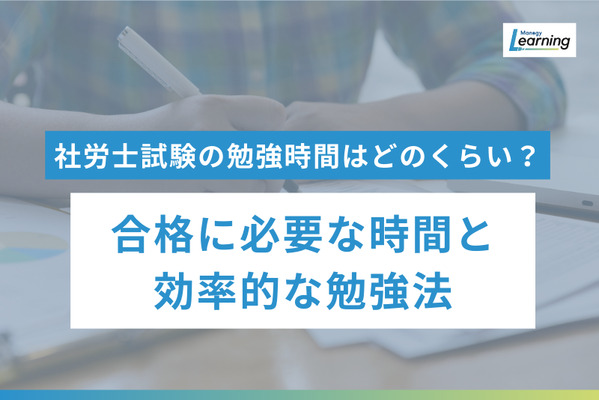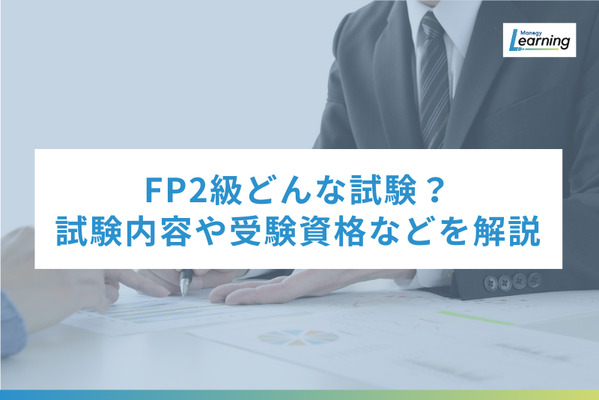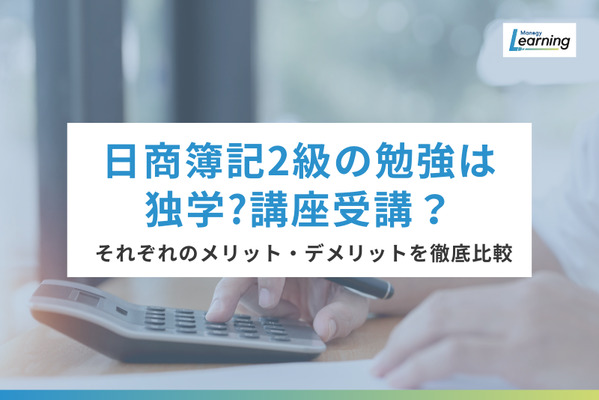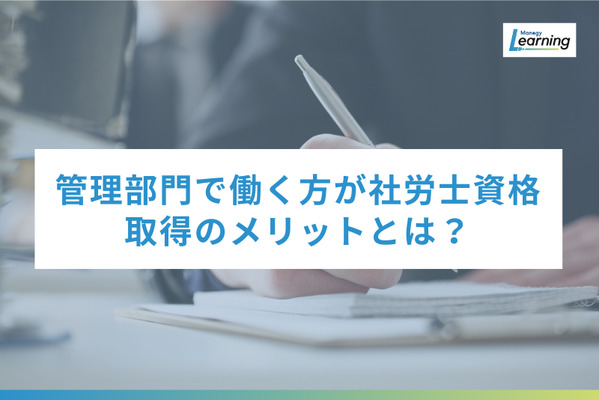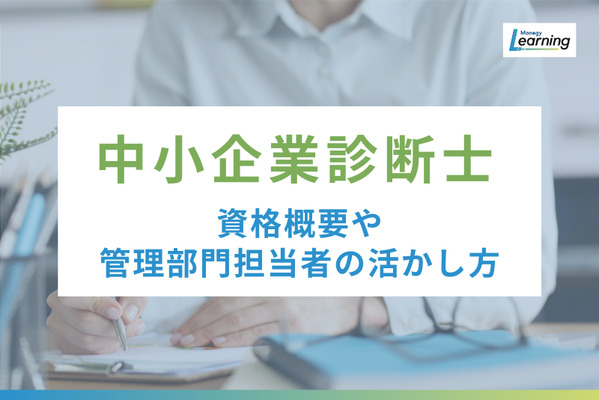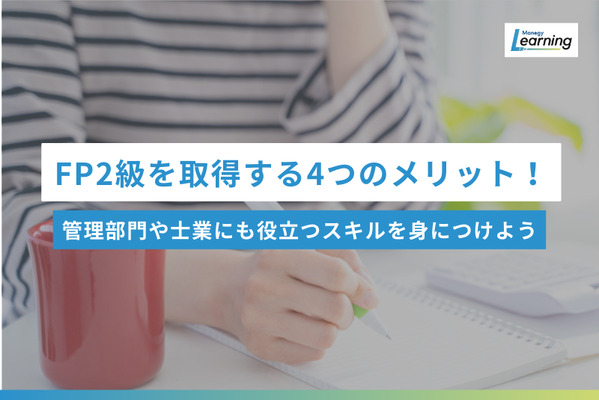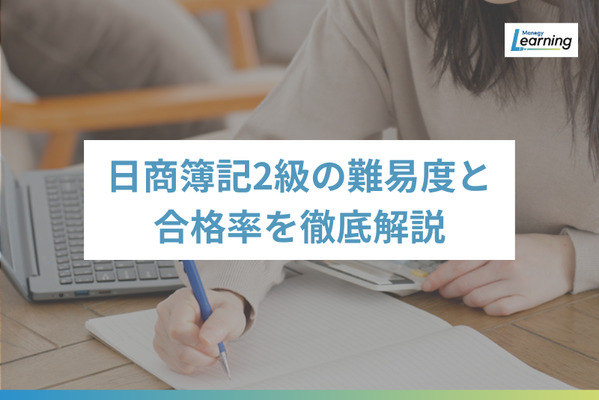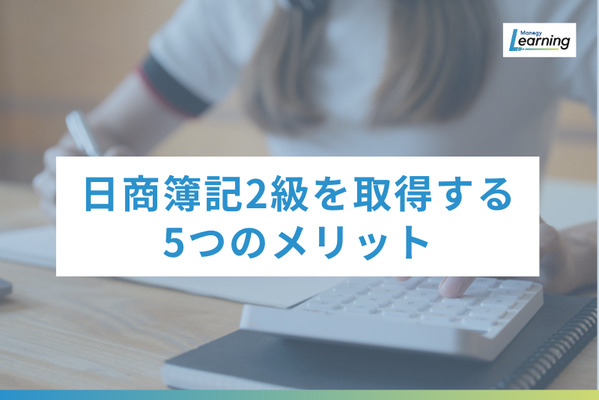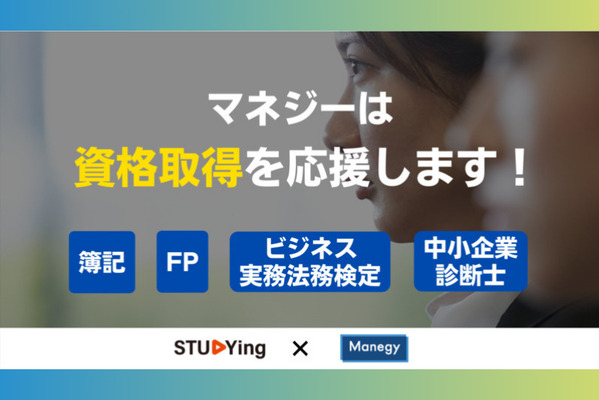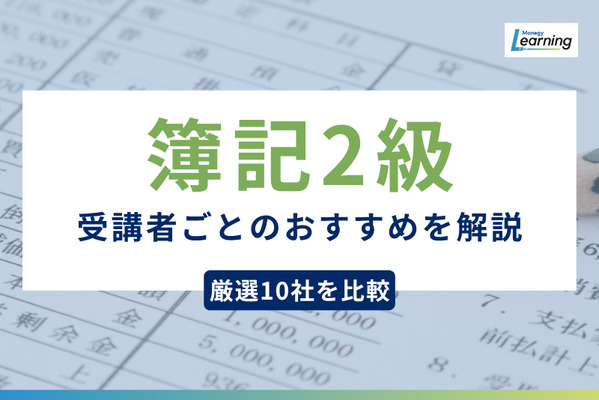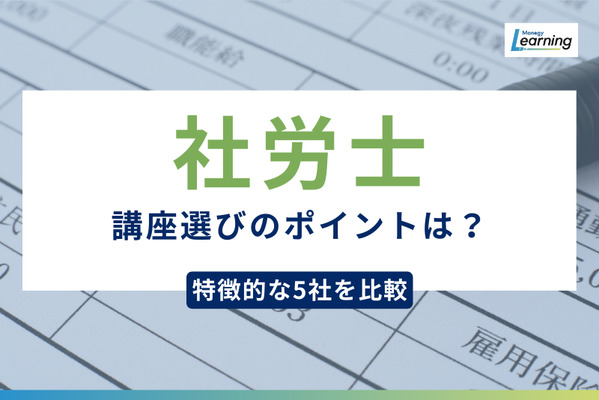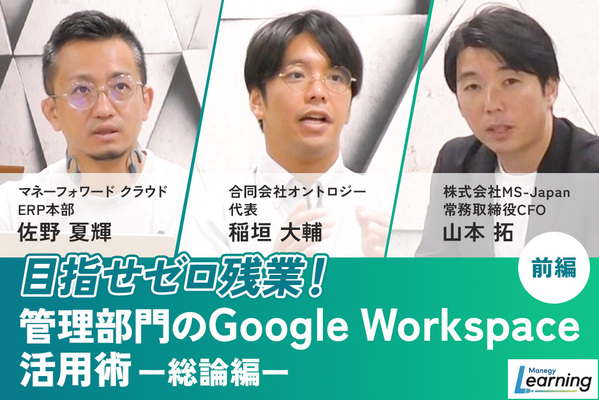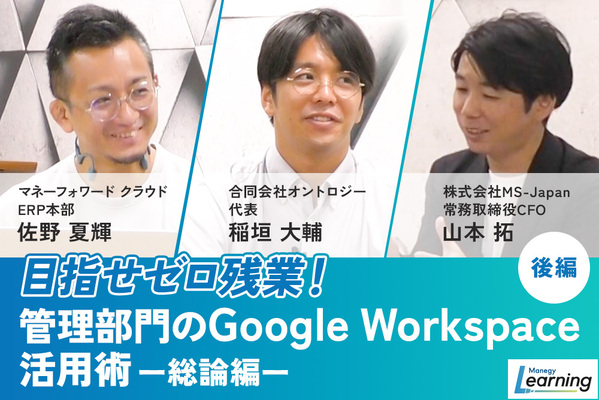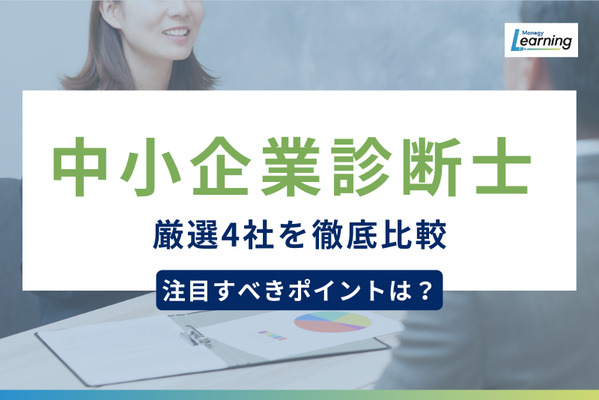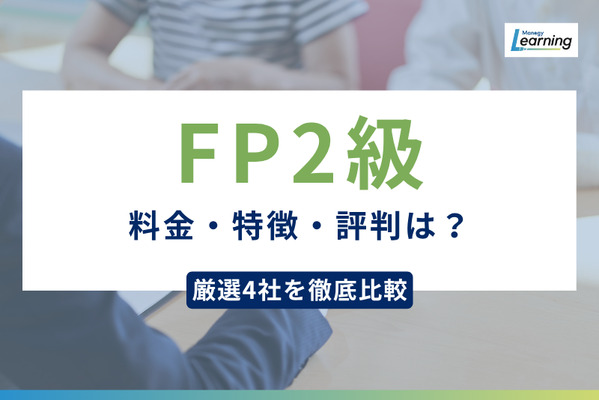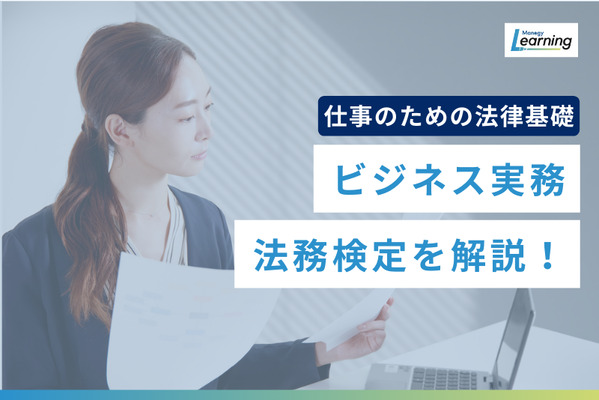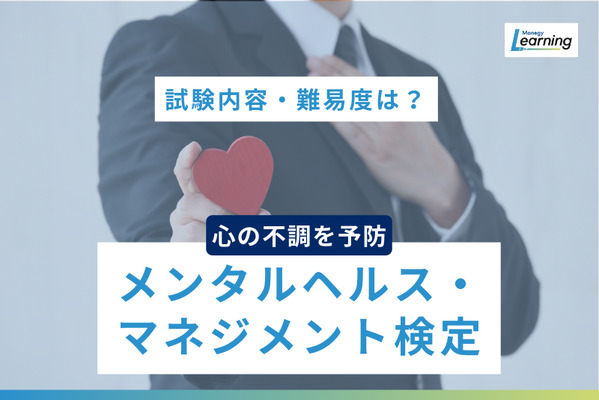司法書士試験の「科目」を徹底解説!|出題範囲や配点、合格を決める「主要科目」などの勉強戦略を紹介
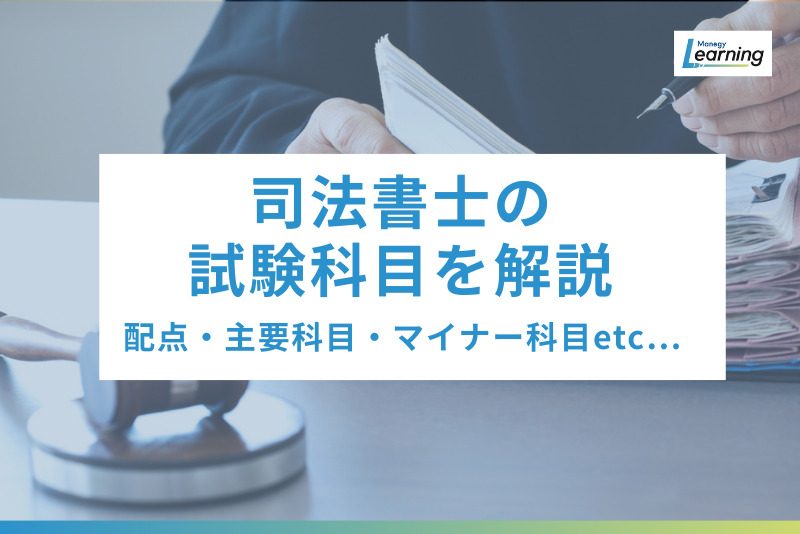
司法書士は、不動産登記、商業登記、相続や遺言、供託手続などを扱う法律事務のプロで、専門性と信頼性を兼ね備える国家資格です。特に、登記業務では高度な法的知識と実務スキルが求められ、登記法のプロとして地域社会に貢献します。
司法書士の資格を取得するには、毎年1回実施される国家試験突破、または法務大臣の認定を受ける必要がありますが、ほとんどの人は国家試験に合格して司法書士となります。なお、試験は筆記試験と口述試験で構成されています。
本記事では、筆記試験の「科目」を中心に、出題範囲や配点などを解説しながら戦略的に学ぶ方法をご紹介します。
なお、司法書士の仕事内容について詳しく知りたい方はぜひこちらの記事をご確認ください。
この記事を読んだ方にオススメ!
司法書士試験とは?全11科目の配点と出題数
司法書士試験は毎年1回実施され、筆記試験と口述試験の2段階で構成されています。口述試験最終確認という要素が強く、落ち着いた受け答えができれば落ちることはほとんどありません。
司法書士の筆記試験で出題される科目は計11科目です。筆記試験は例年7月の第1週目の日曜日に、午前から午後にかけて実施され、択一式(午前・午後に実施)と記述式(午後に実施)で構成されています。
司法書士の筆記試験の構成
筆記試験は次の構成で行われます。
| 時間 | 試験内容 |
|---|---|
| 午前の部 | 9:30~11:30 択一式35問(憲法、民法、刑法、商法・会社法) |
| 午後の部 | 13:00~16:00 択一式35問(上記を除く7科目) 記述式2問(不動産登記法、商業登記法) |
択一式70問+記述2問で、配点は択一式210点+記述140点=350点満点。令和5年度までは記述式の配点が70点でしたが、令和6年度から記述式の配点が140点に変更され、試験全体における記述式の重要性がさらに増しました。
試験合格には、最新傾向の把握も重要な要素です。
資格講座を受講すると、最新傾向の共有をはじめとしたサポートを受けられます。受験をする方は、講座受講を検討するのもよいでしょう。
この記事を読んだ方にオススメ!
また、司法書士試験の難易度や合格率については、こちらの記事で解説しております。
ぜひこちらもご確認ください。
この記事を読んだ方にオススメ!
出題科目と配点の一覧表
| 科目 | 日程 | 問題数(択一) | 配点(択一) | 問題数(記述) | 配点(記述) | 配点(択一+記述) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 憲法 | 午前試験 | 3問 | 9点 | - | - | 9点 |
| 民法 | 20問 | 60点 | - | - | 60点 | |
| 刑法 | 3問 | 9点 | - | - | 9点 | |
| 商法・会社法 | 9問 | 27点 | - | - | 27点 | |
| 民事訴訟法 | 午後試験 | 5問 | 15点 | - | - | 15点 |
| 民事執行法 | 1問 | 3点 | - | - | 3点 | |
| 民事保全法 | 1問 | 3点 | - | - | 3点 | |
| 司法書士法 | 1問 | 3点 | - | - | 3点 | |
| 供託法 | 3問 | 9点 | - | - | 9点 | |
| 不動産登記法 | 16問 | 48点 | 1問 | 70点 | 118点 | |
| 商業登記法 | 8問 | 24点 | 1問 | 70点 | 94点 | |
| 合計 | 70問 | 210点 | 2問 | 140点 | 350点 |
主要科目とマイナー科目について
司法書士試験の出題科目は大きく「主要科目」と「マイナー科目」に分類されます。この分類は、配点の比重や学習の重要性をもとに分けられており、戦略的な勉強計画を立てるうえで非常に大切です。
主要科目…民法、商法・会社法、不動産登記法、商業登記法の4科目
主要科目は出題数が多く、また、記述式問題に対応するものもあるため、配点の割合が高く設定されています。配点比率は全体の8割以上を占めており、試験の合否を大きく左右するため、合格を目指すならば最優先で取り組む必要があります。
マイナー科目…憲法、刑法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、司法書士法、供託法の7科目
マイナー科目の出題数はそれぞれ1~5問程度と限られており、配点もそれほど高くはありません。しかし、基準点制度(後述参照)があるため、どれか1科目でも極端に得点が低いと不合格になる可能性があります。そのため軽視することはできず、効率よく知識をインプットする必要があります。
出題形式ごとの違い(択一式/記述式)
司法書士の筆記試験は、択一式と記述式のそれぞれに合った対策を講じて勉強しなければなりません。以下がそれぞれの特徴です。
択一式問題
複数の選択肢のなかから正解の1肢を選ぶマークシート方式で、正確な知識と早く解く力が求められます。全部で70問出題され、1問あたり3点、合計210点となります。
記述式問題
実務に近いかたちでの問題解決力が問われる形式です。不動産登記法と商業登記法から1問ずつ、合計2問出題され、各70点で計140点となります。令和6年度から配点が増え、より重視されるようになりました。
司法書士試験の科目配点と戦略
ここでは各科目の配点と主な傾向を取り上げました。
科目ごとの配点
司法書士試験は科目が多いため、各科目の配点を踏まえたうえで勉強の対策を取ることが重要です。
筆記試験は350点満点で、前述のとおり、択一式が全70問210点(1問3点)、記述式が全2問140点(1問70点)です。なかでも、主要科目(民法、商法・会社法、不動産登記法、商業登記法)は、全体の約8割以上を占める配点構成になっており、これらを重点的に取り組むことが合格への近道となります。
主要科目
主要科目はそれぞれ配点が高く、どの科目もしっかりと取り組まなければなりません。
民法
択一式で20問出題され、配点は合計60点と最も高い配点となっています。民法は人の権利義務関係を定め、家族法・財産法から幅広く出題されます。
商法・会社法
択一式9問で合計27点。商法と会社法は別の法律で、司法書士試験では会社法を中心に出題される傾向です。
不動産登記法
択一式16問(合計48点)に加え、記述式問題が1問(70点)出題されるため、合計118点と司法書士試験のなかで最も配点が高い科目です。択一式と記述式の対策を並行して進めていくのが望ましいです。
商業登記法
択一式8問(合計24点)+記述式1問(70点)で合計94点。こちらも択一式・記述式の両方が出題されるので対策を並行して進めましょう。
マイナー科目
マイナー科目は配点割合こそ小さいものの、基準点制度(後述参照)があるため無視できない領域です。
憲法
配点は3問(合計9点)です。条文と判例を結びつけ、理解を深めながら勉強を進めましょう。
刑法
こちらも配点は3問(合計9点)です。主要な内容を得点できるような勉強をするとよいでしょう。
民事訴訟法
5問(合計15点)と比較的配点が高いため、早めに対策を進めましょう。
民事執行法および民事保全法
配点はそれぞれ1問(合計6点)です。ともに基本的な問題を落とさないことが大切です。
供託法
出題数は3問(合計9点)。出題傾向は大きく変わらないため過去問の活用しましょう。
司法書士法
1問(合計3点)。得点しやすい科目なので確実に取りに行きたい科目です
「合格基準点」とは
合格基準点とは、司法書士試験において「合格するために最低限クリアしなければならない得点ライン」のこと。これを下回ると、たとえ総合得点で合格ラインを超えていても不合格になるため、非常に重要な指標です。例えば、令和6年度試験の基準点をご紹介します。
- 午前の部(択一式問題) 満点105点中78点
- 午後の部(択一式問題) 満点105点中72点
- 記述式問題の基準点 満点140点中83点
このように、択一式と記述式のどちらも基準点を下回らないように、バランスよく勉強することが求められています。
司法書士試験の主要科目の特徴と出題範囲
主要科目は試験の合格を決める存在であり、勉強順番としては最優先で行うのが望ましいです。以下、各科目の特徴と出題範囲を解説します
民法
司法書士試験の中核をなす科目であり、出題数は択一試験の中で最も多いです。幅広い範囲から出題され、特に、「物権・担保物権」の出題が多い傾向にあります。また、判例に基づいた問題が多い傾向のため単なる暗記では対応できません。概念の理解を土台にしながら、論理的に考える力を養う必要があります。
商法・会社法
会社法は会社の組織運営に関するルールを定める法律で、株式会社の意思決定手続きや取締役会の運営、株主の権利などが出題範囲です。条文の数が多く複雑ですが、論点を絞って勉強することで効率的に対応できます。
不動産登記法
不動産登記法では登記事項、申請手続き、登録免許税などが問われます。 条文の正確な理解と、登記事項の判断力が鍵となる実務寄りの科目です。登記申請の可否判断や登記事項証明書の読み取りなど、試験では具体的な登記処理が出題される傾向にあります。記述式でも出題されるため、実際の申請書の構成を理解し、正確に書ける力が不可欠です。
商業登記法
商業登記法は、会社法との関連も強い科目です。設問では法律構造と実務対応の両面を問われます。記述問題では、特に変更登記における必要書類の判断や添付書面の記載が重要です。
以上が、主要科目の各科目の特徴と出題範囲です。一般的には民法から学び始め、登記法、商法・会社法へ進む順番が効率的です。
司法書士試験のマイナー科目の特徴
マイナー科目は配点割合が低いですが、「捨て科目」として扱えるほど容易ではありません。ここでは、マイナー科目である7科目の特徴と要点、捨ててはいけない理由をご説明します。
7科目の内容
憲法
判例と人権論が中心で、比較的取り組みやすい科目とされています。
刑法
犯罪類型に関する問題が出題されます。基礎問題での失点は防ぎたい科目です。
民事訴訟法
手続きが多く、民事執行法、民事保全法との関連も深いため、総合的な理解が必要です。
民事執行法
広範囲ながら出題数は1問のため、あまり深入りしないのが得策と言えそうです。
民事保全法
こちらも出題は1問。条文の知識を理解し、基礎問題を落とさないことが大切です。
司法書士法
司法書士の職務や懲戒制度などの領域が出題されます。
供託法
過去何度も同じ内容が出題されているので、過去問の内容マスターする事がおすすめです。
マイナー科目を捨ててはいけない理由
マイナー科目は配点割合が小さいため、つい後回しになりがちです。しかし、前述の合格基準点制度があるため、捨て科目を作らずにどの科目も一定の得点を獲得するよう心がけましょう。
また、マイナー科目は出題パターンが比較的固定化されており、過去問を分析すれば効率よく得点を伸ばせる可能性があります。短期間の集中学習でも成果が出やすい傾向があるため、しっかり取り組めば貴重な得点源となります
まとめ
司法書士の資格試験は、法律知識と実務力の両面を問われます。
配点の大きい主要科目を中心に、マイナー科目も基準点をクリアする、というバランスの良い勉強戦略が功を奏します。また、択一式と記述式という、それぞれの問題形式に合った方法で演習を繰り返し行うことで、実力が身に付くでしょう。繰り返し演習と時間配分を意識した勉強によって、ぜひ合格を勝ち取ってください。。
この記事を読んだ方にオススメ!

Manegy Learning
Manegy Learningは管理部門・士業の皆さまに向けて、実務に役立つTIPSや資格取得のためのスクール取得などの情報を発信し、みなさまの学びをサポートします。
MS-Japan
https://www.manegy.com/learning/