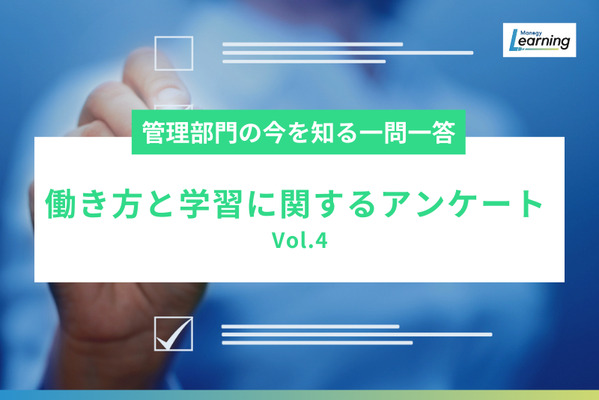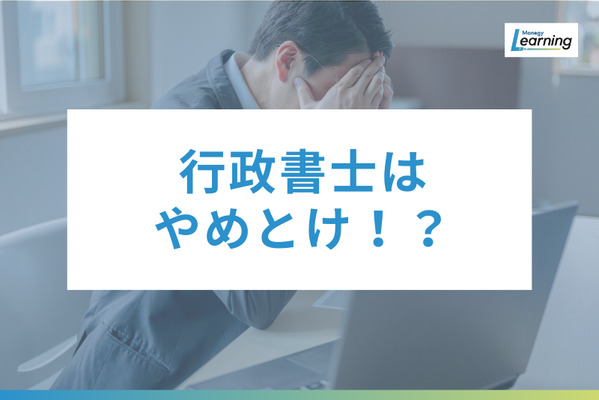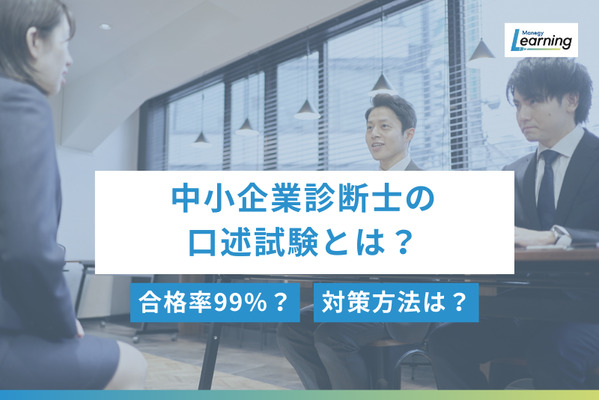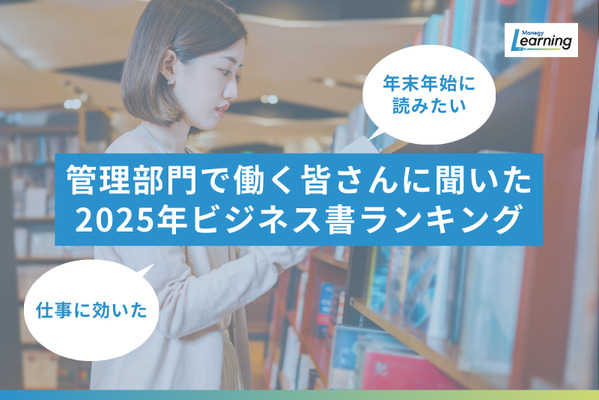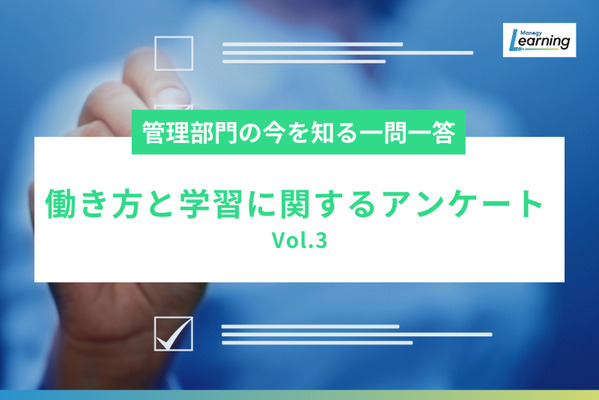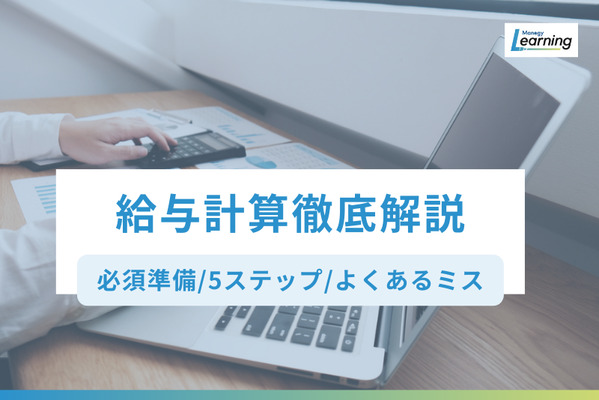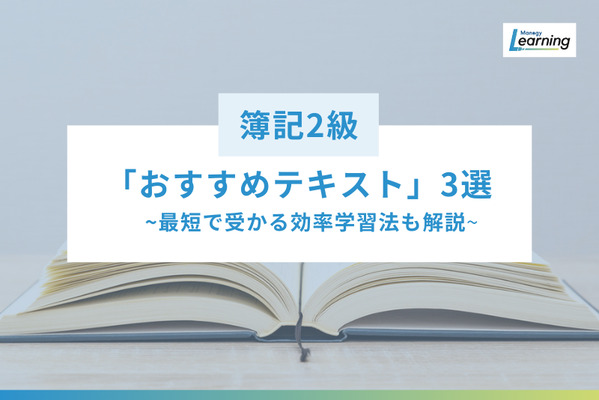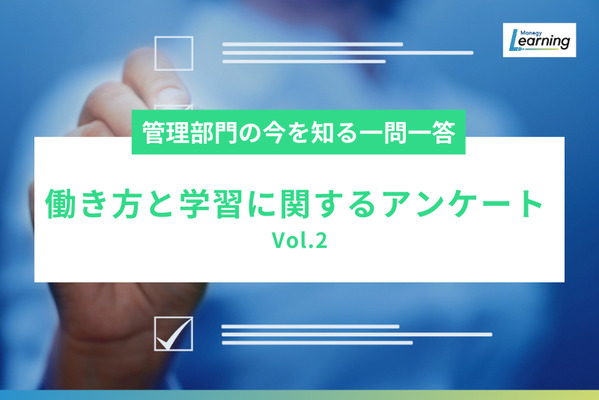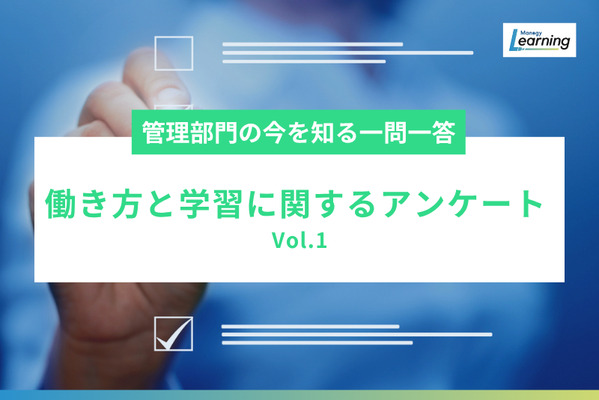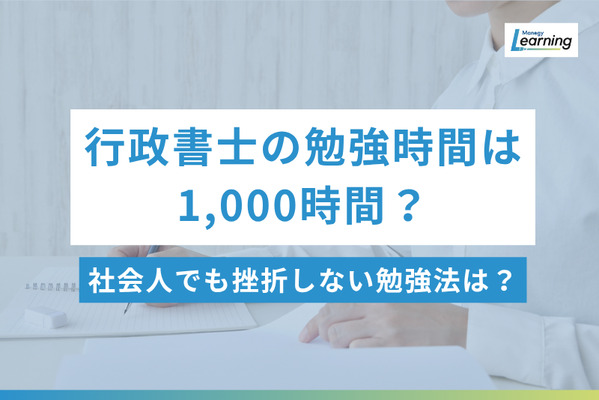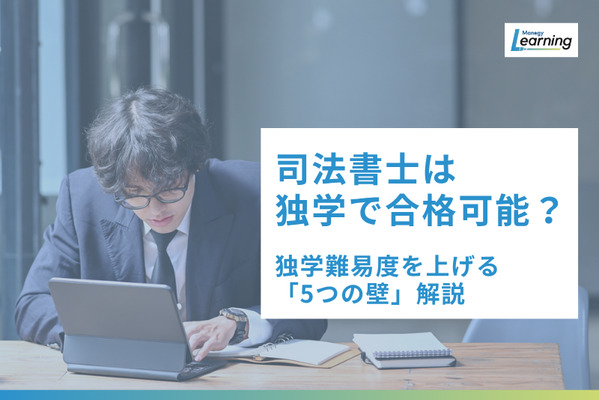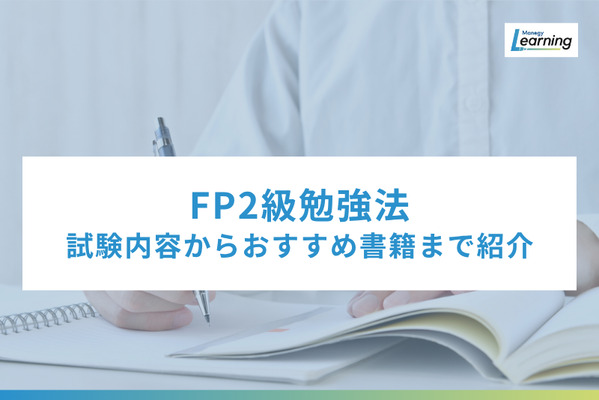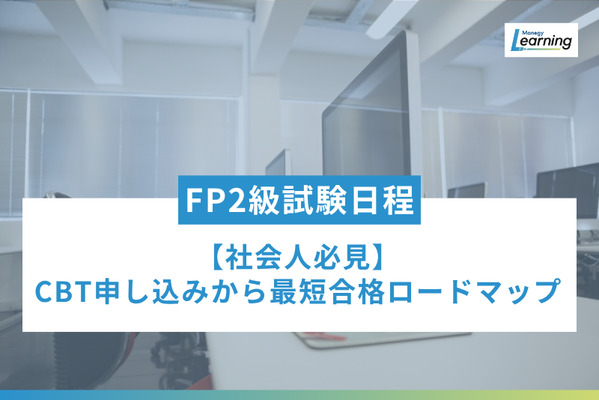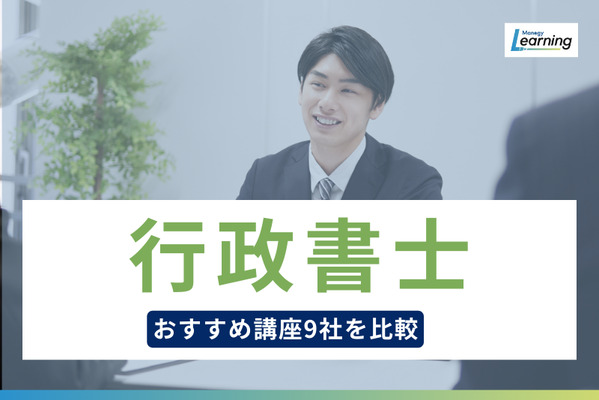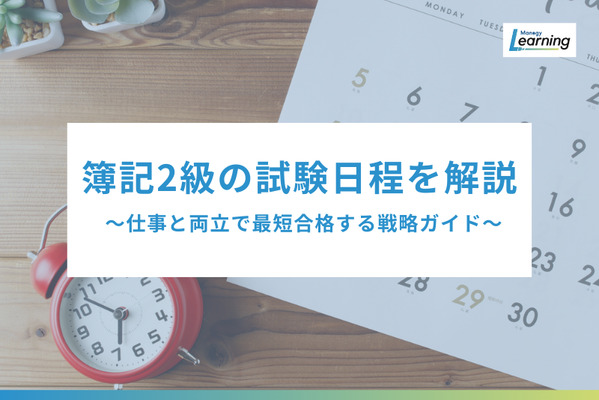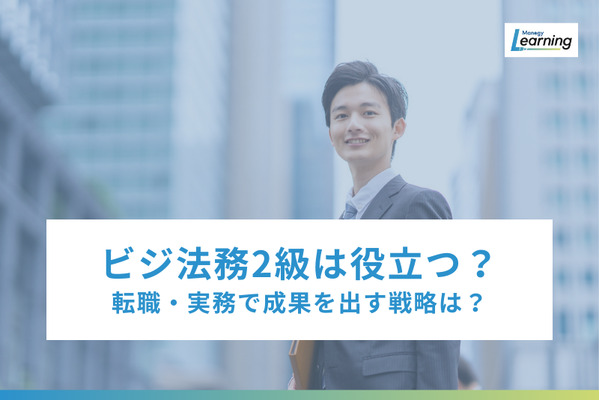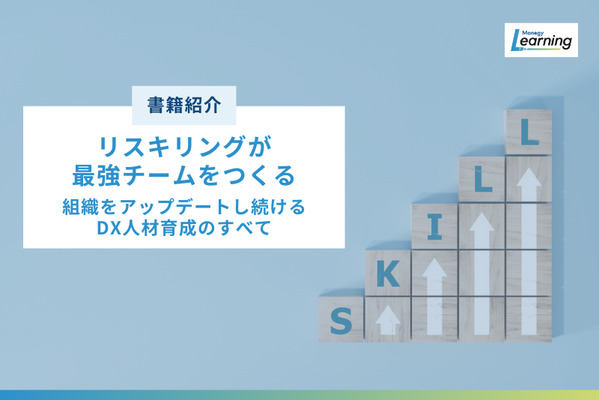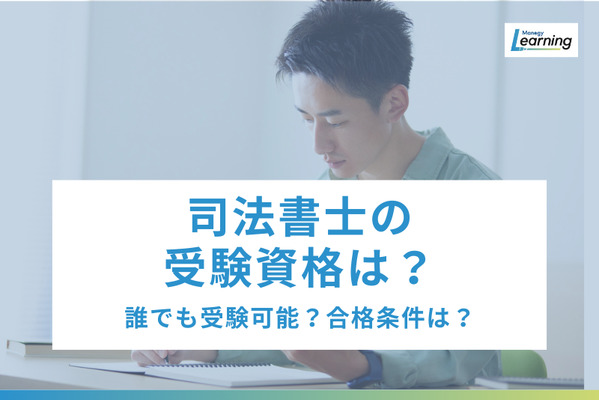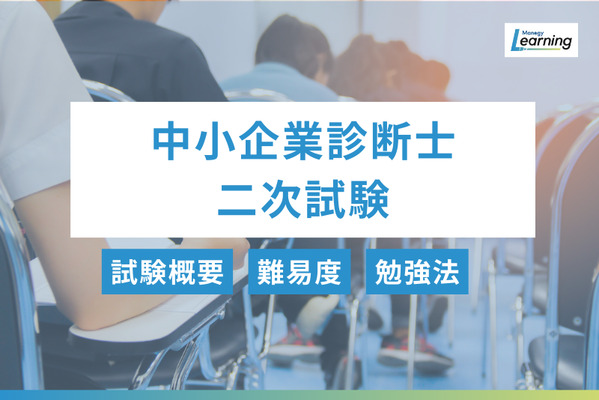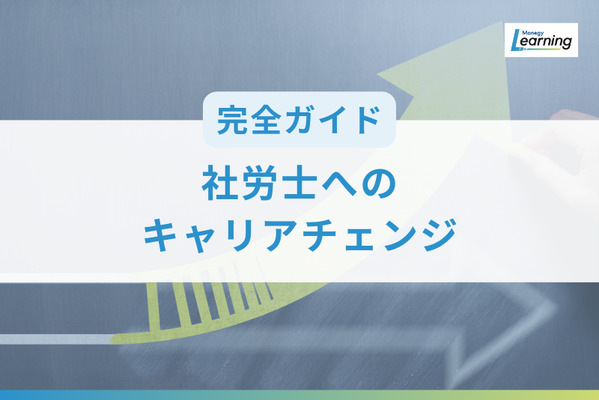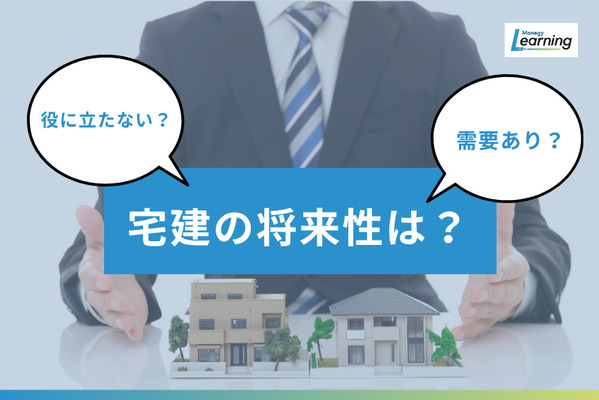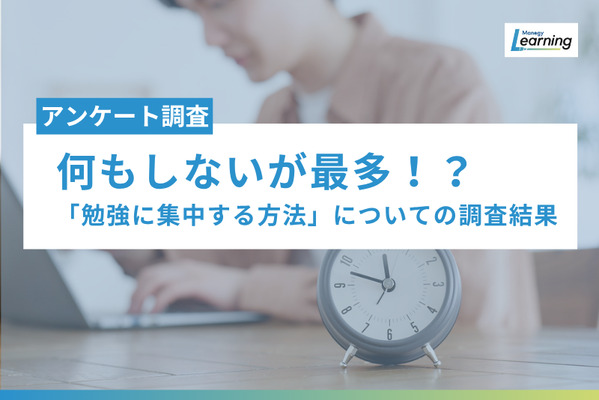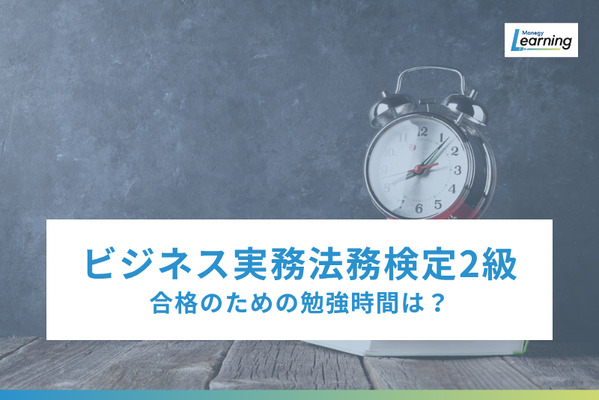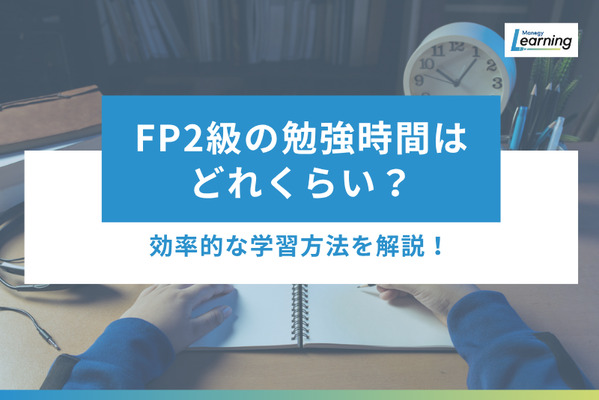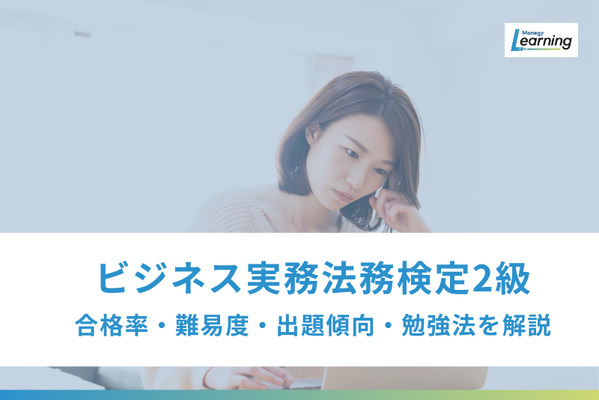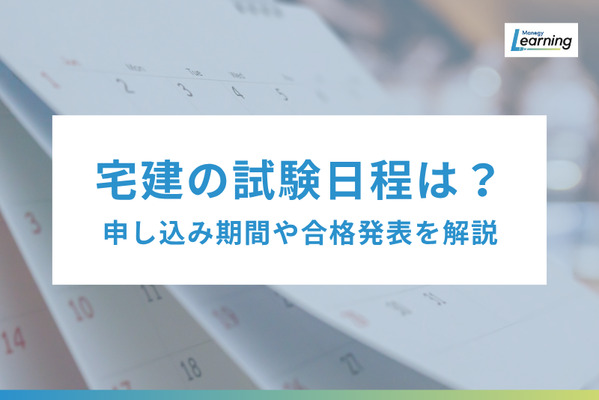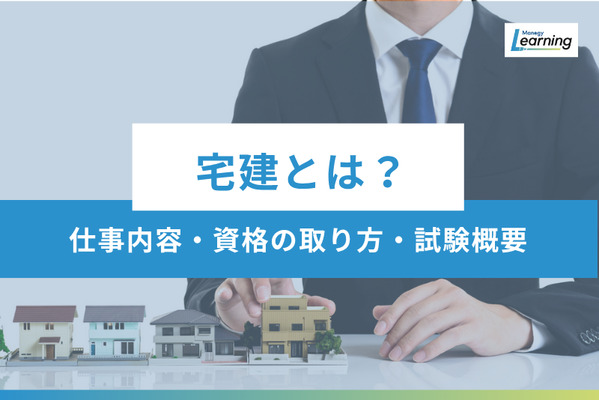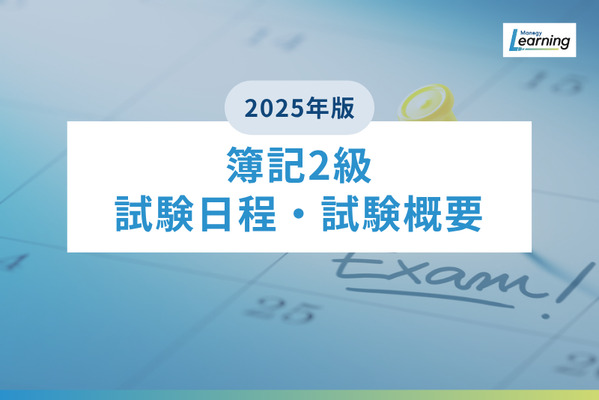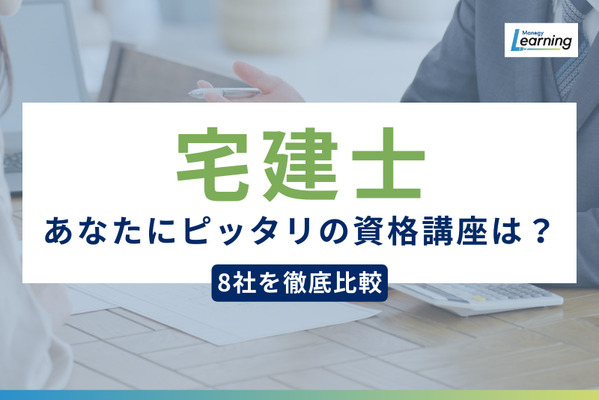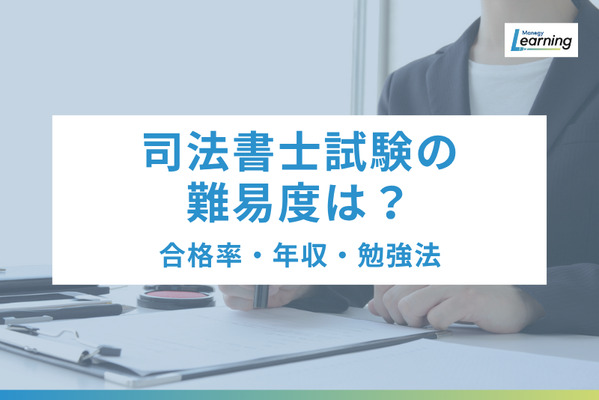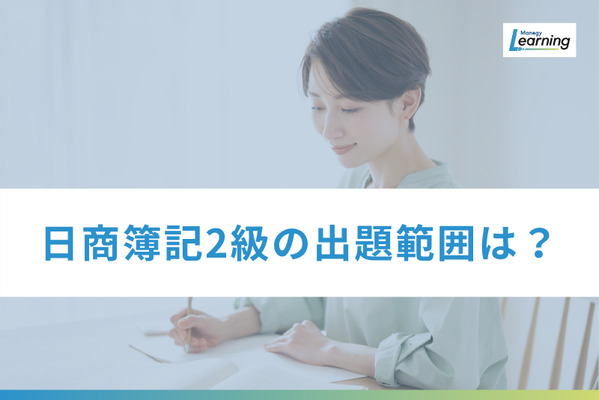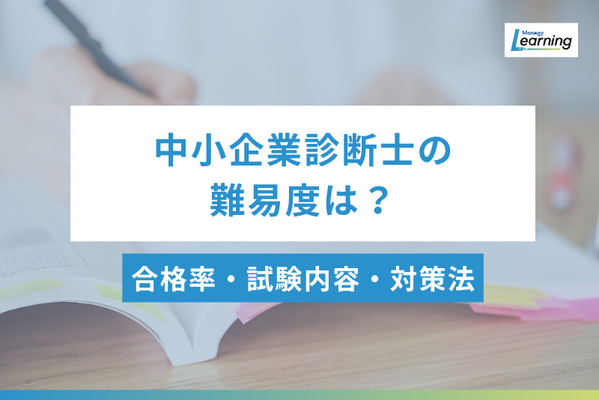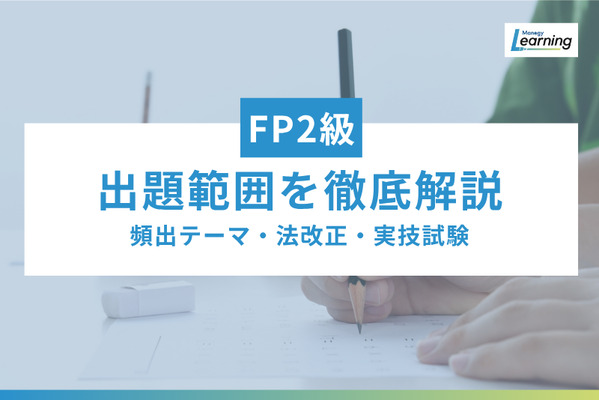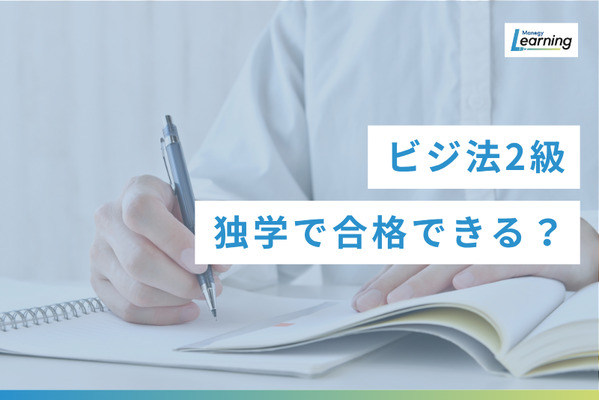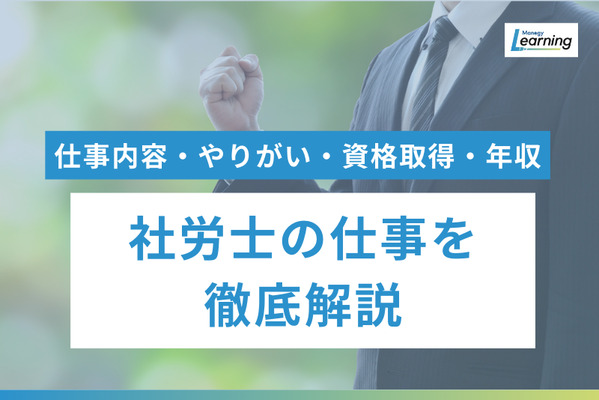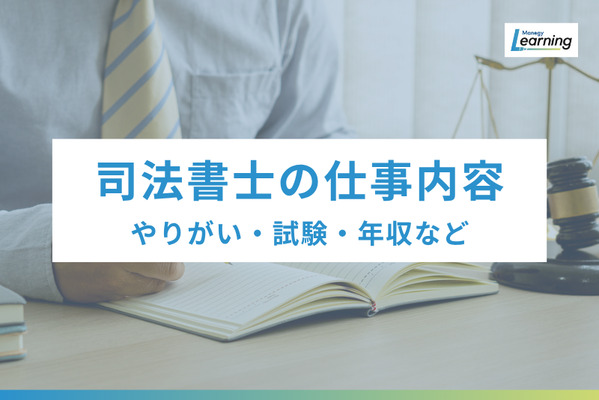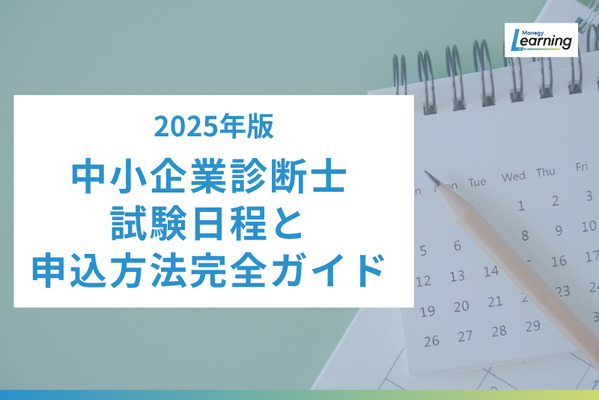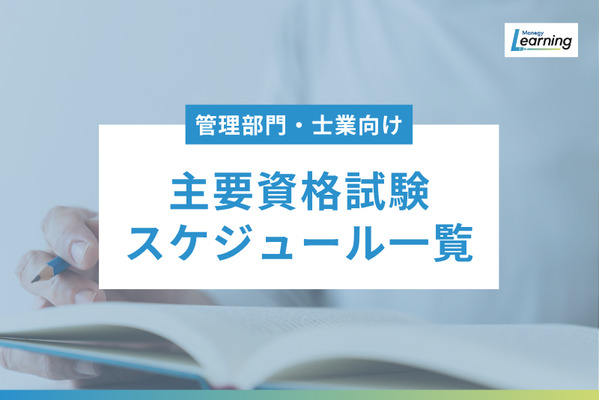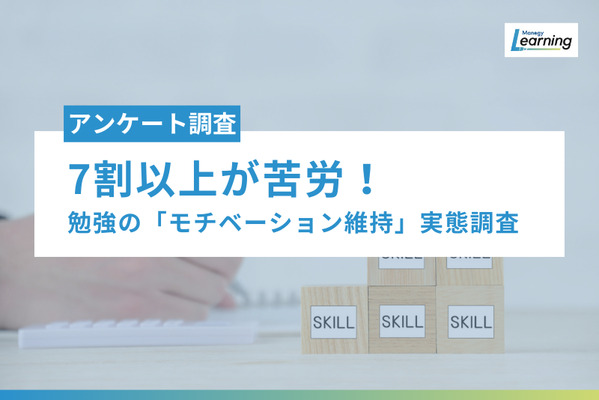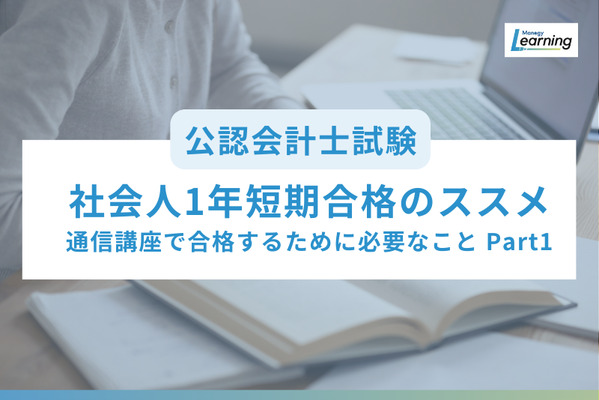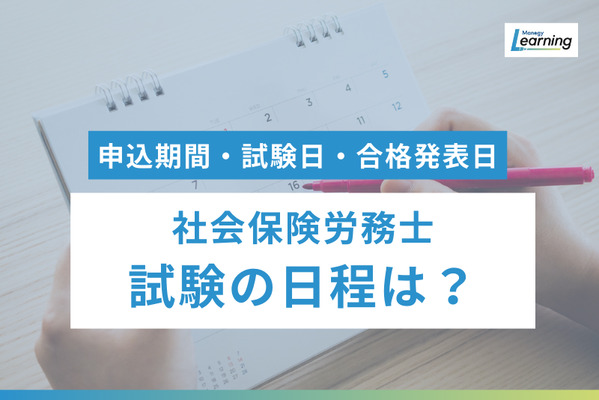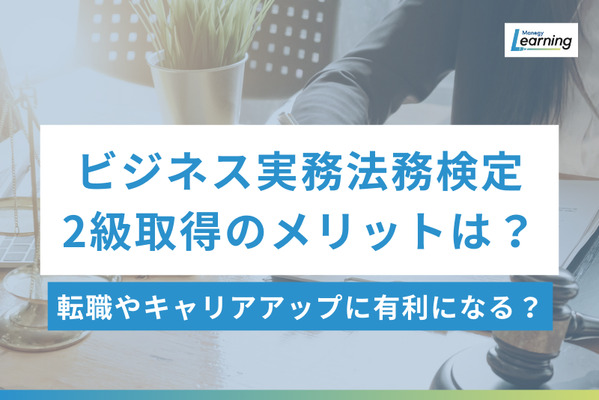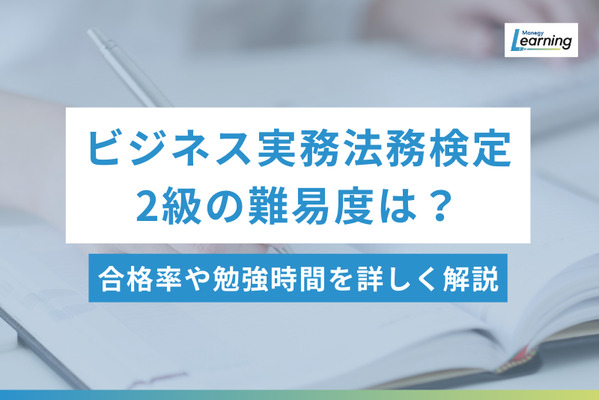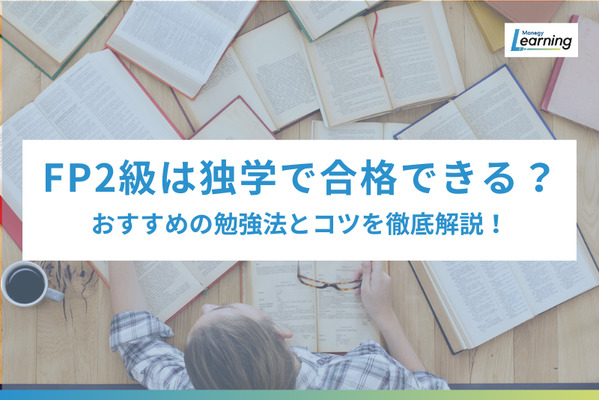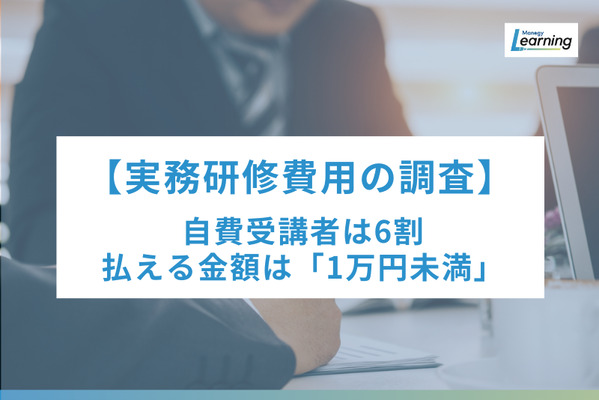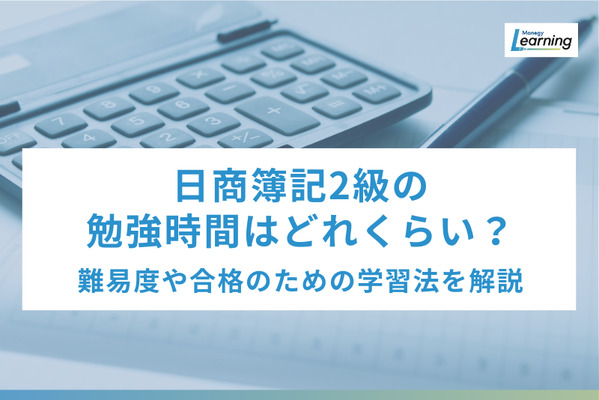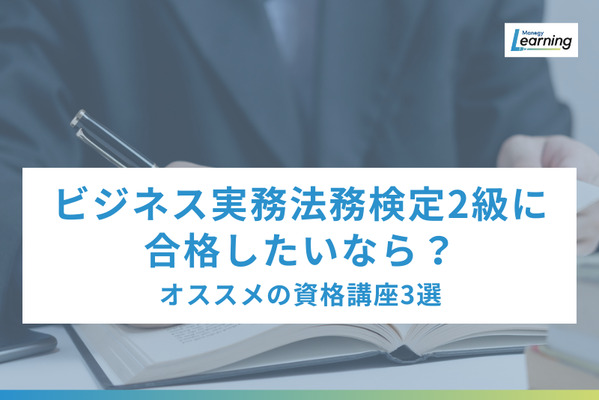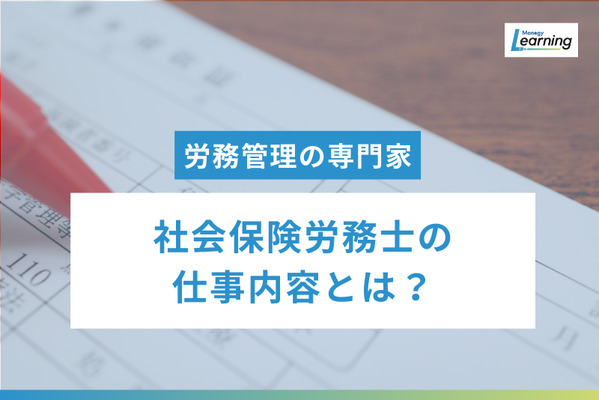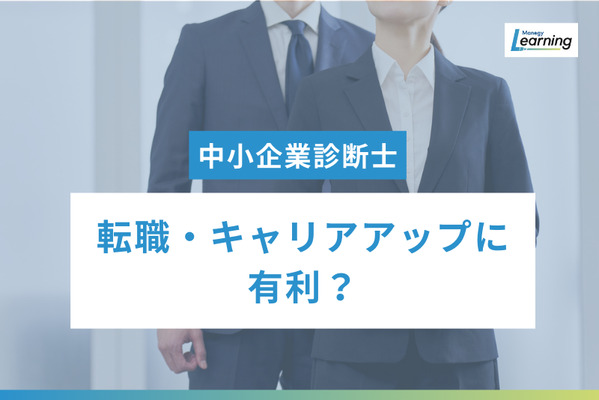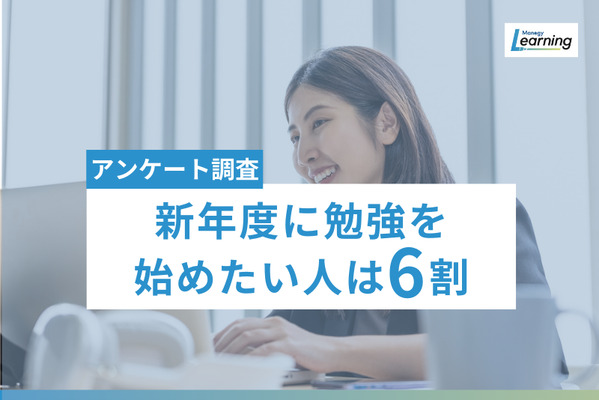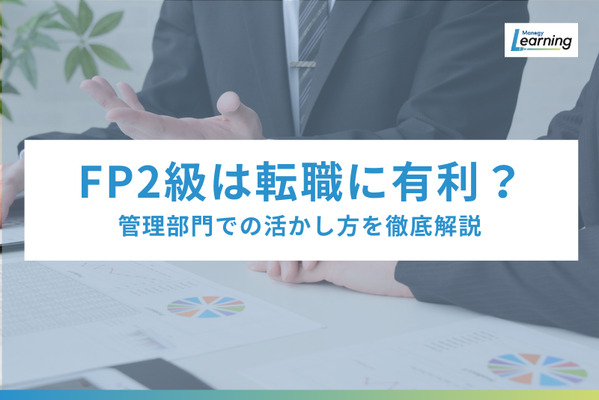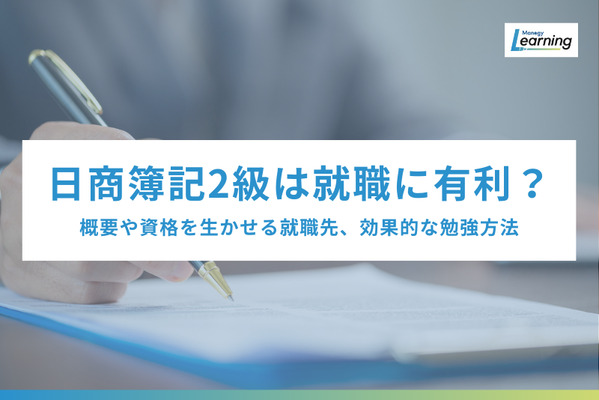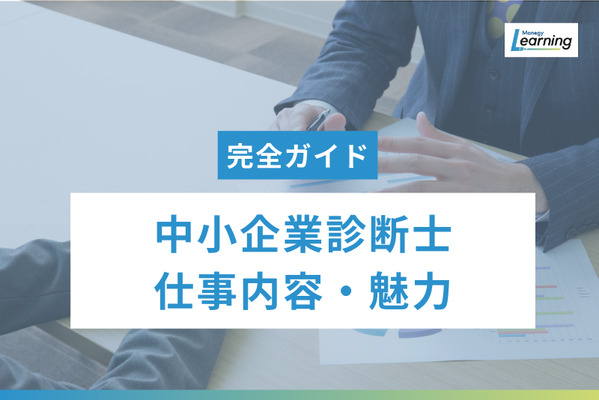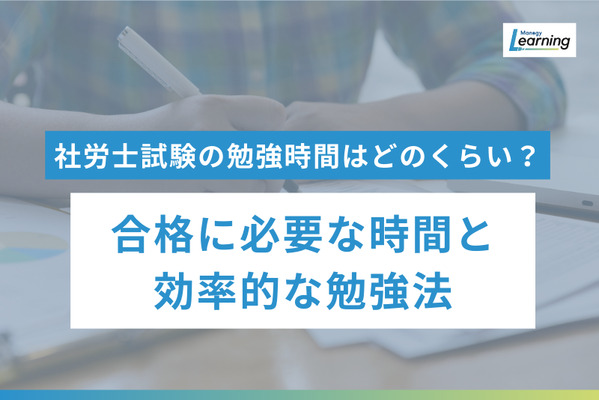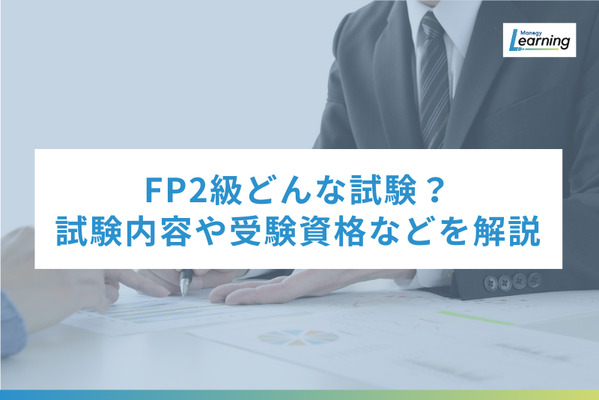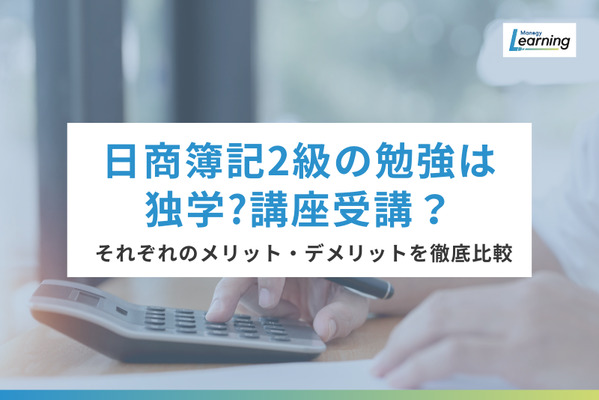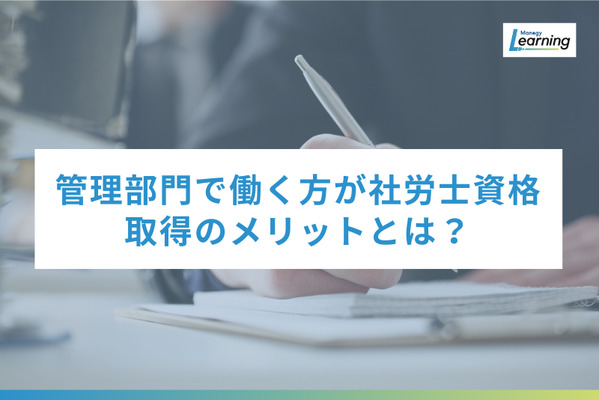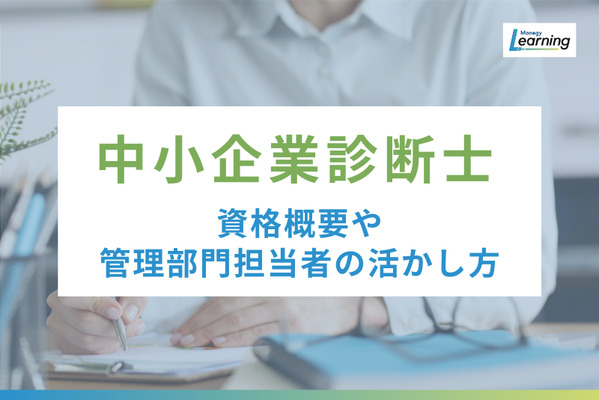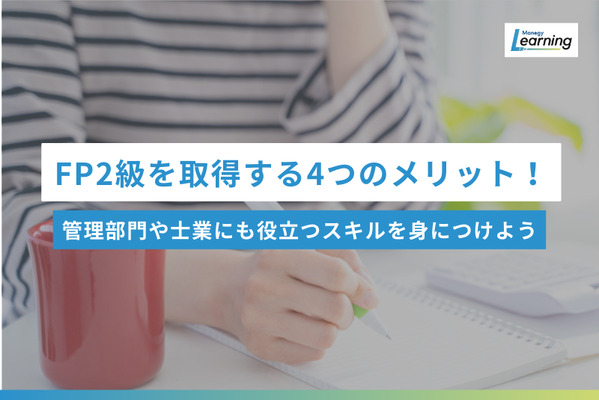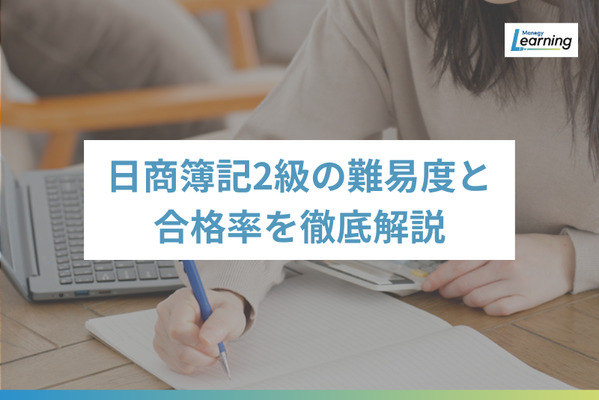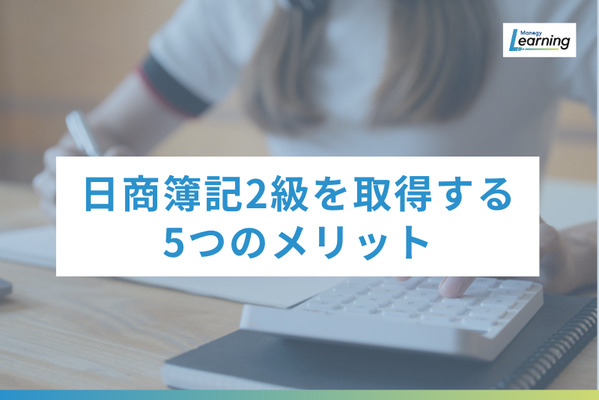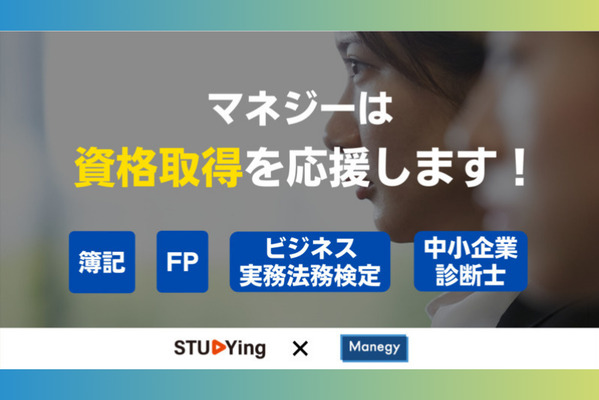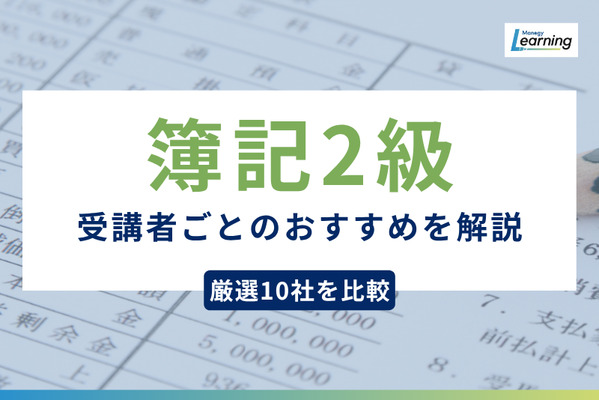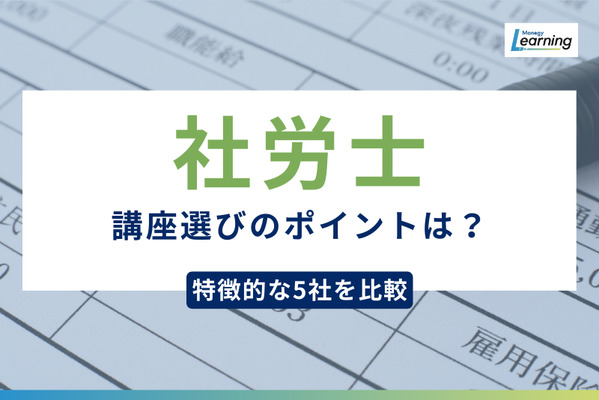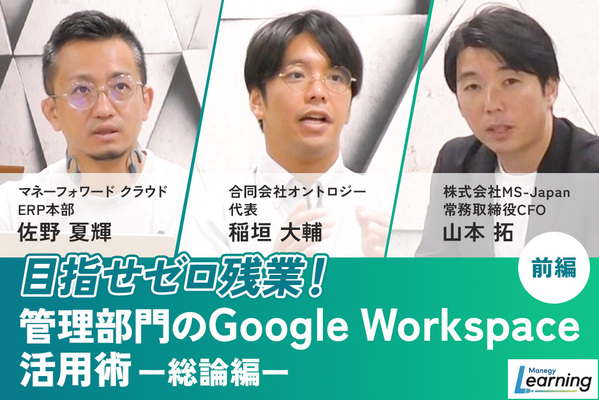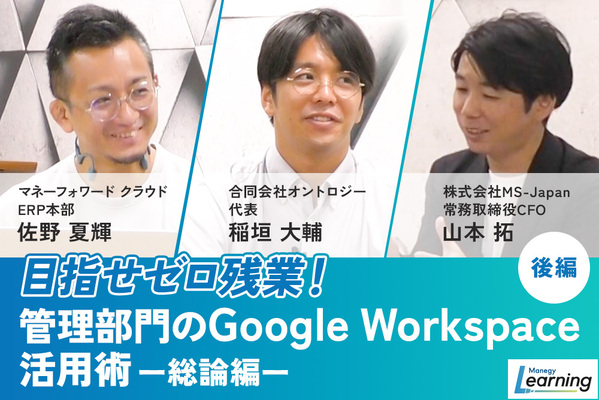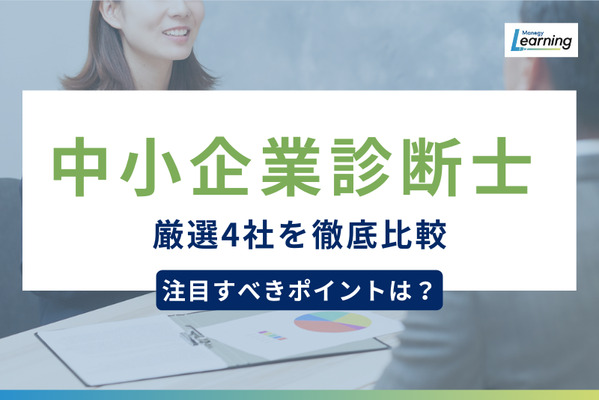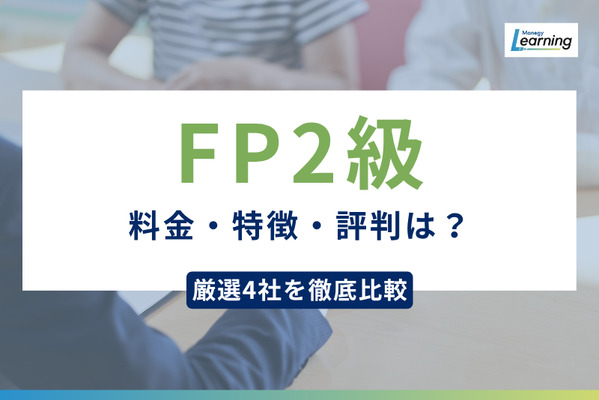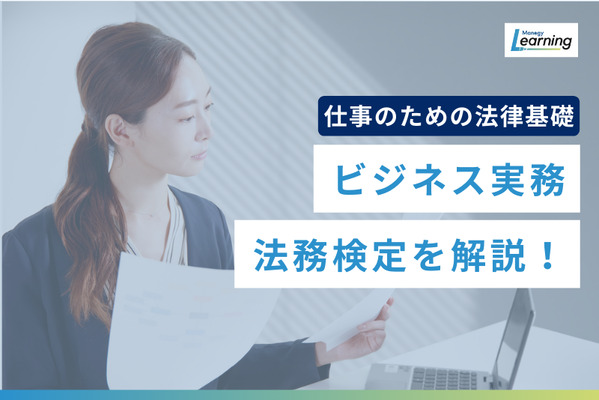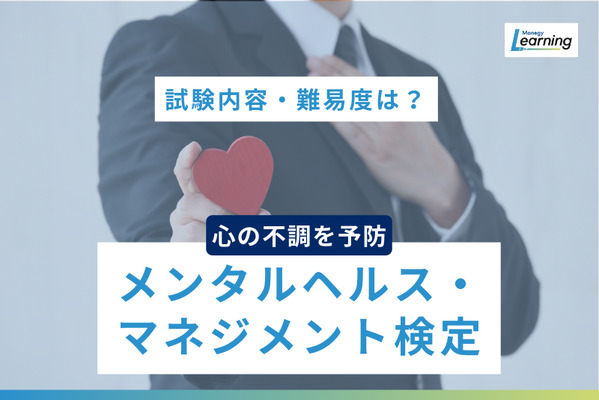中小企業診断士の将来性「役に立たない」は本当?資格を活かすためのポイントを解説!
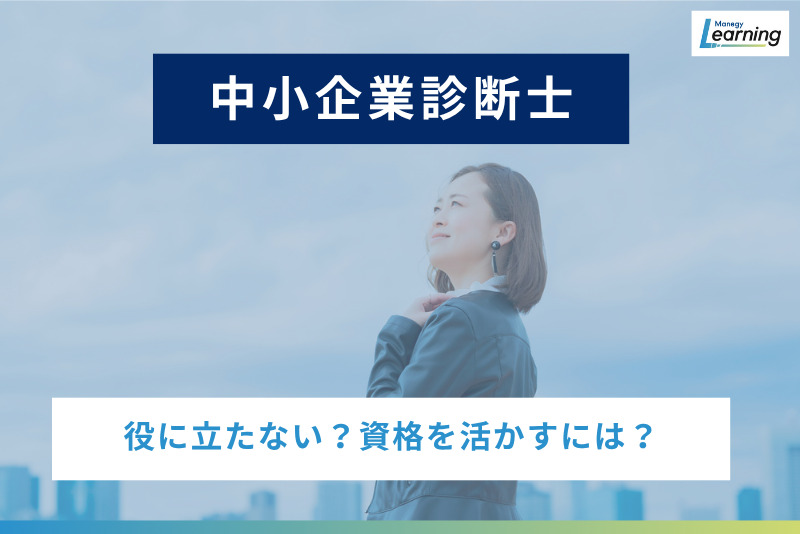
中小企業診断士は、経営コンサルタントの国家資格です。経営課題を分析し、改善提案を行う専門家として、多くの企業や自治体から必要とされています。しかし近年は「将来性がない」「資格だけでは食えない」といった否定的な声も見られます。
なぜ、このような意見があるのでしょうか? 本記事では、中小企業診断士が「役に立たない」と言われる理由を解説するとともに、現役の中小企業診断士の実態や最新の需要動向をもとに、資格の将来性や活かし方について詳しくご紹介します
中小企業診断士が「将来性がない」と言われる理由は?
中小企業診断士は国家資格であるにもかかわらず、「将来性がない」「役に立たない」といった否定的な声が一部であります。その背景には、他の士業と異なる中小企業診断士ならではの事情が関係しています。この章では、なぜそのような声が上がるのか、具体的な理由を解説します。
独占業務がないから
中小企業診断士には「独占業務」がありません。例えば、税理士は税務書類の作成、弁護士は裁判手続きにおける訴訟代理業務、社会保険労務士(以下「社労士」)は労働保険・社会保険に関する書類の作成・提出代行など、法律で定められた独占的な業務があります。しかし、中小企業診断士にはそのような独占業務がなく、経営のアドバイスは無資格者でも行うことは可能です。
このため、「中小企業診断士資格がなくてもコンサルはできる」という認識が広まり、他の士業の資格と比較して、資格の必要性や希少価値が低く見られてしまう傾向があります。
資格だけでは独立が難しいから
中小企業診断士として独立開業し、安定した収入を得るには、資格を取得するだけでは不十分です。
コンサルタントとしての実務経験や専門分野、営業力、人脈、信頼など、総合的なスキルと資源が求められます。
実際、資格取得直後に独立して成功する人は少数派です。多くは企業内での実績を積んだり、支援機関などで経験を重ねたりしたのちに、徐々にクライアントを増やしていきます。そのため、「資格を取っても仕事がない」「活かし方がわからない」と感じる人も少なからずいるのです。
中小企業診断士資格の需要と将来性について
前述のとおり「中小企業診断士は将来性がない」という声はあります。しかし、社会において中小企業を取り巻く環境は日々変化しており、中小企業診断士は経営支援を行う専門家として、その役割がますます求められているのです。ここでは、最新の調査データや政策動向をもとに、資格の需要と今後の展望について具体的に見ていきましょう。
中小企業診断士の調査で6割以上が「需要は伸びる」と回答
一般社団法人 中小企業診断協会が令和3年5月に発表した「中小企業診断士活動状況アンケート調査」によると、中小企業診断士を対象に「今後、中小企業診断士のコンサルティング需要はどうなると思うか?」と尋ねた回答結果は、「伸びると思う」(32.0%)、「徐々に伸びると思う」(29.0%)で、合計61.0%でした。6割以上の中小企業診断士の人々が、今後のコンサルティング需要の増加を見込んでいることがわかります。
現代のビジネス界では、人手不足やデジタル化対応、事業承継など、さまざまな課題に悩む中小企業が多くあります。本調査から、一定数の中小企業診断士が需要を実感していると言えるでしょう。
中小企業診断士資格の今後の需要
コンサル市場(M&A、事業承継など)
近年、国内の中小企業経営者の多くが高齢化しており、事業承継やM&Aの件数が増加しています。経済産業省中小企業庁がまとめた調査によると、2025年までに70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、そのうち約半数の127万人は後継者未定となると推計されています。この後継者不足を支援する専門家が強く求められているのです。
中小企業診断士は、事業評価・財務分析・組織再編などの知識を活かし、M&Aや事業承継の現場で重要な役割を担っています。今後もその需要は増えると言えそうです。
中小企業政策
国や自治体は、中小企業の生産性向上や地域経済の活性化を目的に、補助金・助成金制度を充実させています。例えば、ものづくり補助金や事業再構築補助金などの申請には、事業計画の作成支援が必要です。
こうした支援を行えるのが中小企業診断士です。商工会議所などからもアドバイザーとしての要請があり、官民両方での活躍が期待されています。
DX推進(IT導入など)
中小企業にとってDX(デジタルトランスフォーメーション)は避けて通れない課題です。業務のIT化、データ活用、オンライン販路の構築など、対応すべき分野は広がっています。
中小企業診断士は、経営とITの橋渡し役として、IT導入補助金の活用支援や、業務改善のコンサルティングにおいて、ますます重要な存在となっています。
他士業との違いや強み
企業内診断士と独立診断士 年収やキャリアで有利なのは?
中小企業診断士の資格を取得した後の働き方には、大きく分けて「企業内で活かす」か「独立して活動する」かの2つの道があります。いずれの道にもメリット・デメリットがあり、キャリア形成や収入面での違いもあります。この章では、企業内診断士と独立診断士、それぞれの特徴や年収、活躍するためのポイントについてご紹介します。
企業内診断士のキャリアと年収
中小企業診断士の資格は、企業内でのキャリアアップにも有効です。特に、経営企画など経営陣と距離の近いポジションでの活躍が期待できます。年収においても、資格手当として、給与に反映される場合もあります。
さらに、大企業だけでなく、中堅・中小企業においても「診断士=経営のわかる人材」として重宝されるため、転職市場での評価も高く、キャリア選択の幅が広がるのが特徴です。
この記事を読んだ方にオススメ!
企業内診断士のキャリアと年収
独立診断士の業務は、中小企業の経営支援、補助金申請サポート、事業承継、DX推進など、多岐にわたります。
収入は実力や営業力に左右されますが、なか年収1,000万円以上の独立診断士も珍しくありません。ITや財務など得意分野を作り、他の診断士との差別化をはかることで、高単価の案件を獲得できる可能性が広がります。
一方で、独立診断士は営業や契約、実務すべてを自分でこなさなければならないため、独立後すぐに安定収入を得るのは難しい面もあります。副業として診断士活動を行いながら、徐々に実績を積んで独立するという戦略が現実的です。
AI時代に中小企業診断士の仕事はなくなる?
AIやデジタル技術の進化によって、さまざまな職業が自動化されると言われる時代。中小企業診断士も「AIに代替されるのでは?」という声があります。では、実際に中小企業診断士の仕事はAIに奪われるのでしょうか?
AIの得意分野と人間ならではの役割を比較しながら、これからの時代に求められる中小企業診断士のあり方について解説します。
中小企業診断士の業務でAIができること
AIの進化によって、経営状況分析や定型的な報告書の作成など、一部の業務は自動化されつつあります。特に、数字を扱う部分や過去データの分析は、AIの得意分野です。
将来的には、基本的な財務分析や経営データの可視化といった業務はAIが担い、中小企業診断士の関与が減る部分も出てくるでしょう。
中小企業診断士の業務で人間しかできないこと
一方で、AIにはできない業務も数多く存在します。例えば、クライアント企業の経営者との対話を通じて課題の本質を見抜いたり、従業員の気持ちや社内の空気感を読み取ったりといった経験に基づく洞察は、人間しかできません。
また、クライアント企業の課題に向けた施策を提案するには、その企業の経営者の価値観や組織の文化、業界特性を理解したうえでの柔軟な判断が必要です。こうした、人間ならではの洞察力と判断力が、中小企業診断士の大きな強みです。
AIを活用するために必要なこと
中小企業診断士は、AIに仕事を奪われるのではなく、「AIを使いこなす立場」になることが求められます。AIを使った業務効率化提案や、データに基づく戦略立案など、AIと人間の役割分担をうまく活かすことで、より高度なコンサルティングが可能になります。今後は「AI×中小企業診断士」という新たな価値提供が、自身の将来性を高める鍵となるでしょう。
中小企業診断士の将来性を高めるスキルと戦略
資格を取得しただけでは、中小企業診断士としてのキャリアを成功させることはできません。継続的なスキルアップと、市場の変化に対応できる柔軟な戦略が欠かせないのです。ここでは、将来性をより高めるために有利となるスキルや資格、さらには他士業との差別化を図るための戦略について、具体的に解説していきます。
有利なスキル
IT
業務効率化ツールの導入支援や、IT導入補助金の活用サポートなど、中小企業診断士の現場ではITリテラシーが求められています。
財務
財務分析を活用してクライアント企業の課題や問題点を洗い出し、改善提案を行うことは、経営支援の基本です。そのため、財務に関する知見が必要になります。
人事
働き方改革や人手不足、離職率改善など、人的課題への対応はどの企業でも重要です。人事制度の設計や人材育成の支援ができると、業務上で有利です。
マーケティング
販路開拓やブランド戦略の支援など、売上向上に直接関わるマーケティングスキルは、企業にとって価値のある支援となります。
将来性を高めるヒント
市場の変化に柔軟に対応できる力が必要です。特定の業種に特化する、地方の中小企業支援に強くなる、行政との連携を活かすなど、自分の「強み」と「ポジション」を明確にすることが重要です。
また、他業界とのネットワーク形成も有効です。異業種経験者と交流を深めることで、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性もあります。ほか、SNSやブログなどを通じて情報発信することも、今後は必要な戦略のひとつとなるでしょう。
まとめ|中小企業診断士は将来性のある資格として有望
中小企業診断士には「独占業務がない」「資格を取得するだけでは独立が難しい」といった指摘がある一方で、事業承継・M&A・DX支援・補助金活用など、資格を活かせるフィールドは年々広がっています。現役の中小企業診断士からは「将来性がある」「やりがいが大きい」といった声が多く、今後も企業のパートナーとして重要な存在であり続けるでしょう。
資格を取っただけで終わりではなく、実務経験やスキルを重ねることで、時代のニーズに応じて自分自身を進化させていくことができます。中小企業診断士の資格に興味がある人は、ぜひ取得を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事を読んだ方にオススメ!
中小企業診断士の資格を生かせる求人例
戦略コンサルティング<ヘルスケア領域>
- 仕事内容
- 主な業務内容は以下の通りです。
・経営戦略/事業戦略策定支援、事業計画の策定支援
・経営改善および効率化に向けての業務分析、プロジェクトマネジメント等
・M&Aや再編・再生における支援
・医療機関の建替え等に関連しての戦略立案等
・医療政策に関する調査、その他海外市場進出に関するリサーチ業務等
- 必要な経験・資格
-
【必須】※以下のいずれかの経験
1)経営に関する意思決定に影響を及ぼした経験のある方
2)複雑なプロジェクトマネジメントを実施した経験がある方
3)医療経営に関する知見をお持ちの方
4)上記に類する程度の経営に関する基本的知識を有している方
- 想定年収
- 500万円 ~ 800万円
経営コンサルタント(仙台オフィス)
- 仕事内容
- 会計/財務/成長戦略/事業再生など、経営に関わるコンサル業務全般をお任せします。
- 必要な経験・資格
-
■必須スキル:
基本的なPCスキル(Excel/Word/ppt)
経営企画/営業企画/税理士/公認会計士など数字を扱う業務経験をお持ちの方■歓迎スキル:
・中小企業診断士
・MBAをお持ちの方
- 想定年収
- 500万円 ~ 700万円
経営コンサルタント【ポテンシャル】
- 仕事内容
具体的には以下の業務を行います。
・企業再編支援・企業再生支援
・M&A/MBO(FA業務、デューデリジェンス、PMI)支援
・経営計画策定支援・業績管理制度構築・資金繰り安定化サポート
・株式公開支援
・経営顧問業務 等
- 必要な経験・資格
-
【必要な能力・経験など】
・コミュニケーション能力、論理的思考能力
・PCスキル(ワード、エクセル、パワーポイントの基本操作)
・日商簿記2級相当の会計知識【推奨応募資格】
公認会計士/中小企業診断士/税理士/日商簿記検定1級
- 想定年収
- 440万円 ~ 670万円

Manegy Learning
Manegy Learningは管理部門・士業の皆さまに向けて、実務に役立つTIPSや資格取得のためのスクール取得などの情報を発信し、みなさまの学びをサポートします。
MS-Japan
https://www.manegy.com/learning/