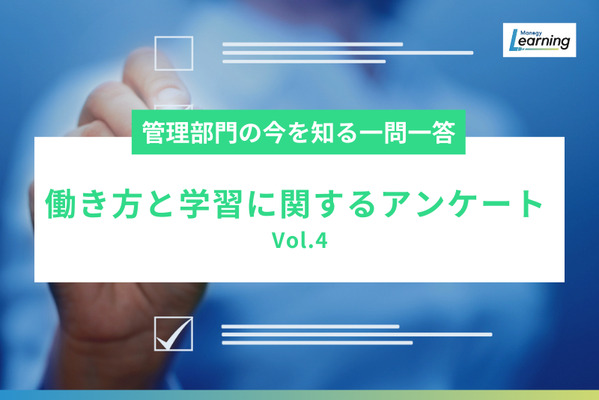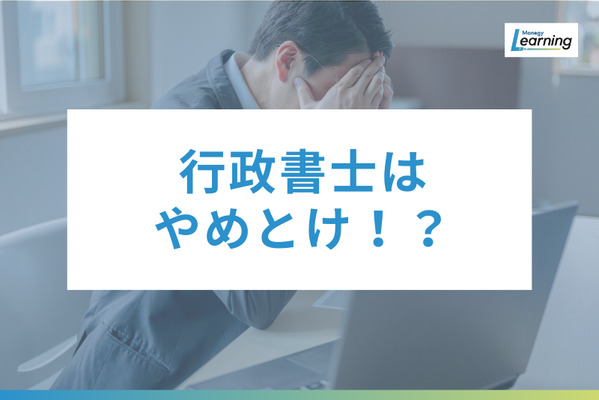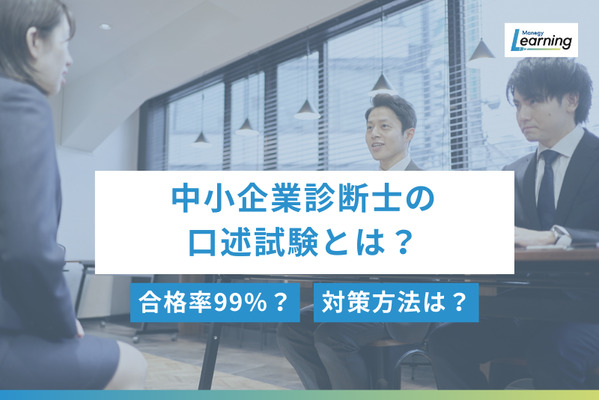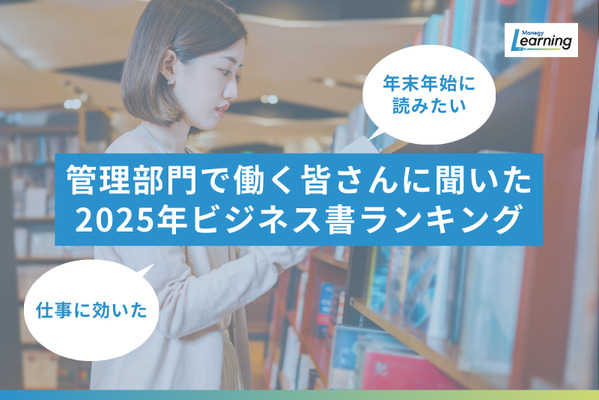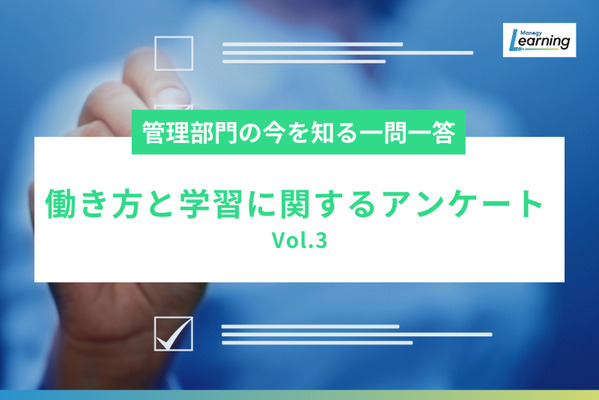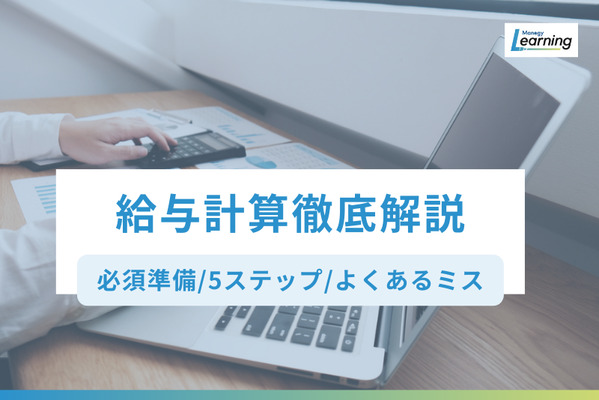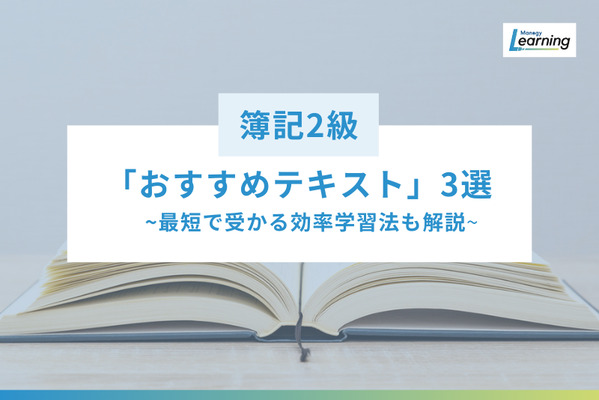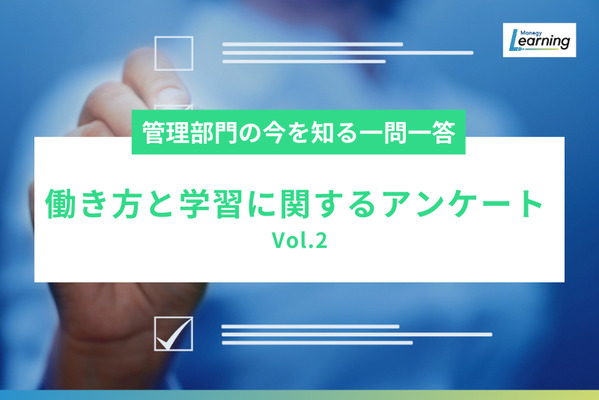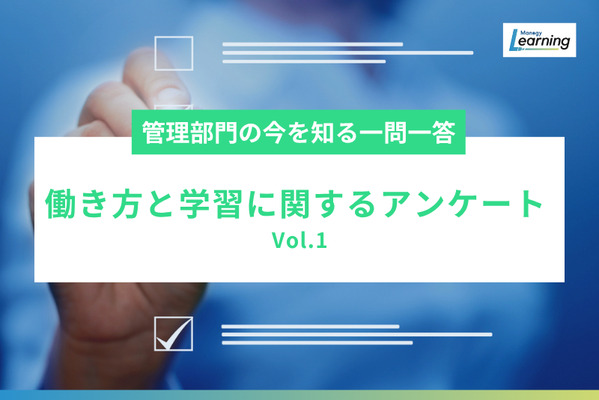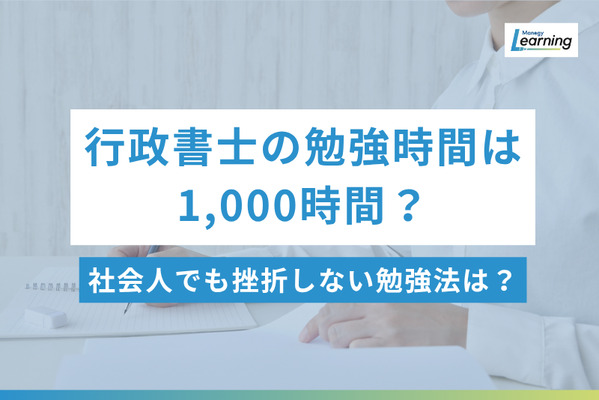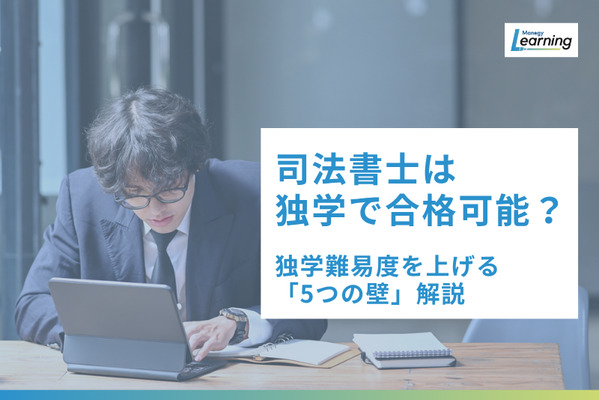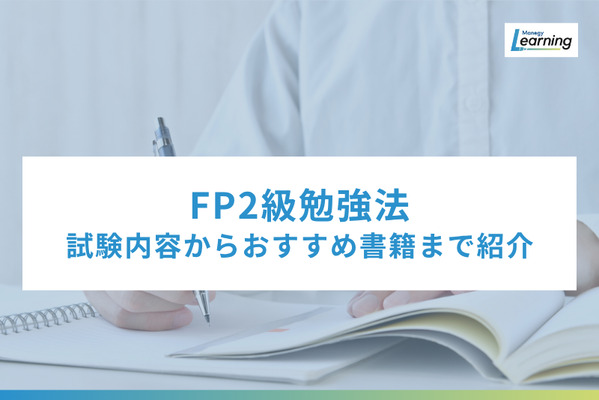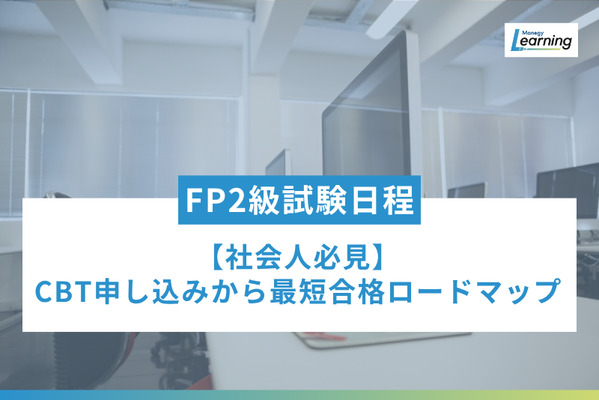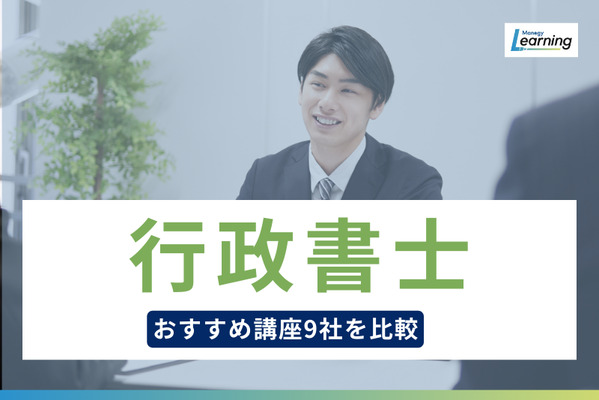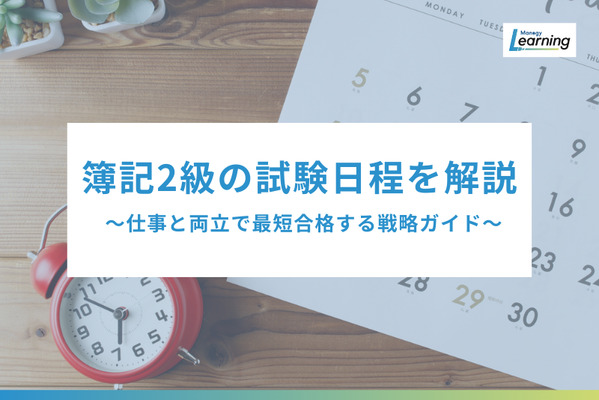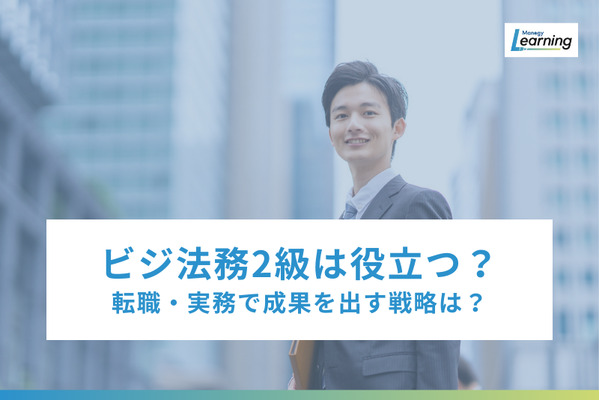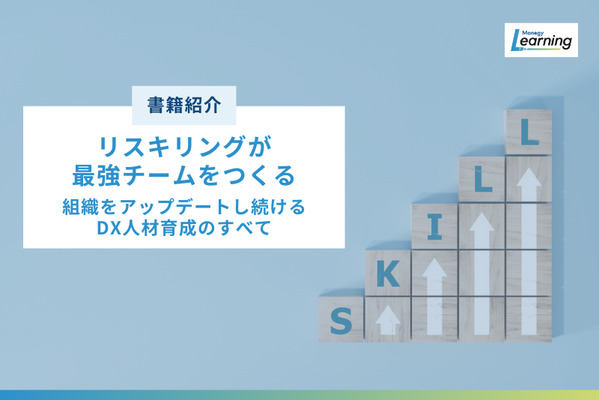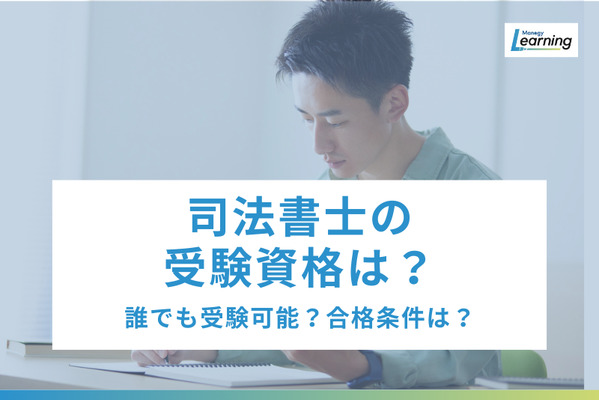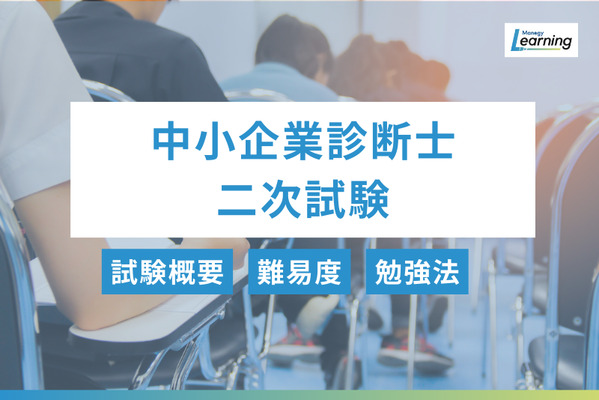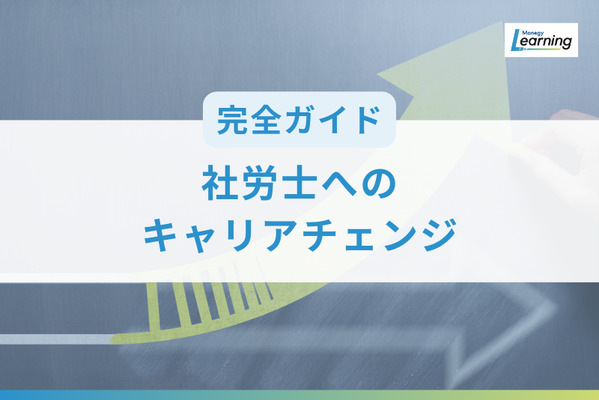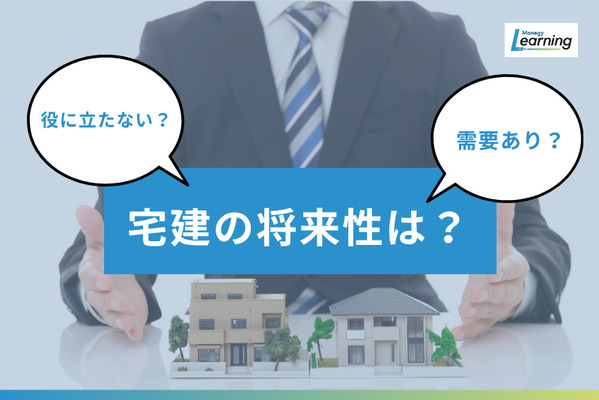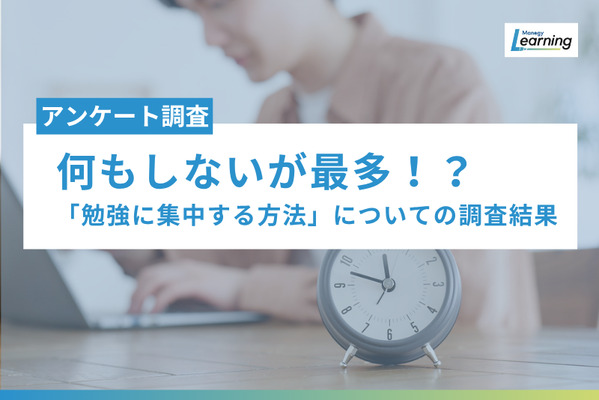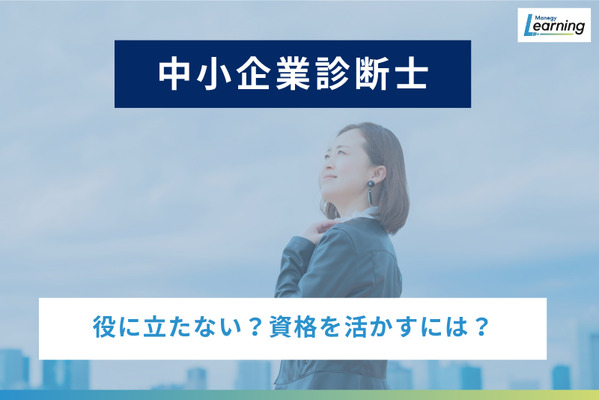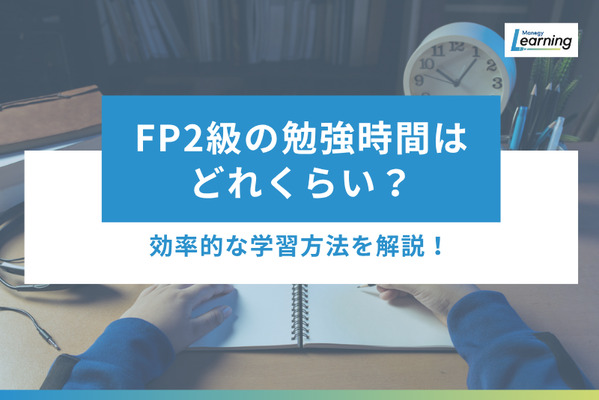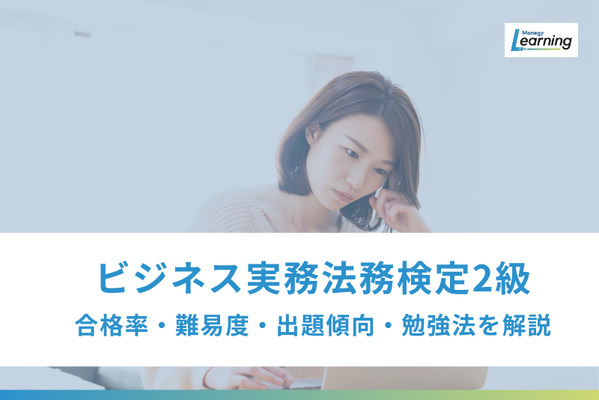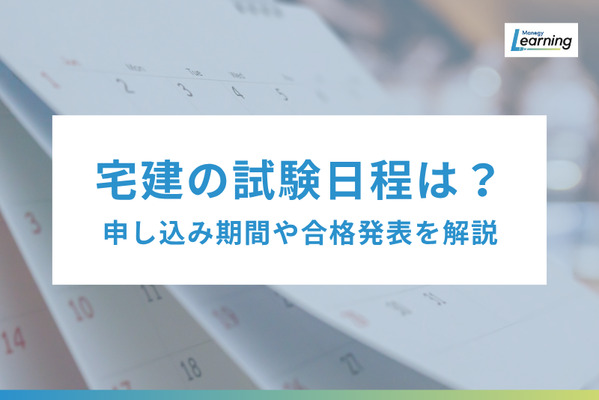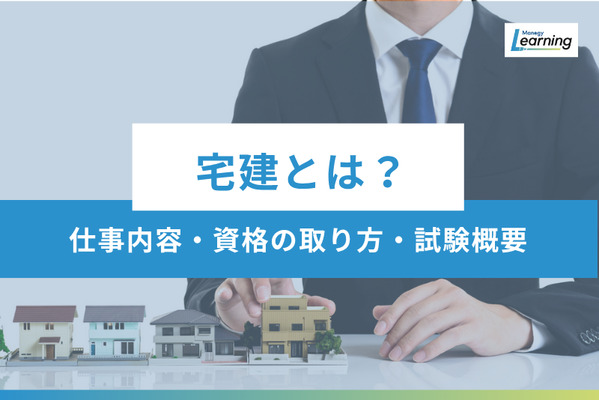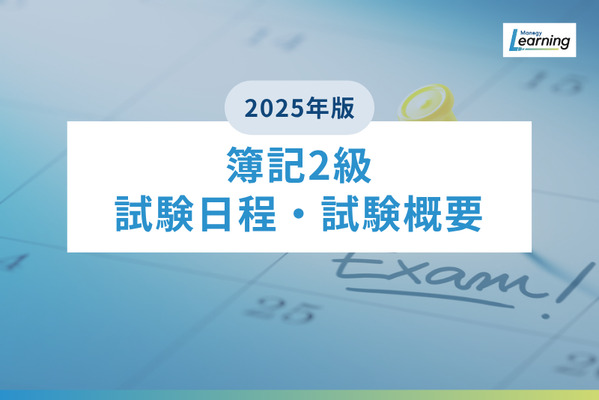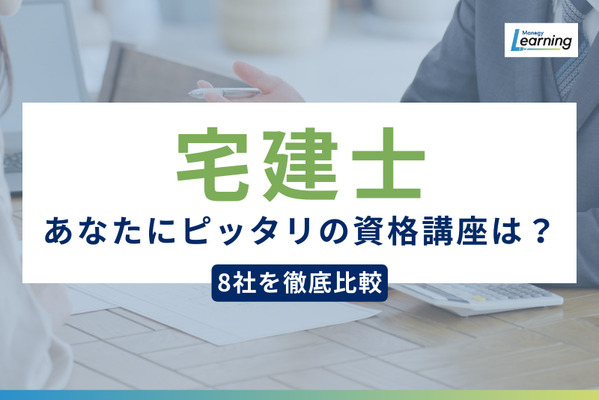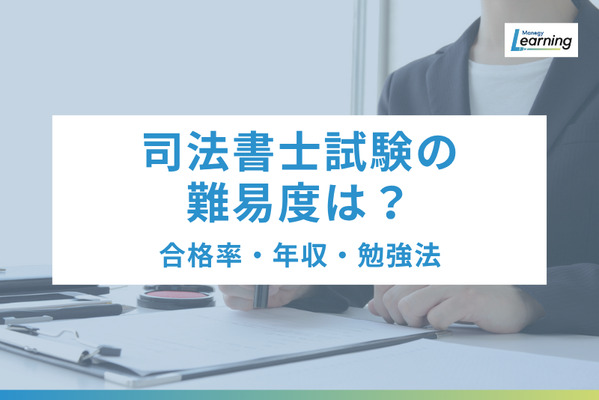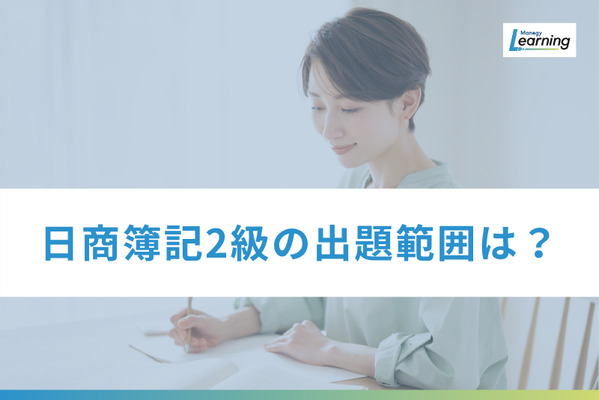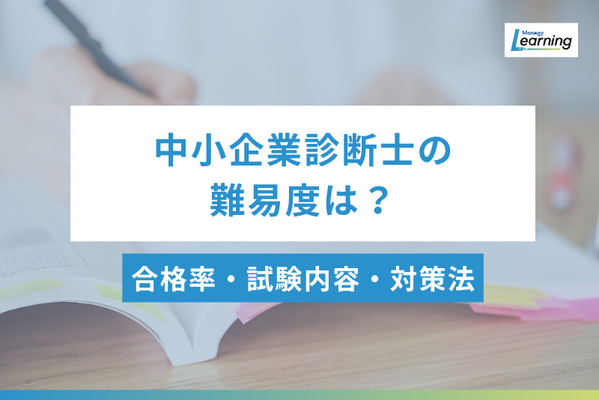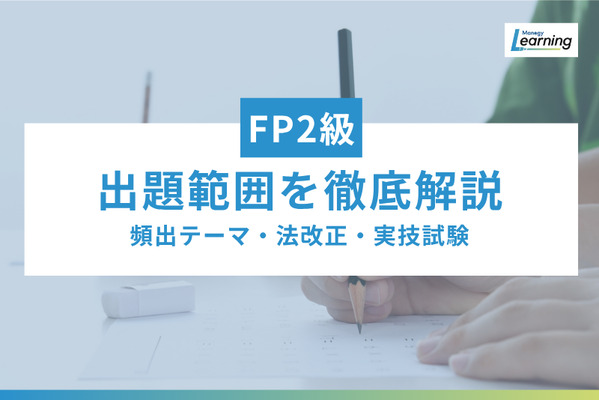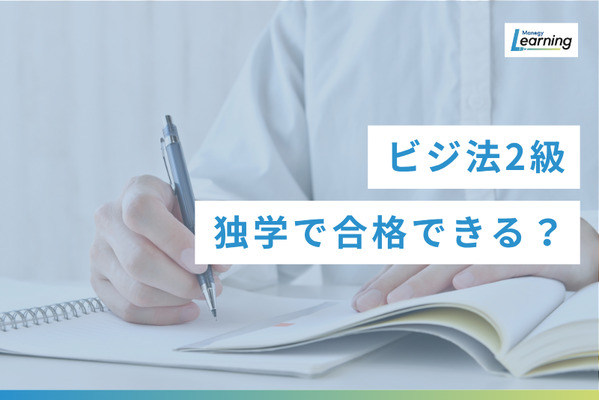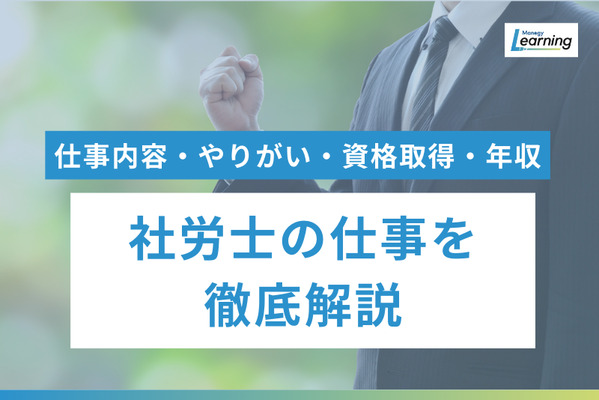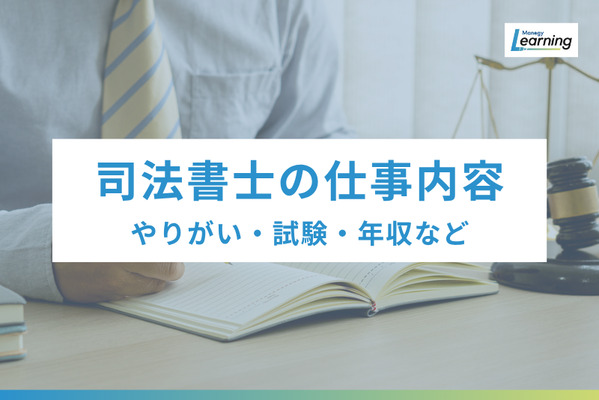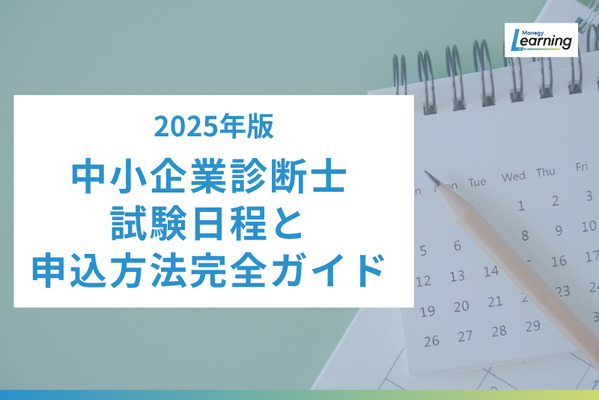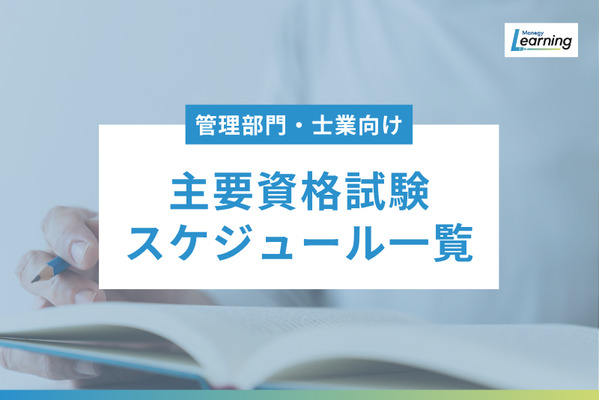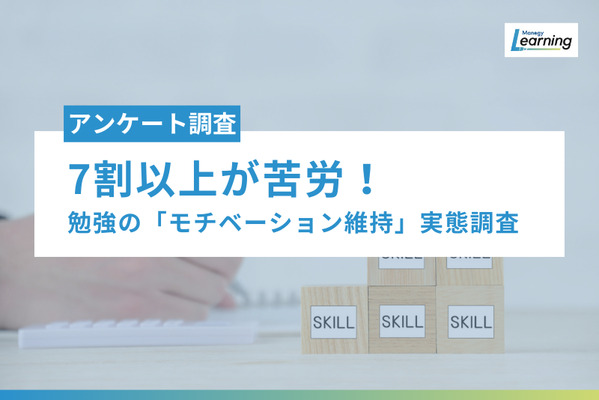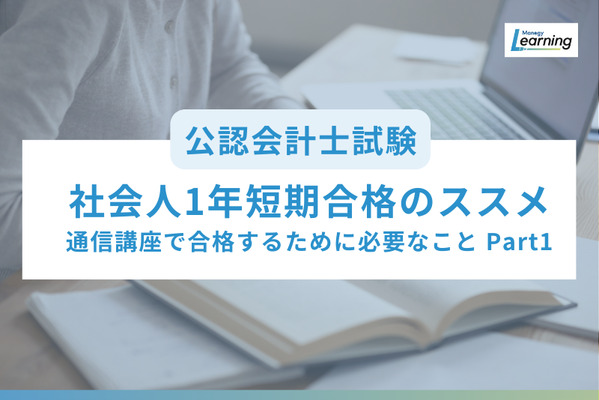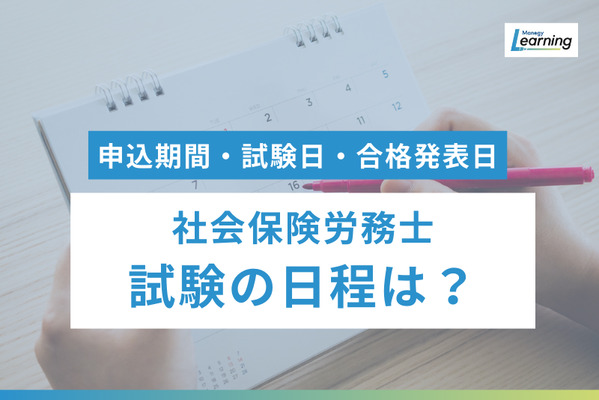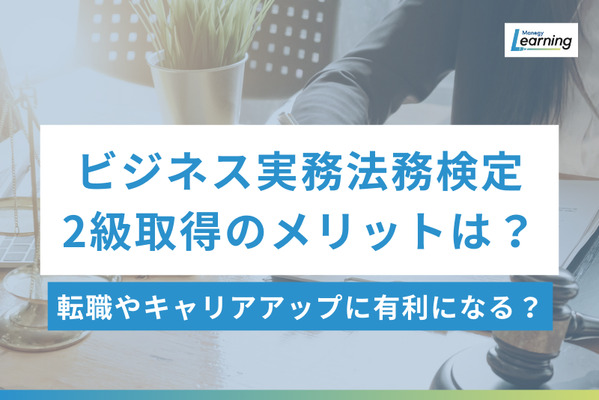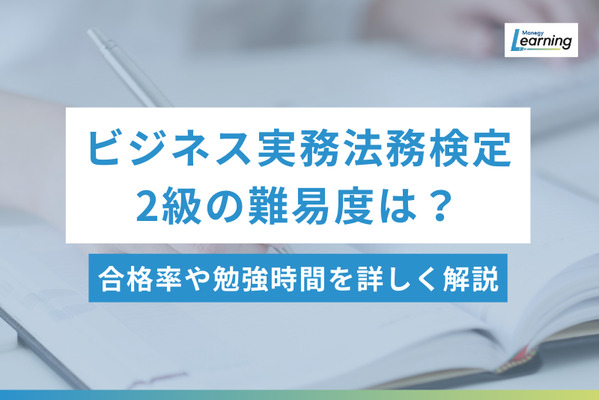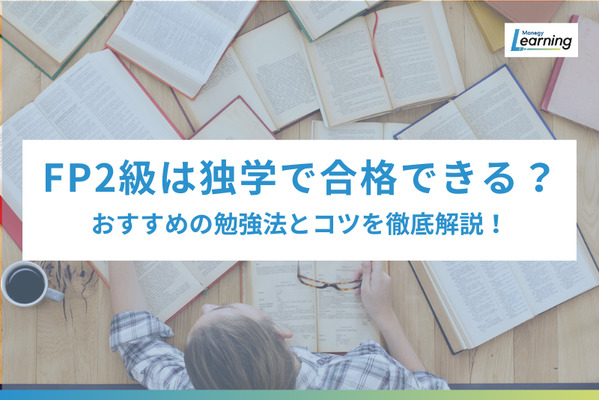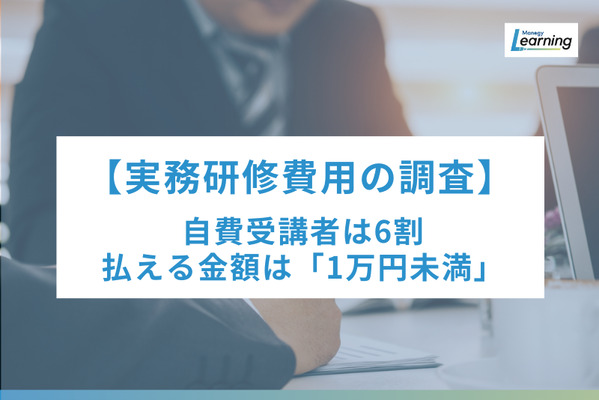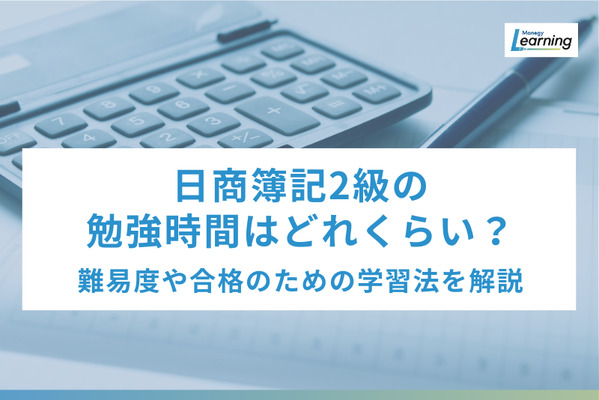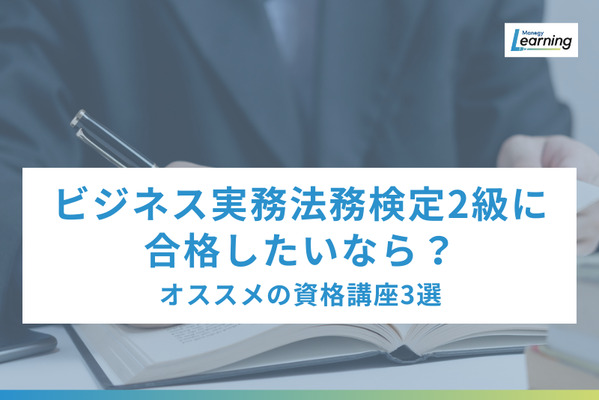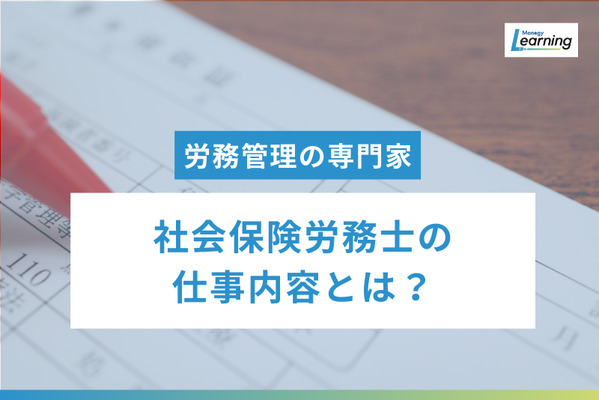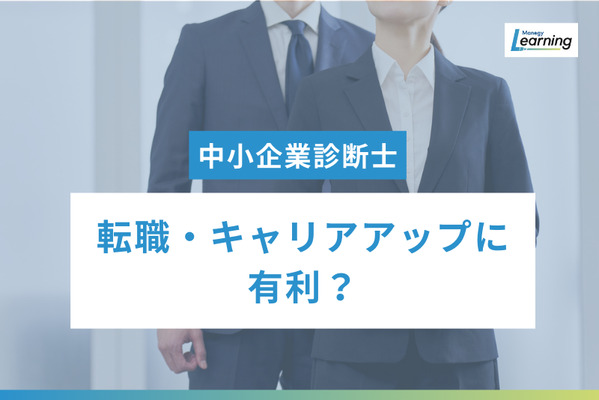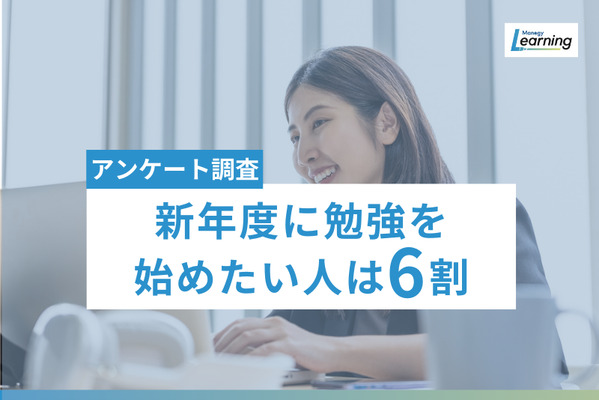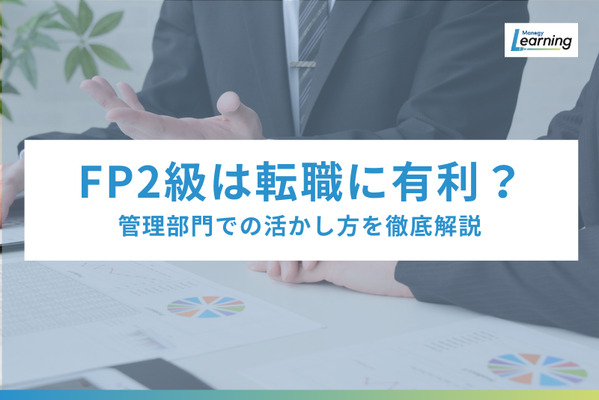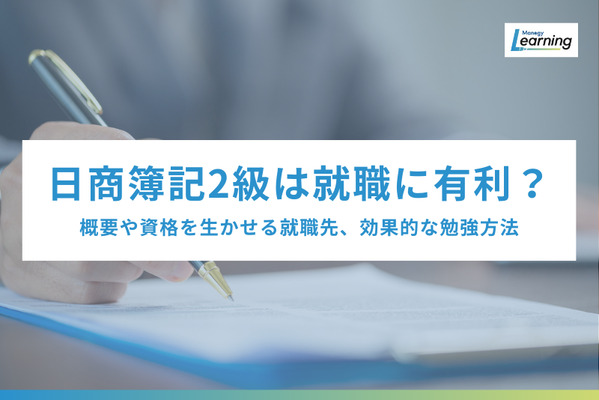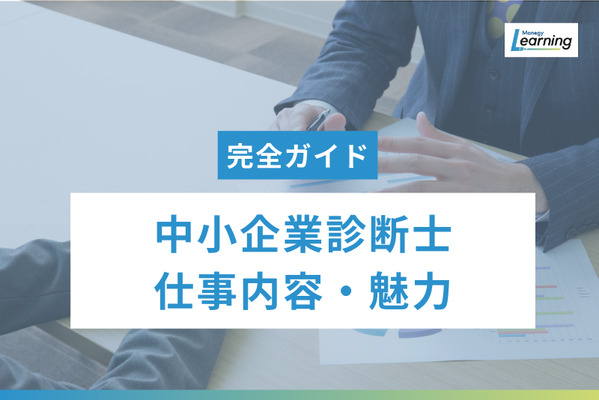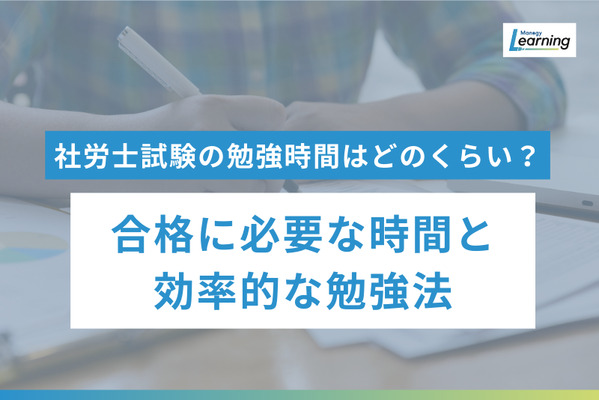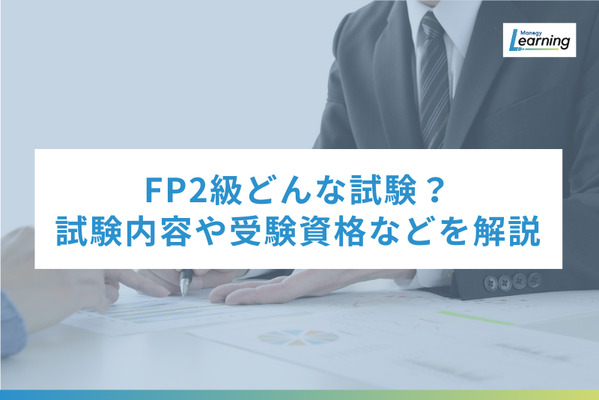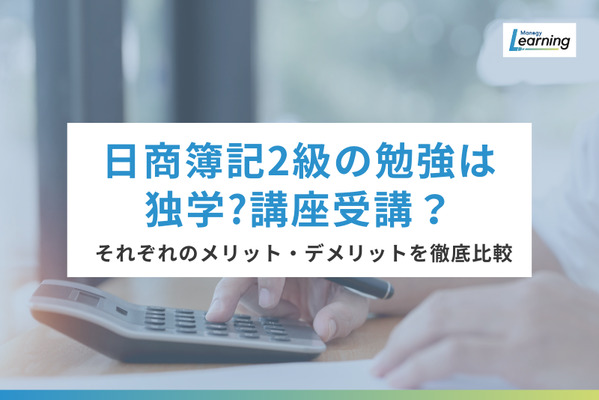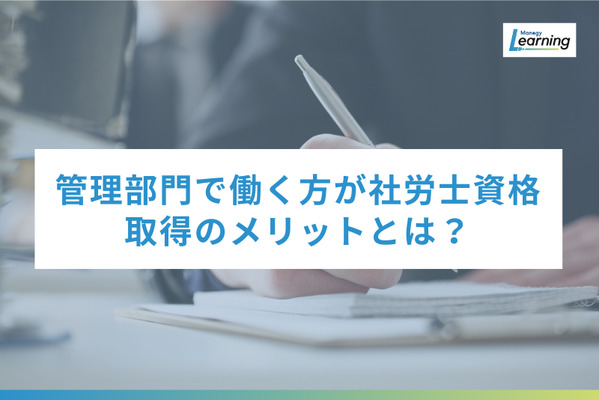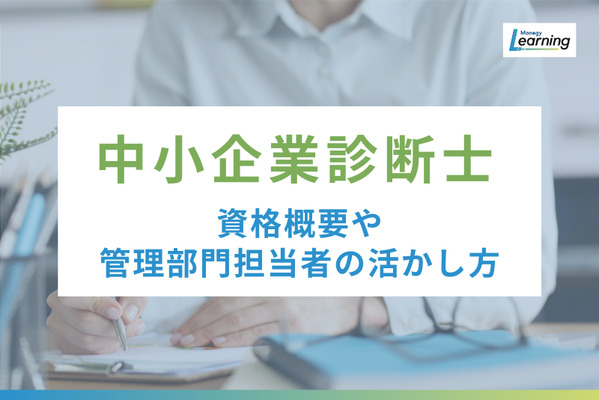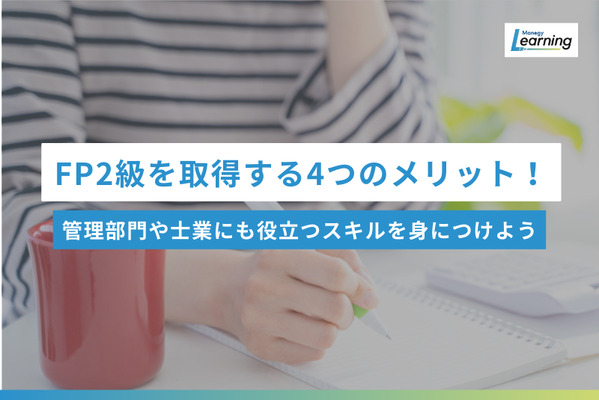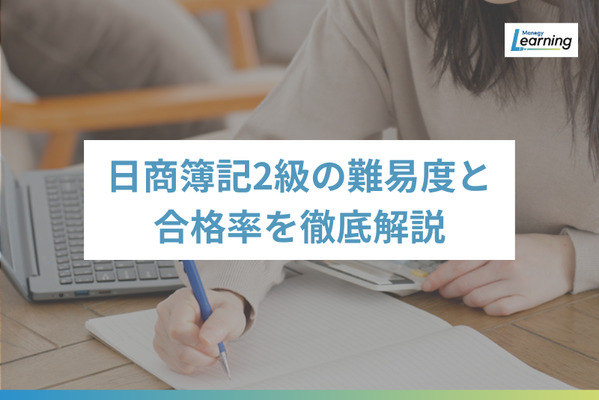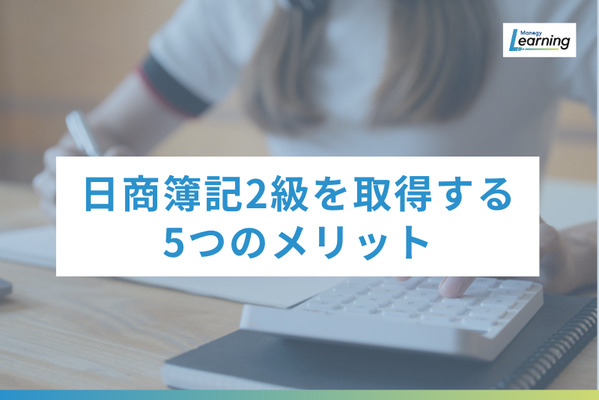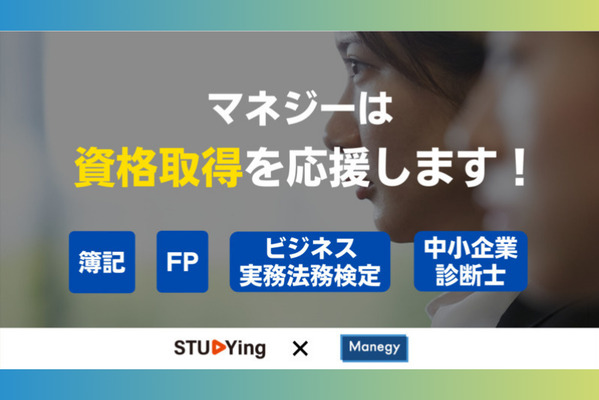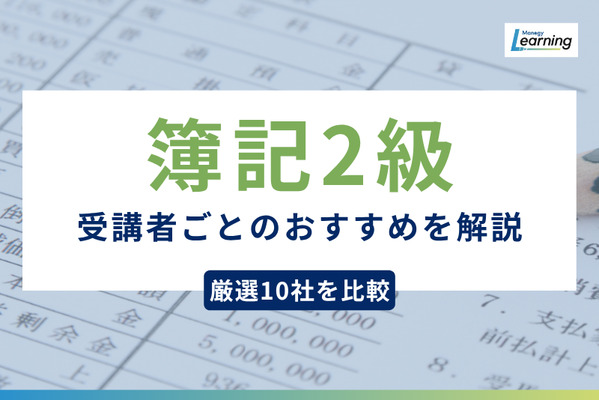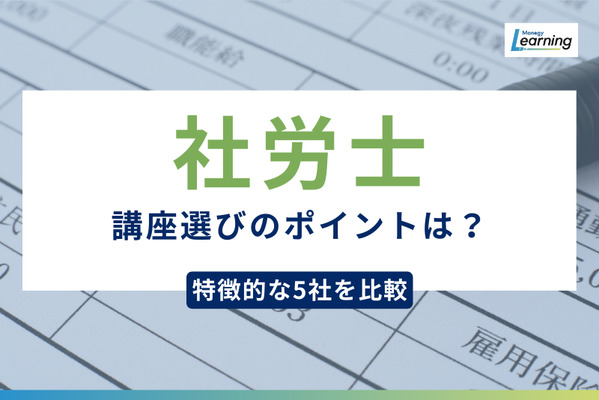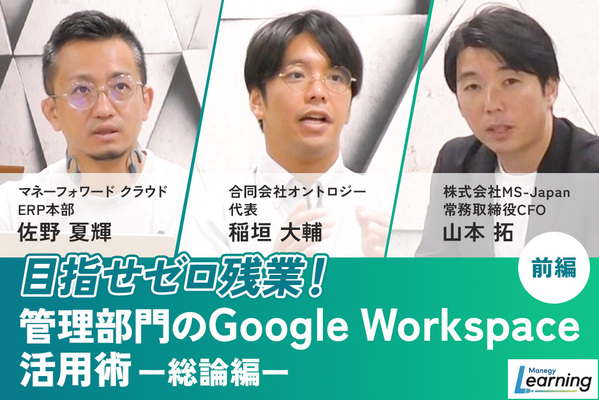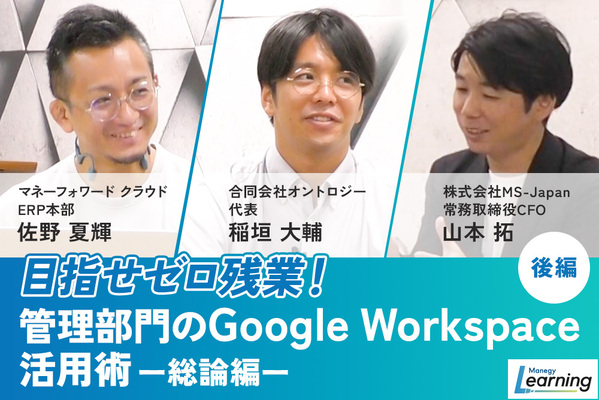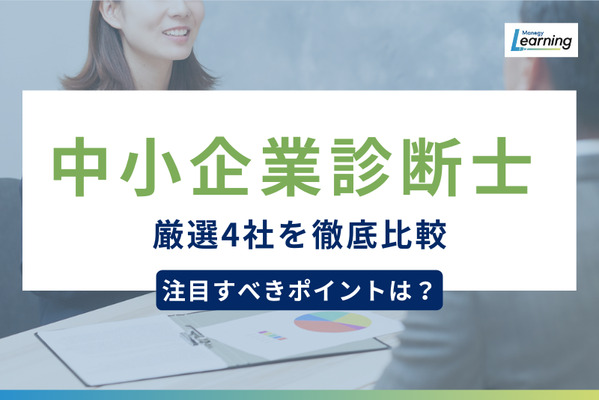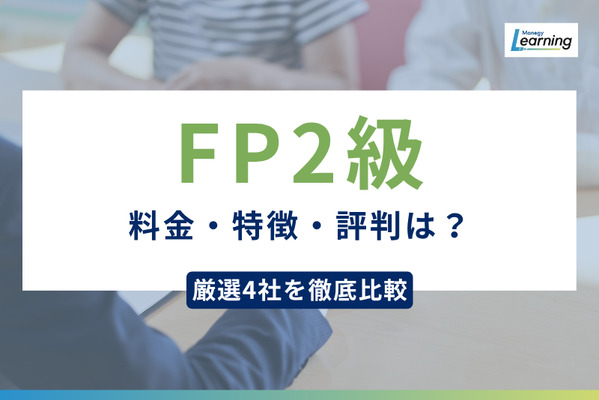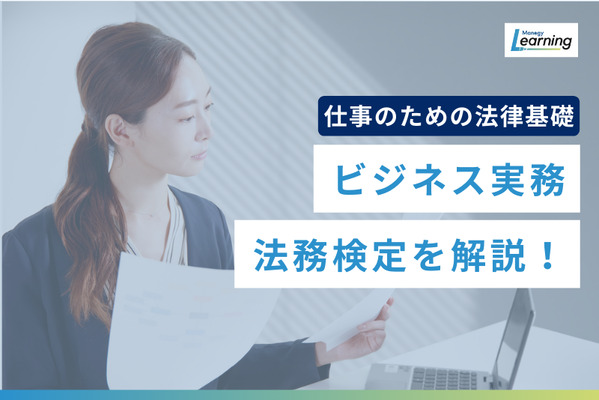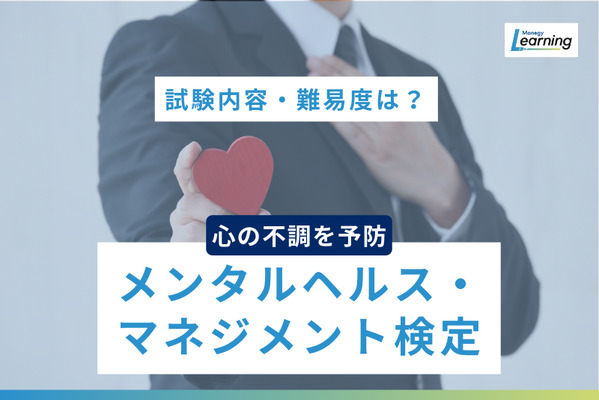ビジ法2級合格のための勉強時間は?効率的な勉強方法を徹底解説!
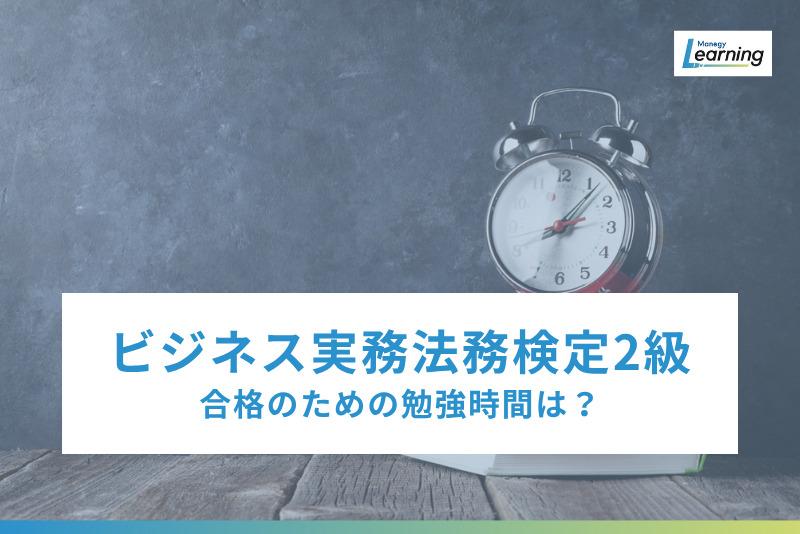
本記事にはPRおよびアフィリエイトリンクが含まれています。
ビジネス実務法務検定(ビジ法)は、東京商工会議所が主催する、企業で働く人のための法律知識を問う民間資格です。なかでも2級は、企業取引の法務や債権の管理と回収、企業財産の管理・活用など、実務に直結する分野の理解が求められるため、「業務に活かしたい」「キャリアアップを目指したい」といった目的を持った受験者も少なくありません。
ただし、合格を目指すには計画的な勉強が欠かせません。特に、社会人は時間が限られているため、効率よく勉強することが大切です。そこで本記事では、タイプ別の勉強時間の目安や勉強スケジュール、独学・講座の選び方、教材の選定法などをわかりやすく解説します。
ビジネス実務法務検定2級合格に必要な勉強時間は?何時間かかる?
ビジ法2級の合格に必要な勉強時間は、受験者自身の法律知識や実務経験の有無によって大きく異なります。一般的には、60~90時間が目安とされています。
とはいえ、これはあくまで平均値であり、「法律を初めて勉強する人」「大学の法学部出身者」「法務実務経験者」など、受験者の経験値によって適切な勉強時間や進め方が変わってきます。以下、それぞれ見ていきましょう。
法律初学者の場合
これまで法律に触れた経験がない人は、まず法律用語の理解に時間がかかる傾向があります。そのため、最初はテキストをじっくり読み込んで、用語や全体像を把握するところから始めるのが効果的です。前述で「勉強時間は60~90時間が目安」と紹介しましたが、これは法学部出身者や法務部勤務経験者も含めた時間です。法律の知識が全くない場合は、100時間以上かかる可能性もあります。
最初の1~2ヵ月はインプットに集中し、その後は過去問や演習問題で知識の定着を図ると良いでしょう。事例形式の問題に慣れるためには、何度も反復練習をすることが大切です。
法学部出身者の場合
法学部である程度法律を学んできた人は、法律の概念の理解や条文の読解に対して抵抗が少ないはずです。その分、学びやすく、法律初学者よりも勉強時間はやや少なめでも合格を狙えるでしょう。勉強方法は過去問演習を中心としたアウトプットを重点的に取り組むとよいでしょう。
法務部勤務経験者の場合
企業法務に携わっている人は、日々の業務と試験範囲が重なる部分が多いため抵抗なく学ぶことができるでしょう。法律初学者に比べて勉強時間は短く済み、比較的スムーズに進められるでしょう。とはいえ、試験には法律の理論的な知識や体系的な理解も必要なので、油断は禁物です。
日頃の実務を活かしながら問題演習を重ねることで、実戦力を身につけられます。
ビジ法2級の試験の難易度と出題傾向や出題範囲は?
この項では、ビジ法2級の試験の合格率と出題傾向、出題範囲などについてご説明します。
合格率からわかる難易度
ビジ法2級の合格率は実施回によってばらつきがありますが、おおむね30~40%の範囲に収まっています。第56回(2024年)の合格率は41.9%でした(出典:東京商工会議所 公式サイト)。合格率が4割程度ということを踏まえると、しっかりとした準備が求められます。
| 試験回 | 実受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第53回(2023年) | 5,218 | 1,523 | 29.2% |
| 第54回(2023年) | 6,351 | 2,455 | 38.7% |
| 第55回(2024年) | 5,454 | 1,828 | 33.5% |
| 第56回(2024年) | 6,586 | 2,759 | 41.9% |
試験方式と出題形式
ビジ法2級の試験方式はIBT方式とCBT方式の2種類から選べます。IBT方式は、受験者自身のパソコン・インターネット環境を利用して受験する試験方式です。一方、CBT方式は各地のテストセンターに来場して、備え付けのパソコンで受験します。
ビジ法2級は全問多肢選択式で構成され、記述問題はありません。実際のビジネス現場を想定した事例問題や、法律実務の応用問題が出題されます。
出題範囲と合格基準について
東京商工会議所の公式サイトには、ビジ法2級の基準について「企業活動の実務経験があり、弁護士などの外部専門家に対する相談といった一定の対応ができるなど、質的・量的に法律実務知識を有している(知識レベルのアッパーレベルを想定)」と記載されています。また、出題範囲は「3級の範囲および2級公式テキスト(2025年度版)の基礎知識と、それを理解した上での応用力」とあり、合格基準は「100点満点中70点以上」となっています。
つまり、2級公式テキストの内容を着実に学び、基礎はもちろん、実務に即した応用問題を解けるようにしておくのが理想です。
【タイプ別】忙しい人が効率的に勉強できるスケジュール3パターン
忙しい社会人にとって、勉強時間の確保は資格取得の課題のひとつです。ここでは、勉強時間および期間を3パターンに分けて、進め方をご提案します。
パターン① 平日特化型(3ヵ月程度)
平日に1日1時間程度時間を確保できる人に適した勉強スタイルです。平日に集中して進めることで、土日はしっかりリフレッシュできます。スケジュールモデルとしては、以下のように、基礎固め→問題演習→総合力チェックと苦手つぶしといった流れで学習を進めることをおすすめします。
1ヵ月目:テキストを読み進めながら基礎固めをする。
2ヵ月目:過去問を分野ごとに解き、出題傾向をつかむ。
3ヵ月目:模試形式で総合力をチェックし、苦手分野を重点的に復習する。
出社前や帰宅後など、平日の生活サイクルに1時間程度学ぶことで、勉強を習慣化できるのがポイントです。
パターン② 毎日コツコツ型(4〜6ヵ月程度)
通勤時間や家事の合間など、1日30分ずつを積み重ねる勉強スタイルです。スキマ時間で30分確保すればよいのでハードルが低く、生活のリズムに合わせれば長期的に継続しやすいのが特長です。まとまった時間をとりにくい多忙な人は、できる範囲で勉強時間を作ることで挫折しにくくなります。
勉強の進め方は、まず前半はインプット中心でテキストを少しずつ読み進めます。2~3ヵ月目以降は問題演習を始め、徐々にアウトプットに比重を移しましょう。
パターン③ 短期集中型(1ヵ月~1.5ヵ月程度)
「期間限定でしっかり勉強し、なるべく早く合格したい」という人は、短期集中型で臨むのがぴったりです。例えば、平日に2時間、休日に5時間程度の勉強をすれば、週20時間の勉強時間を確保できます。これを続けられれば1ヵ月~1.5ヵ月で合格圏内に到達可能です。
勉強は、最初の1週間でテキスト全体を読み、2週目からは本格的に過去問演習、最終週で模試形式の総仕上げを行います。短期間で一気に学ぶため、集中力の高い状態を保ちやすいことも利点です。
独学と講座、どちらが自分に合っている?
ビジ法2級の勉強方法は、テキストや無料動画などを使って自分で勉強していく独学スタイルと、通信・通学講座などを活用するスタイルのどちらかから選べます。ここでは、独学と講座のそれぞれの特徴をご説明します。
独学が向いている人の特徴
独学は以下のような人に向いています。
- 自分でスケジュール管理をできる人
勉強計画を自分で立てて、自己管理しながら進められる人なら独学は合っています。
- 費用を抑えたい人
通信・通学講座に比べて、勉強の費用を安価に抑えられます。ビジ法2級の受験料(IBT方式7,700円、CBT方式9,900円)を除き、テキスト代などだけで済ませることができれば、10,000円前後の費用で合格可能です。 - モチベーションを保って黙々と進めたい人
自分のペースで着実に勉強を進めたい人は、図解豊富なテキストと問題集を使い、インプットとアウトプットを繰り返すことで、知識の定着率が高まって実力がつきます。
講座が向いている人の特徴
対して、講座受講は次のような人におすすめです。
- モチベーション維持が不安な人
授業参加や課題提出、模擬試験など、講座は“やらなければならないこと”が多いゆえに、勉強を継続しやすくなります。
- 最短合格を目指したい人
試験の出題傾向に即したカリキュラムで勉強でき、時間効率が高まります。特に、大手講座は、長年蓄積したデータに基づいた独自のカリキュラムに基づいた授業を展開し、重要ポイントを凝縮した講義を受けられます。。 - 効率的に学びたい人
オンライン講座なら、Web模試や講義動画でIBT方式とCBT方式にそれぞれ対応しています。忙しい社会人にとって、スキマ時間でも学びやすいのがメリットです。
独学で合格を目指す場合のおすすめ教材は?
独学の場合、教材選びもとても大切なポイントになります。下記にテキスト選びのポイントを2点解説しているので、ぜひ参考にしてください。
テキスト選びのコツ
- 図解豊富で法律用語解説があるもの
特に、法律になじみがない人にとって、テキストを選ぶ際の最大のポイントは「理解しやすいかどうか」です。図解や法律用語解説が掲載されているテキストは、法律の知識があまりない人でも読みやすく、勉強のハードルを下げてくれます。
- 最新の法改正に対応し、過去問が掲載されているもの
法律は常に変わります。資格試験は最新の法改正に沿った内容で出題されるため、最新版のテキストを使うことで正確な知識を得られます。
また、過去問を多数掲載している教材は試験対策にとても有効です。例えば、東京商工会議所から発行されている公式のテキストは最も信頼性が高く、問題演習で出題形式に慣れるのに適しています。
編集部のおすすめ教材3選
以下、初学者から実務経験者まで幅広く対応できる、おすすめの教材を厳選して3つご紹介します
「ビジネス実務法務検定試験(R)2級公式テキスト〈2025年度版〉」
ビジネス実務法務検定は公式サイトに基づいた内容が出題されます。迷ったら公式サイトを使えば安心でしょう。
「2025年度版 合格革命 ビジネス実務法務検定(R) 2級テキスト&一問一答」
インプット・アウトプットが一冊にまとまっており、IBT試験に対応しています。一問一答形式でまとまっているので、スキマ時間の勉強がメインになる人におすすめです。
「法務教科書 ビジネス実務法務検定試験(R)2級 精選問題集 2025年版」
過去9回分の試験から頻出問題をピックアップし、解答の根拠となる法令の条文を示して明解に解説しています。問題演習と傾向の把握を同時に行えます。
インプットとアウトプットの黄金比は「3:7」
コロンビア大学のアーサー・ゲイツ博士が行った実験によると、新しいことを覚える際は、インプット3割:アウトプット7割のバランスが最も効果的だったという結果が出ております。
勉強をする際、ついついインプット過多になりがちですが、この黄金比を意識してアウトプットを積極的に行うようにしましょう。
- インプット(3割)
まずは、テキストや問題集の序盤章を読み、要点とおさえながら全体像を把握します。ここで、基本的な知識をしっかりと得ましょう。
- アウトプット(7割)
過去問や一問一答・精選問題をひたすら解き、反復することで知識を定着させます。間違えた問題は、テキストに戻って再度学んでから解き直します 。
このインプットとアウトプットの最適なバランスの勉強によって、学力が効果的に伸びる可能性が高まります。特に、「知識より判断力」を優先するビジ法2級の試験では向いている勉強方法です。
まとめ|自分に合った勉強方法と教材でビジ法2級合格を目指そう!
ビジ法2級は、社会人として法律知識を体系的に学べる有益な資格です。その分、合格には勉強をしっかりする必要があります。自分のレベルや生活スタイルに合った勉強計画を立てることが、合格への近道になります。
効率的で自分に適した勉強方法と教材を選ぶことで、限られた時間のなかでも十分合格を目指すことが可能です。ぜひ、本記事を参考に、ビジ法2級合格を目指してみてはいかがでしょうか。

Manegy Learning
Manegy Learningは管理部門・士業の皆さまに向けて、実務に役立つTIPSや資格取得のためのスクール取得などの情報を発信し、みなさまの学びをサポートします。
MS-Japan
https://www.manegy.com/learning/