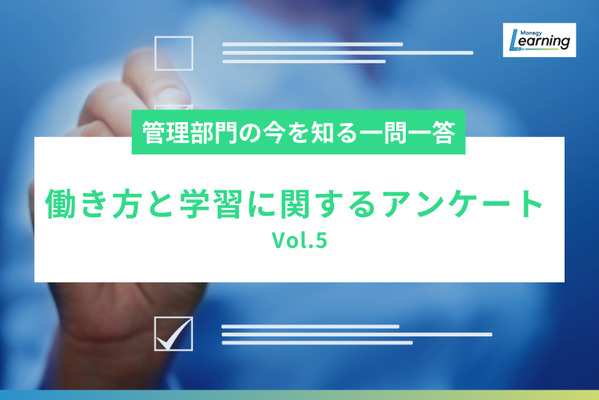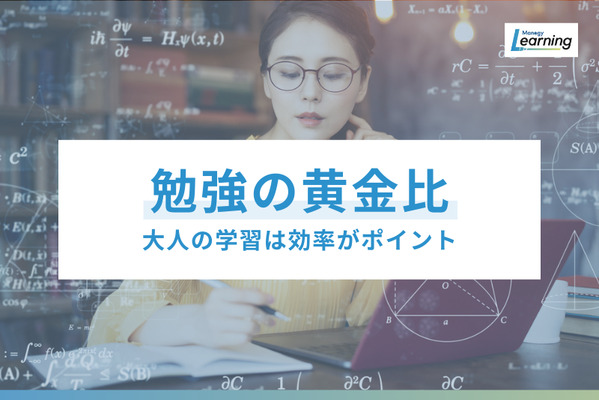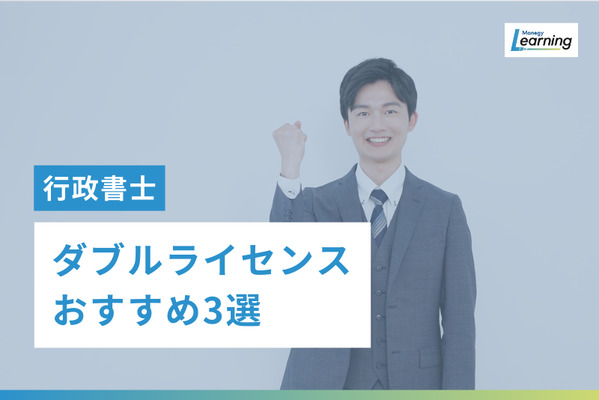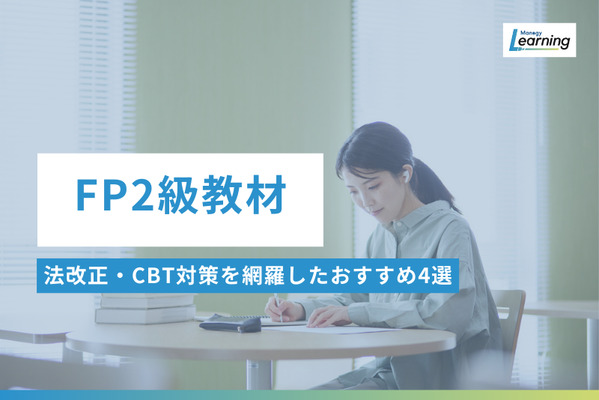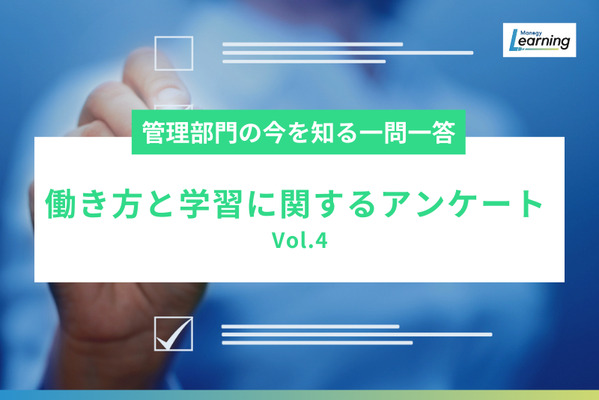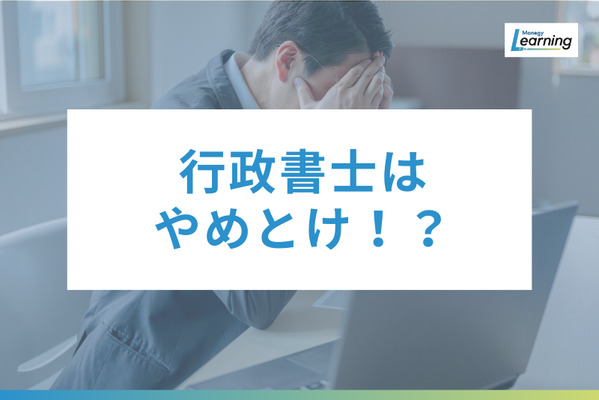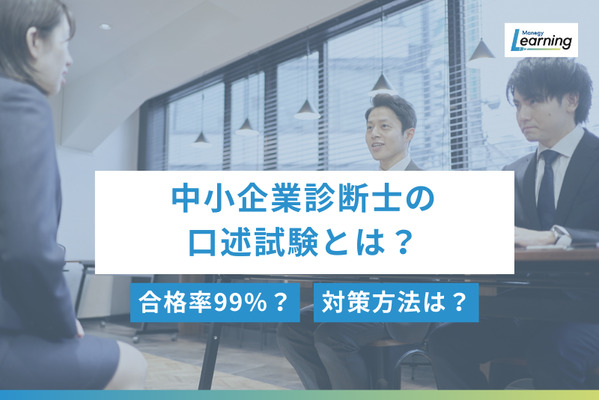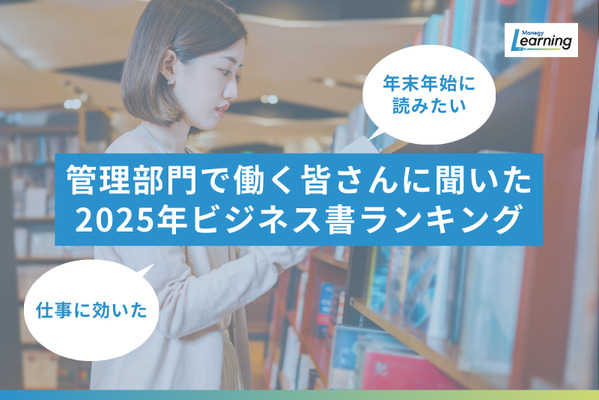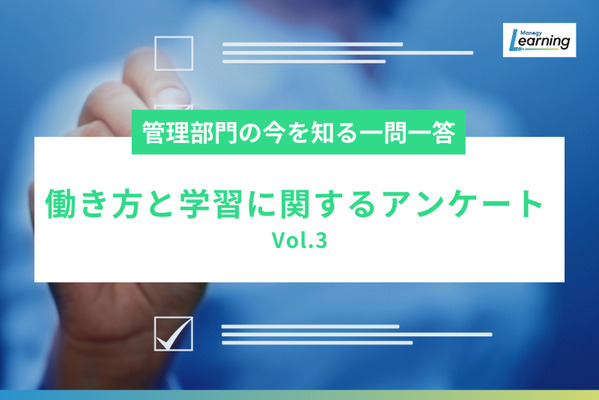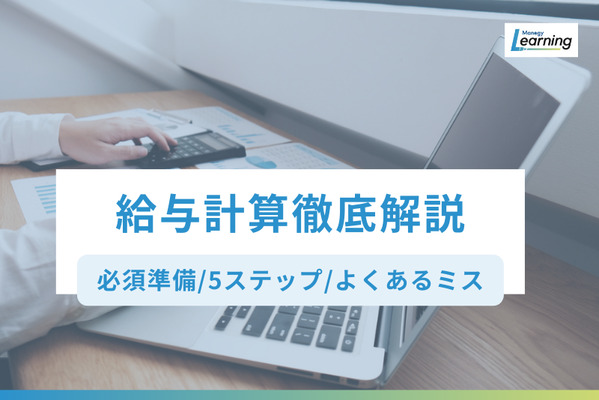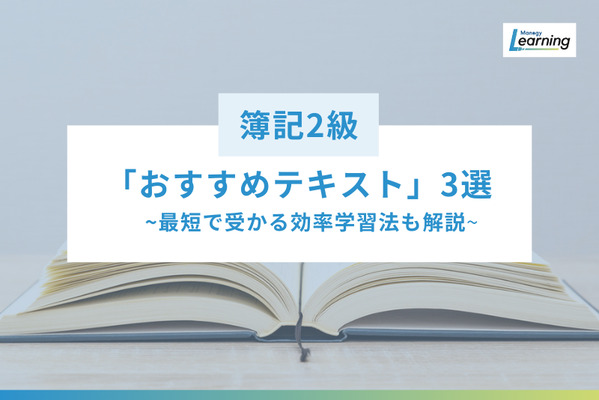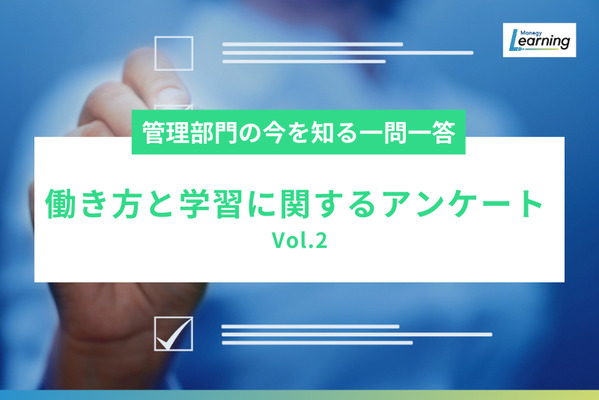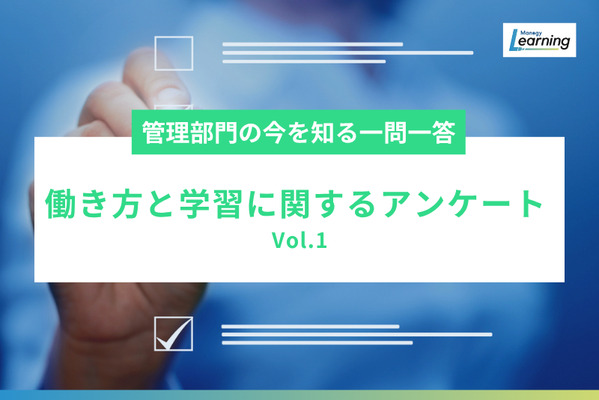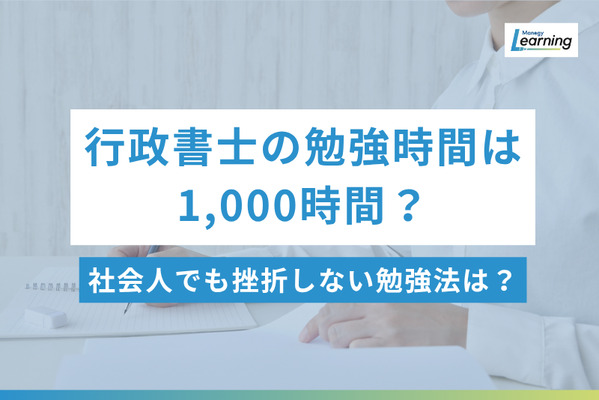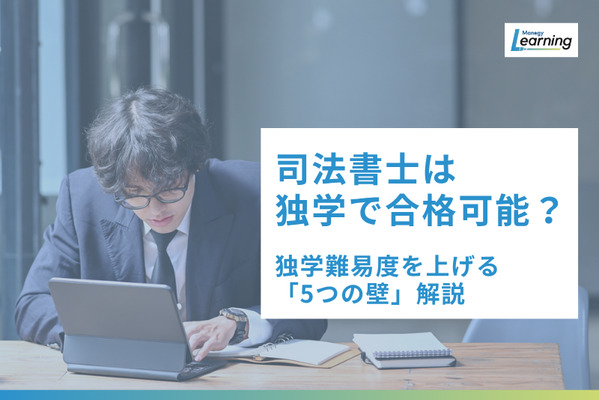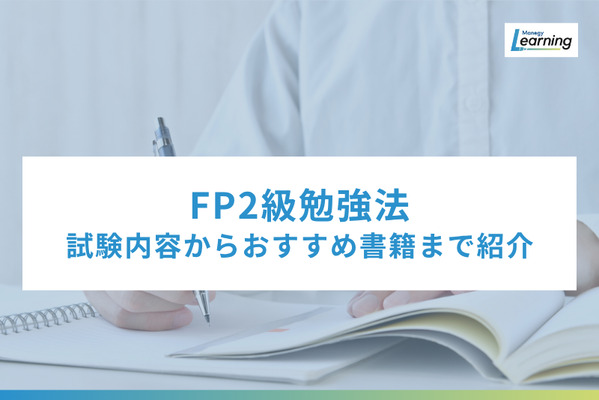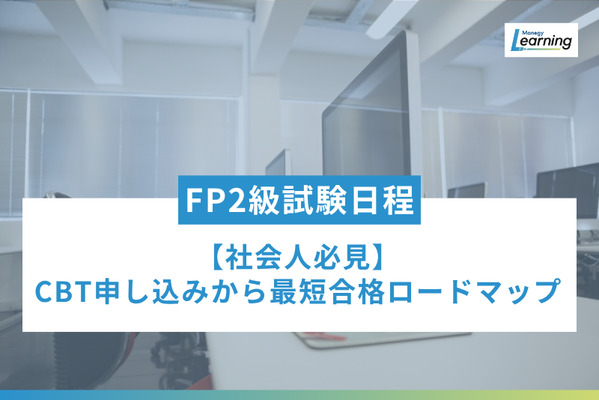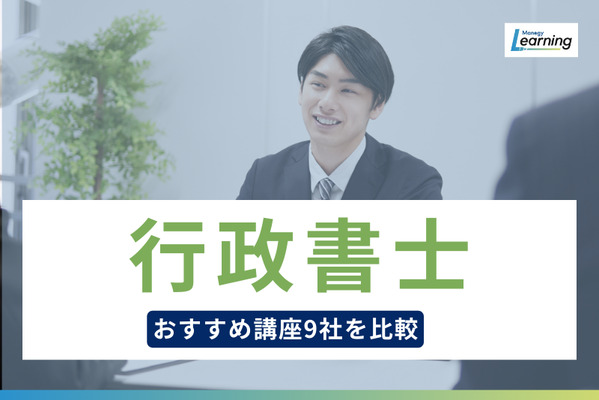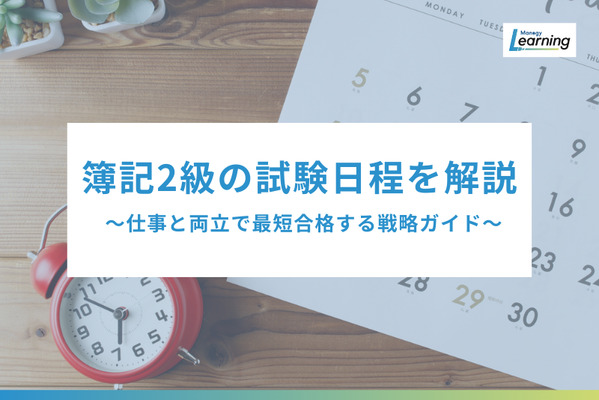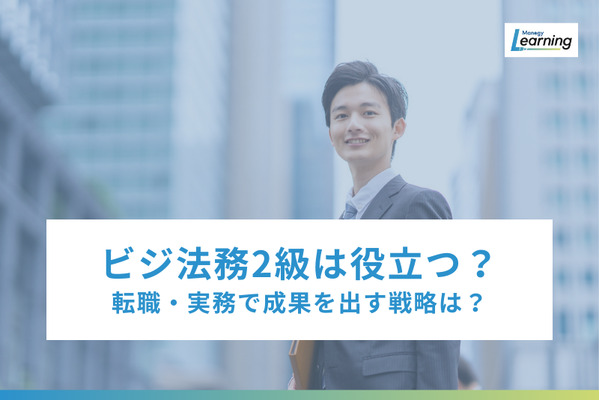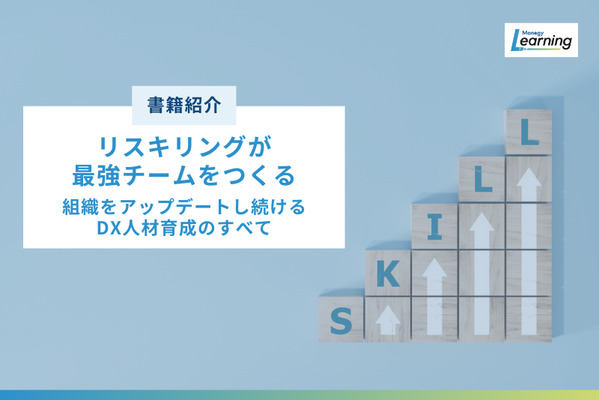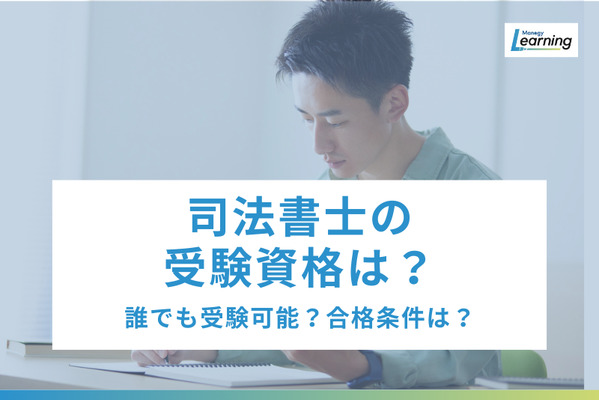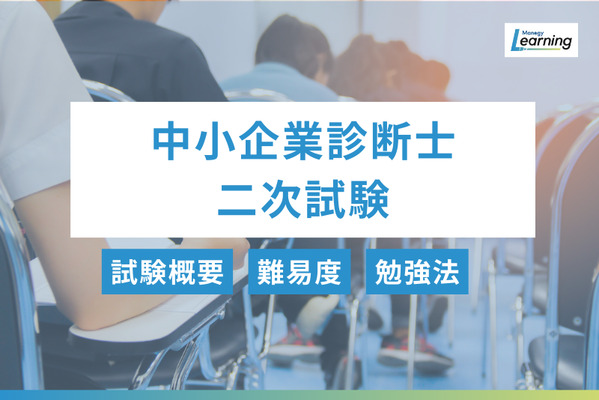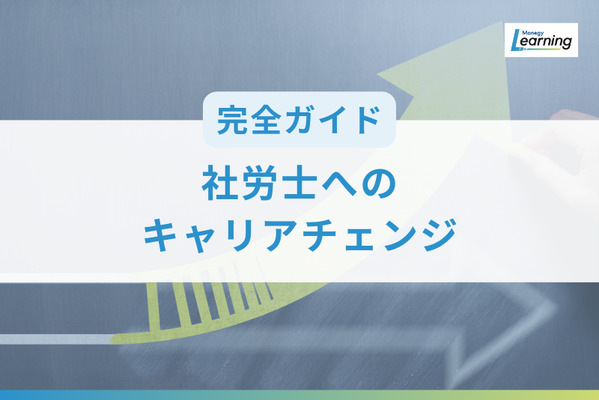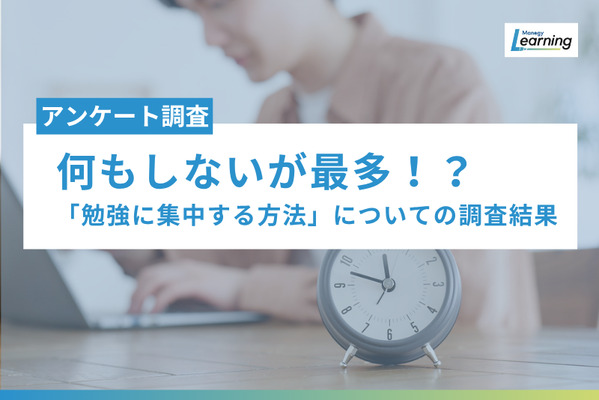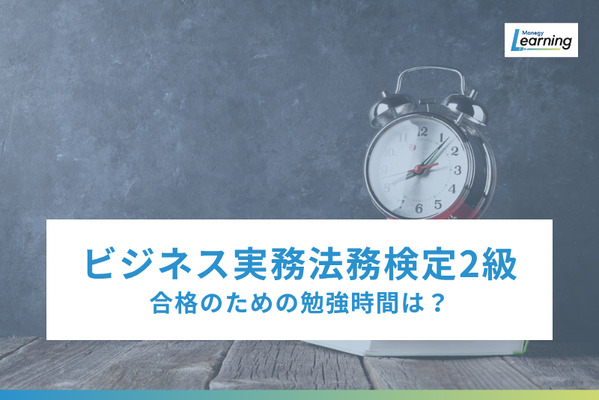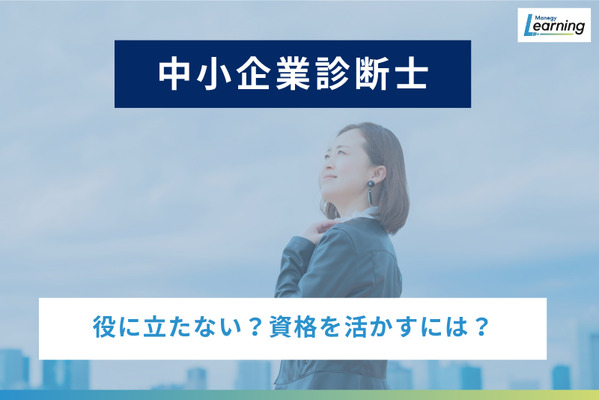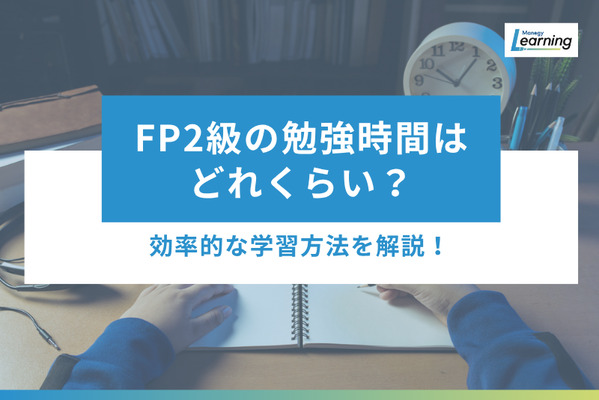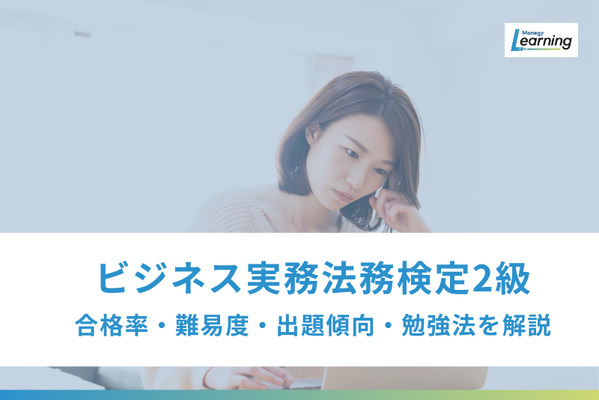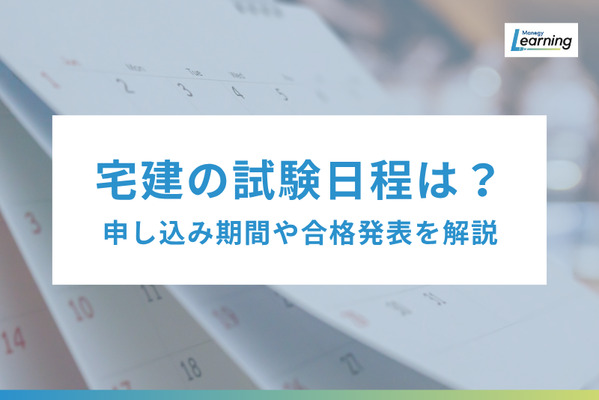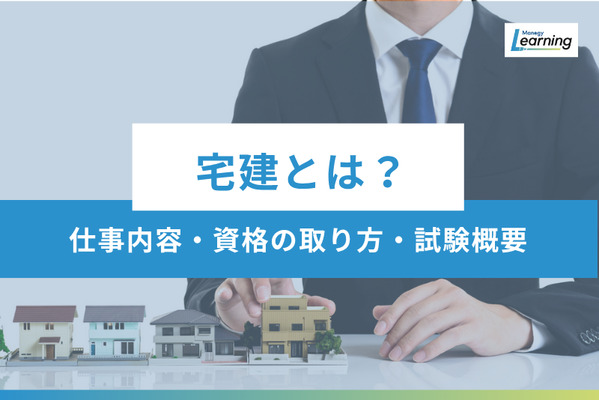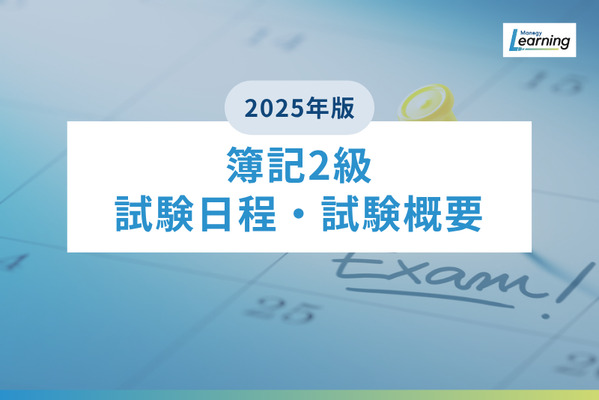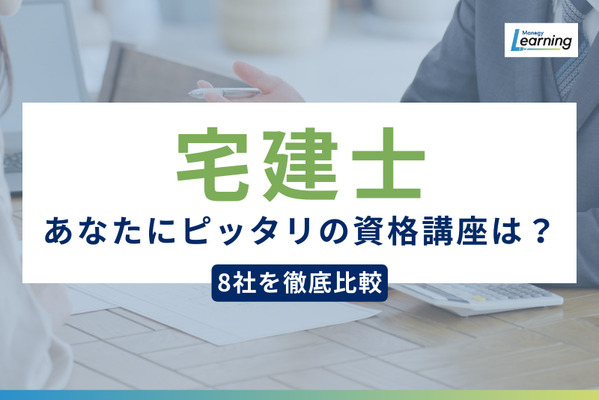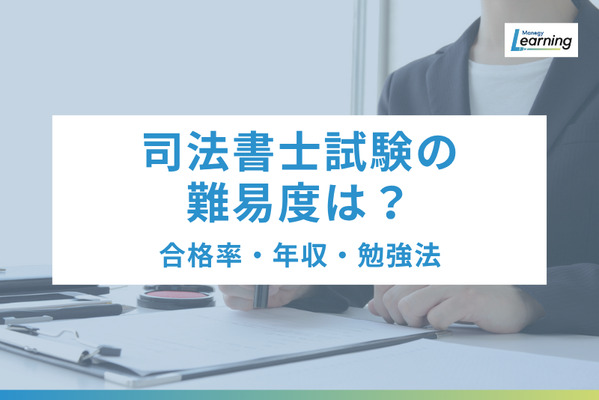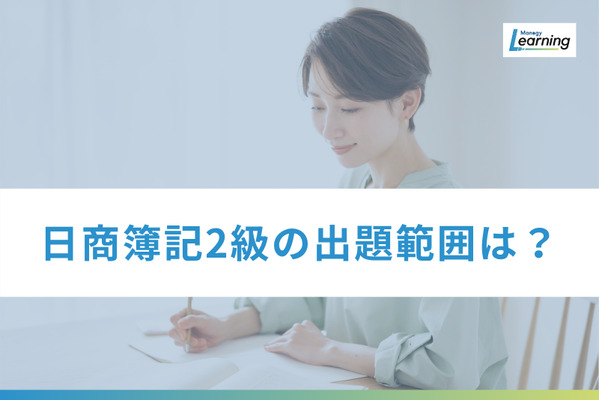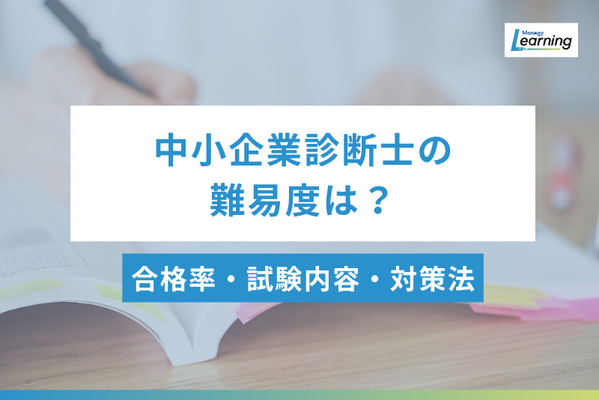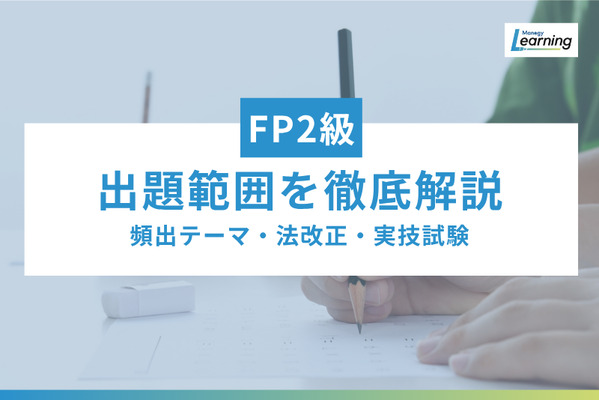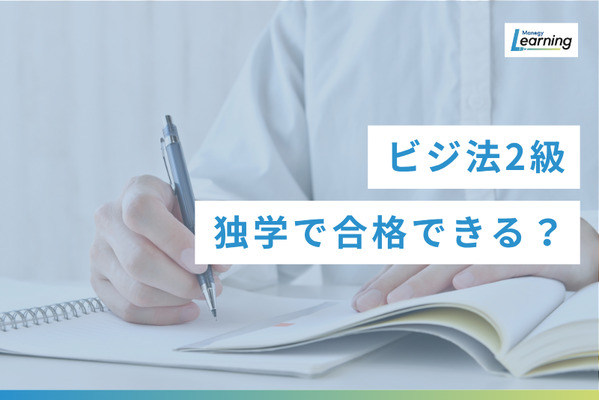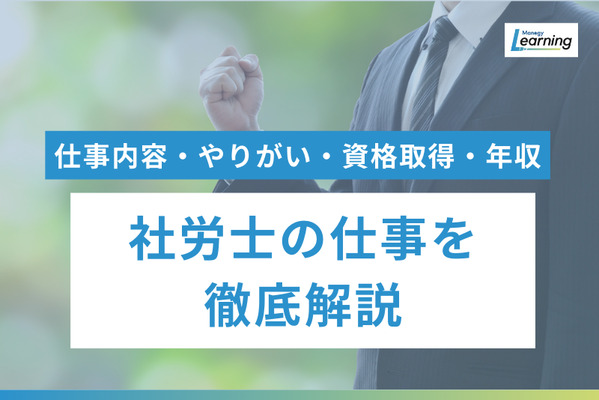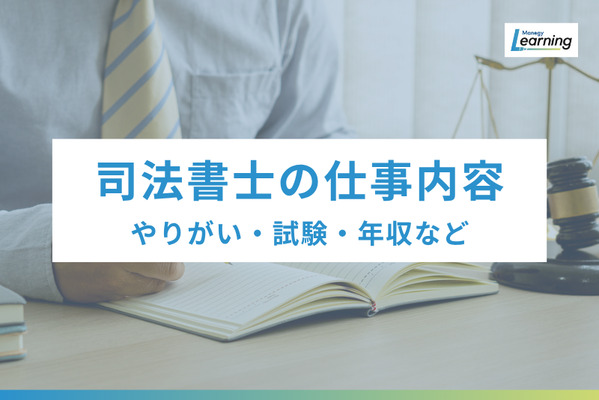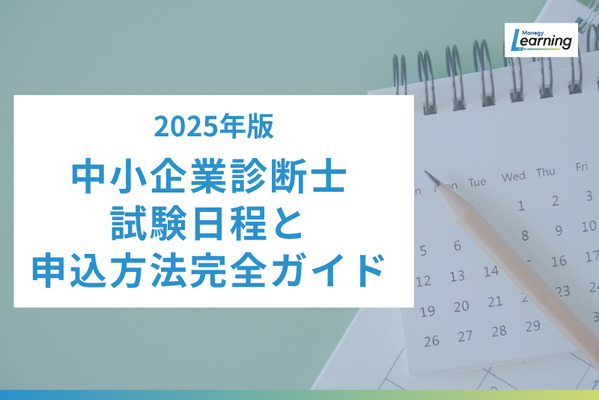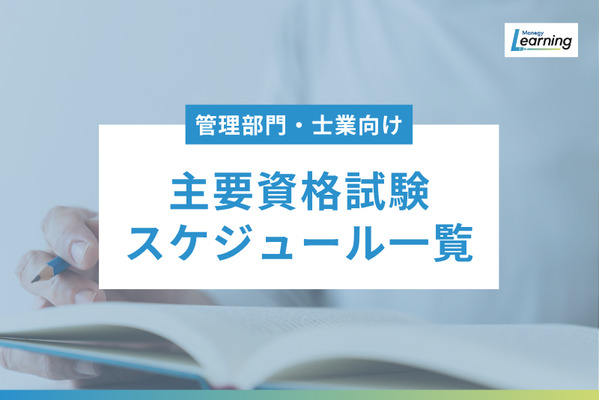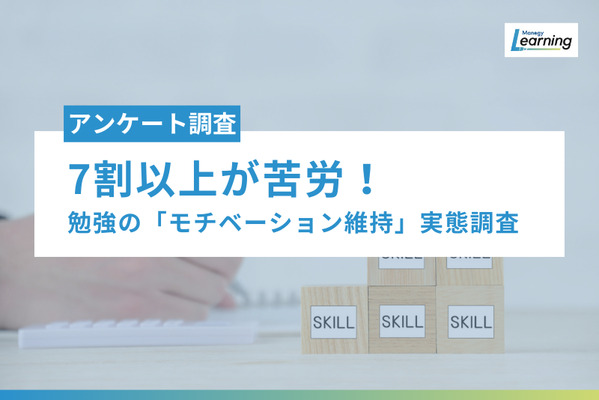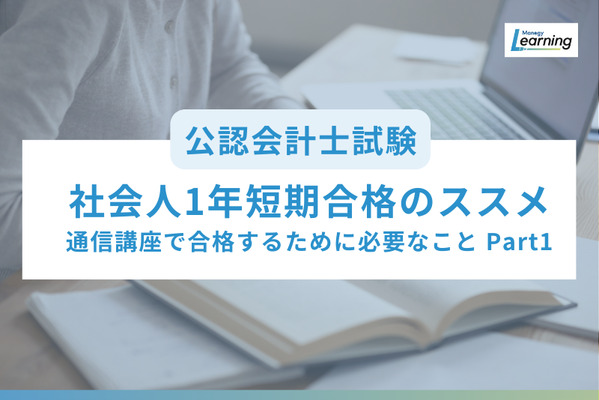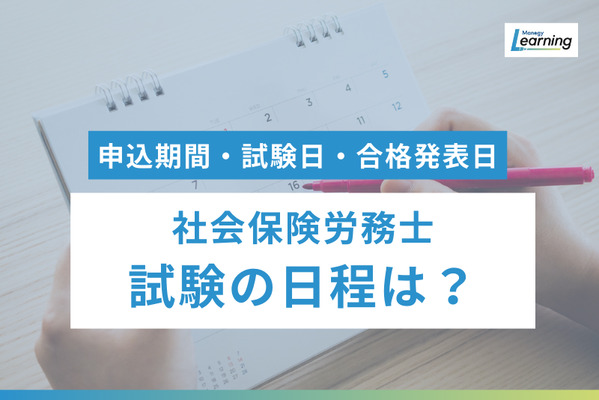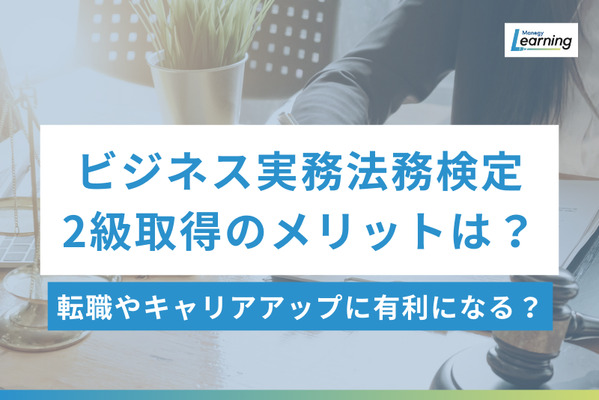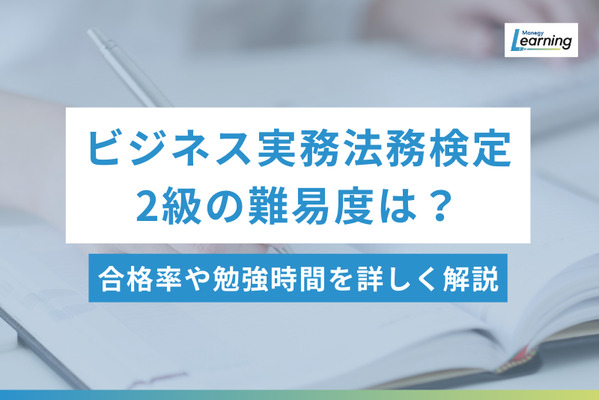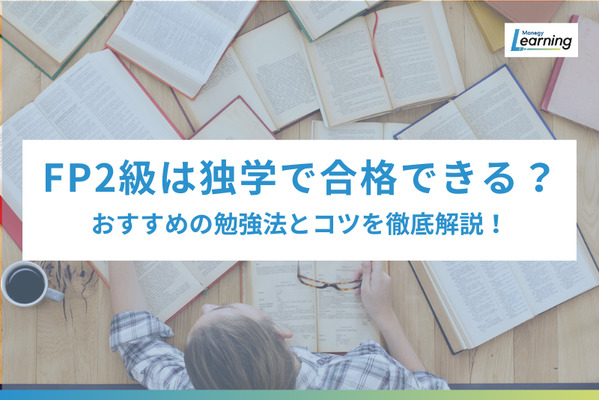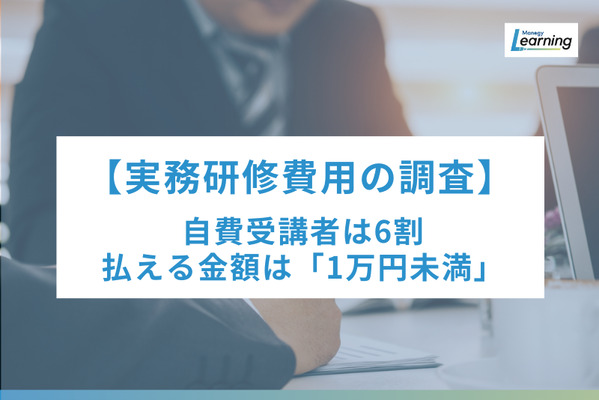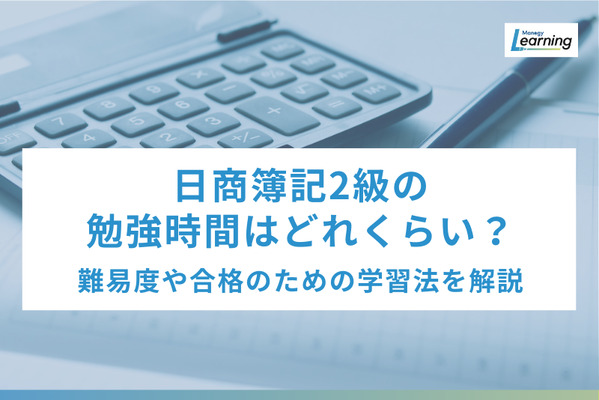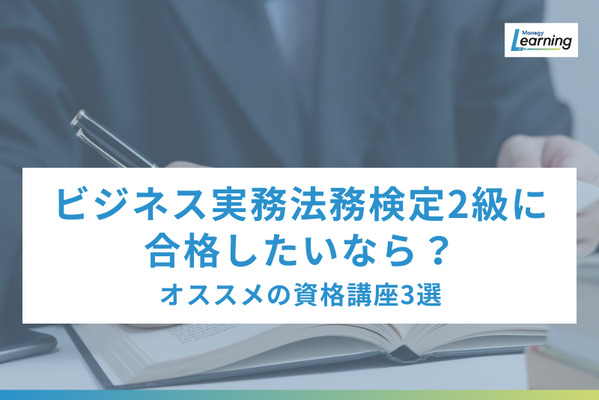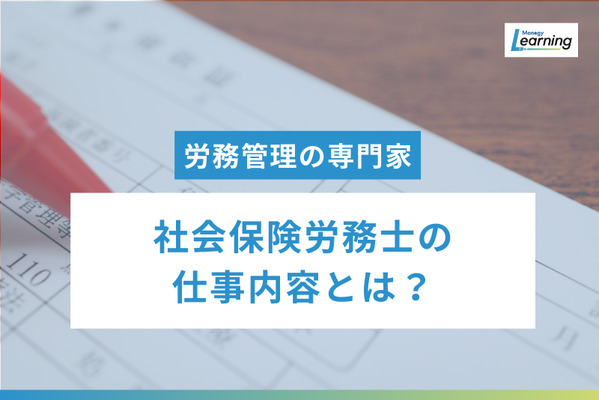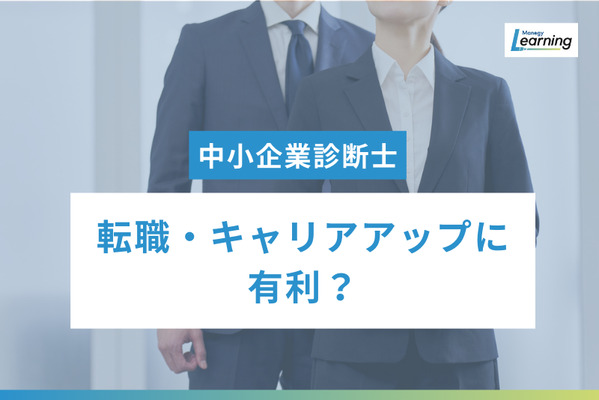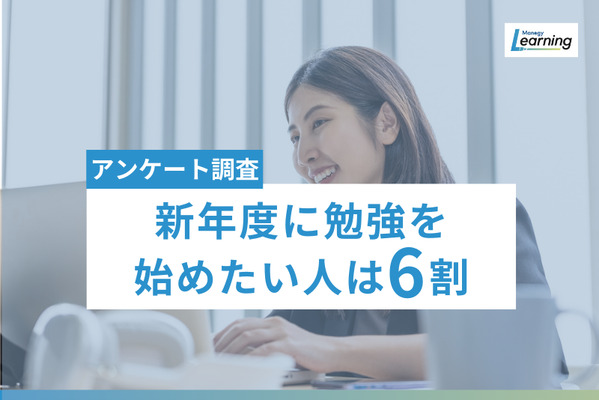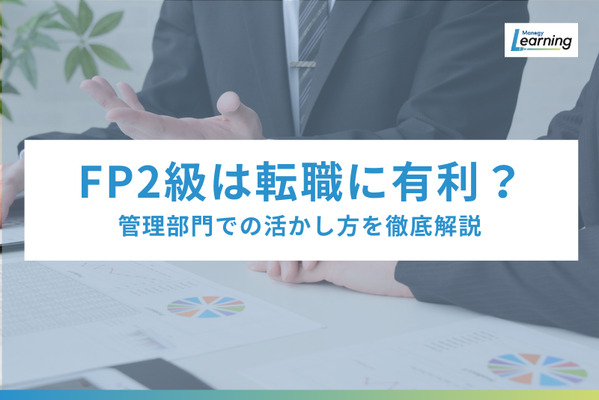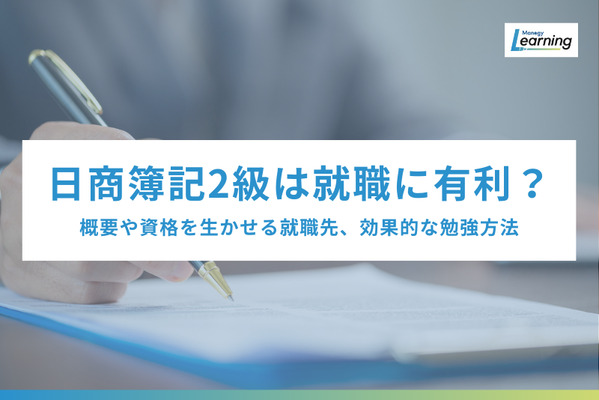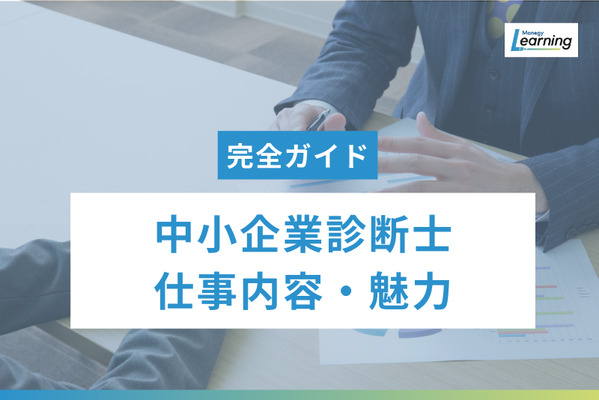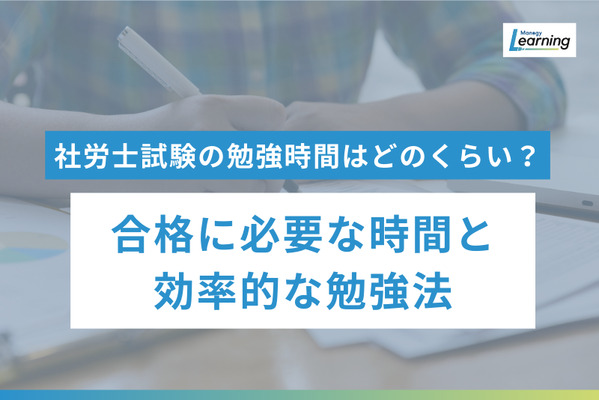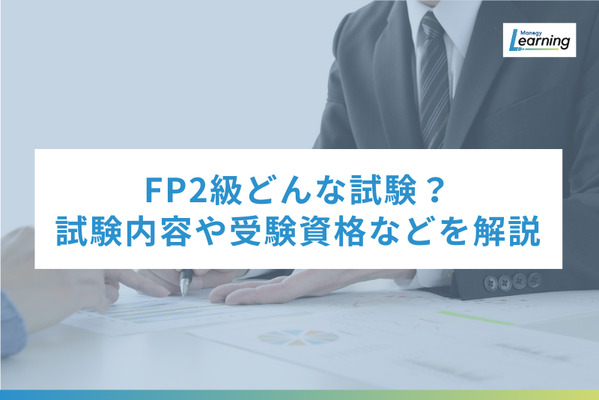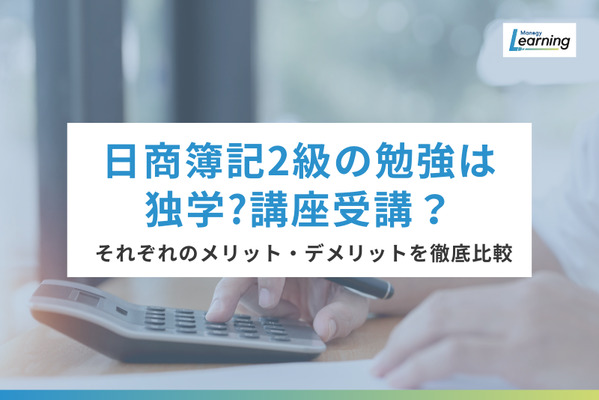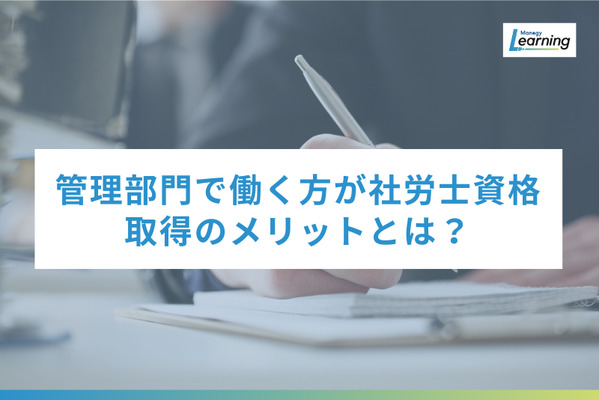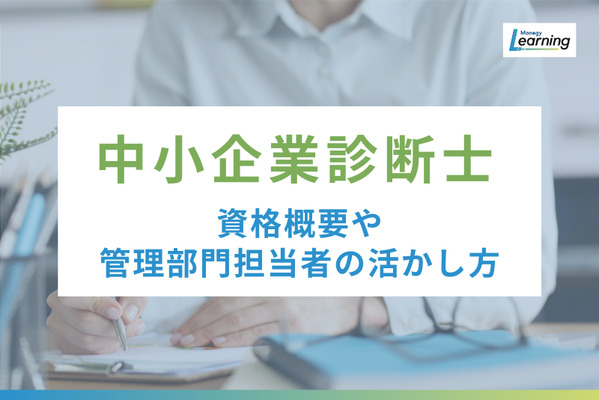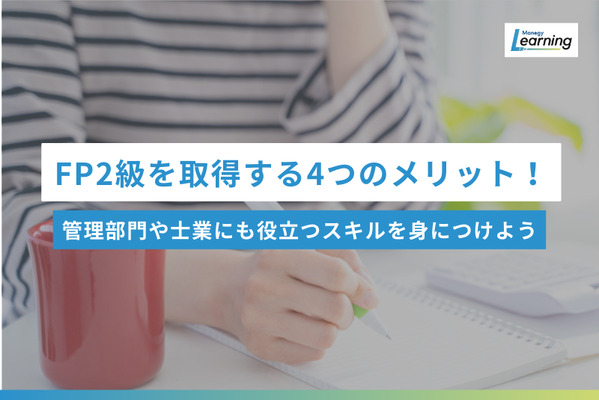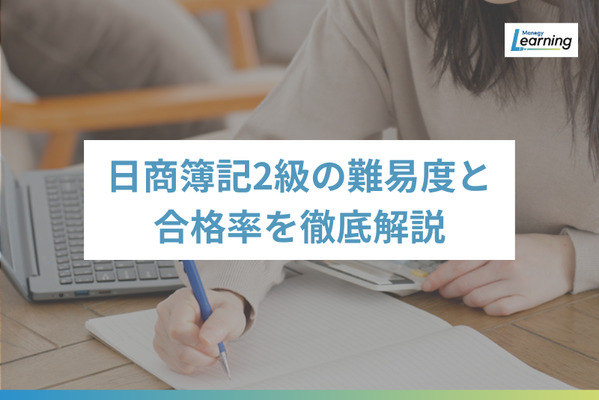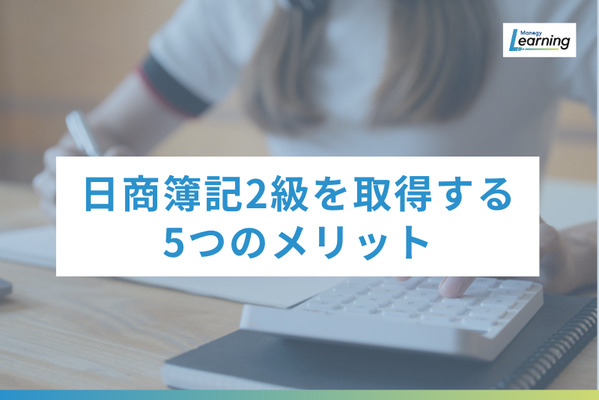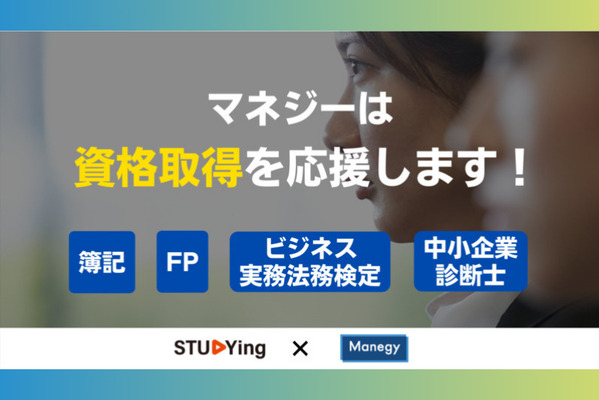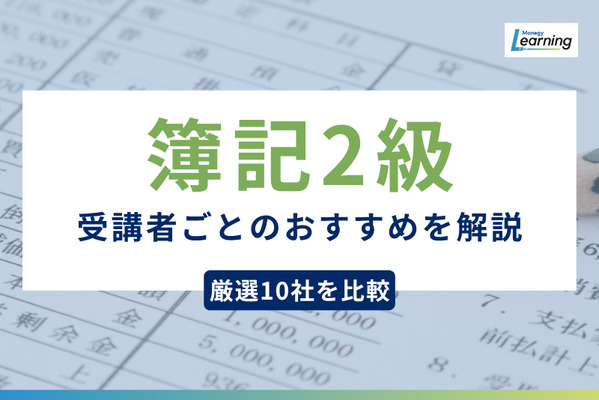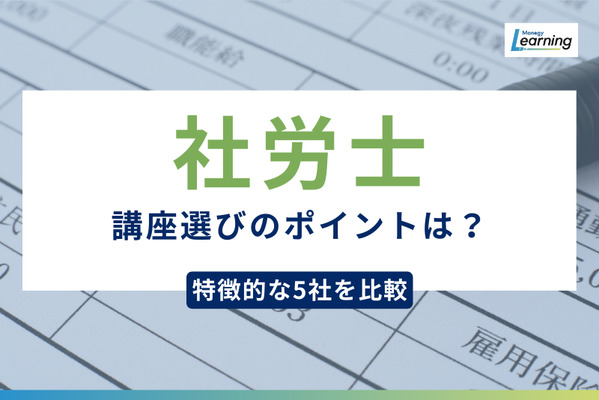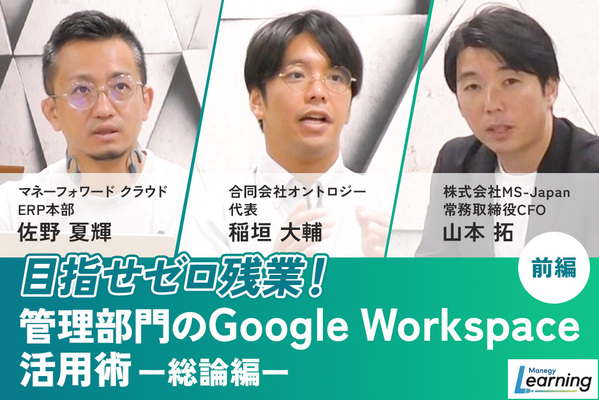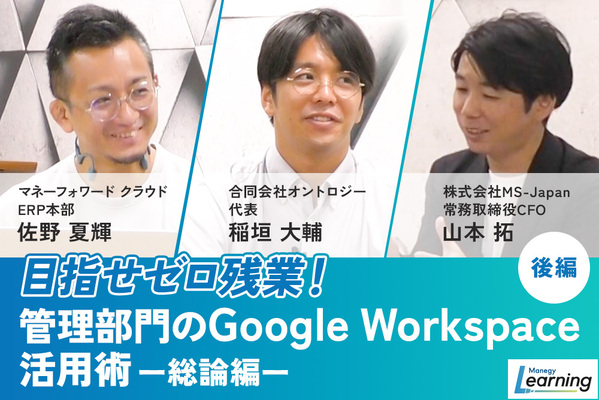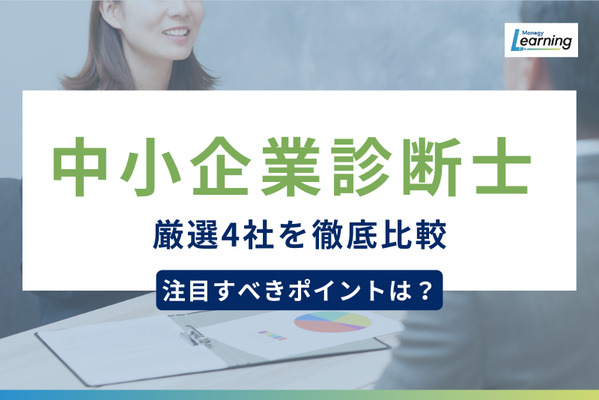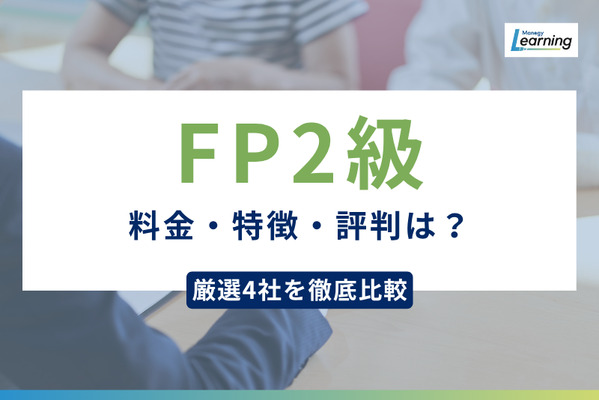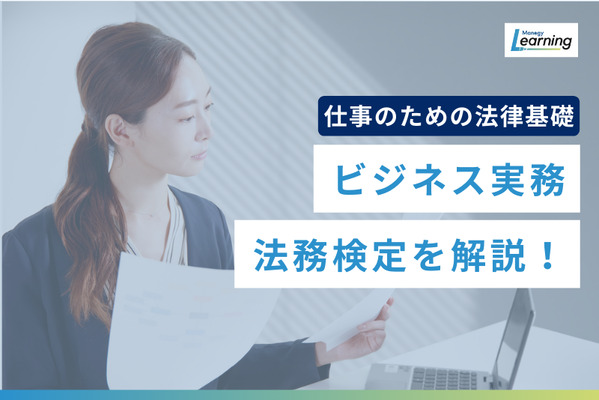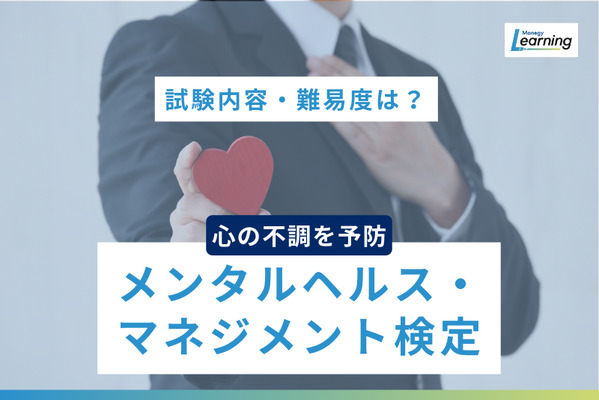宅建の将来性は?資格は役に立たない?需要や今後について徹底解説
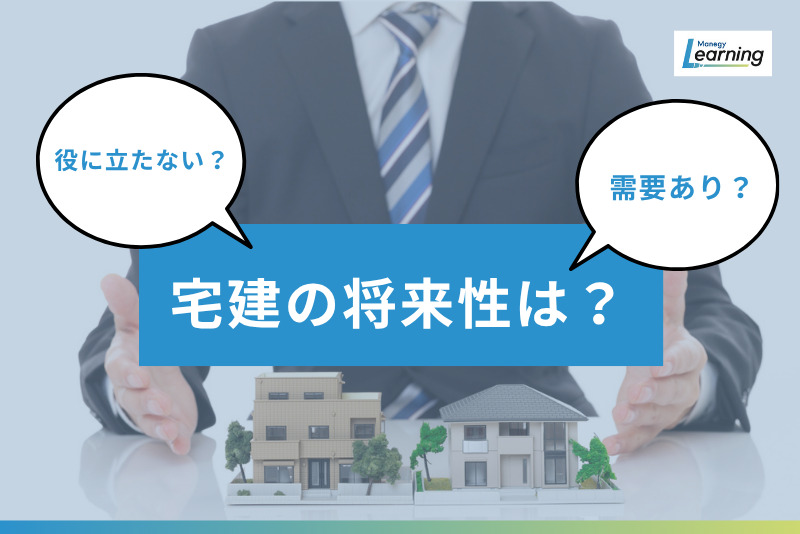
数ある国家資格のなかでも、「宅建」は受験者の多い資格です。一方で、近年はAIの進化や人口減少の影響から、不動産業界の将来に不安を感じる人が一定数おり、宅建の将来性に疑問の声もあるようです。
本記事では、「宅建資格は今後も役に立つのか」と疑問を感じている人に向けて、その将来性や活躍の場、キャリアの広がりを解説します。
宅建とは?主な業務内容と設置義務について解説
宅建は「業務独占資格」です。「業務独占資格」とは、有資格者以外が携わることを禁じられている業務を独占的に行なえる資格のことです。宅建の主な業務は、以下の3つに分類されます。
不動産の売買や賃貸契約に関わる重要事項の説明
不動産の売買契約や賃貸契約において、物件に関する法的情報や制限事項、設備内容などを、契約前に買主や借主に対して説明する業務です。これは宅建士にのみ認められた独占業務であり、トラブル防止の観点からも極めて重要です。
不動産取引における重要事項説明書(35条書面)への記名
説明した内容を明文化し、契約者が内容を確認したことを証明するために、宅建士が自ら記名・押印します。
契約内容を記した書面(37条書面)への記名
契約書(37条書面)に記名・押印します。不動産契約の最終段階においても、宅建士の役割は大きいです。
独占業務と設置義務について
前述のとおり、宅建には法律で守られた独占業務があります。不動産取引において、顧客など関係者へ「説明責任」を果たすための資格は宅建だけであり、最大の強みと言えるでしょう。
また、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業の「事務所」において、業務従事者5人につき1人以上の割合で、専任の宅建士を設置することが義務付けられています(宅地建物取引士の設置義務)。つまり、不動産業界において宅建士は欠かせない存在であり、安定した雇用環境につながっています。
「宅建の将来性は不安」と言われる理由は?
一方で、「将来性がないのでは?」といった否定的な声も聞かれます。こうした声の背景には、社会構造の変化や技術革新があります。本項では、なぜ「宅建の将来性は不安」と言われているのかをご説明します。
AIやITによる代替の懸念
近年は不動産業界でもテクノロジーの活用が急速に進んでいます。例えば、電子契約の導入や、VRを活用したオンライン内見、チャットボットによる物件紹介など、かつては人間が担っていた業務が次々とデジタル化されています。
こうした動きにより、「いずれ宅建士の仕事もAIに奪われてしまうのではないか」との懸念が広がっています。実際、書類作成や簡単な案内業務はAIでも代替可能です。
人口減少や空き家増加による不動産市場縮小の懸念
日本の人口は減少傾向にあり、2024年10月1日のデータによると、人口は約1億2380万2,000人と、前年比で約55万人減少しました。この減少は14年連続で、減少数・減少率ともに過去最大となっています。この人口減に伴って、不動産市場の縮小も予測されています。特に地方では空き家の増加が深刻化しており、「そもそも不動産の取引自体が減っていくのでは」と考える人も少なからずいるのです。
上記のことから、不動産業界における変化や課題によって「宅建の将来性は不安」という声があがっています。しかし一方で、宅建士の活躍の場がむしろ拡大している側面もあります。次項でご説明しましょう。
宅建士はAIに仕事を奪われる?人間にしかできない仕事とは
「宅建は役に立たない」という意見もありますが、果たして本当にそうでしょうか。
確かに、物件情報の検索や条件マッチングのようなデータを扱う業務や、書類作成といった定型業務は、AIが得意とする領域です。しかし、不動産取引で重要なのは、顧客のこだわりや本音を引き出し、生活背景や将来設計まで含めた最適な提案をすることです。このような臨機応変な対応と高度なコミュニケーションスキルは、AIには難しいとされています。
また、契約内容の説明やリスクの認識についても、宅建士でなければできない業務です。誤解を防ぐ説明力や、トラブル発生時の対応力が求められる業務は、AIにとってかわられることは無いでしょう。
今後の宅建の需要はどうなる?
宅建士の需要は、法律で定められた設置義務によって支えられているだけでなく、不動産市場の変化に伴い多様化しています。ここでは、実際の求人動向や活躍の場の広がりをご紹介します。
宅建士の活躍フィールドの多様化
かつては「不動産業界だけで活用できる資格」というイメージがあった宅建ですが、近年では活躍のフィールドが大きく広がっています。例えば、建設業界や銀行などの金融業界、流通業界、小売業界なども宅建士が活躍する場です。建設会社では、自社の建設物件を販売する際に宅建士が必要です。銀行は不動産を担保にした融資をすることが多く、大手銀行のなかにはグループ会社に不動産販売会社を持っているところもあり、宅建士の存在が重宝されます。流通業界や小売業界などは、出店計画の際に宅建の知識などを求めている会社もあります。
さらに先に述べたとおり、不動産テック分野においても、AIやIoTを活用した不動産サービスの開発のために、法的知識と現場の実務経験を持つ宅建士の存在が欠かせません。こうした背景から、宅建士の需要は単なる「物件仲介」以外にも広がっているのです。
新領域での宅建の需要
人口減少や空き家問題でも、宅建士の役割が大きくなっています。空き家活用の一例として、地方では移住希望者に暮らしの情報提供や物件案内を行うほか、空き家をリノベーションして地域活性化や地方創生につなげるプロジェクトを実施するといった活動が、全国的に増加しています。こうした取り組みでは、物件の法的調査や取引手続き、利活用計画の立案に宅建の専門知識が活かされています。
宅建士が今後求められるスキルとは?
今後は、これまでの知識中心の人材ではなく、時代に適応したスキルを備えた専門家が求められると考えられています。
デジタル人材
電子契約やVRなどITツールなどを使いこなし、顧客に対してオンラインでも高品質なサービスを提供できる宅建士は、今後ますます価値を増します。いわゆる「不動産テック」分野では、こうしたITスキルを持つ人材が重宝されています。
法知識+コミュニケーション力が高い人材
物件に関する法的リスクや税務の知識を持ちつつ、顧客と信頼関係を築けるスキルは、不動産営業に欠かせません。顧客が安心し、納得できる取引を支える存在として、宅建士のニーズは今後も根強く残るでしょう。
マーケティング思考のある人材
市場や顧客のニーズおよび行動傾向を読み取り、提案型の営業を行える宅建士は、企業からも高く評価されます。特に、個人の価値観が多様化する現代において、画一的な営業では通用しないため、柔軟なマーケティング視点が鍵となります。
宅建の資格で広がるキャリアパス
宅建の資格を取得したあとのキャリアはさまざまです。企業内でキャリアアップを目指すだけでなく、独立や副業などを視野に入れることも可能です。ここでは、3パターンの主なキャリアについて触れます。
独立
宅建の資格を取得してから企業内である程度の経験を積んだのち、不動産仲介業を独立して開業するパターンです。独立して自分の裁量で顧客対応や物件提案を行い、自由に働くことができます。もちろん、独立は収入面などでリスクを伴いますが、自身の専門性と信頼を武器に活躍し、成功している人は大勢います。
ダブルライセンス
宅建の資格は、他の資格と組み合わせることで市場価値が一段と高まります。例えば、賃貸不動産経営管理士やマンション管理士、管理業務主任者、ファイナンシャルプランナー(FP)、行政書士、司法書士などです。特に、「不動産の3大資格」と呼ばれる宅建・マンション管理士・管理業務主任者の国家資格を複数取得することで、不動産に関する高い知識をアピールできます。
また、ダブルライセンスは幅広い業務に対応できるだけでなく、顧客に対してワンストップのサービスを提供できます。複数の資格を保持する人材は企業からの評価も高く、キャリアアップや給与アップにつながるケースも多いです。
副業
近年は副業を持つ社会人が増えています。しかし、専任の宅建士(※1)は宅建業法により、副業や他の業者との兼務が基本的に禁じられています。たとえ副業先が宅建業者であっても、副業は許されていないのです(一部例外あり)。一方、東京都は令和6年11月より、専任の宅建士が勤務時間外(夜間や休日など)に副業を行うことを原則として認めています。ただし、副業を行うには審査に通る必要があります。
副業の一例として、不動産投資のアドバイスや契約書のチェック、物件紹介のサポートといったサービスを個人で提供することができるでしょう。
※1:専任の宅建士…宅地建物取引業を営む事務所に常勤し、専ら宅地建物の取引に関する業務に従事する宅建士のこと。
宅建試験の難易度と勉強時間|忙しい社会人でも合格できる方法
宅建は人気が高く、毎年多くの人が資格取得の受験に挑戦しています。ここでは試験の概要と、社会人が無理なく合格を目指すための勉強時間の目安を紹介します。
試験概要
宅建試験は、例年10月の第3日曜日に全国一斉で実施されます。受験資格は特に制限がなく、誰でも受験可能です。以下、今年度(2025年)の試験概要です。
・試験日時:2025年10月19日(日)13時~15時(登録講習修了者は13時10分~15時)
・受験資格:特になし
・受験手数料:8,200円
・試験形式:四肢択一式(マークシート)による筆記試験
・問題数:50問(ただし、登録講習(※2)修了者は45問)
・試験時間:2時間(ただし、登録講習修了者は1時間50分)
・合格基準:毎年変動
・合格率の推移:例年13~18%程度
※2登録講習…宅地建物取引業法第16条第3項に基づいた講習で、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が実施。
勉強時間
社会人が宅建合格を目指す場合、学習時間は一般的に200~600時間程度と言われています。目安としては、法律関連の初学者が独学で取り組む場合は600時間以上、資格予備校に通う場合は400時間程度、法学部出身者や不動産取引の知識を持っている人ならさらに短い勉強時間で合格を狙えるでしょう。
まずは基礎知識の習得にしっかり時間をかけ、その後は過去問や模試を使った実践演習に進むのが王道の勉強方法です。また、通信講座やオンライン教材を活用することで、効率的に学べます。
資格講座を利用して勉強を考えている方は、こちらの記事がおすすめです。
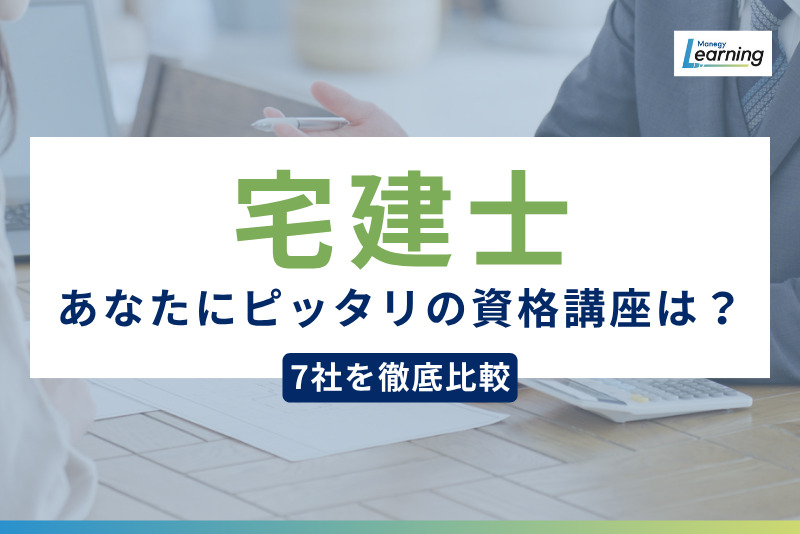
宅建士講座おすすめスクール徹底比較|価格・教材・サポート体制で選ぶ、あなたにぴったりのスクールは?
宅建士講座を価格・教材・サポート体制など、様々な視点から徹底比較。LEC東京リーガルマインドをはじめ、特徴のある7社を紹介し、あなたに最適な講座選びをサポートします。
まとめ|宅建は将来性ある資格
宅建は、法令で定められた独占業務を持ち、宅建業者の設置義務により安定的な需要が保障された国家資格です。AIや人口減少といった社会の変化はありますが、物件説明や契約交渉など、人間ならではの柔軟な判断力とコミュニケーション力が不可欠な業務を担い、価値が高い資格であることは変わりません。
これからの時代は、ITツールを活用し、マーケティング視点を持つなど変化に対応できる宅建士が求められており、資格の価値は時代とともに進化しています。もし、今後さらにキャリアを広げたいと考えているのであれば、ぜひ宅建の取得を検討してみてはいかがでしょうか。
宅建の資格を活かせる求人例
法務スタッフ(ポテンシャル採用)
- 仕事内容
-
・契約書のリーガルチェック(不動産売買契約書、重要事項説明書、業務委託契約書等) 一からの起案ではなく個々の契約の実情に合わせて基本の契約書を修正していきます。
・営業資料など対外文書のリーガルチェック
・社内法務相談、社外専門家とのパイプ役
・営業部門からの問合せ対応、トラブル対応
・コンプライアンス関連業務
・その他営業担当の契約締結のためのフォロー全般
※業務内容補足:本ポジションでは、主に不動産取引に関する契約法務に従事していただきます。
- 必要な経験・資格
-
【必須】
■深く法律に携わった経験(司法試験受験・法学部卒等)、もしくは企業法務の経験をお持ちの方
■不動産業界、当社事業に興味をお持ち頂いた方
■宅建取得に前向きな方(入社後1年での取得を目指して頂きます)
■PCスキル:Word、Excel、電子メールでのやりとりに抵抗がないこと【歓迎】
■不動産業界での契約法務に関する実務経験
■Microsoft365アプリ使用経験(Teamsやsharepointなど)【歓迎資格】
■宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、行政書士、FPなど
- 想定年収
- 400万円 ~ 500万円
上場不動産会社の法務スタッフ求人
- 仕事内容
不動産の法務業務に幅広く携わって頂く予定です。
選考を通じ、ご希望・適性から配属先を決定し、下記の通り配属先ごとの業務をお任せします。下記業務
【法務室の業務】
■契約書作成・審査
■係争案件への対応
■事業部門からの問合せ対応【コンプライアンス室の業務】
■監査・査察対応
■債権回収
■事業活動に係る法的判断及び法務リスク管理に関する事項の統括
■遵法精神の啓蒙に関する事項の統括
■内部統制システムの運用の統括
■与信管理
■コンプライアンスに関わる業務など
- 必要な経験・資格
-
<必須条件>
・法務業務のご経験<歓迎条件>
・弁護士(司法修習生可)、司法書士、宅建資格のいずれか保有されている方
・不動産業界での法務経験者
- 想定年収
- 300万円 ~ 500万円

Manegy Learning
Manegy Learningは管理部門・士業の皆さまに向けて、実務に役立つTIPSや資格取得のためのスクール取得などの情報を発信し、みなさまの学びをサポートします。
MS-Japan
https://www.manegy.com/learning/