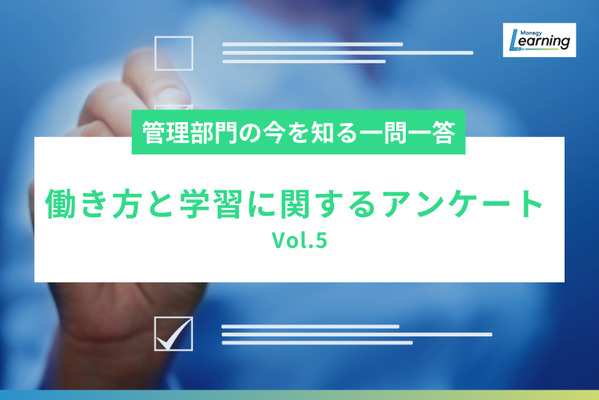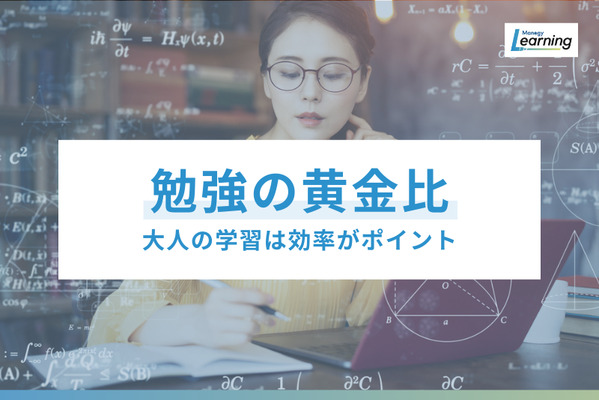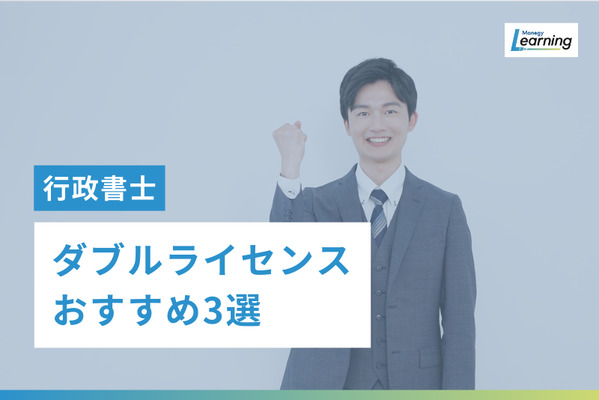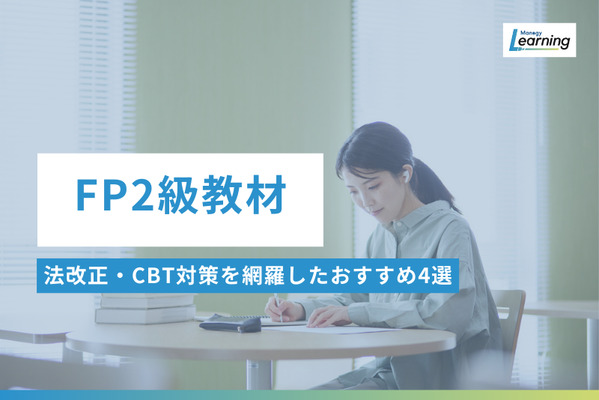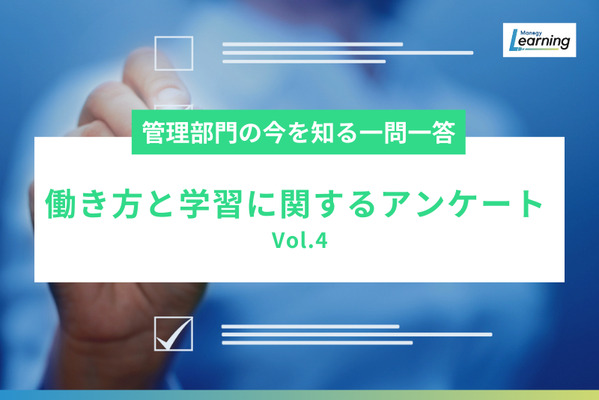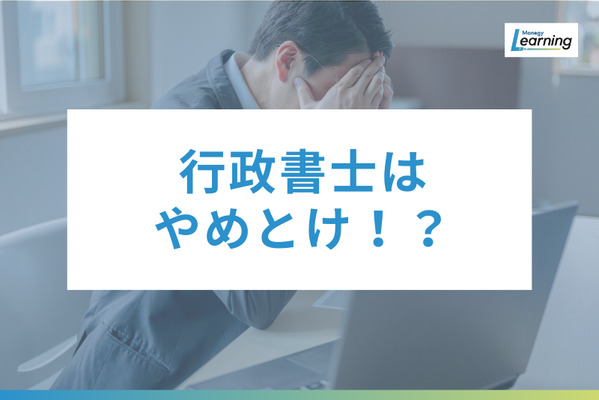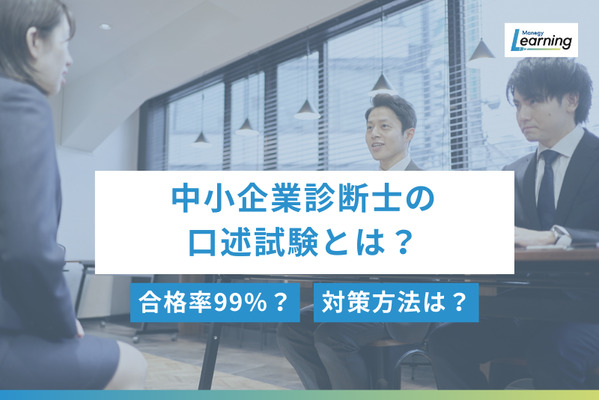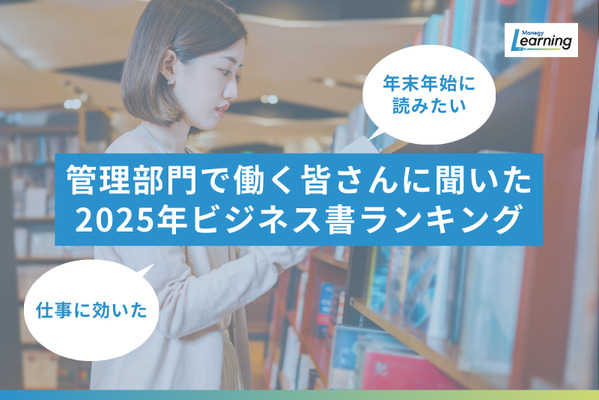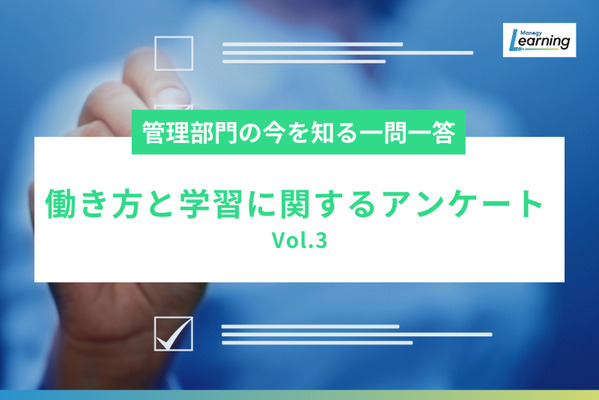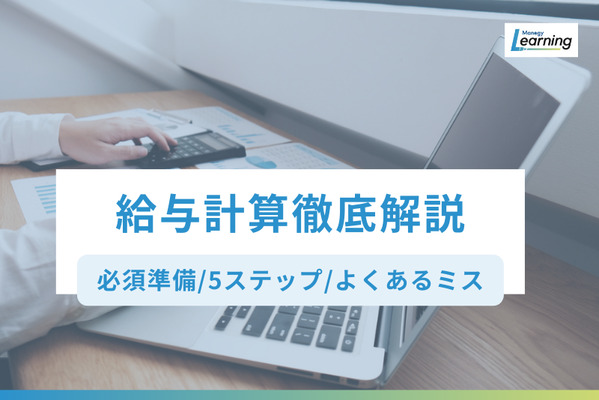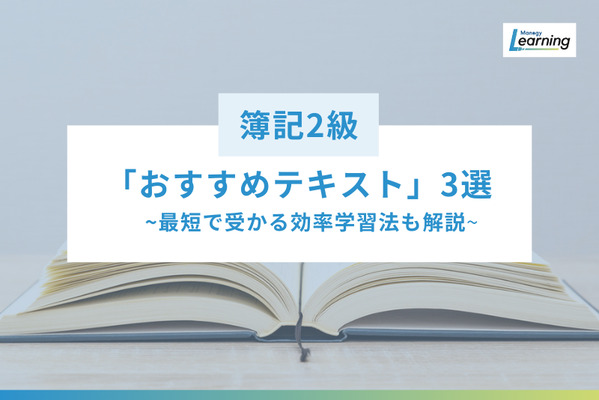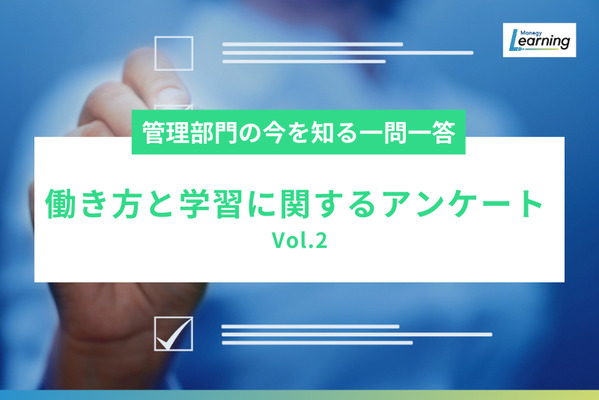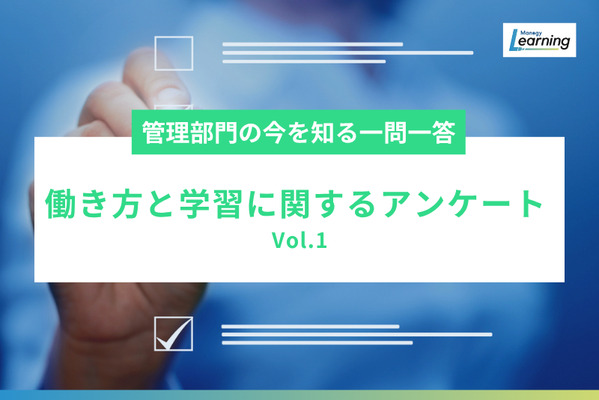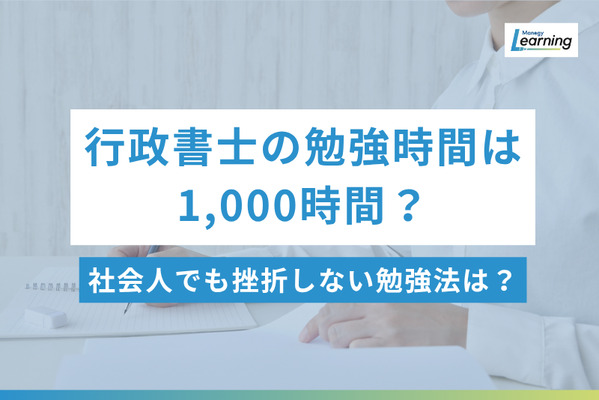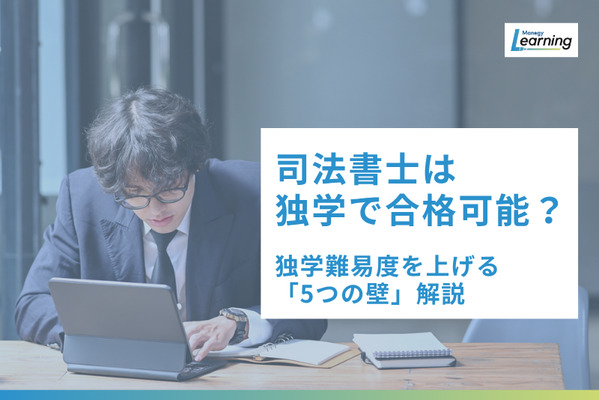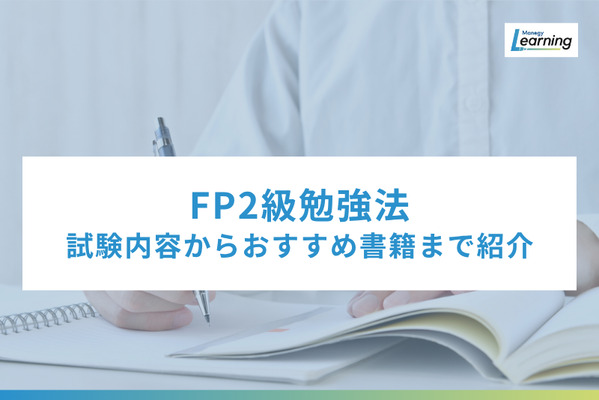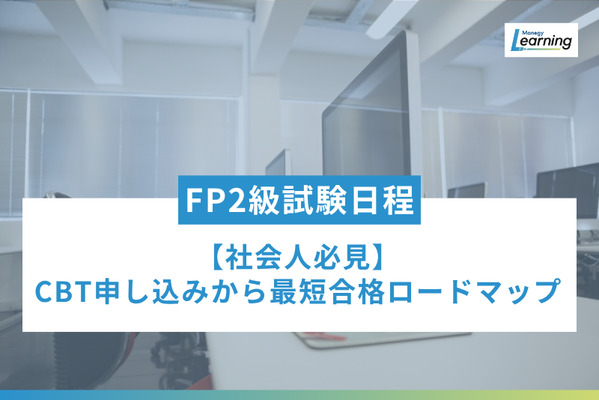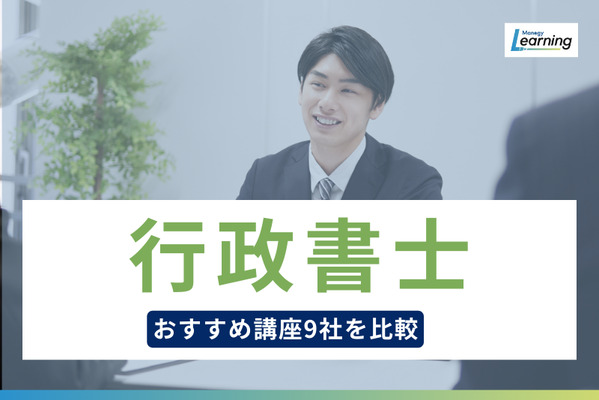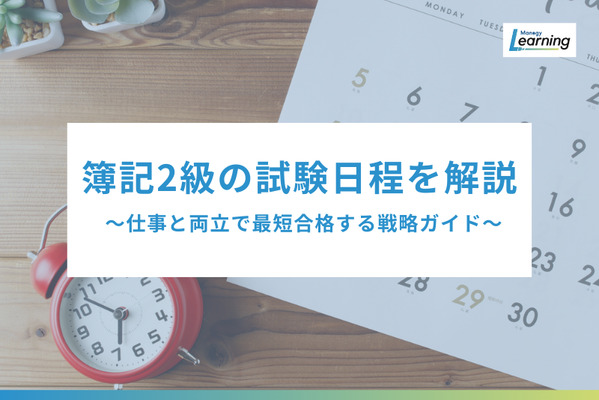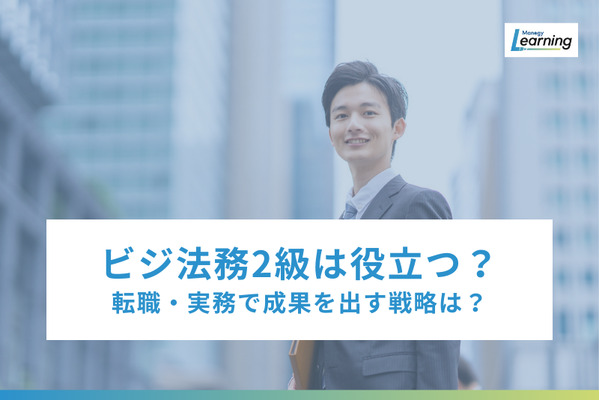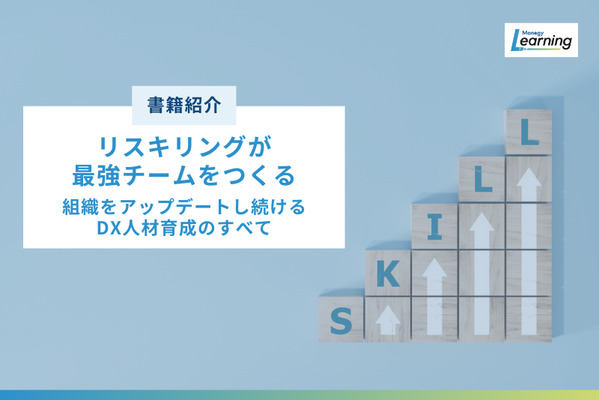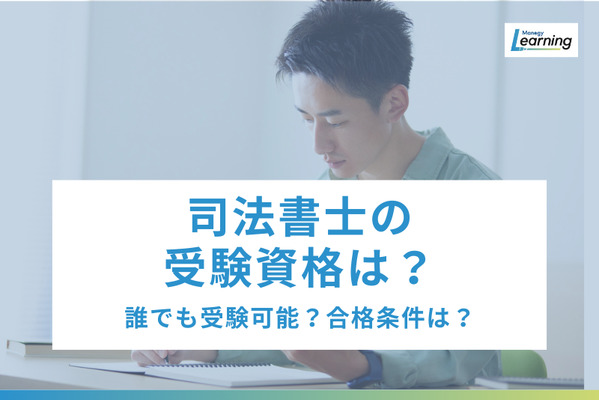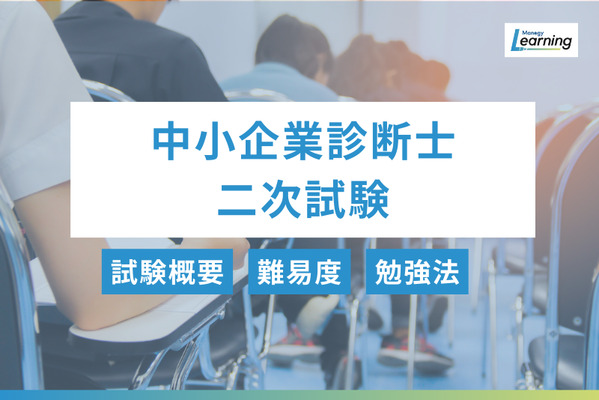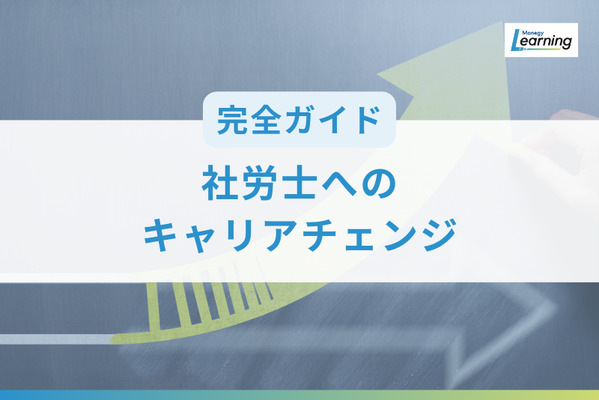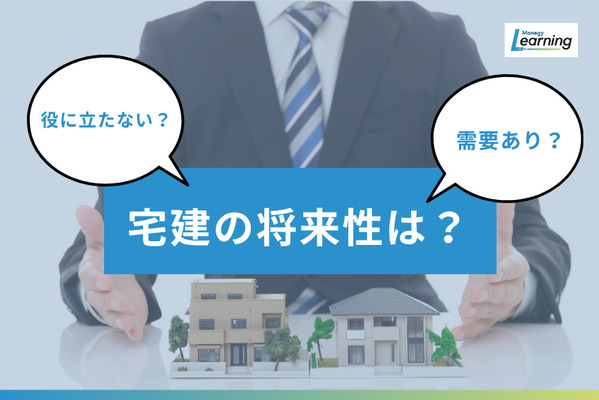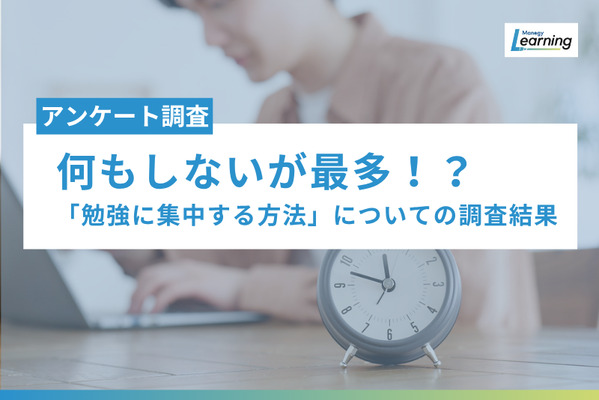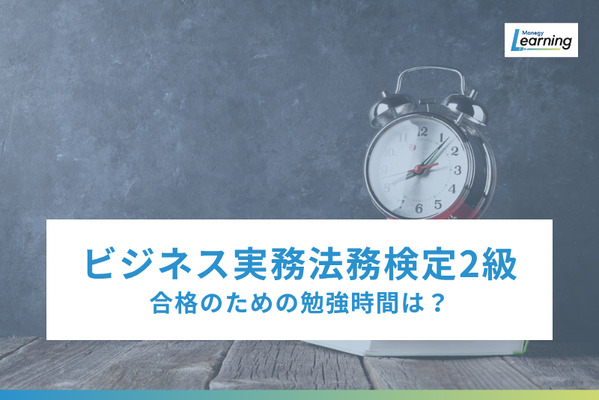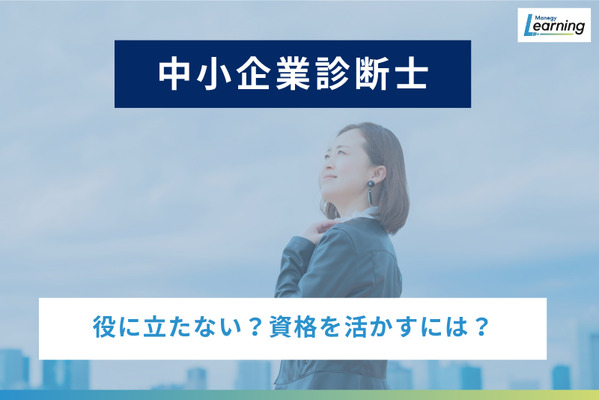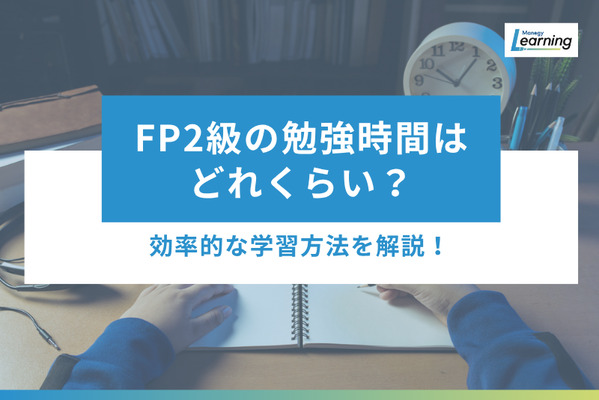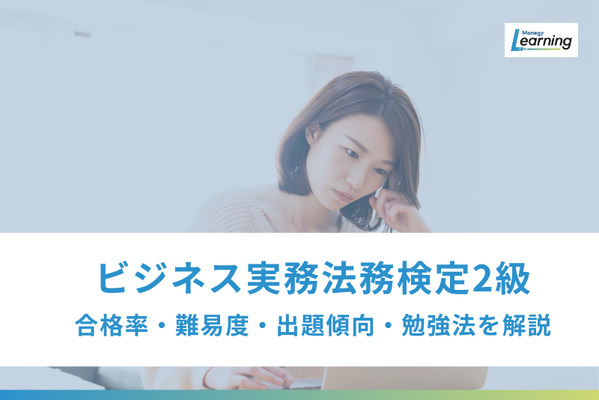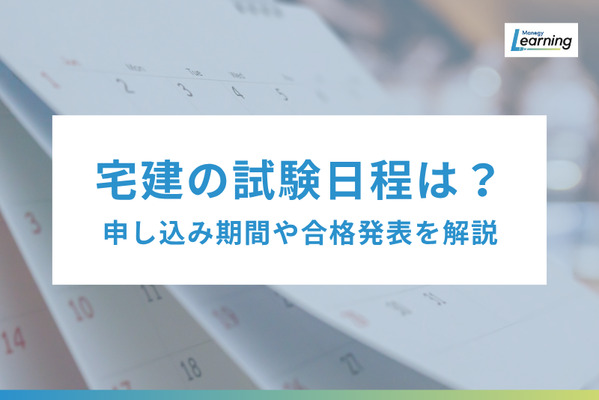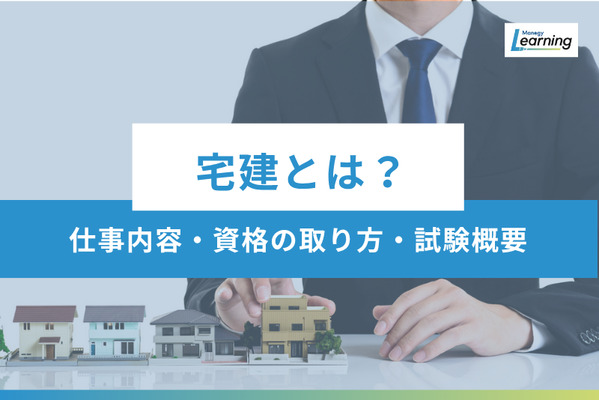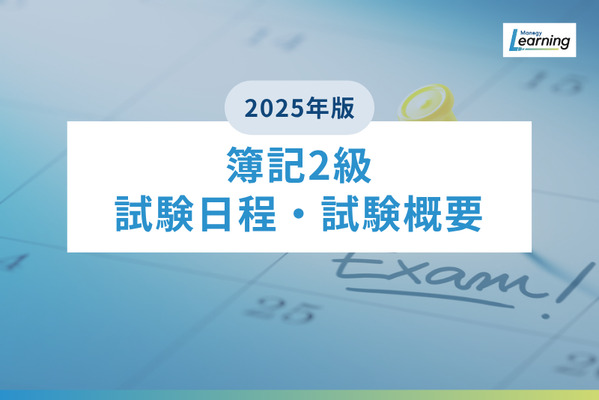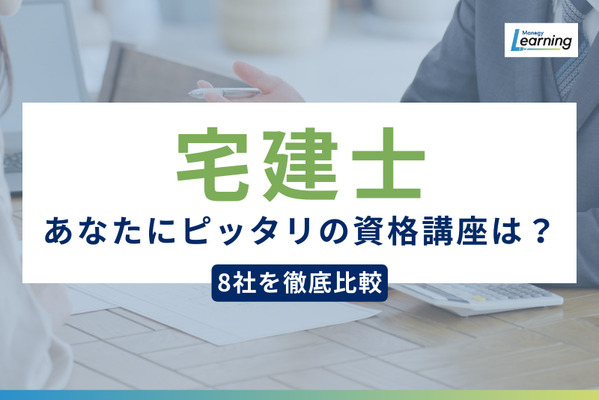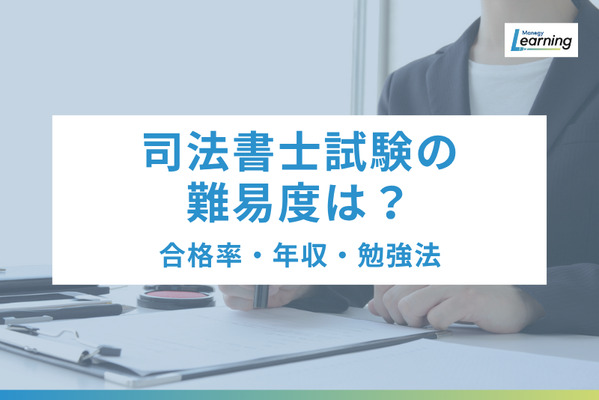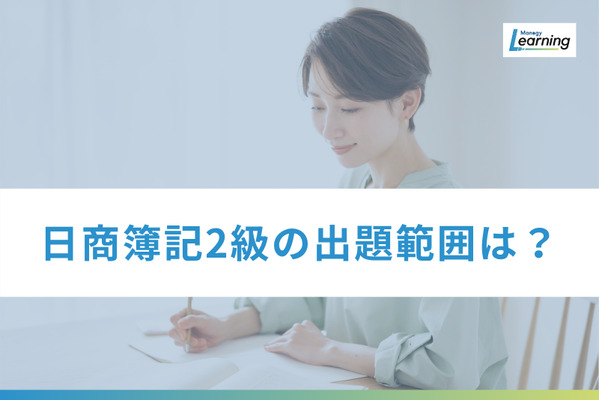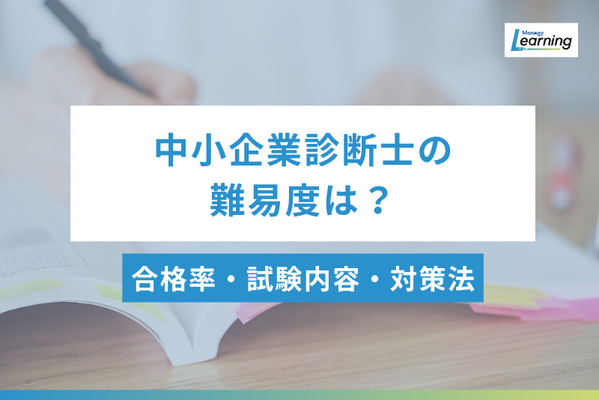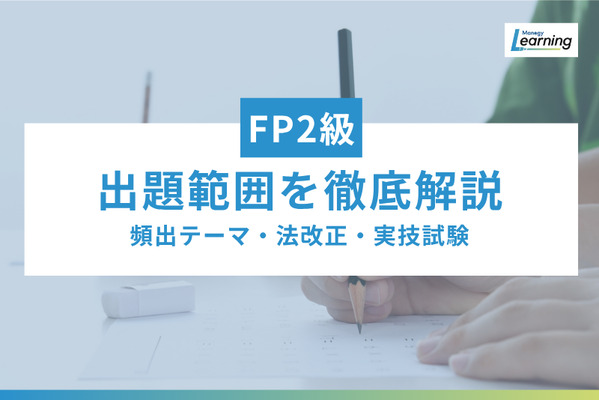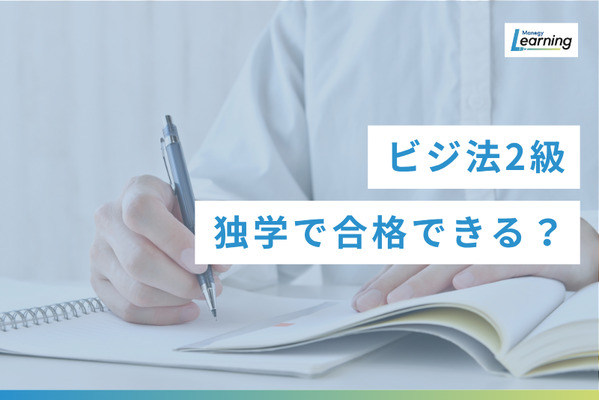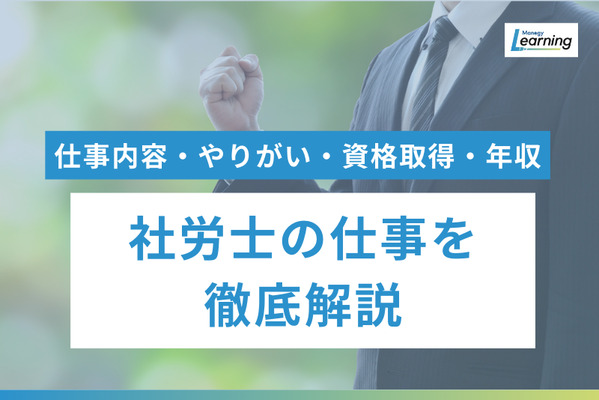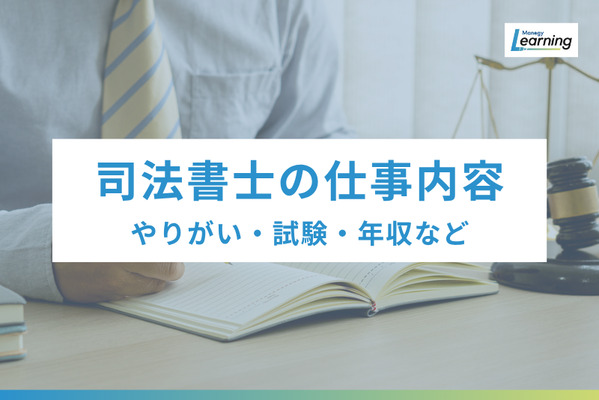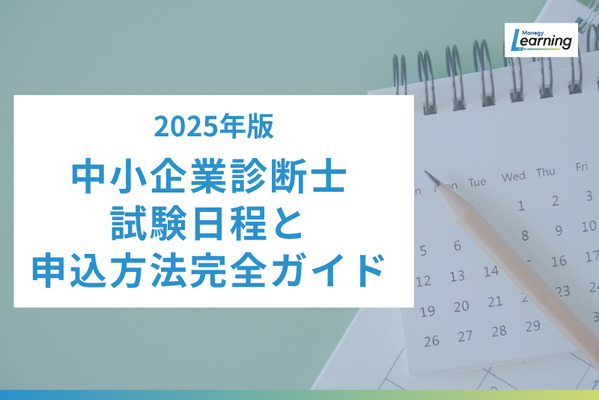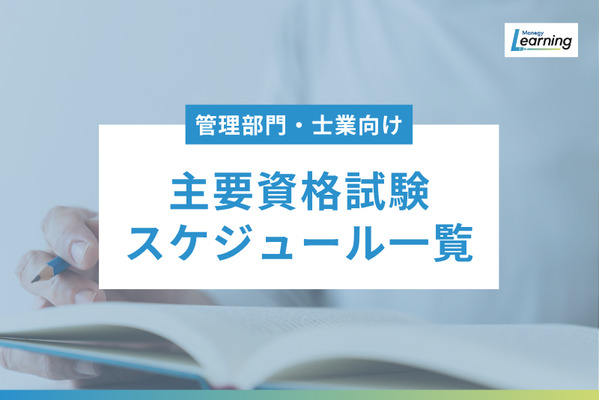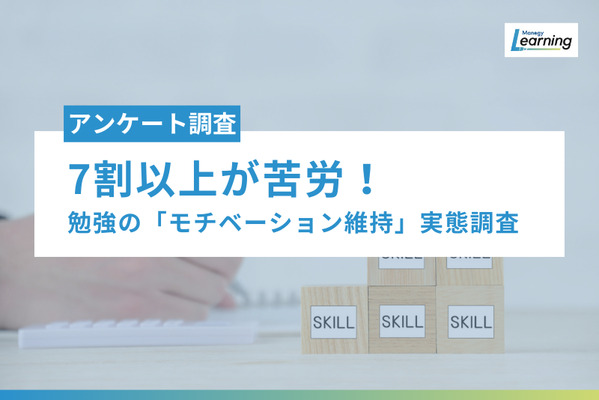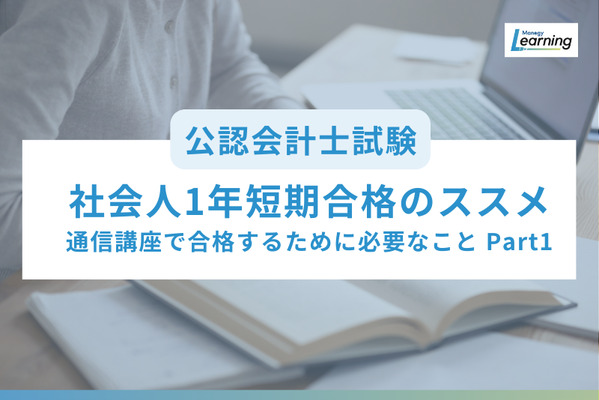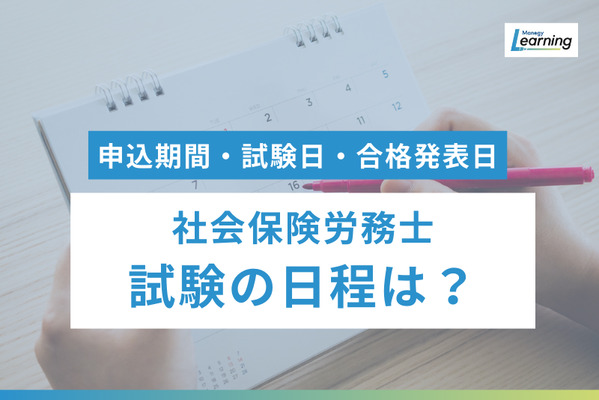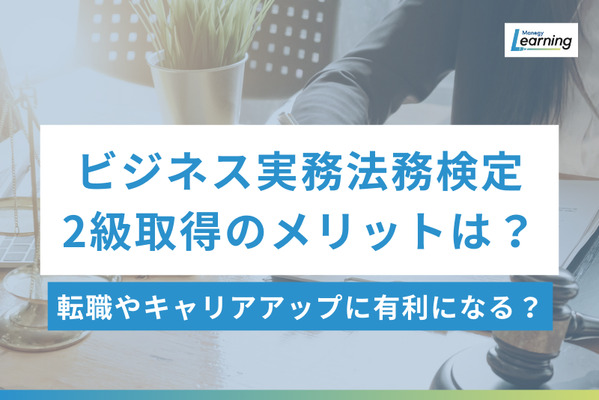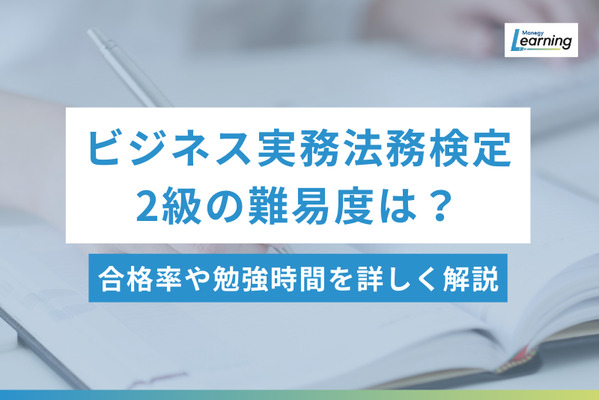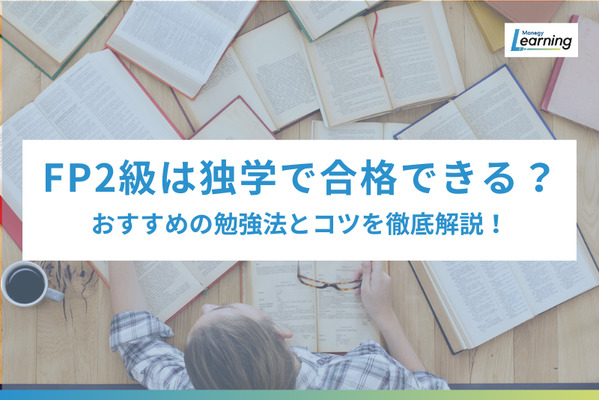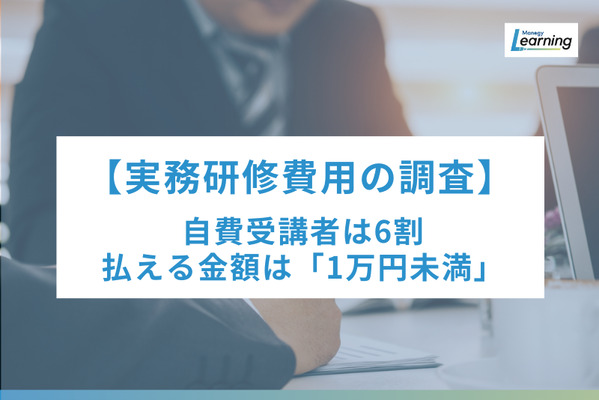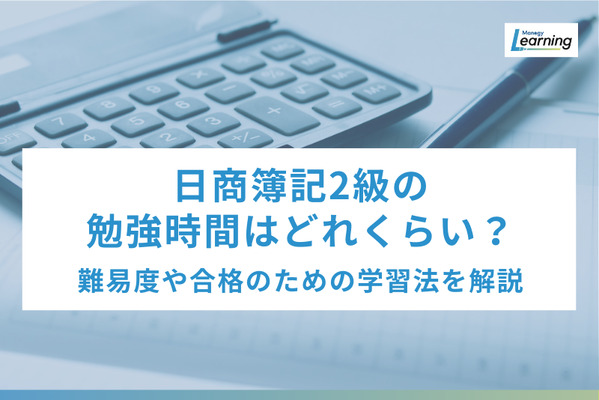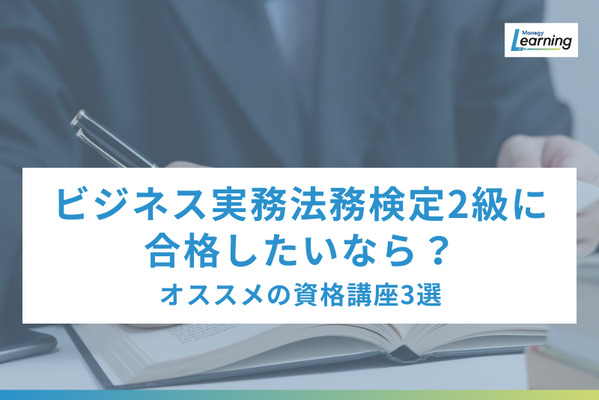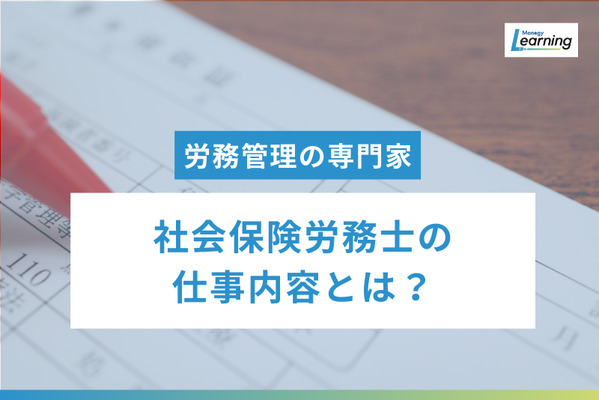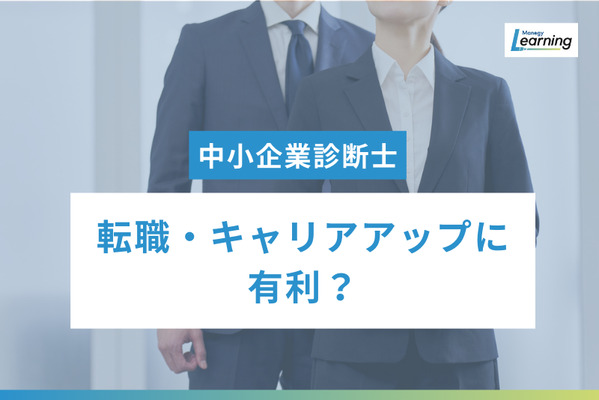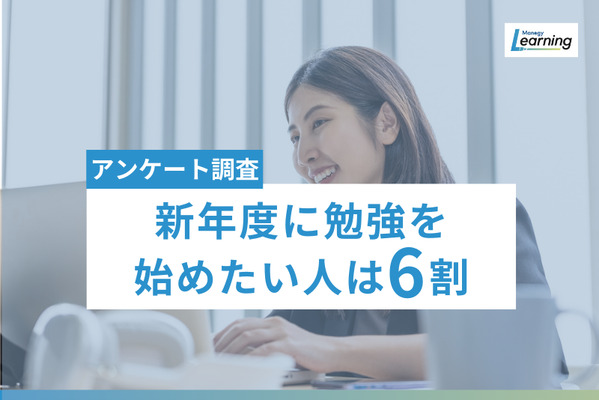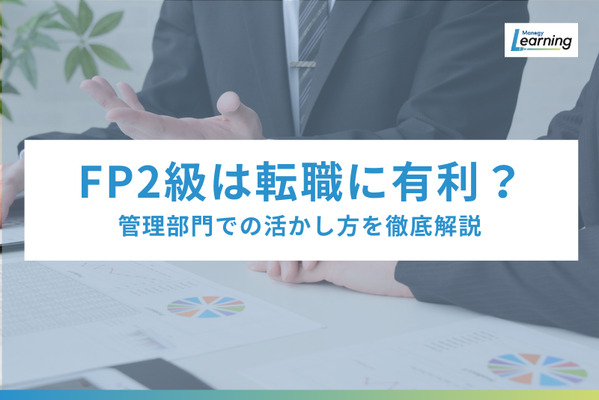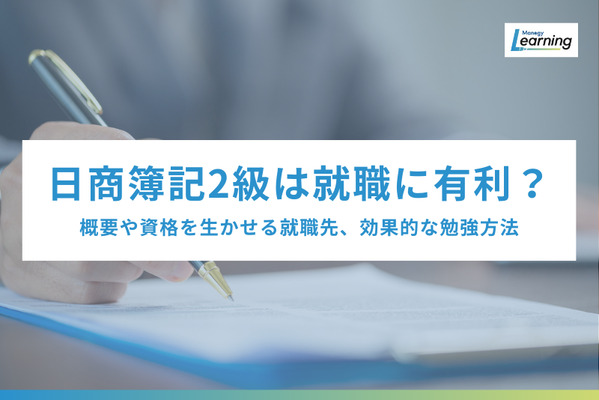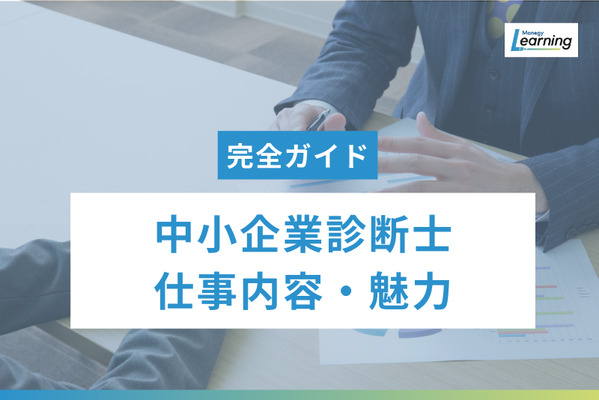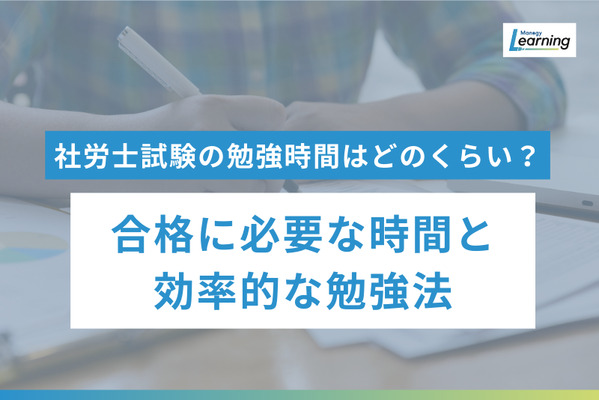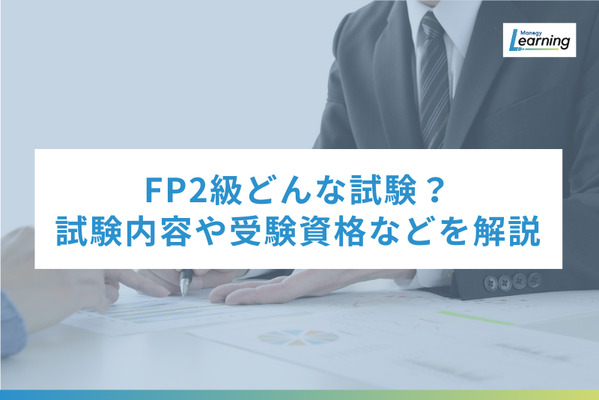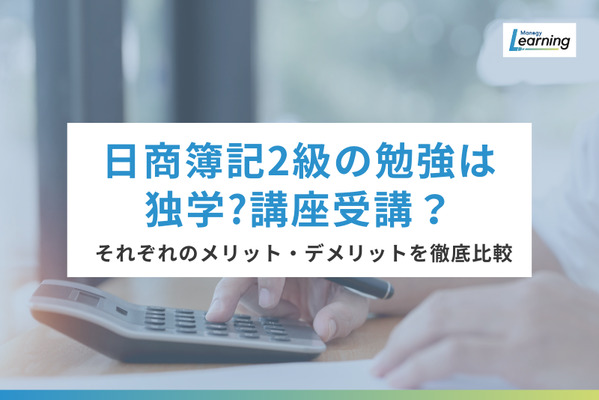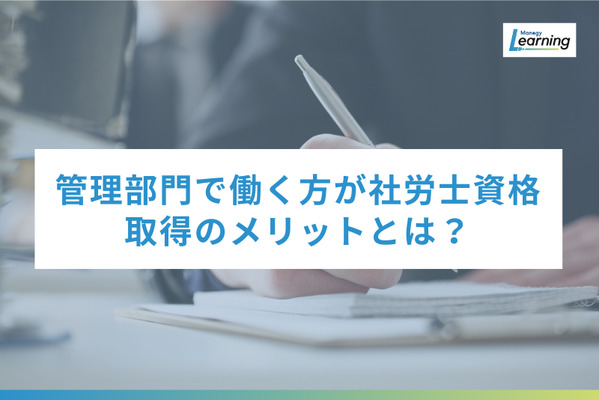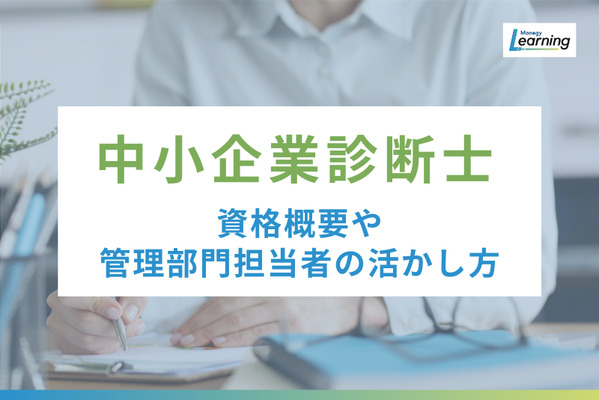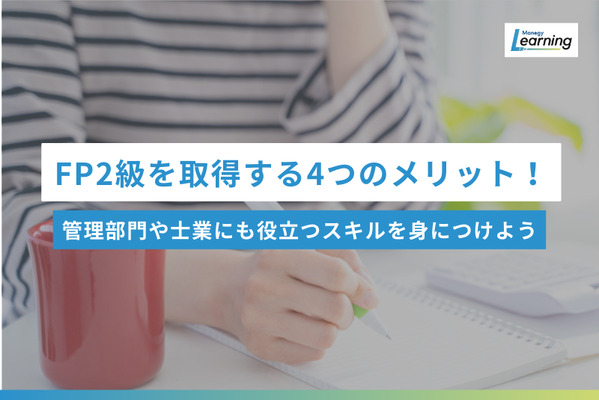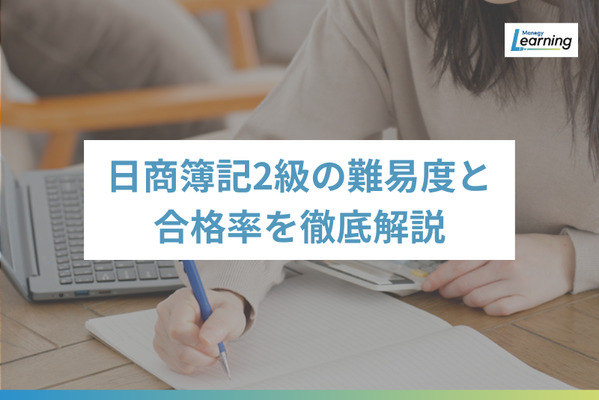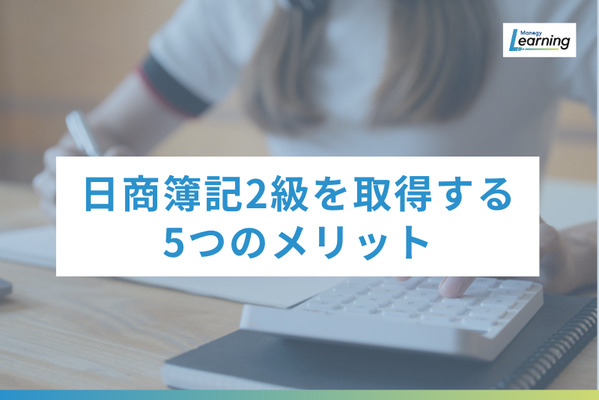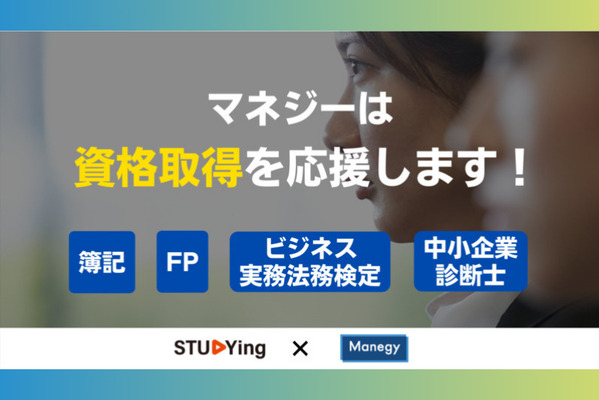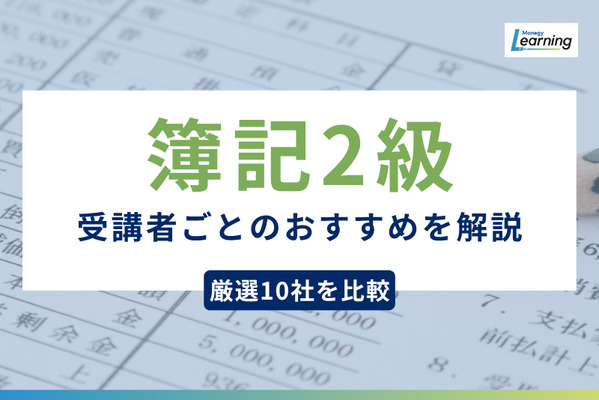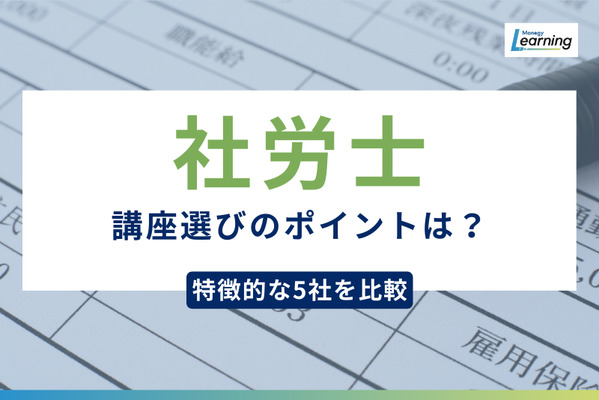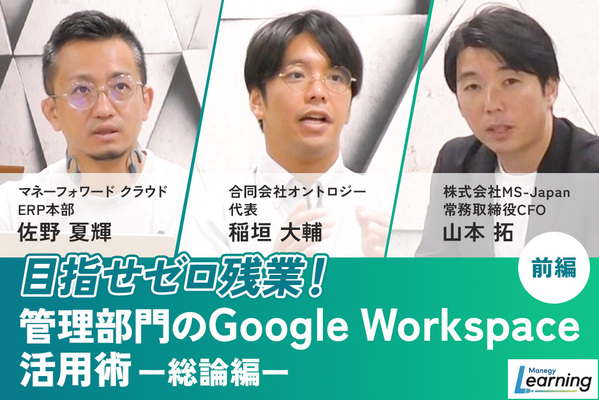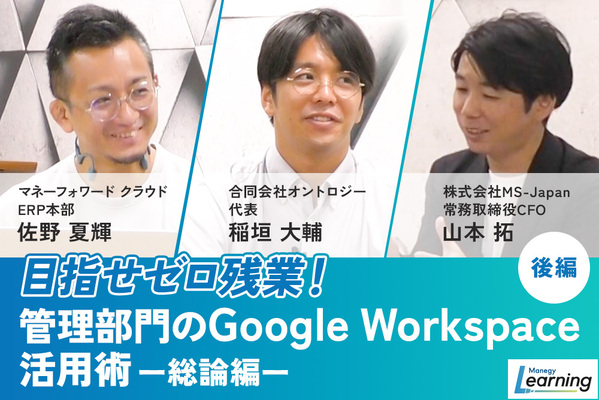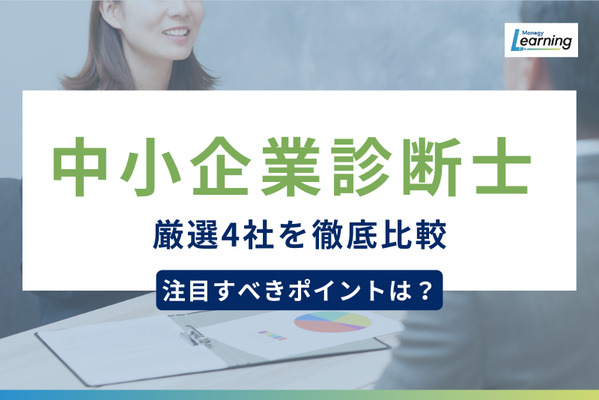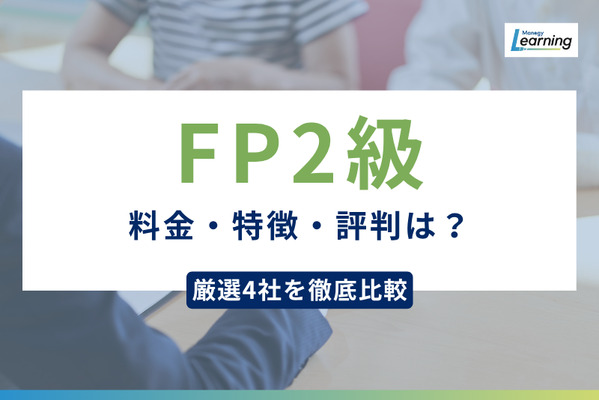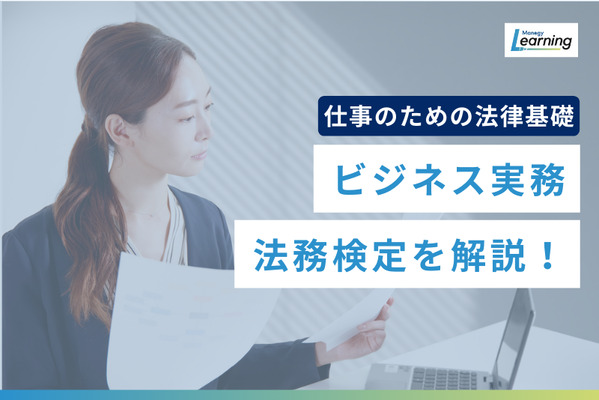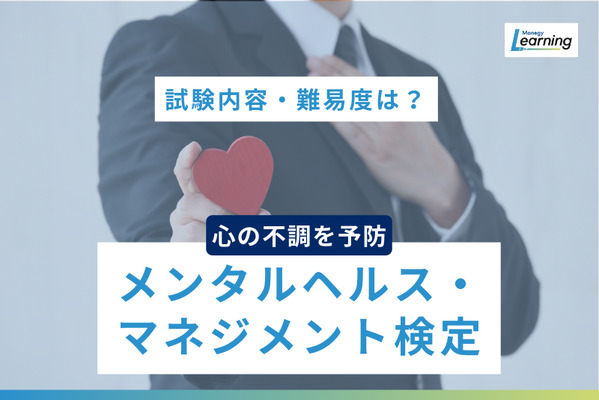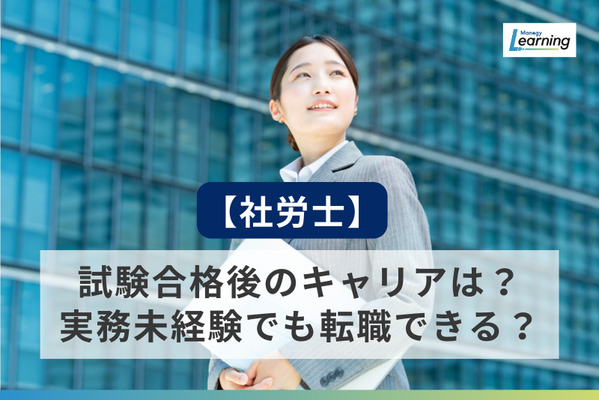社労士は独学で合格できる?向き不向き、勉強法、テキストなどを解説

本記事にはPRおよびアフィリエイトリンクが含まれています。
社会保険労務士(以下「社労士」)は、労働・社会保険に関する専門家として、企業の人事・労務管理や手続きをサポートする国家資格を持つ専門家です。毎年多くの人が社労士試験に挑戦しますが、合格率は低く、難関資格として知られています。受験を目指す方の中には「独学で挑戦したい」と考えている人もいるでしょう。
本記事では、独学合格の可能性、向いている人の特徴、勉強法、テキスト選び、通信・通学講座との比較など、社労士試験を独学で目指すうえで押さえておくべき情報を総合的に解説します。
社労士は独学で合格可能?
社労士試験に独学で挑戦することは可能なのでしょうか。ここでは、主な勉強方法と独学で合格することの現実について解説します。
社労士受験の勉強方法は主に3つ
社労士試験の勉強方法には、主に以下の3つの方法があります。
独学
市販のテキストや問題集を使って、自分のペースで学習を進めます。コストを抑えられる反面、計画性や自己管理能力が問われます。
通信講座
オンラインでの動画講義や教材を用いて勉強します。勉強のスケジュール管理をある程度自分で行うことができ、質問サービスや添削指導などのサポートも充実しているケースが多いです。
通学制講座
スクールに通い、対面で講師の直接指導を受けられます。疑問点をすぐに質問できたり、受験仲間を見つけて情報交換や励まし合いをできたりするのが魅力です。一方、受講料は高めで、通学や授業による時間の制約もあります。
社労士の独学合格は、厳しいのが現実
社労士試験の合格率は例年6~7%と非常に低く、難関資格に分類されます。独学で合格する人も確かに存在しますが、その多くは実務経験者や法学部出身者など、もともと一定の知識がある人が中心です。
法律に初めて触れる初学者が独学だけで合格を目指すのは難易度が非常に高く、まれなケースと言えるでしょう。
社労士の独学が難しい理由は「3つの壁」
なぜ、社労士の試験勉強は独学だと難しいのでしょうか。その背景には「時間」「精神」「情報」に関する3つの大きな壁が存在します。
他の業務内容も詳しく知りたいという方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
時間の壁:社労士の勉強時間は800~1,000時間が目安
合格に必要な勉強時間は、800~1,000時間と言われています。この数字は社労士全体のものであり、独学者に限れば、1,000時間以上かかる可能性は高いでしょう。
働きながら受験する社会人の場合、この膨大な勉強時間をどう捻出するかが最初の大きな課題になります。
精神の壁:独学は孤独とモチベーションとの戦い
独学では、周囲と比較できないため、自分の進捗や理解度に不安を感じやすくなります。また、疑問点が出てきた際には、自力で解決しなければならず、時間がかかったり不正確な理解のまま進んでしまったりするリスクが想定されます。モチベーションを維持する仕組みを作らないと、途中で挫折するリスクが高まります。
情報の壁:独学は最新情報の収集が大変
社労士試験では、法改正や統計データなどについて最新の情報を正確に把握しておく必要があります。しかし、独学の場合、これらの変更に気づくのが遅れたり、理解を誤ったまま学習を進めてしまう可能性があります。
通信講座や通学講座では基本的に最新情報をすぐに得られますが、独学では自ら情報を積極的に集め、適切に学習へ反映させる力が求められます。
社労士の独学に向いている人・向いていない人
社労士の勉強は長期戦になるため、独学を始める前に、自分の性格や経験、ライフスタイルが独学というスタイルに適しているかを見極めることが非常に重要です。
独学に向いている人の特徴
計画的に勉強を進められる人
独学では、誰かに勉強の進捗を管理してもらうことができません。そのため、長期間にわたる勉強計画を自分で立て、それに沿って淡々と実行できる能力が必要です。特に、社労士試験は範囲が広く、各科目にまんべんなく時間をかける必要があるため、勉強計画をしっかり組み、継続的に実行する力が欠かせません。
1人でも学習を継続できる人
質問相手がいない環境でも、勉強への意欲を保ち続けられる人は独学でも合格を目指せるでしょう。日々の進捗管理や理解度の確認も、自己責任としてやり遂げる精神的な強さが求められます。
自分で問題を解決できる人
学習中に発生する疑問点を、書籍やインターネット、資料を駆使して解決する姿勢がある人は、独学でも十分な成果を上げられます。わからないからといって手を止めるのではなく、解決の手段を模索し、論点を自分のものにする力が独学には求められます。
独学に向いていない人の特徴
初学者や人事・総務などの経験がない人
法律や労務知識がない人や、人事・総務の業務経験がない人が、いきなり独学で社労士試験に挑むのは難易度が高いでしょう。用語の理解に時間がかかるうえ、試験の出題傾向や要点がわからないまま勉強を進めてしまうリスクがあります。
計画と実行が苦手な人
計画を立てることが苦手な人や、立てても継続して実行できない人は、独学では計画倒れになりがちです。特に、社会人で仕事と勉強を両立する場合、スケジューリング能力は非常に重要です。
人に質問しながら学びたい人
疑問をすぐに誰かに質問したい人や、コミュニケーションを取りながら理解を深めたいというタイプの人は、一人で進める独学では不安やストレスを感じやすいかもしれません。
この記事を読んだ方にオススメ!
社労士を独学で勉強する際のポイント
独学での学習を成功させるには、戦略的かつ実行可能な方法で学習を進めることが不可欠です。以下のポイントを意識して、学習の質を高めていきましょう。
無理のない勉強スケジュールを立てる
社労士試験の勉強は長期戦です。最初から「毎日5時間勉強する」といったハイレベルな目標を設定すると、途中で燃え尽きてしまうリスクがあります。まずは、平日は1時間、休日は2~3時間と実現しやすい時間から始め、徐々に学習時間を延ばしていく方法がおすすめです。
インプット・アウトプットのバランスを意識する
勉強は、テキストや講義などから知識を得る「インプット」と、問題を解いたり説明したりする「アウトプット」の両方が大切です。脳科学の研究では、効果的な勉強方法として、「インプット3割:アウトプット7割」のバランスが推奨されています。
なぜなら人間の脳は、「使う情報」を重要と判断する性質があるためです。
まずは、テキストなどを読み、基本的な知識をおさえるインプット(3割)をしてから、過去問や精選問題をひたすら解くアウトプット(7割)を実行しましょう。間違えた問題は、テキストに戻って再度学んでから解き直し、再度インプットから行いましょう。
苦手科目を作らない
社労士試験の大きな特徴として、科目ごとに「合格基準点」があります。総合得点が基準を満たしていても、1科目でも基準点を下回ると不合格になるのです。そのため、バランスよく全科目を学習することが、合格への鍵となります。つい得意科目ばかりを勉強してしまいがちですが、苦手科目こそ積極的に取り組み克服する事が大切です。
この記事を読んだ方にオススメ!
社労士の独学におすすめの教材
教材選びは、学習効率と合格の可能性を大きく左右します。市販の教材を選ぶときには、信頼性・分かりやすさ・法改正への対応などを重視しましょう。
教材選びのコツ
最新版のものを選ぶ
法律は随時改正されるため、古いテキストでは試験に対応できません。最新版のテキストや問題集を使用するのがベストです。
図やイラストが豊富なものを選ぶ
文章ばかりのテキストは、初学者にはハードルが高いものです。図表やイラストを多用した、視覚的に理解を助けてくれる教材は記憶の定着にも役立ちます。
シリーズ化されたものを選ぶ
テキストと問題集が連携しているシリーズ化されたものは、インプットとアウトプットを効率よく行うことができます。
社労士の勉強に役立つおすすめ教材
テキスト関連
2025年度版 みんなが欲しかった! 社労士の教科書(TAC出版)
図表が豊富で、初学者や独学者にも理解しやすい構成です。
うかる!社労士 テキスト&問題集 2025年度版(日本経済新聞出版)
最新の法改正に対応したテキスト+過去5年分の過去問で構成されており、この本だけで合格に必要な知識が身に付きます。
ごうかく社労士基本テキスト〈2025年版〉(中央経済グループパブリッシング)
試験の頻出事項を網羅した豊富な情報量と、過去問を解きながら読み進められる実践的な構成で、合格に必要な知識が効率よく身につきます。
2025年版 社労士 合格のトリセツ 基本テキスト(東京リーガルマインドLEC総合研究所 社会保険労務士試験部)
全編オールカラーと豊富なイラスト・図解で、視覚的に理解しやすく、挫折しないで学び始められる工夫がされています。
問題集・過去問関連
みんなが欲しかった!社労士の問題集 2025年度版(TAC出版)
択一式問題と選択式問題それぞれにつき、本試験と同じ形式で演習をすることができ、過去の本試験と予想問題を同時に必要な分だけ確認できます。
社労士 合格のトリセツ基本問題集 2025年版(東京リーガルマインド)
アプリ付きで、全ての問題がスマートフォン・タブレット・PCなど、さまざまなデバイスでいつでも学習できます。
ごうかく社労士基本問題集[過去&予想]〈2025年版〉(中央経済グループパブリッシング)
『基本テキスト』に完全準拠しており、テキストでのインプット直後に対応する問題を解くことで、知識を効率よく確実に定着させられる点
2025年版 ユーキャンの社労士 過去&予想問題集(自由国民社)
論点別問題350問の全肢解説と予想模擬試験が、合格へと導いてくれる問題集の決定版です。
効率的な学習には講座の受講もおすすめ
独学での合格も可能ですが、講座を受講することは合格への有力な選択肢です。専門家のサポートは、出題範囲が広く、法改正も多い社労士試験において大きな助けとなります。
通信・通学講座に共通する最大のメリットは、法改正や最新情報に完全対応した教材で学べる点です。これにより、常に最適な状態で試験勉強に集中できます。
通信講座のメリット
- 自分のペースで学習できる
時間や場所に縛られず、通勤中や家事の合間など、スキマ時間を有効活用できます。 - コストパフォーマンスが高い
通学講座に比べて受講料が安価な傾向にあり、費用を抑えつつ質の高いサポートが受けられます。
通信講座のデメリット
- 対面サポートがない
講師への質問はメールなどが中心になるため、その場で疑問を解決できない場合があります。 - 自己管理が必須
学習ペースを自分で管理し、モチベーションを維持する強い意志が求められます。
通学制講座のメリット
- 講師から直接指導が受けられる
疑問点をその場で質問・解決でき、講師の実務経験を交えた解説は理解を深めます。 - 受験仲間と切磋琢磨できる
同じ目標を持つ仲間がいる環境は、モチベーション維持の助けになります。
通学制講座のデメリット
- 受講料が高額
受講料は20万円以上になることも多く、金銭的な負担が大きくなります。 - 時間と場所の制約
決まった日時に校舎へ通う必要があり、仕事などとの両立が難しい場合があります。
この記事を読んだ方にオススメ!
社労士は自分に合った勉強法で合格を目指そう!
社労士試験は合格率が非常に低い難関国家資格です。独学で合格することは可能ですが、時間管理・情報収集・自己解決力においてかなり高度なスキルが求められます。自分の性格や勉強スタイルに合った方法を見極め、必要であれば通信講座や通学講座の導入も検討するのがよいでしょう。
社労士の資格は、あなたのキャリアを大きく後押しする力になります。ぜひ、ご自身に合ったスタイルで合格を掴み取ってください。

Manegy Learning
Manegy Learningは管理部門・士業の皆さまに向けて、実務に役立つTIPSや資格取得のためのスクール取得などの情報を発信し、みなさまの学びをサポートします。
MS-Japan
https://www.manegy.com/learning/