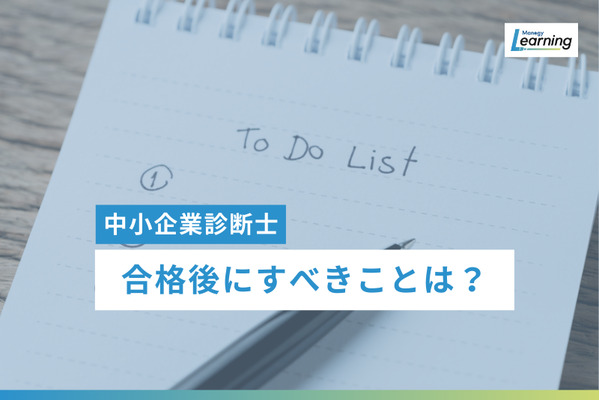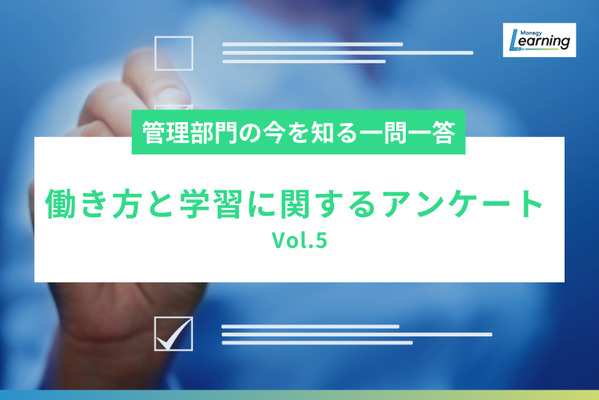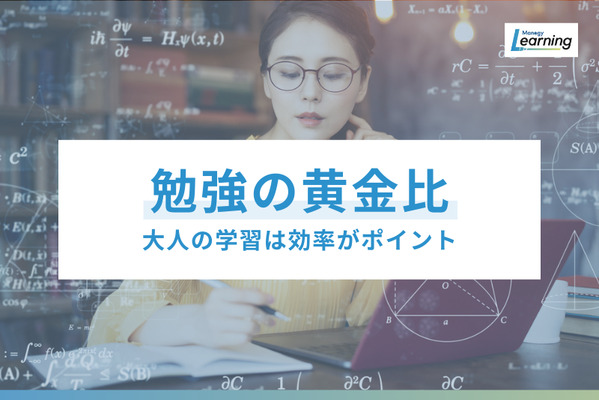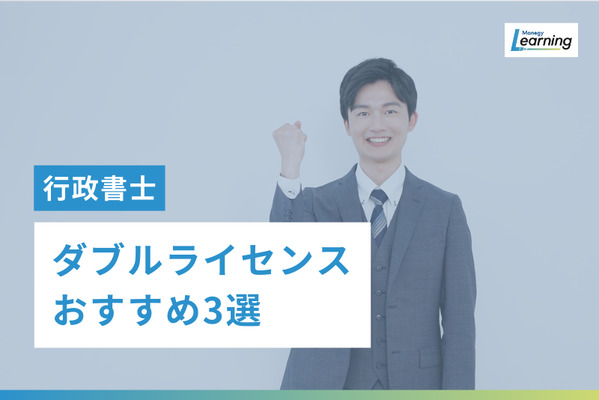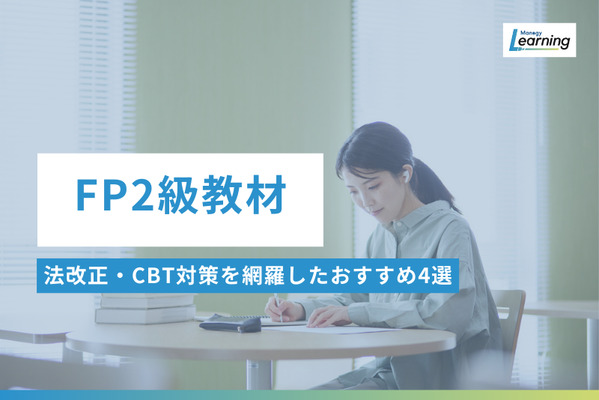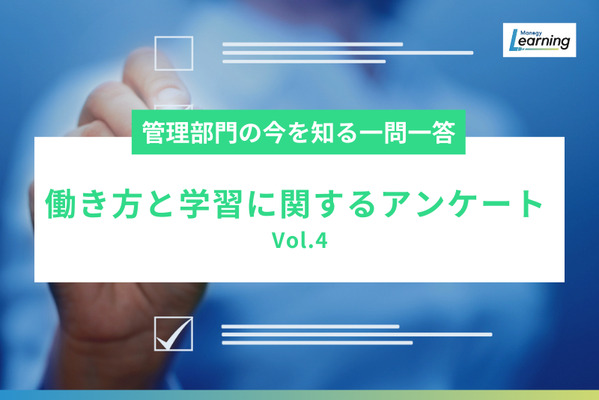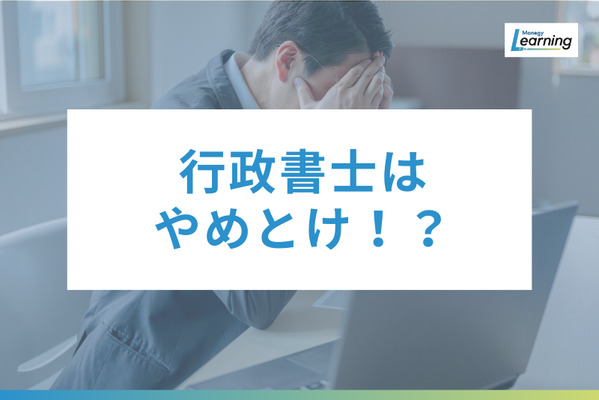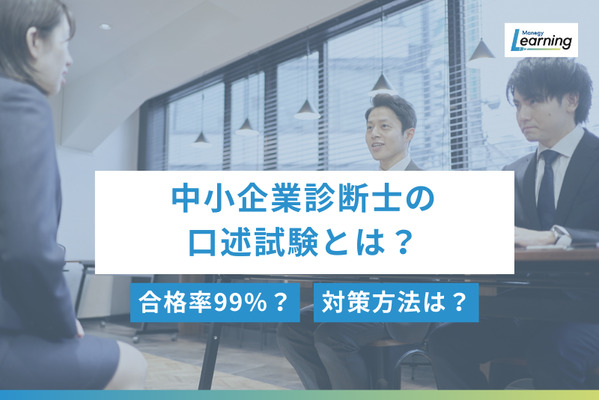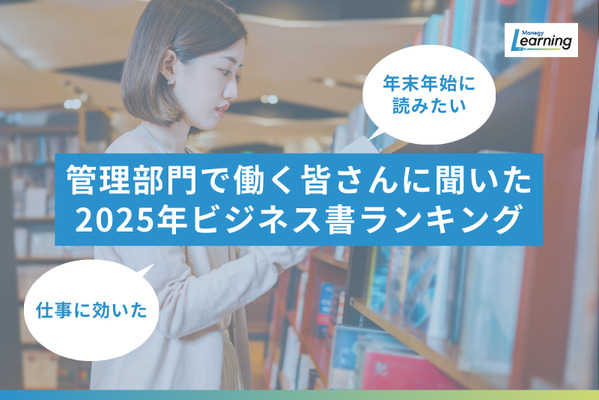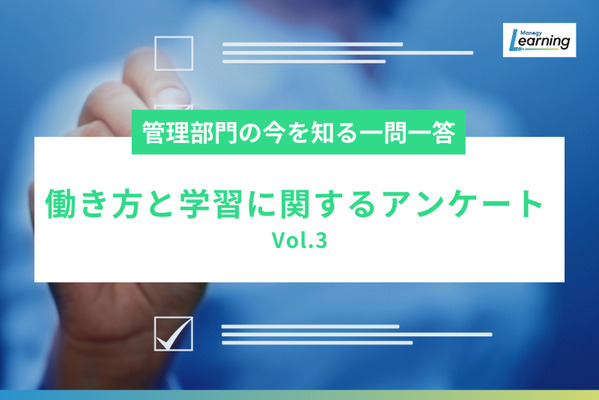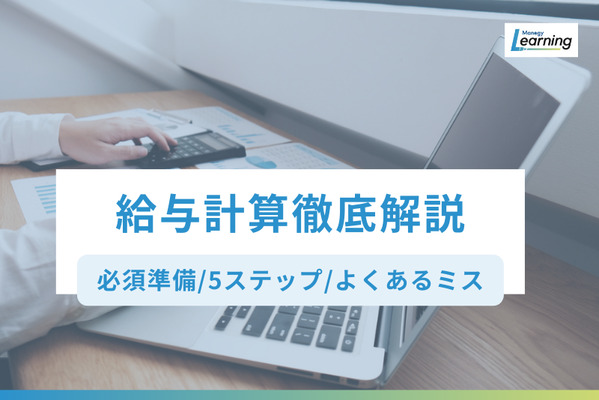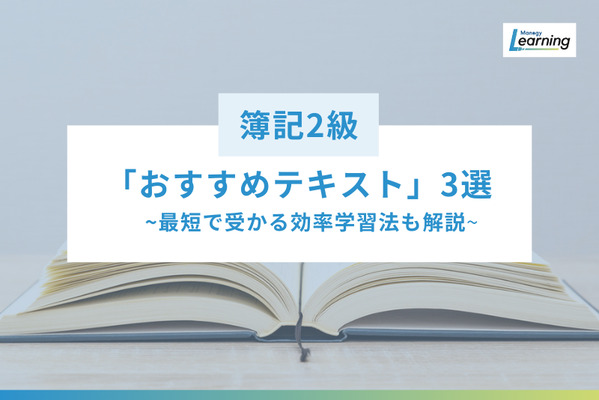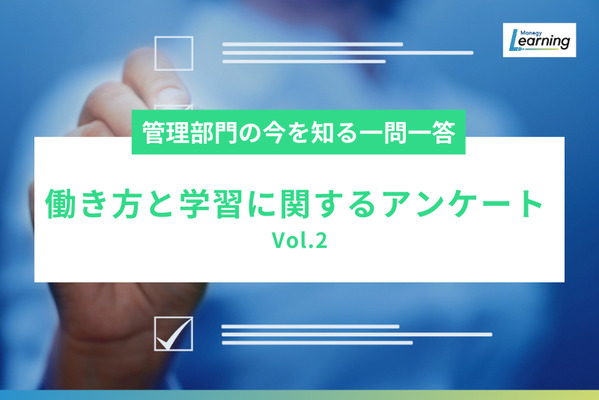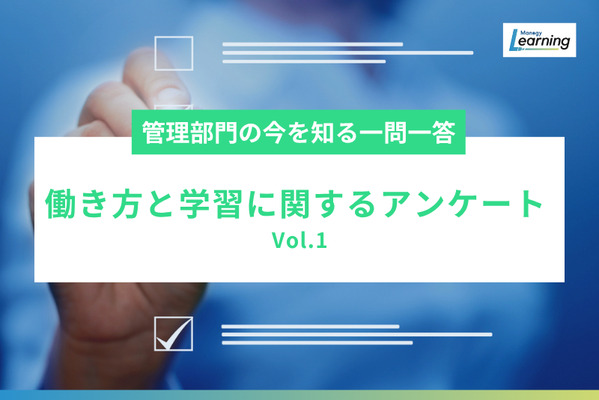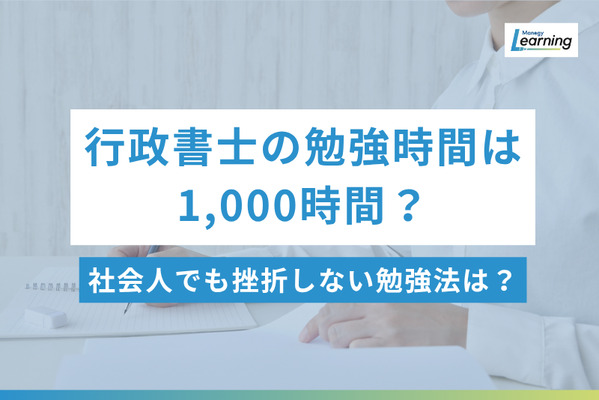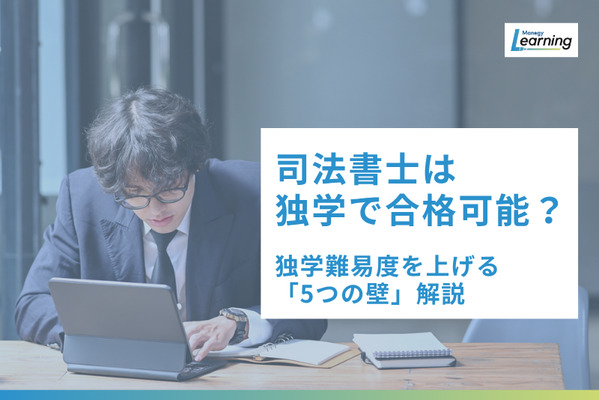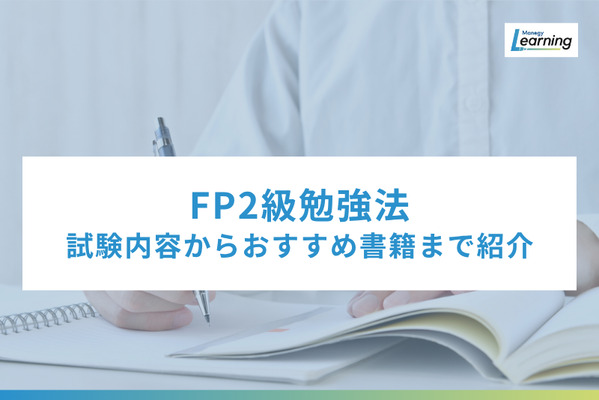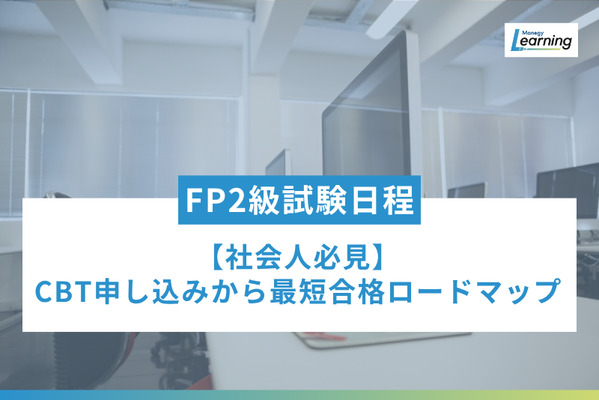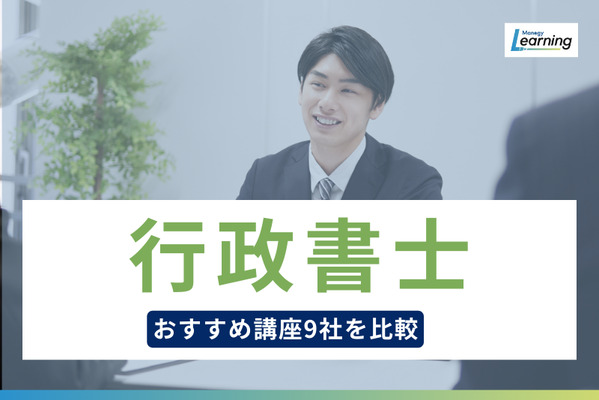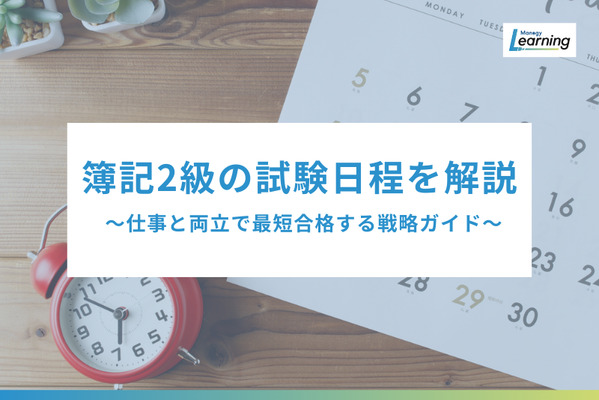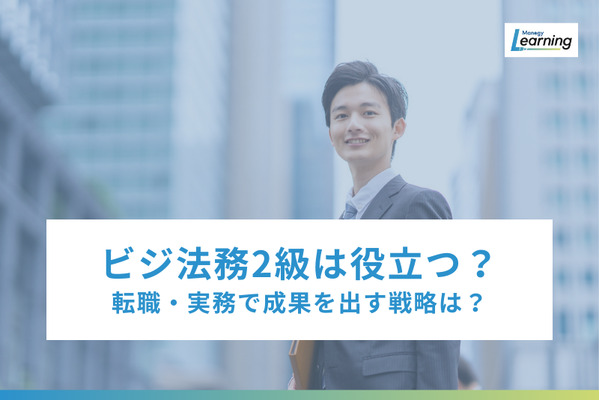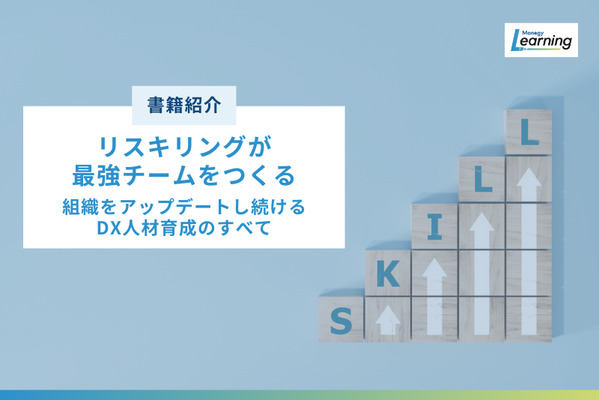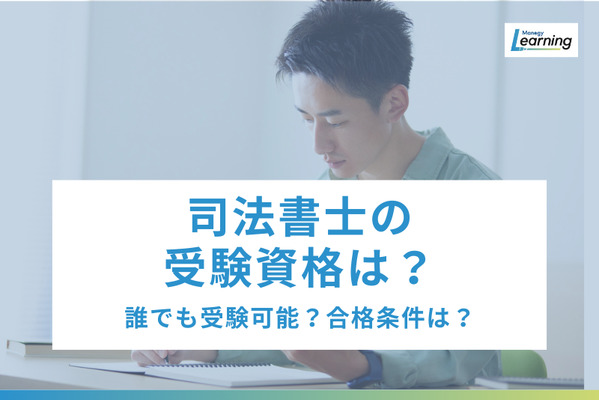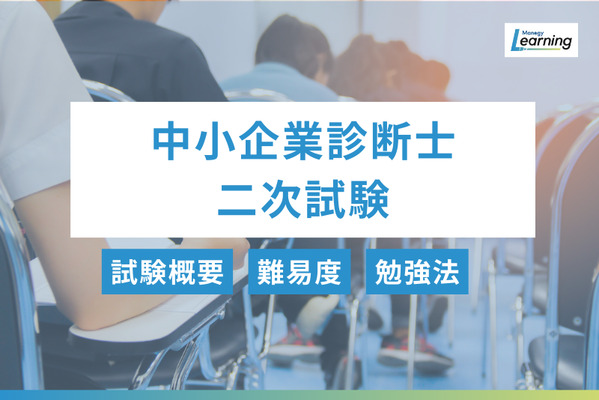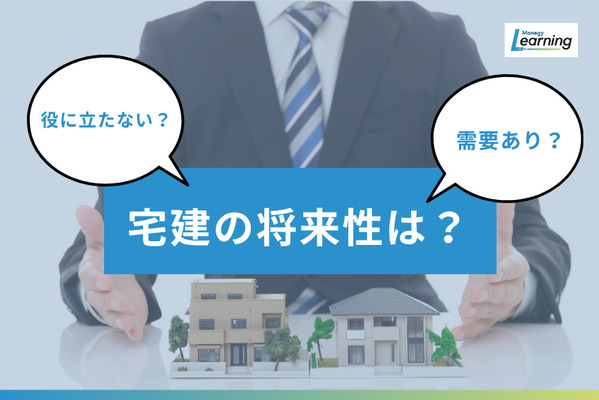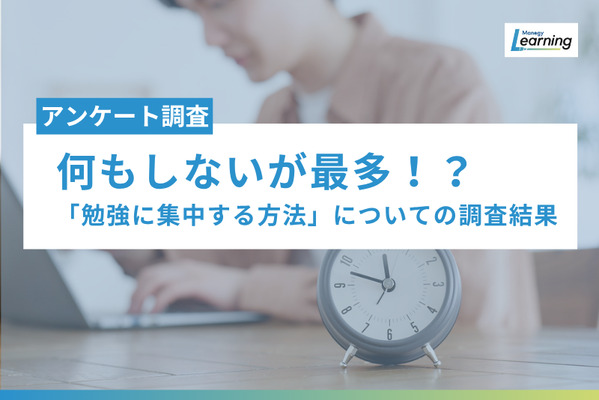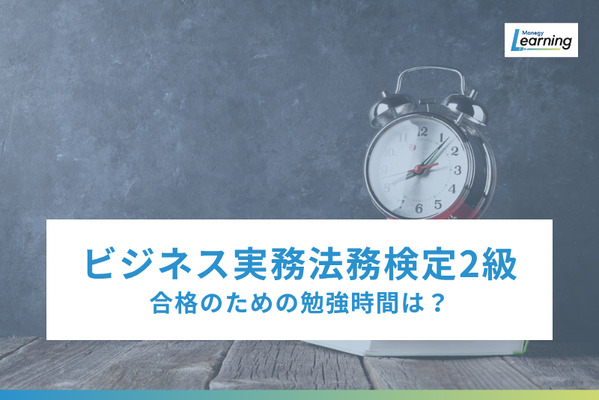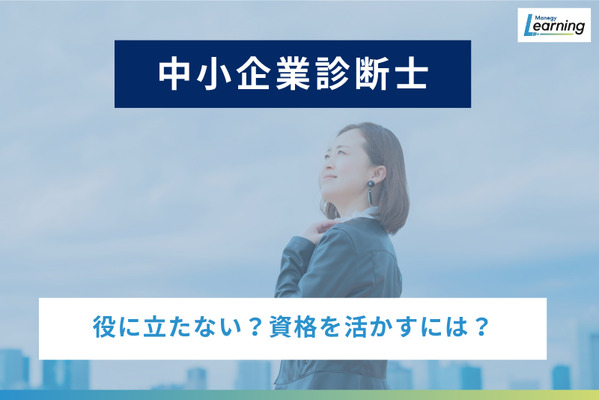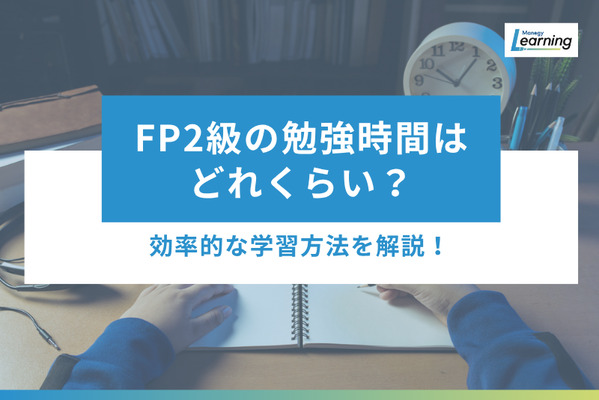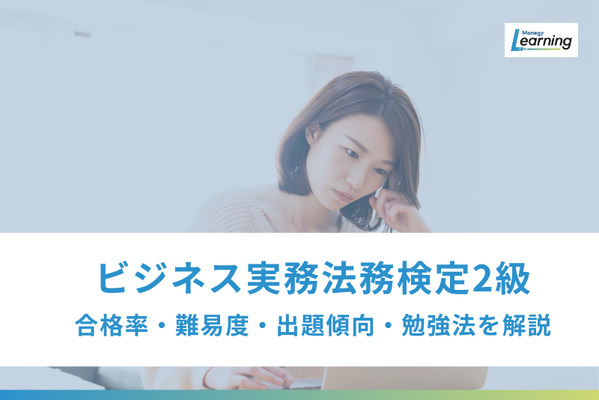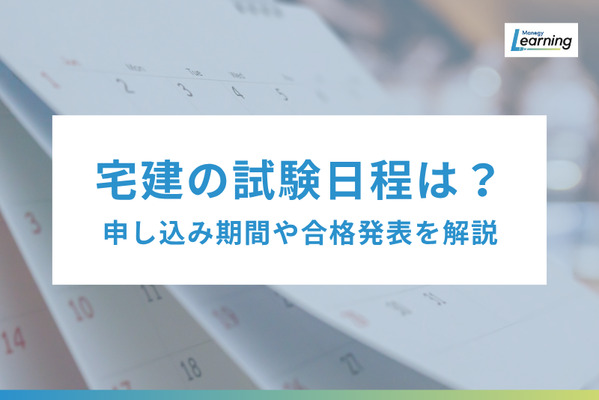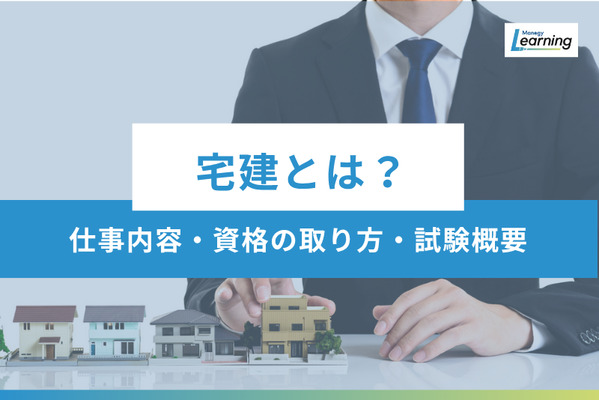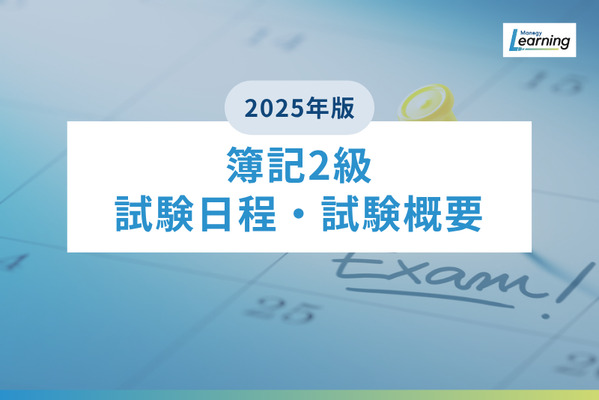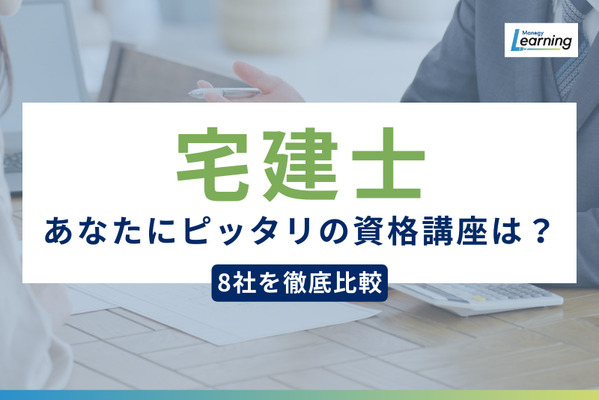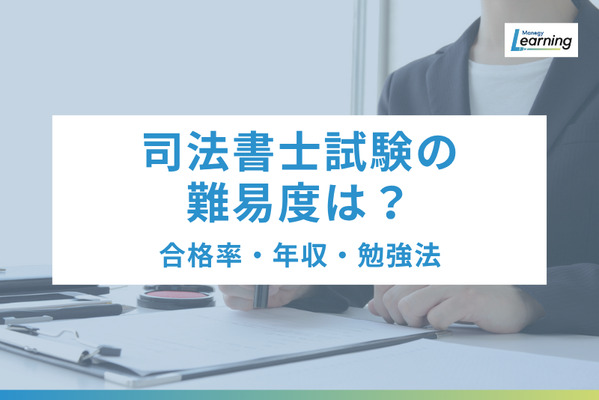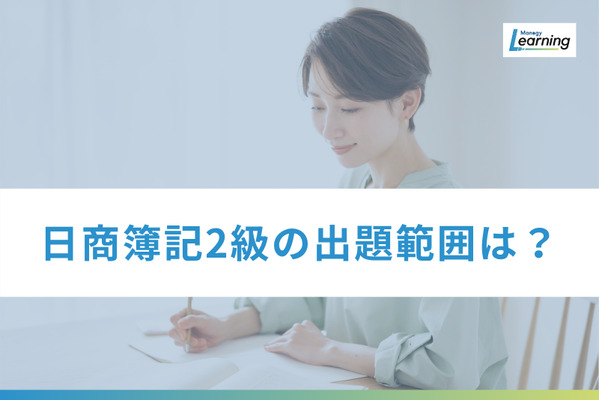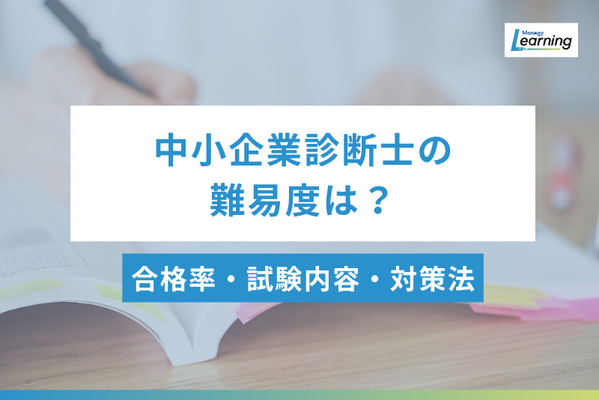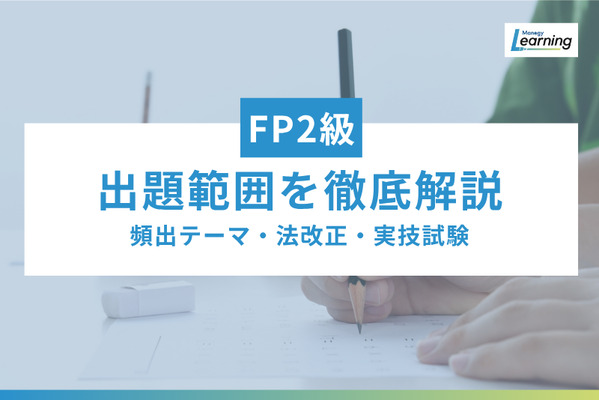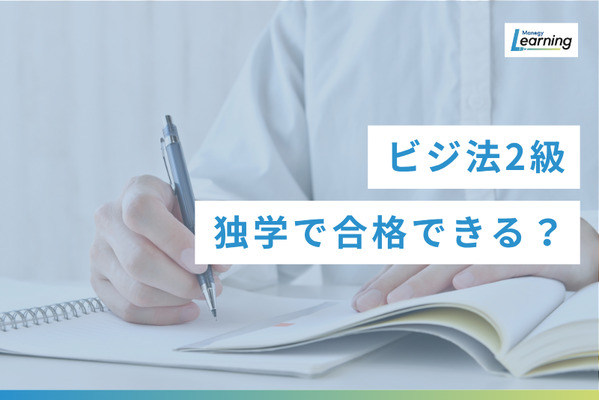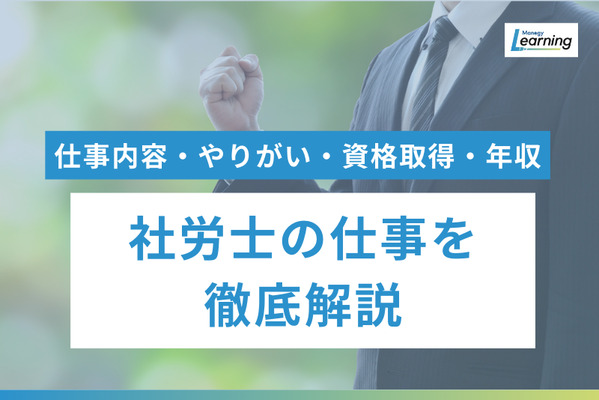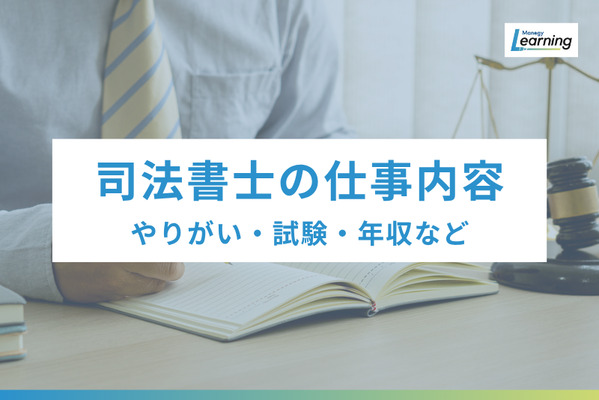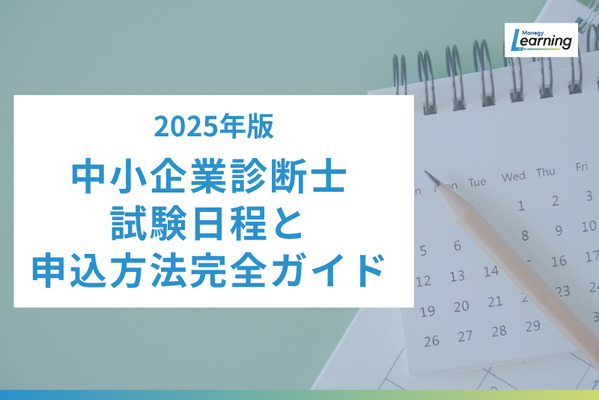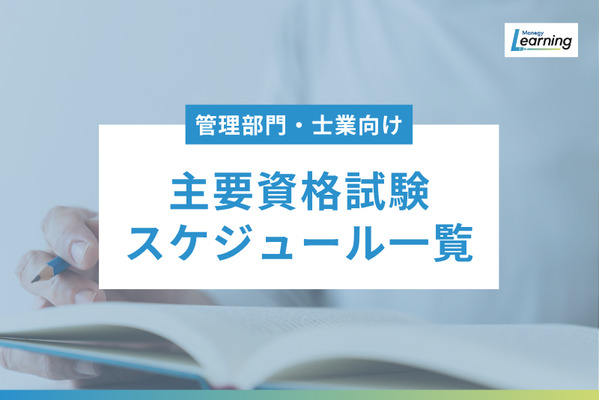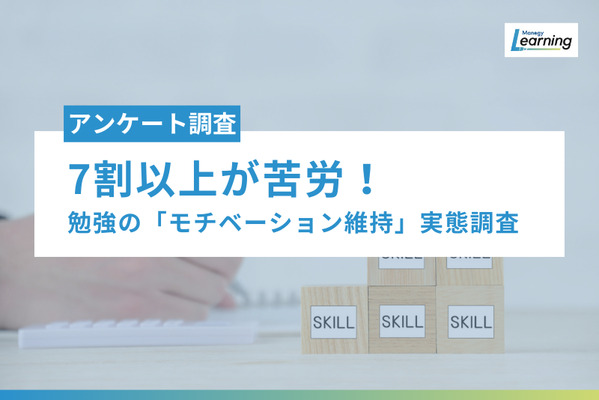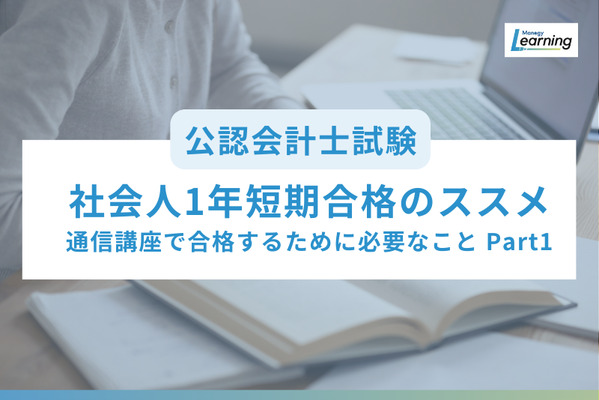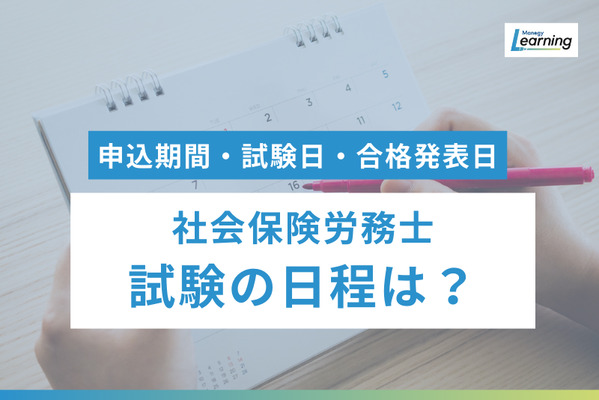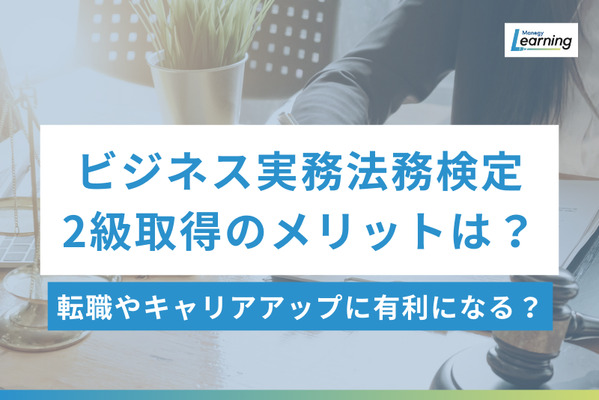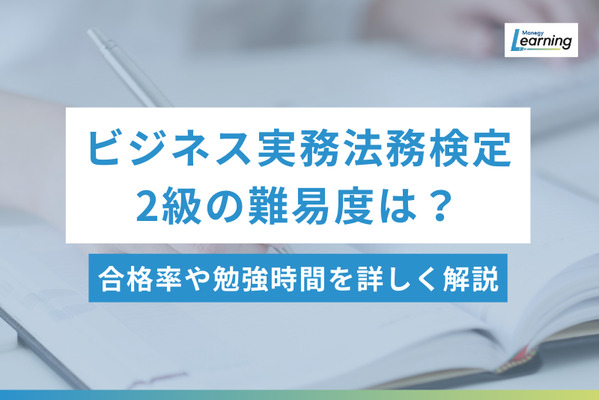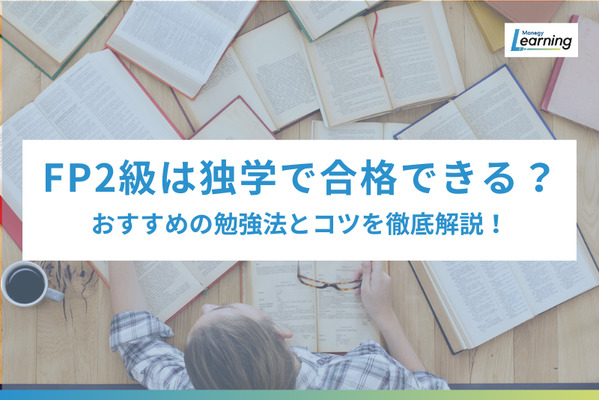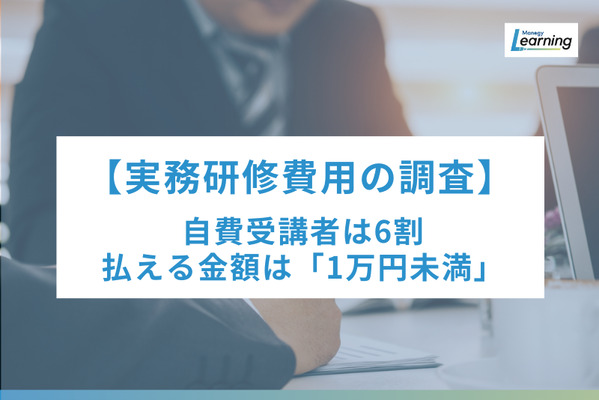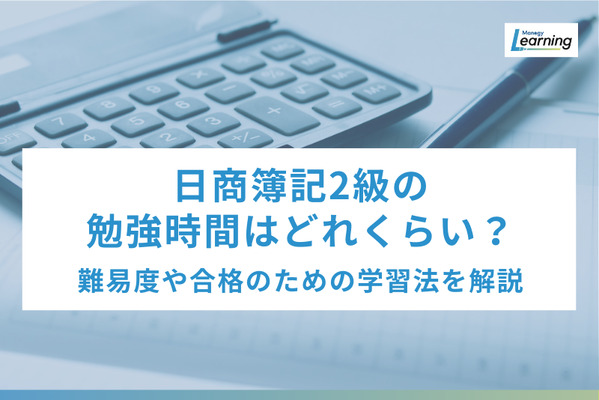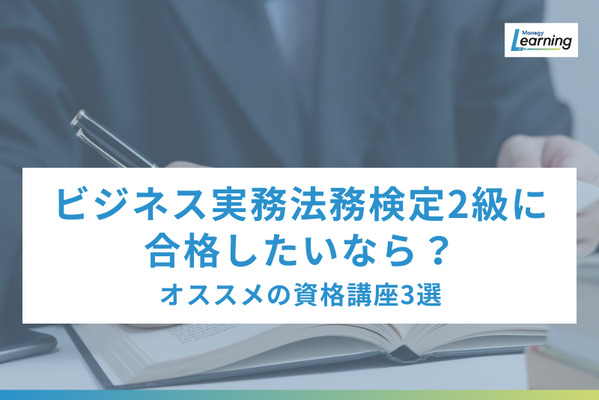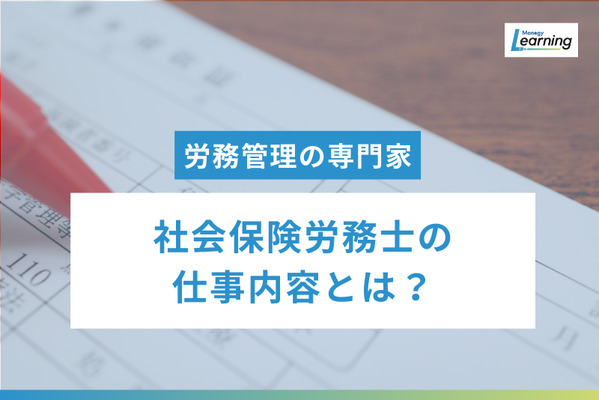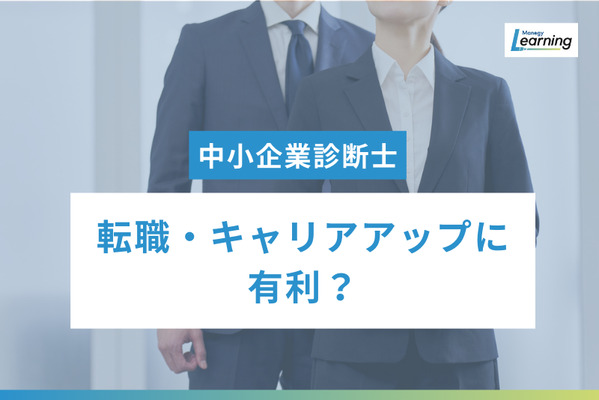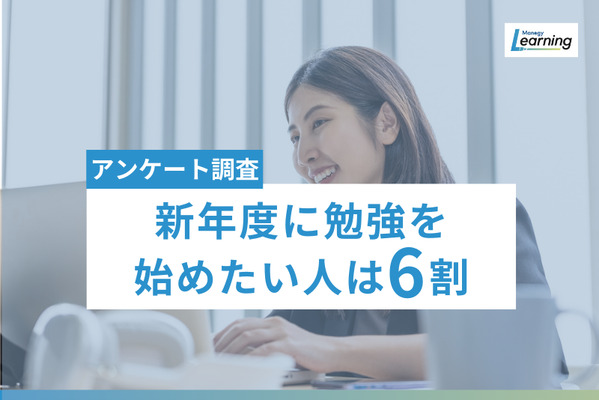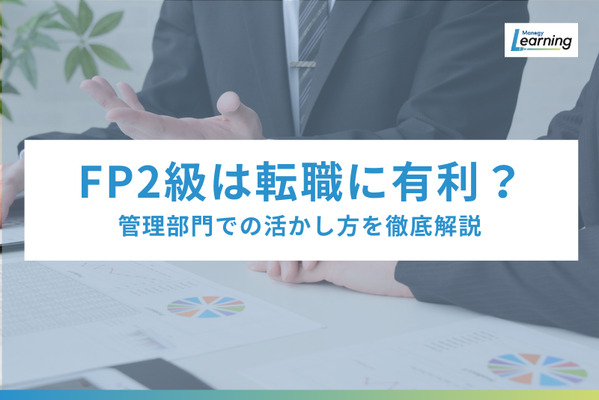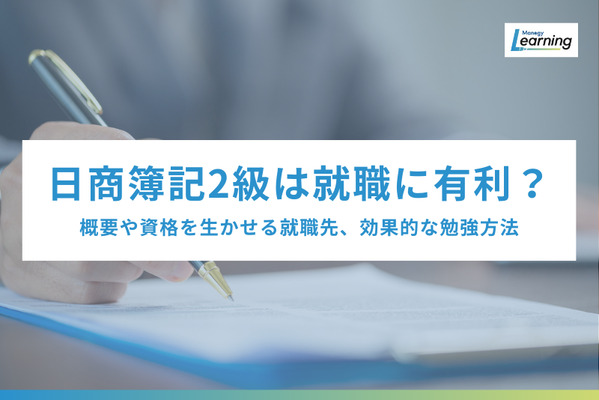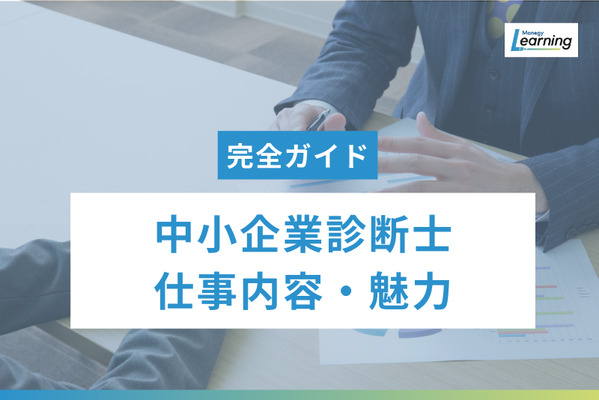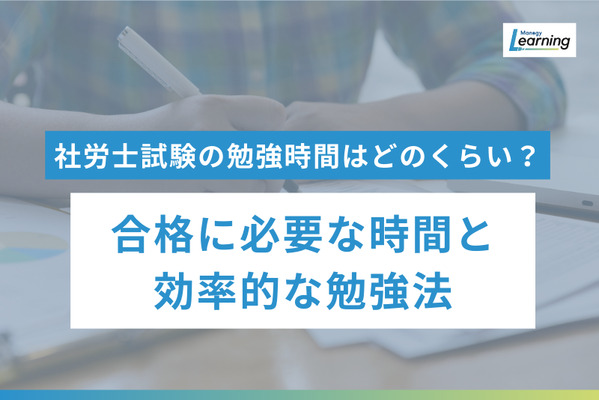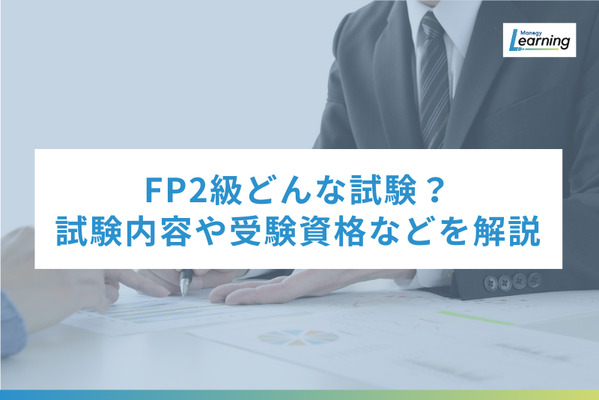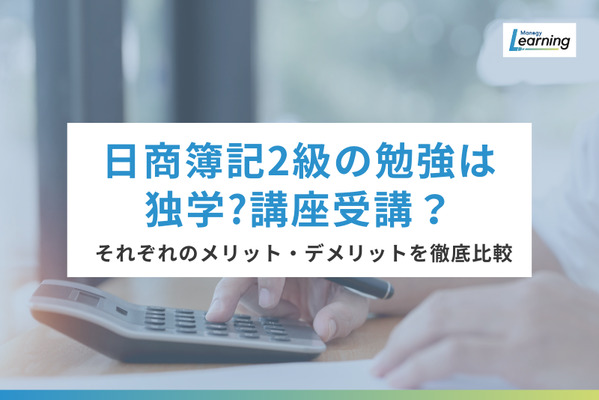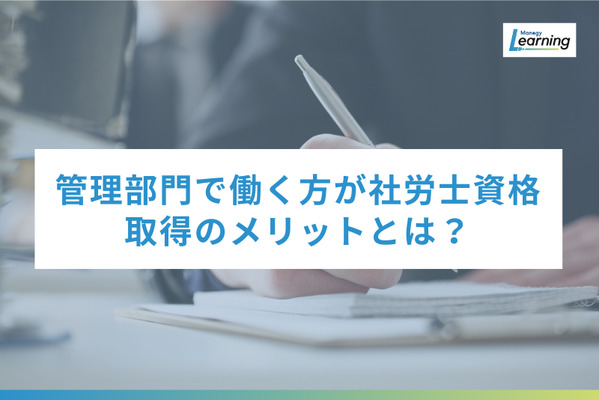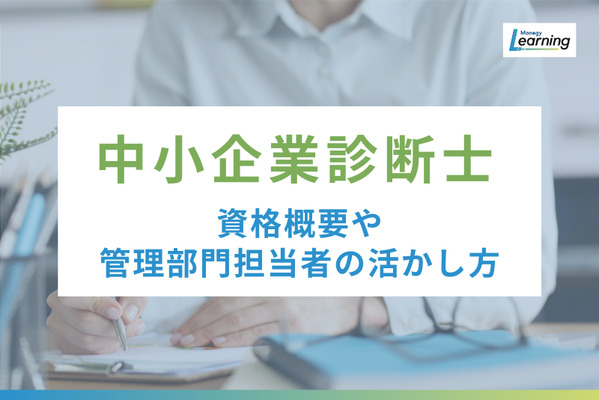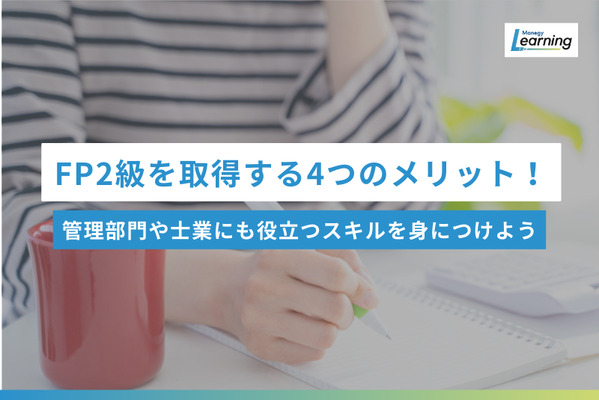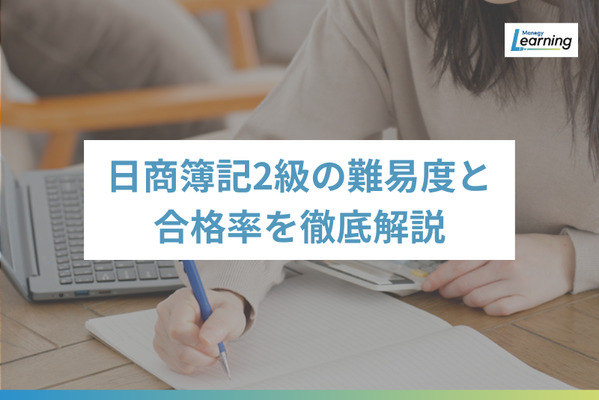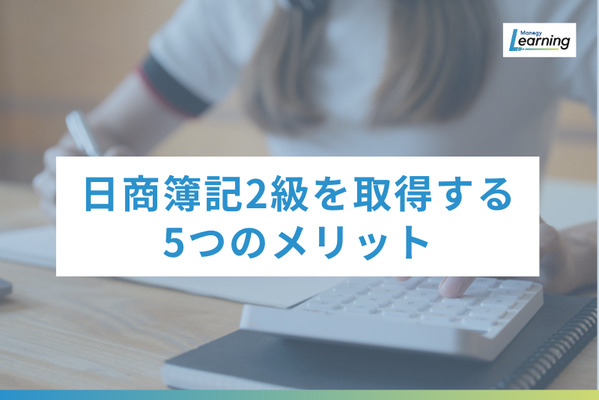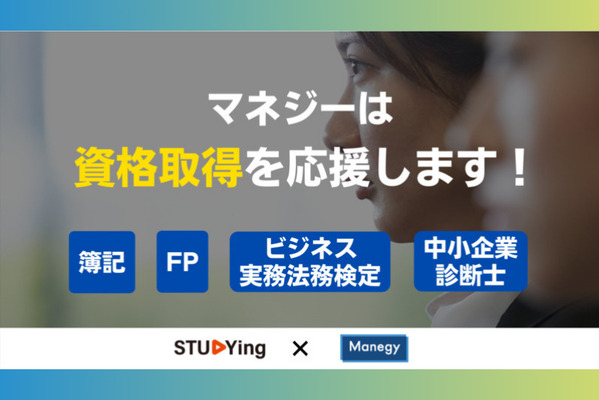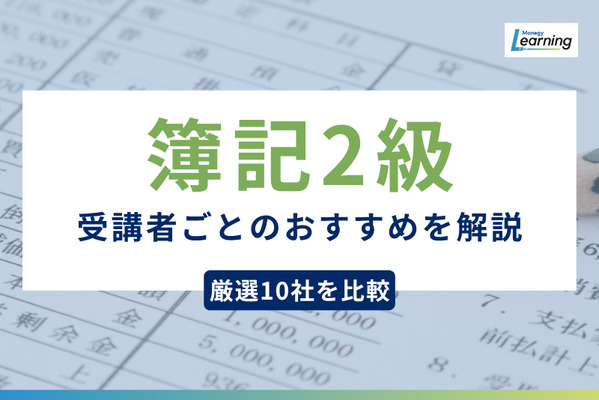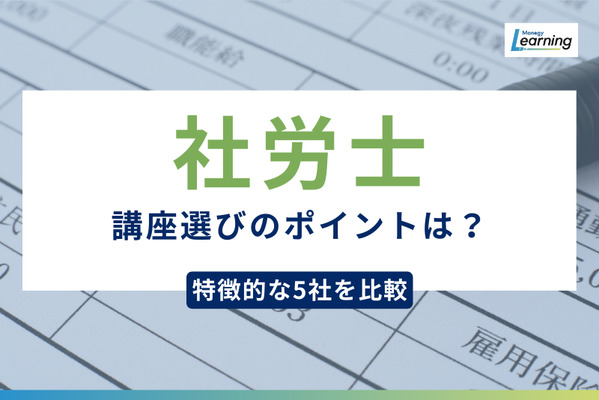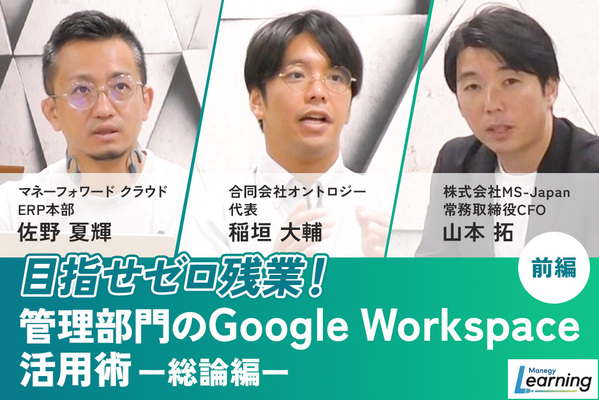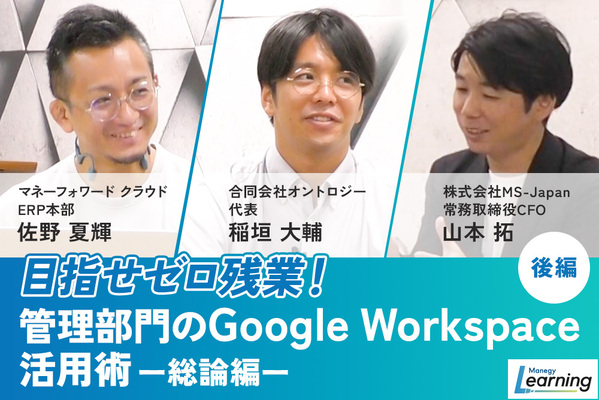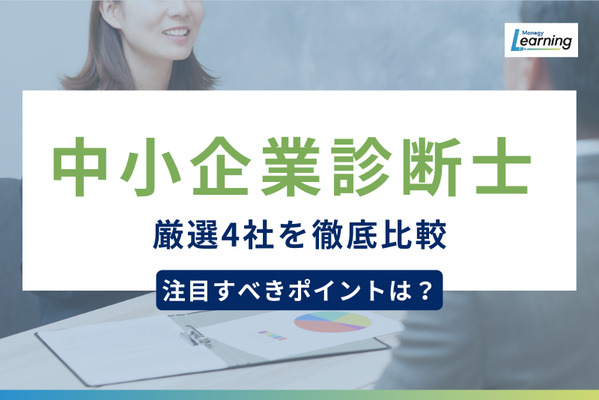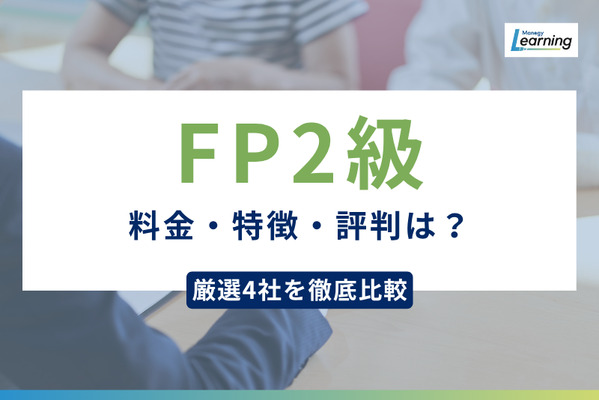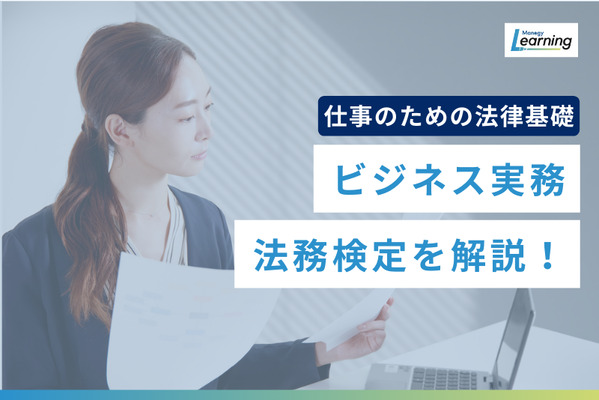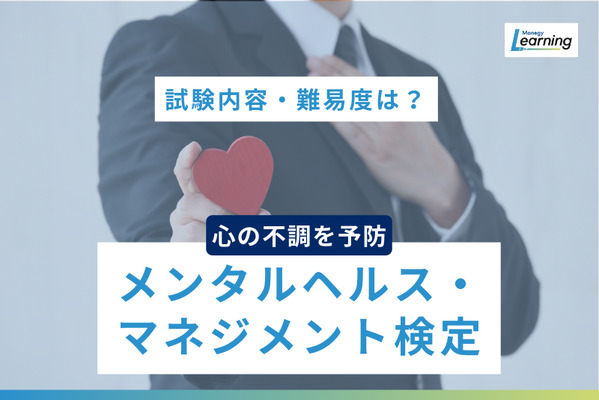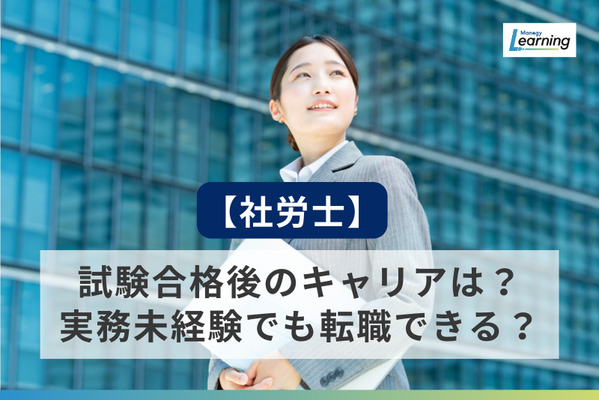社労士への転職・キャリアチェンジ完全ガイド|未経験から専門性を武器に高年収を目指す方法
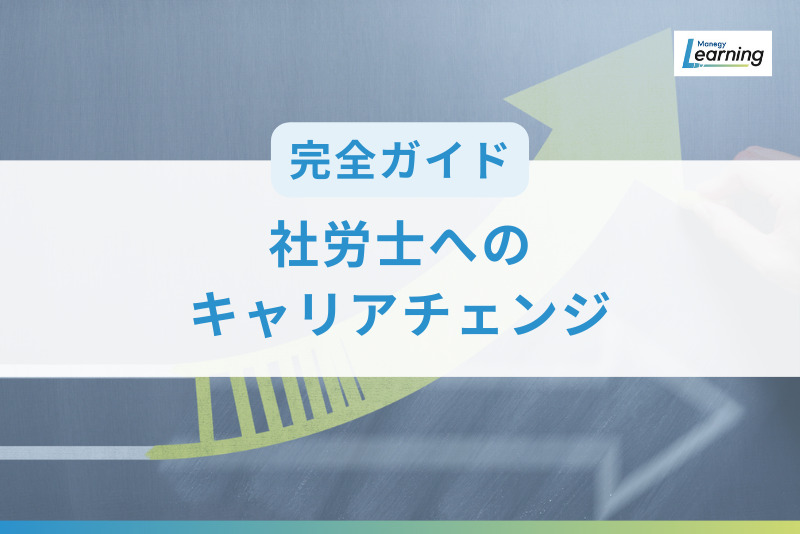
働き方の多様化や法改正が急速に進む現代社会において、「人」に関わる専門家である社会保険労務士(社労士)の重要性はますます高まっています。
本記事では、専門性を身につけてキャリアアップしたい方、人事や労務に携わる仕事に興味がある方、そして社労士へのキャリアチェンジを考えている方に向けて、最新のデータや事例を交えながら、社労士というキャリアの魅力と具体的な道のりを解説します。
社労士はなぜ需要が高いと言われているのか?仕事内容とあわせて解説
社労士の仕事は、企業における「人」に関する専門家として、労働・社会保険諸法令に基づき、書類作成や手続き代行、そして労務管理や人事に関するコンサルティングを行うことです。具体的には、以下の3つの業務に大別されます。
- 1号業務(手続代行業務)
労働・社会保険の加入・脱退手続き、給付金や助成金の申請など、行政機関に提出する書類の作成と提出を企業に代わって行います。 - 2号業務(帳簿作成業務)
労働者名簿や賃金台帳など、法律で作成が義務付けられている帳簿書類を作成します。 - 3号業務(コンサルティング業務)
就業規則の作成・変更、人事制度の構築、働き方改革への対応、労使トラブルの予防・解決など、企業の「人」に関する課題を専門的知見からサポートします。
なお、社労士の独善業務にあたるのは1号業務・2号業務であり、3号業務は独占業務ではありません。
しかしながら、近年の法改正、例えば働き方改革関連法や育児・介護休業法の改正、テレワークの普及などにより、企業の労務管理は複雑化しています。これに伴い、専門的なアドバイスができる3号業務の需要が高まりつつあり、社労士の活躍の場は大きく広がっています。
社労士の仕事内容や魅力について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事もご確認ください。
この記事を読んだ方にオススメ!
年収1,000万・独立開業も可能!?社労士資格がもたらす3つの未来
未経験からでも挑戦でき、多くのメリットを持つ社労士へのキャリアチェンジ。その魅力を3つのポイントからご紹介します。
年齢関係なく活躍できる(年齢制限、退職がない)
社労士は、定年のない「生涯現役」が可能な資格です。全国社会保険労務士会連合会が公表した「社会保険労務士白書(2024年版)」によると、登録している社労士の年齢構成は50代が最も多くで、40代から60代が全体の4分の3以上を占めています。
さらに、過去10年の合格者データによると、30代の割合が最も多く、続いて40代、50代と続きます。
多くの人が社会人として経験を積んだ後に、キャリアアップや専門性を求めて挑戦している姿がうかがえます。知識と経験が重視されるため、年齢を重ねることがキャリアの強みとなるのです。実際に、令和6年度の社労士試験では最高齢81歳の方が合格しており、何歳からでも挑戦できる資格であることがわかります。
独立可能
社労士資格の大きな魅力の一つが、独立開業できる点です。全国社会保険労務士会連合会の「社会保険労務士白書(2024年版)」によれば、実に登録者の6割以上が開業社労士として活躍しています。
独立開業した場合、年収は本人の営業力や専門性次第で大きく変わりますが、年収1,000万円以上を得ている開業社労士も3割以上存在し、勤務社労士と比べて高収入を目指せる可能性を秘めています。
柔軟な働き方が可能
社労士の働き方は、企業内での勤務から独立開業まで多様です。 近年、一般の企業と同様にテレワークや時短勤務を取り入れる事務所も増えていますが、社労士も同様の傾向にあります。
さらに、社労士の場合は、
1.高度な専門性が求められるため働く場所や時間に縛られにくい
2.独立開業という選択肢により自らの裁量で仕事をコントロールしやすい
という特徴も加わるため、柔軟な働き方を実現しやすい職種と言えます。
専門性を活かしながら、仕事とプライベートのバランスを取りたい方にとって、社労士は非常に適したキャリアといえるでしょう。
この記事を読んだ方にオススメ!
社労士になるには?資格取得からキャリア開始までの全手順
社労士としてキャリアをスタートさせるまでの道のりは、大きく4つのステップに分かれます。
【STEP1】社労士試験の受験資格をチェック
まず、社労士試験を受けるための資格があるかを確認します。受験資格は大きく分けて「学歴」「実務経験」「国家試験合格」の3つがあり、いずれか1つを満たせば受験できます。
- 学歴: 大学、短期大学、高等専門学校(5年制)の卒業など。
- 実務経験: 指定された業務に3年以上従事した経験など。
- 国家試験合格: 行政書士試験や司法書士試験など、厚生労働大臣が認める国家試験に合格していること。
詳細は社会保険労務士試験オフィシャルサイトをご確認ください。
【STEP2】社労士試験に合格する
受験資格を満たしたら、いよいよ最難関である試験合格を目指します。社労士試験は合格率が例年6〜7%台の難関国家資格であり、合格に必要とされる勉強時間は一般的に800〜1,000時間が目安と言われています。
学習スタイルは、市販のテキストで自分のペースで学ぶ「独学」と、確立されたカリキュラムで効率的に学ぶ「予備校・通信講座」の利用に大別されます。ご自身のライフスタイルや予算に合わせて最適な学習計画の立案・実行が、合格への鍵となります。
【近年の合格推移】
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| 第56回(令和6年度) | 6.9% |
| 第55回(令和5年度) | 6.4% |
| 第54回(令和4年度) | 5.3% |
【STEP3】社労士登録をする
試験に合格しただけでは「社労士」を名乗ることはできません。全国社会保険労務士会連合会に備える社労士名簿に登録することで、初めて社労士として活動できます。
登録には、2年以上の実務経験が必要です。実務経験がない場合は、連合会が実施する「事務指定講習」を修了することで、登録要件を満たすことができます。
【STEP4】キャリアをスタートさせる
社労士登録を終えたら、いよいよキャリアのスタートです。主な就職先としては、以下のような選択肢があります。
- 社会保険労務士事務所・法人:
最も代表的な就職先。様々な企業の労務管理に携わることができ、将来の独立開業を目指すための実務経験を積むのに最適です。 - 一般企業の人事・総務部:
「勤務社労士」として、自社の労務管理や人事制度の構築に専門性を発揮します。特に近年、コンプライアンス遵守の観点から企業内での社労士の需要は高まっています。 - コンサルティングファーム:
人事・労務分野のコンサルタントとして、より専門的で高度な課題解決に取り組みます。 - 会計事務所・弁護士事務所など他士業の事務所:
他の専門家と連携し、ワンストップで顧客の課題解決を支援します。
最近の調査では、社労士の求人は「一般企業」が4割以上を占めており、様々な業界で活躍の場が広がっていることがわかります。
あなたのキャリアが武器になる!社労士として活かせる経験とは?
これまでのキャリアで培った経験は、社労士の業務に大いに活かすことができます。
人事・総務の経験
給与計算、社会保険手続き、就業規則の作成などに直接関わってきた経験は、即戦力として高く評価されます。現場で感じた課題意識は、より実践的なコンサルティングに繋がります。
営業経験
顧客との信頼関係構築やニーズのヒアリング能力は、特に独立開業を目指す場合に不可欠です。企業の経営者に寄り添い、課題を的確に把握する力は、コンサルティング業務の質を大きく左右します。
事務経験
正確な書類作成能力やスケジュール管理能力は、1号業務(手続代行)や2号業務(帳簿作成)をミスなく迅速に進める上で非常に重要です。
ITスキルを活かした経験
近年、労務管理のDX(デジタルトランスフォーメーション)が進んでいます。勤怠管理システムや給与計算ソフトの導入・運用支援、クラウドサービスを活用した業務効率化の提案など、ITスキルを持つ社労士の需要は急速に高まっています。データ分析に基づいた人事戦略の提案など、活躍の幅はさらに広がるでしょう。
まとめ
社労士は、専門性を武器に、年齢に関わらず長く活躍できる将来性豊かなキャリアです。独立開業や柔軟な働き方など、多様なキャリアパスを選択できる点も大きな魅力です。
道のりは決して平坦ではありませんが、これまでの社会人経験を活かし、挑戦する価値は十分にあります。働き方が大きく変化し続ける現代社会において、「人」の専門家である社労士の役割は、今後ますます重要になっていくことは間違いありません。この記事が、あなたの新たな一歩を後押しできれば幸いです。
この記事を読んだ方にオススメ!

Manegy Learning
Manegy Learningは管理部門・士業の皆さまに向けて、実務に役立つTIPSや資格取得のためのスクール取得などの情報を発信し、みなさまの学びをサポートします。
MS-Japan
https://www.manegy.com/learning/