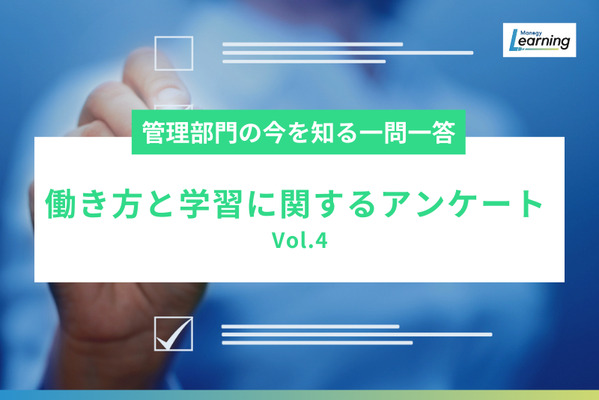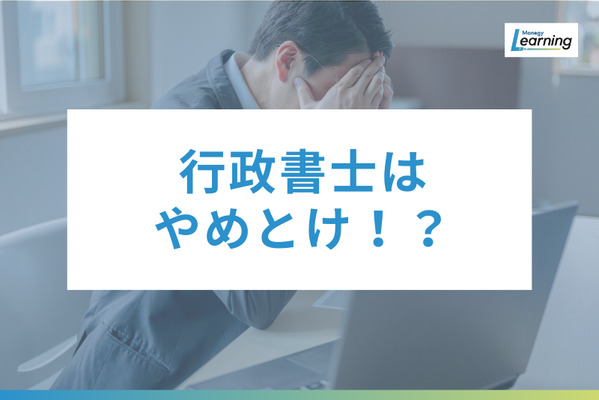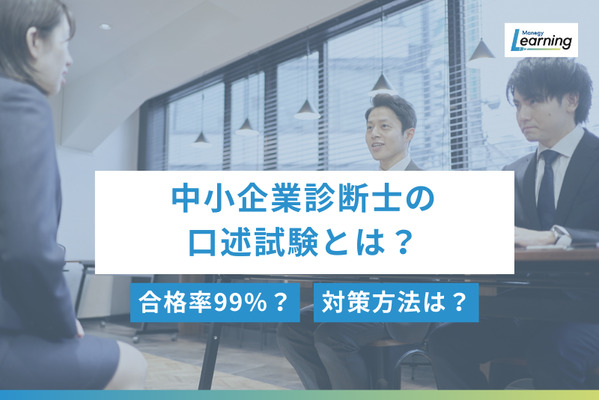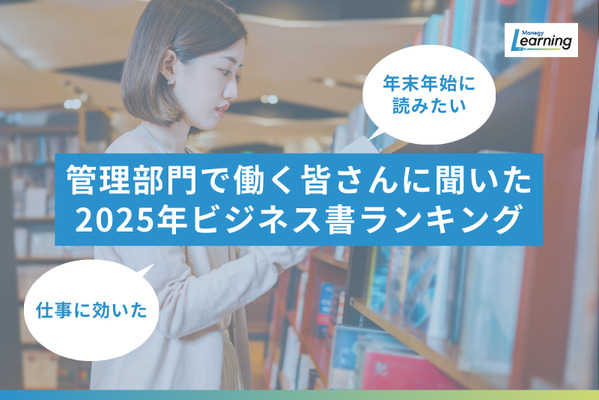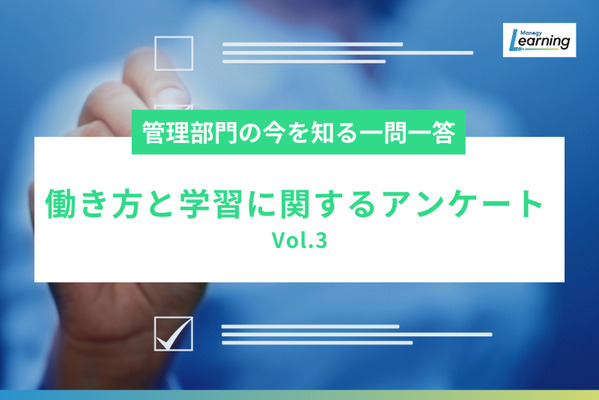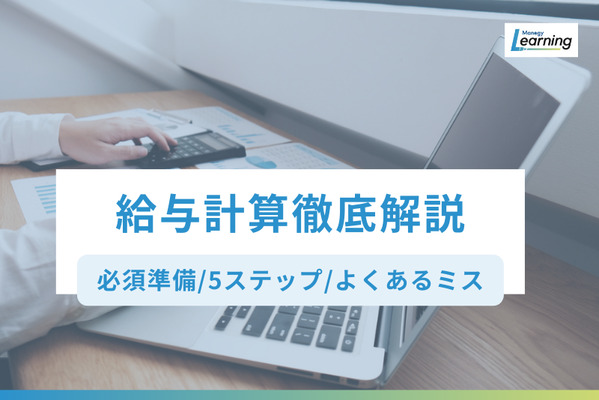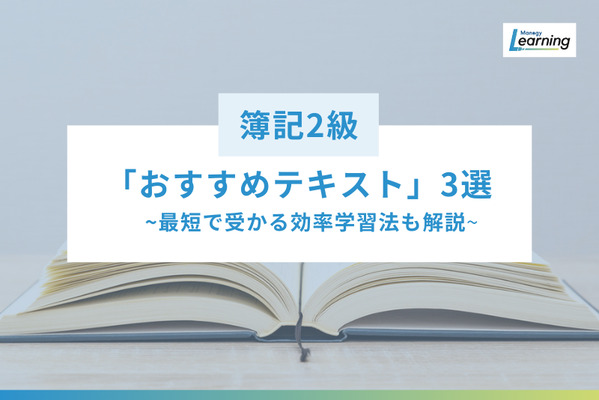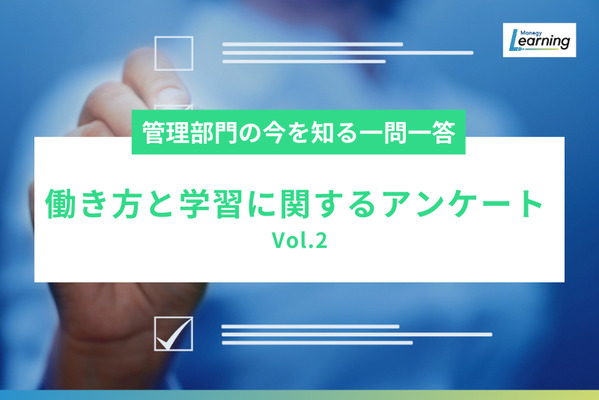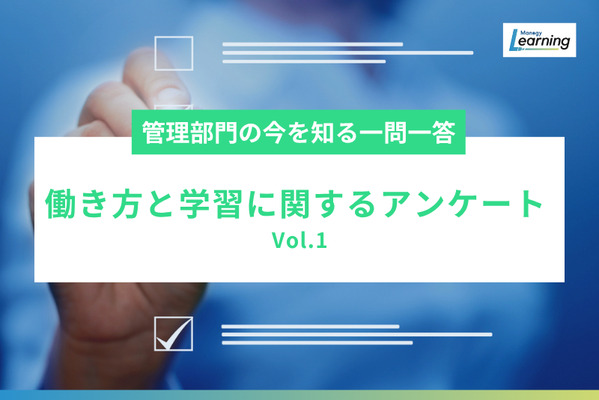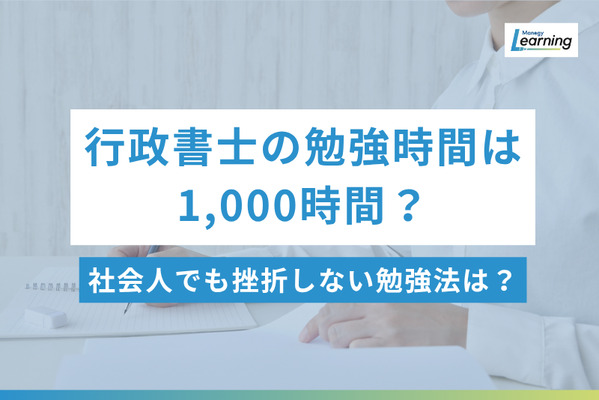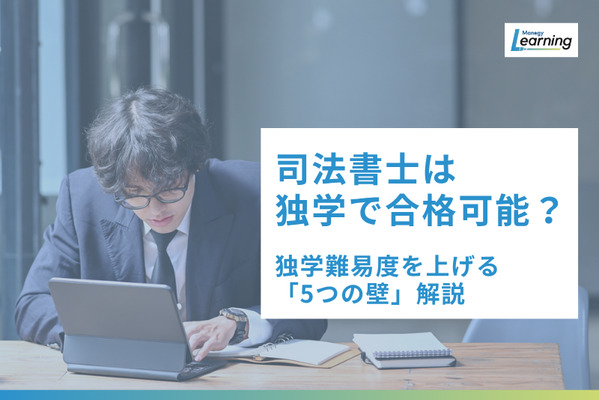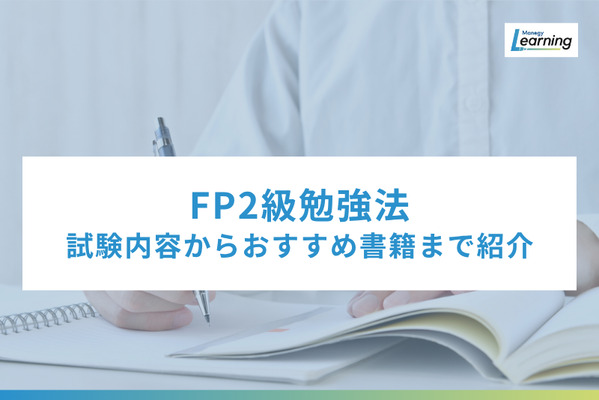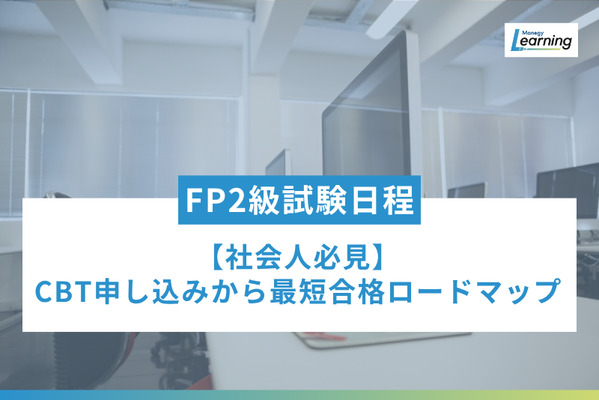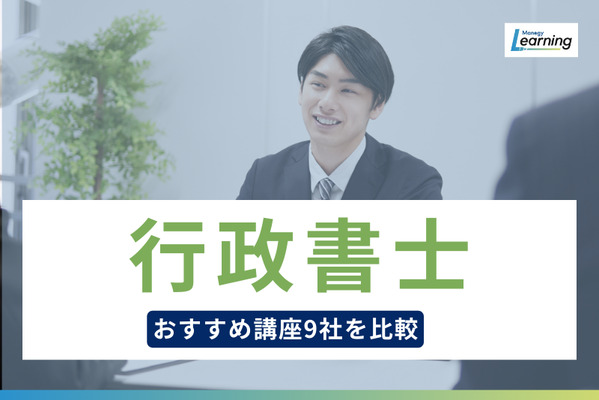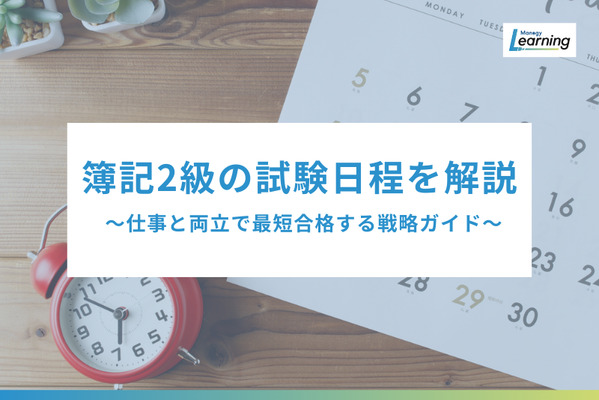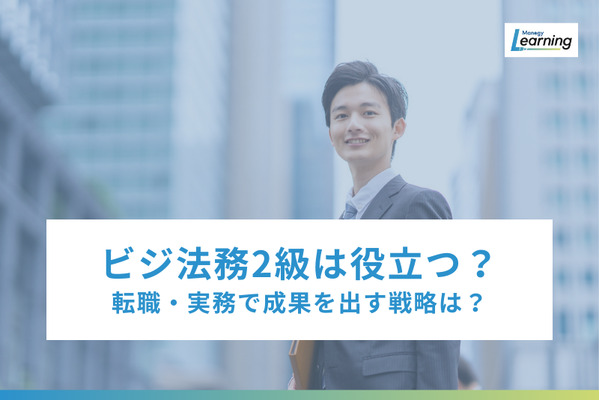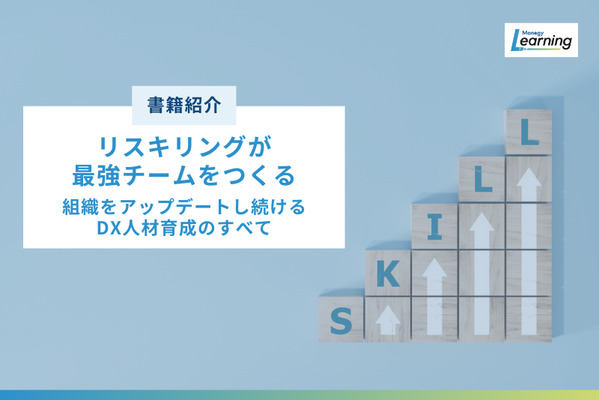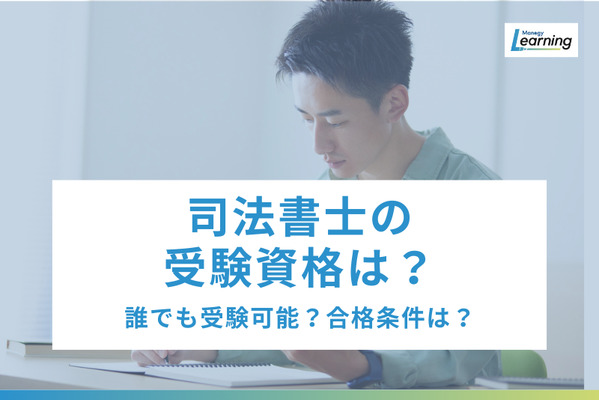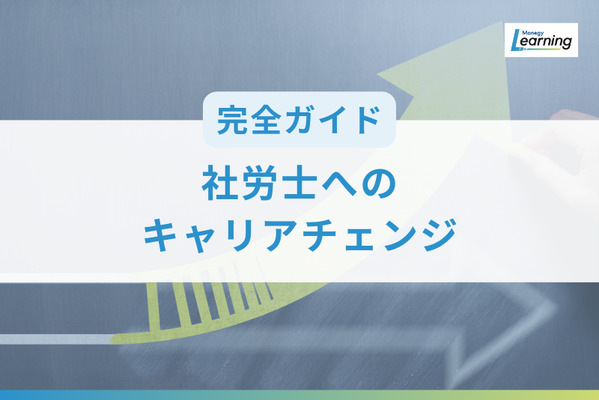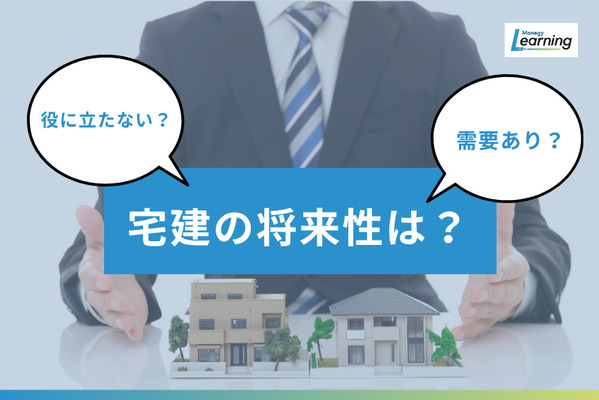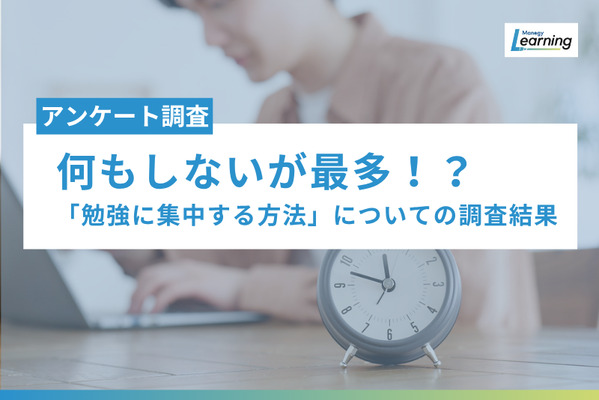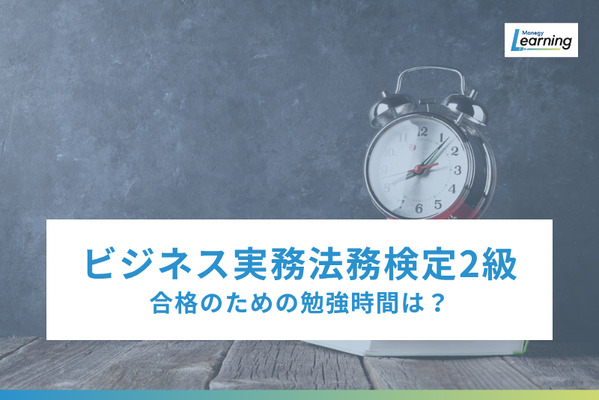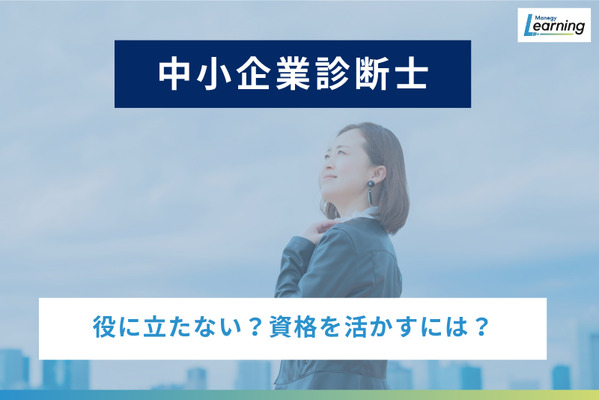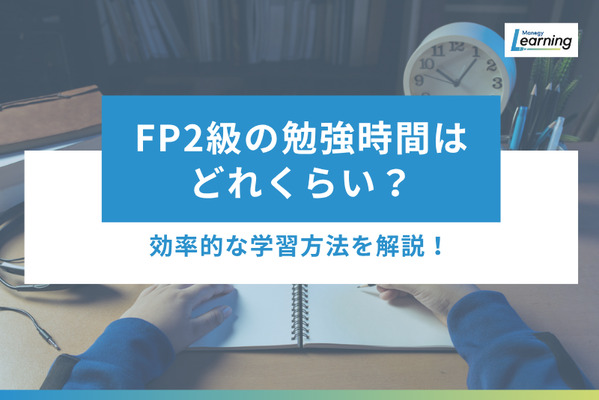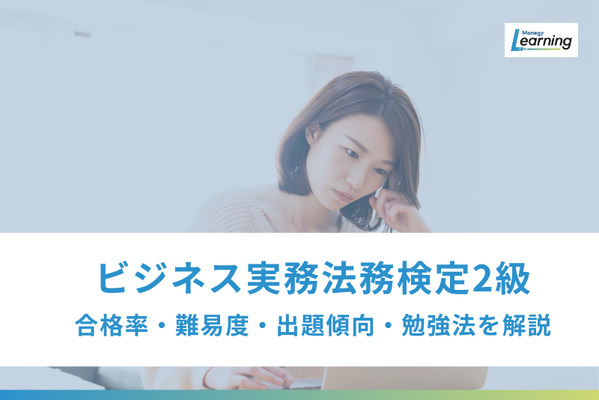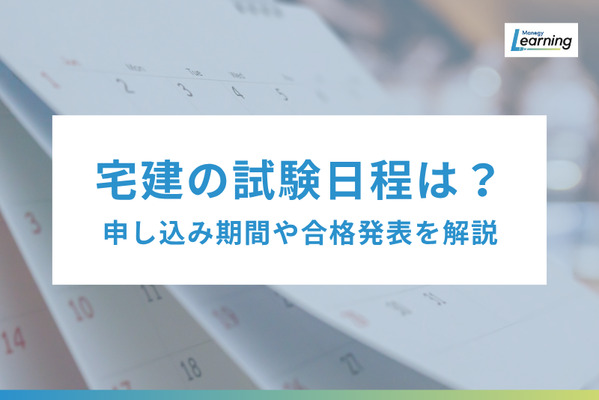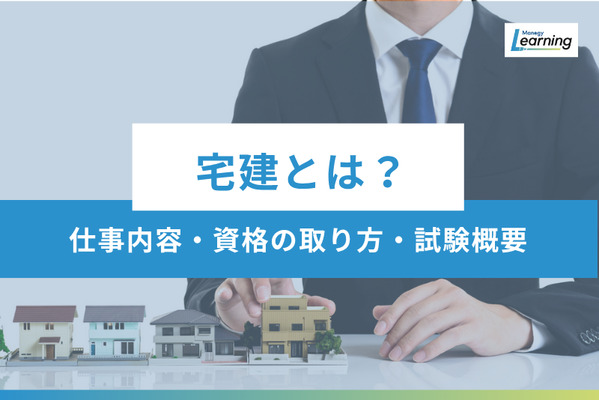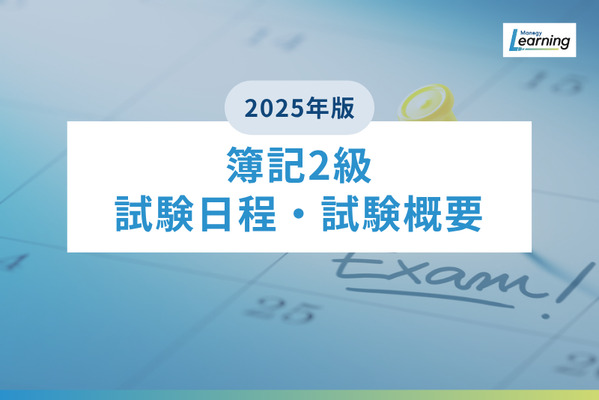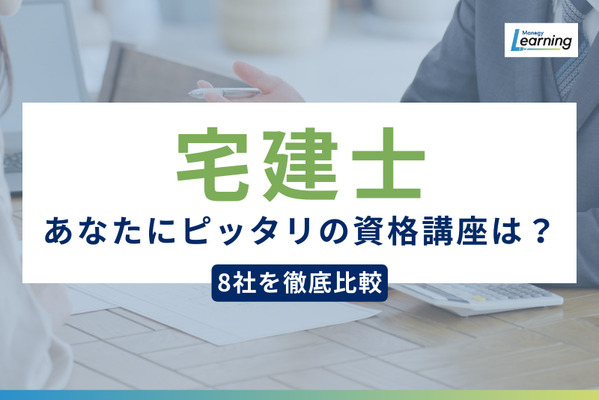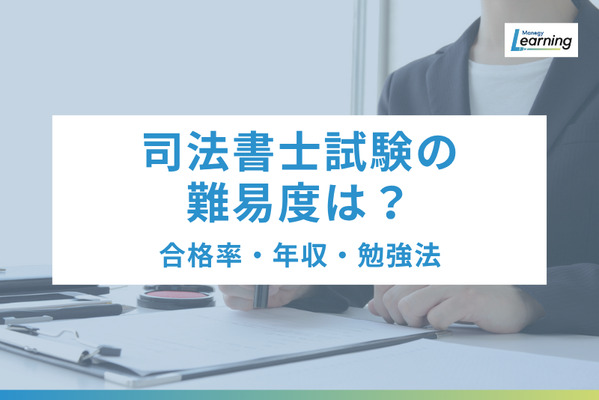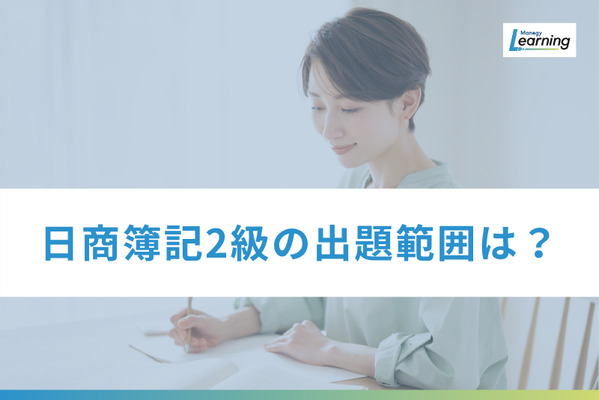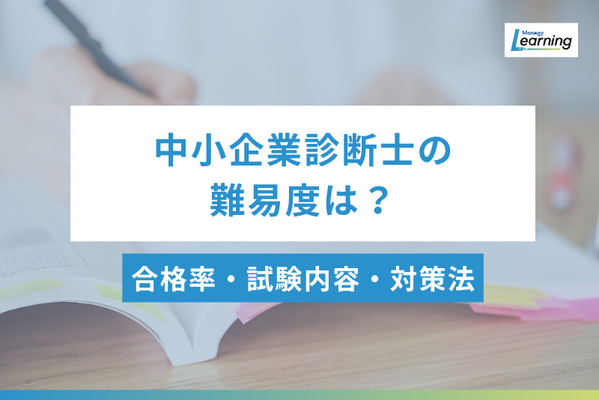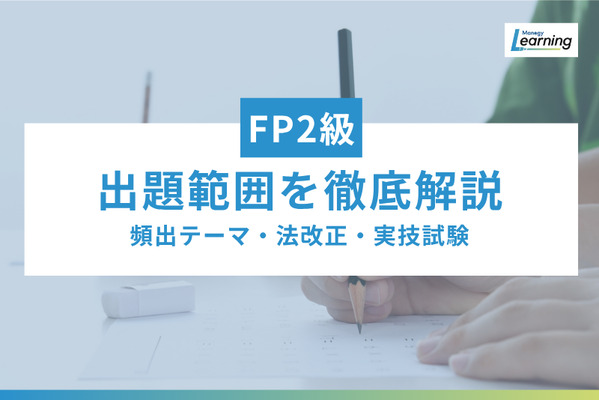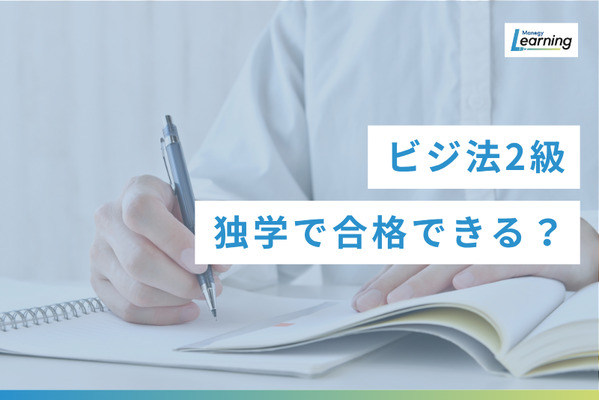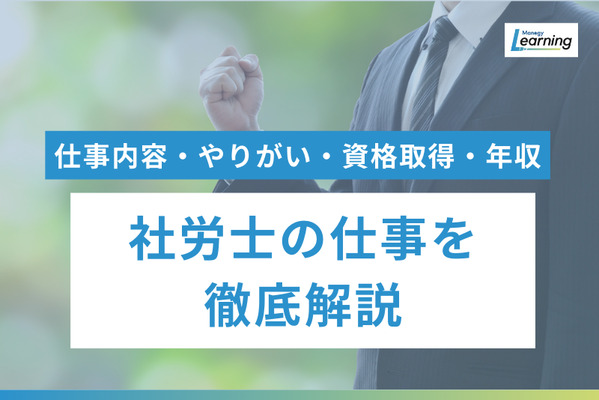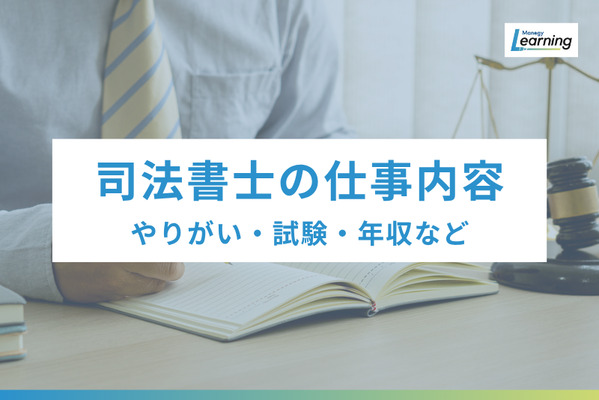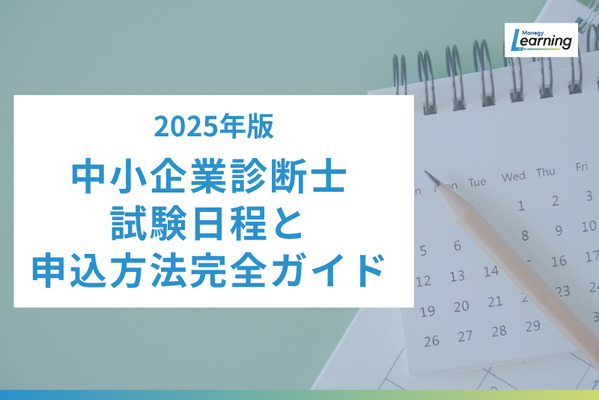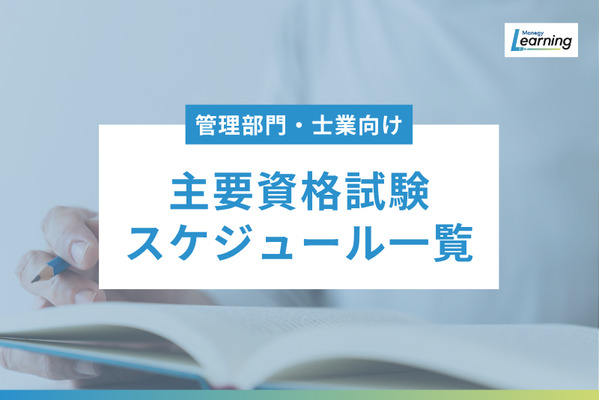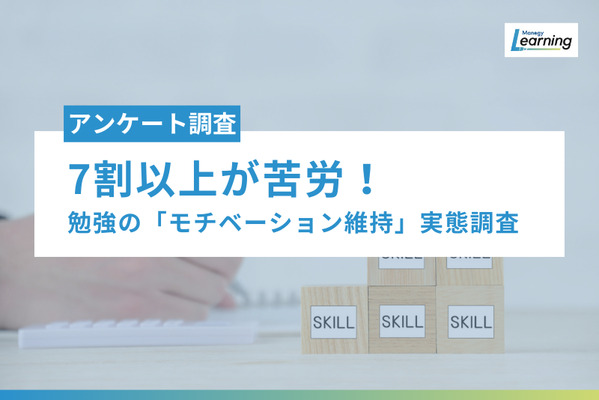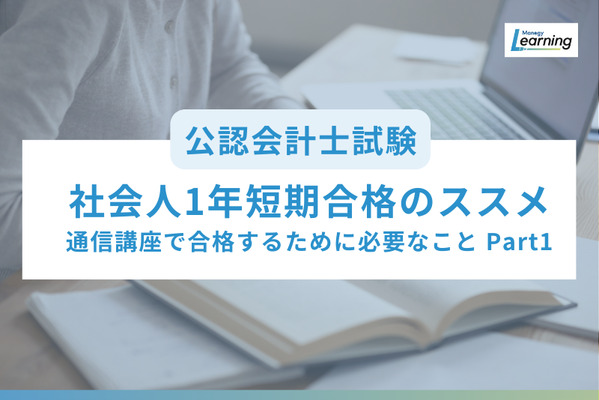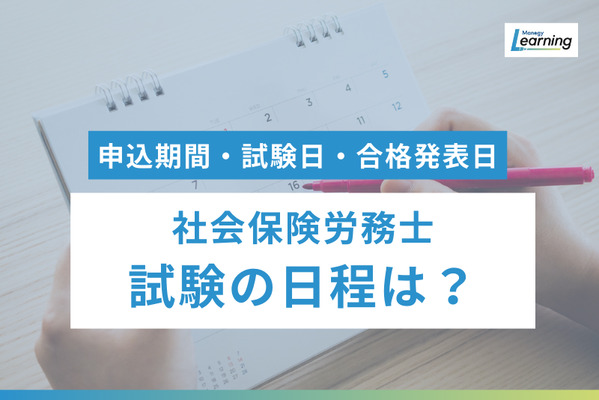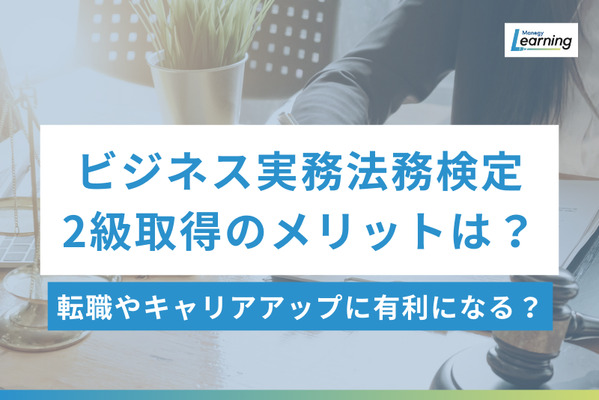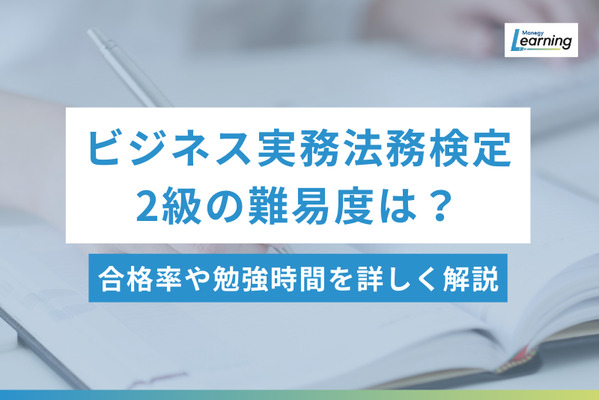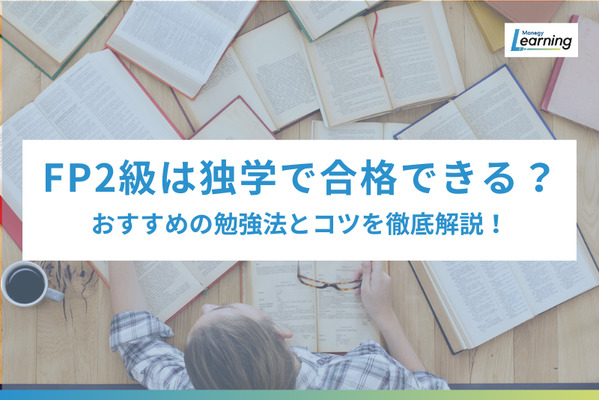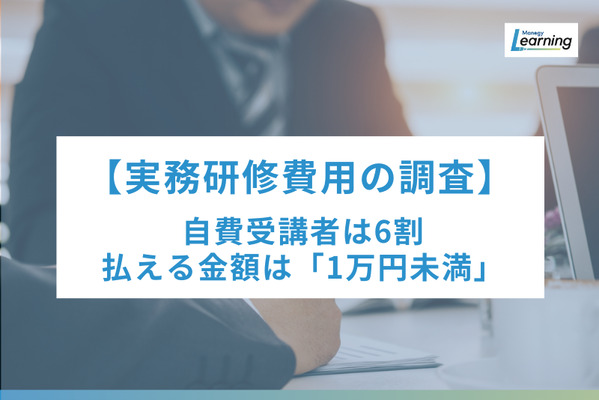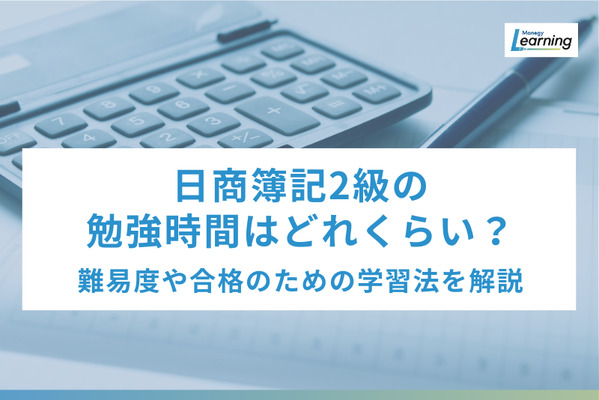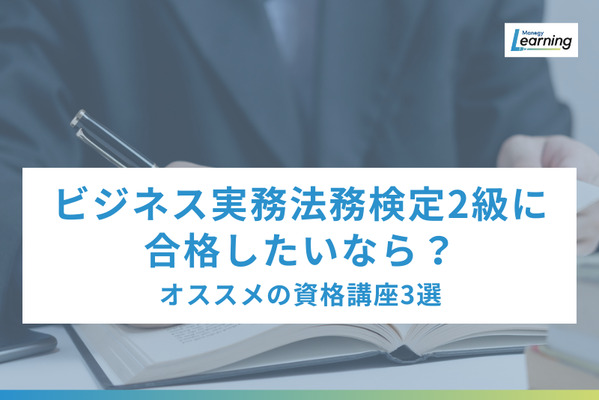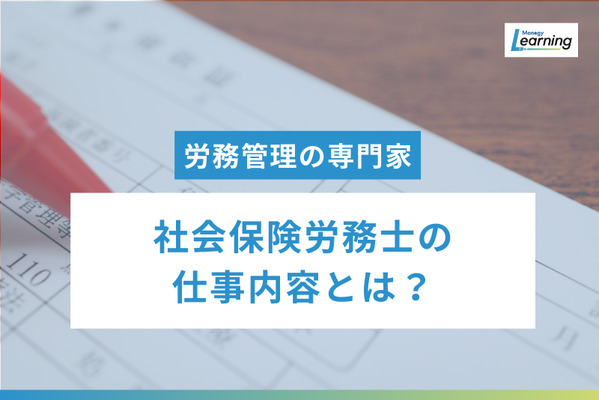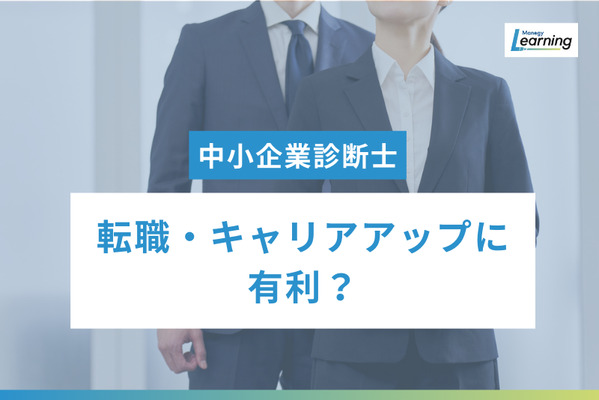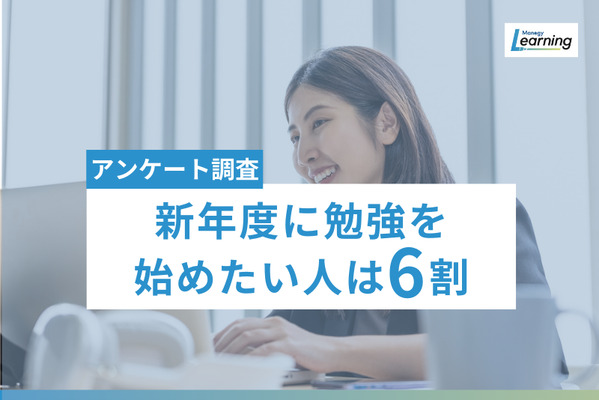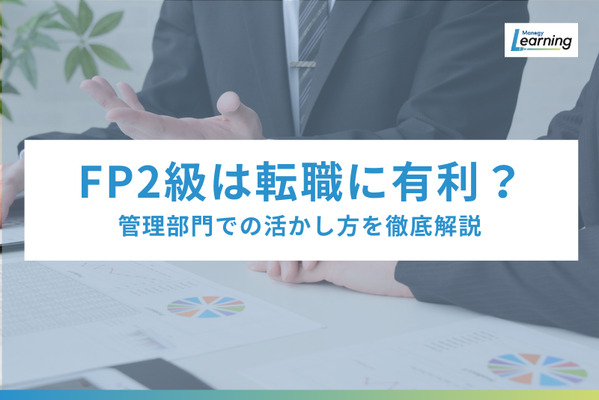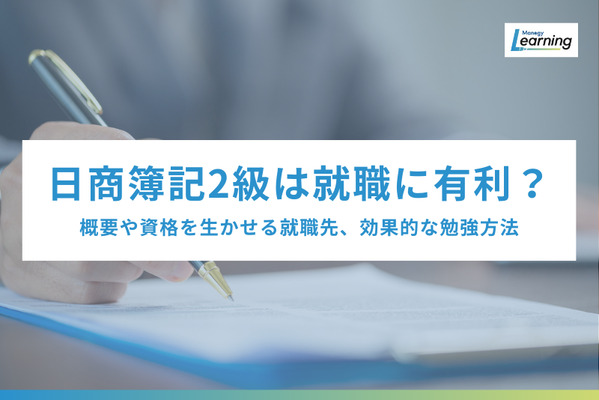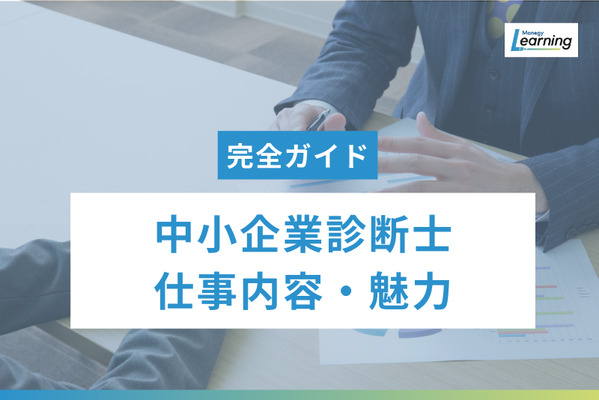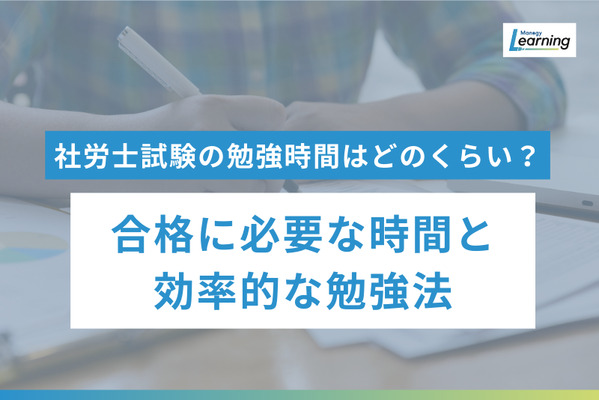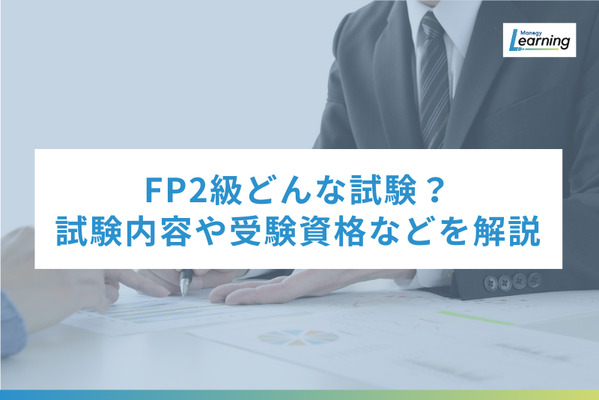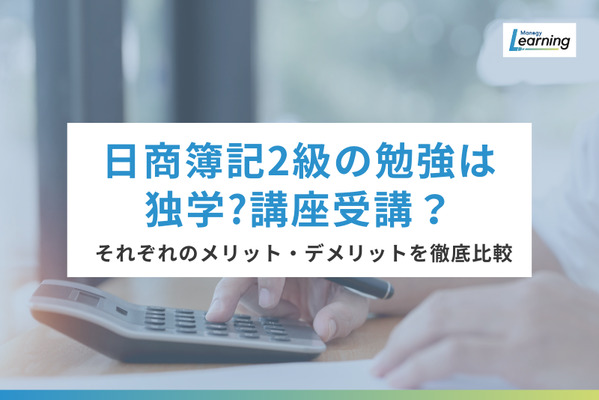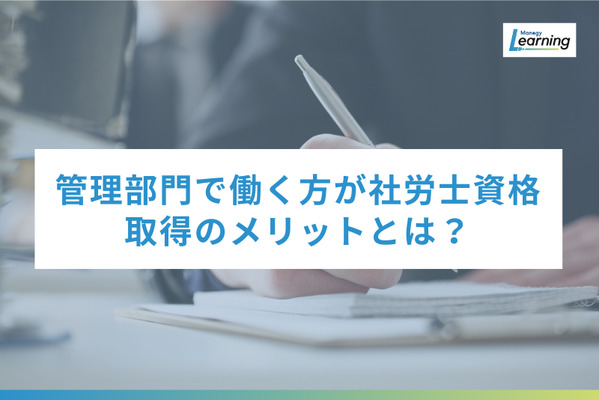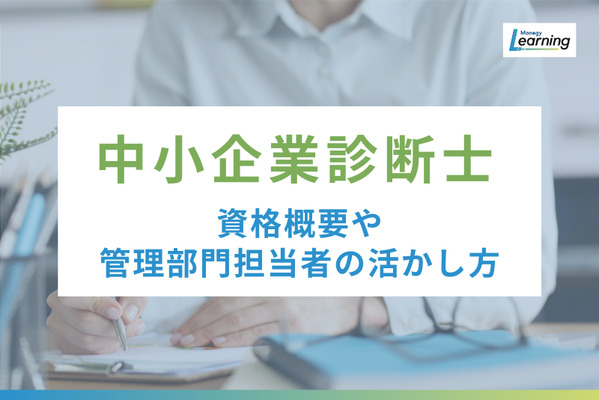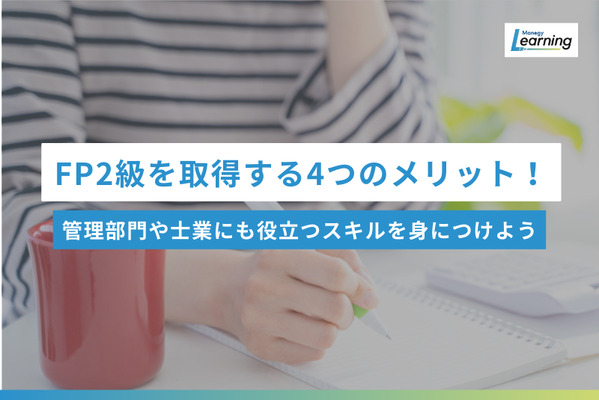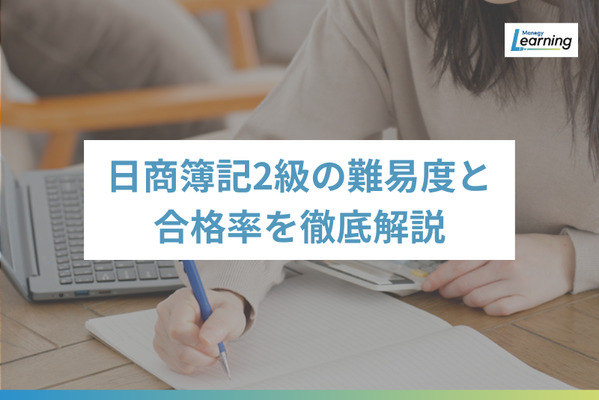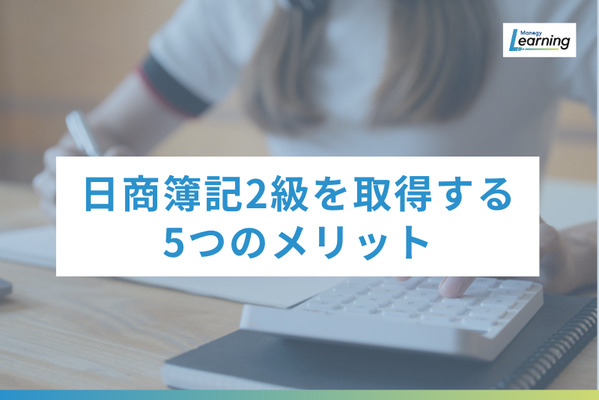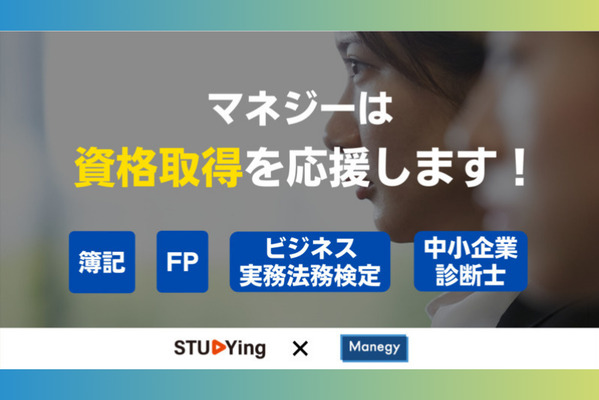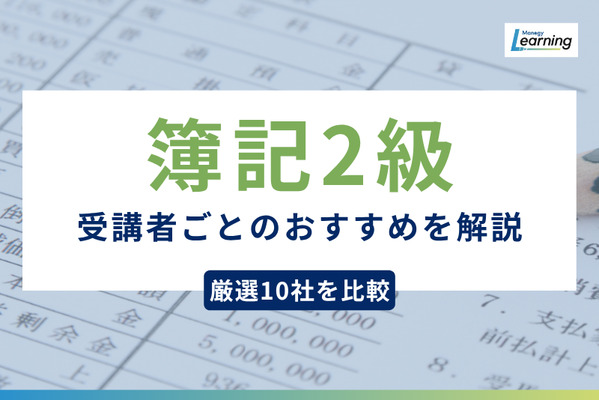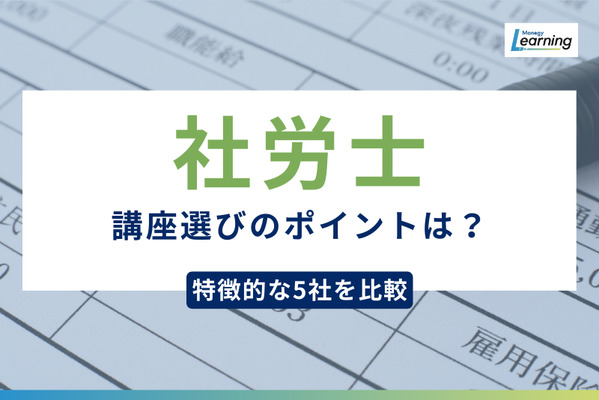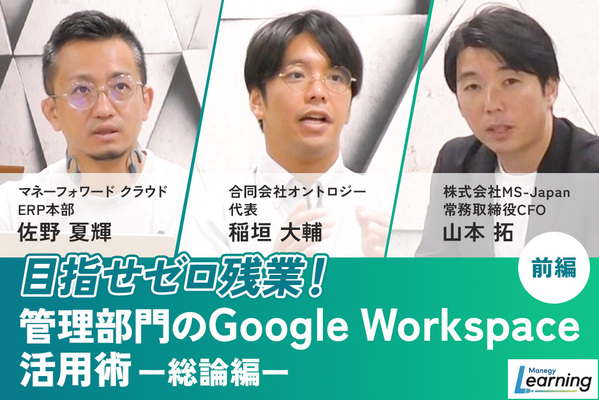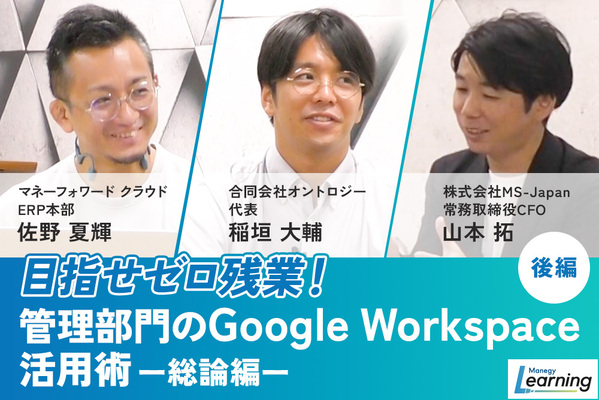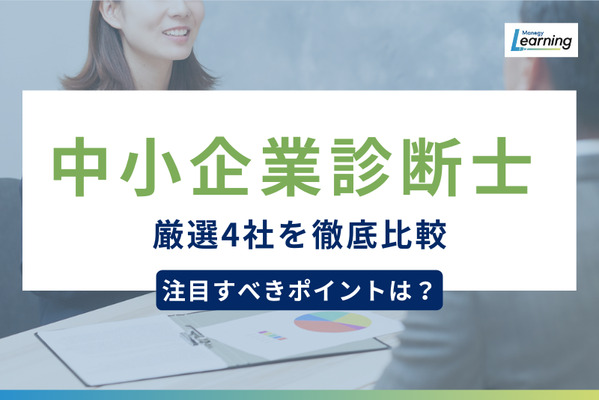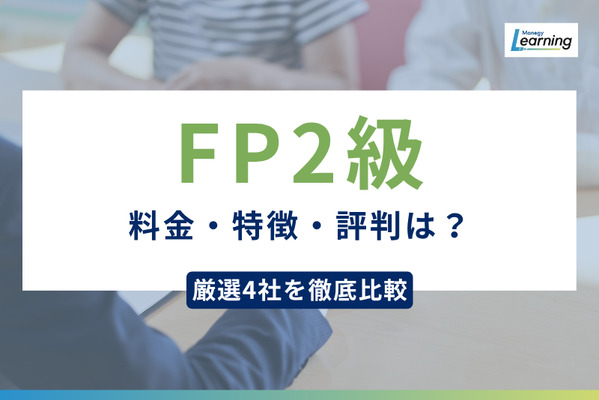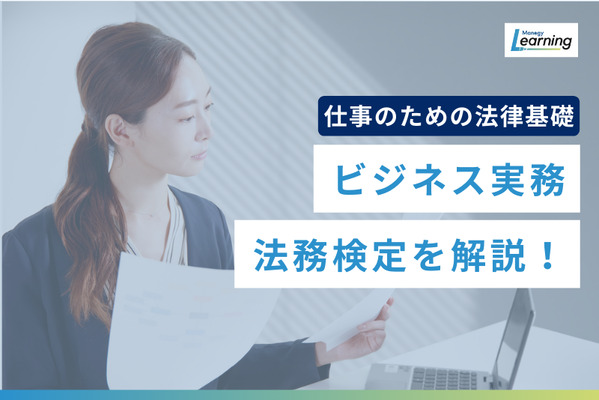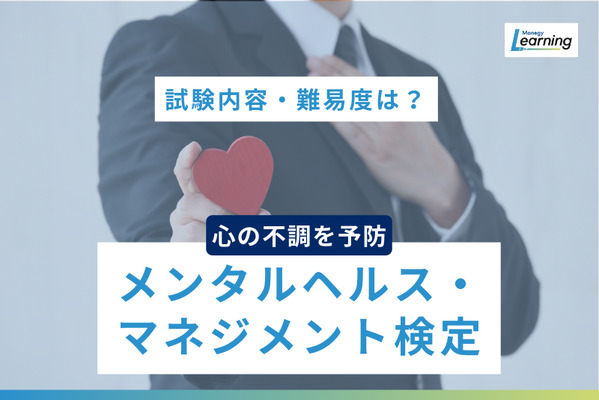中小企業診断士の二次試験とは?試験概要や難易度、勉強法などを徹底解説!
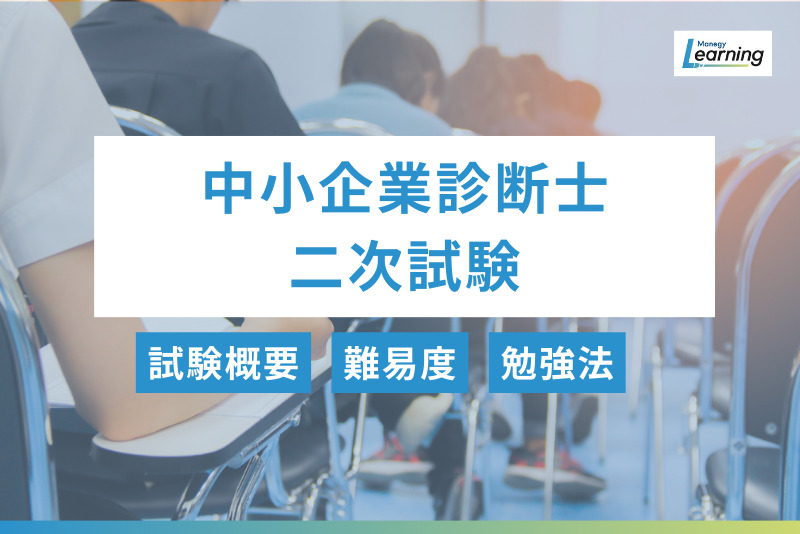
中小企業の経営内容を診断し、課題に対して助言・指導を行う専門家「中小企業診断士」。難関資格のひとつです。
中小企業診断士の資格は一次試験と二次試験で構成され、二次試験は一次試験を突破しなければ受験できません。二次試験は筆記と口述(面接)があり、いずれも中小企業の経営課題を的確に把握し、論理的に解決策を提示する力が求められます。特に筆記試験は、時間配分・記述力・分析力の全てを兼ね備えている必要があります。
本記事では、中小企業診断士の二次試験の概要から難易度、勉強法まで、二次試験という壁に挑む方に役立つ情報を詳しく解説します。
中小企業診断士 二次試験の概要
この項では、中小企業診断士の二次試験(筆記・口述)について、概要をご紹介します
2025年度の試験日程・形式・受験料・持ち物は?
筆記試験
試験日:2025年10月26日(日)
試験地:札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各地区
受験料:17,800円
持ち物:筆記用具、受験票、身分証明書、時計(会場での持ち込み可否は直前案内を確認すること)
試験形式:4事例(組織戦略・人事戦略、マーケティング戦略、生産管理、財務会計)。論述式で記述力を問う
試験時間:各事例80分(1日で実施)
合格基準:総合点240点以上(4事例合計で60%以上)で、かつ、各事例で40点未満(40%未満)が1つもないこと
口述試験
試験日:2026年1月25日(日)
試験地:札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各地区
受験料:不要(筆記試験の申し込み時に支払った受験料に含まれる)
持ち物:受験票など
試験形式:面接方式(個別) ※筆記試験の合格者のみが受験対象。筆記内容の理解と実務的説明力を確認
試験時間:10分程度
合格基準:回答の論理性、態度、受け答えの的確さなどを総合評価
【2025年度版】試験までのスケジュール(出願期間、実施日、合格発表など)
ここでは、中小企業診断士の二次試験の出願期間から合格発表日までをご紹介します。出願から合格発表までは約5か月間かかり、長期戦となります。
出願期間:2025年9月2日(火)~9月22日(月)(インターネットによる申し込み) 二次筆記試験日:2025年10月26日(日) 口述試験受験資格を得た人の発表:2026年1月14日(水) 口述試験日:2026年1月25日(日) 合格発表日:2026年2月4日(水)
試験当日の心構え
時間に余裕をもって行動する
試験当日は誰でも緊張するものです。時間に余裕がないと、焦りからミスが増えることがあります。試験会場には少し早めに到着するように心がけましょう。試験開始までの時間は、これまで勉強したテキストや問題集などの付箋、過去問で何度か間違えた箇所のみを見返す程度にして、落ち着いて過ごしましょう。
口述試験の服装
服装に決まりはありませんが、面接形式のため、落ち着いた色合いとデザインで清潔感のある服装で臨むのがベターです。迷った場合はスーツを着用するのがよいでしょう。
筆記試験の試験科目と口述試験の主な内容
ここでは、二次試験の筆記試験の試験科目と口述試験の主な内容について解説します。
筆記試験
| 事例 | 分野 | 内容 |
|---|---|---|
| 事例Ⅰ | 組織戦略・人事戦略 | 組織構造、人材育成、人事制度、働き方改革など |
| 事例Ⅱ | マーケティング戦略 | 商品戦略、販売促進、流通チャネル、ブランド戦略など |
| 事例Ⅲ | 生産管理 | 生産体制、工程改善、技術導入、現場マネジメント |
| 事例Ⅳ | 財務会計 | 資金繰り、損益分岐点分析、投資意思決定、財務指標分析 |
それぞれの与件文から課題を抽出し、論理的に整理した記述回答が求められます。
口述試験
試験内容:筆記試験で出題された4事例の内容に関連した質問 質問内容例:事例Ⅰ~Ⅳの設問に関する理解や改善提案、コンサルタントとしての助言内容など
口述試験では、筆記試験で出た課題や結論を説明できるか確認されます。形式は面接形式で、短時間で的確に受け答えする能力が問われます。
中小企業診断士 二次試験の難易度や試験免除について
本項では、中小企業診断士の二次試験の難易度と合格基準、難所、試験免除について詳しくご説明します。
難易度と合格基準
一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会が発表した過去のデータを見ると、二次試験の合格率は近年おおむね18~19%前後で推移しています。(一次試験合格率は20~30%で推移。)一次試験合格者という一定の実力層のなかでの競争なので、この18~19%前後という合格率は、数字以上の難易度に感じるかもしれません。
二次の筆記試験は先に述べたとおり4つの事例(事例Ⅰ~Ⅳ)で構成され、それぞれ100点満点となっています。合格基準は総合点240点以上(4事例合計で60%以上)で、かつ、各事例で40点未満(40%未満)が1つもないこと。つまり「トータルで合格ラインに届いていても、1科目の大きな失敗で足切りになる」という厳しさがあるのです。部分的な得意不得意では突破できず、4事例をバランスよく仕上げる力が必須です。また、口述試験も評定が60%以上であることが合格基準となっています。
筆記試験と口述試験、本当の難所はどこか?
二次試験の山場は筆記試験です。単純な知識はもちろんのこと、文章を論理的に組み立てる論理構成力や、制限時間内で分析や記述をこなすスピードなど、様々な要素が求められます。前述のとおり、4事例全てで一定以上の点数を取らなければならず、各分野に対する理解とアウトプット能力が極めて重要です。
一方、口述試験は筆記試験を通った人のみが受けられ、口述試験自体の合格率は例年99%以と言われています。
二次試験が免除される場合がある!?
中小企業診断士は、一次試験に合格後に二次試験を経て実務補習を受けることで資格を取得できます。しかし、一次試験合格後に「中小企業診断士養成課程(または中小企業診断士登録養成課程)」と呼ばれるプログラムを修了すると、二次試験と実務補習を免除され、中小企業診断士の資格を得られます。
養成課程は、中小企業大学校東京校か民間教育機関に通学して受講します。独立行政法人 中小企業基盤整備機構の公式サイトに掲載されている中小企業大学校東京校の中小企業診断士養成課程は、「事例に基づく演習や企業診断実習を通じて中小企業の経営診断に関する知識、手法を習得修得し、実務能力の高い中小企業診断士を養成する6カ月間のプログラム」と説明されています。
ただし、養成課程は通学に最低半年~2年程度要し、費用も100万円以上(中小企業大学校の場合は受講料234万3,000円 ※2025年現在)かかることが一般的です。二次試験と実務補習が免除されるのは大きなメリットですが、時間・費用ともに大きな負担がかかります。
二次試験合格のための勉強法
筆記試験の時間配分
二次の筆記試験は1事例につき80分の制限時間で実施されます。この限られた時間内で、設問の確認、文章の読み込み、解答作成、見直しまでを終えなければなりません。そのため、本番までに自分に合った時間配分パターンを見つけておくことが重要で、過去問を繰り返し解くことでそのパターンを確立できます。
例えば、最初の15~20分で設問を読み込み、次に20分程度で解答の骨組みを作り、残り時間で文章としてまとめ上げ、最後の5分程度は見直しの時間にあてる、といった方法があります。自分の時間配分パターンをしっかりものにできれば、本番でも落ち着いて対応できるようになるでしょう。
有筆記試験の過去問分析
資格試験対策で最も重要なのは、過去問の繰り返し演習です。出題傾向(テーマ、頻出ワード、形式)を把握しておくことで、本番での対応力が身に付きます。できれば近年5~10年分の過去問を分析し、慣れておきましょう。
ただし、ただ解くだけでは十分ではありません。重要なのは、出題傾向や設問の意図、解答に必要な情報の見極め方を分析することです。また、解答後は必ず模範解答や高評価の答案と照らし合わせ、自分の解答との違いを分析します。このとき、「どの部分の根拠が不足していたか」「論理展開が曖昧になっていないか」を明確にしておくと、次の演習に活かせます。こうした分析を積み重ねることで、試験本番における対応力が格段に向上します。
筆記試験の記述対策
二次の筆記試験はマークシート式ではなく記述式です。出題される4科目ごとの与件文に事例企業の状況が書かれており、設問に答えるかたちで企業の分析や助言を行います。単に知識を並べるのではなく、与件文に基づいた具体的で論理的な文章を書くことが求められます。そのためには、与件文の事実と設問で求められている要素を結びつける思考能力を鍛えなければなりません。
解答は「根拠(与件文の事実)→分析(問題点や原因)→提案(改善策や方針)」という流れを意識して作成します。また、文章は簡潔かつ明確にまとめ、冗長な表現や根拠のない主観的意見は避けます。できれば練習の段階で、講座の講師や資格保有者、勉強仲間などに自分の答案を読んでもらい、伝わりやすさや論理性について確認してもらうとよいでしょう。記述対策は、時間をかけて継続的に行うことで能力が向上します。
まとめ:二次の筆記試験を制すれば中小企業診断士の資格取得が叶う!
中小企業診断士の二次試験は、一次試験以上に難関です。特に、筆記試験が最大の山場であり、記述力・論理力・時間管理の全てが厳しく問われます。
受験する場合は、まずは受験および合格発表までのスケジュールをしっかり把握し、試験概要を確認しておきましょう。試験の内容や難易度、難所はもちろん、試験免除についても理解し、そのうえで対策をとることが大切です。
勉強は、過去問を分析しながら繰り返し解き、自分に合った時間配分パターンをつかみます。記述の思考能力を高めるため、限られた勉強時間を最大限に活かしながら戦略的に対策を進めてください。
二次試験を突破できれば、中小企業診断士として第一歩を踏み出すことができます。ぜひ、自身の新たなキャリアを築き上げてみてはいかがでしょうか。

Manegy Learning
Manegy Learningは管理部門・士業の皆さまに向けて、実務に役立つTIPSや資格取得のためのスクール取得などの情報を発信し、みなさまの学びをサポートします。
MS-Japan
https://www.manegy.com/learning/