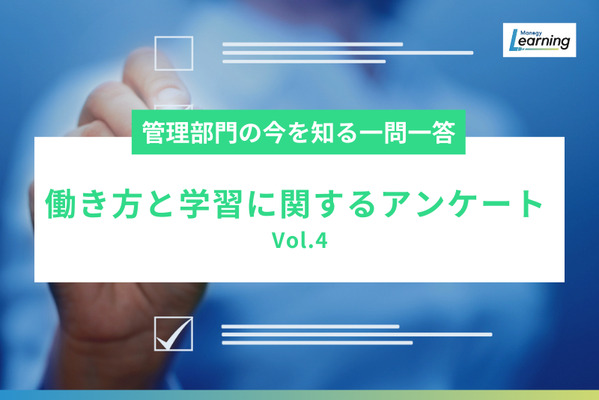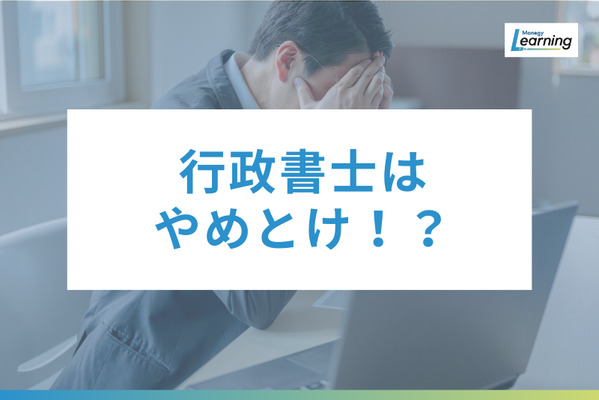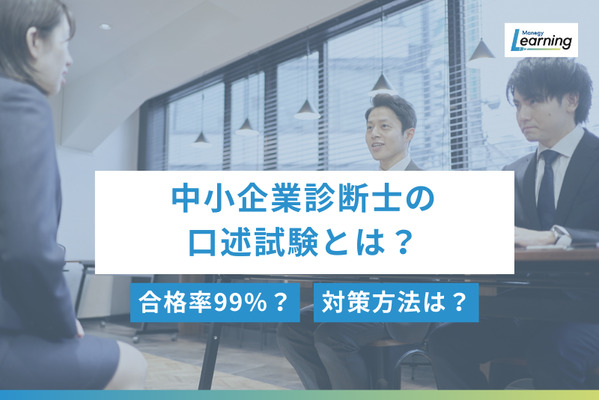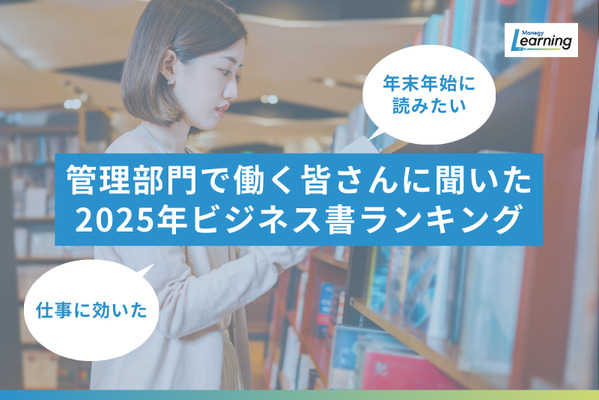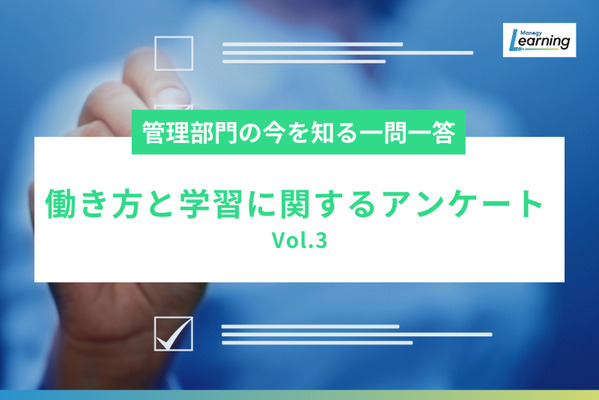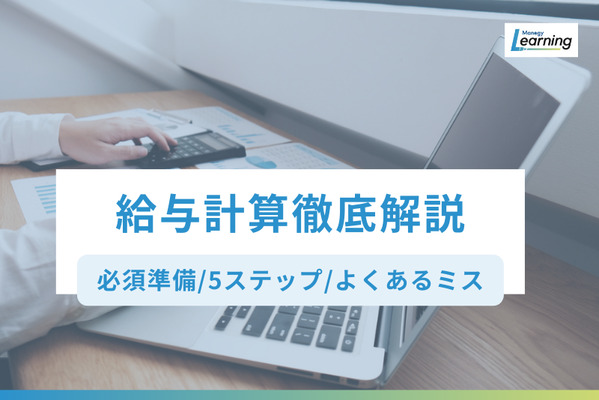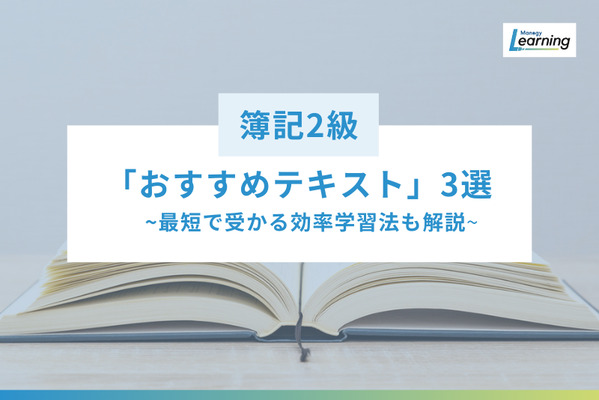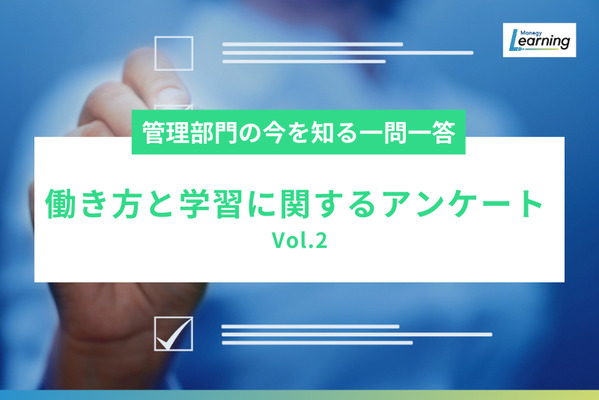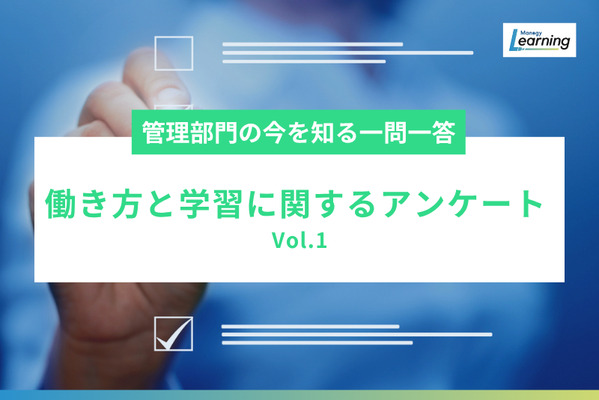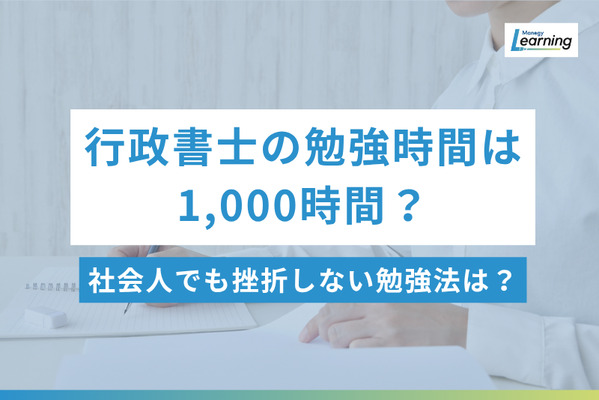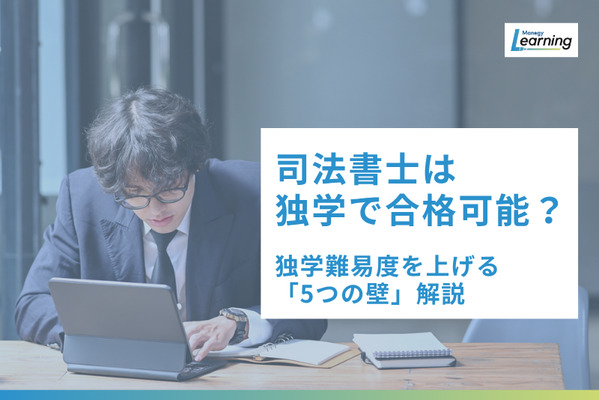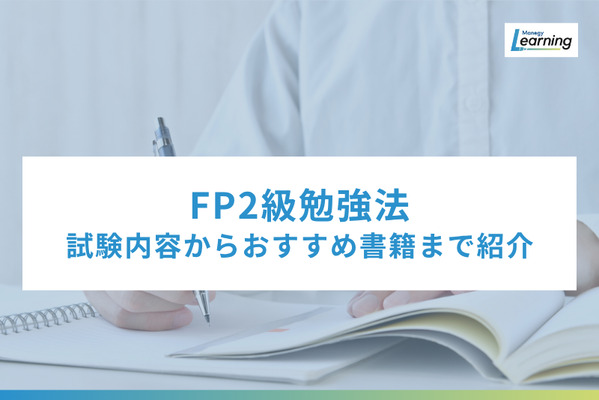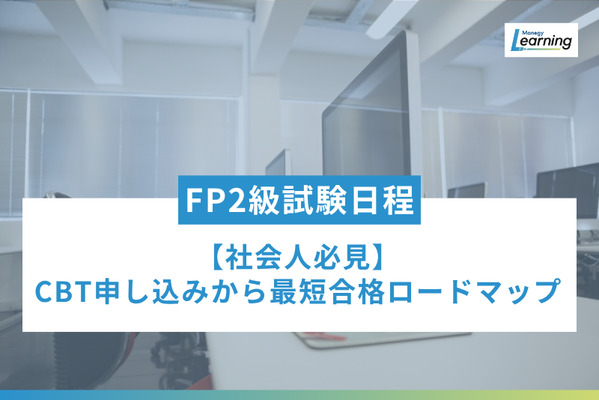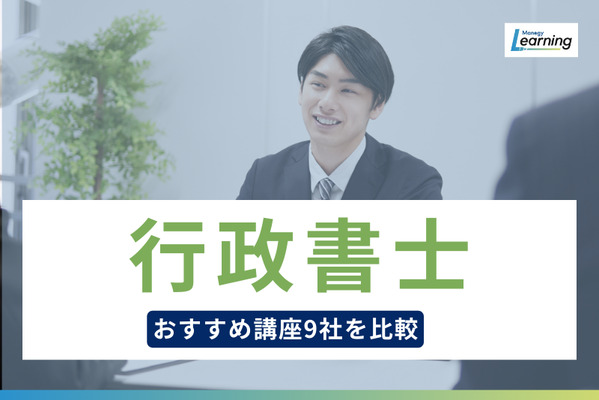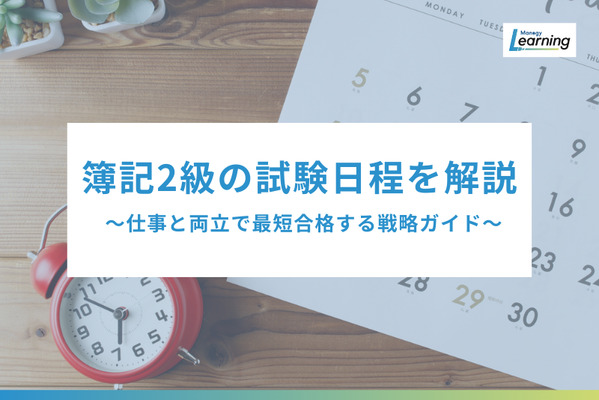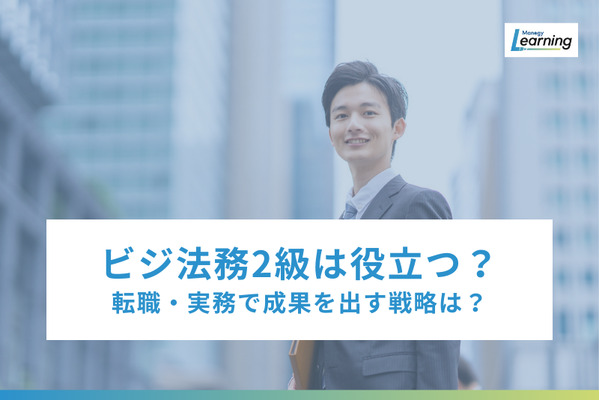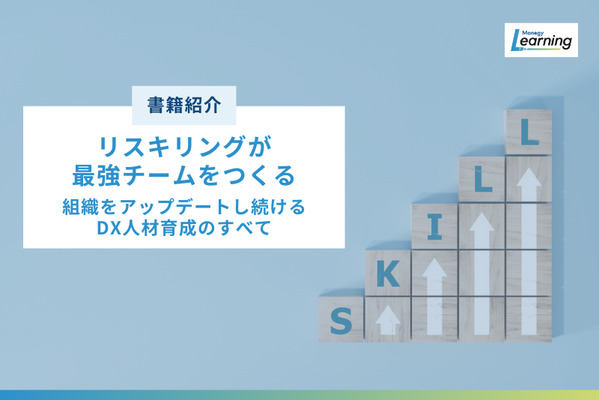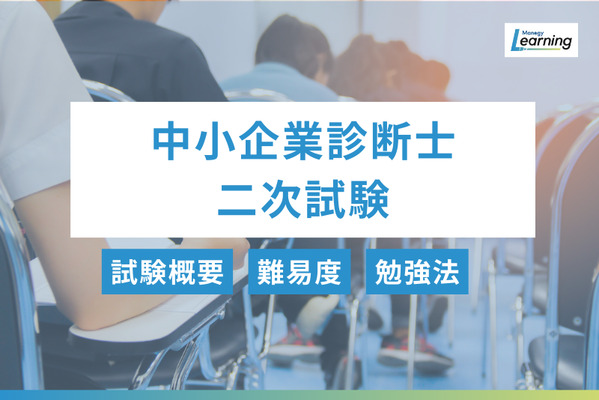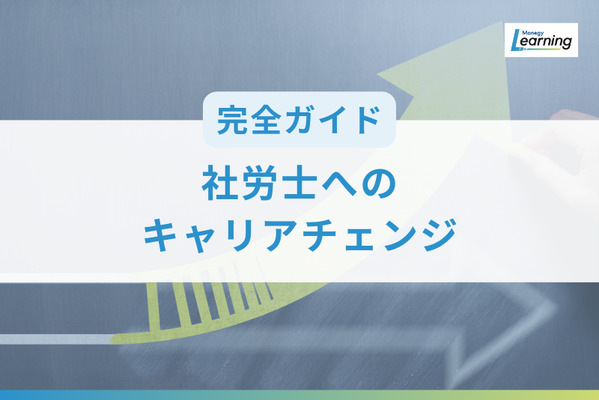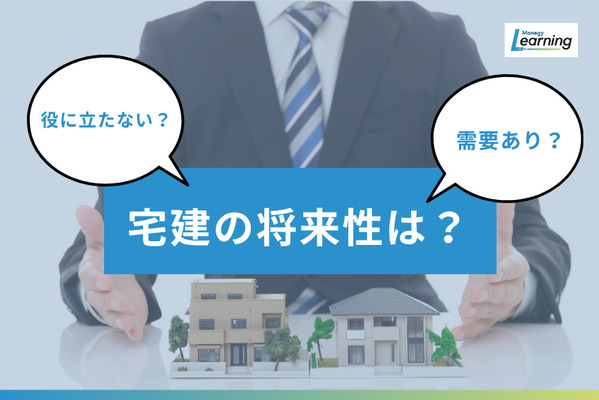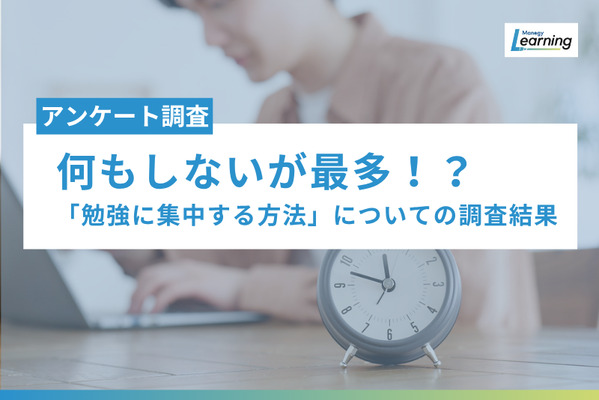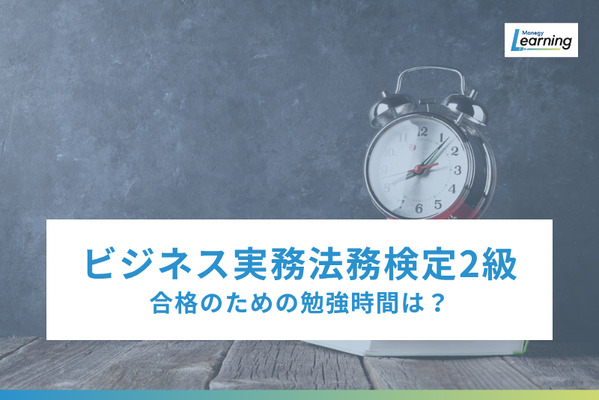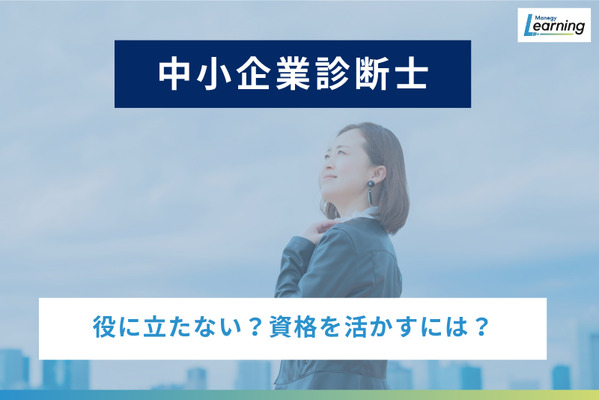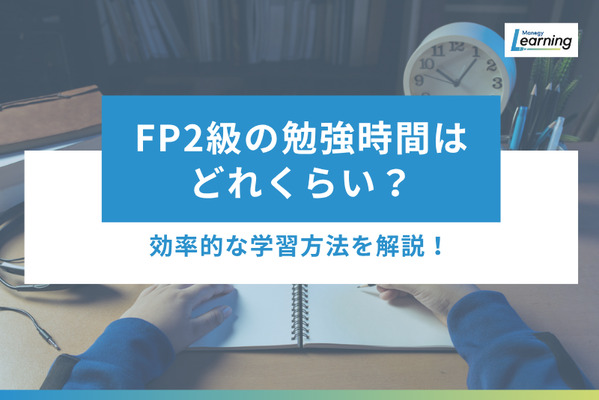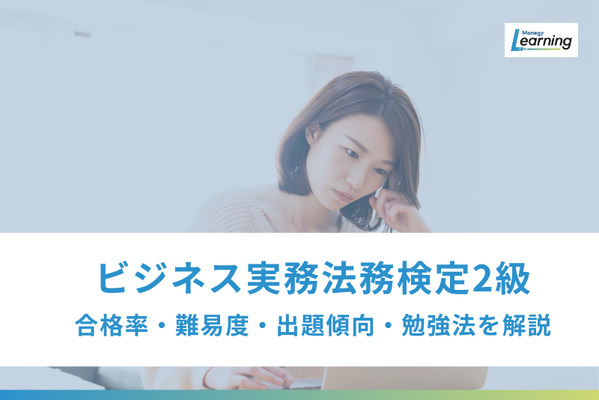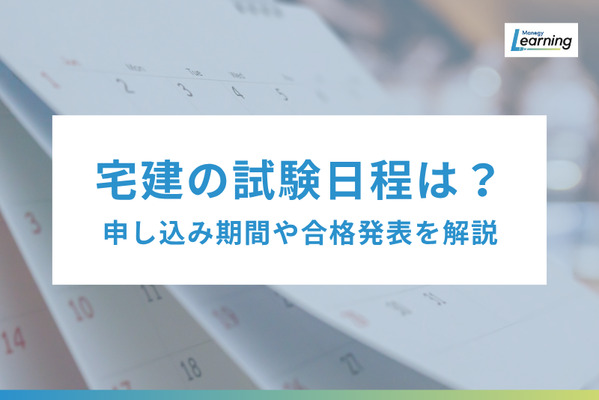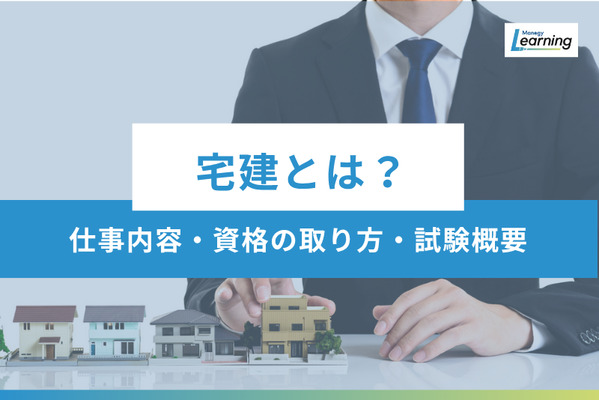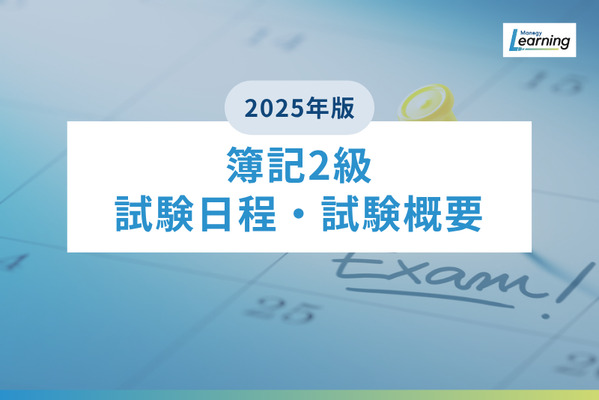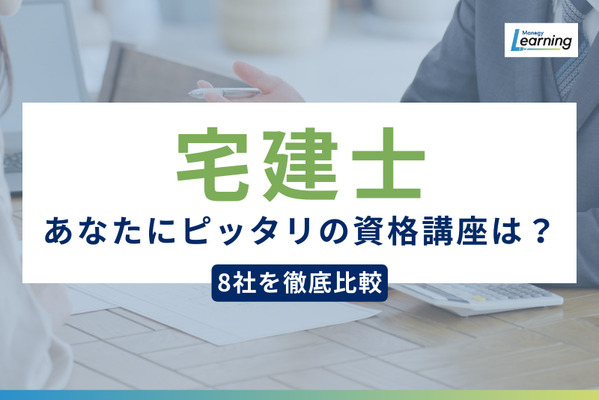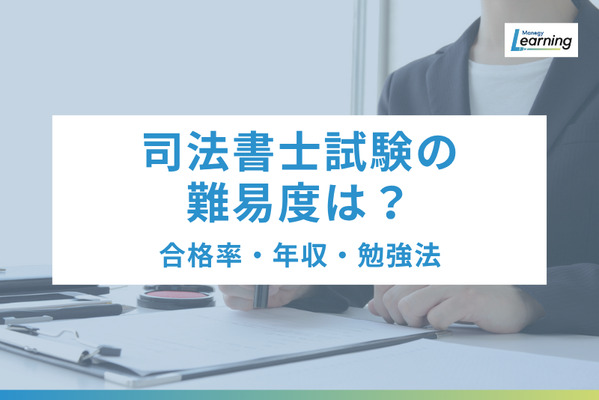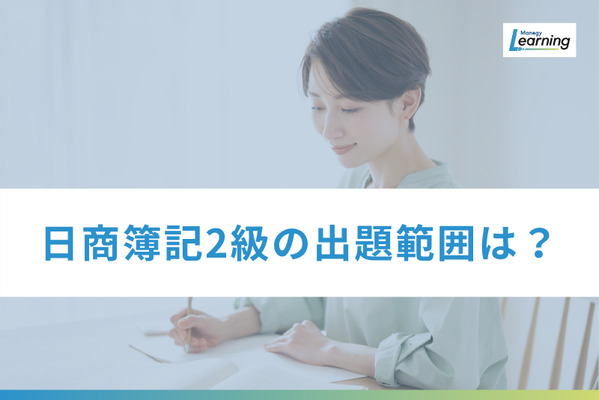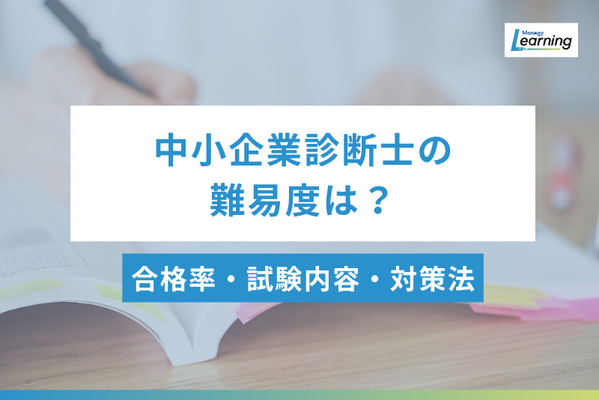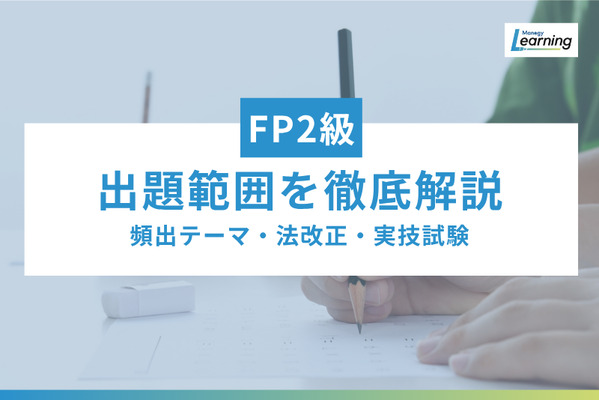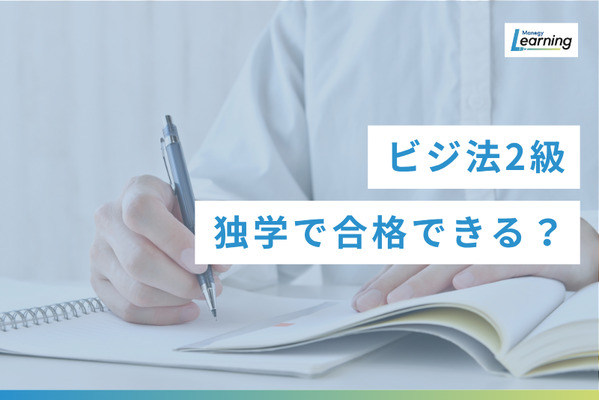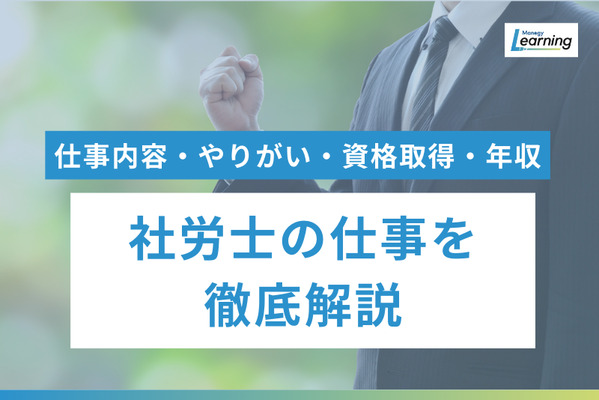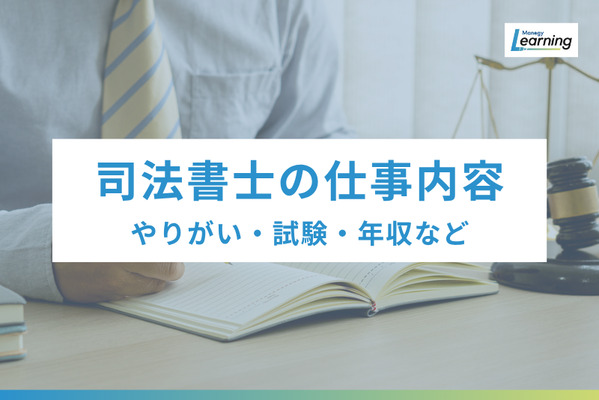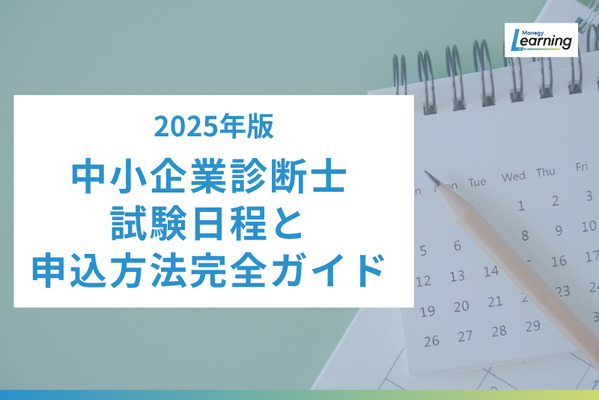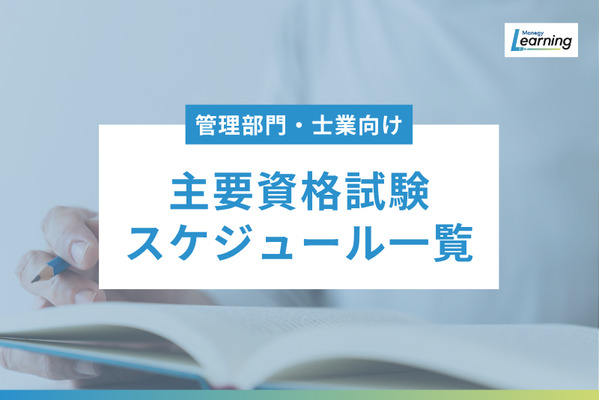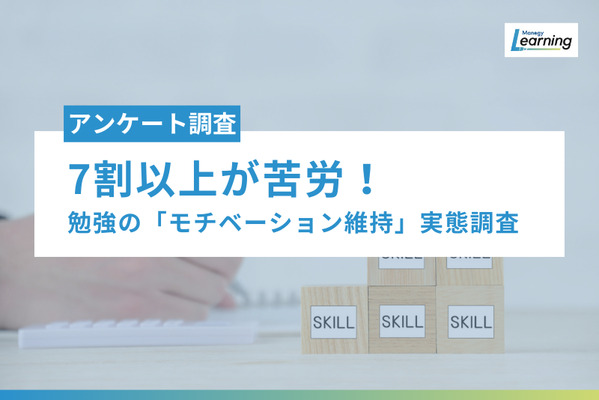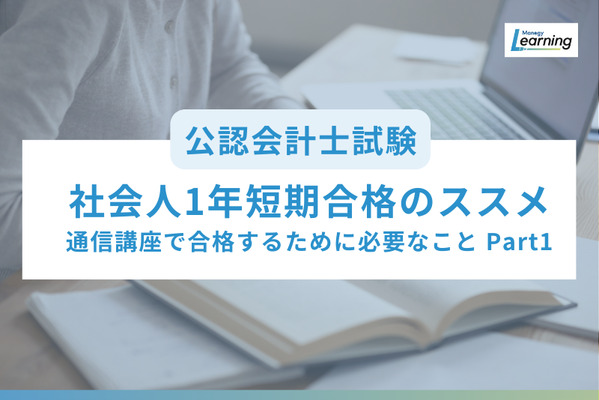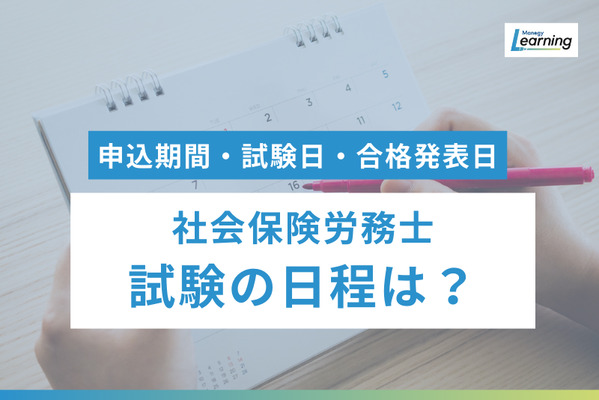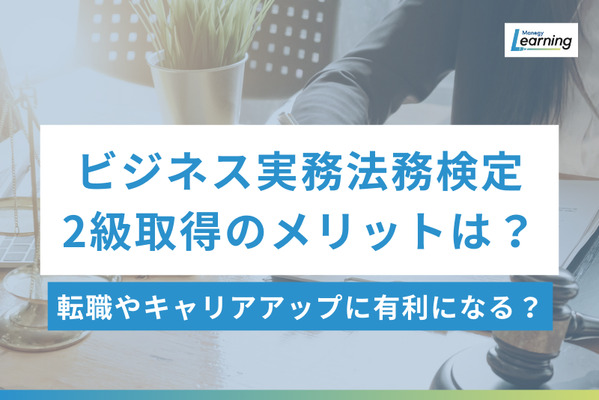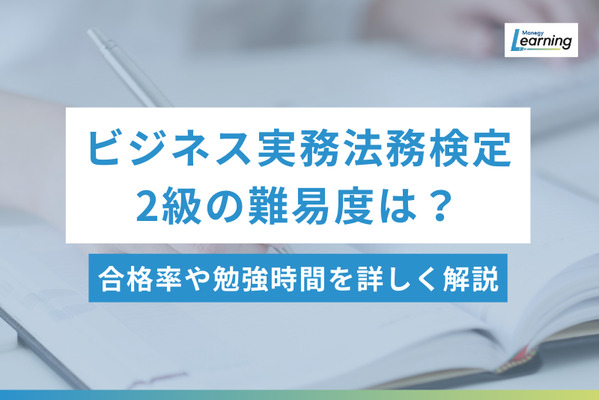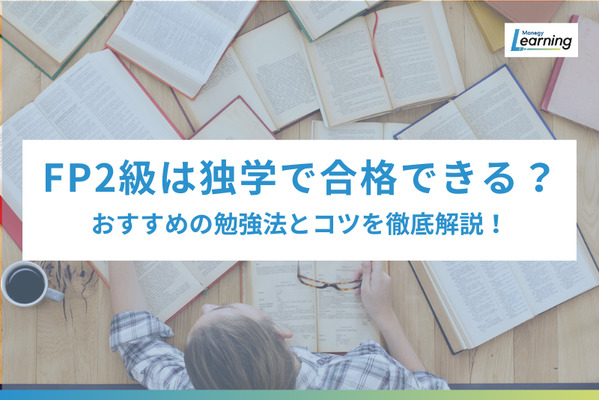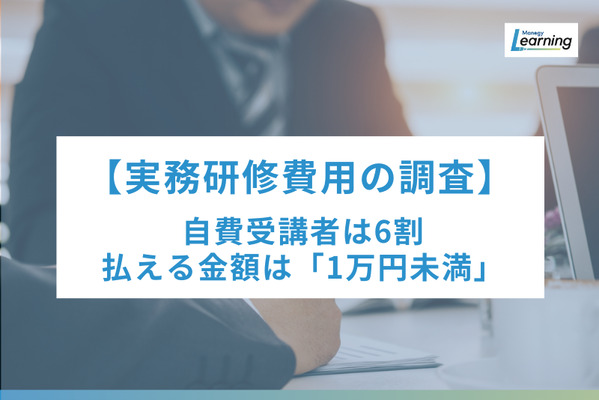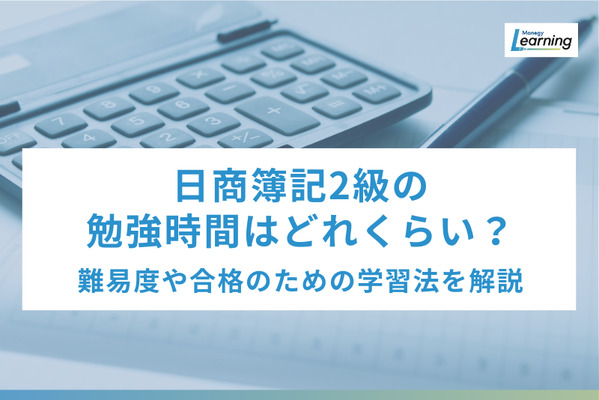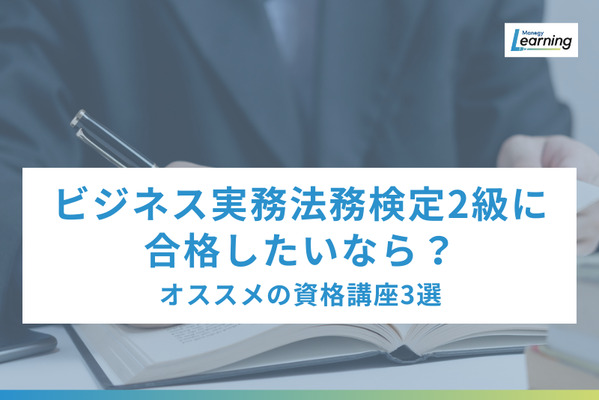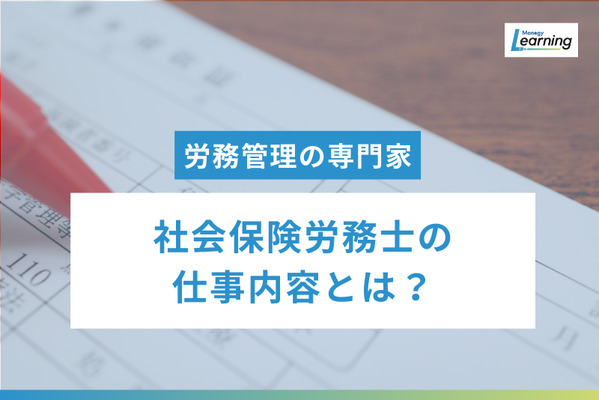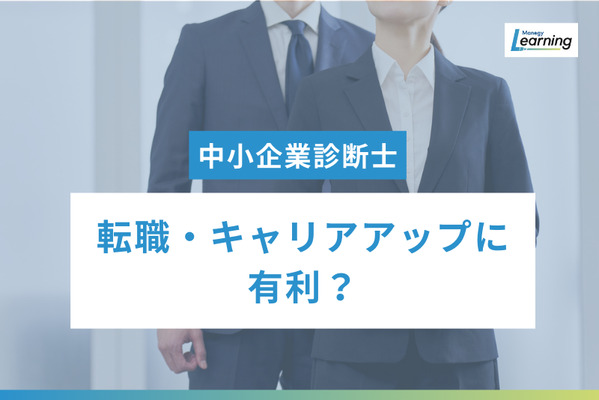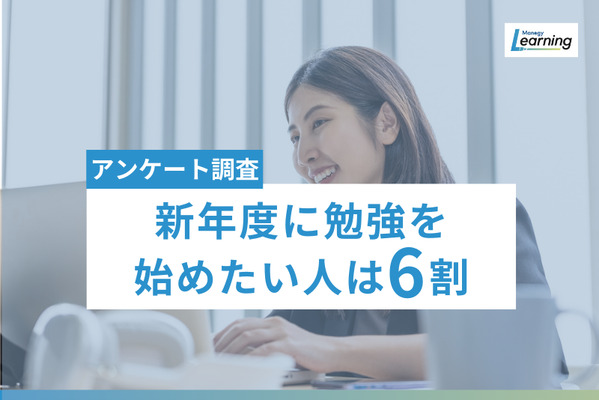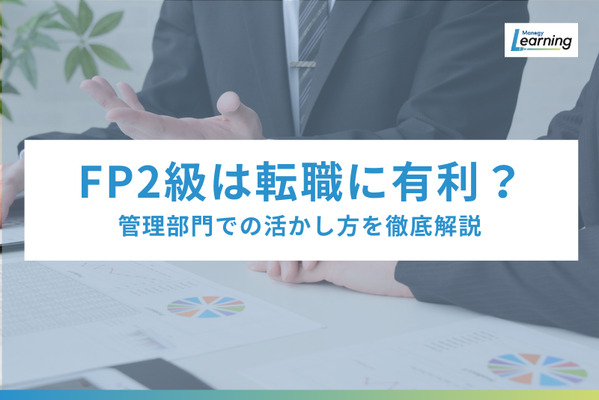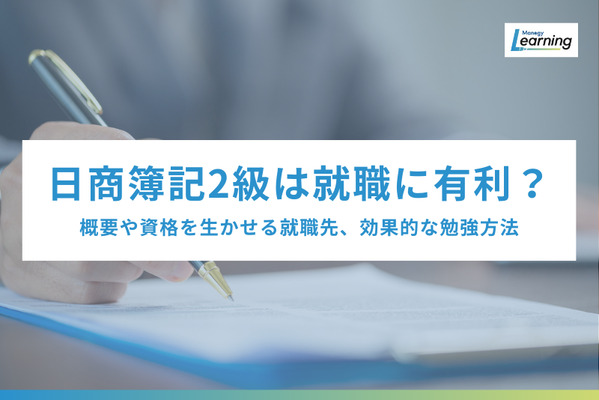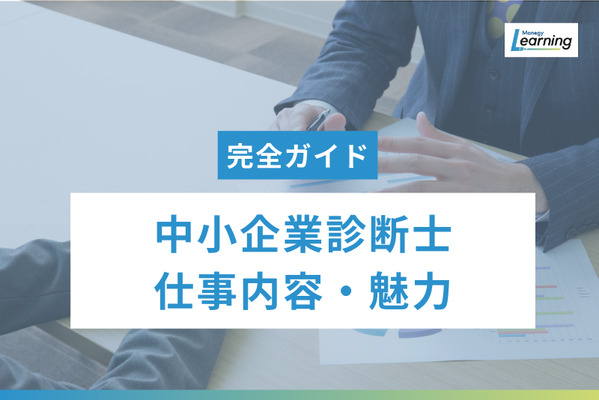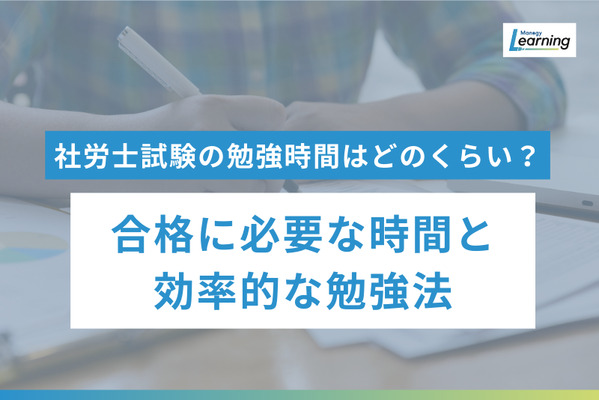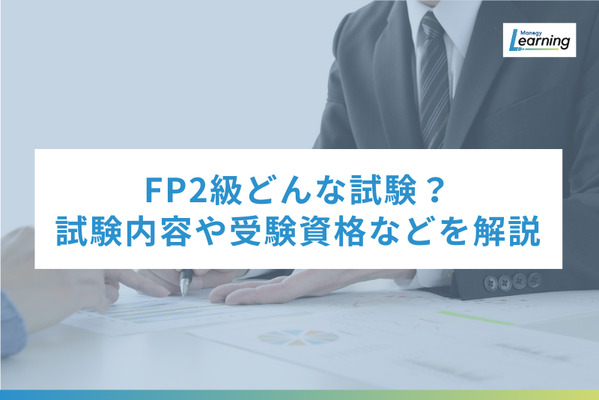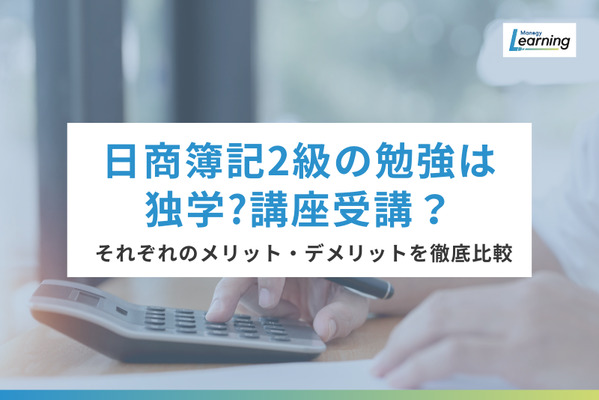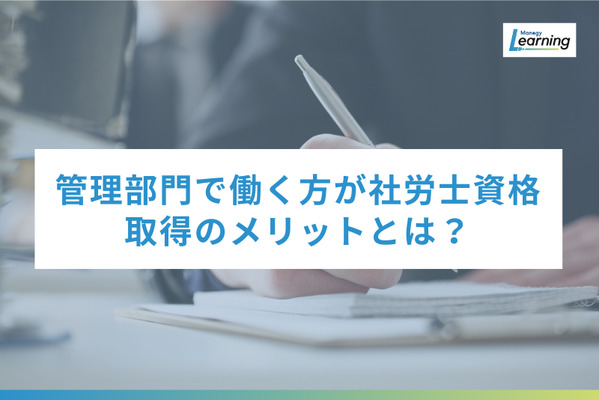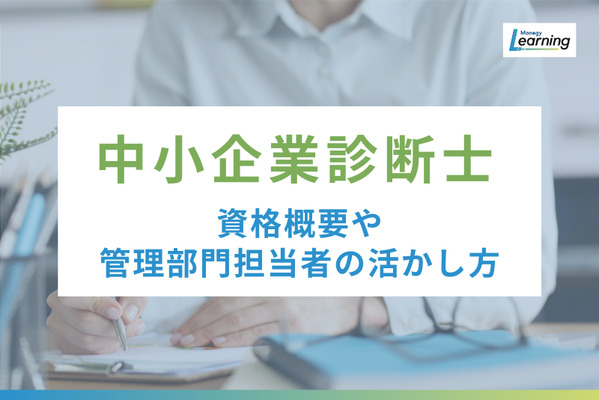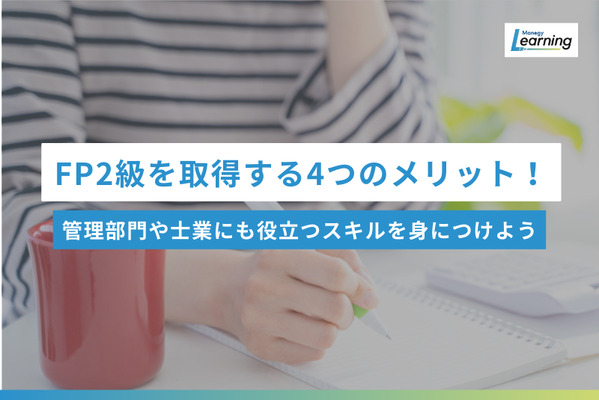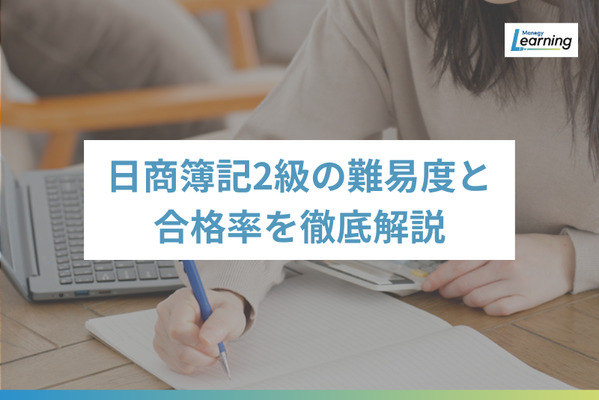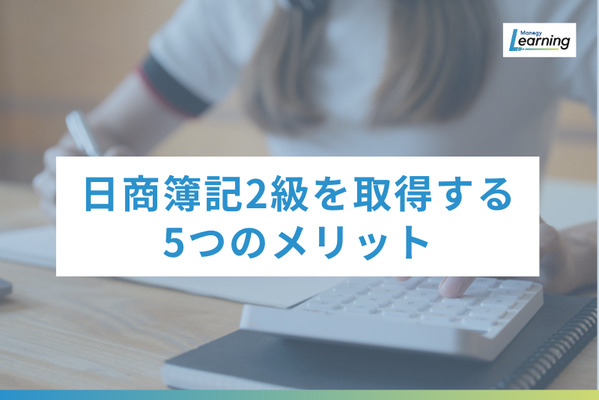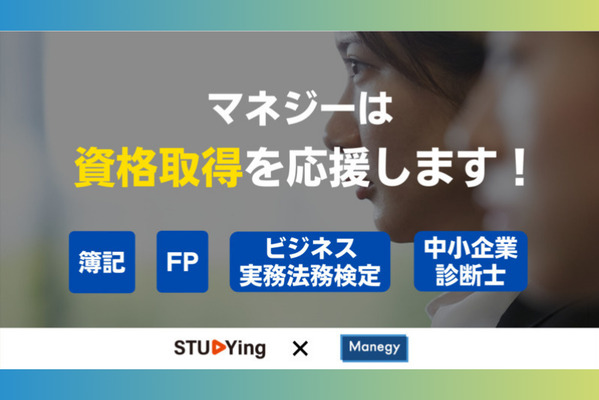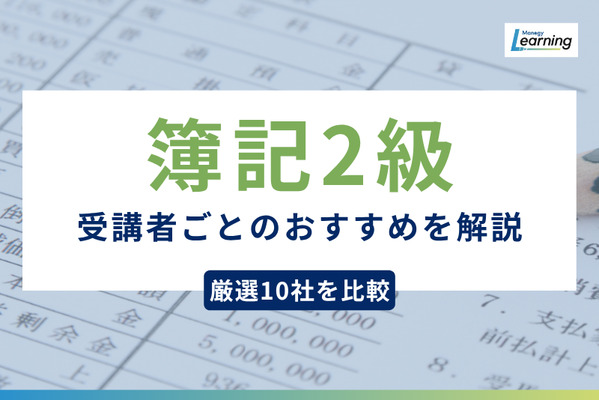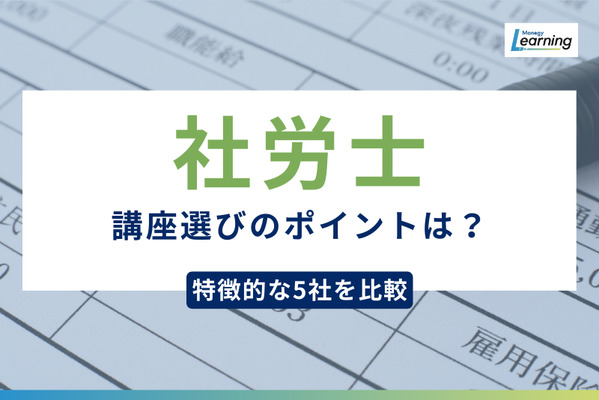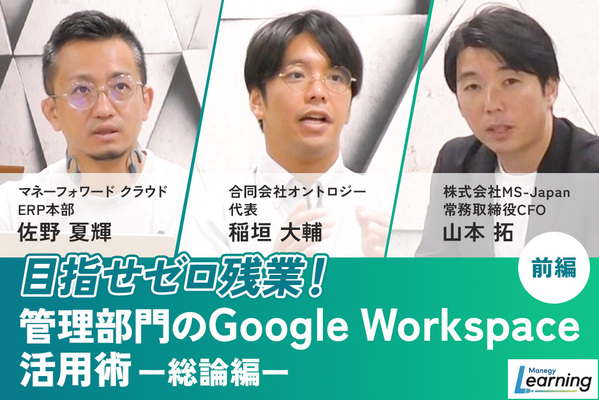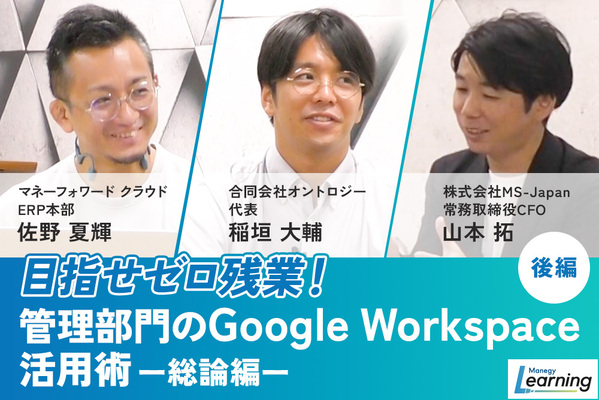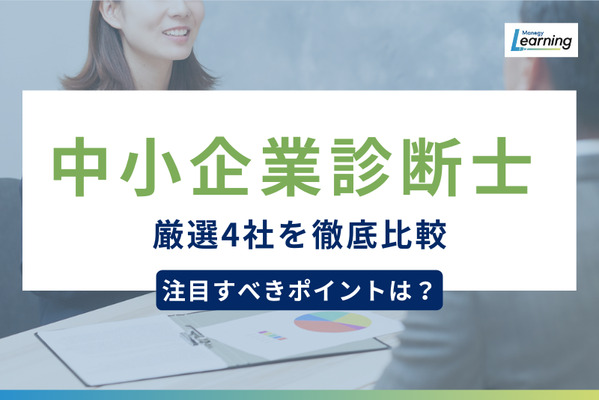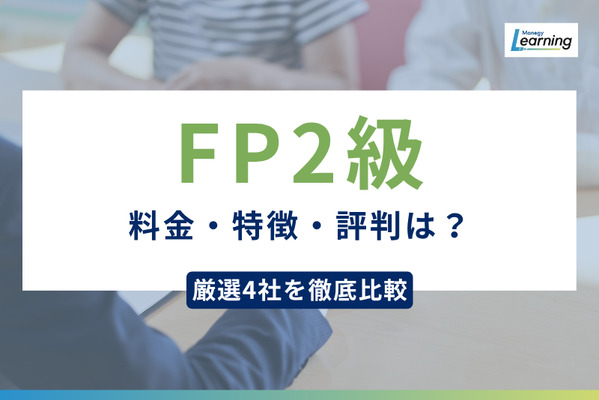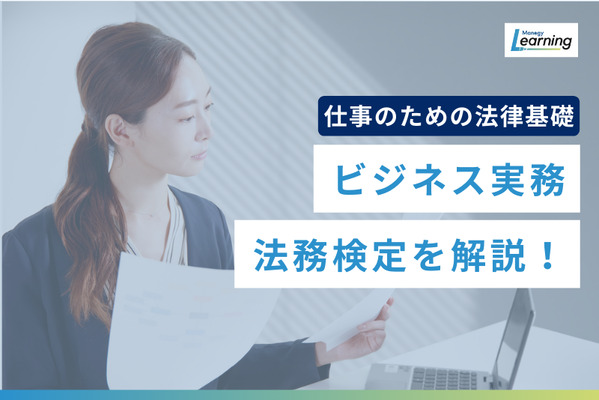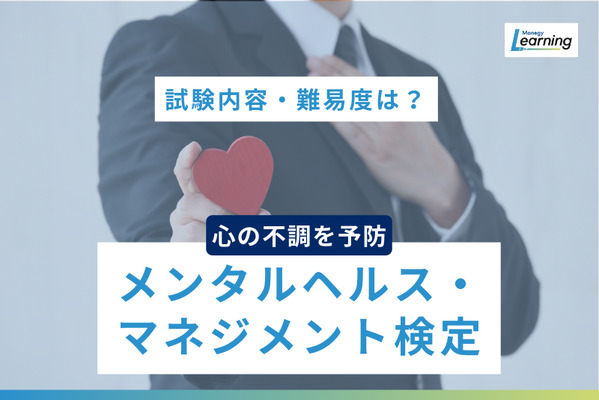司法書士の試験の受験資格は?未経験や学歴不問でも挑戦できる理由と合格への条件を解説
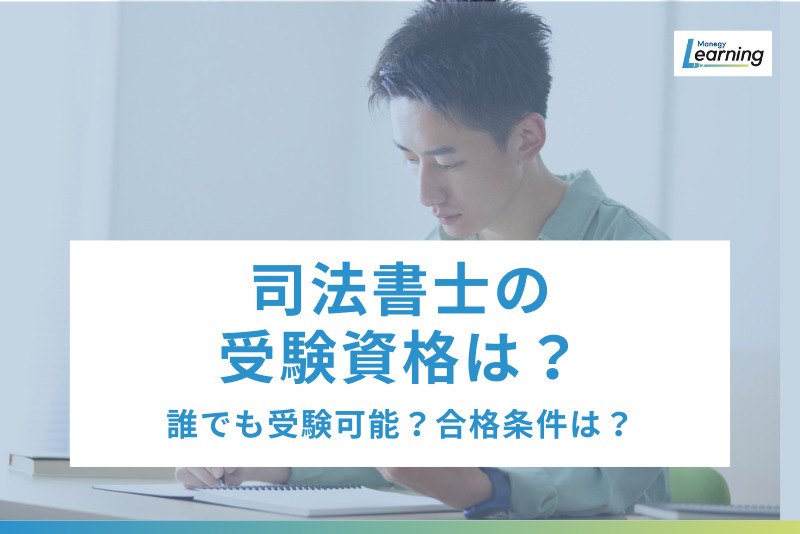
司法書士は法律に関する国家資格のひとつです。読者の皆さんのなかにも、今まさに受験勉強に励んでいる人や、挑戦を検討している人がいるのではないでしょうか?
しかし、合格率は例年4~5%程度と難関資格と言われています。
「将来のために法律の専門性を身につけたい。でも、今さら挑戦できるだろうか…?」
「法学部出身ではないし、法律の知識もないから、司法書士を目指すのは無謀かも…」
司法書士を目指す人の中には、こうした不安や迷いがある方もいるかもしれません。特に、社会人や異業種からの挑戦者は、法律分野は敷居が高く感じられるかもしれません。
しかし実際のところ、司法書士試験には学歴や年齢などの受験資格が一切なく、誰でも挑戦することができる資格です。これまでの経歴や専門知識の有無に関わらず、努力次第で合格を目指せるのです。
この記事では、司法書士試験は未経験者でも挑戦できる理由、合格に必要な条件や勉強方法の選び方、さらには合格後のキャリアパスや将来性までを詳しく解説します。
【結論】司法書士に受験資格はない!未経験でも挑戦できる2つの理由とは?
司法書士は、法律関連の仕事や学業が未経験でも受験できる“オープン”な資格試験です。この項では、未経験でも挑戦できる主な理由を2つご紹介します。
理由①:「学歴・年齢不問」だから
司法書士を管轄している法務省が公式サイトなどで公開している
令和7年度司法書士試験受験案内書によると、「この試験は、司法書士法第6条の規定に基づいて行われるものであり、受験資格の制限はなく、誰でも受験することができます」と記載されています。
つまり、司法書士試験は、学歴や職歴などの条件が一切課されていないのです。そのため、これまで法律に触れたことがない人や、全く別分野のキャリアを積んできた人であっても、受験を申し込めば試験を受けられます。例えば、高校卒業後すぐに受験したり、定年退職後に挑戦したりすることもできます。勉強さえすれば、人生のどの時点から挑戦しても合格できる可能性があるのは魅力的でしょう。
理由②:合格者の大半が30代以上だから
受験資格は学歴・年齢不問とはいえ、実際にどのような人が合格しているのか気になると思います。
法務省の公式発表データ令和6年度司法書士試験の最終結果についてによると、司法書士試験の合格者は幅広い年代で分布していることがわかります。合格者の平均年齢は41.50歳で、最低年齢は20歳(1人)、最高年齢は73歳(1人)でした。年代別で合格者を分けると以下のとおりです。
年代別合格率
| 年代 | 合格者の割合 |
|---|---|
| 20代 | 14.2% |
| 30代 | 30.9% |
| 40代 | 30.5% |
| 50代 | 17.1% |
| 60代以上 | 7.2% |
合格者のメインは30代~40代で全体の60%以上を占め、30代以上では約85%となっています。このデータから司法書士試験は、社会人経験やライフステージを経てから挑戦しても、合格できる資格と言えます。長期的な視点をもって受験に取り組むことができ、現役時代はもちろん、定年後やセカンドキャリアとして挑む人にも門戸が開かれています。
司法書士合格に向けた勉強
司法書士は誰でも挑戦できますが、合格率は例年4~5%程度と非常に難しい資格試験です。ここでは、合格するための勉強について紹介します。
勉強時間をしっかり確保する(目安は約3,000時間)
司法書士試験の出題範囲は広く、民法や会社法・商法、不動産登記法、商業登記法など、11科目分の膨大な知識を正確に理解し記憶する必要があります。一般的には、合格までにおよそ3,000時間の勉強が必要と言われています。
例えば、2年間で合格を目指す場合は、年間1,500時間、1日あたり約4~5時間の勉強が必要になります。社会人は毎日約4~5時間を勉強に費やすのは難しいでしょうから、平日は通勤時間や就業時間外の早朝・夜の時間を使い、休日にまとまった勉強時間を確保するのが現実的なスケジュールとなるでしょう。
試験科目の詳細を知りたい方は下記の記事がおすすめです。
この記事を読んだ方にオススメ!
継続的に勉強する
司法書士試験の勉強は長期戦です。約3,000時間の勉強量を短期間で詰め込むのは現実的ではなく、2~3年など時間をかけて計画的に進めるのがよいでしょう。勉強を継続させるには、例えば以下のような方法があります。
- 年間、月間、週間とそれぞれ目標設定を変えて勉強計画を立てる。
- 定期的に模擬試験を受けて実力を確認する。
- モチベーションを維持するため、SNSや通学の予備校などで勉強仲間を作って励まし合う。
独学と講座受講、どちらがおすすめ?
司法書士試験の勉強方法は大きく分けて、独学・通信講座・通学型予備校の3つがあります。それぞれの特徴や向き不向きを理解し、自分に合った方法を選ぶことが合格への近道です。
勉強スタイル別の特徴と費用・向き不向き
以下は、勉強方法ごとの詳細な比較です。
| スタイル | 特徴 | メリット | デメリット | 費用目安 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独学 | 市販のテキストと問題集、無料動画などで学ぶ | ・費用が安い ・自己ペースで学べる |
・情報収集や勉強計画の設計が難しい ・やる気維持や自己管理が必要 |
数千円~数万円 | 自学力が高く、時間を柔軟に使える人 |
| 通信講座(オンライン含む) | 録画やライブの講義+添削サポート | ・比較的自己ペースで学びやすい ・講座によっては費用が手頃 ・地方でも受講可能 |
・自己管理が必要 ・質問があっても、即時対応が難しい |
約10~30万円程度 | ・自宅で集中して勉強できる人 ・多少の法学知識がある人 |
| 通学型予備校 | 専門講師による対面指導。定期模試などもあり | ・質問対応が迅速 ・勉強仲間と切磋琢磨できる ・やる気や程よい緊張感をbrしやすい |
・通学時間が発生する ・授業時間が決められているため、スケジュール調整が必要 ・受講費用が高め |
約20~50万円程度 | ・人とのコミュニケーションで良い刺激を得られる人 ・対面学習で成果を出せる人 ・自己管理や自学力に自信がない人 |
通信・通学講座で勉強しようと考えている方には、こちらの記事がおすすめです。
この記事を読んだ方にオススメ!
教育訓練給付制度について
「教育訓練給付制度」は、雇用保険加入者や過去に加入していた人が、指定講座を受講して修了した場合、一部受講料が支給される公的制度です。
教育訓練給付制度は、
- 専門実践教育訓練
- 特定一般教育訓練
- 一般教育訓練
の3種類に分類されますが、司法書士講座が対象になるのは、「特定一般教育訓練」「一般教育訓練」となるため、今回はこの2種類について解説します。
対象者条件
| 制度 | 対象者 |
|---|---|
| 特定一般教育訓練 | 下記いずれかの条件を満たす人で、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した人 1.雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等 特定一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある人 2.雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった人 一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある人 |
| 一般教育訓練 | 下記いずれかの条件を満たす人で、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した人 1.雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等 一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある人 2.雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった人 雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある人 |
支給額
特定一般教育訓練:
最大で受講料の50%(上限25万円)
一般教育訓練:
最大で受講料の20%(上限10万円)
※講座は通信型・通学型のいずれも対象です。
申請条件
- 講座の出席率や修了要件(例:通信講座なら添削提出80%+修了試験60点以上)を満たすこと
- ハローワークでの事前確認と申請手続きが必要
※一般教育訓練の場合は講座の受講・修了後の申請のみ
教育訓練給付制度は、大手予備校の司法書士講座でも対象となるものが多く、例えば費用が50万円前後の講座を受講すれば、最大10万円が戻ります。講座受講を希望していても費用面で迷っている人にとっては、活用するメリットが大きい制度です。
制度詳細は厚生労働省の 公式サイトをご確認ください
司法書士合格後のキャリアパスと将来性
司法書士資格に合格後は、どのようなキャリアパスや将来性があるのでしょうか? 本項で見ていきましょう。
司法書士合格後のキャリアパス
司法書士資格取得後の道は大きく3パターンに分けられます。司法書士事務所などに勤務する「勤務司法書士」、自身の事務所を立ち上げる「独立開業司法書士」、一般企業などで働く「企業内司法書士」の3つです。ここでは、それぞれの活躍の場や収入、働き方の特徴を表でまとめました。
| タイプ | 活躍の場 | 特徴 |
|---|---|---|
| 勤務司法書士 | 司法書士事務所、法律事務所 | 実務を学びながら収入も安定。OJTで効率よくスキル習得できる |
| 独立開業司法書士 | 自身の事務所、不動産・金融顧客対象外部営業 | 顧客開拓や経営が不可欠。自由度が高く、労働時間も自分で調整できる |
| 企業内司法書士 | 不動産・金融系企業の法務部 | 福利厚生が充実している場合が多い。対応範囲が限定される可能性もあるが、安定性は高い |
ダブルライセンスでキャリアをさらに強化
司法書士の資格だけでなく、他の資格も保有することで、キャリアパスは大きく広がります。ここでは、資格ごとのダブルライセンスのメリットを取り上げます。
司法書士+行政書士:会社設立や契約書作成など、許認可関連の仕事を一括で請け負える。
司法書士+宅建士:不動産取引と登記実務が可能になり、不動産会社や個人客からの信頼が高まる。
司法書士+税理士・社会保険労務士:税務・労務面の相談にも対応でき、コンサルティング業務が可能に。
司法書士+土地家屋調査士:測量・境界調整などと登記を一体的に対応できる。
以上、複数資格を持つことで、業務の幅が広がり、クライアントからの受注チャンスが格段に広がります。専門性とサービス品質が向上すれば、ロイヤリティやリピート率も高められ、独立後の成功確率が大きく上がるでしょう。
ダブルライセンスについては、こちらの記事で詳細を解説しています。ぜひご確認ください。
この記事を読んだ方にオススメ!
AIに仕事を奪われる?司法書士の将来性
AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの発展により、書類作成や登録申請の定型業務は自動化が進んでいます。一方で、以下の領域では人間である司法書士の価値が保たれるでしょう。
- 家族構成や相続事情に応じた判断と提案
- 複雑な不動産取引や法人設立における調整
- 金融または契約トラブルに対する解決支援
- 個々の事情に応じた文書のカスタマイズ説明
つまり、事務処理はAI、対人折衝やコンサルは人間、というスタイルが今後の主流になるでしょう。自身の専門性と対話力を磨き、人間にしかできない業務で差別化することが重要です。
司法書士の受験に関するQ&A
Q.どんな試験内容?
司法書士試験の筆記は「午前・午後の択一式」「午後の記述式」で構成され、科目は民法や会社法・商法、不動産登記法、商業登記法など、全部で11科目あります。合格には、総合点に加えて科目ごとの足切り基準もあり、高度な理解力と正確性が問われます。
Q.口述試験はどういうもの?
筆記試験合格者を対象に、10月中旬に1日で実施されます。内容は書面での説明や短い事例問題への口頭応答で、合格率はほぼ100%。記述内容の理解度や応答の的確さなどが評価されます。
Q.合格したらすぐ司法書士になれる?
合格後は研修期間が必要です。「中央新人研修」「ブロック新人研修」「司法書士会研修」の全てを受講しなければなりません。その後、都道府県の司法書士会への登録申請をして登録が完了すると、晴れて司法書士として活動できます。
まとめ|司法書士は努力すれば合格する可能性は誰にでもある!
司法書士試験は「誰でも挑戦できる」国家資格です。受験資格の制限がなく、令和6年度の合格者の平均年齢は41.5歳で、30代~40代の人が全体の60%以上を占めました。何歳からでも挑戦でき、努力すれば未経験者でも合格できます。勉強時間は約3,000時間必要ですが、計画を立てて継続して学べば、十分に目標を達成できます。自分に合った勉強スタイルを選び、AI時代の現代も活躍できる司法書士を目指してみませんか。

Manegy Learning
Manegy Learningは管理部門・士業の皆さまに向けて、実務に役立つTIPSや資格取得のためのスクール取得などの情報を発信し、みなさまの学びをサポートします。
MS-Japan
https://www.manegy.com/learning/