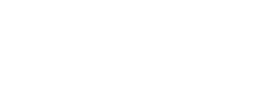2024年のトレンド予想
経理
中央経済社/旬刊経理情報編集部
「旬刊・経理情報」は1973年の創刊以来、一貫して会計・税務・財務・法務などの新制度や実務問題を、タイムリーに、わかりやすく取り上げてきた専門実務誌。決算対策、税制改正、株主総会対応などの定番企画のほか、M&Aやサステナビリティ開示、不祥事対応など部門横断的な記事も随時掲載。(毎月1日・10日・20日発行。全面2色刷。)
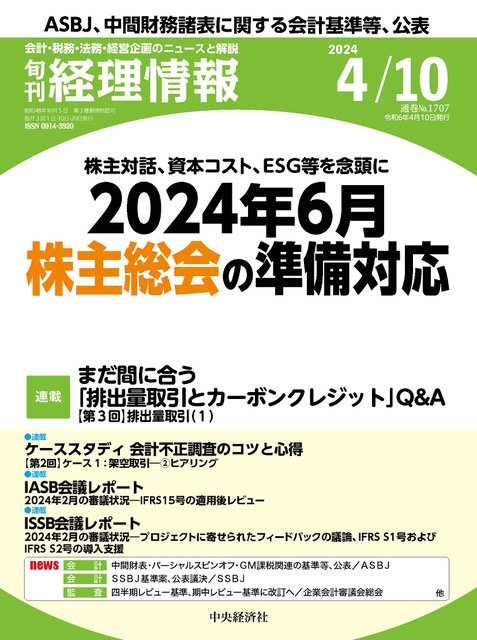
昨年、インボイス制度の開始という大きな変化があり、年明けには電子帳簿保存法の義務化がスタート。大きな制度変更があった経理部門ですが、結果的に業務の電子化とペーパーレス化が進んだ1年となりました。その翌年となる2024年度、経理部門には一体どのような動きが出てくるのでしょうか?
今回は経理に関する専門誌として50年以上の歴史を持ち、多くの経理パーソンに読まれている旬刊経理情報の編集部の方に2024年度の経理周辺のトレンドに関してお話をお聞きしました。
新型コロナの流行に続いてインボイス、電子帳簿保存法で大きく進んだ経理業務のデジタル化

Manegy編集部: 2024年度のお話に入る前に、まず経理部門の2023年度を振り返りたいと思います。昨年度はインボイス制度の開始や電子帳簿保存法義務化の開始など、多くの企業の経理業務に大きな影響を与えました。
旬刊経理情報編集部: そうですね、インボイス制度に向けたシステム導入が進んだこともそうですし、コロナ禍の数年間で経理部門を含む管理部門全体のデジタル化が進みました。また、年明けには電子帳簿保存法の義務化がスタートしたため、その準備として法改正に合わせて関連業務のデジタル化が進んだ1年だったと言えるでしょう。
Manegy編集部: 法改正やそれに伴うデジタル化は多くの企業で共通するトピックでしたね。他にもありますか?
旬刊経理情報編集部: 法改正や経理実務以外だと、上場企業を中心に経営課題としてSDGsやGX、人的資本の開示など、従来の会計とは異なる点で企業を評価する動きが進んだ1年だったと感じます。それに伴い、今まで決算を早く正確に締めることを担っていた経理財務部門の役割に変化が出始めている印象です。
Manegy編集部: 企業価値の評価の仕方が変化し、人材や事業の継続性などの無形資産の部分が重要視される動きですね。
旬刊経理情報編集部: はい、会計や税務などと主旨は異なりますが、財務面以外にも自社の価値向上という意味では経理部門としても無視できない流れです。また、最近大型のM&AやTOBのニュースも多く耳にしますよね。こうした動きも、企業価値向上というか成長戦略の手段として選択されることが増えてきていることなども、認識しておくべきでしょう。

システム導入後に重要になるのはデータ活用
Manegy編集部: こうした流れを踏まえて、2024年度はどのような年になって行くのでしょうか?まずは実務寄りの部分からお聞かせください。
旬刊経理情報編集部: 実務寄りの部分となると、法改正関連で言えば「J-SOXの改訂」「上場企業の四半期報告書の廃止」「プライム上場企業の英文開示義務化」などが挙げられます。
「J-SOXの改訂」による変更点はいくつかありますが、先ほどの企業価値向上の話と通じる部分として、内部統制の目的の一つが「財務報告の信頼性」から「報告の信頼性」に変わったことは意義深いと思っています。これは財務情報だけでなく非財務情報に関しても重要であるということを意味しており、企業価値の評価の基準が変わってきていることに起因していると考えられます。
他にもITリスクや運用方法に関わる部分の変更も含まれており、時代とともに変化するさまざまな企業リスクを減らすために運用体制の見直しを行うなど、経理部門の実務に影響する部分もある程度含まれます。2024年の4月から開始となるため、すでに内容をチェックして対応済みの方々が多いと思いますが、期が変わるタイミングで改めて内容を把握しておくと良いでしょう。
Manegy編集部: 「四半期報告書の廃止」については、上場企業の経理財務部門としては大変助かる変更だという話も耳にします。
旬刊経理情報編集部: 四半期の開示書類の一部が単純に減るため楽になる方々も一定数いらっしゃると思います。決算短信と重複している部分が多いということで廃止して一本化することになったわけですが、業務という意味では単純に作成するものが減るため、嬉しい変更と感じる人も多そうです。
経営的な目線で見ると、ここにかかっていた手間やコストを本業に関わるところに振り分けられるということで、これもある意味でサステナブルな変更だと言えますね。
Manegy編集部: こういう変更はどんどんしていって欲しいですね。上場企業以外に影響のある変更はいかがでしょうか?
旬刊経理情報編集部: 上場企業以外にも影響が強いところでいうと、少し先にはなりますが「リース会計基準の変更」が検討されているのはご存じですか?
Manegy編集部: はい、2026年を目途に変更内容が議論されているようですね。
旬刊経理情報編集部: こちらは現在、議論の最中で、2026年度の適用に向けて準備が進められていますが、どうも1年先送りになりそうです。その意味ではまだ先の話かもしれませんが、特に借手のオペレーティング・リースの取扱いが変わり、多くの企業でB/Sが膨れ上がるなど大きな影響が出るため、注視していく必要がありそうです。
Manegy編集部: 制度改正以外のトレンドとしては何が挙げられますでしょうか?
旬刊経理情報編集部: 新型コロナウイルスの流行から昨年のインボイス・電子帳簿保存法への対応などで、多くの企業でシステム導入やペーパーレス化が進みました。それが次の段階に進む動きが出てくる可能性が考えられます。
Manegy編集部: 次の段階というと、例えば「システム同士の連携」でしょうか?
旬刊経理情報編集部: それもありますが、本質的にはデジタル化したことで蓄積されたデータをどのように活用して経営に活かしていくか、という点です。決算のための会計システムなど、基幹のシステムはもともと使っている企業が多かったところに、法改正による経費精算や請求書管理など周辺業務のシステム導入が進みました。これまでの業務がシステム化されるとデータが蓄積され、それらのデータが連携されて処理されるようになるのはもちろんですが、連携されたデータを活用するフェーズには至っていない企業も多いと思います。
数年前からDXという言葉が使われていますが、データ活用というところまで進んでようやく真の意味でのDXが進んでいくのだろうと思います。
Manegy編集部: データという意味では、会計システムに集める経理周りのデータ以外とも連携すると、経営判断に役立つ情報がこれまで以上に出していける状態になりそうです。
旬刊経理情報編集部: そうですね。これまでは決算を早く、正しく、効率よく終わらせることが、「管理部門」としての経理の役割だったかもしれませんが、それが大きく変化するタイミングに来ているのかもしれません。そのためにも、生成AIやRPAなどもうまく利用して従来の業務を自動化したり、BPOなどの活用で変化に適応していく必要があるかもしれません。
AIに代替されない次世代の経理部門になるために必要なこととは?
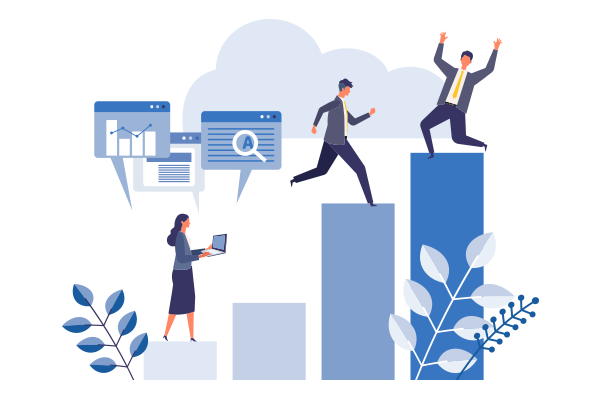
Manegy編集部: システム導入はもちろん、生成AIやRPAといった便利なツールが数多く普及してくると、経理部門の実務や役割にかなり影響がありそうです。
旬刊経理情報編集部: 数十年前から徐々にパソコンが普及し、経理業務が紙からシステムに、そしてクラウドに、と変わっていったのと同様に、ルーティン業務はどんどん効率化されていくことになるでしょう。そのスピードは過去に会計システムが普及したのに比べて、早いだろうと思います。
Manegy編集部: 経理部門に限らず、Excelの関数などを業務で使えると便利ですが、生成AIなどのツールがそのくらい普及することを想定して、使っていけるようになる必要がありそうです。
それも踏まえて、経理部門として、あるいは経理担当者個人として、どのようなことに取り組んで行くべきでしょうか?
旬刊経理情報編集部: ツールの活用などもありますが、あくまでもそれは手段です。本質的な部分として経理部門が目指すべきは「経営の意思決定を支援する役割を担うこと」だと考えます。
そのためには、いろいろなことを知り、考え、実行する必要があるので、そういった部分に時間を使えるようにするために既存の業務を効率化する。その手段の一つとして便利なツールを使いこなせることも必要だということです。
Manegy編集部: 経営の意思決定を支援することが本質ということで、それができるようになるためには、本当にいろいろな知識やスキルが必要になりそうです。
旬刊経理情報編集部: まずは自社のビジネスを理解し、自社の経営者がどうしたいのか?を理解する必要があります。自社の事業内容や目指すことをきちんと理解したうえで、自社のビジネスにかかわる制度改正や、関連するニュースなどに広くアンテナを張る必要があります。
制度改正等への対応はもちろんですが、会社の状況によって他にもたくさんのことが挙げられるでしょう。例えば、TCFD提言以降、企業経営にはESGやSDGsといったサステナブルな経営が求められていますが、サプライチェーンへの影響も出る可能性があります。取引先が取引相手にもGXへの取り組みを求めるような動きです。
Manegy編集部: 一定のGXへの取り組みをしているなど、サステナブルな経営をする会社としか取引しないということですね。
旬刊経理情報編集部: 事前に周辺知識を持っていないと、急に対応を求められても難しい可能性があります。そのためにも、自社の事業や取引先の状況によってはCO2排出量に関してもアンテナを張っておく必要があるかもしれません。
それを踏まえて経理の方々が具体的にすべきことの一つとして、自社の事業を理解し周辺の動きにアンテナを張ることは意識すべきだと言えます。
Manegy編集部: 確かに目の前の業務だけやっていても、そう言った部分については考える機会がないかもしれません。
旬刊経理情報編集部: また、経営をサポートするためには自社のデータの活用や周辺情報へのアンテナが必要ですが、それを基に正しい経営判断をするために、経営に対して情報提供することも必要になります。そのためにはプレゼンスキルも重要になってきます。
Manegy編集部: なるほど、これからの時代、AIやシステムに負けないため経理になるには、会計や税務の知識だけというわけにはいかないようですね。
旬刊経理情報編集部: ベースとなる専門知識はもちろん大事ですが、自動化されないスキルも身につけて行く必要がありますね。
読者へのメッセージ
Manegy編集部: ここまで、2024年度の経理部門のトレンドについてお話をお聞きしましたが、最後にこれをご覧の経理の方や管理部門の方にメッセージをお願いします。
田上氏: 制度面では少し先ですが、リース会計基準の変更内容に気を配っておく必要があるでしょう。
また、経理部門の役割が大きく変化する流れに乗り遅れないように、周辺情報へのアンテナの感度を高めることや、データ活用スキル、プレゼンスキルなど、システムやAIに代替されないための+αのスキルが重要になると思うので、それを意識しておくと良いでしょう。
Manegy編集部: ありがとうございました。
取材・文/Manegy編集部 有山智規