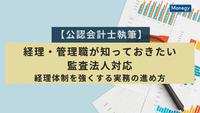公開日 /-create_datetime-/
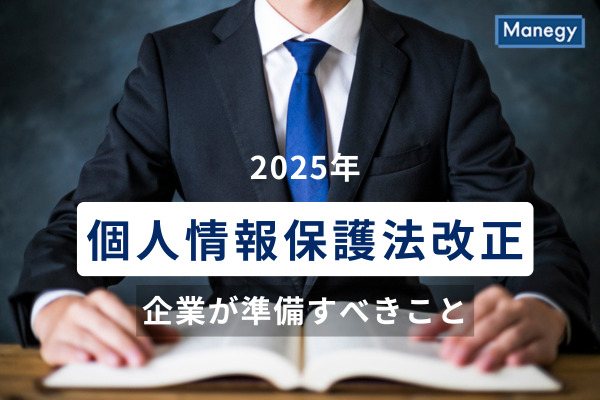
個人情報保護法の2025年改正について
2025年改正の背景
個人情報保護法については、2022年4月から施行されている2020年改正法の附則において、法律の施行から3年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、改正法の施行状況についての検討を行い、必要があるときは措置をとるとされていました(以下、「見直し規定」といいます。)。2025年改正は、この見直し規定を踏まえて行われるものです。
2025年改正に向けた現在の状況
見直し規定に基づく検討作業は2023年11月から開始されており、有識者や関係団体等へのヒアリング等を経て、2024年6月27日に「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直しにかかる検討の中間整理」(以下「中間整理」といいます。)が個人情報保護委員会から公表されました。また、2024年6月27日から同年7月29日まで、中間整理についてのパブリックコメント手続が実施され、1,731の団体・事業者・個人から、合計2,448件の意見が提出されました。
中間整理はその時点までの議論や検討を踏まえた個人情報保護委員会の考えをまとめたものであり、2025年に改正される内容が含まれている可能性があります。中間整理のうち、特に重要と思われるポイントについては、後述します。
想定される今後のスケジュール
2025年改正については、以前の個人情報保護法改正時のスケジュールに照らすと、2024年末頃に改正大綱が公表され、具体的な改正事項が明らかになると予想されます。その後、2025年春の通常国会での審議を経て、2025年改正法が公布されることになると予想されます。2025年改正法の施行時期については、公布から1年後ないし2年後(2026年から2027年頃)になる可能性が高いと予想されます。
lockこの記事は会員限定記事です(残り3905文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -
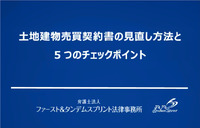
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

法務担当者がM&Aに携わるメリットとは?市場価値を高める役割や必須スキルを解説(前編)
ニュース -
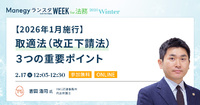
2026年1月施行!取適法の3つの重要ポイントを弁護士が解説【セッション紹介】
ニュース -
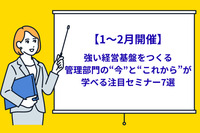
【1〜2月開催】強い経営基盤をつくる管理部門の“今”と“これから”が学べる注目セミナー7選
ニュース -
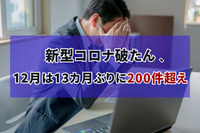
新型コロナ破たん、12月は13カ月ぶりに200件超え
ニュース -

【累計視聴者92,000人突破!】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』2月に開催決定!
ニュース -
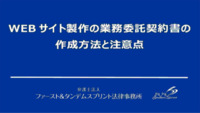
WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

1月の提出期限に間に合わせる!支払調書作成効率化の最適解とは?
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -
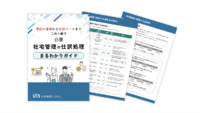
簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -
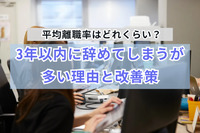
平均離職率はどれくらい?3年以内に辞めてしまう人が多い理由と改善策
ニュース -

【2026年新春】総勢300名様にAmazonギフトカードが当たる!Manegyお年玉キャンペーン開催中
ニュース -

管理部門担当者は何学部が多い?アンケート調査で見えた管理部門の出身学部とキャリアの関係
ニュース -

ランサムウェア感染経路と対策|侵入を防ぐ
ニュース -
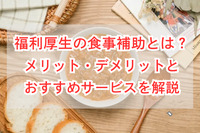
福利厚生の食事補助とは?メリット・デメリットとおすすめサービスを解説
ニュース