公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
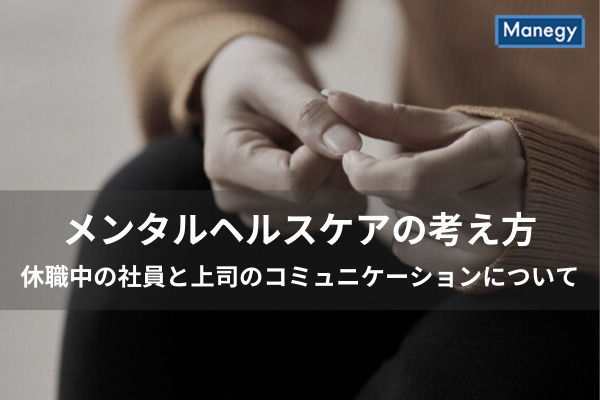
企業では、メンタルヘルスの問題で休職するケースが増えています。貴重な人材を失う前に、企業は復職プログラムを進める必要があるでしょう。そのプロセスにおいて、休職者とどのように連絡をとるべきか、今回の記事では休職中のコミュニケーションについて解説します。
現代の職場環境では、メンタルヘルスケアの重要性が高まっています。社員が休職や離職に追い込まれる理由で最も多いのがストレス性疾患などメンタル面でのトラブルです。
休職には法的な定義がなく、そのルールは社内規程などで決めておく必要があります。精神的に不安定になった休職者にとって、職場からの連絡は相当なストレスになってしまう恐れがありますが、適切なコミュニケーションを継続しなければ、休職からそのまま退職に進んでしまうかもしれません。
会社としては人材の損失を防ぐため、休職者と定期的に連絡をとりたいですが、そのタイミングは、社員が復職に向けてどのプロセスにいるかを目安にするとよいでしょう。まず休職の初期段階では心身の回復を最優先にする必要があるため、頻繁な連絡は避けなければなりません。目安は1カ月に1回程度です。休職者への連絡では、体調の回復度や生活の状況など、確認事項を最低限に絞ります。
やがて段階的なプロセスを経て、主治医から復職可能と診断がされた場合は、1週間に1回程度に連絡回数を増やすとよいでしょう。
休職中の社員から上司に連絡することは、休職の初期段階ではまずないでしょう。もしも連絡をノルマにしてしまうと、社員の体調が悪化する危険性があります。連絡方法も負担が少ないように、電話ではなくメールで行うなど、事前に決めておくことをおすすめします。
基本的には会社側からの定期連絡でコミュニケーションをとりますが、主治医による定期的な診断結果などは、社員からその都度連絡するルールを決めるとよいかもしれません。体調の回復が進めば、徐々に連絡もスムーズになるでしょう。
明確な体調不良を訴える社員以外に対しても、企業にはメンタルヘルスケアを強化することが求められています。この取り組みでは、社員の不調を予防し、早期発見と適切な措置を実施し、休職などの対応と職場復帰の支援というように、段階的にケアを進めることが重要です。
場合によっては衛生管理者や産業医を社内に常駐させて、積極的にメンタルヘルスケアを推進する必要があるかもしれません。休職者との連絡についても、こうした健康管理責任者を通じて行うことが可能になるでしょう。
健康管理・産業医(メンタルヘルスケア)サービスについては、以下のページで詳しく紹介しています。
https://www.manegy.com/service/health_care/
メンタルヘルスの不調は、周囲が考える以上に苦しいものです。まして休職中ともなれば、生活の不安も加わって一層精神的に不安定になる可能性があります。しかし会社側からすると、休職者との連絡を欠かすことはできません。連絡が必要な場合は、休職者の回復プロセスを目安にすることが重要です。状況によっては、健康管理責任者を介して連絡をとることも検討するべきでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

オフィスステーション導入事例集

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

ライセンス契約とは?主な種類・OEM契約との違い・契約書の記載項目までわかりやすく解説

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)

複雑化するグローバル人事・給与の現場──日本企業が今備えるべき論点をDeel Japan西浦氏に聞く

2025年「ゼロゼロ融資」利用後倒産 433件 増減を繰り返しながらも月間30件台を持続
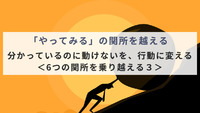
「やってみる」の関所を越える ― 分かっているのに動けないを、行動に変える ―<6つの関所を乗り越える3>

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
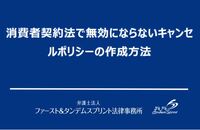
消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

大容量ファイル同期の課題を解決!法人向けオンラインストレージ選定ガイド

労務コンプライアンス経験は転職で強い?求められるスキルと成功事例を徹底解説(前編)

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり
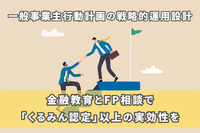
一般事業主行動計画の戦略的運用設計: 金融教育とFP相談で「くるみん認定」以上の実効性を

社員が自走する! 働きがいの溢れるチームの作り方【セッション紹介】
公開日 /-create_datetime-/