公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

官民のさまざまなデータを見ても、企業の実感を指標にしてみても、現在の日本が慢性的な労働力不足にあることは間違いないでしょう。では、なぜ労働力不足なのか、原因を深く考えたことはあるでしょうか? 今回の記事では、その根本的な原因にスポットを当てて検証してみます。
厚生労働省が公開した「令和6年版労働経済の分析」によると、現在に至る10年間でどの産業分野においても、労働力不足につながる欠員率の上昇が見られます。また企業規模が小さいほど欠員率が高まっていて、フルタイムよりもパートタイムでの欠員率上昇が顕著です。
2023年のデータではフルタイムの場合、とくに中小企業で建設業・卸売業・小売業・宿泊/飲食業などの労働力不足が深刻です。パートタイムの場合も同様の傾向ですが、小規模企業の宿泊/飲食業では欠員率が12%近くに達しています。2012年のデータと比較すると、現在の労働力不足の深刻さは明白です。
では、現在のこの労働力不足は、いったい何が原因で引き起こされているのか、「令和6年版労働経済の分析」を中心に、主な原因と考えられるものを順次紹介します。
労働力不足が深刻化したことには、少子高齢化の進行が大きく関わっています。国内では生産年齢人口が減少する一方、高齢化(長寿化)により消費者人口は減っていません。少ない労働力で多くの消費者を支えるというアンバランスが、今後さらに継続する状況にあるのです。
政府が推進する働き方では、労働時間の短縮も継続的な課題になってきました。しかし「2024年問題」として話題になったように、企業が求める総労働時間に対して、労働者が提供できる総労働時間が足りなくなっています。これが労働力需給ギャップであり、現在その数値がマイナスにあることが、国内の労働力不足を明確に示しています。
転職が一般的になったとはいえ、転職する方向はより大きな企業に向いています。大企業間の転職または大企業への転職は増えているものの、中小企業への労働力移動は長期的に低迷する状況です。また、同業種間での転職に比べて、異業種間での転職は少ないままです。結果的に中小企業や特定の業種において、労働力不足がさらに悪化しているといえるでしょう。
新しく社会人になる世代は、以前とは異なる価値観で職場を選びます。賃金は当然重要な条件ですが、とくに労働時間と休日を重視する傾向が強いようです。必要な休日を提示できない企業は、どの業種でも就職先の選択肢から脱落せざるをおえません。最近では福利厚生の充実度も重要な条件になっています。
求人を出す企業側と、求職者側とのマッチング効率が下がっていることも、労働力不足の一因と考えられます。最近の求人には質的改善が見られていますが、ハローワークでも民間のサービスでも、マッチングの効率は低下傾向にあります。求職者のニーズに対して、企業側の対応が遅れているのかもしれません。
労働力不足には、前述したように複数の要素が関わっています。中には改善が難しい問題もありますが、企業はこれらの原因を検証した上で、適切な対策を立てなければなりません。最後に、労働力不足への有効な対応策をいくつか挙げてみましょう。
●非正規労働者の活用
非正規労働者は労働時間を増やしたいという意向が強いため、副業や兼業も含めて労働需要の再分配を行う。同一労働同一賃金の原則を遵守することも重要。
●女性労働者の活躍支援
仕事と家庭の両立が可能な職場環境を整備し、女性の継続的な就労と職場復帰を促す。また、男女の区別なく積極的に登用する仕組みづくりも必要。
●高齢労働者の活躍支援
65歳以上の求人が少なく、求職者は多いというマッチングのロスが生じているため、高齢労働者の採用枠を拡大する。再雇用制度の拡充も図る。
●業務支援システムの導入
サポートシステムによる代行が可能な業務では、担当者とシステムで業務分担を明確にする。部門間をまたいで管理を一元化するシステム構築も視野に入れる。
人事管理の業務支援サービスについては、以下のページで詳細を紹介しています。
https://www.manegy.com/service/humanresource_management/
労働力不足の根本的な原因は、少子高齢化などの社会構造の変化にあり、それに労働力需給のギャップが拍車をかけていると考えられます。この構造を改善するのは容易ではないですが、女性や高齢者などを積極的に支援する仕組みができれば、一定の労働力増が見込めるのではないでしょうか。企業にとっては社会に埋もれている労働力を、進んで耕起する努力が求められるでしょう。
参考資料
「令和6年版 労働経済の分析」を公表します_厚生労働省
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト①/税務

採用計画で市場価値を上げる8つのスキル|戦略人事へのキャリアパスを徹底解説【転職成功事例つき】(前編)

フランチャイズ契約とは?ロイヤリティ・テリトリー・競業避止など契約条項を徹底解説
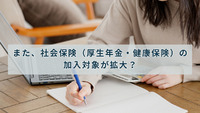
また、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象が拡大?

自己理解の深化が退職予防に影響、2306人を調査

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

オフィスステーション年末調整

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
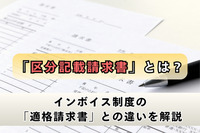
「区分記載請求書」とは?インボイス制度の「適格請求書」との違いを解説

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革
公開日 /-create_datetime-/