公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

生成AIの普及が急速に進む中、企業がその利便性を活かす一方で、著作権問題や倫理的な課題が浮上する場面も増えています。文化庁の「AIと著作権」(令和5年度著作権セミナー資料)でも、著作権法を正しく理解し、AIを適切に利用する重要性が強調されています。本資料を基に、自社の社員がAIを安全かつ効果的に活用できるようにするためのポイントをお伝えします。
まず、著作権法の概要を社員が理解することが必要です。著作権法は、著作者の権利を保護しつつ、公正な利用を促進するために設けられています。その対象となる著作物は、思想や感情を創作的に表現したものであり、文芸や音楽、美術などが含まれます。しかし、単なる事実やデータ、アイデアそのものは保護の対象外です。この基本的な枠組みを社員に周知することで、日常業務でのAIの利用時にも、何が保護対象かを正しく認識することができます。
生成AIは、既存の著作物を学習データとして利用することで、新たなコンテンツを生成します。この学習段階での著作権侵害の可能性は、日本の著作権法において、情報解析を目的とした利用であれば許諾なしで可能とされています。これにより、AI学習における著作権侵害リスクは低減しますが、利用目的や範囲によっては問題が生じる可能性もあります。このため、学習データや生成物の使用範囲について、社員が適切に判断できる基準を設けることが重要です。
一方、生成AIが作成したコンテンツが既存の著作物と類似している場合、著作権侵害が成立する可能性があります。侵害の判断基準として、「類似性」と「依拠性」が挙げられます。類似性とは、生成されたコンテンツが既存の著作物と表現上の本質的な特徴を共有していることを指します。また、依拠性とは、新しいコンテンツが既存の著作物に依拠していることを意味します。これらの基準に照らし、AIが生成したコンテンツを確認するプロセスを社員に教えることで、法的リスクを未然に防ぐことができます。
生成AIが作成したコンテンツが著作物として保護されるかどうかも、社員が知るべき重要な論点です。著作物として保護されるためには、人間の創作性が介在している必要があります。AIが完全に自律的に生成したコンテンツは、著作権の対象外とされる可能性がありますが、出力結果を人間が選択・編集した場合には、その結果物が著作物として認められる場合があります。このポイントを理解することで、社員は生成AIの出力を業務で利用する際に適切な手続きや対応を取れるようになります。
著作権的に問題がない場合でも、AIを使用したコンテンツが社会的な批判や炎上を招くケースがあります。以下の点に注意し、倫理的なリスクを回避することが重要です。
AIが学習データとして利用した既存の著作物に対する敬意や配慮が欠けていると、クリエイターやその支持者から反発を招く可能性があります。元の作品がなければ生成されたコンテンツは存在しなかったという視点を持ち、適切な対応を考える必要があります。
消費者や社会は、クリエイティブな作品に対して人間の感性や創造性を求める傾向があります。AI生成物が無機質で感情が感じられないと受け取られると、ネガティブな印象を与えることがあります。
AIを使用していることを明示せずにコンテンツを公開すると、後からAI生成物であることが判明した際に信頼を損なうリスクがあります。制作過程の透明性を確保することで、信頼性を維持できます。
AIが生成したコンテンツが特定の文化やコミュニティに関連する場合、適切な配慮がないと「文化の盗用」と見なされるリスクがあります。社会的・文化的な背景を理解し、慎重に扱うことが求められます。
社員が著作権に関するリスクを回避するためには、法務部が主体となって教育を実施することが不可欠です。まず、研修を通じて著作権法の基礎やAIとの関係について解説することが効果的です。具体的には、生成AIを活用する際の事例を交えながら、どのような場面で著作権問題や倫理的な問題が生じる可能性があるのかを示すと理解が深まります。
また、自社で生成AIを利用する場合のガイドラインを明確化し、それに基づいて社員が安心してAIを活用できる環境を整備することも重要です。ガイドラインには、著作権の遵守だけでなく、倫理的な配慮や社会的影響の評価についても盛り込むべきです。
AIの利活用は、業務効率化やイノベーションの促進に寄与する一方で、著作権問題や倫理的なリスクが潜在的な課題となり得ます。社員が著作権法の基礎を理解し、AI利用時の注意点や社会的・倫理的な配慮を把握することで、これらのリスクを軽減し、安心してAIを業務に活かすことが可能になります。
法務部として、常に最新の著作権情報や社会的動向を基に教育やガイドラインの整備を行い、生成AIを最大限活用できる環境を構築していきましょう。企業としての信頼性と社会的責任を果たすためにも、法的な遵守だけでなく、倫理的な視点からの対応が求められます。
参考資料)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/93903601.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
■関連記事
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
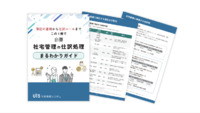
簿記の基礎から実務まで!社宅管理の仕訳処理 まるわかりガイド

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

外注と業務委託の違いとは?契約形態や活用シーンをわかりやすく解説

社員同士の交流を促進する「まかないランチ会」開催 岐阜市のITベンチャーのユニークな支援策
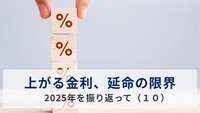
上がる金利、延命の限界=2025年を振り返って(10)
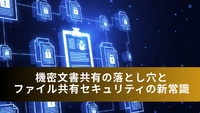
機密文書共有の落とし穴とファイル共有セキュリティの新常識
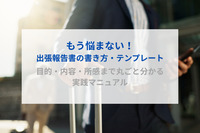
もう悩まない!出張報告書の書き方・テンプレート|目的・内容・所感まで丸ごと分かる実践マニュアル
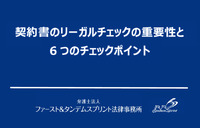
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

人的資本開示の動向と対策

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
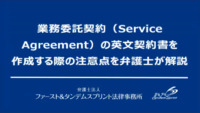
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
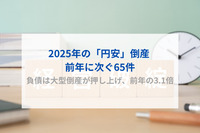
2025年の「円安」倒産 前年に次ぐ65件 負債は大型倒産が押し上げ、前年の3.1倍

全社参加型ランニングなどのウェルネス企画 100kcal消費で給食を寄付、社員交流も促進

外注と下請けの違いとは?意味・メリット・契約時の注意点をわかりやすく解説

不正アクセス対策の鍵はゼロトラスト:境界防御からの脱却

M&Aブーム継続、仲介業者の罪=2025年を振り返って(9)
公開日 /-create_datetime-/