公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?

昨今のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、個人のブログやSNSなど、誰もがインターネット上で簡単に自分の創作物を発表できるようになりました。また、インターネットの普及により、インターネット上で商品やサービスを提供するECは私たちの日常生活の一部となっています。実店舗を持たないEC事業は比較的参入障壁が低く、始めやすいビジネスといえるかもしれませんが、自社ECサイトにおいて、インターネット上に存在する他人の著作物を利用する場合などは、うっかり、または知らずに著作権侵害をしてしまわないよう、著作権について十分に理解した上で事業を行うことが求められます。
この記事では、EC事業者が知っておきたいインターネット上の著作物と著作権法の関係を解説します。
著作権法は、著作物の創作者(著作者)に対して、その作品を保護する権利を与え、他人による著作物の無断利用を規制する法律です。
創作者の権利は、人格的な利益を保護する「著作者人格権」と、財産的な利益を保護する「著作権(財産権)」の二つに分かれます。著作者人格権は、著作者だけが持つことができる権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(著作権法第59条)。一方、著作権(財産権)は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます(著作権法第61条第1項)。したがって、著作者が、創作した著作物の著作権(財産権)を他人に譲渡している場合、第三者が、その著作物を利用する際には権利者(著作権者)の許諾が必要です。
また、著作権が著作物を創作した者に付与される権利であるのに対し、著作物等を伝達した者に付与される権利は「著作隣接権」と呼ばれており、例えば、実演家や放送事業者等が著作隣接権者となります。
著作権法第1条は、著作権法の目的を以下のように定めています。
第1条(目的)
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
著作権法の基本的な考え方は、創作者に対して、その著作物を一定の期間、独占的に利用する権利を与えることです。これにより、創作者は自らの作品に対して経済的な利益を得ることができます。また、創作者に一定の権利を与えることによって、創作活動を奨励し、文化や研究の発展を促進することも目的とされています。
著作権法は著作物を保護するための法律ですが、具体的に、どのようなものが著作物にあたるのでしょうか。著作権法第2条では、「著作物」を以下のように定義しています。
第2条(定義)
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
著作物とは、文学、音楽、映像、美術、写真、ソフトウェアなど、創作的な表現を含む幅広いものです。著作権法で保護される著作物は、印刷など固定されている必要はなく、インターネット上の情報も含まれます。なお、著作物とは、「思想又は感情」を表現したものであるため、天気予報や死亡記事のような「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」(著作権法第10条第2項)は著作物には該当しません。
誰でも簡単にアクセスできるインターネット上の情報ですが、著作権法第2条に定められる著作物にあたる場合、他人が無断で利用することはできません。インターネット上の文章を印刷する、画像、音楽、動画などをダウンロードする等、著作物の利用には、著作権者や著作隣接権者の許諾が必要となります。
ただし、……
◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
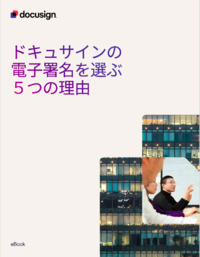
2,000人の経営幹部に聞く!電子署名導入のメリットと懸念点を徹底解剖

OFFICE DE YASAI 導入事例
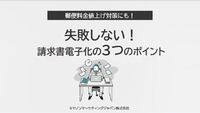
【郵便料金値上げ対策にも!】失敗しない!請求書電子化の3つのポイント
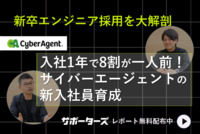
【新卒エンジニア育成】入社1年で8割が一人前!サイバーエージェントの新入社員育成

【2025年版】ビジネス実務法務検定2級 合格率・難易度・出題傾向・勉強法は?最新データで合格の道筋を解説!

上半期の「後継者難」倒産 2番目の230件 高齢化の加速で、事業承継の支援が急務に
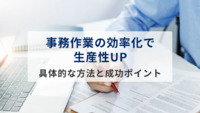
事務作業の効率化で生産性UP!具体的な方法と成功ポイントを徹底解説

【満足度95%】『ManegyランスタWEEK -2025 Summer-』開催決定!
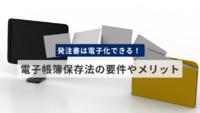
発注書は電子化できる! 電子帳簿保存法の要件やメリットを解説
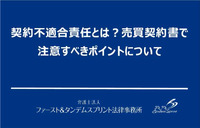
契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
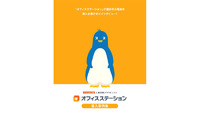
オフィスステーション導入事例集

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
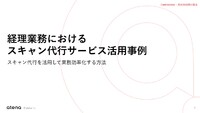
経理業務におけるスキャン代行活用事例

Microsoft OneNoteとは?できることや簡単な使い方などを解説

介護業における外国人雇用|就労可能なビザ・雇用時の注意点を解説
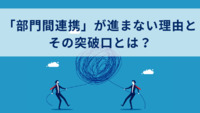
「部門間連携」が進まない理由と、その突破口とは?
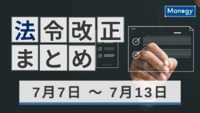
毎月勤労統計調査 令和7年5月分結果速報 など|7月7日~7月13日官公庁お知らせまとめ

東南アジア市場における越境EC事業とは?|成功のためのポイントやおすすめのプラットフォームについて解説
公開日 /-create_datetime-/