公開日 /-create_datetime-/

リーマンショック級の経済情勢の悪化がない限り、今年10月には、消費税が10%に引き上げられることになっていますが、消費税がどうして生まれ、どのように創設されたのかをご存知ですか?
今回は消費税の歴史を振り返ってみましょう。
消費税導入の始まりは1954年のフランス
消費税は、消費に対して課税される間接税であり、商品の消費やサービスの提供を受ける消費者が負担し、納めるのは商品やサービスを提供する事業者です。
初めて消費税が導入されたのは1954年のフランスで、元になったのは1917年の支払税です。支払税は1920年に売上税となり、さらに1936年に生産税と名前を変えながら、いまの形となり、現在160か国ほどで導入されています。
日本での導入は平成元年(1989)
日本に消費税が導入されたのは平成元年(1989)、竹下登内閣の時ですが、消費税導入をめぐっては、賛成・反対の攻防が10年ほど続き、選挙にも大きな影響を与えてきたことは周知のとおりです。
まず、財政再建のための“消費税導入”を掲げたのが大平正芳内閣で、1979年1月に閣議決定したものの、その年に行われた総選挙の争点となり、導入反対の声が高まるなかで、選挙中に導入を断念しています。もちろん、国民的な導入反対の声に押され、自民党は総選挙で大幅に議席を減らしました。
しかし、財政赤字を解消するためには、どうしても新たな税が必要ということで、中曽根康弘内閣は、1987年2月に名称を「売上税」として法案を国会に提出しました。しかし、圧倒的な反対の声で、同年5月には廃案に追い込まれました。
そして、1988年12月、竹下登内閣の時に消費税法が成立し、1989年4月、ついに消費税法が施行となりました。ところが、消費税法施行直後、政界を巻き込んだ未公開株ばらまきのリクルート事件によって、竹下首相は退陣を表明し6月に辞任することになりました。
常に政権を脅かしてきた消費税
このように、時の政権を脅かすほどの影響力を持っていた消費税は、紆余曲折を経ながらも導入となりましたが、導入後も政権にとっては、まさにアキレス腱のような存在でした。
消費税だけが理由ではありませんが、政治改革をめぐる大きな流れもあり、結党以来38年間という長期間、政権を維持してきた自民党が下野することになり、非自民の8党連立による細川護熙内閣が誕生しました。
細川護熙79代内閣総理大臣の登場は、世間の耳目を一身に集めましたが、次第に連立政権内の足並みの乱れが表面化するようになり、1994年2月、突然「消費税を廃止し、国民福祉税(税率7%)構想を発表。しかし、あまりの反響の大きさに翌日に撤回し、期待を集めた連立内閣も長くは持ちませんでした。
税率10%への長くて厳しい道のり
次に登場したのが、なりふり構わずに政権に返り咲きたい自民党が放った禁じ手ともいえる、社会党の委員長を総理候補とする、自民党・社会党・さきがけによる“自社さ”連立の村山富市内閣です。
村山内閣では、消費税を3%から4%に引き上げ、さらに地方消費税1%を加えた税制改革関連法を1994年に成立させています。
その後1997年に橋本龍太郎内閣が税率を5%に引き上げ、2009年には「4年間は消費税率を上げない」と訴えた民主党が総選挙で大勝し、鳩山由紀夫内閣が誕生しました。ところが、菅直人内閣に変わると、2010年の参院選直前に「消費税10%」を打ち出したことで、選挙は惨敗となります。
後を受けた野田佳彦内閣は、議員定数削減などを条件に、2014年に消費税率8%、2015年10%に引き上げる法案を成立させて解散に踏み切り惨敗、民主党そのものが解体するところまで追い込まれ、自公連立による安倍晋三内閣が誕生して今日に至っています。
3度目の増税延期はあるのか
ことごとく、政権にダメージを与え続けてきた消費税は、安倍内閣によって2014年に8%に引き上げられましたが、2015年の10%に引き上げは2017年4月へ1年半延期、さらに2019年10月に2年半延期となり、いよいよ、その期日が近づいています。
消費税が政権のダメージにつながるというトラウマからか、安倍政権では2度、引き上げを延期したものの、さすがに3度目はないだろうというのが大方の見方です。さて、どういう結論になるのでしょうか。景気は下降局面にあることを示す各種調査もあり、安倍政権にとって消費税増税は、最後の試練になりそうです。
まとめ
安倍政権は、2019年10月に税率10%に引き上げる方針を表明していますが、政権へのダメージを避けるため軽減税率の導入や、キャッシュレス決済によるポイント還元など、増収分を上回る額を経済対策に注ごうとしています。
そうなると、増税する意味が、一体どこにあるのだろうかという疑問も湧き上がってきますが、とにもかくにも、消費税が10%になるかどうかは、これからの景気の動向次第のようです。経理や財務担当者にとっては準備しておかなければならないことも多いだけに、秋まで落ち着かない日々となりそうです。
関連記事:「住民税」のルーツは明治維新の地租改
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ
ニュース -

採用だけの人事経験は転職で不利?評価されるスキルとキャリアの広げ方を徹底解説(前編)
ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト①/会計
ニュース -

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」
ニュース -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -
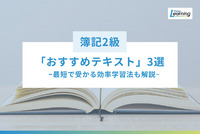
【社会人向け】仕事と両立で簿記2級に合格する「おすすめテキスト」3選。3級の知識が曖昧でも最短で受かる効率学習法も解説
ニュース -
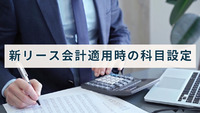
新リース会計適用時の科目設定
ニュース -

多角化する企業グループで重宝される「子会社管理経験」|経理のキャリア価値とは(前編)
ニュース -

労務コンプライアンス経験は転職で強い?求められるスキルと成功事例を徹底解説(前編)
ニュース -

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり
ニュース



































