公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?
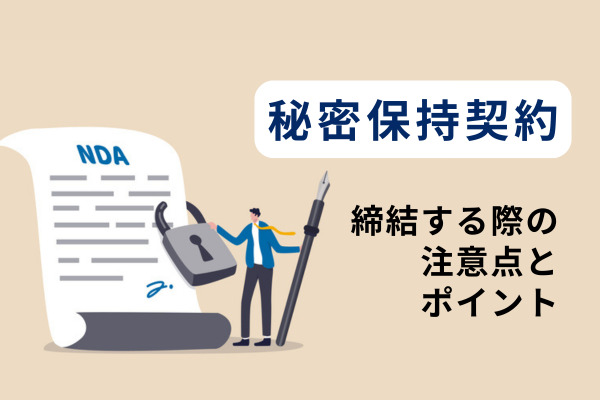
秘密保持契約とは、取引相手から受け取った秘密情報を他へ漏えいしたり不正利用したりしないことを約束するために締結する契約です。英語の頭文字をとってNDA(Non-Disclosure Agreement)ともよばれます。
たとえば新規取引を行う際には、自社の内部情報を相手方に伝えなければならない場合がありえます。しかし、情報提供後、もし取引相手が自由に情報を世間に広めたり勝手に利用したりすると、大きな損失が発生してしまうでしょう。そこで秘密保持契約を締結し、情報漏えいや不正利用を禁止して情報提供企業の利益を守る必要があります。
現代の情報化社会において、情報は企業にとっての「命」ともいえます。社内の重要情報を守るための「秘密保持契約」を適切に締結することは、企業が生き残るためにもはや必須ともいえるでしょう。
以下のような場合には秘密保持契約書を作成すべきです。
上記以外でも秘密保持契約書が必要なケースはあります。判断に迷ったときには弁護士などの専門家からアドバイスを受けましょう。
秘密保持契約書は、以下のような手順で作成しましょう。
STEP1 契約内容の協議
まずは、当事者双方が話し合って秘密保持契約の内容を定めなければなりません。
特に以下のような点が重要です。
STEP2 原案の作成
どういった内容にすべきかが決まったら書面に起こして原案を作成しましょう。
当事者のどちらかが作成して相手方に交付します。
どちらが原案を作成しなければならないという決まりはありませんが、自社で作成した方が有利な内容にしやすいでしょう。
STEP3 内容のチェックと修正
原案を相手方に渡すと、相手方が内容をチェックして返答をしてきます。特に問題なければそのまま双方が調印しますが、相手方に意見があれば修正が必要となる可能性もあります。
最終的に合意できるまで協議や修正を継続しましょう。
STEP4 契約書の作成と調印
契約書の最終的な内容が固まったら書面を作成し、当事者双方が署名(記名)捺印します。
日付を入れて双方が記名捺印した契約書を当事者の人数分作成し、お互いが1通ずつ保有します。
これで秘密保持契約書が完成します。
秘密保持契約を締結する際には、必ず「秘密保持契約書」を作成すべきです。
確かに秘密保持契約は、当事者が口頭で合意しただけでも成立します。しかし口頭で約束しただけでは証拠が残らずトラブルが発生するリスクが高まってしまいますので、自社の利益を守る対策として、あまりに不十分といえます。
以下で秘密保持契約書を作成しない場合のリスクをみていきましょう。
◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

OFFICE DE YASAI 導入事例

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
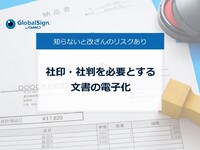
社印・社判を必要とする文書の電子化

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

【会計】金融資産の減損における期中期間の簡便処理、検討─ASBJ、金融商品専門委 旬刊『経理情報』2025年7月20日号(通巻No.1749)情報ダイジェスト②/会計

【2025年版】ビジネス実務法務検定2級 合格率・難易度・出題傾向・勉強法は?最新データで合格の道筋を解説!

【対談インタビュー】採用から組織を変える力を育てる。マクロミルと外部人材が共創する人事と組織のかたち。
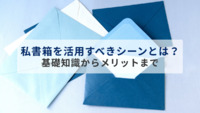
私書箱を活用すべきシーンとは?基礎知識からメリットまで解説

1-6月の「人手不足」倒産 上半期最多の172件 賃上げの波に乗れず、「従業員退職」が3割増
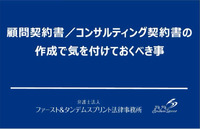
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

中堅大企業のための人事給与アウトソーシング導入チェックポイント

法人向けクラウドストレージのバックアップサービスとは

上半期の「後継者難」倒産 2番目の230件 高齢化の加速で、事業承継の支援が急務に

大規模プロジェクトに最適なクラウドストレージへのデータ移行手順

アフターコロナで対面増、ジャケット着用が半数超に 夏のビジネス現場や就活に広がる「汗の不安」
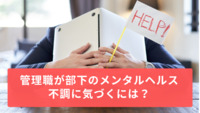
管理職が部下のメンタルヘルス不調に気づくには?
公開日 /-create_datetime-/