公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
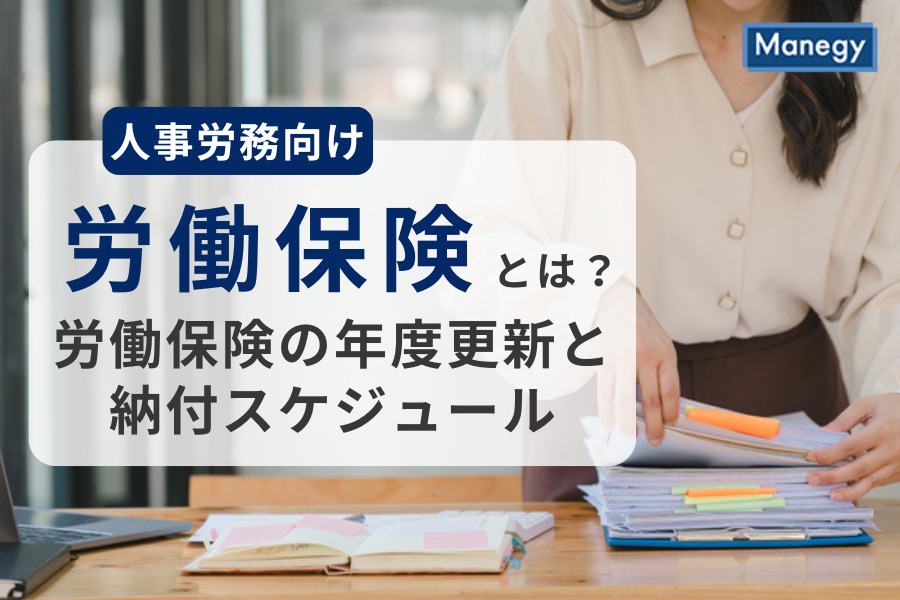
労働保険は、事業主が負担すべき重要な社会保険制度の一つであり、労働者の安全と生活を守るための仕組みとして機能しています。
その中でも「労働保険料の納付」は、事業主が守るべき義務の一つであり、特に年度更新の際や納付スケジュールに沿った適切な手続きが必要です。しかし、手続きが複雑であるため、正確な知識を持つことが重要です。
本記事では、労働保険の基本から労働保険料の納付方法、よくある質問まで、わかりやすく解説します。
労働保険とは、労働者の安全と生活を守るために事業主が負担する社会保険制度の総称であり、「労災保険」と「雇用保険」の2つの制度から構成されています。労災保険は、労働者が業務上の事故や通勤中の災害によって被害を受けた場合に、医療費や休業補償を給付する制度です。一方、雇用保険は、失業時の生活を支える給付や再就職を促進するための支援金を提供します。
これらの保険制度は、全ての労働者が安心して働ける環境を作るための基盤として機能しており、事業主は一定の条件のもと、労働保険料を負担する義務があります。本記事では、労働保険料に関する基本的な考え方や手続きについて詳しく解説します。

労働保険料とは、労働保険制度(労災保険と雇用保険)を運営するために、事業主が負担する費用を指します。この保険料は、労働者が安心して働ける環境を維持し、業務上の災害や失業に備えるための財源として活用されます。
労災保険料は全額を事業主が負担し、労働者の業務内容や職場環境に応じて保険料率が設定されます。一方、雇用保険料は事業主と労働者の双方が負担し、給与総額を基にした一定割合が保険料として計算されます。
労働保険料は、事業規模や従業員数に応じて異なり、毎年度の見直し(年度更新)によって正確な金額が確定します。正しい保険料を納付することは、事業主の法的義務であり、労働者の福祉を支える重要な役割を果たします。
労働保険の年度更新とは、毎年事業主が前年度の保険料を精算し、次年度の概算保険料を申告する手続きのことです。この手続きは、労働保険料の適正な運用を目的としており、事業主にとって法的に義務付けられています。
➀賃金集計表を作成する
まずは、「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」(以下、賃金集計表)を作成します。この賃金集計表は提出の必要はないですが、年度更新に関連する記録として保管しておきましょう。
確定保険料を算出する際には、前年度の賃金台帳を基に、前年4月から今年3月に支払われた賃金総額に保険料率を掛けて計算します。また、厚生労働省が提供する「年度更新申告書計算支援ツール」を活用することで、計算作業を効率化できますので、下記あわせてご確認ください。
厚生労働省|主要様式ダウンロードコーナー (労働保険適用・徴収関係主要様式)
➁申告書を作成する
作成した賃金集計表を基に、「労働保険概算・増加概算・確定保険料 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」(以下、申告書)の作成を進めます。
この申告書には、上段に確定保険料の計算内訳、下段に概算および増加概算保険料の計算内訳を記載する欄があります。それぞれの保険料を以下の方法で算出し、正確に記入してください。
確定保険料の計算内訳
前年度に支払われた賃金総額を基に確定保険料を算出し、その額を記載します。
概算・増加概算保険料の計算内訳
新年度に支払予定の賃金総額を見積もり、それに基づいて概算保険料を記入します。
新年度の賃金総額の見積もり
前年度の賃金総額を参考に計算します。
保険料率の変更がある場合
保険料率が改定されていると、概算保険料と確定保険料に差異が生じる可能性がありますので注意してください。
さらに、労災保険と雇用保険は対象となる従業員が異なるため、それぞれを分けて計算する必要があります。正確な区分を行い、誤りがないよう注意しましょう。
➂申告書の提出と保険料の納付
申告書の記載が完了したら、提出と保険料の納付を行いましょう。提出の締め切りは7月10日です。提出先として対応可能な機関は以下の通りです。それぞれの機関では、申告書の提出と保険料の納付が同時にできる場合と、申告書の提出のみを受け付ける場合があります。
| 機関 | 対応可能な内容 |
|---|---|
| 金融機関(銀行・郵便局・信用金庫) | 申告書提出と保険料納付の両方が可能。 申告書提出のみの対応は不可。 |
| 都道府県労働局や労働基準監督署 | 申告書提出と保険料納付の両方が可能。 申告書提出のみの対応も可能。 |
| 社会保険・労働保険徴収事務センター | 申告書提出のみが可能。 保険料納付は不可。 |
なお、労働保険料は一括納付が原則ですが、概算保険料が40万円以上の場合、3回に分けて分割納付することもできます。
・年度更新の時期
年度更新は通常、毎年6月1日から7月10日までの間に行われます。この期間内に申告書を提出し、保険料を納付する必要があります。
労働保険料の納付方法にはいくつかの選択肢があり、事業の規模や状況に応じて適切な方法を選ぶことができます。それぞれの方法には特徴や注意点があるため、事前に把握しておくことが重要です。
1. 口座振替による納付
・概要
事業主が指定した銀行口座から自動的に保険料が引き落とされる方法です。
・メリット
手続きが簡便で、納付漏れを防ぐことができます。また、窓口に行く手間を省けるため、業務効率化につながります。
・注意点
引き落とし日までに口座残高を十分に確認しておきましょう。また、初めて利用する場合は事前に申請が必要です。
2. 窓口での納付
・概要
金融機関や郵便局の窓口で納付書を提出して支払う方法です。
・メリット
納付書をその場で確認してもらえるため、安心感があります。
・注意点
年末年始や休日の営業日を確認し、余裕を持ったスケジュールで手続きしましょう。
3. e-Govを利用したオンライン納付
・概要
労働保険料をインターネットを通じて電子納付する方法です。
・メリット
オンラインで完結するため、時間や場所に縛られずに手続きが可能です。
・注意点
初回利用時にはアカウント登録や設定が必要となるため、事前準備を行いましょう。また、システムトラブルに備え、早めに手続きすることを推奨します。
4. 分割(延納)による納付
・概要
一括納付が難しい場合に、保険料を複数回に分割して納付する方法です。
・メリット
資金繰りの負担を軽減することができます。
・注意点
分割納付を選択するには、年度更新の際に申請が必要です。また、納付スケジュールを守らない場合、延滞金が発生する可能性があります。
・納付時の注意点
納付期限は厳守しましょう。期限を過ぎた場合、延滞金が発生するケースがあります。申請内容に不備があると手続きが遅れる場合があるため、書類やデータの確認を徹底しましょう。万が一トラブルが発生した際には、労働局や金融機関に早めに相談してください。

労働保険料の納付に関して、事業主や人事・労務担当者が抱きがちな疑問をまとめましたので、ご参考ください。
A: 納付期限を過ぎた場合、速やかに労働局または金融機関に相談してください。
延滞金が発生する可能性がありますが、早めに手続きを行うことでリスクを最小限に抑えられます。また、口座振替を利用している場合は、引き落としが完了しているか確認してください。
▼詳しくはこちら
厚生労働省|労働保険料等を滞納した場合の事務処理
A: 労働保険料は、従業員の賃金総額に所定の保険料率を掛けて計算します。
計算に不安がある場合は、社労士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。また、労働保険料の計算ツールを活用するのも効果的です。
▼詳しくはこちら
厚生労働省|労働保険料の計算方法
A:はい、申告書提出後に内容にミスが見つかった場合は、速やかに管轄の労働局に連絡し、訂正申請を行ってください。
修正申告が受理されれば、正確な保険料を納付できます。
▼詳しくはこちら
厚生労働省|労働保険料等の申告内容について訂正が必要なとき
A:保険料率の変更があった場合、年度更新の際に通知されます。最新の保険料率を確認し、正確に計算を行いましょう。労働局の公式サイトや通知書を参照してください。
▼詳しくはこちら
厚生労働省|令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)
A:労働者を一人でも雇用している事業所は、原則として労働保険に加入し、保険料を納付する義務があります。ただし、事業の内容や規模によって一部例外がある場合もあるため、詳細は労働局に確認してください。
▼詳しくはこちら
厚生労働省|労働保険の成立手続きはおすみですか?
労働保険料の管理を適正に行うことは、事業主にとって法的義務を果たすだけでなく、労務リスクを最小限に抑えるためにも重要です。以下は、労働保険料の適切な管理方法についてのポイントです。
・納付期限を把握する
納付スケジュール(年度更新や各期の納付期限)を事前に確認し、カレンダーやリマインダーに登録しておきましょう。
・繁忙期との調整をする
年末年始などの繁忙期と重なる場合は、早めに手続きを進めることでトラブルを回避できます。
・賃金台帳を整備する
従業員の賃金総額を正確に把握するために、賃金台帳を定期的に更新し、適切に保管しましょう。
・変動への対応をする
賃金総額に大きな変動があった場合、速やかに労働局へ連絡し、保険料の再計算や修正手続きを行います。
・保険料計算ツールを使う
専用の計算ツールや給与計算ソフトを活用することで、計算ミスを防ぐことができます。
・スケジュール管理アプリを導入する
納付期限の管理に役立つアプリやタスク管理ツールを導入することで、効率的な運用が可能になります。
・担当者を決める
労働保険料の管理を担う担当者を明確にし、役割分担を徹底しましょう。
・チェック体制を構築する
必要な手続きや書類をダブルチェックする体制を整えることで、ミスの発生を未然に防ぎます。
・社労士や税理士へ相談する
労働保険の手続きや計算が複雑な場合は、社労士や税理士などの専門家に相談することを検討してください。
・顧問契約を活用する
労務リスクを軽減するために、専門家と顧問契約を結ぶのも有効です。
・前年のデータと比較する
前年度の保険料や賃金データを基に、今年度の計算や納付計画を立てるとスムーズに進められます。
・差異を分析する
前年度との差異を分析することで、今後の保険料計画に役立てることができます。
労働保険料の納付は、事業主が守るべき重要な義務であり、労働者の安全と生活を支える基盤です。本記事では、労働保険の基本から保険料の計算方法、納付スケジュール、適切な管理方法について解説しました。
特に、年度更新や納付期限の厳守はトラブルを防ぐために重要です。また、口座振替やオンライン手続きを活用することで、業務効率化も図れます。さらに、正確な賃金データの管理や専門家への相談など、適正な管理体制を整えることで、ミスを防ぎ、スムーズな運用が実現できるでしょう。労働保険料の納付を適切に行い、事業運営の基盤をしっかりと支えましょう。
参考文献)
厚生労働省|労働保険制度
厚生労働省|労働保険とは
厚生労働省|労働保険料の申告・納付
厚生労働省|主要様式ダウンロードコーナー (労働保険適用・徴収関係主要様式)
厚生労働省|労働保険料等の口座振替納付
厚生労働省|労働保険料等の口座振替納付・電子納付
厚生労働省|労働保険料等を滞納した場合の事務処理
厚生労働省|労働保険料の計算方法
厚生労働省|労働保険料等の申告内容について訂正が必要なとき
厚生労働省|令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)
厚生労働省|労働保険の成立手続きはおすみですか?
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

英文契約書のリーガルチェックについて

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート

クラウドストレージはバックアップになる?ランサムウェアとDR対策
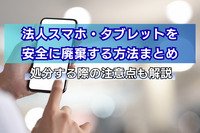
法人スマホ・タブレットを安全に廃棄する方法まとめ|処分する際の注意点も解説

領収書の偽造は犯罪!刑罰・見破り方・防止策を徹底解説

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

法人専用ファイル共有を選ぶべき理由

地方公務員の男性育休取得率、過去最高を更新 人材確保には課題も 総務省が調査結果を公表

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」

ファイル共有のセキュリティ対策と統制

1月23日~1月29日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
公開日 /-create_datetime-/