公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
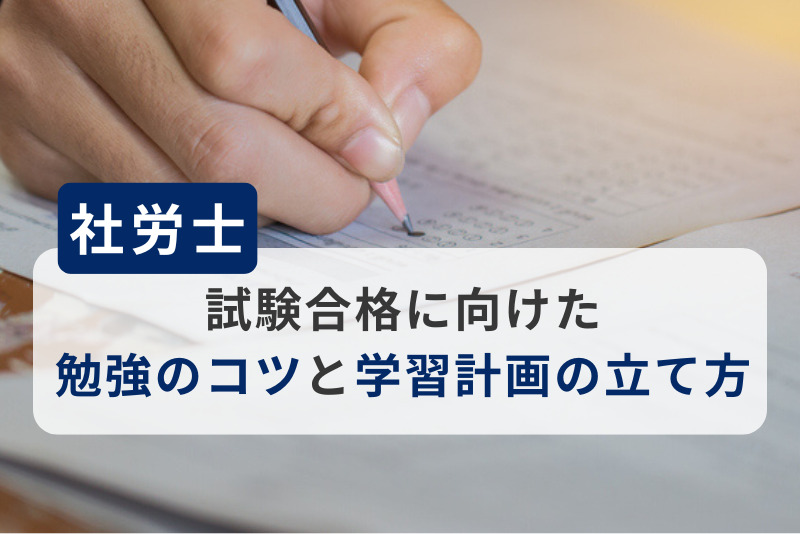
社労士試験の学習をするにあたって、そもそも勉強方法が想像できない、あるいは勉強を開始はしているけれど、今の勉強方法で合っているのかがいまいち自信がない等、一人で悩んではいませんか?特に独学で学習をされる方は、相談にのってもらえる相手もいないので不安になりますよね。
このコラムでは、そんな方のために、試験合格に向けた勉強のコツと学習計画の立て方をご紹介していきます。是非今後の学習に役立てて頂ければと思います。
まずは、社労士試験の基本となる「労働基準法」から学習をスタートしましょう。
労働基準法は社労士試験の中の憲法のようなものであり、全ての労働科目の基本となります。労働基準法の趣旨をしっかり理解することで、他の科目へスムーズに移ることができますし、年次有給休暇、割増賃金、休憩時間・休日等、社会人にとっては比較的馴染みやすい内容も多くなっているので、とりかかりやすい科目ともいえるでしょう。労働基準法でまずは労働科目の基礎を理解し、応用となる科目に取り組んでください。
他にも「労働保険徴収法」は「労災保険法」「雇用保険法」両者の徴収手続について定めた法律です。そのため、「労災保険法」「雇用保険法」を先に学ぶべきだといえるでしょう。
また、社会保険科目では「健康保険法」が最も歴史のある法律であるため「厚生年金保険法」と「国民年金法」よりも先に勉強を始めるべきです。
そして、「国民年金法」と「厚生年金法」は年金制度でまさに同じ関係にあるといえます。1階部分が「国民年金法」、2階部分が「厚生年金法」と例えられるように、この順番で勉強をしましょう。何事も基礎が大切です。
順番としては、……
記事提供元

Manegy Learningは管理部門・士業の皆さまに向けて、実務に役立つTIPSや資格取得のためのスクール取得などの情報を発信し、みなさまの学びをサポートします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも

AIの反社チェック・コンプライアンスチェック 信じちゃダメです。本当に絶対ダメです。

フランチャイズ契約とは?ロイヤリティ・テリトリー・競業避止など契約条項を徹底解説

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ

攻めと守りの「AIガバナンス」: 経産省ガイドラインの実践と運用課題

ラフールサーベイ導入事例集

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

オフィスステーション年末調整
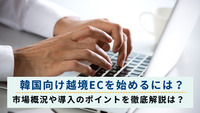
韓国向け越境ECを始めるには?市場概況や導入のポイントを徹底解説

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

越境ECで売上を伸ばす海外レビュー戦略とは?重要性・実践方法・注意点を解説
公開日 /-create_datetime-/