公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

令和になってから新設された税制の1つに、「ひとり親控除」があることをご存じでしょうか。シングルマザー、シングルファーザーを対象とした税制優遇措置で、対象となる人は必要な手続きをすれば、課税対象となる所得を控除できます。
そこで今回はひとり親控除とは何か、また類似した控除制度である寡婦控除や扶養控除とはどう違うのかについて詳しく解説します。
ひとり親控除とは税制に創設された所得控除の一つで、2020年(令和2年)に制度化されました。ひとり親とは母子家庭・父子家庭における親のことで、両親がいる家庭に比べて経済的な環境が厳しいので、一種の救済措置として導入された税制度です。
ひとり親控除は、「その年の12月31日の現況で、婚姻をしていない人または配偶者の生死が明らかではない人」のうち、以下が該当する場合に、所得税の課税対象となる所得金額から35万円(住民税は30万円)が控除されます。
・事実上の婚姻関係にある、もしくは婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
・生計を同じくする子供がいる人。この場合の子供は、その年の総所得金額が48万円以下で、かつ他の人の同一生計配偶者・扶養親族になっていない人に限られます。
・合計所得金額が500万円以下(給与収入のみの場合は年収で約677万円以下)であること。
ひとり親控除が創設される前から、母子家庭に対しては「寡婦控除」の規定がすでにありました。寡婦とは夫と離婚・死別した後に再婚していない女性を指します。
ひとり親控除の創設に合わせて、寡婦控除の制度全体が見直されました。たとえば、以前は年間合計所得金額が500万円超の人でも控除対象でしたが、ひとり親控除の創設後は、500万円以下の人のみが控除対象とされています。なお、父子家庭を対象とした「寡夫控除」についても以前から規定はありましたが、ひとり親控除の創設後はその適用要件にすべて含まれる形となり、制度として一本化されました。寡婦控除のみ、ひとり親控除とは別枠での規定があります。
寡婦控除の対象となるのは、上記のひとり親控除の要件に該当しない人のうち、その年の12月31日の時点で以下の条件に当てはまる人です。対象となる場合、所得税27万円(住民税26万円)の控除を受けられます。
・夫との離婚後に結婚しておらず、扶養家族がおり合計所得額が500万円以下の女性。
・夫との死別後に結婚していない、または夫の生死が明らかではない状況で、合計所得額が500万円以下の女性。
つまり合計所得額が500万円以下で、離婚で寡婦となっているなら扶養親族がいる場合のみ、死別・生死不明で寡婦となっているなら扶養親族がいない場合でも寡婦控除が適用されます。
なお、寡婦控除の条件を満たす子供を扶養しているときは、寡婦控除ではなく、より控除額が大きいひとり親控除の対象とされます。また男女問わず対象となるひとり親控除とは異なり、寡婦控除が対象となるのは名前の通り女性のみです。寡婦控除の条件を満たしていても、男性は控除対象外です。
扶養控除とは、扶養親族がいる場合に所得税の課税対象となる所得から控除を受けられる制度のことです。「配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童、市町村から養護を委託された老人」「納税者と生計を同じくしている」「年間の合計所得金額が48万円以下」「青色申告者・白色申告者の事業専従者ではない」の条件を満たす家族がいると、控除対象となります。
扶養控除では、所定の要件を満たす扶養家族がいるかどうかのみが条件となっていて、ひとり親控除のような寡婦・寡夫であることや合計所得が500万円以下であること、扶養対象が子供であることなどの条件はありません。
また、ひとり親控除だと控除額は所得税35万円、住民税30万円が固定となっていますが、扶養控除は扶養対象となる親族の年齢や生活形態によって控除額が違ってきます。ひとり親と扶養控除は、条件を満たせば併用可能です。両者の違いは以下の通りです。
・ひとり親控除……一律で所得税35万円、住民税30万円。
・扶養控除……その年の12月31日時点での扶養対象者の年齢が、「16歳以上(一般扶養親族)」だと所得税38万円、住民税33万円、「19歳以上23歳未満(特定扶養親族)」だと所得税63万円、住民税45万円、「70歳以上で同居老親等(老人扶養親族・同居老親等)」だと所得税58万円、住民税45万円、「70歳以上で同居老親等以外の者(老人扶養親族・同居老親等以外)」だと所得税48万円、住民税38万円。
ひとり親控除を適用する方法について、会社員の場合と個人事業主など確定申告をする場合とで異なります。
企業や官庁などで勤務する給与所得者の場合、所属先の組織で年末調整が行われるときに「扶養控除等申告書」を提出しますが、書類の中にある「ひとり親」の欄にチェックを入れれば控除を受けられます。
確定申告用紙の第一表の「所得から差し引かれる金額」欄の中にある「寡婦・ひとり親控除」の欄に控除額を記入します。先述の通り所得税については控除額が一律35万円であり、表中にあらかじめ0が4つ記載済みなので、「35」だけを書き入れます。
ひとり親控除は必要な手続きをしないと受けられません。対象となる人は、会社員であれば年末調整時の扶養控除等申告の書類、自営業者であれば確定申告時の提出書類に、必要なチェック・記載を行いましょう。手続きさえすれば35万円(住民税30万円)の所得控除を受けられ、節税が可能です。またひとり親控除と類似の控除として、寡婦控除や扶養控除などもあるので、違いを知っておくと理解をより深められます。
参考サイト
国税庁|No.1171 ひとり親控除
国税庁|No.1172 寡夫控除
国税庁|No.1170 寡婦控除
国税庁|No.1180 扶養控除
経理COMPASS|ひとり親控除(2020年創設)とは?|ひとり親の税金はどう変わった?
弥生|ひとり親控除とは?適用要件や寡婦控除との違い、申告方法を解説
COOP共済|シングルマザーを応援!ひとり親家庭が知っておきたい暮らしのお金②
freee|確定申告における扶養控除とは?配偶者控除との違いや控除金額についても紹介
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

経理業務におけるスキャン代行活用事例

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

軽減税率導入で複雑化する請求書の消費税処理、経理担当者の手間を軽減するには?

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

収入印紙の消印とは?正しい押し方・使える印鑑・注意点をわかりやすく解説
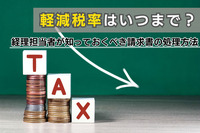
軽減税率はいつまで?経理担当者が知っておくべき請求書の処理方法

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト①/会計
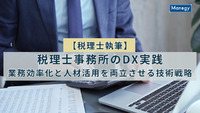
【税理士執筆】税理士事務所のDX実践──業務効率化と人材活用を両立させる技術戦略

消込とは?エクセルでは限界も。経理を圧迫する煩雑な業務が改善できる、システム化のメリット

内部統制報告書とは?提出が義務付けられる企業、記載事項・作成手順を解説
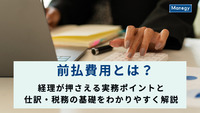
前払費用とは?経理が押さえる実務ポイントと仕訳・税務の基礎をわかりやすく解説
公開日 /-create_datetime-/