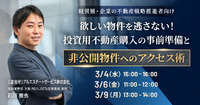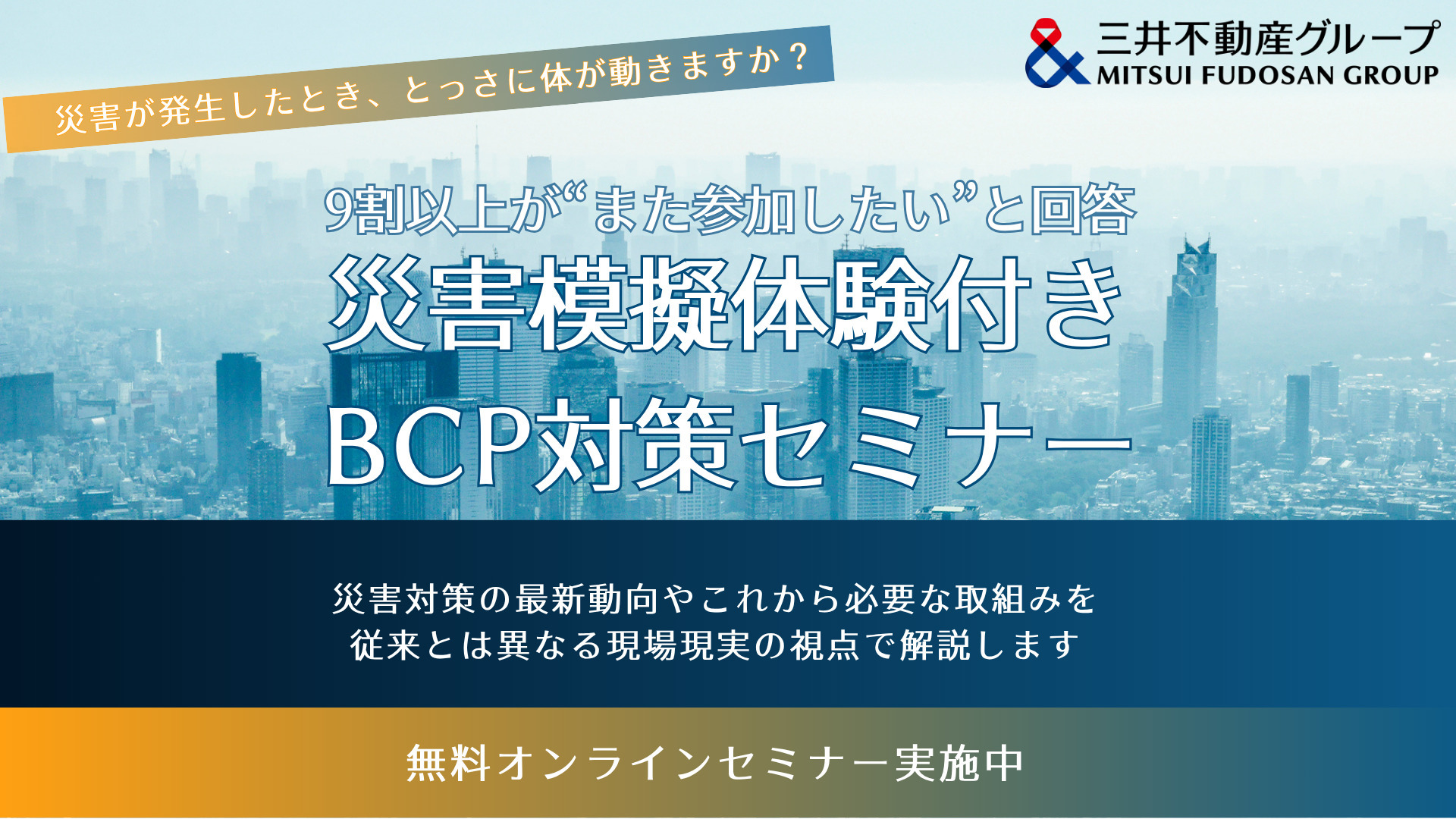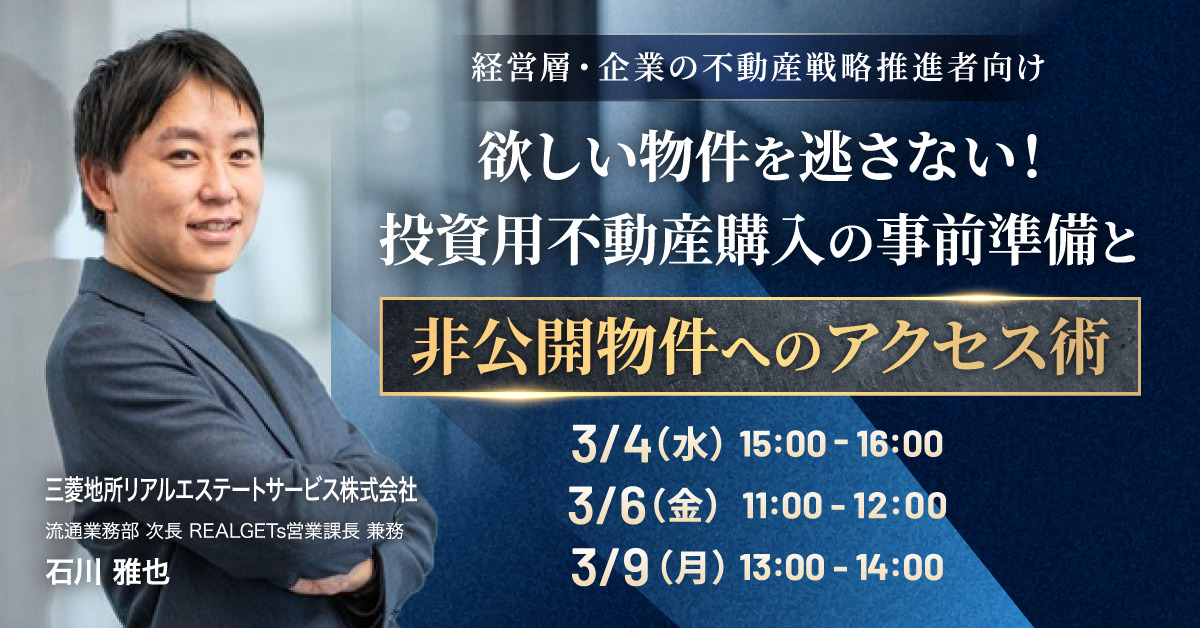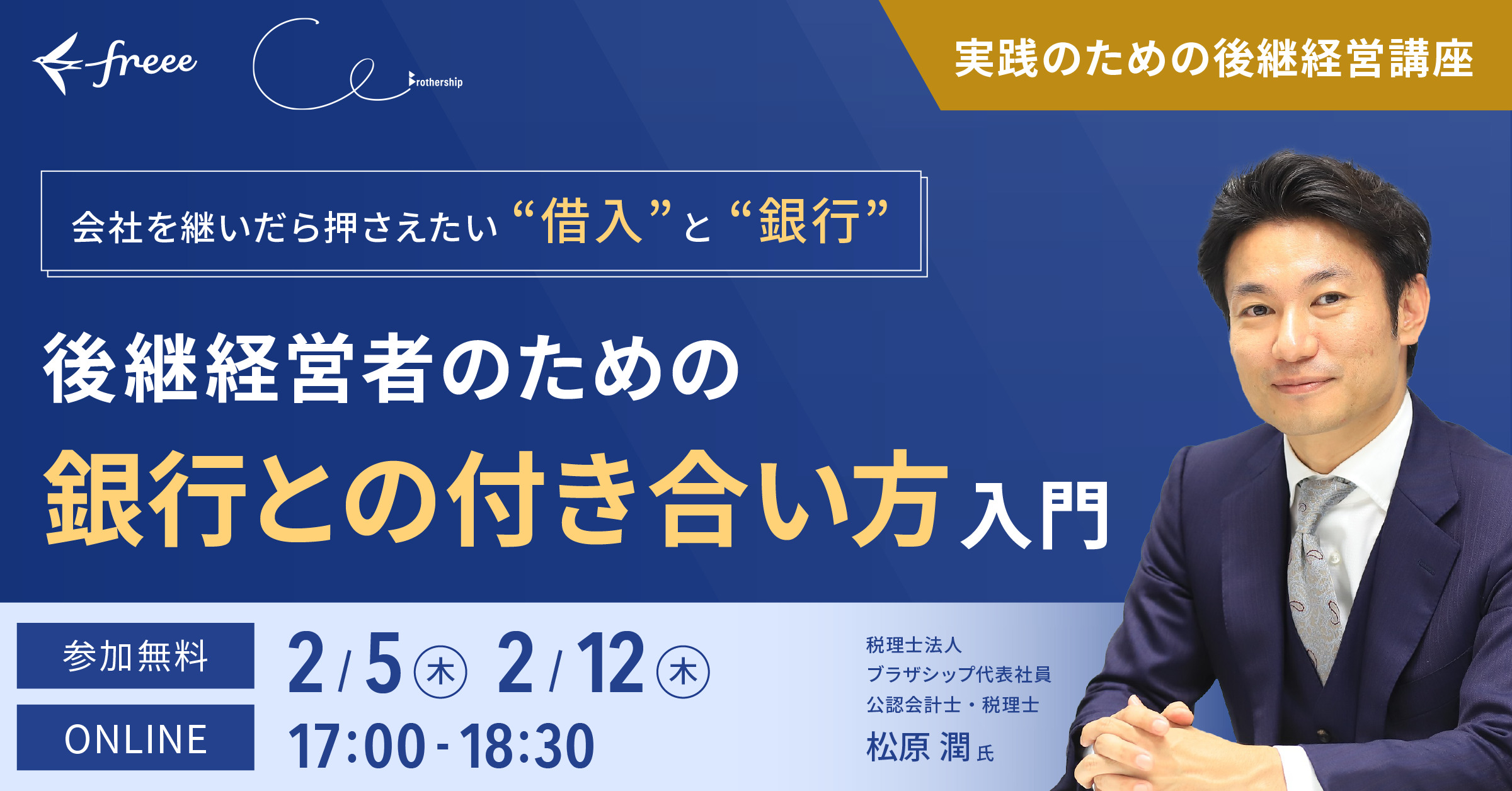公開日 /-create_datetime-/
【社労士執筆】外国人労働者雇用のポイントと労務管理の注意点

ご存じの通り、近年の日本における労働市場は少子高齢化の影響もあり、労働供給すなわち働き手の不足が目立ってきています。2024年における従業員の退職や採用難、人件費高騰などを原因とする人手不足倒産は過去最多を更新しております(https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250109-laborshortage-br2024/)し、直近では新卒社員を集めるために初任給を大幅に上昇させる企業も出始めています。
こういった状況の中注目されているのが外国人雇用で、外国人労働者を積極的に受け入れることによって人材を確保し、事業の安定・拡大を図っていこうとする動きがあります。外国人労働者の適正かつ有効な受け入れについては、入管法と労働法という二つの視点から考える必要がありますが、今回の記事では主に労働法の観点から、外国人労働者雇用のポイントと労務管理の注意点についてご紹介していきます。
目次本記事の内容

▼この記事を書いた人
寺山 晋太郎
社会保険労務士
社会保険労務士法人 宮嶋社会保険労務士事務所
福島県出身。一橋大学社会学部卒業。大手鉄道会社にて現業や本社勤務など様々な業務を経験。2014年第一子誕生を機に育休を取得。その後現職に転じ、働きながら社労士資格を取得。社労士業の傍ら、3児の父親としても奮闘中。
1 外国人労働者雇用の現状と背景
まず外国人雇用の現状です。平成19(2007)年より、外国人労働者を雇い入れた事業主は、その雇用もしくは離職の際に、ハローワークへ届け出ることが義務化されており、その統計結果は厚生労働省より年一回のペースで公表されております。
最新のデータである令和6(2024)年10月末現在における外国人労働者数は2,302,587人と、前年よりも253,912人増加しており、過去最高の人数になっております。外国人労働者を国籍別にみると、最多がベトナム、続いて中国、フィリピンの順になっています。
また人数の増加に伴って、外国人労働者を雇用する事業所の数もどんどん増えており、その数は342,087箇所とこちらも過去最高の数値になっています。このように、外国人労働者とそれらの方々を雇い入れる事業所の数は、過去例のないペースで増加しているというのが現状です。
この背景にあるのは、特に人材の確保が難しい業種の存在です。外国人労働者の内訳を在留資格別にみると、最も多いのが「専門的・技術的分野」であり、続いて「身分に基づく在留資格」「技能実習」「資格外活動」となりますが、ここで注意しておかなければならないことは、「専門的・技術的分野」には「特定技能」も含まれるということです。
「特定技能」とは令和元(2019)年より創設された在留資格で、人材の確保が困難な状況にある産業上の分野(介護、建設、自動車整備など)において外国人労働者を受け入れるためのものです。近年はこの「特定技能」の増加が非常に著しく、令和6(2024)年10月においては206,995人で対前年比49.4%増と、全在留資格の中でも最も大きい伸び率になっています。このことからも、国内において人手の確保が難しい業種において外国人労働者の受け入れが進んでいることが分かります。
外国人労働者の受け入れは今後も拡大することが見込まれ、それに伴い外国人労働者における労務管理の重要性も増していくことが予想されますので、次項以下で具体的な注意点、ポイントなどをご説明していきます。
lockこの記事は会員限定記事です(残り5526文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース -

工具器具備品とは? 税務・会計処理・減価償却・仕訳を解説
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト①/会計
ニュース -

2025年、上場廃止への「TOB・MBO」は112社 TOBの買い手は約30%がアクティビストを含む「ファンド」
ニュース -
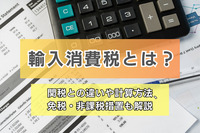
輸入消費税とは?関税との違いや計算方法、免税・非課税措置も解説
ニュース -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -
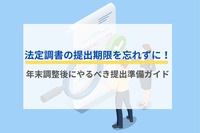
法定調書の提出期限を忘れずに!年末調整後にやるべき提出準備ガイド
ニュース -

1月23日~1月29日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

【最大16,000円】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』に参加してAmazonギフトカードをGET!
ニュース -
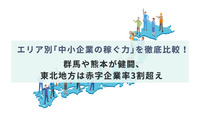
エリア別「中小企業の稼ぐ力」を徹底比較!群馬や熊本が健闘、東北地方は赤字企業率3割超え
ニュース -

出納業務とは?経理・銀行業務との違いや実務の流れをわかりやすく解説
ニュース