公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
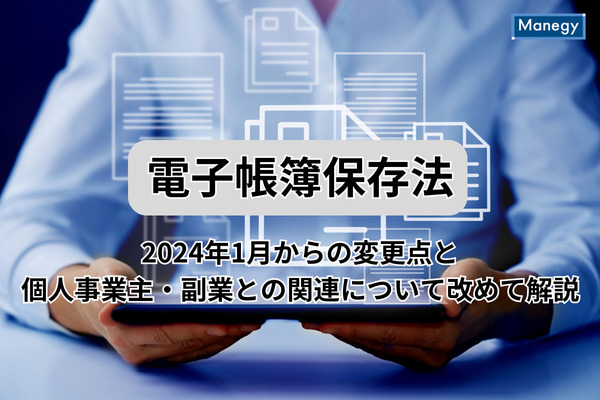
現在のビジネスシーンでは、国税に関わる帳簿などの書類や取引・契約関連の書類は、紙だけでなく電子データとして保存するのが一般的になっています。しかし紙から電子データへ、電子データから紙へと情報を転換する際、電子帳簿保存法を厳守する必要があります。思わぬところで法律違反にあたるおそれもあるため、同法の内容をしっかり押さえておくことが重要です。
そこで今回は電子帳簿保存法とは何か、直近の改正点のポイントについて詳しく解説します。
電子帳簿保存法とは、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を略した言い方で、国税関連の帳簿・書類をデータとして保存する際の手法について取り決めた法律です。
「電子」と名前に含まれているように、帳簿を紙の書類として管理する場合は無関係ですが、電子データとして保存・管理する場合は電子帳簿保存法のルールに従う必要があります。
具体的な保存のルールは細かく規定されていますが、骨子となるのは以下の2つの要件です。
・真実性の確保・・・「タイムスタンプを使用して取引情報の授受を行う」「訂正・削除の履歴を確認できるシステムもしくは訂正・削除ができないシステムにて保存する」「訂正・削除の防止に関する規程を定めて、それに基づく運用を行う」
・可視性の確保・・・「保存に使用しているパソコンやソフト、プリンターなどの機器類のマニュアルを保存場所に備え付け、画面や書面へと明瞭かつ迅速に出力できるようにしておく」「保存に使用しているパソコンなどの概要書を備え付ける」「検索機能を確保する」
なお、電子データの保存期間については、会社法、法人税法、所得税法などによって規定されています。基本的に法人は7~10年、個人事業主(副業含む)は5~7年で、法人であれば10年、個人事業主であれば7年の最長期間でどのデータも保存しておけば、法に抵触することは避けられます。
そして電子帳簿保存法では、以下の3種類の電子データ保存に関する取り決めがされています。
・電子帳簿等保存(自社内にてパソコンなどで作成した電子データの保存)
電子帳簿等とは、パソコンのソフトなどで電子的に作成された国税関連書類のことです。その保存方法に関するルールが、電子帳簿保存法において定められています。ただし紙の書類があれば、電子データ化するかどうかは任意とされており、電子データ化する場合は同法で定められたルールに従う必要があります。
・スキャナ保存
事業活動の中で取り交わす取引・契約関連の種類をスキャナで取り込んだり、スマホで撮影したりして電子データ化して保存する際のルールが、電子帳簿保存法において定められています。こちらも紙の書類があればスキャナ保存するかどうかは任意とされており、スキャナで保存する場合は同法で定められたルールに従う必要があります。
・電子取引のデータ保存
電子取引とは事業活動の中で取り交わす取引・契約関連の書類を、電子データのままでやり取りすることです。方法としては、メール添付、クラウドサービス、会計システムなどがあり、実際に行う際のルールが電子帳簿保存法において定められています。2025年現在、電子取引のデータについては紙に印刷して書類として保存することは法律で禁止されています。
電子帳簿保存法はパソコンのワープロソフト・表計算ソフトが急激に普及し始めた1998年に施行され、その後何度も改正が重ねられました。インターネットの普及やITの開発が進む中、法律も時代に合わせて変更する必要があるためです。 最近の大きな改正では2022年1月に、経済界のペーパーレス化を進めることを目的とした改正法が施行されています。
この改正法の目玉とも言える大きな変更点は、電子取引データを紙に出力しての保存が禁止され、電子データのままでの保存が義務化されたことです。それまでは電子取引のデータを紙に印刷した後、電子データは削除することも可能でした。しかし改正法は電子取引の記録は電子データのまま保存すべきことを企業に義務付けました。たとえば「メールで送られてきたPDFファイルを紙に印刷しておいたから、送られてきたPDFファイルは削除してしまおう」ということはできなくなったのです。
このようなルールを作ることで、電子取引のデータをわざわざ紙に印刷する必要性も動機もなくなり、ペーパーレス化が大きく前進します。国がこのルールを作った目的もその点にあります。「どうしても紙で内容をチェックしたい」という場合は印刷しても構いませんが、その場合でも、元の電子データは電子帳簿保存法のルールに則って(保存期間については会社法、法人税法、所得税法などに則って)保存されている必要があります。
この電子取引の電子保存の義務化は猶予期間が設けられていて、2023年12月末日までは紙で保存してもよいとされていました。しかし2024年1月からは完全に禁止事項とされています。
その他の改正法の中身としては、規制緩和の内容が盛り込まれています。従来は電子取引以外の帳簿書類を電子データに変換する場合、事前に税務署に申請して承認を得る必要がありましたが、それが不要となりました。さらに帳簿の訂正・削除をする場合、その変更履歴を確認できるように反対仕訳を記載するなどの対応が要りましたが、それも不要となっています。他にも複雑な検索要件が取引年月日、取引金額、取引先だけでOKになったり、タイムスタンプ付与期間が従来の「3営業日以内」から「2カ月と概ね7営業日以外」へと大幅に延長されたりと、電子データの扱いに関する規制が大きく緩和されています。
電子帳簿保存法の対象書類となるのは以下の通りです。
・国税関係帳簿・・・仕訳帳、総勘定元帳、売掛帳、買掛帳、現金出納帳、固定資産台帳など
・国税関係書類・・・貸借対照表、損益計算書、試算表、棚卸表などの決算関係書類、および請求書、見積書、納品書、注文書、領収書などの取引関係書類。なお取引関係書類については、自らが発行するものは控えを、取引相手から送られたものはその原本が対象です。
・電子取引の電子データ・・・電子メール、EDI、クラウドサービスなどを通して受け取った紙に印刷されていない請求書、見積書、納品書、注文書、領収書などの電子データ
以上のうち、電子取引の電子データについては、2024年1月以降、電子データのまま保存することが電子帳簿保存法によって義務化されています。
個人で事業をしている方に加えて、一定規模の副業をしている方も、国税関連の書類や取引・契約関連の書類をやり取りするため、電子帳簿保存法を厳守する必要があります。
直近の法改正との関連では、やはり「2024年1月以降は電子取引データを印刷して紙の状態で保存することが法律で禁止されている」ことを抑えておく必要があります。
従来は紙での保存が基本であった領収書、請求書、注文書といった取引情報は、取引相手から紙の状態で受け取った場合は紙のままでの保存でも問題ありません。しかし電子データとしてメール、クラウドサービスなどを通じて送付されてきた場合、その電子データは法律に則って保存しておく必要があります。電子データで授受したら、電子データとして保存する必要があるため注意しましょう。紙の書類で保存したい場合は、取引相手に紙の状態で郵送・送付してもらうのが原則です。
電子帳簿保存法は時代・技術の変遷とともに改正が重ねられています。2024年1月からは対象書類を電子データでやり取りしている場合は、原則電子データで保存することが義務化されました。副業により同法の対象書類をやり取りしている方も厳守する必要があるため、該当する場合は注意が必要です。
電子帳簿保存法に対応したシステムの導入により、コンプライアンス違反を避けることができ、書類管理にかかる業務や保管コストなども削減できます。自社・自分だけで対応することに不安を感じているなら、そうした外部サービスを活用するのもおすすめです。
参考サイト)
弥生|【2024年最新】電子帳簿保存法とは?改正点もわかりやすく解説
弥生|電子帳簿保存法の対象書類一覧!具体的な対象書類の保存方法も解説
弥生|電子帳簿保存法に個人事業主はどう対応する?ポイントを解説
ミラサポ|どうすればいいの?「電子帳簿保存法」
国税庁|電子帳簿等保存制度
マネーフォワード|電子帳簿保存法とは?2024年からの改正内容・対象書類を簡単に解説
freee|電子帳簿保存法とは?対象書類や保存要件・改正内容についてわかりやすく解説
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

令和7年度 税制改正のポイント

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
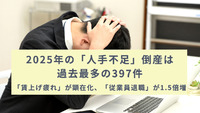
2025年の「人手不足」倒産は過去最多の397件 「賃上げ疲れ」が顕在化、「従業員退職」が1.5倍増

「組織サーベイ」の結果を組織開発に活かす進め方と方法論
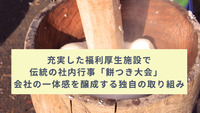
充実した福利厚生施設で伝統の社内行事「餅つき大会」 会社の一体感を醸成する独自の取り組み

キャッシュフロー計算書を武器にする|資金繰りに強い経理が転職市場で評価される理由(前編)
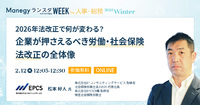
2026年法改正の全体像!労働・社会保険の実務対応を解説【セッション紹介】

サーベイツールを徹底比較!

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

人的資本開示の動向と対策
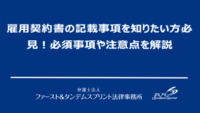
雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

旬刊『経理情報』2026年1月10日・20日合併号(通巻No.1765)情報ダイジェスト①/税務

販売代理店契約における販売手数料の設計のポイントや注意点とは?サプライヤー側の契約審査(契約書レビュー)Q&A

「ディーセントワーク」の解像度を上げ、組織エンゲージメントを高めるには
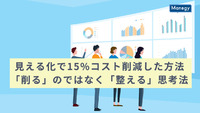
見える化で15%コスト削減した方法|「削る」のではなく「整える」思考法

法務担当者がM&Aに携わるメリットとは?市場価値を高める役割や必須スキルを解説(前編)
公開日 /-create_datetime-/