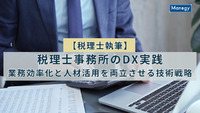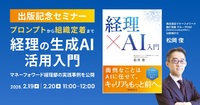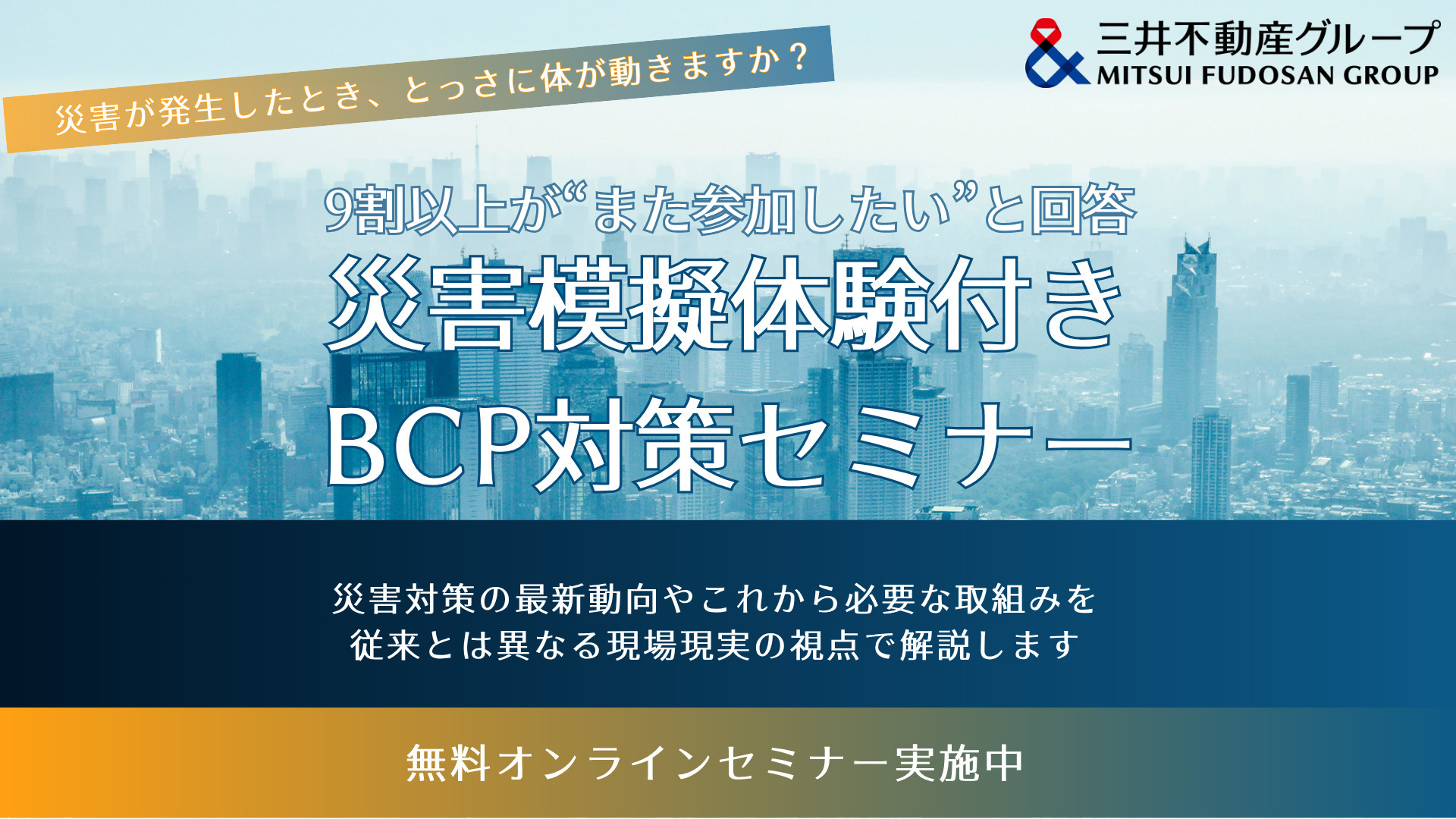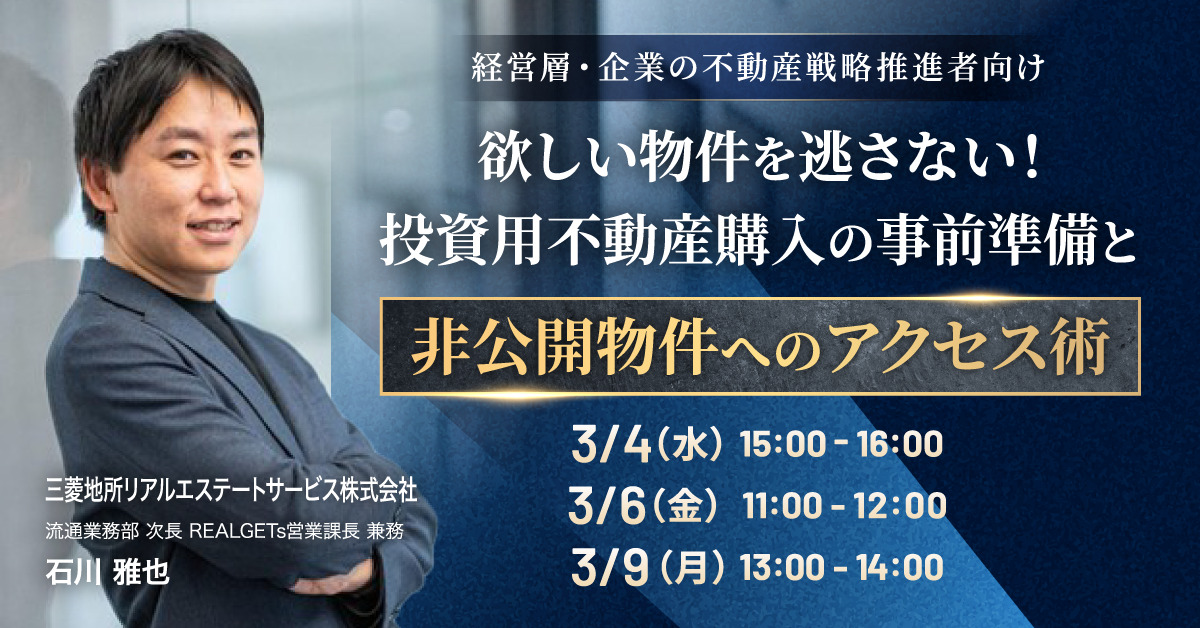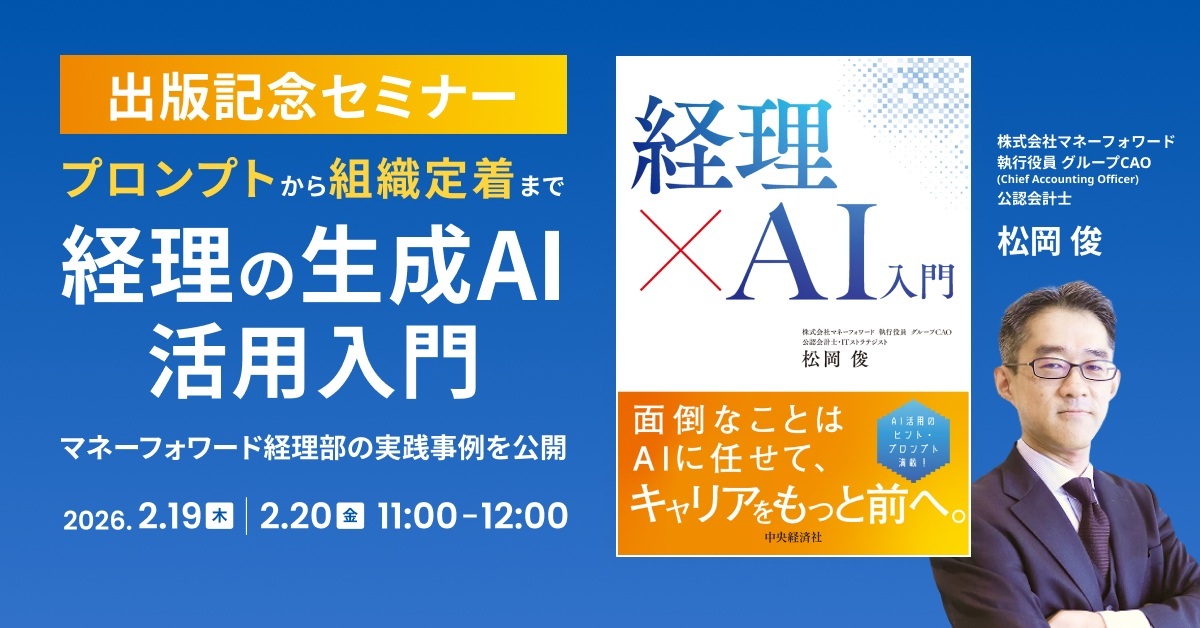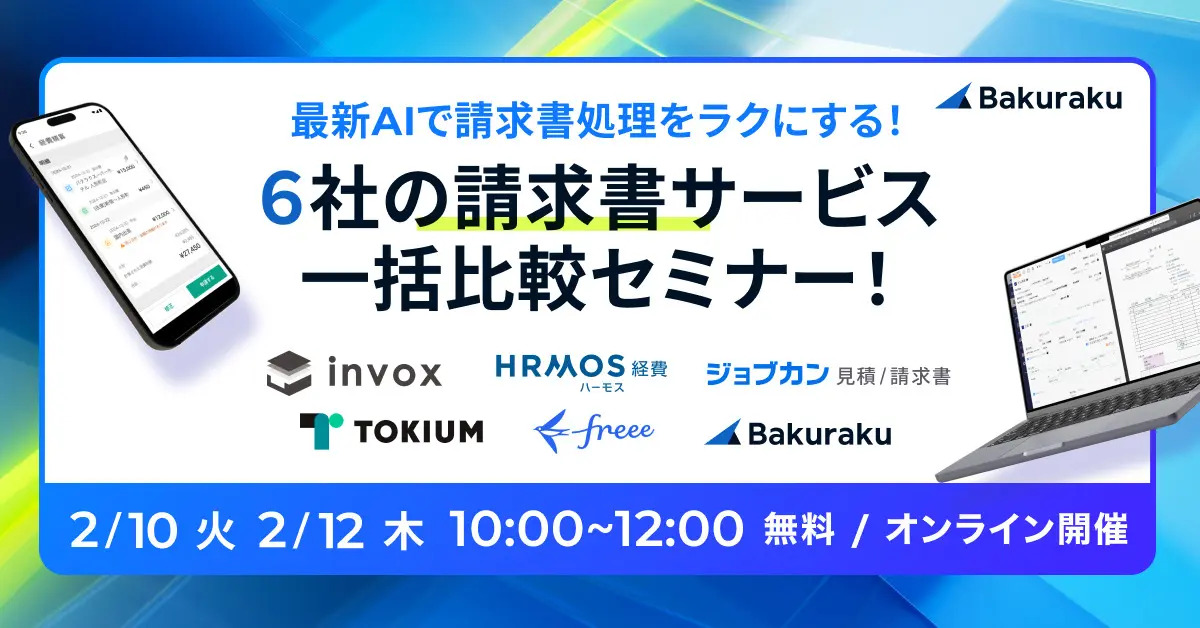公開日 /-create_datetime-/
いまさら聞けない「エンゲージメント」とは|第1回 エンゲージメント向上に力を入れる企業が増えているのはなぜ?
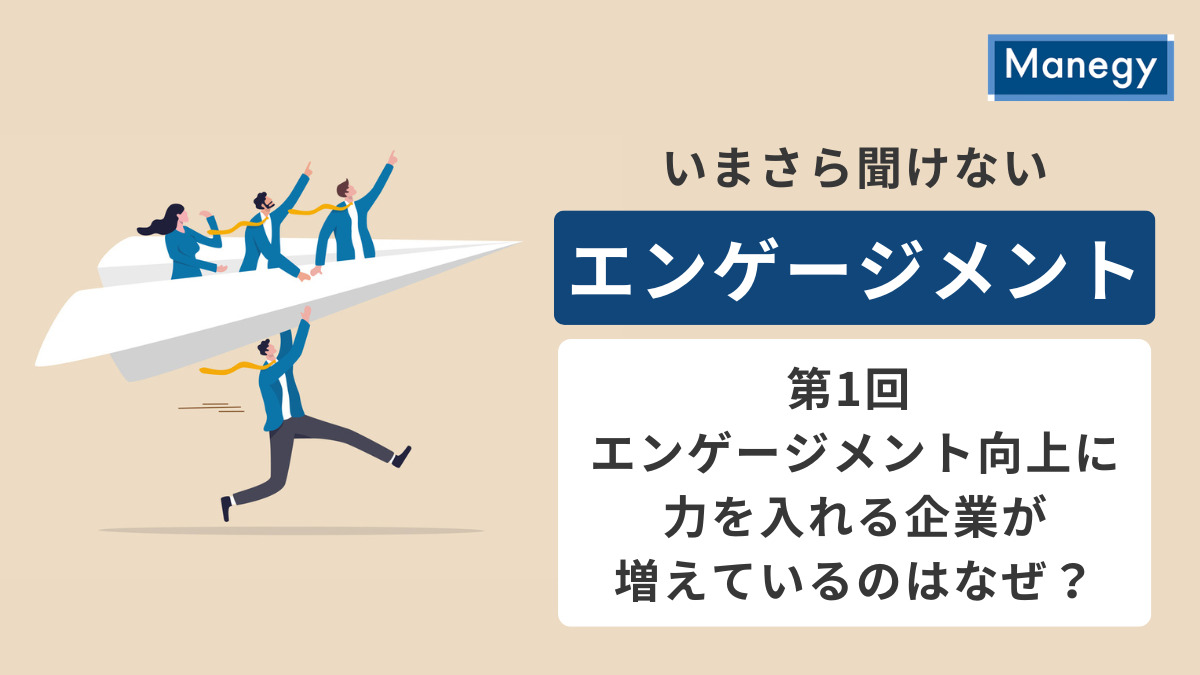
日本では少子高齢化が進み、労働人口の減少が深刻な課題となっています。
加えて、IT技術の進展や消費者行動の変化など、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした状況の中で、企業が環境の変化に適応し、持続的な成長を遂げるには、新たなイノベーションを創出できる「人材」の確保が欠かせません。
このような背景から、投資の分野でも関心が高まり、人的資本経営への注目が集まっています。特に多くの企業が注目するのが「エンゲージメント」です。これは事業成果や生産性と相関があり、組織状態を可視化すると同時に、組織と従業員の結びつきの強さを示す指標として注目されています。
本連載では、企業がエンゲージメント向上に取り組む意義や、エンゲージメント向上のポイントなどについてお伝えしていきます。
目次本記事の内容
「採用しても、採用しても、組織が疲弊する負の連鎖」
「経営が期待をかけていた優秀な社員が離職してしまう」
「先月まで張り切っていた社員が、急に『次の会社が決まったから』と辞めてしまった」
上記のように、優秀な人材の採用・定着に課題感を抱えている企業は少なくありません。
厚生労働省が23年10月に実施した調査では、新規大卒就職者の3年以内の離職率は32.3%となっており、
大卒で入社した新入社員の約3人に1人が3年以内に離職していることが明らかとなっています。
背景には、転職活動の一般化や働く価値観の多様化があります。
人材の流動性が高まったことで、従業員を定着させる難易度は年々上がっているのが現状です。
※参考:厚生労働省|新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します
このように、離職に歯止めがかからず、人材が流出すると既存社員への負荷が高まります。 それにより徐々に組織が疲弊していくため、その疲弊を解消するために採用を行います。
しかし、離職に対して根本的な課題を解決していないため、採用しても結局定着せずに悪循環に陥っている企業は少なくありません。
この悪循環を断ち切り、従業員から選ばれ続けるために多くの企業が「エンゲージメント」に注目しています。
lockこの記事は会員限定記事です(残り2469文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -
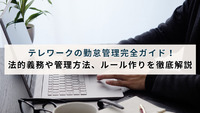
テレワークの勤怠管理完全ガイド!法的義務や管理方法、ルール作りを徹底解説
ニュース -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

越境ECで売上を伸ばす海外レビュー戦略とは?重要性・実践方法・注意点を解説
ニュース -
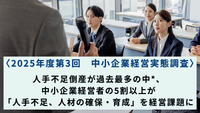
〈2025年度第3回 中小企業経営実態調査〉人手不足倒産が過去最多の中*、中小企業経営者の5割以上が「人手不足、人材の確保・育成」を経営課題に
ニュース -

収入印紙の消印とは?正しい押し方・使える印鑑・注意点をわかりやすく解説
ニュース -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント
おすすめ資料 -

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方
おすすめ資料 -
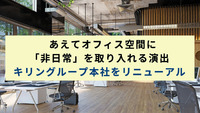
あえてオフィス空間に「非日常」を取り入れる演出 キリングループ本社をリニューアル
ニュース -
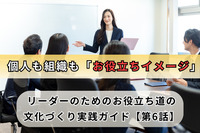
個人も組織も「お役立ちイメージ」/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第6話】
ニュース -

「給与レンジ」を適切に設計。採用力や定着率を高める効果も
ニュース -
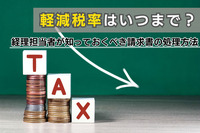
軽減税率はいつまで?経理担当者が知っておくべき請求書の処理方法
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト①/会計
ニュース