公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?

就労ビザを持たない外国人を採用する際には就労ビザ取得の手続きが必要です。ビザの審査は年々厳しくなっていますので、正しい知識を持って申請することが大切です。外国人採用の手続きについて企業の人事部・採用担当者の皆さまは、次のようなお悩みがあるのではないでしょうか。
「そもそも就労ビザってどんなものなの?」
「就労ビザの種類には何があるの?」
「就労ビザを取得する方法は?」
「就労ビザの審査って何を見ているの?」
「就労ビザの取得にはどのくらい時間がかかるの?」
この記事では、就労ビザの説明から取得の手順・ポイントまでを分かりやすく解説します。
一般的に「就労ビザ」と言われているものは「在留資格」のことを指すことが多いです。「ビザ」と「在留資格」は全く異なるものです。
◆ビザ(査証)とは
日本に入国する前に海外の日本公館で発行されるものです。日本に入国するために必要なものです。入国が保証されるものではありませんが、入国手続きに必要になります。
◆在留資格とは
日本に入国した後に付与される資格です。日本に滞在し活動するため必要なものです。
分かりやすく例えると、「ビザ(査証)」は日本に来るための許可証、「在留資格」は日本で活動するための許可証です。
厳密には「就労ビザ」というものは存在しませんが、「日本で就労するために必要な在留資格」のことを指しています。この記事では「日本で就労するために必要な在留資格」の意味で「就労ビザ」と記載します。
日本には様々な職業があります。就労ビザも職業の性質や職種にあわせ現在16種類あります。
原則として保有する就労ビザで認められている活動の範囲内でのみ就労が認められます。
なお、日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者といった身分系のビザは日本人と同様に違法でない限りは制限なく就労することができます。ただし、日本人の配偶者と離婚するなど身分に変更があった場合は在留資格の変更も必要になりますので、家族情報に変更があった際などは必ず届出をしてもらうようにしましょう。
外国大使館や外国領事館の構成員としての活動。外国大使館や外国領事館の構成員の配偶者や子も該当します。
外国大使館や外国領事館、国際機関の公務活動。外国大使館や外国領事館の職員は「公用ビザ」を取得します。また、海外政府から公務で派遣される者の配偶者や子も該当します。
◆WRITER

弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】
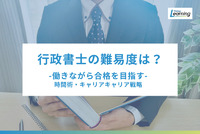
行政書士の難易度は「管理部門での実務経験」で変わる? 働きながら合格を目指す時間術とキャリア戦略

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。

今、何に貢献しますか?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第7話】

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
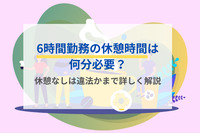
6時間勤務の休憩時間は何分必要?休憩なしは違法かまで詳しく解説

軽減税率導入で複雑化する請求書の消費税処理、経理担当者の手間を軽減するには?

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!

文書管理データ戦略:法人セキュリティの決定版
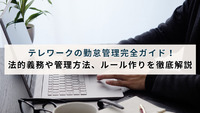
テレワークの勤怠管理完全ガイド!法的義務や管理方法、ルール作りを徹底解説
公開日 /-create_datetime-/