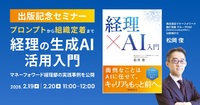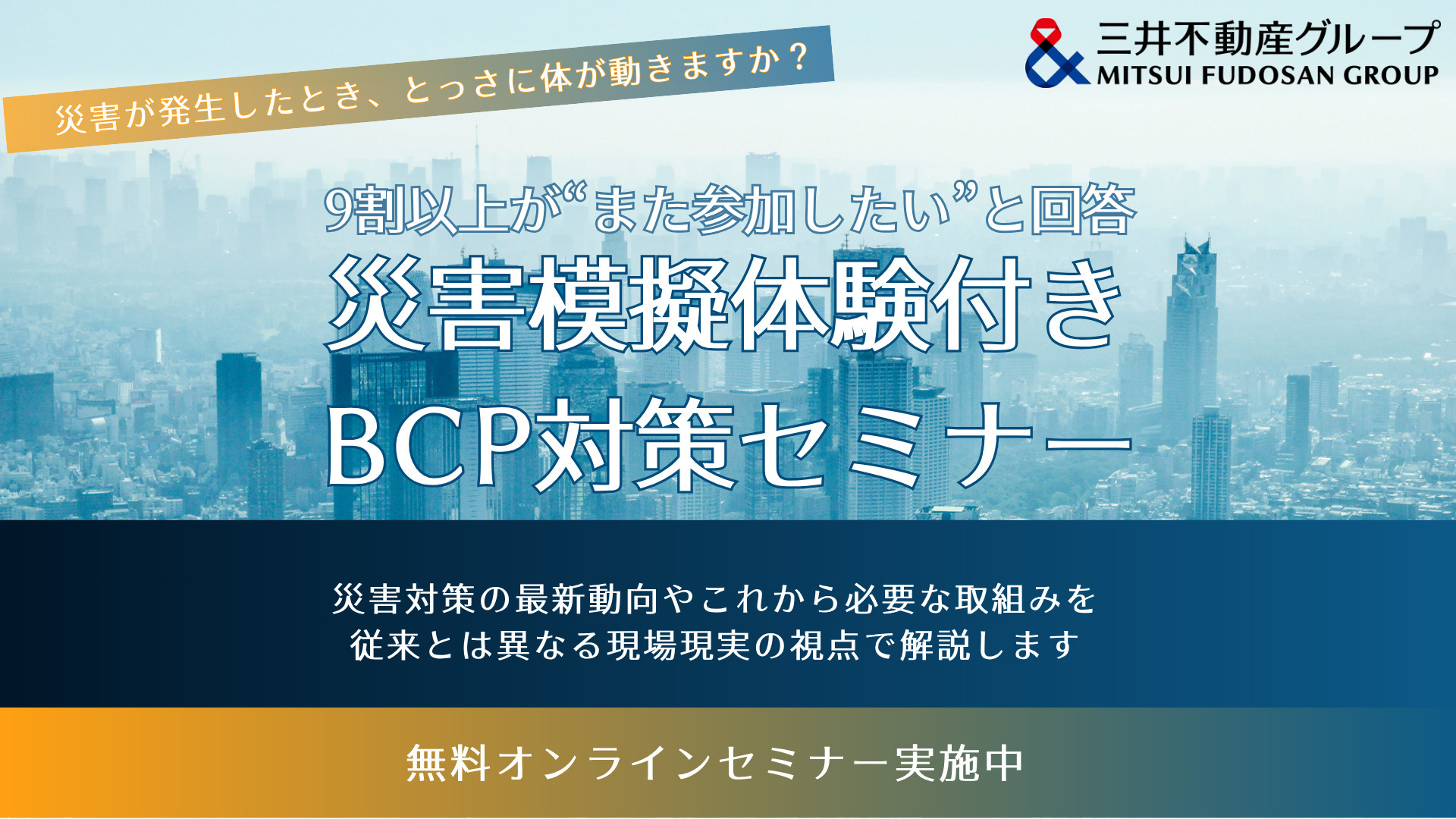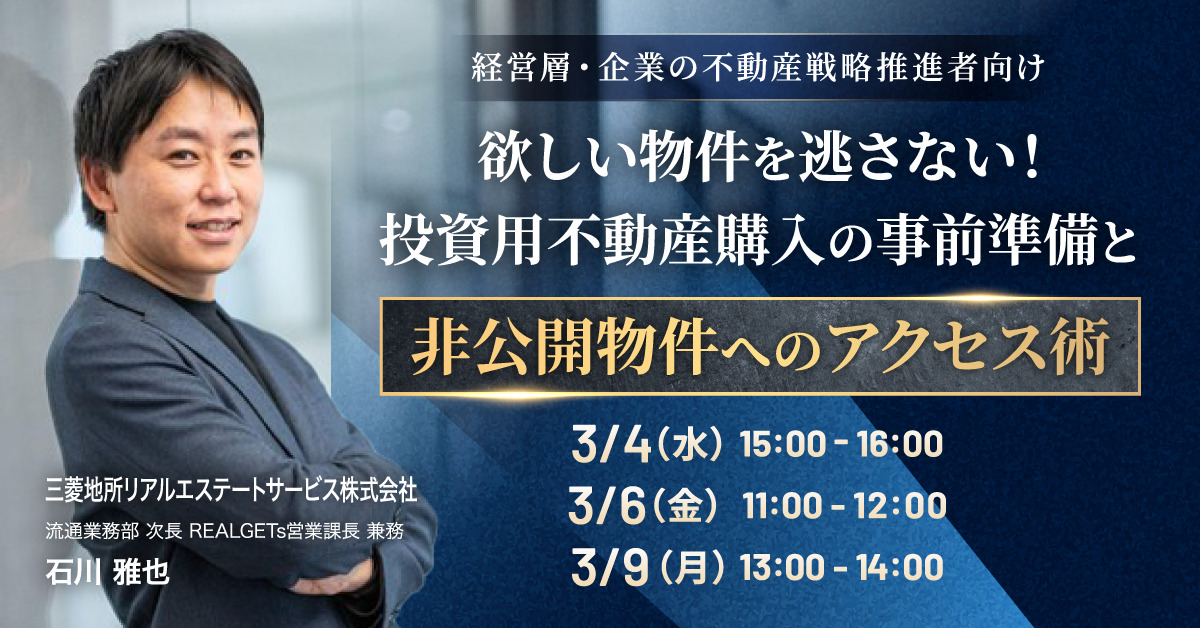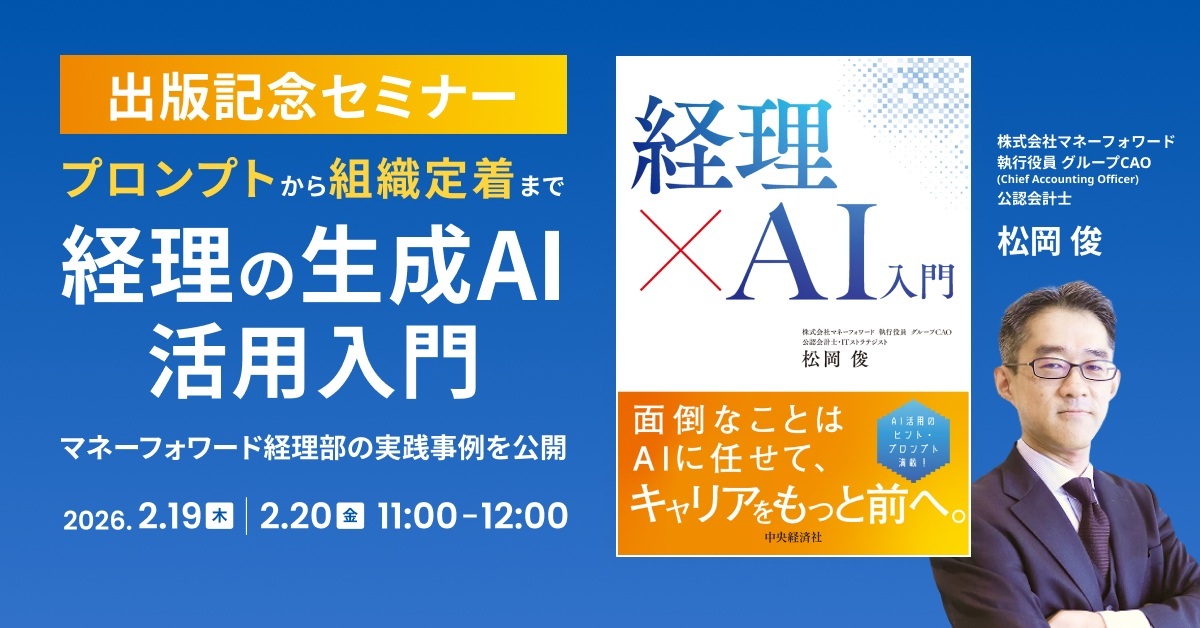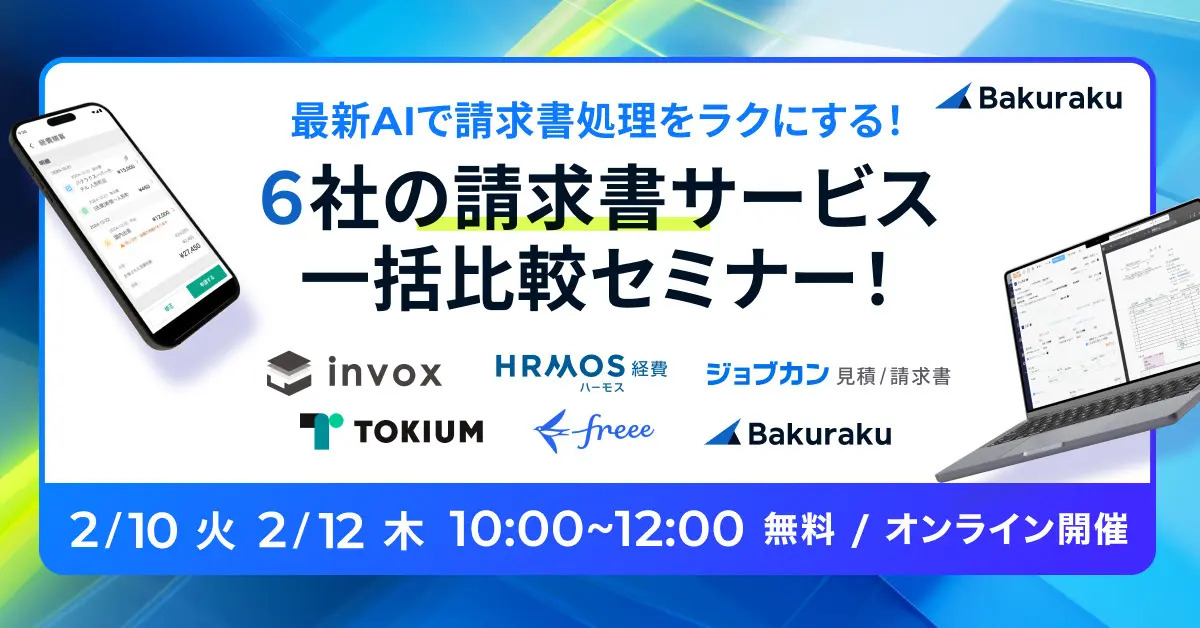公開日 /-create_datetime-/

育児休業を取り巻く環境変化と制度の変遷
現代の日本において、労働者が仕事と子育てを両立することの重要性は、ますます高まっています。労働力不足の昨今、企業にとっても育児休業制度の整備は不可欠です。特に、男性の育児休業取得が推奨されるようになり、政府もその促進に力を入れています。 こうした変化に対応するため、育児・出産に関する法律は改正を重ねてきました。
例えば、令和4年には「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設され、男性が子の出生直後に柔軟に休業を取得しやすくなりました。また、育児休業の分割取得が可能になり、育児と仕事を両立しやすい環境が整えられています。
さらに、令和7年4月には、新たに「出生後休業支援給付金」および「育児短時間就業給付金」が創設されます。これにより、子の養育中の収入減を抑制し、育児と仕事のバランスを取りやすくすることで、さらなる育休取得の促進が期待されています。
本記事では、これらの新制度について詳しく解説します。
lockこの記事は会員限定記事です(残り2396文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

軽減税率導入で複雑化する請求書の消費税処理、経理担当者の手間を軽減するには?
ニュース -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
ニュース -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

収入印紙の消印とは?正しい押し方・使える印鑑・注意点をわかりやすく解説
ニュース -
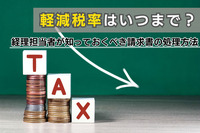
軽減税率はいつまで?経理担当者が知っておくべき請求書の処理方法
ニュース -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト①/会計
ニュース -
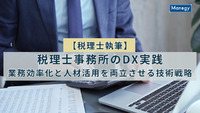
【税理士執筆】税理士事務所のDX実践──業務効率化と人材活用を両立させる技術戦略
ニュース -

消込とは?エクセルでは限界も。経理を圧迫する煩雑な業務が改善できる、システム化のメリット
ニュース -

内部統制報告書とは?提出が義務付けられる企業、記載事項・作成手順を解説
ニュース -
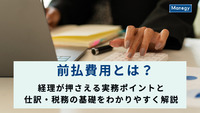
前払費用とは?経理が押さえる実務ポイントと仕訳・税務の基礎をわかりやすく解説
ニュース