公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?
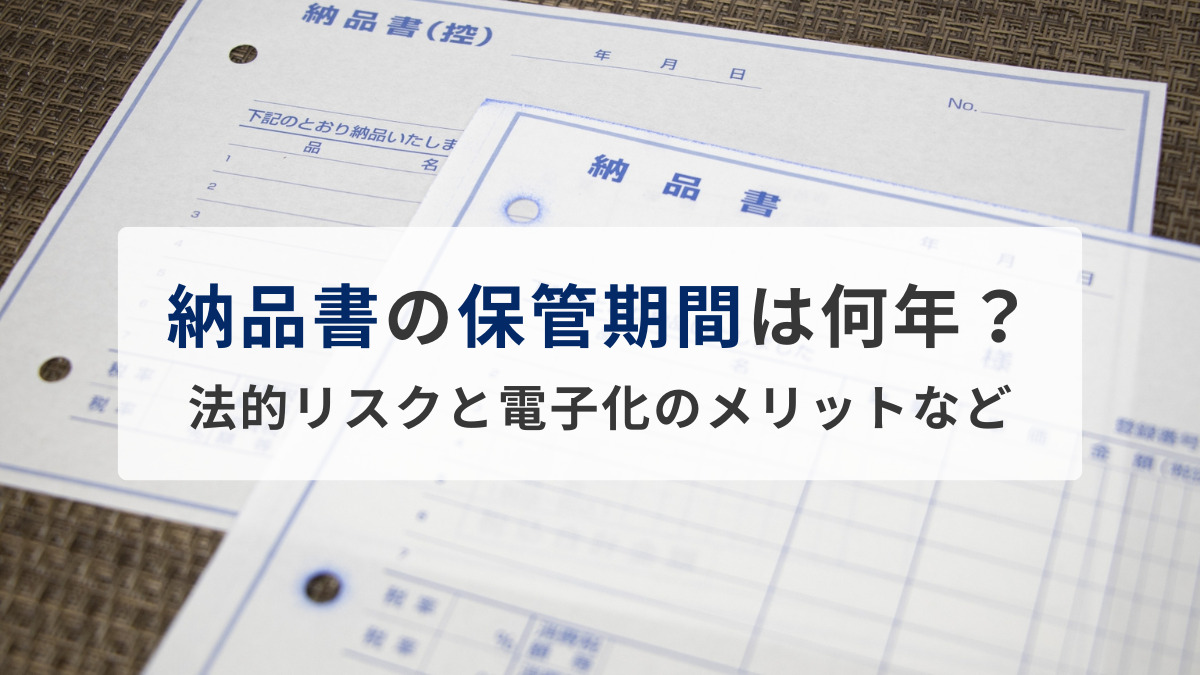
この記事を読んでわかること
納品書の保管期間は法律で定められており、会社法と税法で異なる
保管期間を守らないと罰則や税務リスクがある
電子化すると保管や検索が容易になり、コスト削減にもつながる
納品書は、取引の証拠として機能し、経理処理や税務申告の際に必要不可欠な書類です。納品書を適切に保管することで、企業は法的リスクを回避し、税務調査にも迅速に対応できるようになります。納品書の保管期間が法令でどのように定められているのかをしっかり理解し、遵守することが重要です。
また、納品書の紙での保管と電子による保管には、それぞれメリットとデメリットがあります。この記事では、納品書の保管期間に関する法令の規程や、それを守らなかった場合のリスクについてわかりやすく解説します。さらに、納品書の管理方法として、紙媒体と電子化のそれぞれの利点や具体的な方法についても取り上げます。
ここでは電子データでの文書保存に関する電子帳簿保存法についても言及しますが、それに適したサービスも存在します。
<関連記事>
【弁護士監修】企業の書類保管期間一覧!保存すべき書類とその保管方法
【弁護士監修】通帳の保管期間を徹底解説! 保管期間や安全な処分方法は?
【弁護士監修】給与明細の保管期間とは? 3つのメリットやリスクを詳しく解説
【弁護士監修】賃金台帳の保管期間と保存方法を徹底解説! 違反のリスクと電子化のポイント
【弁護士監修】決算書の保管期間と法令遵守の重要性|永久保存が望ましい社内文書も紹介
納品書の保管期間は、一般的に以下の二つの法律が基準となります。
会社法に基づく保管期間は10年
会社の経理書類の一部として、各事業年度の計算書類(貸借対照表など)や事業報告と共に、附属明細書を保存すること、そしてその保存期間が定められています。納品書はこの付属明細書に該当すると考えられ、10年間の保管が必要です(会社法435条4項)。なお、保管期間の起算は「計算書類を作成した時から」とあるので、決算の締め日の翌日が起算日になると考えられます。
税法に基づく保管期間は7年
税法では、納税にする書類の保管期間が定められています。納品書は、所得税法や法人税法に基づく経理書類の一部として扱われます。以下が主な保管期間の例です。
・所得税法個人事業主の場合、納品書は確定申告期限の翌日から5年間保管する必要があります(所得税法施行規則102条4項)。
・法人税法法人の場合、納品書を含む会計帳簿は確定申告書の提出期限の翌日から7年間保管する必要があります(法人税法施行規則67条2項)。
特定の条件下では、納品書の保管期間が異なる場合があります。以下はその一例です。
・特例適用期間の延長税務調査で問題が見つかった場合や申告内容に誤りがあった場合、通常の保管期間を超えて納品書の保管が必要となることがあります。
・特定の取引の性質建設業などの長期計画の場合、契約期間や工事の完了日を基準に保管期間が延長されることがあります。
以上のように、納品書の保管期間を定める法令は複数あります。各法令に基づき、納品書は7年ないし10年間保管するべきものと考えるのが適切です。企業はこれらの法的要件を理解し、適切に納品書を管理する必要があります。
納品書の保管期間が、会社法で10年、税法で5年と異なるのは、目的の違いによるものです。
会社法は、企業活動を正しく行うために定められた法律です。企業活動でトラブルがあった場合、納品書は事実を確認する重要な書類です。企業と個人顧客間でトラブルがあった場合の消滅時効は ①権利を行使できることを知ったときから5年、②権利を行使できるときから10年なので、会社法に基づき納品書を保管する場合は、10年間保管することが望ましいでしょう。
一方、税法では、追徴課税には時効が存在します。そのため、......
記事提供元

株式会社LegalOnTechnologiesは、「法とテクノロジーの力で、安心して前進できる社会を創る。」をパーパスに掲げ、2017年に森・濱田松本法律事務所出身の弁護士2名によって創業されました。
法務知見と生成AIなどの最新のテクノロジーを組み合わせた企業法務の質の向上と効率化を実現するソフトウェアを開発・提供するグローバルカンパニーです。法務業務を全方位でカバーするAI法務プラットフォーム「LegalOn」を展開しています。
また米国にも拠点を置きグローバル向けのAI契約レビューサービス「LegalOnGlobal」を提供しています。
グローバルにおけるリーガルテックサービスの有償導入社数は 6,500社を突破しています。 (2024年12月末現在)
2025年1月から事業をコーポレート全域に広げAIカウンセル「CorporateOn」を提供開始しました。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴
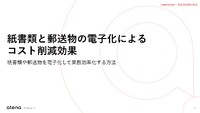
紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント

サーベイツールを徹底比較!

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト①/税務

自己理解の深化が退職予防に影響、2306人を調査
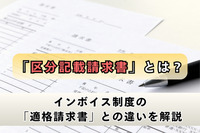
「区分記載請求書」とは?インボイス制度の「適格請求書」との違いを解説

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革

産業医の探し方|初めての選任で失敗しない4つのポイント

棚卸評価損の仕訳とは?計算方法・仕訳例・評価方法をわかりやすく解説

攻めと守りの「AIガバナンス」: 経産省ガイドラインの実践と運用課題
公開日 /-create_datetime-/