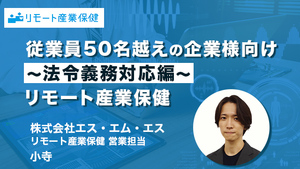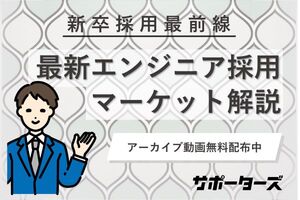公開日 /-create_datetime-/
【社労士執筆】人手不足倒産のリスクを避けるための採用・労務管理
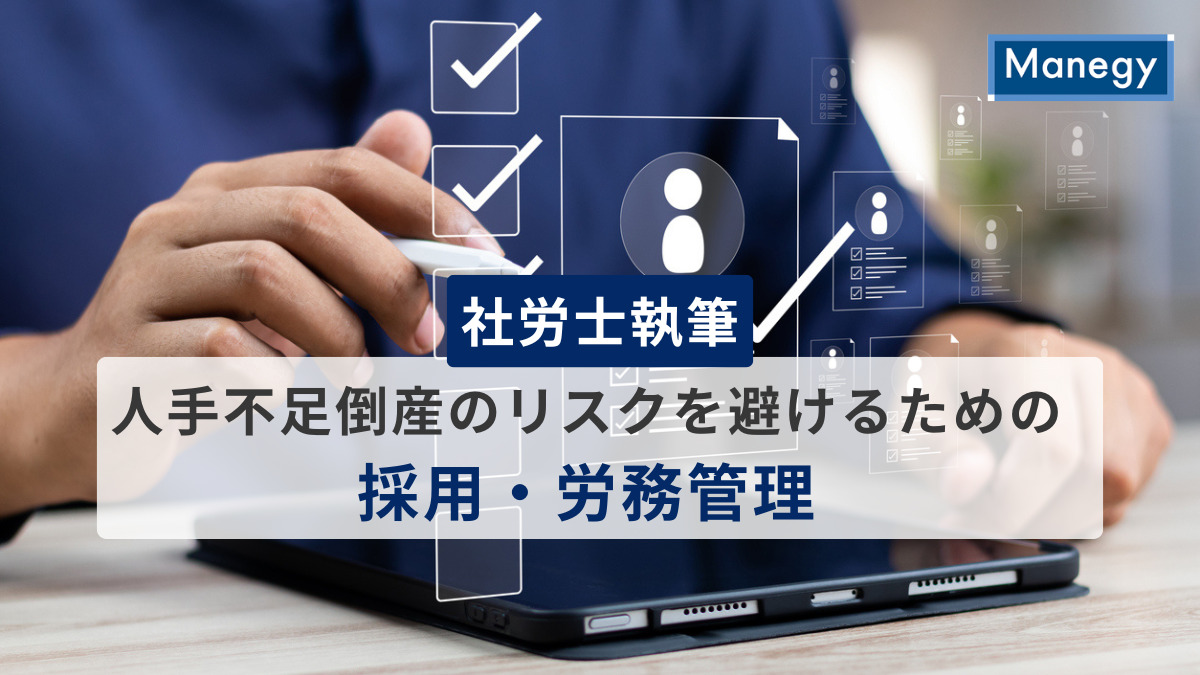
目次本記事の内容
人手不足倒産の状況
現在、人手不足による倒産が急増しており、帝国データバンクによると2024年の累計では、従業員の退職や採用難、人件費高騰を原因とする人手不足倒産は342件となっています。前年比で1.3倍増加し、2013年以降最多であり、2年連続で大幅に増加しています。全体のうち、建設業と物流業が40%を占め、その他、飲食業、美容室などの美容業、労働者派遣業、警備業の倒産も急増しています。
東京商工リサーチによると、2024年度(4-2月)の人手不足による倒産は過去最多の283件の前年同期比88.6%増となっており、産業別では通所・短期入所介護事業、訪問介護事業などのサービス業が前年同期比で68.6%増の86件となり、過去最多となっています。
厚生労働省における令和6年上半期雇用動向調査結果の概要の未充足求人の状況によると、産業別の未充足求人数は、卸売業・小売業が270.6千人で最も多く、次に医療・福祉が269.5千人となっています。欠員率では、建設業が5.4%と最も高く、次に鉱業・採石業・砂利採取業が4.6%、宿泊業・飲食サービス業は4.4%となっています。
lockこの記事は会員限定記事です(残り4931文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -
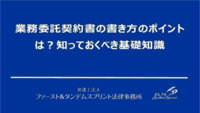
業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -
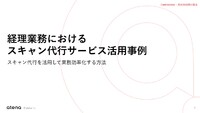
経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -
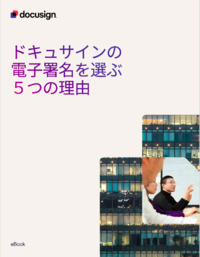
2,000人の経営幹部に聞く!電子署名導入のメリットと懸念点を徹底解剖
おすすめ資料 -

【会計】金融資産の減損における期中期間の簡便処理、検討─ASBJ、金融商品専門委 旬刊『経理情報』2025年7月20日号(通巻No.1749)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

【対談インタビュー】採用から組織を変える力を育てる。マクロミルと外部人材が共創する人事と組織のかたち。
ニュース -
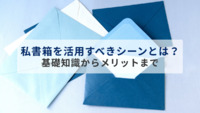
私書箱を活用すべきシーンとは?基礎知識からメリットまで解説
ニュース -

1-6月の「人手不足」倒産 上半期最多の172件 賃上げの波に乗れず、「従業員退職」が3割増
ニュース -

法人向けクラウドストレージのバックアップサービスとは
ニュース -
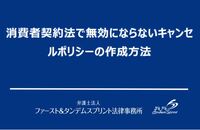
消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -
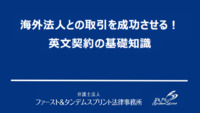
海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
おすすめ資料 -

BillOneの導入で請求書業務はこう変わる
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

上半期の「後継者難」倒産 2番目の230件 高齢化の加速で、事業承継の支援が急務に
ニュース -

大規模プロジェクトに最適なクラウドストレージへのデータ移行手順
ニュース -

アフターコロナで対面増、ジャケット着用が半数超に 夏のビジネス現場や就活に広がる「汗の不安」
ニュース -
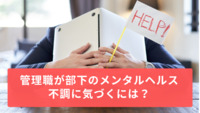
管理職が部下のメンタルヘルス不調に気づくには?
ニュース -
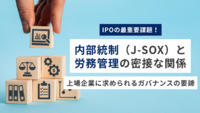
IPOの最重要課題!内部統制(J-SOX)と労務管理の密接な関係:上場企業に求められるガバナンスの要諦
ニュース
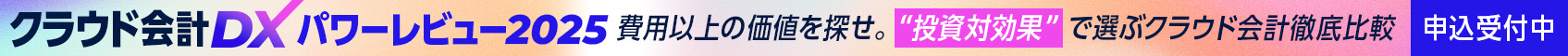










 ポイントをGETしました
ポイントをGETしました