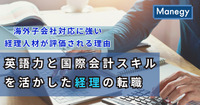公開日 /-create_datetime-/
税務調査のチェックポイント8選|事前対策と調査官が狙うポイントを完全解説!
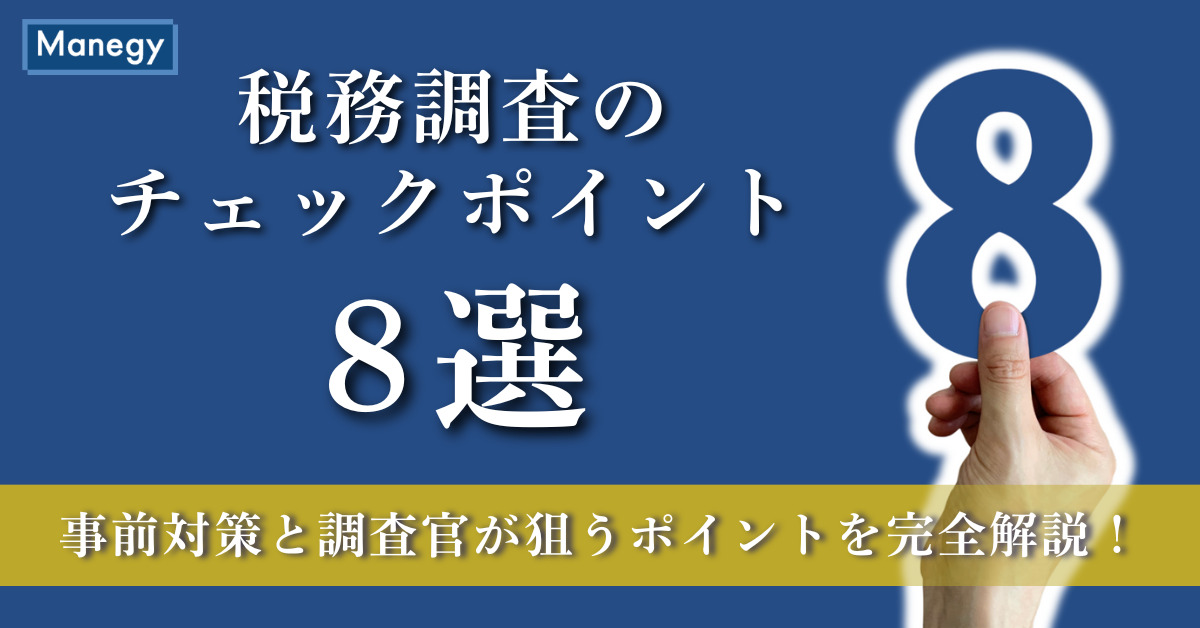
税務調査は、企業や個人事業主にとって避けては通れないものです。
「突然の税務調査にどう対応すればいいのか?」、「調査官はどこを重点的にチェックするのか?」といった疑問や不安を抱えている方も多いでしょう。
この記事では、税務調査の基本的な流れや、調査官が注目するポイントを詳しく解説し、事前準備の方法や適切な対応策を紹介します。
適切な対策を講じることで、調査のリスクを軽減し、スムーズな対応が可能になりますので、ぜひ最後までご覧ください。
税務調査とは
税務調査とは、企業や個人事業主が適切に税務申告を行っているかを確認するために、税務署や国税局が実施する調査のことです。
法人税や所得税、消費税など主な税目は「申告納税制度」を採用しており、納税者自身が計算・申告・納税を行う仕組みになっています。
しかし、意図せず誤った申告をしてしまうケースや、意図的に不正を行うケースもあるため、税務当局は必要に応じて申告内容の正確性を確認するために税務調査を行います。
適正な申告と納税を促し、公平な税制を維持するためにも、税務調査は重要な役割を果たしています。
税務調査の目的
税務調査が行われる主な目的は、以下の3つに分けられます。
申告内容の正確性を確認するため
企業や個人事業主が提出した申告書が、税法に基づいて正しく作成されているかを確認することが目的のひとつです。
記帳ミスや計算ミスなどが原因で誤った申告をしているケースもあるため、税務署はこれらの誤りを発見し、適正な納税が行われるように調査を実施します。
税務不正の防止・発見のため
一部の納税者が意図的に売上を過少申告し、架空の経費を計上するなどの不正行為を行うことがあります。
税務調査を通じて、不正を未然に防ぐとともに、不適切な処理が発覚した場合には是正を求める役割を担っています。
税制の公平性を保つため
適切な納税をしている企業・事業主と、不正を行っている事業者の間に不公平が生じないよう、公正な税負担を確保することも税務調査の目的のひとつです。
すべての納税者が適正に申告・納税を行うことで、健全な税制が維持されます。
税務調査の種類
税務調査には、大きく分けて「任意調査」と「強制調査(犯則調査)」の2種類があります。
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
任意調査
任意調査とは、税務署の職員が企業や個人事業主を訪問し、申告内容の確認を行う調査のことです。
一般的に事前に通知があり、2日程度かけて帳簿や領収書などの書類が調査されます。
「任意」という名称ですが、調査対象となった場合、正当な理由なく拒否することはできません。
また、通常は事前に連絡がありますが、特定の事情がある場合は「無予告調査」として、突然調査が行われることもあります。
無予告調査は、帳簿書類の隠蔽や改ざんが疑われるケースや、国税通則法74条の10に該当する状況にて実施されるため、事前に税務リスクを管理しておくことが重要です。
強制調査(犯則調査)
強制調査とは、国税局の査察部が裁判所の令状を取得し、事前通知なしで実施する調査です。
これは、主に巨額の脱税や悪質な不正が疑われるケースに適用され、納税者が調査を拒否することはできません。
立件を目的とした犯罪捜査の一環であり、調査対象となった場合、刑事罰を受ける可能性もあります。
一般的な企業や個人事業主は「任意調査」の対象となることがほとんどですが、調査の種類によって対応の仕方が変わるため、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。
税務調査の流れ
一般的な税務調査(任意調査)は、以下の流れで進行します。
1.税務署からの事前通知
2.調査実施日の日程調整
3.必要書類の準備
4.調査当日の対応
5.調査結果の通知と対応
1.税務署からの事前通知
調査の実施が決まると、税務署から企業または顧問税理士に電話で事前通知が入ります。
通知は義務ではありませんが、通常は2~3週間前に連絡があるため、その間に必要な準備を進めることが可能です。
2.調査実施日の日程調整
事前通知を受けた後、調査実施日を税務署と調整します。
企業側の業務に支障が出ないよう、都合のよい日程を相談することができますが、長期間の延期は難しい場合があるため、早めに対応の準備を進めましょう。
3.必要書類の準備
調査当日に必要な帳簿や決算書、領収書などの書類を準備します。
顧問税理士がいる場合は、事前に相談し、過去の申告内容や会計処理に問題がないか確認しておくことが重要です。
4.調査当日の対応
調査当日は、税務調査官が会社や店舗、事務所を訪問し、帳簿の確認やヒアリングを行います。
多くの場合、2日間にわたって調査が行われ、経理担当者や経営者が質問に回答する形で進みます。
5.調査結果の通知と対応
調査終了後、税務署から指摘事項が通知されます。
何も問題がなければ「申告是認」となりますが、修正が必要な場合は「修正申告」や「更正処分」が行われることもあります。
納得がいかない場合は、不服申し立てや再調査の請求も可能です。
税務調査の対象になるケース
税務調査はすべての企業や個人事業主に対して毎年行われるわけではなく、特定の条件を満たす場合に実施されることが一般的です。
特に、税務署が「申告内容に問題がある可能性が高い」と判断した企業や個人事業主は、調査の対象になりやすい傾向があります。
ここでは、法人企業と個人事業主それぞれが税務調査の対象になりやすいケースについて解説します。
法人企業が税務調査の対象になりやすいケース
法人企業の中でも、特に以下のような特徴を持つ企業は税務調査が入りやすいとされています。
過去に税務調査で指摘を受けた企業
過去の税務調査で申告ミスや修正申告の指摘を受けた企業は、数年後に再び調査の対象になる可能性があります。
これは、前回の指摘事項が改善されているかを確認するためのフォローアップ調査が実施されることがあるためです。
特に、意図的な売上の過少申告や経費の水増しが疑われた場合、再調査のリスクが高まります。
売上の変動が大きい企業
急激に売上が増加または減少した企業は、税務署に不審を抱かれやすい傾向にあります。
特に、前年度と比較して売上が大幅に下がっている場合、「意図的に売上を少なく申告しているのではないか?」と疑われることがあります。
また、売上が増加しているにもかかわらず、利益がほとんど増えていない場合も、経費の不正計上や利益の圧縮を疑われる要因となります。
経費の割合が異常に高い企業
売上に対して経費の割合が極端に高い企業は、税務調査の対象になりやすいとされています。
例えば、同業他社と比較して人件費や交際費が異常に高い場合、不適切な経費計上が行われている可能性があると判断されることがあります。
特に、接待交際費や広告宣伝費など、支出の用途が不明確な項目が多い場合は、詳細な説明を求められる可能性が高いです。
現金取引が多い業種
現金取引が主流の業種(飲食業、美容業、小売業、パチンコ業界など)は、税務調査が入りやすいといわれています。
これは、現金売上の記録が不透明になりやすく、売上の一部を意図的に申告しない「売上除外」のリスクがあると判断されるためです。
業種ごとの平均的な売上・利益率のデータと比較して異常な数値が見られる企業は調査の対象になりやすくなります。
海外取引が多い企業
海外取引を行っている企業も税務調査の対象になりやすい傾向があります。
特に、海外の法人と取引をしている企業や、海外資産を保有している企業は、適正な申告が行われているかを厳しくチェックされることが多いです。
国際取引における税務のルールは複雑であり、移転価格税制やタックスヘイブン対策税制の適用を受けるケースもあるため、税務調査のリスクを意識しておく必要があります。
個人事業主が税務調査の対象になりやすいケース
法人企業だけでなく、個人事業主も税務調査の対象となることがあります。
特に、以下のような特徴を持つ個人事業主は、税務署から注目されやすい傾向があります。
確定申告をしていない
個人事業主は毎年確定申告を行う義務がありますが、申告を怠っている場合、税務署から指摘を受ける可能性があります。
税務署は、取引先企業の申告内容から売上の情報を把握できるため、「申告していない=所得隠し」と判断されることがあります。
確定申告をしていない場合、過去数年分の所得について調査が行われ、多額の追徴課税を課される可能性があるため注意が必要です。
売上が1,000万円に近い
消費税の課税事業者になる基準は、「2年前の年間売上が1,000万円を超えているかどうか」です。
そのため、売上が1,000万円にわずかに届かない個人事業主は、「意図的に売上を調整しているのでは?」と疑われ、税務調査の対象になることがあります。
インボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者を選択する個人事業主も増えており、売上の管理がより厳しくチェックされる傾向にあります。
経費が異常に多い
個人事業主は法人企業と比べて経費の自由度が高いですが、あまりにも経費が多すぎると、税務署から疑われる可能性があります。
特に、接待交際費や旅費交通費が異常に多い場合、プライベートの支出を事業経費として計上しているのではないかとチェックされることが多いです。
税務調査では、レシートや領収書の提示を求められるため、日頃から適切に管理しておくことが重要です。
現金取引が多い業種
個人事業主でも、飲食業や小売業、エステ・美容関係などの現金取引が多い業種は、税務調査が入りやすいといわれています。
これは、売上をごまかしやすい環境が整っていると判断されるためです。
現金売上の帳簿が適切に管理されているか、売上除外が行われていないかが重点的にチェックされるため、日々の記帳を正確に行うことが求められます。
副業で大きな収入を得ている
最近では、副業としてフリーランスや個人事業を行う人も増えていますが、副業収入がある人も税務調査の対象になりやすい傾向があります。
特に、会社員としての給与とは別に、YouTubeやブログ、アフィリエイト、転売などで一定の収入を得ている場合、確定申告の義務が発生します。
税務署は、プラットフォームを通じた収益情報を把握しており、申告漏れがないかを監視しているため、副業収入がある場合は適切に申告を行うことが重要です。
参考:副業で収入を得ている人は要注意!サラリーマンも税務調査の対象に
税務調査のチェックポイントリスト
税務調査では、調査官が企業や個人事業主の申告内容を確認し、誤りや不正がないかをチェックします。
特に、売上や経費の申告内容と実態の整合性が重視され、帳簿や領収書、決算書などを細かく調査されることが一般的です。
ここでは、税務調査で必ず確認される主要なチェックポイントについて解説します。
1.売上の申告内容と実態の差異
2.経費の計上
3.領収書・請求書の適正管理
4.人件費・給与の処理
5.交際費・接待費の妥当性
6.仕入れ・棚卸資産の整合性
7.消費税の計算ミス・未納のチェック
8.海外取引・海外送金に関する注意点
1.売上の申告内容と実態の差異
売上の申告内容に誤りがあると、税務調査で大きな指摘を受ける可能性が高くなります。
特に、以下のようなポイントが重点的に確認されます。
売上の計上漏れ
売上を意図的に申告から除外していないかを確認されます。
取引先の申告内容と比較され、売上の相違がないかチェックされることが一般的です。
預金通帳や請求書と照合し、帳簿上の売上と実際の入金額が一致しているかが調査されます。
売上の期ズレ
売上を翌期にずらして計上することで、税負担を軽減しようとする行為が疑われる場合があります。
例えば、3月決算の会社が3月に引き渡した売上を4月の売上に計上していないかを調査されます。
調査官は納品書や検収書の確認を行い、売上計上の時期が適切かどうかを精査します。
2.経費の計上
経費が適切に計上されていなければ、不正な申告と見なされることがあります。
以下のポイントが税務調査で特に注目されます。
経費が売上に対して異常に多くないか
売上に対して異常に経費が多い場合、過大な経費計上が疑われます。
特に、交際費、広告費、業務委託費などが過大になっていないかが調査されます。
架空経費の計上
実際には発生していない経費を計上していないかを確認されます。
外部取引先との契約書や請求書を精査され、取引の実態があるかどうかをチェックされます。
3.領収書・請求書の適正管理
領収書や請求書の管理が適正でないと、税務調査で問題視される可能性があります。
特に、以下の点が確認されます。
領収書の不備
相手先の名称や年月日が記載されていない領収書は、経費として認められないことがあります。
自分で追加記入するのではなく、発行者に正式な記載を依頼することが推奨されます。
領収書の頻度と金額
特定の取引先や店舗の領収書が異常に多い場合、不正計上の可能性が疑われます。
交際費や接待費として計上されている場合、業務との関連性が説明できることが求められます。
4.人件費・給与の処理
給与や役員報酬の処理は税務調査で特に厳しくチェックされるポイントです。
以下の点が重点的に確認されます。
架空の人件費が計上されていないか
実際には勤務していない従業員への給与支払いがないかを調査されます。
社会保険料の支払い状況や賃金台帳を確認し、従業員の実態をチェックします。
役員報酬が過大でないか
役員報酬が事業規模に対して異常に高い場合、不当な利益操作と見なされることがあります。
役員報酬の金額決定の経緯を説明できるようにしておくことが重要です。
5.交際費・接待費の妥当性
交際費や接待費は、業務との関連性が明確でなければ経費として認められないことがあります。
以下の点が重点的に確認されます。
交際費の対象者
交際費が本当に取引先との業務上のものか、個人的な支出が含まれていないかをチェックされます。
実際に交際費を使った相手の記録を残しておくことが推奨されます。
領収書の内容
領収書に記載されている内容が業務と無関係でないかを調査されます。
交際費の支出が特定の業者に偏っていないかが確認されます。
6.仕入れ・棚卸資産の整合性
仕入れや棚卸資産の計上が適切でなければ、税務調査で指摘を受ける可能性があります。
仕入れの計上時期
仕入れた商品の計上時期が適正であるかをチェックされます。
実際には翌期に仕入れたものを当期に計上していないかが確認されます。
在庫の過少申告
期末在庫の金額を意図的に少なく申告することで、利益を圧縮していないかが調査されます。
棚卸表と実際の在庫数が一致しているかが確認されることが一般的です。
7.消費税の計算ミス・未納のチェック
消費税の申告内容に誤りがあると、税務調査で指摘される可能性が高くなります。
売上に対する消費税の申告漏れ
売上にかかる消費税が正しく申告されているかを確認されます。
消費税の計算に誤りがないか、控除の適用が適正かどうかがチェックされます。
仕入税額控除の適用
仕入税額控除を適用する際、適格請求書(インボイス)の管理が適正であるかを調査します。
必要書類の保存がされていない場合、仕入税額控除が認められないことがあります。
8.海外取引・海外送金に関する注意点
海外取引がある場合、税務調査では特に慎重にチェックされます。
海外取引の売上計上
海外からの売上が正しく申告されているかが調査されます。
国際取引における税務ルールに準拠しているかが確認されます。
海外送金の履歴
海外への送金が適正なものであるか、資金の流れが透明であるかを調査します。
タックスヘイブン対策税制の適用対象にならないかもチェックされます。
税務調査前に準備すべきことは?
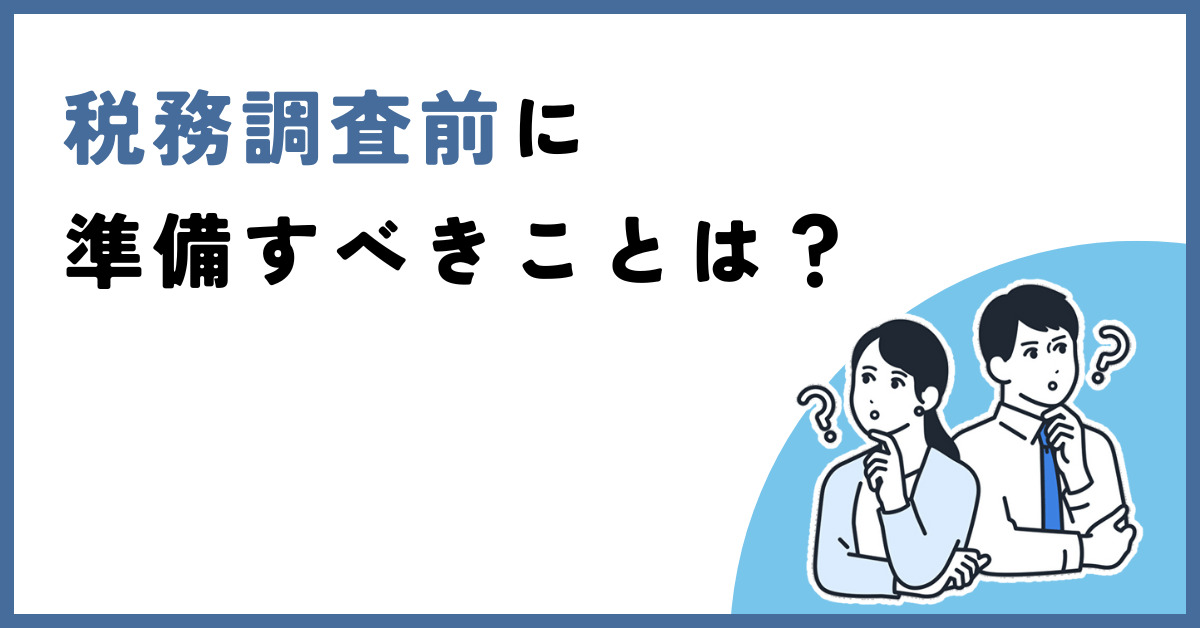
税務調査の通知を受けたら、事前準備をしっかり行うことで、スムーズな対応が可能になります。
調査当日に慌てないためにも、帳簿の整理や過去の決算内容の見直し、税理士との相談を徹底し、リスクを最小限に抑えましょう。
ここでは、税務調査前に準備すべき重要なポイントを解説します。
帳簿の整理と正確な記帳
税務調査では、帳簿が正しく整理されているか、記帳が適切に行われているかが厳しくチェックされます。
以下の準備をしておくことで、スムーズな調査対応が可能になります。
帳簿や関連書類の整理
- 直近3年〜5年分の帳簿を準備し、すぐに提示できる状態にする。
- 申告書、元帳、売上帳、仕入帳、経費帳、賃金台帳、固定資産台帳などを整理する。
- 預金通帳や契約書、請求書、領収書などの証憑書類も揃えておく。
記帳の正確性を確認
- 売上や経費の計上時期が適切かどうかをチェックする。
- 記帳ミスや記録漏れがないかを確認する。
- 帳簿と通帳の入出金が一致しているかを見直し、ズレがあれば修正する。
経費の適正管理
- 交際費、接待費、広告費、人件費など、税務調査で指摘されやすい経費を重点的にチェックする。
- 領収書の内容(取引先名、日付、金額、用途)を確認し、不備があれば補完する。
- 高額な経費については、事業との関連性を明確に説明できるよう準備する。
過去の決算内容の見直し
税務調査では、過去の決算内容が適切に処理されているかもチェックされます。
特に、利益や損益の計上、申告内容の整合性を見直すことが重要です。
申告内容の整合性チェック
- 申告書と決算書の内容に矛盾がないかを確認する。
- 売上や利益の変動が極端でないかをチェックする。
- 仕入れや売上の計上タイミングが適切かを見直し、期ズレがないかを確認する。
税務リスクの洗い出し
- 過去に税務調査を受けた場合、指摘事項が改善されているかをチェックする。
- 架空取引や過大な経費計上など、不適切な処理がないかを再確認する。
- 固定資産や棚卸資産の評価方法が適正かを見直し、不明点があれば税理士に相談する。
契約書や議事録の見直し
- 重要な取引の契約書が適切に保管されているかを確認する。
- 業務委託契約や賃貸契約など、契約の内容が妥当であるか確認する。
- 役員報酬の決定プロセスが議事録に明記されているかをチェックする。
顧問税理士との事前相談
税務調査に対応する際、税理士のサポートを受けることで、スムーズに対応できます。
調査当日に慌てないためにも、事前に税理士と相談し、必要な準備を整えておきましょう。
税理士との打ち合わせ
- 税務調査の通知を受けたら、速やかに税理士と打ち合わせを実施する。
- 調査官の質問が予想されるポイントを整理し、適切な回答を準備する。
- 過去の申告内容を振り返り、リスクのある項目がないかを確認する。
必要書類の準備
- 税務調査で求められる書類(帳簿、通帳、契約書、領収書など)をリストアップする。
- 書類の不備がないかをチェックし、必要に応じて補完する。
- 調査官に預ける可能性のある書類は、事前にコピーを取っておく。
調査当日の対応方針を決める
- 調査当日の流れを確認し、税理士の立ち会いを依頼するか検討する。
- 税務調査官の質問に対する基本的な対応方針を決める。
- 即答できない質問には「後日回答」とするなど、無理に答えず冷静に対応することが重要です。
調査結果に問題があった場合の対処法
税務調査の結果、何らかの指摘を受けた場合は、適切に対応することが重要です。
誤った対応をすると、追加の税負担が増えたり、今後の調査リスクが高まる可能性があります。
ここでは、税務調査後に指摘を受けた場合の対応策や、ペナルティの回避方法、不服申し立ての手順について詳しく解説します。
指摘事項の対応
税務調査の結果は、主に以下の3つのパターンに分かれます。
それぞれの対応方法を理解し、適切な処理を行いましょう。
申告是認(問題なし)
申告是認とは、調査の結果、申告内容に問題がなかった場合に出される通知です。
この場合、追加の納税や修正申告は不要で、税務調査はこれで終了となります。
修正申告(申告内容に誤りがあった場合)
調査官から申告内容に誤りがあったと指摘された場合、修正申告を求められることがあります。
修正申告は義務ではありませんが、指摘事項に納得できる場合は、速やかに修正を行いましょう。
▼修正申告の流れ
1.調査官から指摘内容の説明を受ける。
2.必要に応じて税理士と相談し、対応方針を決定する。
3.修正申告書を作成し、税務署へ提出する。
4.追加の税金を納付する。
更正(税務署側が修正を決定)
納税者が修正申告に応じなかった場合、税務署が独自に計算し、修正後の税額を通知する「更正処分」が行われることがあります。
更正通知書が届いた場合、内容に納得できる場合はそのまま追加納税を行いますが、不服がある場合は異議申し立てが可能です。
罰則・ペナルティの回避策
税務調査の結果、追加の税金が発生する場合、一定のペナルティが科されることがあります。
以下のような税金が追徴される可能性があるため、早めに対策を講じましょう。
延滞税
延滞税とは、本来の納付期限を過ぎて納税した場合に発生する利息のような税金です。
遅れるほど金額が増えるため、早めの納付が重要です。
過少申告加算税
過少申告加算税は、申告内容に誤りがあり、本来よりも税額が少なかった場合に課せられる税金で、追加納税額の10%(50万円を超える部分は15%)が加算されます。
ただし、税務調査前に自主的に修正申告をすれば免除されます。
無申告加算税
無申告加算税は、期限内に申告しなかった場合に課されるペナルティです。
税務調査後の申告では50万円までの部分は15%、超える部分は20%、また自主的に期限後申告をすれば5%に軽減されます。
重加算税
重加算税は、売上の除外や架空経費計上などの悪質な隠蔽行為があった場合に課される税金です。
ペナルティは通常の加算税よりも重く、 35~40% の税率が適用されます。
不服申し立て・再調査請求の手順
税務署の指摘内容に納得がいかない場合、不服申し立てや再調査請求が可能です。
以下の手順で適切に対応しましょう。
調査官との協議
まずは、調査官と話し合いを行い、指摘事項について詳細な説明を求めます。
場合によっては、証拠を提示することで指摘を撤回してもらえる可能性もあります。
再調査請求(税務署への異議申し立て)
調査結果に不服がある場合、 更正通知を受け取った日から60日以内 に税務署へ異議申し立てを行うことができます。
税務署内部で再審査が行われますが、納税者側が有利な判断になる可能性は低い傾向にあります。
国税不服審判所への審査請求
税務署での再調査に納得できない場合、決定通知から1ヶ月以内に国税不服審判所へ審査請求を行うことができます。
こちらは税務署とは異なる第三者機関が審査を行うため、判断が覆る可能性が高いとされています。
裁判(行政訴訟)
国税不服審判所での判断にも納得できない場合、裁判所へ訴訟を提起することが可能です。
ただし、訴訟には多額の費用と時間がかかるため、税理士や弁護士と相談し慎重に判断する必要があります。
税務調査に備えた日常的な対策
税務調査は、すべての事業者に対して必ず実施されるものではありません。
しかし、申告内容に不備があると、調査の対象となる可能性が高まります。
適切な対策を日常的に行うことで、税務調査のリスクを軽減し、万が一の調査に対してもスムーズに対応できる環境を整えることができます。
ここでは、税務調査に備えた対策として、「定期的な帳簿の整理」と「専門家との連携」について解説します。
定期的な帳簿の整理
帳簿の整理を定期的に行うことは、税務調査のリスクを減らすうえで欠かせません。
決算時だけでなく、毎月の収支を確認し、記帳ミスや申告漏れを未然に防ぐことが重要です。
特に、会計ソフトやクラウド型の会計サービスを活用すれば、記帳の手間を削減し、リアルタイムで財務状況を把握することができます。
さらに、売上や仕入れ、在庫データを一元管理できるため、整合性の取れた正確な帳簿を維持しやすくなります。
また、電子帳簿保存法の改正やインボイス制度にも対応した最新の会計ツールを導入することで、税務リスクを最小限に抑えられます。
手間のかかる記帳作業を効率化し、いつ税務調査が入っても慌てない万全の準備を整えましょう。
専門家(税理士・会計士)との連携を強化する
税務調査に適切に対応するためには、税理士や会計士との連携が重要です。
専門家のサポートを受けることで、申告ミスや税務リスクを未然に防ぐだけでなく、調査時の対応もスムーズに進めることができます。
決算時だけでなく、四半期ごとや月次で税理士に会計データを確認してもらうことで、記帳ミスや申告漏れを防ぐことが可能です。
また、税法は頻繁に改正されるため、最新のルールを把握し、適切な処理ができているか専門家にチェックしてもらうことも大切です。
さらに、自社の経理処理や申告内容にリスクがないか、税務調査で指摘されやすいポイントを定期的に見直すことで、より適正な会計管理が可能になります。
税務調査の通知を受けた際には、速やかに税理士に相談し、調査官の質問に対する適切な回答を準備することが重要です。
日頃から専門家と連携しておくことで、税務調査に備えた万全の体制を整えることができます。
まとめ
税務調査は、企業や個人事業主にとって避けられないものですが、適切な準備と対応を行うことで、その影響を最小限に抑えることが可能です。
調査官が重点的に確認するチェックポイントを押さえ、日頃から帳簿管理や経費の適正処理を徹底することが重要です。
また、税務リスクを減らし、調査への備えを万全にするためには、クラウド会計ソフトや税務ツールの活用も効果的です。
自動記帳やデータ管理の効率化により、正確な申告をサポートし、税務調査への対応力を高めることができます。
税務調査に備えた会計ソフト・ツールをチェックし、自社に最適なシステムを導入しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド
おすすめ資料 -
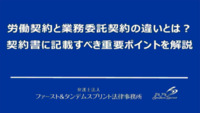
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -
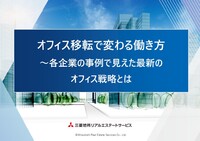
オフィス移転で変わる働き方
おすすめ資料 -

40年ぶりの労働基準法“大改正”はどうなる?議論中の見直しポイントと会社実務への影響を社労士が解説
ニュース -
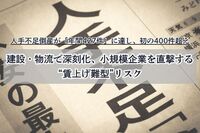
人手不足倒産が「年間427件」に達し、初の400件超え。建設・物流で深刻化、小規模企業を直撃する“賃上げ難型”リスク
ニュース -
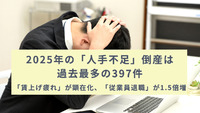
2025年の「人手不足」倒産は過去最多の397件 「賃上げ疲れ」が顕在化、「従業員退職」が1.5倍増
ニュース -

「組織サーベイ」の結果を組織開発に活かす進め方と方法論
ニュース -
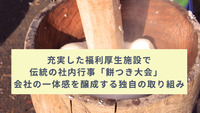
充実した福利厚生施設で伝統の社内行事「餅つき大会」 会社の一体感を醸成する独自の取り組み
ニュース -
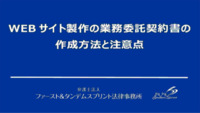
WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
おすすめ資料 -

生成AI時代の新しい職場環境づくり
おすすめ資料 -

1月の提出期限に間に合わせる!支払調書作成効率化の最適解とは?
おすすめ資料 -
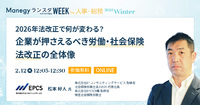
2026年法改正の全体像!労働・社会保険の実務対応を解説【セッション紹介】
ニュース -

「ディーセントワーク」の解像度を上げ、組織エンゲージメントを高めるには
ニュース -
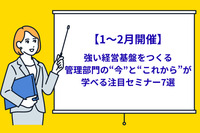
【1〜2月開催】強い経営基盤をつくる管理部門の“今”と“これから”が学べる注目セミナー7選
ニュース -
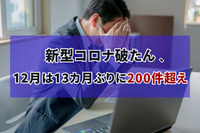
新型コロナ破たん、12月は13カ月ぶりに200件超え
ニュース -
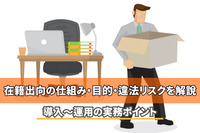
在籍出向の仕組み・目的・違法リスクを解説|導入〜運用の実務ポイント
ニュース