公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?
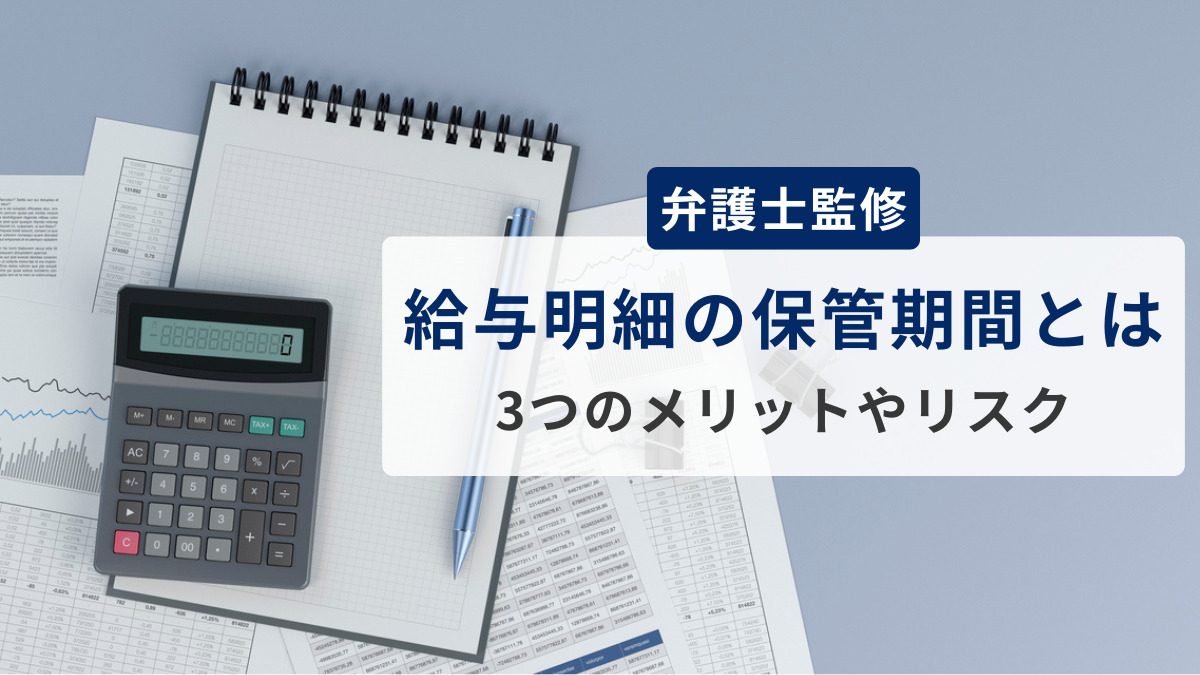
この記事を読んでわかること
給与明細の法的な保管義務はないが、望ましい保管期間はある
給与関連書類の保管期間
給与明細、給与関連書類の適切な保存方法
給与明細は、毎月の給与の詳細が記載された重要な書類です。従業員にとって、給与は生活の基盤であり、その明細は収入の証明となるだけでなく、税務申告や社会保険の手続きにも必要不可欠です。
実は企業に給与明細の法的な保管義務はありません。したがって遵守すべき保管期間もありませんが、給与関係書類には保管義務が定められているものがあるので注意が必要です。なお、法的義務はないとはいえ、適切な期間、給与明細を保管することは、従業員の権利を守り、トラブルを未然に防ぐために重要です。
この記事では、給与関係書類の法定保管期間や、給与明細を含む給与関係書類を保管することのメリットおよび適切な保管方法について詳しく解説します。
<関連記事>
【弁護士監修】企業の書類保管期間一覧!保存すべき書類とその保管方法
【弁護士監修】通帳の保管期間を徹底解説! 保管期間や安全な処分方法は?
【弁護士監修】納品書の保管期間は何年? 法的リスクと電子化のメリットについても解説
【弁護士監修】賃金台帳の保管期間と保存方法を徹底解説! 違反のリスクと電子化のポイント
【弁護士監修】決算書の保管期間と法令遵守の重要性|永久保存が望ましい社内文書も紹介
給与明細に法律で定められた保管期間はありませんが、給与関係書類の保管期間は、法律によって定められています。ここでは、労働基準法と国税通則法の規定に基づく給与関係書類の保管期間について説明します。
労働基準法では給与明細自体の保存期間を定めていませんが、関係書類である以下の書類に関しては、5年間の保管を義務付けています。(労働基準法109条)
・労働者名簿
・賃金台帳(従業員の給与の支払い状況を記載した書類)
・解雇に関する書類
・災害補償に関する書類
・賃金その他労働関係の書類
国税通則法では、国税の徴収権の消滅時効が定められています。その消滅時効までは、国税に係る給与関連書類も保管が必要であると解釈でき、その期間は最長で7年間です。国税に係る給与関連書類には、以下のようなものがあります。
記事提供元

株式会社LegalOnTechnologiesは、「法とテクノロジーの力で、安心して前進できる社会を創る。」をパーパスに掲げ、2017年に森・濱田松本法律事務所出身の弁護士2名によって創業されました。
法務知見と生成AIなどの最新のテクノロジーを組み合わせた企業法務の質の向上と効率化を実現するソフトウェアを開発・提供するグローバルカンパニーです。法務業務を全方位でカバーするAI法務プラットフォーム「LegalOn」を展開しています。
また米国にも拠点を置きグローバル向けのAI契約レビューサービス「LegalOnGlobal」を提供しています。
グローバルにおけるリーガルテックサービスの有償導入社数は 6,500社を突破しています。 (2024年12月末現在)
2025年1月から事業をコーポレート全域に広げAIカウンセル「CorporateOn」を提供開始しました。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

サーベイツールを徹底比較!

オフィスステーション導入事例集
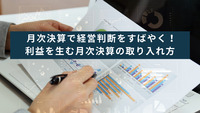
月次決算で経営判断をすばやく!利益を生む月次決算の取り入れ方

経理の予算管理とは?基本から予実管理・差異分析・ツール活用まで実務目線で解説

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識
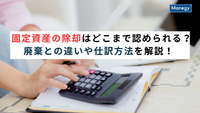
固定資産の除却はどこまで認められる?廃棄との違いや仕訳方法を解説!

バリューチェーン分析を戦略に活かす方法
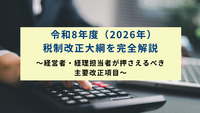
令和8年度(2026年)税制改正大綱を完全解説~経営者・経理担当者が押さえるべき主要改正項目~

与党が2/3超の議席を獲得!選挙を踏まえた今後の補助金・助成金の影響について中小企業診断士が分かりやすく解説
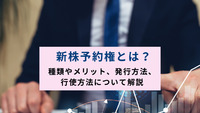
新株予約権とは?種類やメリット、発行方法、行使方法について解説
公開日 /-create_datetime-/