公開日 /-create_datetime-/

通勤中や業務中に従業員が交通事故に遭ったり、労災事故が発生してしまったりした場合、企業側は損害賠償責任をはじめとする様々な責任を負う可能性があります。被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士の視点から、企業側が負う責任とその対応策について解説します。

▼この記事を書いた人
小杉晴洋
弁護士法人小杉法律事務所
弁護士
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
公益財団法人日弁連交通事故相談センター研究研修委員会 青本編集部会所属。
交通事故をはじめとし、労災、学校事故など様々な不法行為に基づく損害賠償請求を専門としている。被害者側損害賠償請求専門弁護士として、数多くの判例誌掲載、執筆、講演などの実績がある。
交通事故や労災事故が発生した場合の企業の対応とは
交通事故・労災事故に必要な初動対応
交通事故や労災事故が発生した際には、速やかに被災従業員に医療機関の受診を勧めましょう。労災指定病院への受診を勧め、企業側からも病院に連絡しておくことで、被災従業員が初診から労災保険適用での療養を受けることが可能になります。
労災保険に関して、企業側は、以下の、労働者災害補償保険法施行規則第23条1項及び同条2項に定められている「事業主の助力等」を行う責任があります。
・労働者災害補償保険法施行規則第23条1項「保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。」
・同条2項「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。」
また、通勤災害ではない業務中の交通事故の場合では、「事業主の助力等」の他に、以下のとおり労働安全衛生規則第97条に定められている「労働者死傷病報告」を行う必要があります。
・労働安全衛生規則第97条「事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。」
この労働者死傷病報告については、被害従業員が死亡した場合や休業が4日以上になる(見込みがある)場合は速やかに、それ以外は四半期ごとに提出する必要があります。 このように、労災保険への支給請求書の作成について被災従業員にサポートをしながら、労働者死傷病報告の作成も進めなくてはなりません。
加えて従業員の休業が発生するような場合には、休業期間の最初の3日間(いわゆる待期期間)については、労災保険からではなく企業側から、平均賃金の60%を被災従業員に支払う必要があります。
労災事故が発生した場合に企業が問われる法的責任の範囲
労災事故については、まず企業側が発生の防止について労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を負っていることは言うまでもありません。そのうえで実際に労災事故が発生してしまった場合には、基本的には企業側は先ほどみたような「事業主の助力等」や「労働者死傷病報告」などの義務を負います。加えて、労働基準法第75条ないし第80条に定められているように、従業員に対して療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償・葬祭料補償などをしなければなりません。しかし、労災保険による給付が行われる場合には労働基準法上の責任を免れることができます。ところで、被害者側からみると、労災保険による給付のみでは発生した損害の全額を填補できないような場合があります。特に労災保険は慰謝料に相当するような、精神的苦痛に関する給付がないため、被害者側が損害賠償請求権を行使し、それにより企業側の賠償責任(民法415条の債務不履行責任:安全配慮義務違反が根拠となることが多いです。)が認められれば、労災保険による給付額を差し引いた金額を支払う責任が生じる場合があります。
企業側は労災保険利用を拒否できない?
企業側は通勤災害や業務災害が発生した場合には、被災従業員が適切な補償を受けられるよう様々な責任を負うことになります。
他方で、企業側としては労災事故の防止に十分な管理責任を果たしていたと考えられる場合や、当該災害の発生自体に疑義があるような場合には、企業側としては労災保険利用を拒否したい場合も考えられます。
とはいえ、労災事故の該当性や企業側の管理責任の遂行性、ひいては労災保険利用の適用可否を判断するのは労働基準監督署長であり企業ではありません。基本的には協力する、拒否する場合にはしっかりと書式を揃えて同規則第23条の2「事業主の意見申出」の手続を使うのが、企業側としてあるべき姿であるといえるでしょう。
lockこの記事は会員限定記事です(残り5949文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】
ニュース -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ
ニュース -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く
ニュース -

朱に交われば赤くなる!?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第1話】
ニュース -

面接日程調整の“理想”は「当日~翌日」も、実態は「1~5日」…採用現場のスピード対応に潜む課題とは
ニュース -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点
おすすめ資料 -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

ラフールサーベイ導入事例集
おすすめ資料 -

採用だけの人事経験は転職で不利?評価されるスキルとキャリアの広げ方を徹底解説(前編)
ニュース -
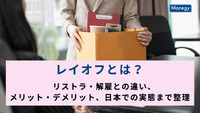
レイオフとは?リストラ・解雇との違い、メリット・デメリット、日本での実態まで整理
ニュース -
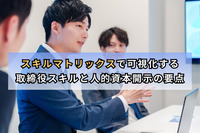
スキルマトリックスで可視化する取締役スキルと人的資本開示の要点
ニュース -

2025年の「早期・希望退職」 1万3,175人 2年連続で1万人超、「黒字リストラ」が定着
ニュース -

ケアの倫理から労働の倫理を問い直す②~法の精神が要求する新たな組織原理~
ニュース



































