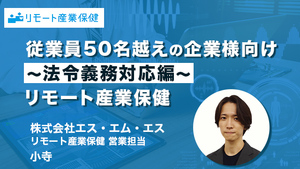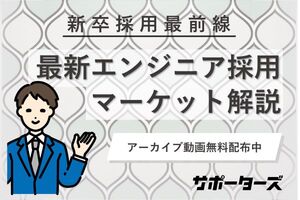公開日 /-create_datetime-/
知らなかったでは済まされない“海外リスク”から企業を守る!グローカリストの挑戦【株式会社Glocalist 代表取締役CEO 吉川 真実 氏】
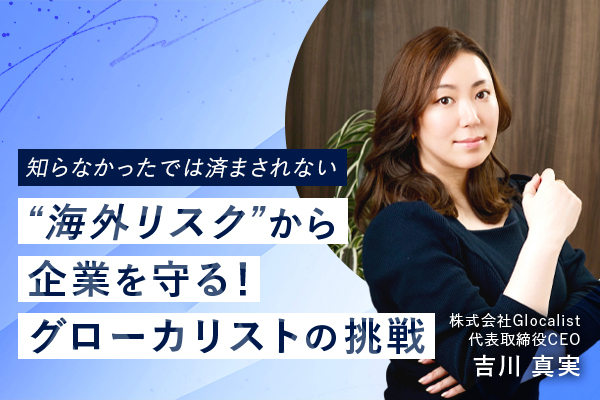
今回は、世界中の外部リスク情報を言語の壁を越え、誰でも簡単に「検知・共有・整理」し、組織の対応を促すことで、事業リスクを事業機会に転換するツール「Glocalist(グローカリスト)」を提供する株式会社Glocalistの代表取締役CEOである吉川真実氏にお話を伺いました。
海外駐在の実体験に基づき、グローバル展開する日系企業及び駐在員の課題解決への取り組みをご紹介します。
吉川 真実
株式会社Glocalist 代表取締役CEO
立命館大学を卒業後、株式会社リクルートに新卒入社。
グローバル市場への事業展開と駐在を経験。
その後、2013年にクロスボーダーマーケティング事業で起業。
アジアを中心に10か国に拠点・現地法人(JV)を立ち上げる。
2020年に自身の海外駐在とグローバル企業支援の経験を活かし、世界中の外部リスクへの対応と解決を支援する株式会社Glocalistを創業、代表取締役CEOに就任(現任)。
グローバルビジネスにおける地政学リスク・各国の政策・法規制リスク・経済安全保障リスクに代表されるような外部起因リスクに向き合い続けている。
――まず吉川さんのご経歴を教えてください。
中学・高校時代にオーストラリア留学を経験し、海外への興味が芽生え、大学時代にはバックパックでヨーロッパを巡り、自然とグローバルな視点が身につきました。
一方で、経営者経験のある両親の影響で、大学時代に学生起業にも挑戦しました。
当時、話題になっていた起業家や経営者を支援する番組の関連イベントにも参加していました。
残念ながら、学生起業はうまくいきませんでしたが、両親から将来的に起業するためにも一度、組織で働く経験を勧めてもらいリクルートに就職を決めました。
――前職ではどのような経験をしましたか?
前職では、最初にマーケティング関連の部署に配属されました。
当時はまだ紙媒体が中心の時代で、どこにどのように配置すれば多くの読者の手に取ってもらえるかを試行錯誤していました。
それと並行して、新卒採用の書類選考やグループディスカッションのファシリテーターなど選考の入り口部分にも携わっていました。
その後、営業に異動した際に海外での「現地採用」や「グローバル人材採用」といったテーマに触れ、その難しさを肌で感じました。
その経験を通じて、「グローバル人事の本質的な仕組みづくりが必要だ」と強く思うようになりました。
――実体験が現在の事業にも繋がっているんですね。
そうですね。
前職の海外事業を通じて、現地の状況を体感できたことが、今の事業につながったと思います。
たとえば、現地で日々情勢が変化し、それに伴って法律も変わります。
進出時点では問題なかったことが数か月後には制度変更でリスク要因になる、ということも珍しくありません。
いわゆる「カントリーリスク」や法改正への対応体制が整っていないと、事業継続そのものが脅かされると実感しました。
「誰が、いつ、何を調べ、どこに報告すればよいのか」すらわからないことも多々あります。
その時に一般的には、法律事務所のレポートを頼りにするのですが、どうしてもタイムラグがあって、それを待っていては間に合わないというケースもあります。
そのような中で、本社と海外現地子会社の間に立ち、両者を理解しながら橋渡しできる存在、すなわち“Glocalist(グローカリスト)”が必要不可欠だと強く実感するようになりました。
――まさに、実体験から生まれた「グローカリスト」という発想ですね。では、日系企業が海外で外的リスクの情報を収集しようとする際、一番の課題や苦労はどのようなところにあるとお考えですか?
一言でいうと、「現場で何が起きているのかが、本社に正確に伝わっていない」という“情報の非対称性”が一番の課題だと思います。
現地では法制度も文化も常に変化しているのに、本社が持っている情報は、進出を決めた当時のままだったりします。
しかも、「誰が情報を集めるのか」「誰に、どうやって報告するのか」というルートや責任分担も明確にされていないケースが多い。
大企業でも、そのあたりの仕組みがしっかり整備されていないと、リスクをモニタリングするどころか、そもそも現地で何がリスクかも把握できない、ということが起きるんです。
私自身も、現地で何が起きているかを把握しきれず、監査対応のたびに悩んだ経験があるからこそ、「このギャップを埋める仕組みが必要だ」と感じましたし、それが今のグローカリストの原点にもなっています。
――貴社が手がける「グローカリスト」は、現地法人運営における“情報の断絶”を埋める仕組みでもあると感じました。実体験として、どのような課題感があったのでしょうか?
たとえば、企業が海外に進出するタイミング―ジョイントベンチャーを提携したり、クロスボーダーM&Aで現地企業を買収したりという段階では、ものすごく入念に情報収集をされます。
それこそ、リスクや法令対応、人材確保など、あらゆる角度からチェックされるんですね。
でも、実際に「会社を買収しました」「現地法人が立ち上がりました」となった後の“日常のモニタリング”については、どうしても手薄になってしまうケースが多いように感じています。
現地法人の設立=ゴール、というような雰囲気が少なからずあって、お祝いムードで一息ついてしまう。
でも、むしろ本番はそこからなんですよね。
特に「何かが起きた時に気づけるか」という点は、大きな課題でした。
例えば、何か現地で法改正があったとしても、「たまたまこんな話聞いたけど、うちの会社は対応しなくていいの?」と言ってくれたことで、ようやく本社が把握するといったことがあります。
そんな、ある意味で運任せの情報伝達になっている企業も少なくありません。
日本人駐在員同士のつながりで、現地の日本人会や商工会、フットサルや野球などの社会人部活動を通じた飲み会で、「そういえばこの前、〇〇の法律が変わったらしい」といった情報を初めて耳にするケースも多くあります。

――日本国内と違って、現地では“情報にアクセスすること自体が難しい”という事情もあるわけですね。
そうなんです。
日本にいれば、官公庁の情報発信や各種メディア、士業の方々の解説などを通じて、「今、企業として対応すべきこと」が自然と耳に入ってくる仕組みがあります。
たとえば最近だと「電子帳簿保存法の対応は進んでいますか?」といった情報も、自動的に目や耳に入りますよね。
でも、海外ではそもそも言語の壁が大きくて、タイならタイ語、ベトナムならベトナム語で情報が発信されます。
ガイドラインの変更や新たな法規制が出ていたとしても、それを日本語や英語でキャッチできる環境にない企業がほとんどです。
つまり、自分たちが理解できる言語で、必要な現地情報に継続的にアクセスできる仕組みがないということが、日系企業の海外展開における最大の課題だと実感しました。
――お話を伺っていて、2つ印象に残ったことがあります。1つはやはり言語の壁。もう1つは、新興国や成長途中の国では、公的機関の情報発信体制が整っていない点です。
おっしゃる通りです。
特にASEAN諸国など、これからの成長が見込まれる国々では、法令やガイドラインが突然出てくることが多いんですが、それがタイ語やベトナム語で発表されるので、そもそも気づくことが非常に難しいんです。
しかも、それが事業に直結する内容であっても、大手メディアに掲載されるとは限りません。
たとえば「人材紹介業の免許ガイドラインが変更されました」といった話は、業界的にはニッチで、メディアが取り上げるにはやや小粒なんですよね。
現地法人の経営陣が「自ら気づく仕組み」を持っていないと、対応が遅れる可能性もあるわけですので、そこが一番の課題です。
しかも、そうした制度変更や法令は、管轄の省庁だけでなく、他の省庁から出てくることも多いんですよ。
だから、「自分たちの監督省庁だけを見ていればOK」というわけではない。
日本の本社であれば、人事部が労務領域を見て、法務部が契約やリスクを管理して、それぞれ専門部署が情報をキャッチしてくれます。
そして、必要があれば経営陣にアラートが上がってくる。
でも、現地法人だと、それらをすべて一人の日本人駐在員やマネージャーが担わなければならないんです。
私自身も「顧問弁護士との月1回の打ち合わせで十分な情報が得られているのか?」といったことも、最初の海外駐在の時は全くわかりませんでした。
でも、経営の現場にいれば、知らなかったでは済まされないリスクが数多く存在します。
だからこそ、言語の壁を超えて、本当に必要な情報にアクセスできる環境づくりが不可欠であり、それを支えるのが私たちグローカリストの使命だと思っています。
――「駐在員」というと一つの職種のような印象を受けますが、多様な機能を背負って現地に赴任しているんですね。
そうなんです。
「駐在員」は営業、事業企画、総務、コンプライアンス、会計・財務などマルチタスクが前提で派遣されています。
私自身は事業企画や営業として現地に入っていましたが、他にもコーポレート機能として行かれている方、コンプライアンスの観点から派遣されている方など、本当にさまざまです。
現地では、駐在員同士で「どういう職務で来られているんですか?」と確認し合うのが、会話の導入になるほどなんですよ。
多様性がある一方で、「現地の全てを一人で見る」状態になっていることも、負担の大きさにつながっています。
特に現地拠点では人員も限られているので、複数の機能を兼務しているケースがほとんどです。
日本本社からは、ボードメンバーの方々から戦略的な方向性の確認が求められたり、コーポレート部門からは経理・財務・法務・コンプラなどの問い合わせがあったり。
事業部側からも、生産拠点を持っている企業であれば品質保証や調達の観点でも相談が入ってきます。
各部門はそれぞれ「この話は誰に聞けばいいのか」と、現地の駐在員に忖度しながらボールを投げてくるといった状態が日常的に起きています。
そのため、現地の担当者は、毎月かなりの時間をかけて情報を整理し、報告書をまとめています。
たとえば政策の方向性、法律やガイドライン、為替や税法に関する情報など、本当に多岐にわたります。
私たち「Glocalist」では、そうした情報収集と可視化の部分をDXで支援することで、現地担当者の負担を減らし、企業として必要なリスクモニタリングを安定的に継続できる仕組みを提供しています。
――なるほど。グローカリストは「情報を収集し、翻訳し、継続的に届ける」ことによって、現地法人の実務を支え、日本本社との橋渡しになる存在なんですね。
まさにその立ち位置です。
とくに今は、グローバルERPの導入などで会計の国際基準化が進んでおり、会計・財務系の駐在員の方も増えてきています。
また、コンプライアンスやESGの観点でも、グローバルに対応する必要が出てきている。
そうした環境下で、「言語の壁」「情報源の断片化」「モニタリングの持続可能性」という3つの課題をテクノロジーで解決することが、私たちグローカリストの役割だと考えています。
やっぱり実際に現地で困った経験があったからこそ、「みんなが本当に困っていることって何だろう?」という視点が自然と育ちました。
たとえば、「この法令、どう報告しました?」「日本語訳って持っている?」みたいなやり取りを、駐在員同士でよくしていたんです。
そういう実感値があったからこそ、グローカリストは“現地法人が本当に必要としている情報”をどう届けるかという点にこだわってきました。
――グローカリストのような情報サービスは他にもいくつかありますが、御社ならではの強みや、追加で解決している課題があれば教えてください。
大きく2つあります。
ひとつはスピード感、もうひとつは網羅性です。
たとえば、法律事務所さんが「今月の法令まとめ」などを出してくださるケースもあるのですが、それって翌月になってようやく「先月こういう変更がありましたよ」とわかるという形なんですよね。
でも東南アジアでは、そうした“タイムラグ”が命取りになります。
現地では「まず法令を出して、あとから運用を決めよう」みたいな、スタートアップ的な行政運用が珍しくありません。
たとえば、ベトナムの人民委員会で今日承認された法令が、発令3日後から即適用されるということもあります。
つい先日も、1月2日に発令された法令が、1月10日から輸出入規制と関税の変更に適用される、というケースがありました。
しかもそれが医療品や衣料品などの物流・貿易に直結する内容だったんです。
医療関連の企業にとっては非常にクリティカルな変更で、もしその情報が月末の「まとめ」になっていたら、すでにコンテナが動いている状況なので、完全に手遅れになります。
“月次まとめ”では間に合わなくなる恐れがあります。
だからこそ、グローカリストでは、発令当日に情報を即キャッチし、必要に応じて企業に対策のアラートを届けるという仕組みを重視しています。
加えて、重大な影響が予想される場合には、関税局など現地当局にパブリックコメントを出す、「行政への働きかけ」まで含めたサポート体制を構築しています。
これらの動きは、単に情報を届けるだけではなく、“どう動けばいいか”まで踏み込んでサポートできるという意味でも、他の情報配信サービスやメディア翻訳とは一線を画すポイントだと思っています。
スピード感と網羅性の両立は、私が現場で「これがあれば助かったのに」と思ったリアルな経験から設計しています。
“法律が変わった”という事実だけでなく、「それがどの範囲で、どのように影響するのか?」までを正しく把握するには、連邦・州・市それぞれの発信をキャッチする仕組みが絶対に必要です。
そこを一元的に整理・配信していけるのが、グローカリストのもう一つの大きな強みだと思っています。
――グローカリストとして、これからどのような展開を考えていらっしゃいますか?
現在は、各国の法令や行政文書を自動で取得するクローラーを独自開発し、即時性を高めています。
これにより、「法令が発令された当日」に現地で何が起きているかを把握できる体制を整えています。
また今後は、生成AIの実装によって、ユーザーが必要とする情報を、自分で指定してレポート化できる機能も拡充していく予定です。
たとえば、建設業界で現場安全に関わる担当者が「直近の現場安全関連法の変更点」をピンポイントで抽出し、正確性の高いレポートとして即利用できるようになる仕組みです。
これは、従来のようにコンサル会社やシンクタンクに都度依頼する必要がなくなるという意味で、“情報の即時性”と“網羅性”に加えて、“個別最適性”という第三の価値を提供していくフェーズに入ったと考えています。
――最後に、Manegyの読者である管理部門の皆さまへメッセージをお願いします。
グローバルビジネスを展開する企業の中で、コーポレートに所属する方々、特に経理・財務・法務・コンプライアンスといった機能を担う皆さまには、日々「正確な判断」「タイムリーな対応」が求められているかと思います。
そして今、海外展開を進めていく中では、複数国・複数領域を横断的に見なければならない担当者が増えており、“人材リソースは限られているのに、情報負荷はどんどん高まっている”という構造的な問題が生じています。
私たちグローカリストは、まさにそうした状況にある皆さまの “気づきの早さ”と“判断の質”を支えるインフラでありたいと考えています。
また、同じ管理部門の中でも、国際担当と国内担当で“会話がなかなか交差しない”という声もよく伺います。
だからこそ、ぜひ一度、海外側の業務に関心を持って、部門内で対話を深めてみていただきたい。
企業の持続的な成長には、こうした“内部連携の横串”こそが、大きな推進力になるはずです。
――ありがとうございました。

Glocalist(グローカリスト) は、海外進出企業が直面するリスクを 検知・共有・整理・管理 するための グローバルマネジメントツール です。 政府機関や国際機関などから発信される情報をもとに、海外ビジネスに伴う多様なリスクを可視化・分析し、実務に活かせる形で一元管理できます。
サービス対応国は、ベトナム、インド、タイ、インドネシア、マレーシア。2025年9月1日より、新たにアメリカ、フィリピン、シンガポールの3カ国も加わりました。 今後もサービス対応国を順次拡大してまいります。


インタビュアー
清水 悠太(しみず ゆうた)/ 株式会社MS-Japan マーケティングDivision / 執行役員
ベンチャー・IPO準備企業を中心とした法人営業を経験した後、キャリアアドバイザーとしてCFO、管理部長、会計士、税理士、弁護士を中心に延べ5000名のキャリア支援を経験。
現在はマーケティングDivision長および執行役員として、マーケティングと新規事業・新規サービスの開発を担当。
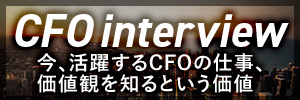
CFOインタビュー掲載ご希望の方は、下記フォームよりお問い合わせください。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-
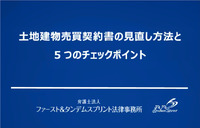
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -
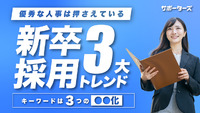
【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -
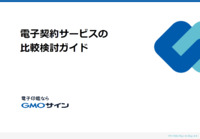
他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介
おすすめ資料 -

労働契約関係における権利と義務
ニュース -
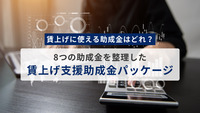
賃上げに使える助成金はどれ?8つの助成金を整理した「賃上げ支援助成金パッケージ」について中小企業診断士が分かりやすく解説
ニュース -
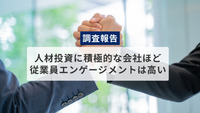
<調査報告>人材投資に積極的な会社ほど従業員エンゲージメントは高い
ニュース -

業績マネジメントとは?概略と実行ステップを解説
ニュース -
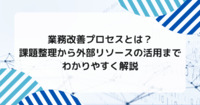
業務改善プロセスとは?課題整理から外部リソースの活用までわかりやすく解説
ニュース -

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料
おすすめ資料 -
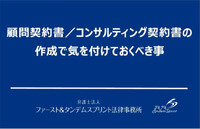
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -
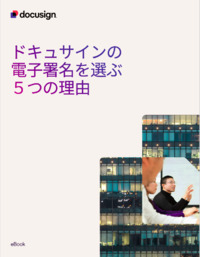
2,000人の経営幹部に聞く!電子署名導入のメリットと懸念点を徹底解剖
おすすめ資料 -

Docusign CLM 導入事例(ウーブン・バイ・トヨタ株式会社)
おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集
おすすめ資料 -

約40年ぶり「労働者性判断基準」見直しへ
ニュース -
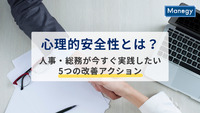
心理的安全性とは?人事・総務が今すぐ実践したい5つの改善アクション
ニュース -
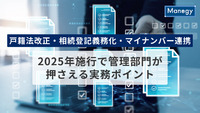
【司法書士執筆】戸籍法改正・相続登記義務化・マイナンバー連携|2025年施行で管理部門が押さえる実務ポイント
ニュース -
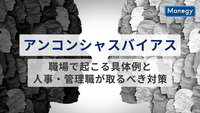
アンコンシャスバイアスとは?職場で起こる具体例と人事・管理職が取るべき対策
ニュース -

「噛むこと」が向上させるのは健康にとどまらない!? 脳科学者とロッテ社に聞いてみた
ニュース










 ポイントをGETしました
ポイントをGETしました