公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
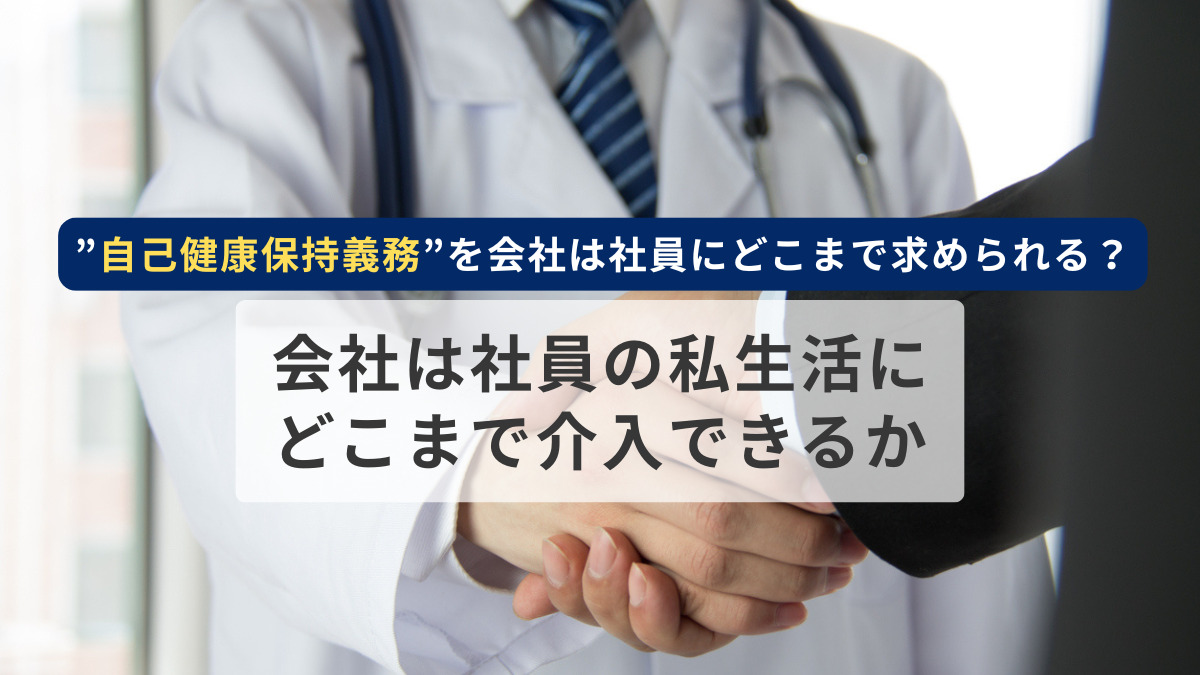
体調不良を繰り返したり、医療機関の受診を拒む社員に対し、会社はどこまで介入することができるのでしょうか。
仕事のパフォーマンスを損なわないよう社員に適切な体調管理を促すために、会社ができることを考えます。
「明らかに本人の不摂生が原因で体調を崩して業務に支障をきたす社員に対し、もっと自己管理するように注意することはできるでしょうか?」
人事担当者から、このような質問を受けることがあります。
会社には、社員が過重労働にならないように配慮したり、職場環境を良好に保つよう配慮する義務があります。
事故や労務トラブルが起これば、それを怠ったということで安全配慮義務違反に問われることもあります。
一方で、社員が明らかに二日酔いの状態であったり、不健康な食生活をしていたり、朝までゲームをしていて寝不足だったりと、会社として、本人の不摂生を指摘したくなるケースがあります。
「会社の対応に不備があった場合に会社の責任が問われるのはやむを得ないが、社員にも自己の健康はきちんと管理してもらいたい」というのが、多くの人事担当者の率直な意見でしょう。
これは、法律上も、もっともな意見です。
社員には雇用契約上、自己の健康を保持する義務があり(これは本稿では「自己健康保持義務」といいます)、その不履行により業務に支障が生じている場合には、会社が必要な範囲で私生活に言及することができると考えます。
しかし、そもそも自己健康保持義務がどのようなものか、また自己健康保持義務を尽くしてもらうために会社がどこまで介入できるかについて理解し、労使双方が共通認識を持っていないと、トラブルに発展しかねません。
そこで以下では、自己健康保持義務がどのようなもので、実務上どのような点に注意しなければならないかを解説します。
※続きは以下からご確認ください
記事提供元
『企業実務』は、経理・総務・労務で直面する課題を解決できる記事を凝縮した月刊誌。税制改正・新法令への対応・社会保険事務など、具体的な処理方法を毎月お届けしています。
またWebサービス『企業実務サポートクラブ』では、実践的なセミナー開催・専門家へのネット相談窓口・社内規程の文例ダウンロードなどを設け、実務担当者を強力にサポートしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?

「ピアコーチング」で横のつながりを強め、組織パフォーマンスに結びつけていく方法とは

会社の存在理由から、法人の税金ルールを理解しよう

【2月の季節(時候)の挨拶】言葉に趣が出るビジネスシーンでの表現・例文まとめ

「エンゲージメント」と「コミットメント」の対立構造〜組織の成長に必要なのは「義務」か「自発性」か〜

PPAP廃止後のロードマップ|取引先と揉めない安全な移行手順

英文契約書のリーガルチェックについて

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
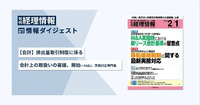
旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト②/会計

2026年1月施行「取適法」法改正に伴う「対応が必要な契約」を即座に把握できる人はわずか1割

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】

お金の流れと損益が一致しない『減価償却費』を理解しよう

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート
公開日 /-create_datetime-/