公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

自己健康保持義務とは少し異なりますが、労働者が疾病等により労務提供できなくなった場合に、療養に専念する義務のことを「療養専念義務」といいます。
疾病が私傷病による場合、労働者は、雇用契約に基づく労務提供義務を自己の都合によりできない状況、すなわち労務提供義務の不履行の状態になっています(有給休暇その他の法律上認められた休暇を取得するときは別です)。
このような状況において、会社が休職命令を発令するなどして、一定期間の療養を認めるようなケースでは、労働者においては、療養に専念することでなるべく早く回復して復帰することが求められます。したがって、労働者は、休職期間中に、疾病が悪化したり、回復に反するような行動をしないことが求められます。
しかし、会社側の対応として注意が必要なのは、メンタル疾患等の場合、日常生活を問題なく送れる日があったり、日常生活を問題なく送れるようにするためのリハビリをしていたりすることです。 外形的には仕事をしないで遊んでいるようにみえ、会社側が誤解してしまうケースがあります。
実際に私傷病休職中の行動について、療養専念義務に違反したかどうかが問題となった事案(マガジンハウス事件・東京地判平成20年3月10日)で裁判所は、「私傷病欠勤期間中に、オートバイで頻繁に外出していたこと、ゲームセンターや場外馬券売場に出かけていたこと、飲酒や会合への出席を行なっていたこと、宿泊を伴う旅行などをしていたことを療養専念義務に反する行為であると主張するが、うつ病や不安障害といった病気の性質上、健常人と同様の日常生活を送ることは不可能ではないばかりか、これが療養に資することもあると考えられていることは広く知られていることや、原告が、連日のように飲酒などを行ない、これが原告のうつ病や不安障害に影響を及ぼしたとまで認めるに足りる証拠もないことからすれば、原告の上記行動を特段問題視することはできないというほかない」と判断しており、療養中の行動については、それが療養に反するかどうかを医師の意見も聞きながら慎重に判断することが求められます。
* * *
自己健康保持義務の問題は、当該労働者の労務提供の状態が、本来予定されている正しい労務提供と言えるか、また業務遂行にどのような影響、支障を与えているかという観点から捉えることが重要です。
個別の私生活の行動を批判するのではなく、「あくまで私生活は自由であるが、結果として、労務提供に影響が出ているとなると会社としては困るし、そこは介入せざるを得ない」というスタンスで注意指導をしていくことが求められます。
記事提供元
『企業実務』は、経理・総務・労務で直面する課題を解決できる記事を凝縮した月刊誌。税制改正・新法令への対応・社会保険事務など、具体的な処理方法を毎月お届けしています。
またWebサービス『企業実務サポートクラブ』では、実践的なセミナー開催・専門家へのネット相談窓口・社内規程の文例ダウンロードなどを設け、実務担当者を強力にサポートしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

管理部門兼任の社長が行うべき本業にフォーカスする環境の構築

英文契約書のリーガルチェックについて

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

サーベイツールを徹底比較!

「エンゲージメント」と「コミットメント」の対立構造〜組織の成長に必要なのは「義務」か「自発性」か〜

PPAP廃止後のロードマップ|取引先と揉めない安全な移行手順
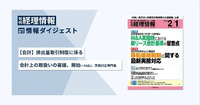
旬刊『経理情報』2026年2月1日号(通巻No.1766)情報ダイジェスト②/会計

2026年1月施行「取適法」法改正に伴う「対応が必要な契約」を即座に把握できる人はわずか1割

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

お金の流れと損益が一致しない『減価償却費』を理解しよう

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ

労働保険料の勘定科目を完全解説|仕訳処理と経費計上の正しい考え方
公開日 /-create_datetime-/