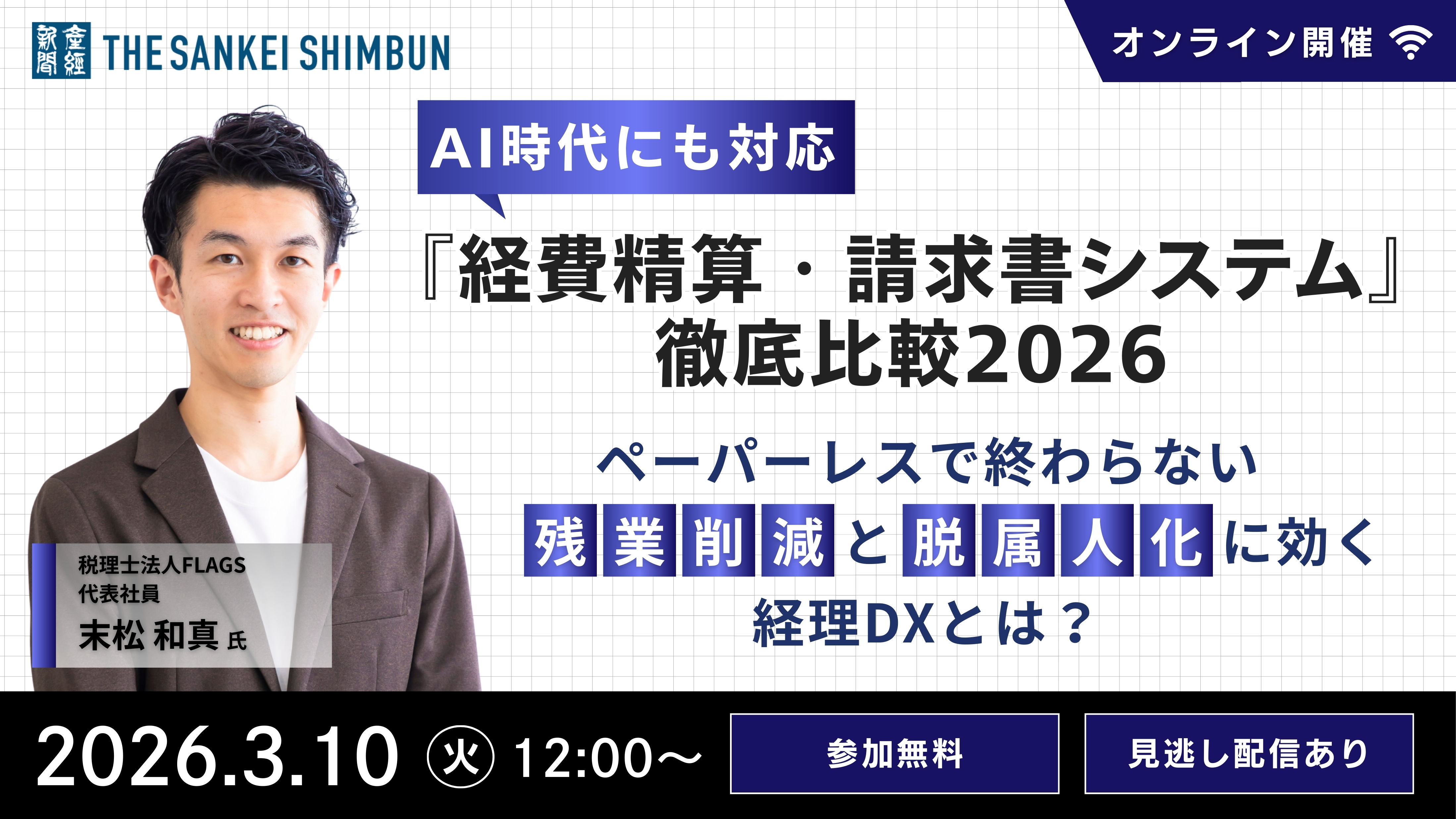公開日 /-create_datetime-/
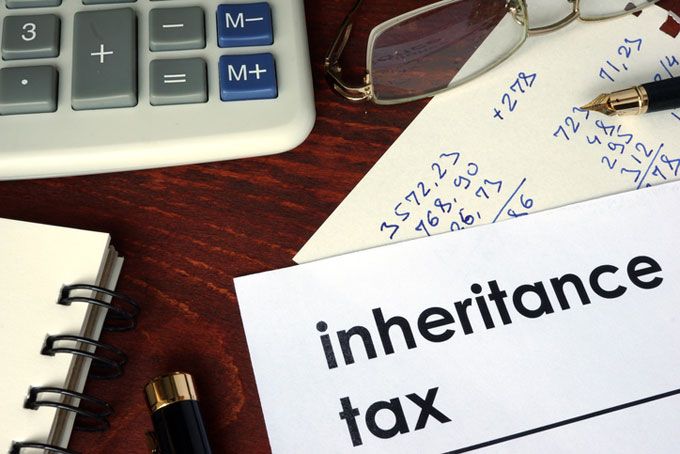
平成27年より相続税の基礎控除額が「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」から「3,000万円+法定相続人の数×600万円」に引き下げられました。
基礎控除額が減少したことにより、都内で不動産をお持ちの方など、これまでよりも多くの方が相続税申告の対象となると言われ、実際に東京国税局管轄では、亡くなった方全体に対して相続税の申告をされた方の割合が6-7%であったものが、平成27年度の相続税の申告分より12%後半に跳ね上がりました。
新聞や雑誌などで取り上げられていたことから、相続対策をお考えになった方も、多くいらっしゃることでしょう。
「相続対策」と聞いたとき、真っ先に浮かぶのは「相続税を減らすこと」であると思います。
しかし、実際に相続が発生した場合に問題となるのは、相続税負担のことだけではありません。
遺族の間で遺産分割争いがおきて、まさに“争族”が巻き起こる可能性があります。
そこで今回は、「相続対策で重要な3つの対策」をまとめました。
相続対策で重要な3つの対策
◆対策1:遺産分割対策
遺産分割対策とは、誰にどの財産を引き継ぐか検討し準備する対策です。遺産の分割方法によっては相続税の金額にも影響が出てくるため最も重要な相続対策です。“争族”を避けるためにも、生前に意思をしっかりと残しておくことが大切です。
【対策例:遺言書の作成】
遺言書は、本人の意向を生前に残す重要な意思表示の手段であり、原則として法律で定められている規定よりも優先されます。法定の相続人や相続割合以外での相続を望む場合は、遺言書を作成しておきましょう。また、遺言書があれば遺産分割協議が不要になり、迅速に相続手続きを進めることができます。遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
◆対策2:相続税節税対策
相続税額の負担を少なくする対策です。相続税は遺産総額をもとに計算しますので、遺産の総額を少なくする対策を行え
ば相続税額も少なくなります。生前贈与により無税又は相続税の税負担率をより少ない税負担率で財産を移動させる方法や、預金を不動産にかえるなどで相続税上の評価額を下げる方法などにより、結果として相続税の負担を軽減させることができます。
【遺産総額を少なくする対策例:生前贈与】
個人間で贈与があった場合、贈与を受けた者(以下「受贈者」といいます)に贈与税がかかりますが、受贈者1人につき年110万円の基礎控除までは課税されません。この基礎控除は、孫5人にそれぞれ100万円ずつ贈与するなどの人数を多くしての活用や、贈与を毎年継続的に長期間にわたって行うなど年数を多くしての活用が効果的です。
この暦年贈与の基礎控除をうまく活用して財産を次世代に引き継いでいきましょう。
【非課税制度を活用する対策例:生命保険の活用】
生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額は、相続税がかかりません。現預金を生命保険金に換えるだけでも相続税額の減少が期待できます。また、生命保険金は受取人独自の財産であり、遺産分割協議の対象にならないため、
任意の受取人を指定しておくことで遺産分割対策としても活用できます。
◆対策3:納税資金対策
相続税は「現金一括納付」が原則です。遺産のうちに不動産の割合が多い場合や自社株式(非上場株式)の評価が高い場合、
相続税が多額になりますが、簡単に換金できず納税資金が足りなくなる恐れがあります。
自社株式の評価や相続税シミュレーションを行い、将来どのくらい納税が発生するか事前に把握し、相続税の納税資金を手当てしておくことが重要です。納税資金対策としては、生命保険の活用、経営者であれば死亡退職金等の設定等が考えられます。
なお、以下の資料もあわせてご参照ください。
◆アクタスWebサイト『Actus Newsletter』(「相続対策で重要な3つの対策」)
記事提供元
アクタス税理士法人
アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名
で構成する会計事務所グループです。中核となるアクタス税理士法人では、税務申告、国際税務、相続税申告など専門性の高い税務コンサルを提供しています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略
おすすめ資料 -

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
おすすめ資料 -

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
ニュース -

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説
ニュース -

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識
ニュース -

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下
ニュース -

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―
ニュース -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
おすすめ資料 -

フリーアドレスの成功事例 ご紹介
おすすめ資料 -

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!
ニュース -
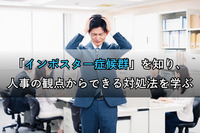
「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ
ニュース -

過重労働の判断基準と健康リスクを徹底解説 ─ 厚労省ガイドラインで学ぶ企業の防止策
ニュース -
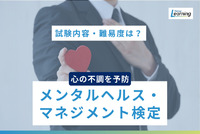
メンタルヘルス・マネジメント検定試験は社会人に役立つ資格?試験の内容や難易度は?
ニュース -

6割の総務が福利厚生と従業員ニーズのギャップを実感するも、3割超が見直し未実施
ニュース