公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
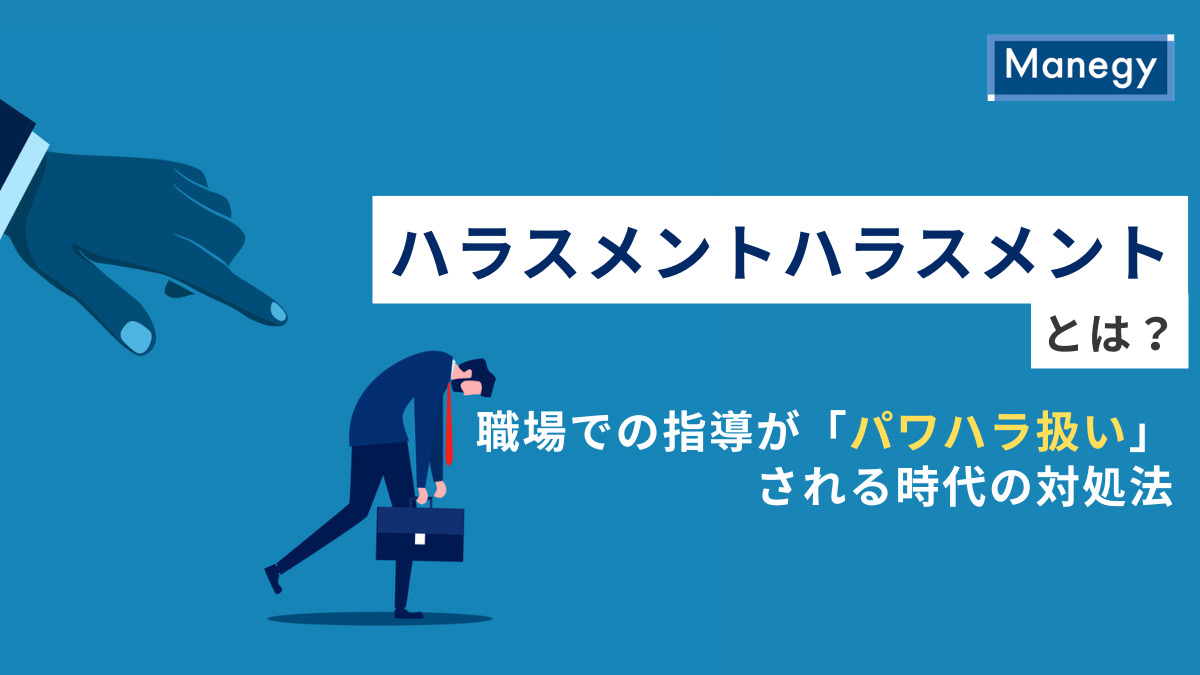
近年、職場でのハラスメント防止対策が強化される中、新たな問題として「ハラスメントハラスメント」(通称:ハラハラ)が注目されています。
この現象は、本来適切である業務上の指導や注意までもがハラスメントとして過剰に主張される状況を指し、企業の人事労務担当者にとって重要な課題となっています。
本記事では、ハラスメントハラスメントの実態と企業の人事労務担当が講じることができる対策について詳しく解説します。
ハラスメントハラスメント(ハラハラ) とは、適切な業務上の指導やコミュニケーションが、受け手によって過度に「ハラスメント」と主張される現象を指します。
上司の正当な指導などが、根拠なくハラスメントとして扱われるケースです。
これは、ハラスメント防止意識の高まりと共に、概念の誤解や拡大解釈から生じています。
一方、ハラスメントハラスメントは、ハラスメント行為が存在しないにもかかわらず、適切な指導がハラスメントとして過剰に主張される行為を指します。
あわせて読みたい
ハラスメントハラスメントが注目される背景には、労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)があります。
これによりハラスメント防止対策が浸透しましたが、一方でハラスメントの定義や範囲への理解不足、インターネット上の情報過多により、概念が拡大解釈される傾向が見られます。
その結果、本来適切な指導がハラスメントと扱われる事例が増加し、この言葉が広まりました。
ハラスメントハラスメントが問題視される最大の理由は、適切な業務指導や管理行為が萎縮してしまうことです。
パワハラ防止策の浸透により、上司や管理職は「パワハラと言われるのでは」と不安を感じ、必要な指導をためらうようになりました。
これにより、従業員の成長機会や組織の生産性向上が阻害されるケースが発生し、真面目な管理職にとって、ある種の"逆差別"が生じているとも言えます。
こうした状況は、管理職の萎縮と職場全体のコミュニケーション停滞を招いています。
管理職は「ハラスメントと言われるかもしれない」という懸念から、必要な指導や注意をためらう傾向にあります。
さらに、部下のプライベートな悩みなどに対しても、過度な干渉を恐れ、以前のような気遣いができなくなっています。
結果として、職場全体のコミュニケーションの質が低下し、チームワークや信頼関係の構築が阻害されています。
ハラスメントハラスメントがどのような場面で起こるのか、具体的な事例を見ていきましょう。
最も典型的な例は、業務上必要な注意や指導が「パワハラ」として扱われることです。
例えば、納期が遅れる部下へ上司が「もっと責任感を」と注意した場合、部下がこれを「高圧的なパワハラ」と主張するケースです。
業務目的があり、社会通念上適切な指導であっても、部下の不快感のみでハラスメントとされる可能性がある点が難しい点です。
人事評価や目標設定の場でも発生します。
上司が客観的に部下の成果を評価し、改善目標を設定しても、部下が「嫌がらせだ」「不当な評価だ」とパワハラを主張するケースです。
特に評価基準が不明確だと起こりやすいですが、企業として適切な評価や目標設定は不可欠です。
不当な主張で上司が萎縮し、適切な指導ができなくなるのは問題です。
職場の雑談や気遣いがハラスメントとされるケースも増えています。
例えば、上司が部下の体調を気遣って声をかけたり、趣味について雑談したりしたとします。
しかし、部下がこれを「プライベートへの過剰な干渉」「セクハラ」と主張し、不快感を訴える可能性があります。
善意の行為でも、相手が不快に感じればハラスメントとされるリスクがあるのです。
このような深刻な影響を防ぐためには、企業として体系的な対策を講じることが不可欠です。
ここでは、実効性の高い防止策を5つ紹介します。
ハラスメントハラスメント防止には、まず組織内でハラスメントの定義と基準を明確化することが重要です。
労働施策総合推進法や厚生労働省指針に基づき、何がハラスメントで、何が適切な業務指導かを具体例と共に示したガイドラインを策定しましょう。
不当な申し立てについても明記し、対処法を整備することで、従業員の認識統一と誤解の軽減が期待できます。
管理職がパワハラと受け取られないための効果的な指導技法やコミュニケーションスキルを習得する研修を定期的に実施しましょう。
「アサーティブコミュニケーション」「フィードバックの仕方」「傾聴スキル」などを実践的に学ぶ場を設けることが有効です。
これにより、上司は自信を持って指導でき、部下も前向きに指導を受け入れやすくなります。
あわせて読みたい
全従業員に対し、ハラスメントに関する正しいリテラシー教育が重要です。
ハラスメントの定義だけでなく、「どのような行為がハラスメントで、何が業務上必要な指導か」を丁寧に解説します。
特に、ハラスメントハラスメントの概念と具体例も周知し、「不当な主張も問題になり得る」という認識を共有することで、安易な主張を抑制し、職場全体の認識レベル向上が期待できます。
あわせて読みたい
ハラスメントハラスメント発生時には、公平かつ迅速な相談窓口と調査フローの整備が不可欠です。
相談窓口は、ハラスメントを受けた側だけでなく、主張を受けて困っている上司や従業員も利用できるようにしましょう。
調査は双方の意見を聞き、客観的事実に基づき公正に判断することが求められます。
透明性を確保し、信頼を高めることにもつながります。
最終的な対策として、ハラスメントハラスメントに関する規定を就業規則に明記することも検討しましょう。
「ハラスメントに関する不当な主張や、正当な業務指導を妨げる行為は就業規則違反とみなす可能性がある」と盛り込むことで、企業としての毅然とした対応を示せます。
これにより、安易な主張の抑止力となり、健全な職場環境の維持に貢献します。
ただし、丁寧な説明と周知が必要です。
ここでは、ハラスメントハラスメントに関してよく寄せられる質問にお答えします。
「昔はこうだった」という発言がハラスメントかどうかは、内容と文脈で判断されます。
単に過去の経験を伝える場合は問題ありません。
しかし、「昔は残業代が出なかった」「もっと我慢強かった」など、現在の労働条件や価値観を否定したり、不適切な慣行を正当化したりする内容であれば、パワハラと受け取られる可能性があります。
発言の意図と相手への影響を考慮し、建設的なコミュニケーションを心がけましょう。
実際にハラスメント被害を受けている場合の相談先として、まず社内の相談窓口やコンプライアンス部門への相談が基本となります。
社内での解決が困難な場合や、会社が適切な対応を取らない場合は、外部の相談機関を利用することも重要です。
労働基準監督署では、労働者からの相談を受け付けており、必要に応じて会社への指導や調査を行います。
また、各都道府県労働局の総合労働相談コーナーでは、ハラスメントに関する相談を無料で受け付けています。
さらに、法的な対応が必要な場合は、労働問題に詳しい弁護士への相談も有効です。
ハラスメントハラスメント(ハラハラ)は、パワハラ防止法の施行により職場でのハラスメント意識が高まる中で発生した新たな問題です。
本来業務上必要な指導や注意が過度に「ハラスメント」として主張される現象で、管理職の萎縮や組織の統制力低下、従業員の成長機会の喪失といった深刻な悪影響をもたらしています。
この問題を解決するためには、企業が体系的な対策を講じることが不可欠です。
具体的には、ハラスメント基準の明確化とガイドライン制定、管理職向けの指導技法研修、全従業員へのリテラシー教育、公平な相談窓口の整備、就業規則への明記などが有効な防止策として挙げられます。
企業は労働施策総合推進法に基づくハラスメント防止義務と安全配慮義務の両立を図りながら、健全な職場環境を維持する必要があります。
適切な指導と過度な主張のバランスを保ち、従業員が安心して働ける環境づくりが今後の重要な課題となっています。
あわせて読みたい
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

退職支援で築く、持続可能な組織力-オフボーディングプログラムサービス資料

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
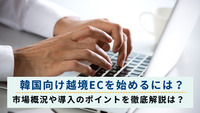
韓国向け越境ECを始めるには?市場概況や導入のポイントを徹底解説
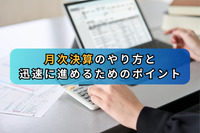
月次決算のやり方と迅速に進めるためのポイント

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】
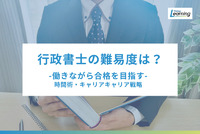
行政書士の難易度は「管理部門での実務経験」で変わる? 働きながら合格を目指す時間術とキャリア戦略

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。

今、何に貢献しますか?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第7話】
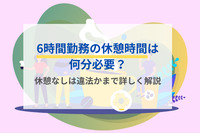
6時間勤務の休憩時間は何分必要?休憩なしは違法かまで詳しく解説

軽減税率導入で複雑化する請求書の消費税処理、経理担当者の手間を軽減するには?

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
公開日 /-create_datetime-/