公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
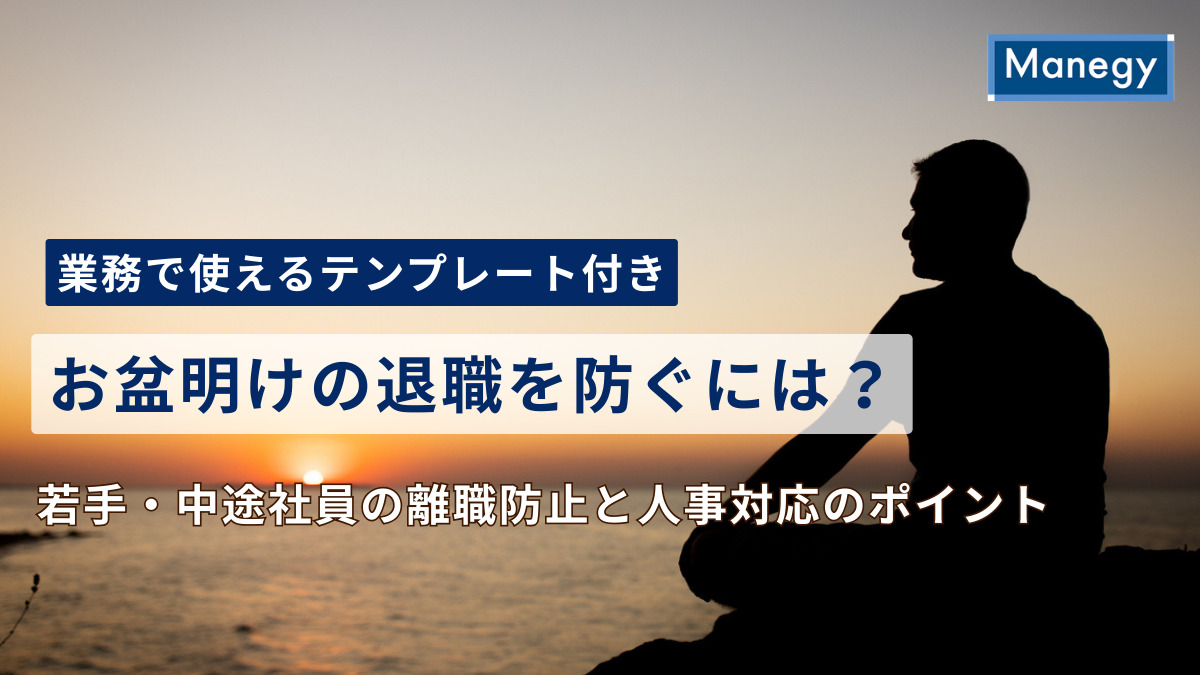
お盆休み明けに「退職の申し出」を受けた――そんな経験を持つ人事担当者は少なくありません。
実はお盆明けの時期は、若手社員や中途社員が離職を決意しやすい“心理的な節目”となっており、注意が必要です。
この記事では、お盆明けに退職リスクが高まる背景をふまえ、事前に把握しておきたい予兆サインや、面談・制度面での有効な対応策をご紹介します。
後半では、業務に使えるテンプレートもご紹介しますので、ぜひご活用ください。
お盆明けは、長期休暇によって心身が一度リセットされるタイミングです。
そのため、社員がこれまで感じていたモヤモヤや不満をあらためて見つめ直し、「このまま今の職場で働き続けるべきか」を静かに再考する機会になりやすい時期でもあります。
特に退職リスクが高まるのは、入社から半年〜1年未満の中途社員や、社会人歴が浅い若手社員です。
業務への慣れや人間関係がまだ構築途上であるこの層は、ちょっとした不安や不満が大きくなりやすく、会社との“ミスマッチ”を強く意識する傾向があります。
また、成果が見えにくい環境や、キャリアの方向性が不透明な場合、「今のうちに転職を考えたほうがいいのでは」という気持ちが芽生えやすいのもこの時期です。
さらに、繁忙期を目前にして負荷の大きさを事前に予感し、「このまま続けるのは難しい」と感じることもあります。
こうした社員の心理に寄り添い、変化の兆しを早めに察知することが、離職を防ぐ第一歩となります。
では、具体的にどのような制度設計や環境づくりが、社員の定着につながるのでしょうか。
次に、人事・労務が実務で取り組めるポイントを整理します。
退職を防ぐためには、個別対応だけでなく、職場全体の土台となる制度設計や環境づくりも欠かせません。
特に若手・中途社員が安心して働き続けられるよう、「不安の芽」を事前に摘み取る仕組みを整えておくことが重要です。
以下では、実務で取り入れやすい制度や職場づくりの工夫をご紹介します。
評価制度や昇格の基準が曖昧だと、社員は「このまま頑張っても報われないのでは」という不安を感じやすくなります。
職種ごとのキャリアステップや、求められるスキル・成果の水準を明示することで、社員は将来像を描きやすくなります。
定着支援の第一歩は「入社後の安心感」です。
など、孤立や不安を感じさせない仕組みが求められます。
日常的に「ちょっとしたこと」を相談できる雰囲気がある職場では、悩みが深刻化する前に対応できます。
Slackや社内チャットでの気軽な声かけ、定例の1on1、匿名の意見箱など、「声を上げやすい仕組み」を意識的に整備しましょう。
ライフステージや価値観に合わせて働き方を選べることは、離職防止につながる大きな要素です。
たとえば、以下のような制度が有効です。
若手や中途社員にとって「自分は成長している」と感じられるかどうかは、モチベーションに直結します。
定期的なスキル振り返りやキャリア面談、業務外の挑戦を後押しする研修制度・資格支援なども有効です。
お盆明けは、社員の心理や働き方を見直すタイミングであると同時に、人事からのアプローチで「離職」を防げるチャンスでもあります。
特に若手・中途社員には、安心感や将来への期待を持てるような丁寧なフォローが欠かせません。
お盆明けは、休暇を経て考えが変わる社員が多いため、「1〜2週間以内」のフォロー面談が有効です。
形式ばらず、気軽な1on1の場を設けることで本音を引き出しやすくなります。
お盆明けは、環境変化や疲労の蓄積から、メンタル面に不調をきたすケースもあります。
無理に引き留めるよりも、「味方である」と伝える姿勢が最も重要です。
引き留めや説得ではなく、「もう少しここでやってみよう」と社員本人に感じてもらう声かけが鍵です。
以下の3点を意識することで、対話の質が大きく変わります。
これらの声かけは、退職を思いとどまらせるだけでなく、社員が「ここでもう少し頑張ってみよう」と前向きに考えるきっかけになります。
とはいえ、すべての変化を感覚だけで見極めるのは難しいものです。
そこで、次に紹介するチェックリストを活用し、退職リスクの兆候を客観的に把握していきましょう。
「なんとなく様子が違うかも」と感じたときこそ、人事・労務の対応が問われる場面です。
以下のチェックリストを活用し、退職リスクの予兆を見逃さないようにしましょう。
| チェック項目 | 備考・具体的な様子 |
|---|---|
| 休み明け以降、表情が暗く笑顔が減っている | 「元気がない」「目が合わない」など |
| 突発的な有休・遅刻・早退が増えてきた | 明確な理由が不明なことも多い |
| デスク周りを整理している、私物が減っている | ロッカーや机がすっきりしすぎている |
| 雑談やチャットなど、社内コミュニケーションが減少した | Slackの既読のみ、返信が遅れるなど |
| 突然、資格取得や転職系セミナーに参加し始めた | 履歴書のブラッシュアップかも |
| 成果や貢献への不満がにじむ発言がある | 「どうせ評価されない」「やってもムダ」など |
| チェック項目 | 備考・具体的な様子 |
|---|---|
| 入社から半年~1年未満の若手・中途社員である | 定着前の“迷いの時期” |
| 評価面談などで期待とのギャップがあった | 昇給・昇格がなかった、伝え方に問題があった |
| 繁忙期や属人化した業務が続き、負担が偏っていた | 「自分ばかりが大変」と感じやすい |
| お盆中に家族・友人から転職を勧められた様子である | 実家での会話が決意の後押しに |
| 同期・前職の同僚が転職・昇進した話をしていた | 比較して「自分は…」と悩むケース |
| チェック項目 | 備考・具体的な様子 |
|---|---|
| 週報や日報の内容が簡素・機械的になってきた | 感情や主体性が感じられない |
| 面談時に「キャパが限界」と繰り返し発言している | 相談というより“限界のサイン” |
| 目を合わせず話を早く終わらせようとする | 関わりたくない心理が見える |
| チーム内の雑談・やり取りに参加しなくなった | 孤立化が進む |
| IT部門から転職サイトの閲覧などの報告があった | 社内PCでのアクセスなどから判明することも |
お盆明けは、社員の意識や感情に変化が起こりやすい時期です。
面談や1on1を実施する際には、単なる業務確認だけでなく、社員の本音を引き出す“安心できる対話”が欠かせません。
ここでは、社員の状態や不安、退職リスクを察知するために使える質問例をカテゴリ別に整理しました。
状況に応じてカスタマイズし、聞き方・タイミング・表情も意識しながら活用してください。
お盆明けは、社員がキャリアや働き方を見直すタイミングであり、離職リスクが高まる時期でもあります。
特に若手や中途社員は、評価や将来への不安を抱えやすく、ちょっとしたきっかけで退職を選ぶことも少なくありません。
人事・労務担当者は、退職の兆候を見逃さず、面談や制度面のフォローで早期対応を図ることが重要です。
本記事で紹介したチェックリストや質問テンプレートを活用し、社員との信頼関係を深めながら、定着率の向上につなげましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

オフィスステーション年末調整
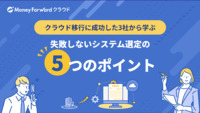
クラウド移行に成功した3社から学ぶ失敗しないシステム選定の5つのポイント

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

【1on1ミーティング】効果的な実践方法と運用時のポイント

【役員の死亡退職金と税金】課税対象額のシミュレーションと「規程がない」時の対応策について解説!
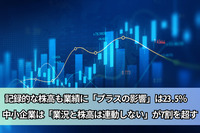
記録的な株高も業績に「プラスの影響」は23.5% 中小企業は「業況と株高は連動しない」が7割を超す
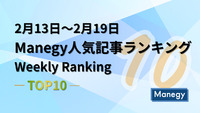
2月13日~2月19日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
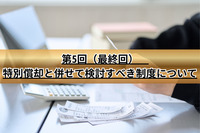
第5回(最終回) 特別償却と併せて検討すべき制度について
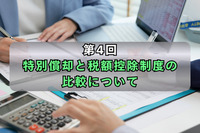
第4回 特別償却と税額控除制度の比較について

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

サーベイツールを徹底比較!

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

中小企業の12.2%が事業資金を個人名義で調達 保証債務に上乗せ負担、債務整理や廃業を複雑に

内部統制報告書の重要な不備・意見不表明とは|企業が押さえたいリスクと開示対応
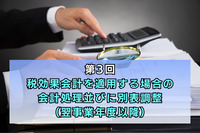
第3回 税効果会計を適用する場合の会計処理並びに別表調整(翌事業年度以降)
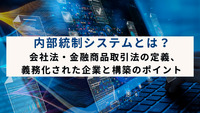
内部統制システムとは?会社法・金融商品取引法の定義、義務化された企業と構築のポイント

政策金利引き上げ 「1年は現状維持」が59.6% すでに「上昇」が52.0%、借入金利は上昇局面に
公開日 /-create_datetime-/