公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。

近年、職場におけるハラスメント問題は社会的にも大きな注目を集めています。
パワーハラスメント(パワハラ)やセクシュアルハラスメント(セクハラ)、マタニティハラスメント(マタハラ)など、その種類は多岐にわたり、被害の内容や程度もさまざまです。
厚生労働省の調査によると、過去3年間にパワハラを経験したことがあると回答した労働者は約30%に上ります。
これは働く人の三人に一人が何らかの形でハラスメントに直面していることを意味します。
こうした背景から、2020年6月に施行された「パワハラ防止法」(改正労働施策総合推進法)により、企業には職場におけるハラスメント防止措置を講じる義務が課せられました。
この義務の一環として、ハラスメント防止研修は従業員の意識改革と行動変容を促す有効な手段と位置づけられています。
単なる形式的な対応にとどまらず、組織の信頼性や生産性を守るための戦略的施策として、その重要性は年々高まっています。
研修の第一の目的は、全従業員がハラスメントに関する正しい知識を持つことです。
法律上、パワハラは「優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超え、就業環境を害するもの」と定義されていますが、現場では“指導”と“ハラスメント”の境界があいまいになりがちです。
そのため研修では、法的な定義に加え、日常業務で起こり得る事例やグレーゾーンに該当する可能性がある行為も具体的に取り上げることが必要です。
また、セクハラやマタハラなど他のハラスメントについても同様に、種類ごとの定義や事例、許容されない行為のラインを明確に伝えることが重要です。
正しい知識が浸透すれば、従業員同士がお互いを尊重し、無意識の加害や見逃しを減らすことができます。
ハラスメント防止において、管理職は現場のキーパーソンです。
部下や同僚から相談を受けた際の初期対応は、その後の事態の行方を大きく左右します。
初動対応を誤れば、被害の拡大や二次被害の発生、企業全体への不信感を招くおそれがあります。
研修では、管理職が習得すべきスキルとして、傾聴力や公平な事実確認の方法、社内外の相談ルートの活用法、再発防止策の立案方法などを学びます。
特に相談を受ける際には、被害者の心情に寄り添いながらも、冷静かつ客観的に状況を把握する力が不可欠です。
これらのスキルはハラスメント対応だけでなく、日常のマネジメント全般にも活かされ、組織全体の信頼性向上に寄与します。
ハラスメント問題は、企業にとって重大な法的リスクを伴います。
被害者から損害賠償請求を受けたり、労働審判や裁判に発展した場合、多額の金銭的負担だけでなく、企業の社会的評価(レピュテーション)にも深刻なダメージを与えます。
特に近年はSNSの普及により、不祥事の情報は瞬時に拡散され、ブランド価値や採用活動への影響も避けられません。
研修を通じて従業員一人ひとりの意識を高め、未然防止の姿勢を強化することは、法的リスクを低減し、企業の信頼を守ることにつながります。
また「ハラスメント防止に真剣に取り組んでいる」という姿勢は社内外へのメッセージとなり、優秀な人材の確保や離職防止にも効果を発揮します。
ハラスメント防止研修は、まず全従業員が共通して理解すべき基礎知識の習得から始まります。
立場や役職にかかわらず、同じ情報と認識を持つことが、職場全体の意識改革に不可欠です。
基本プログラムでは、以下の3つの要素を中心に構成します。
まず、各種ハラスメントの定義を正確に理解します。
パワーハラスメントは「優越的な関係を背景に、業務の適正な範囲を超えて就業環境を害する行為」と定義されていますが、現場では境界が曖昧なケースも少なくありません。
セクシュアルハラスメントでは、性的言動だけでなく、性的な冗談や見た目への不適切なコメントも含まれることを明確に伝える必要があります。
さらに、妊娠・出産・育児に関する不利益な扱いを指すマタニティハラスメントについても、事例を交えて説明することで、従業員が身近な問題として認識できるようにします。
次に、判断が難しい「グレーゾーン」のケースを取り上げます。
例えば、強い口調での業務指示が適正な指導か、それともパワハラに該当するかは、状況や言動の継続性、相手の受け取り方によって評価が分かれます。
研修では、複数の事例をもとに、受け手の感情や職場の環境を踏まえた判断基準を学びます。
具体的なNG言動例を提示することで、従業員が自らの行動を客観視できるよう促し、無意識の加害行為や見逃しを減らすことができます。
最後に、ハラスメントを受けた、または目撃した場合の適切な対応手順を明確化します。
被害を受けた本人だけでなく、目撃者が行動することで早期対応が可能になります。
研修では、社内相談窓口や外部相談機関の連絡先を周知し、相談時のポイントや記録の取り方を説明します。
また、匿名での通報制度や報告後の不利益取り扱い禁止規定についても触れ、安心して相談できる体制が整っていることを従業員に理解してもらうことが重要です。
この基本プログラムを通じて、従業員は「何がハラスメントなのか」「どう行動すべきか」を具体的に理解し、日常業務で実践できる土台を築くことができます。
管理職は、ハラスメント防止の最前線に立つ存在です。
研修では、全従業員向けの基礎知識に加えて、管理職ならではの責任と役割を強化する内容が求められます。
問題が発生した際、初動の対応が遅れると被害の拡大や二次被害につながります。
管理職は、事実確認の際に偏った判断を避け、複数の関係者から冷静かつ公平にヒアリングする技術を学びます。
また、感情的な反応を控え、適切な記録(日時・場所・発言内容など)を残すことも重要です。
相談を受ける場面では、傾聴姿勢を持って相手の話を遮らずに聞き、否定的な言葉を避けることが基本です。
特に「被害者にも原因がある」といった発言は二次被害を引き起こします。
研修では、安心して話せる環境づくりや、相談内容を適切に社内の窓口へつなぐ方法も扱います。
管理職は、発生したハラスメントの再発を防ぐための具体的な改善策を立案・実行する責任があります。
これには、人員配置や業務分担の見直し、コミュニケーション機会の改善などが含まれます。
研修では、社内規定やガイドラインを活用しつつ、現場に即した対策を立案・実行するスキルを身につけます。
対面式研修は、参加者同士が直接議論できるため、意見交換やケーススタディが活発になります。
また、講師の表情や声の抑揚からも多くを学べる点が魅力です。
一方で、日程調整や会場確保が必要で、参加人数や地域的制約が発生しやすいという課題があります。
オンラインのライブ研修は、場所に縛られず全国の拠点から参加できるため、移動時間やコストの削減が可能です。
また、チャット機能を活用して匿名で質問できる点もメリットです。
ただし、通信環境の影響を受けやすく、双方向のコミュニケーションが対面よりも限定される傾向があります。
録画形式のeラーニングは、好きな時間に受講でき、復習もしやすいのが大きな利点です。
受講状況やテスト結果をシステムで管理できるため、企業側も進捗を把握しやすくなります。
しかし、受講者同士の意見交換やリアルタイムでの質疑応答が難しく、主体性の低い社員には学習効果が薄れる可能性があります。
ハラスメント防止研修は、単なる法令遵守のための形式的な施策ではなく、組織文化を守り、従業員の安心・安全な職場環境を実現するための戦略的取り組みです。
全社員が正しい知識を持ち、管理職が適切に対応できる体制を整えることで、企業の信頼性や生産性を高めることができます。
また、未然防止の姿勢を示すことは、社外への信頼構築や人材確保にもつながります。
効果的な研修を継続的に行うことで、ハラスメントのない職場を目指し、全ての従業員が安心して働ける環境づくりを進めましょう。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
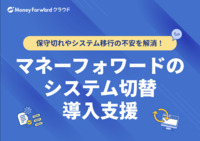
マネーフォワードのシステム切り替え導入支援

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
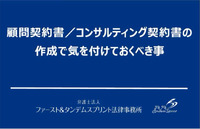
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
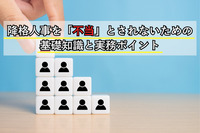
降格人事を「不当」とされないための基礎知識と実務ポイント

従業員満足度(ES)とは?向上させるための7つの方法
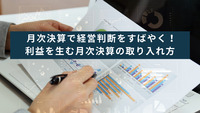
月次決算で経営判断をすばやく!利益を生む月次決算の取り入れ方

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査

経理の予算管理とは?基本から予実管理・差異分析・ツール活用まで実務目線で解説

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

アルムナイ制度導入ケーススタディ+チェックリスト36項目

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割

オフィスステーション導入事例集

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

組織における意思決定の種類とは? トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!

又は・若しくはの違いとは?意味・使い分けと契約書での注意点を例文で解説

振替休日の月またぎ対応!給与計算ミスを防ぐための必須知識

2026年度の「賃上げ」 実施予定は83.6% 賃上げ率「5%以上」は35.5%と前年度から低下

介護休業制度とは?―2025年法改正と制定経緯から考える、仕事と介護の両立支援の本質―
公開日 /-create_datetime-/