公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

「また今月も月末月初の残業地獄か…」「○○さんが辞めたら誰が引き継ぐの?」「紙の請求書が山積みで在宅勤務ができない」。
こんな声は多くの経理部門で日常的に聞かれます。しかし、これを“経理あるある”と片付けるのは危険です。
非効率な経理業務は単なる現場の問題にとどまらず、月次決算の遅延による経営判断の遅れや、手作業ミスによる取引先からの信頼低下、さらには属人化による業務停滞といった深刻なリスクを招きます。
経理が抱える課題は企業の競争力を根底から揺るがしかねません。
本記事では、こうした課題を解決するために「見える化→標準化→自動化」という段階的アプローチを提示し、日常の定型業務から年次決算まで効率化するための具体的なロードマップを解説します。
経理業務が非効率になってしまう背景には、業界や企業規模を問わず共通する構造的な問題があります。
「稟議書は必ず印鑑を押して回す」「請求書は紙で保管するのが安全」といった従来の慣習が、デジタル化の波に取り残されている企業は少なくありません。電子帳簿保存法の改正によってペーパーレス化の環境は整いましたが、現場の意識改革が追いついていないのが現状です。紙ベースの業務フローは、データの検索性を著しく低下させ、リモートワークの障害にもなります。
銀行の入出金データを手作業で会計システムに転記したり、請求書の金額を電卓で再計算したりする作業が日常化している企業では、ヒューマンエラーの発生は避けられません。特に繁忙期には、時間に追われる中で「とりあえず今月は乗り切ろう」という場当たり的な対応が続き、根本的な改善が先送りされがちです。
「この仕訳の判断は経験がものを言う」「月次決算のコツは長年の勘所」といった暗黙知が特定の担当者に集中していると、業務の標準化は進みません。その結果、担当者が休暇を取りづらい環境が生まれ、さらには退職時の業務引き継ぎに膨大な時間とコストがかかります。
インボイス制度、電子帳簿保存法、働き方改革関連法など、経理業務に影響する法改正は年々複雑化しています。しかし、多くの企業では新制度への対応が「やらされ仕事」として認識され、業務効率化のチャンスとして活用されていません。制度対応を機に業務フローを見直せば、コンプライアンス強化と効率化を同時に実現できるはずです。
月次決算を従来の20日から10日に短縮できれば、経営陣は市場の変化により迅速に対応できます。クラウド会計システムの導入により、リアルタイムで財務状況を把握できる環境を整えた製造業A社では、四半期ごとの事業戦略見直しサイクルを月次に短縮し、競合他社に先駆けた投資判断を実現しています。
自動化されたワークフローには承認プロセスや証跡管理が組み込まれているため、人的ミスの削減と同時に内部統制の強化も図れます。経費精算システムを導入したサービス業B社では、不適切な経費申請が95%減少し、監査法人からの評価も向上しました。
単純作業から解放された経理担当者は、より戦略的な業務に時間を割けるようになります。財務分析、予算管理、経営企画支援など、会社の成長に直結する業務にリソースを集中できる環境は、従業員のやりがいと成長機会を大幅に向上させます。
効率化プロジェクトを成功に導くためには、場当たり的な改善ではなく、体系的なアプローチが必要です。ここでは「見える化→標準化→自動化・効率化」という3段階のフレームワークを基に、全体戦略を解説します。
まずは自社の経理業務全体を客観視することから始めます。「毎月やっている作業だから把握している」と思い込まずに、改めて業務フローを洗い出してみてください。
担当者へのヒアリングだけでなく、実際の作業時間を計測することが重要です。特に注目すべきは「待機時間」です。承認待ちや他部署からの資料待ちなど、実作業以外の時間が業務全体の何割を占めているかを可視化すると、意外な発見があるはずです。
見える化によって明らかになった課題を基に、業務プロセスの統一とルール化を進めます。
Eliminate(排除)、Combine(結合)、Rearrange(順序変更)、Simplify(簡素化)の4視点で業務を見直し、効率化を進めます。
標準化されたプロセスを基に、適切なツール導入やアウトソーシングの活用を検討します。重要なのは「ツールありき」ではなく、「業務ありき」で選択することです。
現金管理や仕訳入力の効率化により、日常業務の基盤を強化します。
「小口現金の残高が合わない」「出納記録に時間がかかる」といった課題の根本解決はキャッシュレス化の推進です。
銀行API連携機能を持つクラウド会計ソフトの導入で、入出金データの自動仕訳が可能になります。継続的な調整で最終的には90%以上の仕訳を自動化できます。
月次業務は負荷が集中する領域であり、効率化の効果が大きく表れます。
請求書を紙で送付する作業をWeb請求に切り替えることで、作業時間は大幅に短縮されます。
勤怠管理システムとの連携機能を持つ給与計算ソフトを導入すれば、計算ミスや転記作業を防止できます。
資料収集待ちを減らし、システム連携によりリアルタイムでデータを把握する仕組みを構築しましょう。
年次業務は工数が膨大ですが、資料管理や仕訳のテンプレート化により効率化が可能です。
法人税や消費税の申告を外部専門家に委託することで、社内の負担を減らしつつ知識蓄積も図れます。
クラウド化は導入スピードや拡張性に優れる一方で、カスタマイズやランニングコストに注意が必要です。
専門性の高い業務を外部に委託することで効率化できますが、内部スキルが育ちにくいという課題もあります。
クラウドとアウトソーシングを組み合わせることで、バランスの取れた効率化を実現できます。
A. 日次業務の自動化から始めるのがおすすめです。
A. 定量的な効果と現状維持リスクを示すことが有効です。
A. 金融機関レベルのセキュリティ対策を確認し、自社ポリシーとの適合性を評価してください。
A. 無料ツールや段階的導入で初期コストを抑えつつ改善を進めましょう。
経理業務の効率化は、単なるコスト削減や時間短縮を超え、企業の持続的成長を支える基盤づくりです。小さな改善から始めて成果を積み上げることで、経営判断の迅速化、信頼性の向上、働きやすい環境の実現につながります。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

弁護士業におけるスキャン代行活用事例

ラフールサーベイ導入事例集

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
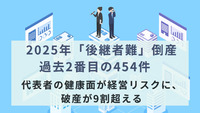
2025年「後継者難」倒産 過去2番目の454件 代表者の健康面が経営リスクに、破産が9割超える

トータルリワード時代の新しい人事制度 ~役割の「拡大 × 深化」を実現する役割貢献制度~

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!

セキュリティ対策評価制度自己評価の進め方

振り返りが回り始めた組織で起きる次の壁 ― 変革を続けられるかどうかを分ける「継続の関所」―<6つの関所を乗り越える5>

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音
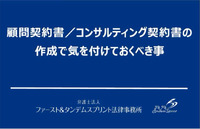
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~
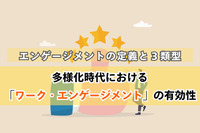
エンゲージメントの定義と3類型:多様化時代における「ワーク・エンゲージメント」の有効性

2025年「税金滞納」倒産159件、2年ぶり減少 破産が9割超、再建支援の遅れが高止まり懸念

ヒエラルキー組織における意思決定の高速化と最適化
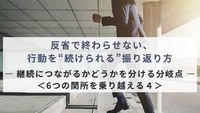
反省で終わらせない、行動を“続けられる”振り返り方 ― 継続につながるかどうかを分ける分岐点 ―<6つの関所を乗り越える4>

なぜ使われない?クラウドストレージ定着を阻む3つの壁
公開日 /-create_datetime-/