公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?
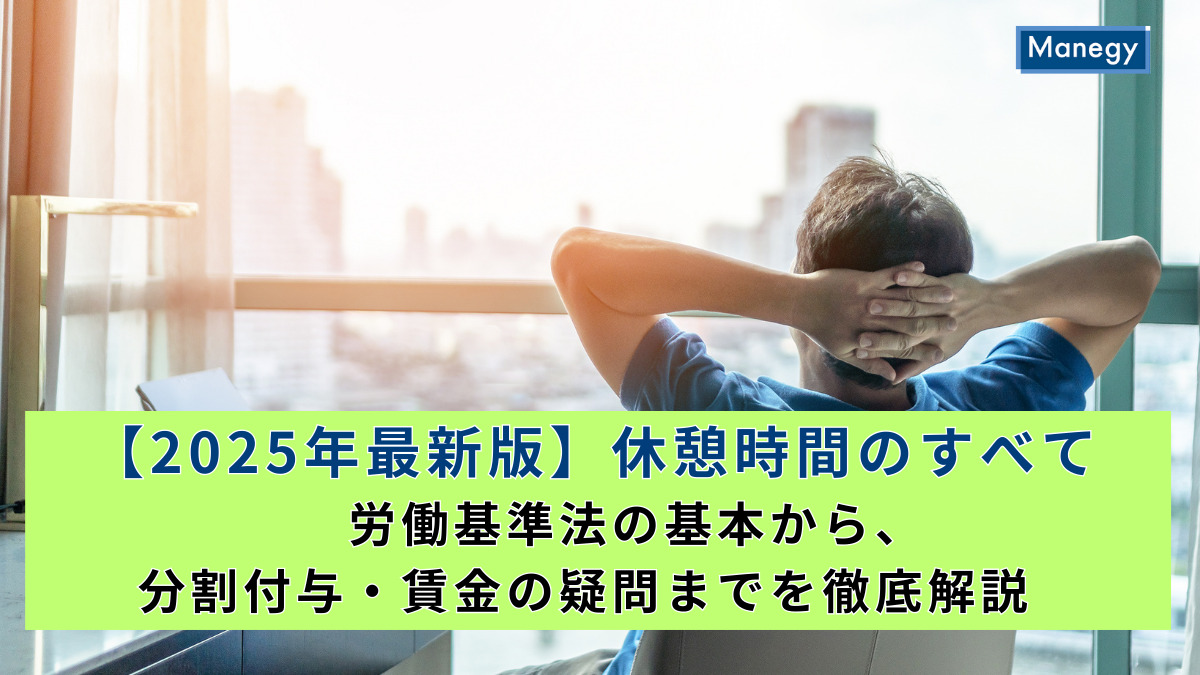
「8時間勤務なら休憩は1時間だけど、10時間働いた場合は?」
「お昼休みに電話番をするのは、休憩時間になるの?」
「タバコ休憩は、給料から引かれるの?」。
休憩時間は身近なテーマですが、こうした現場の素朴な疑問は後を絶ちません。
休憩時間のルールを正しく理解しないと、気づかぬうちに法律違反になっている可能性があります。
労働基準法第34条では、休憩時間に関する明確な規定が設けられており、これに違反した場合は罰則の対象となることもあります。
この記事では、労働基準法の基本から、よくある疑問、そして企業の正しい対応方法まで、休憩時間に関する全てを分かりやすく解説します。
人事労務担当者はもちろん、管理職の方や働く全ての方にとって役立つ内容となっています。
労働基準法では、労働時間を「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義しています。
一方、休憩時間は「労働者が権利として労働から離れることができる時間」です。
重要なのは、拘束時間(会社にいる時間)と労働時間は異なるということです。
例えば、朝9時から夕方6時まで会社にいる場合、拘束時間は9時間ですが、1時間の休憩時間を除けば労働時間は8時間となります。
労働基準法第34条では、休憩時間について以下のように定められています。
労働時間が6時間を超える場合:少なくとも45分の休憩時間
労働時間が8時間を超える場合:少なくとも1時間の休憩時間
ここで注意すべきは「超える」という表現です。
労働時間が6時間ぴったりの場合は休憩時間の付与は不要ですが、6時間1分でも超えれば45分の休憩が必要になります。
同様に、8時間ぴったりの労働時間であれば45分の休憩で足りますが、8時間1分を超えれば1時間の休憩が必要です。
また、10時間勤務や12時間勤務の場合でも、法律上は1時間の休憩で足ります。
ただし、労働者の健康を考慮し、より長い休憩時間を設ける企業も多く見られます。
労働基準法第34条では、休憩時間について3つの重要な原則を定めています。
①途中付与の原則 休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。
労働開始前や終了後に与えることはできません。これは、労働による疲労を回復させるという休憩時間の目的に基づいています。
②一斉付与の原則 原則として、同一事業場の労働者全員に同じ時刻に休憩時間を与える必要があります。
ただし、労使協定を締結することで、一斉付与の例外とすることが可能です。運輸・交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業については、労使協定がなくても一斉付与の例外が認められています。
③自由利用の原則 労働者は休憩時間を自由に利用することができます。
使用者は、休憩時間中に労働者の行動を制限してはいけません。
ただし、事業場の規律保持上必要な制限を設けることは可能です。
A. 休憩時間は無給であり、給与計算の対象となる実働時間には含まれません。
労働法の基本原則である「ノーワーク・ノーペイの原則」により、労働の対価として支払われる賃金は、実際に労働を提供した時間に対してのみ支払われます。
休憩時間は労働から解放された時間であるため、賃金の支払い対象とはなりません。
例えば、朝9時から夕方6時まで働き、12時から13時まで1時間の休憩を取った場合、実働時間は8時間となり、この8時間分の賃金が支払われます。
ただし、会社の福利厚生として有給の休憩時間を設けることは法律上問題ありません。
実際に、一部の企業では従業員のモチベーション向上や定着率改善を目的として、有給の休憩時間を提供している例もあります。
A. 法律上は可能ですが、従業員の休息という本来の目的が達成できる範囲で行う必要があります。
労働基準法では、休憩時間を分割して付与することを禁止していません。
したがって、1時間の休憩時間を15分×4回や30分×2回に分割することは可能です。
しかし、休憩時間の本来の目的は「労働による疲労の回復」と「心身のリフレッシュ」にあります。
あまりに細切れにした休憩では、この目的を達成することが困難になる可能性があります。行政通達では、「まとまった時間の休憩を与えることが望ましい」とされています。
実務的には、昼食時間として30分から1時間程度のまとまった休憩時間を設け、その他に10分から15分程度の小休憩を組み合わせるパターンが一般的です。
分割する場合は、従業員の意見も聞きながら、実際に疲労回復効果のある時間配分を検討することが重要です。
A. 使用者の指揮命令下にあると判断されるため「労働時間」と見なされ、休憩時間ではありません。
休憩時間の3原則の一つである「自由利用の原則」により、労働者は休憩時間中に使用者からの指示や拘束を受けることなく、自由に時間を過ごす権利があります。
お昼休みであっても、電話番や来客対応を任されている状況は、使用者の指揮命下に置かれた状態であり、労働時間に該当します。
このような場合、別途適切な休憩時間を与える必要があります。
最高裁判所の判例(大星ビル管理事件)でも、「労働者が労働から離れることを保障されていない時間は休憩時間とは言えない」との判断が示されています。
企業は、休憩時間中に労働者が完全に業務から解放されるよう体制を整備する必要があります。
仮にこのような状況が避けられない場合は、交代制を採用するか、別の時間帯に同等の休憩時間を設けるなどの対応が求められます。
A. 明確な法的ルールはありませんが、就業規則での定めや他の従業員との公平性が重要な判断要素となります。
タバコ休憩やコーヒー休憩について、労働基準法で明確な規定はありません。
これらの取り扱いは、各企業の就業規則や職場慣行によって決まることが多いのが現状です。
考慮すべき観点は以下の通りです。
公平性の観点:喫煙者のみがタバコ休憩を取れる状況は、非喫煙者との間で不公平感を生む可能性があります。すべての従業員に平等な休憩機会を提供することが望ましいでしょう。
業務への影響:頻繁な小休憩が業務の効率性や職場の規律に悪影響を与える場合は、適切な制限を設ける必要があります。
就業規則での明文化:曖昧な運用を避けるため、小休憩に関するルールを就業規則で明確に定めることが重要です。例えば、「1日2回まで、1回10分以内の小休憩を認める」といった具体的な規定を設けている企業もあります。
実務上は、法定休憩時間とは別に、すべての従業員に平等な小休憩時間を設ける企業が増えています。
これにより、公平性を保ちながら従業員のリフレッシュ機会を確保することができます。
休憩時間の適切な管理には、客観的で正確な記録が不可欠です。
2019年4月に施行された働き方改革関連法により、労働時間の客観的把握が義務化されており、休憩時間も含めた適切な勤怠管理が求められています。
推奨される記録方法:
休憩開始・終了時刻の打刻:ICカードやスマートフォンアプリを活用し、休憩の開始と終了時刻を正確に記録する方法
固定休憩時間の自動控除:毎日決まった時間に休憩を取る場合、システムで自動的に休憩時間を控除する設定
変形的な記録方法:シフト制の職場では、実際の休憩時間に応じて柔軟に記録できるシステムの導入
特に重要なのは、名目上の休憩時間と実際の休憩時間が乖離しないよう監督することです。
システム上では1時間の休憩が設定されていても、実際には30分しか休憩できていないような状況は、労働基準法違反となる可能性があります。
就業規則には休憩時間について明確に記載する必要があります。以下にサンプル条文を示します。
【サンプル条文例】 第○条(休憩時間) 1. 休憩時間は、次のとおりとする。 (1) 所定労働時間が6時間を超え8時間以下の場合 45分以上 (2) 所定労働時間が8時間を超える場合 1時間以上 2. 休憩時間は、労働時間の途中に与えるものとし、原則として午後12時00分から午後1時00分までとする。 3. 業務の都合により、前項の時間に休憩を取ることが困難な場合は、上司の承認を得て、他の時間に取ることができる。 4. 休憩時間は労働者が自由に利用できるものとし、事業場外で過ごすことも可能とする。ただし、事業場内にとどまる場合は、施設利用に関する規則を遵守するものとする。
記載時の注意点として、一斉付与の例外がある業種の場合は、その旨も明記する必要があります。
また、分割付与を行う場合は、その具体的な方法についても規定しておくことが重要です。
新しい働き方に対応した休憩時間の管理も重要な課題となっています。
リモートワーク時の休憩時間: 在宅勤務であっても労働基準法の休憩時間規定は適用されます。
ただし、休憩時間の過ごし方はより自由度が高くなります。
家事をしたり、散歩に出かけたりすることも可能です。企業側は、適切な休憩が取られているかを確認する仕組みを整備する必要があります。
フレックスタイム制での休憩時間: フレックスタイム制では、労働者が始業・終業時刻を選択できますが、休憩時間の付与義務は変わりません。
8時間を超えて労働する日は1時間の休憩、6時間を超え8時間以下の日は45分の休憩が必要です。
コアタイムの設定と合わせて、適切な休憩時間の確保を図る必要があります。
一部の業界では、改善基準告示により独自の休憩時間ルールが設けられています。
運送業(トラックドライバー): 厚生労働省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)では、連続運転時間は4時間以内とし、その後30分以上の休憩または1時間以上の仮眠を取ることが義務付けられています。
また、1日の拘束時間は13時間以内(延長時も16時間以内)と定められており、このうち休息期間は継続8時間以上確保する必要があります。
建設業: 建設業では2024年4月から時間外労働の上限規制が適用され、休憩時間の管理もより重要になっています。
現場の特性上、天候や工期の関係で不規則な勤務になることも多いため、適切な休憩時間の確保と記録が重要です。
医師・看護師等の医療従事者: 医師については2024年4月から働き方改革が本格的に開始され、適切な休憩時間の確保が重要視されています。
連続勤務制限や勤務間インターバルの確保と合わせて、十分な休憩時間の付与が求められています。
A. 雇用形態による違いはなく、労働時間に応じて同じルールが適用されます。
労働基準法の休憩時間規定は、雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。
正社員、パート・アルバイト、契約社員、派遣社員のいずれであっても、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与える必要があります。
ただし、実務上は以下の点に注意が必要です。
短時間労働者の場合:1日4時間程度の勤務であれば休憩時間の付与義務はありませんが、6時間を超える日がある場合は適切な休憩時間を確保する必要があります。
シフト制の場合:勤務時間が日によって変動する場合は、それぞれの日の労働時間に応じて適切な休憩時間を付与する必要があります。シフト作成時に休憩時間も合わせて計画することが重要です。
有期契約労働者の場合:契約期間の長短に関わらず、同様の休憩時間付与義務があります。短期間の契約であっても、労働基準法の規定は完全に適用されます。
実際にあった裁判例・労働基準監督署の指摘事例
休憩時間に関する労働基準監督署の指摘事例や裁判例を見ると、以下のようなケースが目立ちます。
代表的な指摘事例:
名目上の休憩時間中に業務対応を求められていた事例:昼休み中の電話対応や窓口業務により、実質的に休憩が取れていないとして是正勧告を受けた事例
休憩時間の未付与事例:繁忙期に休憩時間を与えずに連続して労働させていたとして指摘を受けた事例
休憩時間の記録不備事例:適切な勤怠管理を行っておらず、休憩時間が適正に付与されているか確認できないとして改善を求められた事例
重要な裁判例: 大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決)では、仮眠時間中も労働者が労働から完全に解放されておらず、実作業に従事する可能性がある状態は労働時間に当たると判示されました。
この判例は、休憩時間の「自由利用の原則」を考える上で重要な基準となっています。
労働基準法違反となった場合の罰則(懲役または罰金)
労働基準法第34条(休憩時間)に違反した場合、同法第119条により「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
実際の処罰に至るケースは多くありませんが、労働基準監督署による是正勧告や改善命令の対象となることは珍しくありません。
また、違反が繰り返される場合や悪質な場合は、書類送検される可能性もあります。
さらに、適切な休憩時間を与えなかったことにより労働者の健康被害が発生した場合、安全配慮義務違反として民事上の損害賠償責任を問われる可能性もあります。
企業のリスク管理の観点からも、休憩時間の適切な付与と管理は極めて重要です。
休憩時間の適切な付与は、労働基準法で定められた企業の義務です。
しかし、それは単なる法的義務に留まらず、従業員の健康を守り、生産性を高め、エンゲージメントを向上させるための重要な投資でもあります。
適切な休憩時間の確保により、労働者の疲労が軽減され、集中力が維持され、結果として業務の質と効率が向上します。
また、ワークライフバランスの改善にもつながり、優秀な人材の確保と定着にも寄与します。
現代の多様な働き方において、休憩時間の管理はより複雑になっていますが、基本的な法律の理解と適切なシステムの構築により、コンプライアンスを保ちながら従業員満足度を高めることは可能です。
この記事で解説した内容を参考に、自社の休憩時間に関するルールと運用を再点検し、従業員が心身ともにリフレッシュできる環境を整えることで、持続可能な組織運営を実現していきましょう。
法令遵守は企業の基本であり、それを通じて従業員と会社の双方が守られる、真のwin-winの関係を築くことができるのです。
この記事を読んだ方にオススメ!

法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

ラフールサーベイ導入事例集

【新卒エンジニア採用】内定承諾の決め手・辞退の本音

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス

経理業務におけるスキャン代行活用事例
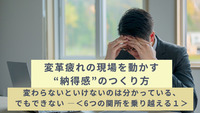
変革疲れの現場を動かす“納得感”のつくり方 ― 変わらないといけないのは分かっている、でもできない ―<6つの関所を乗り越える1>

「一律50万円支給」の転勤支援金制度を新設。住友重機械工業、転勤を“前向きな挑戦”に変える人事施策を導入
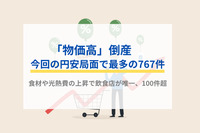
「物価高」倒産 今回の円安局面で最多の767件 食材や光熱費の上昇で飲食店が唯一、100件超
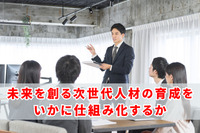
未来を創る次世代人材の育成をいかに仕組み化するか

「フリンジベネフィット」が映す企業文化とその戦略的価値とは

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
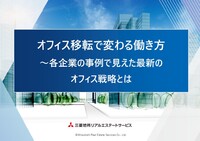
オフィス移転で変わる働き方
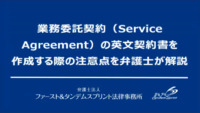
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

中小企業のBCP対策を強化するクラウドストレージ
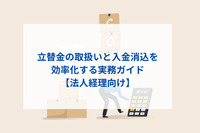
立替金の取扱いと入金消込を効率化する実務ガイド【法人経理向け】
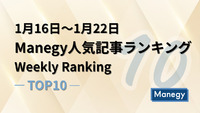
1月16日~1月22日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
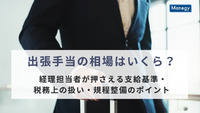
出張手当の相場はいくら?経理担当者が押さえる支給基準・税務上の扱い・規程整備のポイント
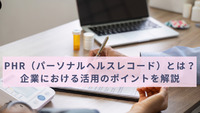
PHR(パーソナルヘルスレコード)とは?企業における活用のポイントを解説
公開日 /-create_datetime-/