公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。

一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の資産について、通常の減価償却ではなく3年間で均等に償却できる制度です。
この制度は、経理処理が簡素化され、償却資産税が非課税となるメリットがある一方、償却方法が固定されるといった制約もあります。
制度の長所と短所を正しく理解し、自社にとって最適か判断することが重要です。
本記事では、一括償却資産の基本的な仕組みから、仕訳方法や実務上の留意点までを解説します。
一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産について、3年間で均等に償却できる特例です(法人税法施行令第133条の2)。
通常の減価償却では、資産ごとに耐用年数に基づいて償却を行いますが、一括償却資産ではその必要がありません。
基準内の資産を合計して処理でき、資産の種類に関わらず一律3年で定額償却できるため、経理処理が大幅に簡素化されます。
この制度を活用すれば、耐用年数や供用開始月の管理が不要となり、経理担当者の負担を軽減できます。
対象となるのは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産です。
例としては、パソコン・プリンター・応接セット・事務用家具・工具器具備品などが該当します。
ただし、以下のような資産は対象外となるため注意が必要です。
一括償却資産は、法人であれば資本金や規模に関係なく利用できる制度です。
これは、中小企業者に限定される「少額減価償却資産の特例」との大きな違いであり、大企業でも適用可能です。
償却の開始時期は、資産を事業の用に供した日(供用開始日)となりますが、月割計算は不要です。
たとえ期中で供用を開始しても、取得年度から年額ベースで均等に償却します。
また、この制度は資産ごとに選択が可能です。
同じ事業年度内でも、一部の資産には一括償却資産を適用し、他の資産には通常の減価償却や少額減価償却資産を適用するといった使い分けが認められています。
このように資産ごとに適用を選択できるため、法人の業績や資産の性質に応じた制度の使い分けが可能です。
減価償却に関する制度には、「一括償却資産」「少額減価償却資産」「通常の固定資産」の3つがあります。
それぞれ金額条件・償却方法・税務上の扱いが異なります。
| 項目 | 一括償却 資産 |
少額減価 償却資産 |
通常の 固定資産 |
|---|---|---|---|
| 金額 条件 |
10万円以上20万円未満 | 10万円以上30万円未満 | 制限なし |
| 償却 方法 |
3年均等 償却 |
全額 即時償却 |
法定 耐用年数 |
| 月割 計算 |
不要 | 不要 | 必要 |
| 償却 資産税 |
課税 対象外 |
課税対象 | 課税対象 |
| 適用 法人 |
全法人 | 中小企業 者等 |
全法人 |
※少額減価償却資産には中小企業者等の要件および年間合計300万円の上限があります。
あわせて読みたい
一括償却資産は通常の固定資産とは異なる処理が求められるため、勘定科目や仕訳方法を正しく理解しておく必要があります。
一括償却資産の取得時には、「一括償却資産」という専用の勘定科目を使用し、固定資産として資産計上します。
決算時には、3年間の均等償却に基づき「減価償却費」として毎年費用処理します。
一括償却資産の会計処理には、以下の2つの方式があります。
決算調整方式とは、会計上・税務上ともに同じ処理を行う方式です。
18万円の資産を購入した場合:取得時
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 一括償却資産 | 180,000 | 現金預金 | 180,000 |
18万円の資産を購入した場合:各期末(3年間)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 60,000 | 一括償却資産 | 60,000 |
申告調整方式では、会計上は通常の減価償却を行い、申告時に税務調整を行います。
この場合は、別表四を用いた調整が必要となり、やや複雑ですが、会計の厳格性が求められる法人に適しています。
方式の選択は、会計方針や顧問税理士の方針に応じて判断します。
一括償却資産は、個々の資産ではなく取得価額の集合体として管理されるため、対象資産を途中で売却・除却しても、その時点で固定資産売却損益や除却損を計上することはありません。
3年間の償却スケジュールに従って減価償却を継続します。
ただし、売却代金は雑収入として処理する必要があります。
また、災害による滅失など例外的な事情がある場合には、税務署や顧問税理士に相談のうえで対応します。
一括償却資産は経理処理を簡素化できる便利な制度ですが、適用には一定の制約もあります。
月割計算や耐用年数の確認が不要で、すべて3年で均等償却できるため、仕訳や管理の手間が軽減されます。
特に、小規模な備品を多数扱う企業では、処理効率の向上につながります。
通常の減価償却よりも早期に費用化でき、損金算入が早まることで、法人税の軽減や資金繰りの改善が期待できます。
一括償却資産は償却資産税の課税対象から除外されるため、固定資産税の負担を軽減できる点も大きなメリットです。
※特に償却資産税の負担が重い地域・業種ではより大きな効果を享受できる可能性があります。
業績に合わせて償却額を増減したり、早期に全額償却したりすることはできません。
制度上、資産の集合体として管理するため、現物管理・保険対応・減損会計などで個別識別が必要な場合に不向きです。
赤字や利益が少ない年度に償却しても、節税メリットが実感しづらいため、制度の恩恵を最大化できないことがあります。
ABC社が18万円のパソコンを4月に購入し、事業に使用したケースです。
一括償却資産を適用すると、月割計算は不要となり、初年度から毎年6万円ずつ、3年間で均等に償却されます。
これにより、通常の減価償却より早期に費用化でき、初期の節税効果が期待できます。
また、月割計算や個別管理が不要なため、経理実務の効率化にもつながります。
さらに、この資産は償却資産税の課税対象外です。
DEF株式会社が前年度に一括償却資産として処理した事務用機器(15万円)を、2年目に5万円で売却した場合です。
一括償却資産では、個別売却時の損益計上は原則行いません。
売却代金5万円は雑収入として計上しますが、売却損や除却損は計上せず、予定通り3年目まで減価償却費の計上を継続します。
これは、一括償却資産が個別ではなく、取得価額の集合体として管理されるためです。
売却代金の受取り:
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金預金 | 50,000 | 雑収入 | 50,000 |
年間償却額の計上:
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 50,000 | 一括償却資産 | 50,000 |
20万円ちょうどの資産は、一括償却資産の対象外です。
対象は「10万円以上20万円未満」の資産に限られます。20万円の資産は、通常の減価償却か、中小企業者等の特例(少額減価償却資産)で処理します。
判定金額は、採用している経理方式(税込経理か税抜経理か)によって変わるため、消費税の取り扱いも含めて確認しましょう。
一括償却資産は月割計算が不要なので、事業の用に供した年度から年額で償却を開始できます。
たとえば3月決算の法人が12月に取得しても、その年度から年間償却額の全額を費用計上可能です。
これにより、経理業務の負担が軽減されます。
原則として、個別の資産を途中で除却や売却しても、除却損や売却損は計上できません。
3年間の均等償却を継続し、償却完了まで費用計上を続けます。
ただし、災害による滅失など特別な事情がある場合は、例外的な処理が認められることもあります。
その際は、顧問税理士や税務署に相談して適切な処理方法を確認してください。
一括償却資産は、10万円以上20万円未満の資産を3年で均等償却する実用的な制度です。
月割計算不要で事務処理が簡素化され、償却資産税も非課税という税務メリットがあります。
制度選択時は、業績、事務負担、資産の性質を総合的に考慮する必要があります。
特に黒字企業は節税効果、赤字企業は償却分散効果を重視し、償却資産税も含めた総合的な税負担で判断することが肝要です。
経理部門は、決算前に制度適用を検討する体制を整えましょう。
判定基準の明確化、書類整備、申告体制構築で制度を効果的に活用できます。
適切な運用により、税負担軽減と事務効率向上を両立し、経営効率化に貢献できます。
この記事を読んだ方にオススメ!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

労使および専門家の計515人に聞く 2026年賃上げの見通し ~定昇込みで4.69%と予測、25年実績を下回るも高水準を維持~

2026年1月の「物価高」倒産 76件 食料品の価格上昇で食品関連が増勢

労基法大改正と「事業」概念の再考察② ~場所的観念から組織的観念へのシフト~

【図解フローチャート付】出張ガソリン代の勘定科目は?旅費交通費と車両費の違いを仕訳例で徹底解説
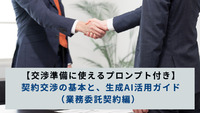
【交渉準備に使えるプロンプト付き】契約交渉の基本と、生成AI活用ガイド(業務委託契約編)

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

サーベイツールを徹底比較!

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

通勤車両/社用車の駐車場利用・管理におけるガバナンス見直しチェックガイド

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~
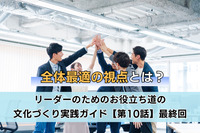
全体最適の視点とは?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第10話】最終回

不登校やきょうだい児も対象に 住友林業が最大3年の「ファミリーケア休業」新設、離職防止へ
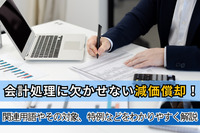
会計処理に欠かせない減価償却!関連用語やその対象、特例などをわかりやすく解説

契約審査とは?担当者が迷わない流れとチェックポイント

新入社員の育成・活躍を促進するオンボーディングとは?
公開日 /-create_datetime-/